 さて、今月(こんかい)もみんなといっしょに時や時間にかかわりのある場所(ばしょ)をたずねていこうと思う(おもう)のだが、準備(じゅんび)はよろしいか。よいしょ。
さて、今月(こんかい)もみんなといっしょに時や時間にかかわりのある場所(ばしょ)をたずねていこうと思う(おもう)のだが、準備(じゅんび)はよろしいか。よいしょ。
今回は「明治・大正時代に東京で、正午をつげた場所(めいじ・たいしょうじだいにとうきょうで、しょうごをつげたばしょ)」にいってみるのだな。明治・大正時代には、まだまだ時計というものは高価(こうか)なもので、いっぱんの人たちが気軽(きがる)に持てる(もてる)ものではなかったのだな。そんな時代(じだい)に、多く(おおく)の人たちに正午を知らせる(しらせる)ために使われた(つかわれた)のが大砲(たいほう)なのだな。
江戸時代(えどじだい)には、お寺(てら)が鐘(かね)を使って時間を人々に知らせたのではあるが、大砲の音(おと)の大きさにはかなわないからなぁ。よいしょと。
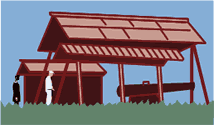
さて、その大砲のおかれた場所は皇居旧本丸(こうきょきゅうほんまる)の小高い丘(こだかいおか)なのだな。
皇居は明治時代になる前の江戸時代には江戸城(えどじょう)と言われていた場所なのだな。
お城のある場所は、もちろん都市(とし)の中心(ちゅうしん)であるのだから、まさに大砲をうってみんなに正午を知らせるのにはピッタリの場所なのだな。
ここでその正午を知らせるのに使われていた大砲について、少し解説(かいせつ)させてもらうのだな。
全長(ぜんちょう)は3.44メートル、口径(こうけい/入る玉の大きさの直径)は17.8センチの青銅(せいどう)でできたカノン砲とよばれるものなのだな。その大砲から出る音がどのぐらい大きかったかというと、丸(まる)ビルという当時ではものすごく大きかった建物(たてもの)が60〜90センチもしずんでしまったと言われるぐらいなのだな。
ホントかどうかはわからないけれどね。ふーっ。
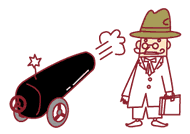 「日々(ひび)正午に大砲を1発はっしゃすること」が決められたのは、明治4年(1871年)の9月9日。それから正午になると全国(ぜんこく)の主(おもな)な都市で、大砲がうたれていたのだな。
「日々(ひび)正午に大砲を1発はっしゃすること」が決められたのは、明治4年(1871年)の9月9日。それから正午になると全国(ぜんこく)の主(おもな)な都市で、大砲がうたれていたのだな。
この大砲の音は、みんなから「ドン」と呼ばれて(よばれて)親しまれ(したしまれ)、土曜日(どようび)の仕事(しごと)が半日(はんにち)で終わって(おわって)いたころは、そのことを「半ドン(はんドン)」と言うようになったのだな。今は週休二日の会社がふえたので「半ドン」という言葉もなくなってしまったのだがな。どっこらしょ。
この大砲によって正午を知らせる「ドン」は、大正11年(1911年)9月に、この「ドン」の仕事をしていた陸軍(りくぐん)の予算(よさん)がけずられてしまったために、やめることになってしまったのだが、東京だけはひきついで、昭和4年(1929年)までつづけられたのだな。その後は「ドン」のかわりにサイレンが正午を知らせるようになったのだな。よいしょっと。
では、今回は、ここまで。さて、次回(じかい)はいったいどこへ行くのか。
みんな楽しみにまっててくれるとうれしいのだな。どっこらしょ。
2001年4月号