さて、今回もみんなといっしょに「時や時間(ときやじかん)」にかかわりのある場所を訪ねて(たずねて)いこうと思うのだが、準備(じゅんび)はよろしいか。よいしょ。
|
 |
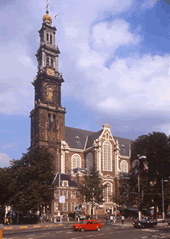 |
 今回はオランダのアムステルダムに行ってみるのだな。ここアムステルダムのカイセル運河(うんが)沿い(ぞい)には、オランダ初期(しょき)バロック様式(ようしき)の建築家(けんちくか)ヘンドリック・デ・カイザーが設計(せっけい)し1639年に建てられた西教会(にしきょうかい)の世界的(せかいてき)にも有名(ゆうめい)な時計塔(とけいとう)があるのだな。この時計塔は、毎正時(まいせいじ)に7.5トンの大鐘(おおかね)が鳴り(なり)、15分ごとに塔の一番上にある3.7トンの鐘が、そして正午(しょうご)には、47個のカリヨン(小さな鐘)が様々(さまざま)なメロディを奏で(かなで)、今も多くの人たちに時を知らせているのだな。 今回はオランダのアムステルダムに行ってみるのだな。ここアムステルダムのカイセル運河(うんが)沿い(ぞい)には、オランダ初期(しょき)バロック様式(ようしき)の建築家(けんちくか)ヘンドリック・デ・カイザーが設計(せっけい)し1639年に建てられた西教会(にしきょうかい)の世界的(せかいてき)にも有名(ゆうめい)な時計塔(とけいとう)があるのだな。この時計塔は、毎正時(まいせいじ)に7.5トンの大鐘(おおかね)が鳴り(なり)、15分ごとに塔の一番上にある3.7トンの鐘が、そして正午(しょうご)には、47個のカリヨン(小さな鐘)が様々(さまざま)なメロディを奏で(かなで)、今も多くの人たちに時を知らせているのだな。
写真提供:オランダ政府観光局
|
 この時計塔が世界的に有名になったのは、その美しさだけではなく、実(じつ)は「アンネの日記(にっき)」を書いたアンネ・フランクが、ナチスに捕まる(つかまる)までの間、隠れ(かくれ)住んで(すんで)いた場所のすぐそばにあり、その鐘のことについて日記の中に書かれているからなのだな。ちょっとその部分を抜き(ぬきだしてみるのだな。「15分ごとに時を告げる(つげる)門の西塔(にしとう)の鐘の音に、父も母もマルゴットもいまだに耳馴れず(みみなれず)に困っています。でも、私はこの鐘の音がはじめからから好きです。特に夜は、仲良し(なかよし)の友達(ともだち)のような気がしますから」これは、隠れ家(かくれが)に移ってから5日目の日記なのだな。隠れていることがナチスにわかったら、すぐに強制収容所(きゅせいしゅうようじょ)送りになってしまうという状況(じょうきょう)で、誰もが外の物音(ものおと)に敏感(びんかん)になり、落ち着かなく(おちつかなく)なってしまうのも無理(むり)はないことなのだな。けれど、アンネには唯一(ゆいいつ)、この音が、自分と外の世界をつなぐものとして感じられたのだな。このあたりが、ジャーナリストになることを夢見ていたアンネの感受性(かんじゅせい)豊かな(ゆたかな)ところなのかなと思うのだな。
この時計塔が世界的に有名になったのは、その美しさだけではなく、実(じつ)は「アンネの日記(にっき)」を書いたアンネ・フランクが、ナチスに捕まる(つかまる)までの間、隠れ(かくれ)住んで(すんで)いた場所のすぐそばにあり、その鐘のことについて日記の中に書かれているからなのだな。ちょっとその部分を抜き(ぬきだしてみるのだな。「15分ごとに時を告げる(つげる)門の西塔(にしとう)の鐘の音に、父も母もマルゴットもいまだに耳馴れず(みみなれず)に困っています。でも、私はこの鐘の音がはじめからから好きです。特に夜は、仲良し(なかよし)の友達(ともだち)のような気がしますから」これは、隠れ家(かくれが)に移ってから5日目の日記なのだな。隠れていることがナチスにわかったら、すぐに強制収容所(きゅせいしゅうようじょ)送りになってしまうという状況(じょうきょう)で、誰もが外の物音(ものおと)に敏感(びんかん)になり、落ち着かなく(おちつかなく)なってしまうのも無理(むり)はないことなのだな。けれど、アンネには唯一(ゆいいつ)、この音が、自分と外の世界をつなぐものとして感じられたのだな。このあたりが、ジャーナリストになることを夢見ていたアンネの感受性(かんじゅせい)豊かな(ゆたかな)ところなのかなと思うのだな。
さて、アンネ・フランク一家が、この西塔の時計塔の鐘の音の聞こえるアムステルダム市内のプリンセンフラハルト263番地(ばんち)の建物(たてもの)の屋根裏(やねうら)に隠れていたのは、1942年7月6日から1944年8月3日の約2年間。最後の8月3日にはアンネ・フランク一家と、一緒に隠れていたファン・アンダーソン一家と、デュッセル医師(いし)の8人と、アンネたちをかくまっていた人々全員は、逮捕(たいほ)され、その後(あと)アウシュビッツ強制収容所に送られたのだな。アンネは、毎日多くの人々が殺されたり、死んでゆくという強制収容所生活でも、しっかりした態度(たいど)を保ち、泣き言なども言わず、少ない食物をいつも母親や姉にわけてやり、お腹がすいている人には、とっておきの小さなパン切れをあげたというのだな。わずか14歳の女の子がよくそんなことが、できたものだと、感心(かんしん)してしまうのだな。
|
|
そしてベルゲン・ベルゼン強制収容所に移された翌年(よくねん)の1945年2月に姉のマルゴットとともにチフスにかかり、それでも希望(きぼう)を捨てずがんばっていたのだけれど、マルゴットが亡くなって(なくなって)すっかり気力(きりょく)を失い(うしない)3月はじめに静か(しずか)に息を引き取ったのだな。外の世界に憧れ(あこがれ)、時計塔の音に耳を澄ませて(すませて)いたアンネは残念(ざんねん)ながら、その音をを二度と聞くことなく死んでしまったのだな。それからわずか数ヶ月後(すうかげつご)戦争(せんそう)が終わり捕まった(つかまった)8人のうち、強制収容所から生きて帰ってこられたのは、父親のオットー氏、たった一人だけだったのだな。
今回は、少し悲しい(かなしい)お話になってしまったけれど、みんなも機会(きかい)があったら「アンネの日記」を読んでほしいと思うのだな。自分が、アンネのような状況(じょうきょう)に置かれた時に、アンネのような行動(こうどう)がとれるのか、そして何よりも希望をすてずがんばることができるのか。
そんなことを考えてみてくれるとうれしいのだな。
写真提供:オランダ政府観光局
2001年10月号