
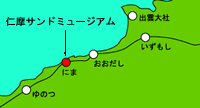 さて、今回(こんかい)もみんなといっしょに「時や時間(ときやじかん)」にかかわりのある場所(ばしょ)を訪ねて(たずねて)いこうと思うのだが、準備(じゅんび)はよろしいか。よいしょ。
さて、今回(こんかい)もみんなといっしょに「時や時間(ときやじかん)」にかかわりのある場所(ばしょ)を訪ねて(たずねて)いこうと思うのだが、準備(じゅんび)はよろしいか。よいしょ。
今回は世界一(せかいいち)の砂時計(すなどけい)のある日本の島根県邇摩郡仁摩町(しまねけんにまぐんにまちょう)に行ってみることにするのだな。この仁摩町には泣き砂(なきずな)で有名(ゆうめい)な琴ヶ浜(ことがはま)があり、それにちなんでつくられた「仁摩サンドミュージアム(にまサンドミュージアム)」に世界一の砂時計があるのだな。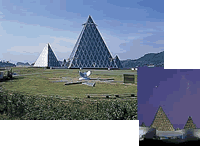
その砂時計の話に入る前に、何やら聞き(きき)慣れない(なれない)「泣き砂」についての説明(せつめい)をするのだな。「泣き砂」というのは海岸(かいがん)や砂漠(さばく)で、その砂の上を歩く(あるく)と小鳥(ことり)の声のような音がでる砂のことなのだな。日本はもちろん世界中にこの「泣き砂」はあって、日本では琴ヶ浜が有名なのだな。その「泣き砂」のことを多くの人に知ってもらおうと建てられた(たてられた)のが「仁摩サンドミュージアム」なのだな。
 そこにある世界一の砂時計が動き(うごき)始めた(はじめた)のは1991年の1月1日から。その日から止まる(とまる)ことなくずっと動き続けて(つづけて)いるのだな。さて、その大きさ(おおきさ)なのだが、高さ(たかさ)は5.2m、直径(ちょっけい)1m、砂の量(りょう)はなんと1トンというすごいものなのだな。この砂時計は1年かけて上から下へ、砂がゆっくりゆっくりと落ちて(おちて)ゆくのだな。そして、毎年(まいとし)大晦日(おおみそか:12月31日)になると町中(まちじゅう)の人たちが博物館(はくぶつかん)に集まって(あつまって)砂時計をひっくりかえすというのだから、この砂時計がいかに町の人たちに愛されて(あいされて)いるのかがわかるのだな。
そこにある世界一の砂時計が動き(うごき)始めた(はじめた)のは1991年の1月1日から。その日から止まる(とまる)ことなくずっと動き続けて(つづけて)いるのだな。さて、その大きさ(おおきさ)なのだが、高さ(たかさ)は5.2m、直径(ちょっけい)1m、砂の量(りょう)はなんと1トンというすごいものなのだな。この砂時計は1年かけて上から下へ、砂がゆっくりゆっくりと落ちて(おちて)ゆくのだな。そして、毎年(まいとし)大晦日(おおみそか:12月31日)になると町中(まちじゅう)の人たちが博物館(はくぶつかん)に集まって(あつまって)砂時計をひっくりかえすというのだから、この砂時計がいかに町の人たちに愛されて(あいされて)いるのかがわかるのだな。
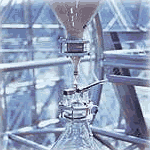
砂の通る「蜂の腰(はちのこし)」と呼ばれる(よばれる)部分(ぶぶん)は0.84mmという細さ(ほそさ)!ここに砂がつまらないようにするのにはとてもとても苦労(くろう)したということなのだな。その上、朝(あさ)と夜(ひる)の温度差(おんどさ)によって砂を入れているガラスの中の圧力(あつりょく)がかわってしまうのでコンピュータを使って(つかって)いつも圧力が一定(いってい)になるように調整(ちょうせつ)しているのだな。つまりは砂時計であっても、超(ちょう)ハイテクな砂時計なのだな。
さてこの「仁摩サンドミュージアム」には、この砂時計の他にも、人間の一生(いっしょう)や地球(ちきゅう)の歴史(れきし)といった時間を砂時計に置き換えたら(おきかえたら)どのぐらいの砂時計になるのかをわかりやすくパネルにした人生100年計(じんせい100ねんけい)と地球46億年計(ちきゅう46おくねんけい)というものもあるのだな。ちなみに地球46億年の砂時計を一年計と同じ砂、同じやり方でつくった場合(ばあい)高さは5000m、その中に入る砂の量は46億トンになるということなのだな。ふー、どっこらしょ。
ということで、今回は世界一の砂時計のある島根県邇摩郡仁摩町(しまねけんにまぐんにまちょう)「仁摩サンドミュージアム」に行ってみたのだが、いかがだったかな?
もし近く(ちかく)に住んで(すんで)いるお友だちは、是非(ぜひ)とも行ってみて、砂時計の実物(じつぶつ)を見てほしいのだな。
仁摩サンドミュージアム
〒699-2305
島根県邇摩郡仁摩町大字天河内町975
TEL:0854-88-3776 FAX:0854-88-3785
■入館時間:AM9:00〜PM4:30
■休館日:毎月第1水曜日
■入館料:大人700円、小・中学生350円
学校、子ども会など団体は100円 (小・中学生のみ)
http://www.nima-cho.ne.jp/museum/
|
2002年4月号