|
 さて、2000年6月から時(とき)にかかわる言葉(ことば)やことわざをご紹介(しょうかい)してきた、わがはいの「時の言葉(ときのことば)」ではあるが、今回(こんかい)からは少し(すこし)内容(ないよう)をかえて「有名人の残した時にかかわる言葉(ゆうめいじんののこしたときにかかわることば)」というものを取り上げて(とりあげて)いこうと思う(おもう)のである。 さて、2000年6月から時(とき)にかかわる言葉(ことば)やことわざをご紹介(しょうかい)してきた、わがはいの「時の言葉(ときのことば)」ではあるが、今回(こんかい)からは少し(すこし)内容(ないよう)をかえて「有名人の残した時にかかわる言葉(ゆうめいじんののこしたときにかかわることば)」というものを取り上げて(とりあげて)いこうと思う(おもう)のである。
言葉は「言霊(ことだま)」といって、そこには、その言葉を言った(いった)人間(にんげん)の魂(たましい)がこもっていると言われてる。心(こころ)して読んで(よんで)ほしいのである。フム。
では、さっそくはじめるとしよう。
第1回目は、1949年に日本人(にほんじん)として初めて(はじめて)「中間子理論(ちゅうかんしりろん)」でノーべル賞(しょう)を受賞(じゅしょう)した物理学者(ぶつりがくしゃ)、湯川秀樹博士(ゆかわひできはかせ)がのこした時にかかわる言葉をご紹介(しょうかい)するのである。
言葉を紹介する前に、まずは湯川秀樹博士について、少し。
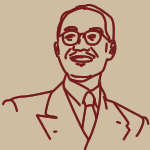 1907年、東京(とうきょう)で生まれ(うまれ)た。湯川博士の父親(ちちおや)は地理学者(ちりがくしゃ)であった。湯川博士は、京都帝国大学(きょうとていこくだいがく/今の京都大学)で理論物理学(りろんぶつりがく)を学び、わずか27歳の時(1935年)に原子核(げんしかく)の中にある陽子(ようし)と中性子(ちゅうせいし)をむすびつけている「中間子(ちゅうかんし)」を発見(はっけん)し「中間子理論」を発表。 1907年、東京(とうきょう)で生まれ(うまれ)た。湯川博士の父親(ちちおや)は地理学者(ちりがくしゃ)であった。湯川博士は、京都帝国大学(きょうとていこくだいがく/今の京都大学)で理論物理学(りろんぶつりがく)を学び、わずか27歳の時(1935年)に原子核(げんしかく)の中にある陽子(ようし)と中性子(ちゅうせいし)をむすびつけている「中間子(ちゅうかんし)」を発見(はっけん)し「中間子理論」を発表。
その後(ご)の素粒子論(そりゅうしろん)/理論物理学の一分野(いちぶんや)に大きな影響(えいきょう)をあたえたのである。
そしてこの「中間子理論」が認められて(みとめられて)、1949年のノーベル賞受賞となったのである。
1949年の日本は、まだ第二次世界大戦(だいにじせかいたいせん)が終わった(おわった)ばかりで、アメリカの占領下(せんりょうか)にあり、まだまだ人々の生活(せいかつ)も、国(くに)としての力(ちから)も、ととのっていないころだったのである。日本人全員(ぜんいん)が、生きる自信(じしん)をなくしていたのであるなぁ。
そんな時に湯川博士がなしとげたノーベル賞受賞というニュースは、日本人全員(ぜんいん)に希望(きぼう)と夢(ゆめ)をあたえたのである。
このノーベル賞受賞のきっかけになったのが、じつは湯川博士の奥(おく)さんのスミさんが言った「ノーベル賞というものは日本人はもらえないものなのですか?」という言葉からだったというのだから驚き(おどろき)なのである。
湯川さんはこの問い(とい)に「どんな国の人でも大きな発見をすればもらえる。きみが助けて(たすけて)くれたら、世界中の物理学者が解決(かいけつ)できないことをとく自信(じしん)がある。」と言い、それからこのノーベル賞受賞をご夫婦(ふうふ)の目標(もくひょう)として、ついに実現(じつげん)してしまったのである。
しかしながら、学会(がっかい)からほとんど相手(あいて)にされなかったころもあったということで、そんな時にも奥さんのスミさんは、湯川博士をはげましつづけたということなのである。すばらしい夫婦愛(ふうふあい)であるなぁ。フム。
それではこの湯川博士が残した時にかかわる言葉をご紹介するとしよう。
「一日生きることは、一歩進歩(いっぽしんぽ)することでありたい」である。
人間生きている以上(いじょう)、何かしら進歩(しんぽ)していかなければつまらないものである。
そして進歩し続けて(つづけて)いくためには、当然(とうぜん)、努力(どりょく)も勉強(べんきょう)もしていかなくてはならないのである。しかしながら本来(ほんらい)、人間というものはなまけものであり、またちょっとのことで落ち込んだり(おちこんだり)する弱い(よわい)生き物(いきもの)である。だからこそ、自分に対して(たいして)進歩することをつねに望んで(のぞんで)いなければいけないという意志(いし)もこの言葉の中にはこめられているのではないだろうか。フムフム。
さて、今回の言葉からしょくんは、なにを感じて(かんじて)くれたかな?
この言葉のもつ意味について、お父さん、お母さん、先生とも話してみてくれたまえ。
それでは次回(じかい)、またここで、お会い(おあい)しよう。きりつ!れい!フム。
2001年3月号
|