|
 さて、今回(こんかい)は今までにお話できなかった「時や時間(ときやじかん)」についてのことわざや格言(かくげん)をいくつか紹介(しょうかい)しようと思う。コホン。 さて、今回(こんかい)は今までにお話できなかった「時や時間(ときやじかん)」についてのことわざや格言(かくげん)をいくつか紹介(しょうかい)しようと思う。コホン。
ことわざや格言には、昔(むかし)の人たちの知恵(ちえ)がいっぱいつまっておる。どの言葉(ことば)もみんなが生きて(いきて)いく上できっと役(やく)にたつことだろう。フム。
ではさっそくいってみよう。
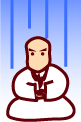 まずは「10年の修行、南無阿弥陀仏(10ねんのしゅぎょう、なむあみだぶつ)」である。これは昔(むかし)の朝鮮(ちょうせん)の言葉で「10年という長い(ながい)間(あいだ)修行(しゅぎょう)をしたお坊さん(ぼうさん)のような立派(りっぱ)な人間であっても、たった一夜(いちや)にして道(みち)を誤って(あやまって)しまうことがある」ということで「長い間の努力(どりょく)が一瞬(いっしゅん)で、なにもかもなくなってしまう」という意味(いみ)である。逆(ぎゃく)に言えば「長い間努力し、築き(きづき)上げたものを大切(たいせつ)にしたいのならば、つねに注意(ちゅうい)をしなさい」ということになるのである。受験勉強(じゅけんべんきょう)を一生懸命(いっしょうけんめい)やってきたというのに、肝心(かんじん)のテスト当日(とうじつ)に寝坊(ねぼう)してテストに間に合わなくてはどうにもならないからのう。フム。 まずは「10年の修行、南無阿弥陀仏(10ねんのしゅぎょう、なむあみだぶつ)」である。これは昔(むかし)の朝鮮(ちょうせん)の言葉で「10年という長い(ながい)間(あいだ)修行(しゅぎょう)をしたお坊さん(ぼうさん)のような立派(りっぱ)な人間であっても、たった一夜(いちや)にして道(みち)を誤って(あやまって)しまうことがある」ということで「長い間の努力(どりょく)が一瞬(いっしゅん)で、なにもかもなくなってしまう」という意味(いみ)である。逆(ぎゃく)に言えば「長い間努力し、築き(きづき)上げたものを大切(たいせつ)にしたいのならば、つねに注意(ちゅうい)をしなさい」ということになるのである。受験勉強(じゅけんべんきょう)を一生懸命(いっしょうけんめい)やってきたというのに、肝心(かんじん)のテスト当日(とうじつ)に寝坊(ねぼう)してテストに間に合わなくてはどうにもならないからのう。フム。
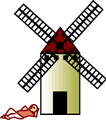 |
つづいて「粉(こな)ひき小屋(こや)でのんびりしたら、帰り(かえり)道は急がねば(いそがねば)ならない」である。これはスペインに伝わる(つたわる)言葉で、「時間をムダにつかってしまったら、どこかでその時間をとりもどさなくてはいけない」という意味である。
テストの話ばかりになって申し訳(もうしわけ)ないが、大事(だいじ)なテストの前日(ぜんじつ)にきちんと勉強(べんきょう)をしなければならないというのに、ついついテレビゲームに夢中(むちゅう)になってしまって、気づいたらもう夕方(ゆうがた)で、結局(けっきょく)、夜おそくまで勉強をしなければならなくなった。そんなことはないかな?
どんな人にも、1日には24時間という時間があって、それをどのように使うかは、その人の自由(じゆう)ではあるが、上手(じょうず)な使い方をすれば、よい1日がおくれるのである。 |
つぎは「双方の鐘を聞かねばならない(そうほうのかねをきかねばならない)」である。
これはスイスの言葉で「争い(あらそい)を終わらせる(おわらせる)ためには、両方(りょうほう)の話を聞かないといけない」という意味である。なぜ、この言葉が「時」と関係(かんけい)あるの?と思うかもしれないが、まあそう急がず(いそがず)、つづきを読んでほしいのである。
じつは、この言葉は、まだ時刻(じこく)を知らせる鐘が、正確(せいかく)ではなかった時代(じだい)のことを言っているのである。世界中(せかいじゅう)で正しい(ただしい)時間が使われ(つかわれ)、しかも誰(だれ)もが時計を持っているという今とちがって、昔(むかし)は、場所(ばしょ)によって時間がばらばらだったのである。その場所の時間で、鐘を鳴らし(ならし)時刻を知らせるのだから、ちょっと場所が違えば(ちがえば)、当然(とうぜん)、鐘の鳴る時刻もかわってしまうのである。だから、2カ所の鐘の音を聞いて、みんなは時刻を確認(かくにん)していたのである。片方(かたほう)の鐘の音だけではあてにならんからな。そのことから、この言葉が生まれたのである。
わかってくれたかな?
さて、今回紹介した言葉からしょくんは、なにを感じてくれたかな。教室(きょうしつ)のみんなや、先生、お父さん、お母さんとも話してみてくれたまえ。コホン。
それでは、次回、またここでお会いしよう。きりつ!れい!フム。
参考文献
「時と時計の百科事典」織田一朗:著
2001年7月号
|