|
 さて、いつもいつもわりとまじめなお話ばかりしているので、今回はちょっとくだけて「落語(らくご)」のお話で諸君(しょくん)の心をちょびっとなごませてみたいと思うのである。 さて、いつもいつもわりとまじめなお話ばかりしているので、今回はちょっとくだけて「落語(らくご)」のお話で諸君(しょくん)の心をちょびっとなごませてみたいと思うのである。
笑い(わらい)というものは、心の栄養(えいよう)であるからなぁ。
古典落語(こてんらくご)に時刻(じこく)を聞いて(きいて)そば代(だい)をごまかすという「時そば(ときそば)」という有名(ゆうめい)な噺(はなし)があるのだが、この「時そば」を聞いて笑うためには、江戸時代(えどじだい)の時刻制度(じこくせいど)を知らないと、その面白さ(おもしろさ)がわからないのである。
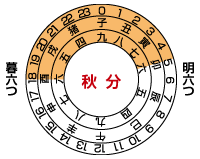 |
江戸時代には、十二支(じゅうにし)で時刻を言う呼び方(よびかた)と、数で時刻を言う呼び方の両方(りょうほう)が使われていて、数で言う呼び方は、その当時(とうじ)、多くの人に時刻を知らせるために使われていた時鐘(じしょう)の鐘が鳴らされる回数(かいすう)をもとにして「八つ」とか「九つ」と言う言い方をしていたのである。コホン。
この鐘を打つ回数は、九つから始まって(はじまって)順々(じゅんじゅん)に減っていき、四つで終わるきまりになっていたのである。その頃使われていた十二支による時刻と、時鐘による時刻との関係(かんけい)は図のようになっているのである。わかってくれたかな?
|
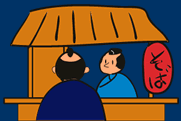 それでは、ここから「時そば」のお話をしよう。
それでは、ここから「時そば」のお話をしよう。
江戸の町で、ある男が真夜中(まよなか)の九つ過ぎ(時鐘が9回つかれる時刻)に屋台(やたい)でそばを頼み(たのみ)、そば屋をさんざんほめたあとで、「ところで勘定(かんじょう/ねだん)はいくらだい?」と聞くのである。するとそば屋は、いい気分(きぶん)で「ヘイ。十六文(じゅうろくもん)でございます」「こんなにうまいのに安い(やすい)ねぇ」と男はおだてる。そして男はそば屋の手に小銭(こぜに)をひとつずつ「ひい、ふう、みい、・・・」と数えながらわたしていくのだけれど、八つめまでいった時に突然(とつぜん)そば屋に「ところで今、何時(なんどき)だい?」と聞くとそば屋はついつられて「ヘイ。九つで」と答える。すると男は「そうかい。十、十一・・・十六文」と一文をごまかして帰ってしまうのである。九つ目をうまくそば屋に言わせることで、一文を得(とく)するというなんともせこい作戦(さくせん)なのだが、目のつけどころがいいのである。さて、「時そば」の面白さはここから。ちょうどその時に、 別(べつ)の男が、うまく一文をごまかした男の様子を見ていて、さっそく自分もまねをしてみようと思うのである。次(つぎ)の日に、そば屋に行き、そば屋をほめまくり「ところで、勘定はいくらだい?」「ヘイ。十六文でございます」「安いねぇ。ちょいと手を出してくれ」と同じように小銭を「ひい、ふう、みい、・・・・」と数えながらわたし、八文までいった時に「ところで今何時だい?」と聞くと「ヘイ。四つで」「そうかい、五つ、六つ・・・十六文」「毎度ありがとうございます」と、時刻を確かめずにやってしまったために、四文もソンしてしまったというオチになるのである。しかも「四つ」というのは、鐘を鳴らす回数では最も少ない回数で、このマヌケな男は、大損(おおぞん)をしてしまったということなのである。今の「〜時」のようにきちんと言う時刻制度では、このようなことはおきようがないのだがね。 別(べつ)の男が、うまく一文をごまかした男の様子を見ていて、さっそく自分もまねをしてみようと思うのである。次(つぎ)の日に、そば屋に行き、そば屋をほめまくり「ところで、勘定はいくらだい?」「ヘイ。十六文でございます」「安いねぇ。ちょいと手を出してくれ」と同じように小銭を「ひい、ふう、みい、・・・・」と数えながらわたし、八文までいった時に「ところで今何時だい?」と聞くと「ヘイ。四つで」「そうかい、五つ、六つ・・・十六文」「毎度ありがとうございます」と、時刻を確かめずにやってしまったために、四文もソンしてしまったというオチになるのである。しかも「四つ」というのは、鐘を鳴らす回数では最も少ない回数で、このマヌケな男は、大損(おおぞん)をしてしまったということなのである。今の「〜時」のようにきちんと言う時刻制度では、このようなことはおきようがないのだがね。
さて、言葉というものは時代とともにその使われ方がかわっていったり、またその言葉そのものが使われなくなったりということもあるのである。諸君(しょくん)も、お父さん、お母さんと話しをしている時など「ふるくさい言い方」とか「いまどきそんなこと言わないよ」とかよく言ったりするんじゃないかな。ま、それは仕方(しかた)のないことである。
ということで、今回はここまで。
次回、またここでお会いしよう。きりつ!れい!フム。
参考文献
「時計にはなぜ誤差が出てくるか」織田一朗:著
2001年10月号
|