|
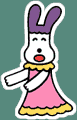 みなさま、1ヶ月ぶりのごぶさたでございます。図工(ずこう)のマルチン先生(せんせい)と、ひと月(つき)交代(こうたい)で音楽(おんがく)の授業(じゅぎょう)を担当(たんとう)させていただいておりますマーリンリンともうします。今回(こんかい)はわたくしのばんでございます。 みなさま、1ヶ月ぶりのごぶさたでございます。図工(ずこう)のマルチン先生(せんせい)と、ひと月(つき)交代(こうたい)で音楽(おんがく)の授業(じゅぎょう)を担当(たんとう)させていただいておりますマーリンリンともうします。今回(こんかい)はわたくしのばんでございます。
これから時と音楽についてのお勉強(べんきょう)をしていきたいと思い(おもい)ますわ。
今回は、みなさまもよくごぞんじの「メトロノーム」についてですわ。
学校(がっこう)の音楽の授業などで、リズムを合わせる(あわせる)時に使ったり(つかったり)、ピアノをやってらっしゃる方でしたら、練習(れんしゅう)の時にはかかせないものですわね。
では、どうしてこの「メトロノーム」が時や時計(とけい)と関係(かんけい)があるのか?
みなさま、きっと不思議(ふしぎ)に思われるかもしれませんわね。
じつは、「メトロノーム」に使われている技術(ぎじゅつ)は、時計の技術とすごくかかわりがあるのでございます。
その証拠(しょうこ)と言ってはへんですけれど、セイコーでは精度(せいど)の高い(たかい)メトロノームを時計の技術を使って作って(つくって)いるのですわよ。
それでは、少し(すこし)ずつわかりやすくご説明(せつめい)いたしますわ。
メトロノームには大きくわけて機械式(きかいしき)のものと電子式(でんししき)のものがありますのよ。
まず機械式のメトロノームに使われている時計の技術についてですわ。
 |
機械式のメトロノームの多くは、写真(しゃしん)にあるような形(かたち)をしていますわね。
まんなかの動く(うごく)棒(ぼう)についている遊錘(ゆうすい)と呼ばれる(よばれる)おもりを動かすことでカチコチときざまれるリズムが、速く(はやく)なったり、遅く(おそく)なったり。
これって何か(なにか)を思いうかべませんこと?
そう、柱時計(はしらどけい)とかの振り子(ふりこ)ですわね。
さきほど「まんなかの動く棒」と書いた(かいた)部品(ぶひん)は「振り子」と呼ばれているのですよ。 |
それでは、次は電子式のメトロノームですわ。
 |
電子式のものの多くは、こちらの写真にあるような形をしていますわ。
電子音(でんしおん)と発光LED(はっこうエルイーディー)がリズムをきざんでくれるのですわ。
この電子式メトロノームには、時計に使われているクォーツと呼ばれる振動子(しんどうし)が使われて、時計の針(はり)を動かすかわりに電子音と光(ひかり)を規則(きそく)正しく(ただしく)出しているのですわ。 |
でも今ではちょっと見ると、機械式のメトロノームのような形をしていても、こちらの写真のように電子式のものもあるのですわ。
この写真でメトロノームの各部品(かくぶひん)の名前(なまえ)を確認(かくにん)してくださいね。
メトロノームと時計の関係、みなさまわかっていただけましたかしら。
それでは今回はここまででございます。また次回(じかい)にお会い(おあい)しましょう。
では、ごきげんよう。
2001年3月号
|