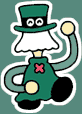 わがはいのページへようこそ。
わがはいのページへようこそ。
これから一緒(いっしょ)に、「時の歴史(ときのれきし)」を勉強(べんきょう)していこうかのう。
くどいようじゃが、「時の歴史」といってもいろいろなものがあるが、今回(こんかい)も「時計の歴史の話(はなし)」じゃ。人が最初(さいしょ)に作った(つくった)時計は、日時計(ひどけい)だと前回(ぜんかい)に勉強したが、日時計には大きな欠点(けってん/わるいところ)があったのじゃ。
そう2000年6月の質問(しつもん)で、みんなが答えて(こたえて)くれたのう。
答えはいくつかあるが一番(いちばん)の欠点は「太陽(たいよう)がでている時にしか使えない(つかえない)」ということなんじゃ。
人の説明(せいかつ)が、だんだんと複雑(ふくざつ)になってくると、夜(よる)も時間を知る(しる)必要(ひつよう)がでてくるのじゃ。そのために作られたのが「水時計(みずどけい)」なんじゃ。
ここからは、その水時計の歴史をおはなししてみようかのう。
 もっとも古い(ふるい)かたちの水時計は、熱帯(ねったい/ものすごくあついちほう)のマレー地方(ちほう)で作られたそうじゃ。2つにわったヤシの実(み)のからの真ん中(まんなか)に穴(あな)をあけて、水に浮かべ(うかべ)、その穴から少しずつ(すこしずつ)水が入って(はいって)いって、沈んで(しずんで)しまったら、そこでたいこをたたいて、みんなに時間を知らせた(しらせた)というものなんじゃ。
もっとも古い(ふるい)かたちの水時計は、熱帯(ねったい/ものすごくあついちほう)のマレー地方(ちほう)で作られたそうじゃ。2つにわったヤシの実(み)のからの真ん中(まんなか)に穴(あな)をあけて、水に浮かべ(うかべ)、その穴から少しずつ(すこしずつ)水が入って(はいって)いって、沈んで(しずんで)しまったら、そこでたいこをたたいて、みんなに時間を知らせた(しらせた)というものなんじゃ。
沈むまでずっとみている人もごくろうさまじゃのう。そのほかにも北インドでは、銅(どう)でできた器(うつわ)のそこに、穴をあけて、それを逆さ(さかさ)にして水に浮かべ、同じ(おなじ)ように使ったということなんじゃ。
 それが、今から3400年ぐらい前(まえ)のエジプトでは、穴のあいた器から水がゆっくりしたたり落ちる(おちる)のを利用(りよう)した水時計が作られたのじゃ。この水時計は石膏製(せっこうせい)で、今ものこっているんじゃ。アメノフィス一世(いっせい)が使ったといわれておる。
それが、今から3400年ぐらい前(まえ)のエジプトでは、穴のあいた器から水がゆっくりしたたり落ちる(おちる)のを利用(りよう)した水時計が作られたのじゃ。この水時計は石膏製(せっこうせい)で、今ものこっているんじゃ。アメノフィス一世(いっせい)が使ったといわれておる。
この水時計は器の内側(うちがわ)にも、めもりがつけられているので、夜(よる)や暗い(くらい)ところでも、手でさわることで時間がわかるように作られていたんじゃ。人はこの水時計で日時計ではわからなかった夜の時間も知ることができるようになったのじゃな。
水時計はそれからいろいろと考え(かんがえ)られて、機械化(きかいか)されて、目覚まし(めざまし)時計になったり、ふえやかねをつかって、規則(きそく)正しい(ただしい)時間を自動的(じどうてき)に多く(おおく)の人につたえられるようなものまでできたのじゃ。
すごいことじゃのう。
とくに、今から2200年ぐらい前のアレキサンドリアのクテシビウスという人が作った水時計によって、水時計はほぼ完成(かんせい)されたものとなり、長い(ながい)時代(じだい)にわたってひろく使われ、機械式(きかいしき)の時計が生まれて(うまれて)からも、しばらくはすたれなかったというんじゃから、すごいことじゃのう。
このクテシビウスの水時計は、2000年7月「時の資料館」でその仕組み(しくみ)を学んで(まなんで)みようかのう。ぜひみてくれたまえ。
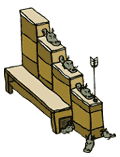 日本の水時計の歴史は、今から1300年前に天智天皇(てんじてんのう)が漏刻(ろうこく)という水時計を作らせて、かねをたたいて時を知らせたといわれているのじゃ。
日本の水時計の歴史は、今から1300年前に天智天皇(てんじてんのう)が漏刻(ろうこく)という水時計を作らせて、かねをたたいて時を知らせたといわれているのじゃ。
右の図(ず)を見て、その仕組みを考えてみてくれんかのう。
その漏刻を使った日が、今の暦(こよみ)でいうと6月10日であったのじゃ。
だから、その日を「時の記念日」としてきめたんじゃ。
かけあしで説明(せつめい)してしまったが、わかっていただけたかのう。
次回は砂時計(すなどけい)について、学んでみようかのう。
2000年7月号