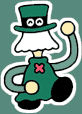 わがはいのページへようこそ。
わがはいのページへようこそ。
今回(こんかい)は「腕時計(うでとけい)の自動巻き(じどうまき)の仕組み(しくみ)」について学んで(まなんで)いこうかのう。「自動巻き」というのは、手(て)でゼンマイを巻かなくても時計を振る(ふる)と回転錘(かいてんすい)という一種(いっしゅ)の分銅(ぶんどう/おもり)が左右(さゆう)に回転(かいてん)し、どちらに回って(まわって)もつねに角穴車(かくあなぐるま)を一定(いってい)の方向(ほうこう)に回転させ、ゼンマイを巻き上げる(まきあげる)仕組みになっているんじゃ。
この自動巻き上げの仕組みには、たくさんの方式(ほうしき)があり、とてもすべてを紹介(しょうかい)しきれるものではないので、ここではセイコーの時計に使われた(つかわれた)3つの方式を説明(せつめい)したいと思うのじゃ。ちなみに、この自動巻きの仕組みを最初(さいしょ)に考え出した(かんがえた)のは、ジョン・ハーウッドという人物(じんぶつ)で1924年に特許(とっきょ)を取得(しゅとく)しておるのじゃな。
それでは、セイコーの3つの自動巻きの方式を見ていくことにしよう。
| 1)マジックレバー方式
|
この方式は、下(した)のイラストのような仕組みになっていて、半円形(はんえんけい)をした部分(ぶぶん)が「回転錘(かいてんすい)」と呼ばれて(よばれて)いるんじゃ。
これは時計の周辺(しゅうへん)にいくほど重く(おもく)なっていて、時計をはめて腕を動かすと左右に揺れ(ゆれ)たり、回転したりするんじゃ。
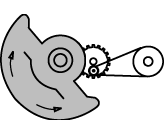 |
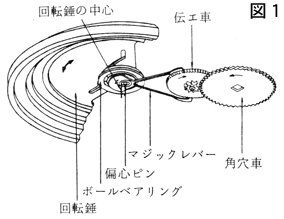 |
「角穴車」というのは、ゼンマイを巻くための歯車(はぐるま)で、この歯車は一定の方向に回してあげなければゼンマイを巻くことができないので、一定の方向の正しい(ただしい)回転に修正(しゅうせい)してあげなくてはならないのじゃ。その役目(やくめ)を果たす(はたす)のがピンセットのような形(かたち)をした「マジックレバー」と「伝え車(つたえぐるま)」なのじゃ。
この「マジックレバー」の動きについては、「時の資料室(ときのしりょうしつ)」に、じつにわかりやすい動くモデル図がのっておる。ぜひ、そちらで動きのしくみを学んで(まなんで)ほしいのじゃ。
|
| 2)遊動車方式(ゆうどうぐるまほうしき) |
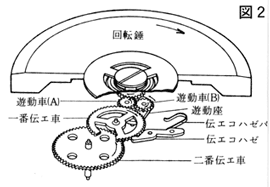 |
この方式は、図2のような仕組みになっていて、「回転錘」が右回転(みぎかいてん)すると、「遊動車(ゆうどうぐるま)」(A)は左回転(ひだりかいてん)して、「一番伝え車(いちばんつたえぐるま)」と噛み合い(かみあい)、「二番伝え車」をへて、「香箱車(こうばこぐるま)」のゼンマイを巻き上げるのじゃ。
この時、「遊動車」(B)は空回り(からまわり)をしておる。
「回転錘」が左回転した時には、逆に「遊動車」(B)が噛み合うという仕組みになっておるのじゃ。
その2つの「遊動車」のはたらきで、つねに一方向(いちほうこう)にゼンマイを巻き上げる仕組みになっておるんじゃ。
図2にある「伝えコハゼ」という部品は、「一番伝え車」が逆転(ぎゃくてん)するのをふせぐためにつけられておるのじゃ。
|
| 3)切換伝え車方式(きりかえつたえぐるまほうしき) |
|
この方式は図3のような切換伝え車という部品が、図4のような組み合わせで、回転錘の動きが右に回転しても、左に回転しても、一定の方向で一番伝え車に回転を伝え、ゼンマイを巻き上げるような仕組みになっているんじゃ。
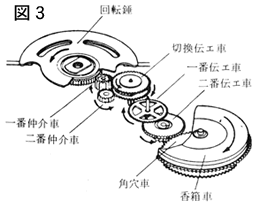 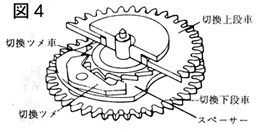
図で見ると大きく見えるが、これらの一番伝え車などの部品の大きさは1ミリ以下(いか)の世界(せかい)なのじゃ。腕時計が精密機械(せいみつきかい)と言われる理由(りゆう)が、おわかりいただけるかのう?
これらの仕組みを使った自動巻き腕時計は、1960年代(ねんだい)からクォーツが一般(いっぱん)に普及(ふきゅう)する70年代前半(ぜんはん)まで、全盛期(ぜんせいき)をむかえたのじゃな。
|
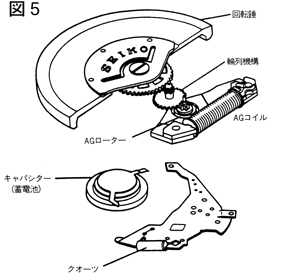 |
そして、クォーツウォッチの時代(じだい)になると、電池切れ(でんちぎれ)の心配(しんぱい)のない腕時計がのぞまれるようになったのじゃ。そこで機械式腕時計の自動巻きの技術(ぎじゅつ)を利用して、電気(でんき)を発電(はつでん)するようになったのじゃ。
その仕組みが1988年に開発された「キネティック」と言われるものなんじゃ。仕組みは図5をみていただきたいのじゃな。
AGローターといわれる部品が高速(こうそく)回転することで、AGコイルに電流(でんりゅう)が流れる(ながれる)仕組みなんじゃ。そこでつくられた電気は、キャパシターと言われる蓄電池(ちくでんち)にためられるようになっているのじゃ。
|
さて、今回はものすごく専門的(せんもんてき)なお話になってしまったが、わかっていただけただかのう。
しかしながら時計の歴史(れきし)をたどっていく時に、この「自動巻き」の仕組みは避けて(さけて)は通れない(とおれない)ものなのじゃ。最後(さいご)まで読んで(よんで)くれてありがとう。
わからないところがあったら質問(しつもん)をメールで送ってくれたまえ。では、今回はここまでじゃ。
次回(じかい)はなにが出てくるか。みんな楽しみにまっててくれたまえ。
※参考文献
「時と時計の百科事典」織田一朗
「SEIKO WACTH 機械時計編」株式会社 第二精工舎
2001年2月号