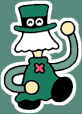 今回(こんかい)もわがはいのページへようこそ。
今回(こんかい)もわがはいのページへようこそ。
今月は「デジタル時計」について学んで(まなんで)いこうかのう。
今はもう当たり前(あたりまえだ)になってしまった液晶(えきしょう)ディスプレイを使って(つかって)時間を数字(すうじ)であらわすデジタル時計ではあるが、このデジタル時計がこの世(よ)に出るまではいろいろな試行錯誤(しこうさくご)があったのだな。
時間を針(はり)ではなく数字でデジタルにあらわしたいという動きが世界的(せかいてき)に高まったのが1960年代(ねんだい)の終わり(おわり)ごろだったのじゃ。
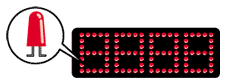 1968年に右(みぎ)のイラストにあるようなLED(えるいーでぃー)(発光(はっこう)ダイオード)を使ったデジタル時計「パルサー」をアメリカのハミルトン社(しゃ)が発売(はつばい)して世界的な話題(わだい)になったのだ。しかし、なにせ光(ひかり)が弱い(よわい)ために昼間(ひるま)は見にくく、しかも電池(でんわ)もすぐ切れて(きれて)しまうというものだったのじゃ。ま、そんな理由(りゆう)から、そのあとにつづくメーカーがあらわれずに、LED方式のデジタル時計はすがたを消して(けして)しまったわけじゃ。
1968年に右(みぎ)のイラストにあるようなLED(えるいーでぃー)(発光(はっこう)ダイオード)を使ったデジタル時計「パルサー」をアメリカのハミルトン社(しゃ)が発売(はつばい)して世界的な話題(わだい)になったのだ。しかし、なにせ光(ひかり)が弱い(よわい)ために昼間(ひるま)は見にくく、しかも電池(でんわ)もすぐ切れて(きれて)しまうというものだったのじゃ。ま、そんな理由(りゆう)から、そのあとにつづくメーカーがあらわれずに、LED方式のデジタル時計はすがたを消して(けして)しまったわけじゃ。
その「パルサー」発売と同じ(おなじ)1968年にアメリカのRCA社(あーるしーえーしゃ)というところが液晶ディスプレイを発表。日本のセイコーはさっそくその技術(ぎじゅつ)を時計に利用(りよう)しようと考え、アメリカのRCA社を訪ね(たずね)たのじゃ。
アメリカでいろいろと液晶ディスプレイについて調査(ちょうさ)したセイコーの技術者(ぎじゅつしゃ)は、日本に帰り(かえり)すぐに研究・開発(けんきゅう・かいはつ)をすすめたわけじゃ。その時すすめていた液晶ディスプレイの方式(ほうしき)はDSM(でぃーえすえむ)方式と呼ばれるもので、電圧(でんあつ)をかけると電子(でんし)が鉄砲玉(てっぽうだま)のように飛び出して(とびだして)液晶にぶつかって数字などのかたちをあらわすという方式だったんじゃ。
ところが、その年の年末(ねんまつ)にある出来事(できごと)がおこったのじゃ。それはアメリカのRCA社に行った時に知り合った(しりあった)ケント大学(だいがく)のファーガソン教授(きょうじゅ)という人から、FEM(えふいーえむ)方式という別の液晶ディスプレイのサンプルが届いたのじゃ。それ見たセイコーの技術者は、そのすばらしさに、それまで研究してきたDSM方式をあっさり捨てて、FEM方式に変えてデジタル時計を作ることに決めたのだな。この時のセイコーの技術者の判断(はんだん)が、1973年に世の中に発売された液晶デジタルウォッチでの世界的成功(せいこう)につながったのじゃ。液晶ディスプレイの主流(しゅりゅう)はFEM方式になったのじゃ。FEM方式は文字などをくっきりと出すことができ、しかも電池(でんち)も長持ち(ながもち)するのじゃ。まさに時計向き(むき)の液晶ディスプレイじゃな。
ちなみに世界初のデジタルウオッチはアメリカのマイクロマ社が発売したDSM方式のものだったのじゃけれどな。
 |
ここの写真にあるのが、1973年に発売された液晶デジタルクォーツの05LCじゃ。
とても28年も前のデザインとは思えない未来的(みらいてき)なものじゃのう。
これは大ヒットになったセイコーの腕時計「スプーン」のもとになったとも言われておる。今見ても全然古さを感じさせないデザインじゃな。
しかしながら当時の技術でこの形を作るのはものすごい大変(たいへん)なことだったとのことなのじゃ。
|
こうしてはじまったデジタル時計じゃが、計算機付き(けいさんきつき)のもの、テレビ付きのもの、コンピュータとつながるもの、ポケベル付きのものなど実に(じつに)いろいろなものが作られたのじゃ。ただしあまりにも機能(きのう)をつめこみすぎたために使い(つかい)にくくなってしまったものもあったようじゃがのう。
さて、今回はここまでじゃ。そうそう、今回の「時の資料室」ではこの液晶ディスプレイの仕組みをセシモッチ教授が説明(せつめい)してくれているから、ぜひそちらものぞいてほしいのじゃ。
参考文献/グッズプレススペシャル「THE SEIKO BOOK」
2001年4月号