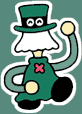 今回(こんかい)もわがはいのページへようこそ。
今回(こんかい)もわがはいのページへようこそ。
今回は人類(じんるい)が作り(つくり)出した(だした)もっとも正確(せいかく)な時計「原子時計(げんしどけい)」について学んで(まんんで)いこうかのう。
前に「クォーツ時計」についてお話をした時に、精度(せいど)つまり時計の正確さを決める(きめる)ポイントは、時計に使われて(つかわれて)いる水晶振動子(すいしょうしんどうし)の振動数(しんどうすう)が関係(かんけい)していることをお話(はなし)したと思う(おもう)のだが、みんなおぼえているかのう。
 ふつうのクォーツ時計でも、1月(ひとつき)にプラスマイナス15秒(びょう)以内(いない)という精度になったのは、時計に入っている水晶振動子が、1秒間に3万2768回という高い振動数を出せるようになったからなんじゃ。
ふつうのクォーツ時計でも、1月(ひとつき)にプラスマイナス15秒(びょう)以内(いない)という精度になったのは、時計に入っている水晶振動子が、1秒間に3万2768回という高い振動数を出せるようになったからなんじゃ。
ちなみに「世界初(せいかいはつ)のクォーツ腕時計のセイコーアストロン」に使われていた水晶振動子の振動数は8192回だったんじゃぞ。高級品(こうきゅうひん)のクオーツ腕時計(うでどけい)には、さらに高い19万6608回のものもあるんじゃ。
それでは人類が作り出したもっとも正確な「原子時計」は、何を使って高い振動数を出しているのか?
それは今の1秒という単位を決めるもとになっているセシウム原子なんじゃ。
セシウム原子は水晶発振装置(すいしょうはっしんそうち)で作った91億9263万1770回に近い周波数(しゅうはすう)の電磁波(でんじは)をあてると、その電波(でんぱ)を吸収(きゅうしゅう)する性質(せいしつ)があるのじゃが、あてている電波の振動数が少しでもずれてしまうと、吸収しなくなるんじゃ。そうするとすぐに、水晶発振装置に信号(しんごう)をおくりそのずれをなおすという仕組み(しくみ)になっておるのじゃ。
この修正(しゅうせい)がつねに行われることによって、正確な振動数をキープし、30万年〜150万年にたった1秒しかくるわないというものすごい精度を実現(じつげん)したんじゃ。
なにやらむずかしい言葉がたくさん出てきたが、わかっていただけたかのう?
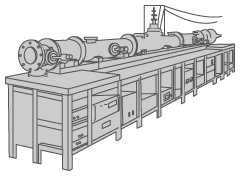 この「原子時計」が初めて発明(はつめい)されたのは1949年のこと。ワシントンにあるアメリカ海軍天文台(かいぐんてんもんだい)のウィリアム・マルコビッツという人なんじゃ。それは今、世界中で使われている方式(ほうしき)とはちょっとちがったものだったんじゃ。
この「原子時計」が初めて発明(はつめい)されたのは1949年のこと。ワシントンにあるアメリカ海軍天文台(かいぐんてんもんだい)のウィリアム・マルコビッツという人なんじゃ。それは今、世界中で使われている方式(ほうしき)とはちょっとちがったものだったんじゃ。
今、使われているセシウム原子時計は、それからまもなくイギリスの国立物理研究所(こくりつぶつりけんきゅしょ)のルイス・エッセンが試作(しさく)に成功(せいこう)したんじゃ。
日本の標準時(ひょうじゅんじ)を決めている(きめている)のもセシウム原子時計で、東京都(とうきょうと)の小金井市(こがねいし)にある郵政省通信研究所(ゆうせいしょうつうしんけんきゅしょ)にあるものなんじゃ。ここではレーザーを使うことにより150万年に1秒しかくるわないという精度を出しているんじゃ。その上、ミリ秒波(びょうは)パルサーという特殊(とくしゅ)な天体(てんたい)を利用(りよう)することで、1億(おく)年に1秒しかくるわないというところまで精度を高めようとしているんじゃ。これもすごいことじゃのう。
この郵政省通信総合研究所のセシウム原子時計の決めた1秒は、茨城県猿島郡三和町(いばらぎけんさしまぐんさんわちょう)からJJY標準電波(ジェイジェイワイひゅうじゅんでんぱ)が発信(はっしん)されているんじゃ。
最近(さいきん)はやっている「電波時計(でんぱどけい)」はみんなこのJJY準電波を受信(じゅしん)しているんじゃ。そう考えてみると、なにやら自分たちとは関係のないように思える「原子時計」も身近(みじか)な感じがしてくるものじゃのう。
さて「日時計(ひどけい)」にはじまり1年間かけて「原子時計」まで「時計の歴史(ときのれきし)」をみんなといっしょに学んできたわけじゃが、いかがだったかのう?
次回(じかい)みんなとお会い(おあい)するのは2001年7月の「夏の時の教室(なつのときのきょうしつ)」じゃ。それまでみんな元気(げんき)でな。
それから、「時の資料館」では「セシウム原子時計の原理(げんり)」についてじゃ。ぜひのぞいてみてほしいのじゃ。
参考資料/「時と時計の百科事典」・グッズプレススペシャル「THE SEIKO
BOOK」
2001年5月号