 さて、今回(こんかい)もみんなといっしょに時や時間にかかわりのある場所(ばしょ)をたずねていこうと思う(おもう)のだが、準備(じゅんび)はよろしいか。よいしょ。
さて、今回(こんかい)もみんなといっしょに時や時間にかかわりのある場所(ばしょ)をたずねていこうと思う(おもう)のだが、準備(じゅんび)はよろしいか。よいしょ。
さて、今回は「日本で初めて時計がやってきた場所(にほんではじめてとけいがやってきたばしょ)」に行って(いって)みたいと思うのだな。
この時計伝来(とけいでんんらい)については、前回(ぜんかい)の「時の歴史(れきし)」の「和時計(わどけい)」のところでも、カンタンにふれてはいるけれど、ここではもう少し(すこし)くわしくやってみたいのだな。よいしょ。
 日本人が初めて、西洋(せいよう)の機械式時計(きかいしきどけい)にせっしたのは、天文(てんぶん)20年(1551年)にスペインの宣教師(せんきょうし)フランシスコ・ザビエルが、山口(山口県:やまぐちけん)の領主(りょうしゅ/その地域(ちいき)を治めて(おさめて)いる人)の大内義隆(おおうちよしたか)に時計を献上(けんじょう/位(くらい)の高い人にものをあげること)した時(とき)であるといわれているのだな。
日本人が初めて、西洋(せいよう)の機械式時計(きかいしきどけい)にせっしたのは、天文(てんぶん)20年(1551年)にスペインの宣教師(せんきょうし)フランシスコ・ザビエルが、山口(山口県:やまぐちけん)の領主(りょうしゅ/その地域(ちいき)を治めて(おさめて)いる人)の大内義隆(おおうちよしたか)に時計を献上(けんじょう/位(くらい)の高い人にものをあげること)した時(とき)であるといわれているのだな。
となると、「日本に初めて時計がやってきた場所」というのは、「山口」になるんじゃないか?と思うだろうが、ちょっと待ってほしいのだな。じつは、フランシスコ・ザビエルは、日本に来て(きて)最初に山口に着いた(ついた)わけではないのだな。
ザビエルは、まず鹿児島(かごしま)に着き(つき)、そこで島津貴久(しまづたかひさ)に会い(あい)、ここで布教活動(ふきょうかつどう)を始めたのだな。
けれど、島津氏から布教を禁止(きんし)されてしまったため、長崎(ながさき)の平戸(ひらと)、山口、堺(さかい)をとおって、京都(きょうと)に行き、そこでキリスト教の布教をしようと思ったのだな。ところが、その時代(じだい)、日本の都(みやこ)である京都は、あいつぐ戦乱(せんらん)のおかげで、荒れ果てて(あれはてて)しまっていてとても、ザビエルのキリスト教の教え(おしえ)に耳(みみ)をかたむけてくれる人はいなかったのだな。そこで、また山口にまいもどり、その時の領主であった大内義隆に時計を始めとする多く(おおくの)の献上品(けんじょうひん)とともに、キリスト教の布教を願い出た(ねがいでた)わけなのだな。
ご苦労(くろう)なことなのだな。よいしょ。 |
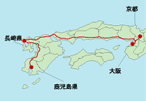 |
ここまでの説明(せつめい)で、みんなはわかってくれたかな。「初めて日本に時計がやって来た場所」
それは正確(せいかく)に言えば「鹿児島」ということになるのだな。どっこらしょ。
さて、この時、献上された時計が、今、世界的にみとめられる日本の時計の歴史の始まりだったといったら、みんなきっとおどろくんじゃないかな?じつは、この時計をもらった大内義隆は、とにかくめちゃくちゃによろこんで、ザビエルにたくさんの金品(きんぴん)をあげようとしたのだが、ザビエルはまったくうけとらなかったのだな。
その態度(たいど)に感心(かんしん)した大内義隆が、山口の町中(まちじゅう)に「ザビエルの新宗教(しんしゅうきょう)の布教については、まったくの自由(じゆう)で、だれでも入りたければ、入ってかまわない」という札(ふだ)までたて、応援(おうえん)したのだな。その結果(けっか)、キリスト教はあっという間(ま)に広がって(ひろがって)、多く(おおく)の信徒(しんと)が生まれた(うまれた)のだな。そうなると、ヨーロッパの宣教師の数(かず)がたりなくなり、日本人の宣教師を育てる(そだてる)ために、各地(かくち)に学校(がっこう)ができたのだな。
その学校で時計作り(づくり)の技術(ぎじゅつ)が伝え(つたえ)られ、時計作りが日本に根(ね)をおろすことになったのだな。
ふーっ。
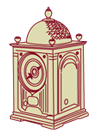 その後(のち)、江戸時代(えどじだい)に鎖国政策(さこくせいさく)があり、日本の時計は和時計として、世界(せかい)の時計の流れ(ながれ)とは、まったく別(べつ)の進化(しんか)をするのだけれど、前回(ぜんかい)の「時の歴史」でも見てもらったように、その技術というのはおどろくべきものがあったのだな。そういった技術のつみかさねがあったからこそ、今の日本の素晴らしい(すばらしい)時計の技術につながっているんじゃないのかな。
その後(のち)、江戸時代(えどじだい)に鎖国政策(さこくせいさく)があり、日本の時計は和時計として、世界(せかい)の時計の流れ(ながれ)とは、まったく別(べつ)の進化(しんか)をするのだけれど、前回(ぜんかい)の「時の歴史」でも見てもらったように、その技術というのはおどろくべきものがあったのだな。そういった技術のつみかさねがあったからこそ、今の日本の素晴らしい(すばらしい)時計の技術につながっているんじゃないのかな。
では、今回はここまでちょっと歴史のような話になってしまったかもしれないが、地理と歴史というものが切って(きって)も切れない関係(かんけい)にあるものなのだな。
さぁ、今回はこんなところで、おしまいなのだな。次回(じかい)はいったいどこにいくのやら。
楽しみ(たのしみ)にまっててくれるとうれしいのだな。よっこらしょ。
(参考文献)
「歴史の陰に時計あり!!」織田一朗
「時計」小田幸子
2001年2月号