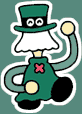 わがはいのページへようこそ。
わがはいのページへようこそ。
今回(こんかい)は「和時計(わどけい)」を紹介(しょうかい)していこうかのう。
この「和時計」というのは、西洋の機械式時計(きかいしきとけい)を手本(てほん)にして、日本独自(にほんどくじ)の「不定時法(ふていじほう)」に対応(たいおう)するようにつくられた日本だけの時計なんじゃ。
まずは、日本への時計伝来(でんらい/伝わったのか)の歴史から学んでいこうかのう。
「時の算数」の中でカックル先生(せんせい)が少し説明(せつめい)しておるのじゃが、こちらでは、さらにくわしくいってみたいと思う。
日本(にほん)に機械時計が伝来(でんらい:やってきた)したのは、天文(てんぶん)20年(1551年)スペインの宣教師(せんきょうし/外国(がいこく)でキリスト教を普及(ふきゅう)させるためにはたらく牧師[ぼくし])フランシスコ・ザビエルが、山口の領主(やまぐちのりょうしゅ)であった大内義隆(おおうちよしたか)に時計を献上(けんじょう/位(くらい)の高い人にものをあげること)したのが最初(さいしょ)であったと言われて(いわれて)おるのじゃ。
そのあとも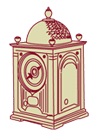 何人(なんにん)かの宣教師が日本にやってきて、時計を献上したという記録(きろく)がのこっているのじゃが、そのころに日本に来た時計はほとんどのこっておらず、現在(げんざい)日本にある時計で、もっとも古い(ふるい)ものは、慶長(けいちょう)16年(1611年)メキシコ総督(そうとく/その地を治めて(おさめて)いた人)のドン・ルイス・デ・ベラスコから徳川家康(とくがわいえやす)にお礼(おれい)として贈った(おくった)目覚ましもついたスペイン製(せい)の時計なのじゃ。 何人(なんにん)かの宣教師が日本にやってきて、時計を献上したという記録(きろく)がのこっているのじゃが、そのころに日本に来た時計はほとんどのこっておらず、現在(げんざい)日本にある時計で、もっとも古い(ふるい)ものは、慶長(けいちょう)16年(1611年)メキシコ総督(そうとく/その地を治めて(おさめて)いた人)のドン・ルイス・デ・ベラスコから徳川家康(とくがわいえやす)にお礼(おれい)として贈った(おくった)目覚ましもついたスペイン製(せい)の時計なのじゃ。
これはイラストをみてもらおうかのう。 |

 |
こうして、ヨーロッパから機械時計が入ってくるようになり、そのうちに日本国内(にほんこくない)でも時計が作られる(つくられる)ようになっていったんじゃ。時計作りの指導(しどう)をしたのは宣教師たちだったのじゃ。
そして、ついに尾張(おわり/今の名古屋)の津田助左衛門(つだすけざえもん)という人が、最初の時計を作ったと記録(きろく)されているのじゃ。
こうした時計師(とけいし/とけいを作る人)は、大名(だいみょう)たちのおかかえとなり、手間暇(てまひま)をかけ、大名たちのためにだけ時計を作っていたんじゃな。そして時計は大名のしゅみをとりいれた美術工芸品(びじゅつこうげいひん)のようになり、また当時(とうじ)の時刻制度(じこくせいど)であった不定時法(ふていじほう)に対応(たいおう)した、世界(せかい)でも日本だけにしかない時計として発展(はってん)していったんじゃ。
こうした時計を「和時計」というんじゃ。
その理由(りゆう)としては、三代目(さんだいめ)の将軍(しょうぐん)である徳川家光(とくがわいえみつ)によって、鎖国政策(さこくせいさく)がとられ、それから300年間、日本はヨーロッパとの交流(こうりゅう)がなくなってしまったことが大きいのお。
その不定時法に対応するために、当時の時計師たちが考え出したさまざまな工夫(くふう)がされたんじゃ。
その工夫をいくつか紹介しようかのう。
時計を不定時法に対応させるためには、大きく言って2つの方法(ほうほう)があるんじゃ。
まずは.機械の運転速度(うんてんそくど)をかえる方法、そしてもう1つは運転を一定(いってい)にしておき、文字板(もじばん)の目盛り(めもり)をかえる方法なんじゃ。その2つの代表的(だいひょうてき)な仕組み(しくみ)を説明するから、よく読んでほしいんじゃ。
<和時計のすばらしい工夫------その1>
■二挺天符(にちょうてんぷ)の自動切換(じどうきりかえ)
 調速用(ちょうそくよう)の棒天符(ぼうてんぷ)は本来(ほんらい)は1本で、左右(さゆう)の分銅(ぶんどう/おもり)の位置(いち)を遠ざけたり(とおざけたり)近づけたり(ちかづけたり)して運転速度をかえるんじゃ。
調速用(ちょうそくよう)の棒天符(ぼうてんぷ)は本来(ほんらい)は1本で、左右(さゆう)の分銅(ぶんどう/おもり)の位置(いち)を遠ざけたり(とおざけたり)近づけたり(ちかづけたり)して運転速度をかえるんじゃ。
天符(てんぷ)のきざみ目は季節(きせつ)による時間変動(じかんへんどう)に対応するきざみが入れてあるんじゃ。分銅の移動(いどう)は毎日(まいにち)、1日2回、昼と夜(ひるとよる)のさかいである、明六ツ暮六ツ(あけむつくれむつ)に行わなければならないんじゃ。
たいへんなことじゃのう。そこでこのめんどうな手間(てま)をはぶくために工夫されたのが、二挺天符である。昼間用(ひるまよう)と夜間用(やかんよう)の2本の棒天符を取り付け、明六ツ暮六ツに自動的(じどうてき)にきりかえる仕組みにしたんじゃ。
<和時計のすばらしい工夫------その2>
■割駒式文字盤(わりごましきもじばん)
 江戸後期(えどこうき)になると調速機(ちょうそくき)に振り子(ふりこ)やひげゼンマイつき円天符(えんてんぷ)が使われるようになり、時計の運転速度をかえることがむずかしくなったんじゃ。そこで考え出さされたのが、割駒式文字盤なんじゃ。
江戸後期(えどこうき)になると調速機(ちょうそくき)に振り子(ふりこ)やひげゼンマイつき円天符(えんてんぷ)が使われるようになり、時計の運転速度をかえることがむずかしくなったんじゃ。そこで考え出さされたのが、割駒式文字盤なんじゃ。
12刻の文字をほった駒(こま)をレールそうちで左右に移動できるようにし、季節による昼夜(ちゅうや)の長短(ちょうたん)におうじて駒を適当(てきとう)な間隔(かんかく)に配置(はいち)できるようにしたんじゃ。
その他にも、季節ごとの時刻板(じこくばん/節板(せつばん))をあらかじめ作っておき、半月(はんつき)ごとに取り替える(とりかえる)ようにしたもの、1枚の板(いちまいのいた)に1年中の各季節の時刻めもりをグラフにして表示(ひょうじ)したものや、割駒式文字盤を自動化(じどうか)したものなど、本当に当時(とうじ)の時計師たちが、知恵(ちえ)と技術(じぎゅつ)を使って作られた様々(さまざま)な工夫が、和時計を発展(はってん)させたんじゃな。
それでは、和時計のいろいろな種類(しゅるい)の和時計を見ていこうかのう。
いかがだったかな。
それでは最後に、江戸時代(えどじだい))も終わり(おわり)に近づいた嘉永(かえい)3年(1850年)にからくり儀右衛門(ぎえもん)とよばれた、天才(てんさい)田中久重(たなかひさしげ)が作った「万年時計(まんねんどけい)」をご紹介しよう。

|
|
万年時計
|
これは、和時計中の最高傑作(さいこうけっさく)と言われるほどの完成度(かんせいど)の高さをほこっていたんじゃ。
写真(しゃしん)を見ていただきたいのだが、この万年時計は6面からなっていて、
1)洋式時刻(ようしきじこく)
2)和式時刻(わしきじこく)
3)24節季(せつき/)の月日(つきひ)
4)曜日(ようび)
5)暦(こよみ)
6)月の満ち欠け(みちかけ)とその日付(ひづけ)
がわかるようになっているんじゃ。
さらに上(うえ)のドームでは、日本地図(にほんちず)がかかれていて、その上を太陽(たいよう)と月がきちんと季節にそった動きをするというすばらしいからくりの時計なんじゃ。今の技術でもこんなものを作ろうと思ったらすごい技術が必要じゃな。
しかしながら、ここまで進化(しんか)した「和時計」ではあったが、1873年の明治(めいじ)の改暦(かいれき)により、ヨーロッパと同じ定時法(ていじほう)が採用(さいよう)されたことによって、すたれてしまったのじゃ。
さて、今回はかなりボリュームがあったと思うが、みんなついてこれたかのう?
次回(じかい)はここまでじゃ。次回はなにが出てくるか。みんな楽しみにまっててくれたまえ。
※
時計/小田幸子
時と時計の百科事典/織田一朗
「和時計図録」 小田幸子 編 発行 株式会社服部セイコー セイコー時計資料館
「江戸のメカニズム」 たばこと塩の博物館 発行編集
2001年1月号