|
 少し、おそくなってしまったが、しょくん、あけましておめでとう。とうとう21世紀(せいき)がはじまってしまったわけではあるが、時代(じだい)がかわろうとも、ここで学ぶ(まなぶ)ことわざや、言葉(ことば)はきっとかわらず生き続けて(いきつづけて)いくことと思う(おもう)のである。21世紀になってもしつこく言わせていただくが「時(とき)」や「時間(じかん)」についてのことわざや、昔(むかし)から言い伝え(いいつたえ)られてきた言葉には、先人(せんじん)つまりわたくしたちよりも前(まえ)に生きていた人たちのちえがいっぱいつまっておる。心して読んで(よんで)ほしいのである。フム。 少し、おそくなってしまったが、しょくん、あけましておめでとう。とうとう21世紀(せいき)がはじまってしまったわけではあるが、時代(じだい)がかわろうとも、ここで学ぶ(まなぶ)ことわざや、言葉(ことば)はきっとかわらず生き続けて(いきつづけて)いくことと思う(おもう)のである。21世紀になってもしつこく言わせていただくが「時(とき)」や「時間(じかん)」についてのことわざや、昔(むかし)から言い伝え(いいつたえ)られてきた言葉には、先人(せんじん)つまりわたくしたちよりも前(まえ)に生きていた人たちのちえがいっぱいつまっておる。心して読んで(よんで)ほしいのである。フム。
では、はじめよう。今回(こんかい)は、まず年の初めらしく「干支(えと)」について学んでみよう。
しょくんは「干支」をすぐに言うことができるかな?それではここで、きちんと言ってみよう。
「干支」とは?
 |
 |
 |
 |
 |
 |
子
(ね/ネズミ)
|
丑
(うし/ウシ)
|
寅
(とら/トラ)
|
卯
(う/ウザギ)
|
辰
(たつ/竜)
|
巳
(み/ヘビ)
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
午
(うま/ウマ)
|
未
(ひつじ/ヒツジ)
|
申
(さる/サル)
|
酉
(とり/ニワトリ)
|
戌
(いぬ/イヌ)
|
亥
(い/イノシシ)
|
となるわけなのだが、しょくん、猫(ねこ)とかライオンとか言って(いって)なかったかな?
さて、なぜ、こんな話を最初(さいしょ)にしたかというと、この「干支」が、江戸時代(えどじだい)は方角(ほうがく)と時刻(じこく)をあらわすのに使われて(つかわれて)いたからなのである。
方角の図(ず)と時刻の図の関係(かんけい)は下にかいておいたから見てほしいのである。
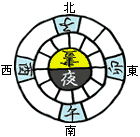
季節(きせつ)によって時間がかわるのは、江戸時代(えどじだい)には「不定時法(ふていじほう)」が使われていたからなのである。
「不定時法」については、時の算数「不定時法の不思議(ふしぎ)」でくわしく説明(せつめい)しているので、そちらを参考(さんこう)にしてほしいのであるが、カンタンに言えば、日の出(ひので)から日没(にちぼつ)までを昼(ひる)、日没から日の出までを夜(よる)として、昼、夜をそれぞれ6等分して「一刻(いっこく)」とした時法(じほう)なのである。
しょくんも知って(しって)いると思うが、日の出と日の入りは、季節によってかわるために、このように「一刻」の長さ(ながさ)をかえていたわけなのである。そうそう、この「不定時法」と今の「定時法」の時刻が自動(じどう)でわかる計算機(けいさんき)をセシモッチ教授(きょうじゅ)が作って(つくって)、「時の資料館(しりょうかん)」においてあるので、みんなぜひためしてくれるとうれしいのである。
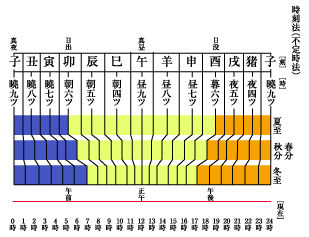
さて、しょくんは「草木もねむる、丑三つ時(くさきもねむる、うしみつどき)」という怪談(かいだん/こわいはなし)ではおなじみの言葉を知っているかな?
「丑三つ時」とは、上の不定時法の図を見てもらえばわかると思うが、今の時間で言えば午前2時から2時半ぐらい、深夜(しんや)のテレビ番組(ばんぐみ)など、もちろんなかった江戸時代では、ほとんどの人が寝ていた時間であるな。だからこそ、お化け(おばけ)や幽霊(ゆうれい)が出る(でる)時間としてふさわしいのである。
しょくんも、あまり夜おそくまでおきていると・・・・。
|
 |
さて、21世紀最初の「時の言葉」はいかがだったかな?
今回の言葉からしょくんは、なにを感じて(かんじて)くれたかな。
教室(きょうしつ)のみんなや先生、お父さん、お母さんとも話してみてくれたまえ。
かさねがさね言うが、しょくんもわたくしの話を聞く(きく)だけではなく、本をたくさん読んで(よんで)何かを学んでほしいのである。コホン。それでは、次回(じかい)、またここでお会い(おあい)しよう。きりつ!れい!フム。
参考文献
時と時計の百科事典/織田一朗
2001年1月号
|