|
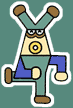 だれがなんといおうと、21世紀(せいき)になろうと、トニカク、わたくしがカックルです。 だれがなんといおうと、21世紀(せいき)になろうと、トニカク、わたくしがカックルです。
さて今回(こんかい)は前回(ぜんかい)にご紹介(しょうかい)した「不定時法(ふていじほう)」についてみんなと学んで(まなんで)いきたいぞ。カックン。
最初(さいしょ)に話(はなし)をしておくと、日本(にほん)に今(いま)のような時間制度(じかんせいど:定時法/1日が24時間で、季節(きせつ)によって1時間の長さ(ながさ)がかわらない)が採用(さいよう)されたのは、今から129年前(まえ)の明治(めいじ)5年(1872年)のことなんだぞ。
これを「明治の改暦(かいれき)」と言って、それまで使って(つかって)いた太陰暦(たいいんれき)は太陽暦(たいようれき)に、不定時法は定時法に改め(あらため)られたんだぞ。カックン。
日本の時計(とけい)は、天智天皇(てんじてんのう)の漏刻(ろうこく)がはじまりで、それを基本(きほん)として平安時代(へいあん)のころまで、定時法が使われていたらしいんだ。
それが、 戦国時代(せんごくじだい)に入る(はいる)と、その時々(ときどき)の国(くに)を治める(おさめる)人間(にんげん)がころころとかわったりして、きちんと時計を管理(かんり)することができなくなり、人々は日の出、日の入りによっておおよその時刻を知る(しる)だけという、まるで原始時代(げんしじだい)のような状態(じょうたい)になってしまっていたんだぞ。
|
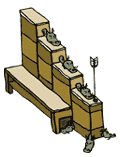 |
ま、そんな状態(じょうたい)のまま、ようやく戦い(たたかい)もおさまり、江戸時代(えどじだい)になったわけだが、その時(とき)に採用されたのが「不定時法」とよばれる、現在(げんざい)のように1日を24等分(とうぶん)する方法(ほうほう)ではなく、昼間(ひるま)と、夜間(やかん)をそれぞれ、6等分するという方法だったっんだぞ。カックン。
6等分の仕方(しかた)は、日の出から日没(にちぼつ)までを昼間とし、日没から日の出までを夜間として、それぞれを6等分したんだぞ。下(した)に春分(しゅんぶん)、夏至(げし)、秋分(しゅうぶん)、冬至(とうじ)の4つの季節の時刻表(じこくひょう)をのせておいたので、見て(みて)ほしいぞ。
黒く(くろく)書いて(かいて)あるところが、夜間。白い(しろい)ところが昼間というふうになっているんだ。
当時(とうじ)、「一刻(いっこく)」と言われていた時間の長さが、季節ごとにちがっているのがわかるだろ?
カックン。
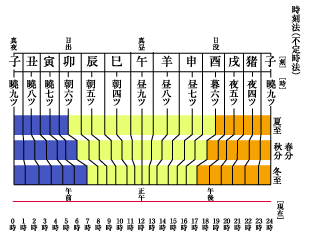
いっけん、複雑(ふくざつ)そうなこの「不定時法」なのだけれど、時計を持たない(もたない)人たちにとって、いいことは、太陽の動き(うごき)をもとにしているから、太陽の位置(いち)をみればおおよその時刻がわかるということなんだぞ。なんか日時計(ひどけい)みたいだな。カックン。
この「不定時法」については、「時の歴史(れきし)」で取り上げて(とりあげて)いる「和時計(わどけい)」と「時の言葉(ときのことば)」の「干支(えと)」にもかかわりのあることだから、両方(りょうほう)のページをよく見くらべて読んで(よんで)ほしいぞ。
さて、今回は歴史の話までしてしまったが、「時」というのは歴史と深い(ふかい)かかわりがあるものなんだぞ。
ま、トニカク今回はここまで、次回(じかい)もよろしくだぞ。カックン。
参考資料:
時と時計の百科事典・時と時計の最新常識100/織田一朗
時計/小田幸子
2001年1月号
|