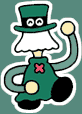 またまたわがはいのページへようこそ。これから一緒(いっしょ)に、時の歴史(ときのれきし)を勉強(べんきょう)していこうかのう。
またまたわがはいのページへようこそ。これから一緒(いっしょ)に、時の歴史(ときのれきし)を勉強(べんきょう)していこうかのう。
前回(ぜんかい)は「水時計(みずどけい)」について勉強したのじゃが、今回(こんかい)は少し(すこし)よくばって「砂時計(すなどけい)」「ランプ式時計(ランプしきどけい)」「ろうそく時計」「香時計(こうどけい)/せんこう時計ともいう」と、大サービスで、いってみようかのう。
「砂時計」のほかは、3つとも、火(ひ)を使う(つかう)時計ということで共通(きょうつう)しているのじゃ。
 |
それでは、みんなもよく知って(しって)いる、真ん中(まんなか)がくびれたガラスのつつの中に砂が入って(はいって)いて、ひっくりかえして使うおなじみの「砂時計」からじゃ。
「砂時計」は今(いま)から1200年前(まえ)ぐらいに、ルイトプランドというフランスのおぼうさんが考え(かんがえ)ついたといわれておるんじゃが、実際(じっさい)に使われだしたのは、機械式時計(きかいしきどけい)が発明(はつめい)された今から700年前よりもちょっと前ぐらいだったらしいのじゃ。 |
人々に長く(ながく)使われていた「水時計」にもこまったところがじつはあったのじゃ。
それは、寒い(さむい)ところなどでは、水がこおってしまって使えなくなること。また暑い(あつい)ところでは、水が蒸発(じょうはつ)してしまって、正確(せいかく)な時間が計れ(はかれ)なくなってしまうということなんじゃ。その点(てん)「砂時計」は、安心(あんしん)じゃのう。
もっとも、つつの中に入れる砂は、つまることがないように、つぶのそろったものをえらばねばならんがのう。
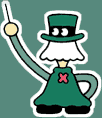 この「砂時計」がおもに使われたのが、書斎(しょさい)や、教会(きょうかい)の説教壇(せっきょうだん/いろいろな神[かみ]のおしえをかたるばしょ)、それから遠洋航海(えんようこうかい/とおいうみへとたびすること)のふねだったのじゃ。
この「砂時計」がおもに使われたのが、書斎(しょさい)や、教会(きょうかい)の説教壇(せっきょうだん/いろいろな神[かみ]のおしえをかたるばしょ)、それから遠洋航海(えんようこうかい/とおいうみへとたびすること)のふねだったのじゃ。
とくに航海用(こうかいよう)の船(ふね)の時計としては、湿気(しっけ)や、温度変化(おんどへんか)、ゆれにも強い(つよい)ので、今から200年ぐらい前まで大活躍(だいかつやく)したのじゃ。30分、1時間、3時間などの砂時計が作られ(つくられ)、ふねの中の時間を計っていたのじゃが、問題(もんだい)が1つだけあったのじゃ。それは、砂がおちたら、砂時計をひっくりかえすやくめの人が、寝て(ねて)しまったり、めんどくさくて、さきにひっくりかえしてしまったりしてしまったことなのじゃ。こればかりは、どうしようもないのお。その後(ご)、機械式時計(きかいしきどけい)がいっぱんに使われるようになった200年ぐらい前になっても、砂時計は、ガラスを作るつくる技術(ぎじゅつ)が発展(はってん)して、安く(やすく)大量生産(たいりょうせいさん)できるようになり、ちょっとした時間を計るのに、ひろく使われるようになったんじゃ。
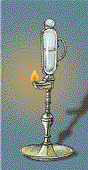
 さて、こんどは火(ひ)を使って時を計る3つの時計を紹介(しょうかい)しようかのう。まずは左(ひだり)「ランプしき時計」じゃ。
さて、こんどは火(ひ)を使って時を計る3つの時計を紹介(しょうかい)しようかのう。まずは左(ひだり)「ランプしき時計」じゃ。
これはランプがもえる時に、油(あぶら)の量 (りょう)がへっていく早さ(はやさ)で、油の入っているつつにかかれためもりをよんで時間を知った(しった)というものなのじゃ。
右(みぎ)の「ろうそく時計」も、みじかくなっていく早さで、時間を知ったわけじゃの。
よく、人間(にんげん)の寿命(じゅみょう)をろうそくにたとえたりするが、なんとなく、もえつきてゆくようすが、なにやら人の一生(いっしょう)のような感じ(かんじ)がするのう。
 「せんこう時計/香時計(こうどけい)」は、中国(ちゅうごく)で使われて、左(ひだり)のイラストのように、下(した)に金属(きんぞく)のおさらをおいて、時間がくるとおもりがおちて、音がなって時を知らせるという仕組み(しくみ)のものもあったんじゃぞ。この「せんこう時計」は、日本につたわって、ひばちの灰(はい)の上に香(こう)をほそながくおいて、そのもえている場所(ばしょ)で時間を知る「香時計」として江戸時代(えどじだい)には、かず多く(おおく)作られたのじゃ。また、「香時計」は「香のかおりを楽しみ(たのしみ)、時間の流れる(ながれる)ことを知る」という日本の文化(ぶんか)から生まれた(うまれた)時計ともいえるのじゃ。
「せんこう時計/香時計(こうどけい)」は、中国(ちゅうごく)で使われて、左(ひだり)のイラストのように、下(した)に金属(きんぞく)のおさらをおいて、時間がくるとおもりがおちて、音がなって時を知らせるという仕組み(しくみ)のものもあったんじゃぞ。この「せんこう時計」は、日本につたわって、ひばちの灰(はい)の上に香(こう)をほそながくおいて、そのもえている場所(ばしょ)で時間を知る「香時計」として江戸時代(えどじだい)には、かず多く(おおく)作られたのじゃ。また、「香時計」は「香のかおりを楽しみ(たのしみ)、時間の流れる(ながれる)ことを知る」という日本の文化(ぶんか)から生まれた(うまれた)時計ともいえるのじゃ。
今回は、イラストをよくみて、それぞれの時計の仕組みをよく観察(かんさつ)してくれるとうれしいのじゃな。
さて次回(じかい)は、「機械式(きかいしき)時計」について学んでみようかのう。
2000年8月号