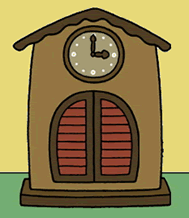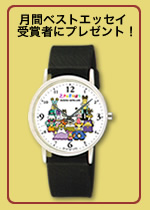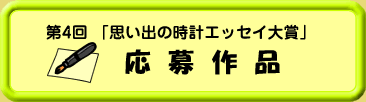 ������� 2004�N1��10���`2004�N12��31�� |
|
|
|
|
�@ |
|
2004�N�̍�i
1��-2���@3���@4���@5���@6��-7���@8��-9���@10��-11���@12��
![]() 12���̍�i�i75��i�j
12���̍�i�i75��i�j
�u��̈ꐺ�v�����@������̃G�b�Z�C
�u���i�̌Î��v�v�J���@�O����̃G�b�Z�C
�u�^�C���C�Y�}�l�[�v�с@���j����̃G�b�Z�C
�u�y�@�A�@�E�@�I�@�b�@�`�v��O����̃G�b�Z�C
�u���v�v�C�`�@�����N����̃G�b�Z�C
�u�����ꏏ�Ȏ��v�v�����@��������̃G�b�Z�C
�u���ƋL�O�i�v�y�c�@�h�q����̃G�b�Z�C
�u�������Ă����Ȃ��́v���{�@�q�O����̃G�b�Z�C
�u�单�����v�v���Z�@�ď@����̃G�b�Z�C
�u���v�v����@����̃G�b�Z�C
�u �����炯�̐U��q���v�v���R�@�傳��̃G�b�Z�C
�u�����Ă�������r���v�v���V�@�O�炳��̃G�b�Z�C
�u����������v�v�����@���炳��̃G�b�Z�C
�u���ꂩ��̎��ԁv�x�c�@�L������̃G�b�Z�C
�u�p�b�|�p�b�|�A�n�g���v�v�����@���T������̃G�b�Z�C
�u�K�̖ڊo�܂����v�v��@�G���q����̃G�b�Z�C
�u���o����̎��v�v����@��仂���̃G�b�Z�C
�u�`�����v�v�����@������̃G�b�Z�C
�u�~�܂�ʂ��́v�K���@��h����̃G�b�Z�C
�u���v�Ƃ̎v���o�v���n�@���ۂ���̃G�b�Z�C
�u�����v�����@����q����̃G�b�Z�C
�u���ӂ���B�v�l�{�@��������̃G�b�Z�C
�u�����Ă���v�����@������̃G�b�Z�C
�u�������Ǝ��v�̊W�v����@�S�G����̃G�b�Z�C
�u���v�͐����Ă���v�V���@�ؓނ���̃G�b�Z�C
�u���������鎞�v�v�T��@������̃G�b�Z�C
�u��Ȏ��ԁv�����@�I��������̃G�b�Z�C
�u�s�莞�@�Ŏ�������Łv����@��������̃G�b�Z�C
�u�������v�v�V���[���@�c�W���g����̃G�b�Z�C
�u�Ƃ�X�q�̎��v��v���c�@�r������̃G�b�Z�C (12���̃x�X�g�G�b�Z�C)
�u�ڊo�܂����v�̃P�[�X�v���c�@�c�삳��̃G�b�Z�C
�u�����z���������̘r���v�v
�u����������̂Ƃ����v����@�C�Ƃ���̃G�b�Z�C
�u�搶�̘r���v�v���Ƃ��@��������̃G�b�Z�C
�u�|�����v�ƉȊw�̐��E�v�����@�~�n������̃G�b�Z�C
�u���̕v���c�@���F����̃G�b�Z�C
�u���̊|���v�v���J��@���q����̃G�b�Z�C
�u��Ԃ��ꂵ�������o�[�X�f�C�v���[���g�v�������܂ꉫ��炿����̃G�b�Z�C
�u�Â������v�v�ᖽ�@�O��ꂳ��̃G�b�Z�C
�u�L�~�̃R�R���E�E�v�v�������D�q����������̃G�b�Z�C
�u�P�O���P���R�S�b�̔閧�v�Έ� �m����̃G�b�Z�C
�u�e���̖ڊo�܂����v�v���q�@��l����̃G�b�Z�C
�u�����v���{�@�Ƃ�݂���̃G�b�Z�C
�u���������ގ��v�v�{�{�@����q����̃G�b�Z�C
�u����łv�ؑ��@�����q����̃G�b�Z�C (12���̃x�X�g�G�b�Z�C)
�u�Z�C�R�[�O�j�v�i�@�N�ꂳ��̃G�b�Z�C
�u�T�C���̂Ȃ����蕨�v�~�R�@�Ⴓ��̃G�b�Z�C
�u�r���v�����������v�q�}�}����̃G�b�Z�C
�u���v�͗F�B�v���Ł@��������̃G�b�Z�C
�u�������v�̎v���o�v�ז�@�݂��q����̃G�b�Z�C
�u�����r���v�v�A��@���l����̃G�b�Z�C
�u�R�����̊|�����v�v���@���䂳��̃G�b�Z�C
�u���j���̘r���v�v���싞�q����̃G�b�Z�C
�u�Ȃ̑��蕨�v��{ �Ă���̃G�b�Z�C
�u���������v�v���Y�@�R������̃G�b�Z�C
�u���̎��v�v�ؑ��@�^������̃G�b�Z�C
�u���߂Ă̎��v�v�g���@���q����̃G�b�Z�C
�u���v�̎v���o�v�^��@�S�コ��̃G�b�Z�C
�u�n�g���v�v�����@��������̃G�b�Z�C
�u���v�̖�ځv�R���@���I����̃G�b�Z�C
�u���܂ꂽ�N���v�n�� �I��q����̃G�b�Z�C
�u���v�Ɛl�ԁv���c�@�m�炳��̃G�b�Z�C
�u�厖�Ȏ��ԁv�c���@�ʊC����̃G�b�Z�C
�u��ɐ��������v�v�r�c�@�F�q����̃G�b�Z�C
�u�u���v�ƕ�v�Γc �ɂ���̃G�b�Z�C
�u����������̂Ȃ��Łv�j����̃G�b�Z�C
�u�m���ȃ��Y���v��{�@�^�߂���̃G�b�Z�C
�u�r���v�̂Ȃ������v�㓡�@������̃G�b�Z�C
�u������A�{���{�����v�A���C�H�v�����f�B����̃G�b�Z�C
�u������Ȃ����w�j���̘r���v�v�e�@��������̃G�b�Z�C
�u���̂Ђ݂v�X�R�@�ׂ���̃G�b�Z�C (12���̃x�X�g�G�b�Z�C)
�u�r���v�͒j������炤!?�v�R�c�@�~�q����̃G�b�Z�C
�u���v���Ă��̂͂�����������ł���v傖��@���V����̃G�b�Z�C
�u�����������{�����v�v������̃p�p����̃G�b�Z�C
�u��̉������v�v���R�@�Njv����̃G�b�Z�C
���́A���Q���N���̐l�ł���B�̎��Ȃ̂��A�͂��܂����N�̏K���ׂ̈��A����6���ɋN���A���9���ɂ͏��ɂ��B��x�Q����Ō�A�钆�ɖڂ��o�܂����Ƃ́A�����Ȃ��B�n�k�ʼnƑ��F���ڂ��o�܂������ł����A���͂������薰���Ă����̂ł���B
����Ȏ��ɂƂ��āA�钆�̎������͓���Y�܂�����̂ł������B���Ԃ��ɁA�������ςݏd�˂ĕ�����悢���̂��A���肸�ɖ���؉H�l�܂�����ԂɊׂ�̂ł���B����̂��Ƃł���̂ŁA�Ƒ��̒N���ɗh�����ċN�����Ă��炤�̂����̂тȂ��B�����ŁA�ƒ��̖ڊo�܂����v���W�߂邱�Ƃɂ����B�P�ڂ̖ڊo�܂��͖��ӎ��Ŏ~�܂�A�Q�ڂ̖ڊo�܂�����T��Ŏ~�߁A�R�ځA�S�ڂ��炢�ŏ㔼�g���N�����A�����ڂ�������B�ڊo�܂����v�����́A�ǂ̎q�����C�ɑ����ł����B����A����Ȃ������Ǝv������A���̕��@�͉Ƒ��ɕs�]�������B�����W�Q�ł���B�����Ŗڂ������̂��A�a�����ɖ������ꂽ��F�̖ڊo�܂����v�ł���B�q�O�}�̊G�̂����A�����ډ����܂��ɗD�ꕨ�ł������B�Ȃ��Ȃ�A�䂪�ƗB��̘^���@�\�������� �i�ł���������B�N�}�̈ꐺ��낵���A�Ƒ����o�́u�N���Ȃ��`���I�I�I�v�́A���Ȃ�[������̎����������N�����Ă��ꂽ�B���߂Ďg�����^���@�\�̕� �����ɉƑ��ꓯ���S���A�Ƒ��̈�����Ղ�̓{�萺�ɁA���͑喞���ł������B�����܂ł��Ȃ��A���̎��v�͒������Ǝ��̈��p�i�Ƃ��đ劈�邱�ƂƂȂ�̂������B
�u���i�̌Î��v�v�J���@�O����̃G�b�Z�C
�����̓c�ɂɂ́A�P�O�N�ԁA�Î��v���u����Ă����B���́A���Ă��܂���������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ������B�̂́A���̎��v���悭���𗧂ĂĂȂ��Ă����B���ł����X�A�]�����疲�ɏo�ăN���������邪�A�{�[���{�[���ƂP�Q���Ȃ�ƁA�邻�̉������܂�Ȃ��������B���Ɍ�������ł́A��i�ɂ悭�����A��̉H����t�ł�B���傤�ǁA���̍����Ƃ���Ɋ|���Ă���A���̉��Ŏ����X����ƁA�Ȃ��Ƃ��Ă����������C���ɂȂ��B
�悭�����ŁA���̉����Ȃ���A���z���A�C�}�W�l�[�V���������Ă����B���a�̏�i���������B�Â��悫����̌i�F�ł���B�܂��A�C������߂��̂ŁA�����⒪�̂ɂ�������������B���Ɋ�������̂́A�Â��ȊC�ӂł���B���̌i�F�����̎��v�̉��ł́A�܂ǂ�݂ƂȂ�A�v�킸�Q�Ă��܂����Ƃ��������B
�C�����ƌ����Ƃ炵�Ă��āA�Ղ��y�����Ȑl�X�̐�����̈łɂ܂���āA�������畷����B�₫�Ƃ�̂ɂ������@�Ɋ������A�ƂĂ��Y����Ȃ��g�������̂ł���Ɗ������B���̈ʒu�́A���́A�ʂ̎��v�ƂȂ��Ă��܂������A���̊y�����ȏ�i�͍����ǂ����ő��݂��Ă���̂��낤���H�S�̕Ћ��ł����Ԃ₫�Ȃ���c�ɂA��ƁA�K�����ẮA�S����܂��o�Ă���̂ł���B������x����k�邱�Ƃ��ł����Ȃ�A��������Ɗώ@�����Ă݂悤�Ǝv�����B
�u�^�C���C�Y�}�l�[�v�с@���j����̃G�b�Z�C
���Ԉ�w�Ƃ������̂�����D���̎��ԑтɂ���āC��邱�Ƃ��Ⴄ�ƌ��N���ʂ��Ⴄ�Ƃ����̂��D�l�Ԃ͊�{�I�ɂ͒��N���āC��Q�邪�C�l�ɂ���Ă͖�N���Ē��Q��l������B�邪���āJ���������̐l�����邪�A��{�͎��R�ɍ��킹�����������������̂ł���B��������^�Ȃ̂ŁA�l�̂��Ƃ͌����Ȃ����E�E�E�B���͋��Ȃ�Ƃ������A�܂��������̂Ƃ��肾�Ǝv���B�D���Ȃ��Ƃ�����Ă�Ǝ��Ԃ͂����Ƃ����Ԃɉ߂��Ă��܂����A�����Ȃ��Ƃ₭����Ȃ����Ƃ�����Ă�Ƃ�����������������̂ł���B������x�͎��Ԃ����C���Ԃ��ɂ��������̂ł���B�^�C���C�Y�}�l�[�Ƃ�������Ȃ��E�E�E�B
�u�y�@�A�@�E�@�I�@�b�@�`�v��O����̃G�b�Z�C
���Ƃ������̂́A�ꐶ�����ɐ����Ă���l�ɂ��A�������R�Ɛ����Ă���l�ɂ������Ɏ��Ԃ�^���Ă����B
�P�l�̒j�ƂP�l�̏����A���ꂼ�ꐶ���Ă��������o�āA�߂��荇�����������A�Q�l�łƂ��Ɏ����߂���������B
���������̎����o�āA�҂��]���̌����̒a���ɁA�݂��Ɏ�����荇����܂������āA�n����ł͂���ȂɎ����o�Ă��Ȃ������̂��낤���A�Q�l�ɂƂ��Ă̒����������̌o�߂������Ȃ���܂���������n�܂����������̗܁B
�����オ�����Ɗ�сA�����߂�ꂽ�Ɣ߂��݁A�c�t���E���w�Z�E���w�Z�E�����w�Z�ɓ��w�����Ɗ�сA�l���̒��őς��Ȃ���Ȃ�Ȃ����X�̋ꂵ�݂ɁA���̎��X�ɗ܂��āA�����Ƃ����Ԃ̎��ł������悤�ȋC�����邵�������������o�Ă���悤�ȋC�����邵�A�l���猩��Q�l���o�����āA���͕����ɂQ�O�N�̎��Ƃ������ƂɂȂ�炵���B
�Q�l�ň���̌������A�A���o�C�g�����Ȃ���~�������̂ŁA�{�������Q�O���N���Ɂu�y�A�E�I�b�`�v���v���[���g���Ă����B
�����ɐ����āA�����ɉƑ����J�������߂Ȃ���A�����d�˂āA���̎��X���ɐ����Ă������Ƃ������ɉ��炩���Ă��ꂽ�B
�f���Ɋ������B���܂ŗ������܂̐��������炢�Ă��ꂽ�B�߂����Ă��������ԈႢ�łȂ��������Ƃ��ؖ����ꂽ�Ɗm�M�ł���B�Ăёf���Ɋ������B
���ꂩ���A�܂��܂��Q�l�̐l���͒������B�v���[���g���ꂽ�u�y�A�E�I�b�`�v�ƂƂ��ɑ�ɉ߂��������B�K���������鎩�M������B���肪�Ƃ��B
�u���v�v�C�`�@�����N����̃G�b�Z�C
�l�ԂƂ������̂́A�y�������ɂ͎��Ԃ�Y��A�y�����Ȃ��Ƃ��͎��Ԃ��v�������Ƃ����A�ƂĂ��������낢�K���������Ă���B
�Ⴆ�A�e���r�Q�[�������Ă��鎞�ɂӂƎ��v������Ƃ����Q���Ԃ����Ă������Ƃ��A�F�B�̉ƂɗV�тɍs�������Ɏ��v������ƁA�����ƂɋA�鎞�ԂɂȂ��Ă���A�������������Ƃ����ɂ���������B�t�ɍl���Č���ƁA�����Ă��鎞��A�����ɂƂ��ċ����̂Ȃ��b������Ă���Ƃ��ȂǂɁA�����C�ɂ��Ă��܂��܂��B
���܂ɖl�͎��Ƃ͂Ȃ낤�A�Ǝv���Ă��܂��܂��B���̋^��͖l�̒��ł́A�܂��𖾂���Ă��܂���B�����ǁA���̋^��ɂ��Ă��܂̖l���킩���Ă��邱�Ƃ��ЂƂ�������܂��B����́A�l�Ԃ�����ł��A�n�����F����������Ă��A���Ƃ������t�͉i���ɂ�������Ȃ����t���Ǝv���Ă��܂��B
����̎��ԂQ�S���ԂƂ����̂́A�ǂ�������Ă킩�����̂��낤���A���������ʂł͐l�Ԃ͓��������Ǝv���܂��B
���v�Ƃ����̂́A�Ƃ��Ă��s�v�c���Ǝv���܂��B�����ǂ̐l�����v���Ă����������ł����H���ԂƂ͂Ȃ�ł����H�ƕ����ꂽ�瓚���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ǝv���܂��B�����������A���i�Ȃɂ��Ȃ��悭�g�����t�ł��Ӗ����悭�킩��Ȃ���������������A���v�����̈�킾�Ɩl�͎v���܂����B
�u�����ꏏ�Ȏ��v�v�����@��������̃G�b�Z�C
���v�͎������ɂ͌������Ȃ����́B�����ꏏ�ɂ���悤�ȋC�����܂��B���N����͖̂ڊo�܂����v�ł͂��܂�A��������ɂ��邢�낢��Ȏ��v�̐j�̉����Ȃ��疰��ɂ��܂��B���͎��v�̐j�̉�����D���ł��B��Q��Ƃ��͐j�̉������Ȃ��ƂȂ����������Ȃ���ł��B���Ԃ̗����\���j�̉��͂킽�������̐����ɂ͌������Ȃ����̂ƂȂ�܂����B
�����j�̉����D���ȗ��R�͖ڂ��҂��Ă��Ă����Ԃ͉߂��Ă����Ƃ��������������Ă���Ƃ������Ƃ������ł��邩��ł��B���̂��Ƃ�F�B�Ɍ����ƁA�`�N�^�N�A�`�N�^�N�����Ă��邳���Ǝv���Ă���l�������܂��B�Ȃ̂ł��ꂩ��A�j�̉����Ǝ��͐����Ă�Ȃ��Ƃ������������Ƃ������Ă��炢�����ł��B
�������v�̎�ނ̒��ň�ԍD���Ȃ��̂́A�����v�ł��B����͐j�̉��͂��Ȃ����ǁA���Ԃ�����Ă���Ƃ������Ƃ��ڂɌ����邩��ł��B���Ԃ��v��킯�ł��Ȃ��̂ɁA�����v���Ђ�����Ԃ������Ȃ�͉̂��ł��낤�Ǝv���܂��B�����A�N�ł��ڂ̑O�ɍ����v������Ƃ����Ђ�����Ԃ��Ă��܂��Ǝv���܂��B���͂��̌�A�S�����������Ă��܂��܂Ō��߂Â��邱�Ƃ��ł��܂��B�����v�ɂ͐l�̋C�������Ђ�������̂�����Ǝv���܂����B
���Ԃ͂����ς��Ȃ������ŗ���Ă���̂ɏꍇ�ɂ���đ�����������A�x���������肷�邱�Ƃ�����܂��B���v�͎������̋C�����ƈꏏ�ȓ���������ƂĂ��s�v�c�ȓ���Ǝv���܂��B���͂���Ȏ��v����D���ł��B
�u���ƋL�O�i�v�y�c�@�h�q����̃G�b�Z�C
���͏��w�Z�̑��ƋL�O�Ɋ|�����v������܂����B���w�Z�̂���ƂĂ������悩�����F�B�ƈꏏ�ɂ��������v�B���A���̎��v�͎��̕����̊��̏�̂��ׂɂ����Ă��܂��B�������Ă���Ƃ��A���̎��v�͂������������낵�Ă��܂��B
�u�J�`�A�J�`�A�J�`�A�J�`�E�E�E�B�v
�i���ɓ��������Ă������Ȍ��C�̂��鎞�v�B���ꂪ�A���̂��������v�ł��B
���̎��v������ƁA���w�Z�̂�����v���o���܂��B�f�U�C�����l���āA�ꐶ�������������ƁA�������낢�S�C�̐搶�Ɏ�`���Ă���������ƁA���ǂ��̗F�B�Ɉ�l��l���b�Z�[�W�����v�̗��ɂ����Ă���������ƁB���ɂ��A�v���o����������̎v���o����݂������Ă��܂��B
���A���͎��̂܂��������ł��B�����p��̖��������Ƃ��ɂ������̎��v���g���Ă��܂��B����ȋꂵ�����Ԃł����̎��v������ƁA�y�����������X��A���͓]���Ă��܂����搶���v���o���̂ł��B�����āA������x���ɏW���ł��A����邱�Ƃ��ł��܂��B�Ƃɋ���Ƃ��̑唼�́A���̎��v�̈ꏏ�ɉ߂����܂��B
���ɂƂ��āA���̑��ƋL�O�i�́A���̋L������݂����点�Ă����A�ƂĂ��厖�ȕ��ɂ��̊Ԃɂ��Ȃ��Ă��܂����B���ꂩ����A���̎��v�ƈꏏ�ɂ��܂��Ă��邱�Ƃ��v���o�ɂ��Ă������Ǝv���܂��B��l�ɂȂ��āA���̎��v�����āA�悩�����Ȃ��Ǝv�����������������܂ŁE�E�E
�u�������Ă����Ȃ��́v���{�@�q�O����̃G�b�Z�C
���̎v���ł̎��v�́C���w�Z�̎��ɍ�������v�ł��B�������Y��Ńf�U�C�����l�������Ƃ��o���Ă��܂��B���w�Z�̑��ƋL�O�ɍ��Ƃ������ƂŁC�ƂĂ��Y�݂܂����B�ƂĂ��Y���ʂ������̃f�U�C���ɂȂ�܂����B�n�߂ɉ����������āC���ɒ������Œ����Ă����܂����B���̎��ɁC��������̐l�������Ă��āC���͋C�����悤�Ǝv�����L��������܂��B�����ĐF��h�芮�����܂����B
���C���̎��v�́C���̕����̕ǂɂ���܂��B�����C���̎��v������Ə��w�Z�����̒��̊y�����������Ƃ����Ĕ߂����������ƂȂǂ��v���o����܂��B�F�B�Ə����������Ƃ����������Ƃ����ł͂ƂĂ��ǂ��v���o�ł���C�����ɂ��ς��Ȃ��v���o�ŁC��ɂ�����x�Ƃ����키���Ƃ̏o���Ȃ����܂łň�ԑ�ȕ��ł��B
���C�l���Ă݂�Ǝ��̎g���Ă��鎞�v�̒��ň�ԑ����g���Ă���Ǝv���܂��B���N����Ƃ��Ɍ��āC�w�Z�֍s���Ƃ��Ɍ��āC���̓r���Ɍ��āE�E�E�B��������ɂ��C���Ԃ�����Ƃ��͂��̎��v�ł��B�������v���݂Ă���̂Ȃ玞�v���������Ă���̂��ȁC�Ǝv���ƁC������ƒp���������Ȃ�܂��B
�������̂��Ƃ����Ă������v�B�������ɃX�C�b�`�̓���Ȃ����Ɂu�J�`�E�J�`�E�E�E�v�ƒǂ��ł��������Ă���鎞�v�B���̎��v�́C���̂��Ƃ�S�Ēm���Ă��邽������̎v���o�̂܂�����ȕ��ł��B���܂ł��肪�Ƃ��B�����āC���ꂩ�����낵�����肢���܂��B
�u�单�����v�v���Z�@�ď@����̃G�b�Z�C
���̘b�ɏo�Ă��鎞�v�́A�ڂ��̉Ƃɂ��鎞�v�ł��B���̒����v�͖l�̐��܂�Ă���O����A�Ƃ�������Ă���Ă��܂��B
�l�����S���������͎̂l�E�܍̍�����ŁA���̍�����l�͂��̎��v�Ƌ��ɉ߂����Ă��܂����B���̍��̖l�͂��̎��v�̂��Ƃ��A���v�Ƃ͌��Ă��炸�A�����Ƃ������Ⴞ�Ǝv���Ă��܂����B�����ɕt���Ă���`�F�[���ŗV��A�����J������߂��肵�ėV��ł��܂����B
�������A���̎��v�������o�����͎̂l�E�ܔN�O�̂��Ƃł��B�l���q���̍��V��ł������v�͓����Ă��Ȃ������̂ł��B�����炩�͕�����܂��A���̎��v�͒����ԋx�e���Ă����悤�ł��B���܍l���Ă݂�ƁA���̍��悭���Ȃ������ȂƎv���܂��B
�����č��A���v�͌��C�ɐU��q��h�炵�Ȃ���A�u�J�`�b�J�`�b�v�Ǝ������݁A�\�ܕ������Ɂu�S�[���E�S�[���v�Ǝ��Ԃ�m�点�Ă���Ă��܂��B���܂ɁA�m�点�鉹���x��Ēx���������ɂȂ邱�Ƃ�����܂����A�����A���v�̐j�����킹�Ă�������A�U��q��h�炵�Ă�������A�����������グ���肵�Ă��܂��B���̎��v�̏��̉��ɂ���āA�Ƒ��̐S���a��A���C�̌��ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B�����ڂ���x�������Ȃ��悤�ɁA���������̉��ŁA�������l�̔w���������Ă���A������撣�낤�Ƃ����C�����ɂ����Ă���܂��B���ꂩ����A�����ƌ��C�ɏ���炵�Ȃ��猩����Ă��Ăق����ł��B
�ڂ��̉Ƃɂ��鎞�v�͂ڂ������̉ƂɈ����z�������ɂȂɂ��̏j���ł���������v�ł��B�W�N�Ԏg���Ă���̂ł����A�܂��܂����ꂢ�ŁA�������ɂȂ�ƁA���ꂢ�ȁA��������܂��B�����z���������́A���̂Ƃ������Ȃ邽�тɁA���ꂢ�ȉ����Ȃ��ƁA�P�P�̃����f�B���y���݂Ȃ��畷���Ă��܂����B�����Ȃ邽�тɁA�u�������H�v�ƁA�y�������ɕ����Ă������ǁA���ɂȂ�ƁA���v�̉����Ȃ��Ă��A�����v��Ȃ��Ȃ�A���v����A���܂茩�Ȃ��Ȃ�܂����B�ł��A�P���̓��̒��̎��́A�w�Z�ɂ������Ԃ��m���߂���x�������܂��B
�����ɂ��邱�ƂɁA�Ȃ�Ă��܂��ƁA���̂��Ƃ�����C�ɂȂ�Ȃ��Ȃ�Ȃ��B�C�ɂȂ�Ȃ����Ƃ́A���킢���Ƃł��B���v�́A���邽�߂ɂ���̂ɁA���Ă��炦�Ȃ��ƁA���v���炢�Ǝv���܂��B�����������Ƃ��C�ɂ��Ȃ���A������������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�ڂ�������������܂��ɐ������Ă��钆�ŁA���v���S�ĂȂ��Ȃ�ǂꂾ�����邾�낤�B���v�̑�����������g���m���Ď��v���ɂ��邱�Ƃ��厖���Ǝv���܂��B������A���ꂩ��͎��v��K�v�ȏ�Ɍ��Ă��������Ǝv���܂��B���v�����������A���C�Ȃ�����Ă���̂ł͂Ȃ��āA�����ɈӖ��������ė���邱�Ƃ��������������Ă��������ł��B
�u�����炯�̐U��q���v�v���R�@�傳��̃G�b�Z�C
�^�钆��������Ȃ����Ԃɂ�������l�Ŗ鎞�v�B�ڂ��̐��܂��O���獡�܂łڂ��̐�����Z��A�Ƒ��̐����𑽂����Ă������v���u�{�[���{�[���v�Ɩ邽�тɂڂ��́A�ڂ��́A���̎��v�̐j�ɖڂ�D����B��ڌ��āu�܂����Ԃ�����v�Ƃ��������̐������Ƃ�B�N���ĐQ�ڂ��Ȃ�������̎��v�̎��������Ɂu�Q�߂����v�Ƃ����C�������������A�Ȃ����������{����Ԃ��Ă��܂��B
�傫�ȐU��q�̕t�������v���B���̍��E�ɓ����U��q�ɖڂ��L�����L���������Ȃ��猩������B�������邱�Ƃ������������v�̓����U��q�����Ă��邾���łȂ����y�����Ȃ����B
���܂ɐU��q���Ƃ܂��Ă��܂��Ɠ����Ȃ����̐U��q�����āA�ǂ������ƍ���Ɠ����ɁA���v�������Ȃ��܂�����Əł���o�Ă���B����ǂ���́A�����̋x�݂ɂ����Ȃ������B��ӐQ�āA�܂������Ă݂�ƌ��C�ɂԂ�Ԃ�h��Ă���B���v�Ɉ��S���邱�Ƃ��������B
�ŋ߂ɂȂ��Ă��̎��v������������Ă����B���w���̂���́A������ڌ��Ď��Ԃ���������������v���ĂȂ������B����Ǎ����̎��v�̏��̑����ɋ������B���N�Ԋ|�����Ă���̂��́A�m��Ȃ�����Ǖ\�ʂɂ����������̏������Ă��̎��v���撣���Ă���Ȃ��Ǝv���悤�ɂȂ����B
�ڂ������܂��O���炠�荡���|�����Ă��鎞�v�B�ڂ��̋��������A���������������̏�Ō��Ă���Ă������v�B���ꂩ������̎��v�����Ȃ��琬���̑��������Ă��炢�����Ǝv���B
�u�����Ă�������r���v�v���V�@�O�炳��̃G�b�Z�C
�ڂ��̎v���o�͘r���v�ł��B���̎��v�́A�ڂ������w�O�N���̂���ɂڂ��̔����������Ă���܂����B�Y��Ȕ��ɓ����Ă��Ĕ����Ă���������Ɍ��\���ꂵ�������ł��B���̎��v�͍�����ɂ��Ă��܂��B�r���v�͍������i�g���Ă��܂��B�@�B�ł͂Ȃ��̂ŃA���[���@�\��X�g�b�v�E�H�b�`�Ȃǂ��g���Ȃ��̂Ŏc�O�ł��B���̎��v����������������Ǝv���܂��B�����Ă���������Ǝg���Ă݂����Ǝv���܂����B���̂��߂ɂ͎��v���厖�Ɏg���ăz�R���Ƃ������v�ɂ��Ȃ����Ƃ�����Ǝv�������䂤�v���ł̂��鎞�v���ڂ��͑�Ɏg�������ȂƎv�����B���̎��v�͂��ꂱ��U�N�Ԃ��炢�g���Ă���̂ő厖�ɂ��悤�Ǝv���܂��B
�ł��l�͋@�B�̎��v�������Ǝv���܂��B�Ȃ��Ȃ畁�ʂ̎��v�Ɣ�ׂĉ��ɂ����ăX�g�b�v�E�H�b�`�Ƃ��A���[���Ƃ����t���Ƃ������Ă��邩��ł��B�����䂤�@�\����������A�����Ǝg���₷���Ȃ�Ǝv���܂��B���̕����A�X�g�b�v�E�H�b�`�Ƃ��Ŏ��Ԃ̐��m�ɑ��ꂽ��A�A���[���Œ��ɂ�����ƋN�����܂��B�r���v����Ȃ̂��������炻�ꂾ���ł��낢��ł��邩��ł��B�ڂ����ق����Ǝv���܂����B
���ʂ͘r���v�͂����Ȃ��ƂɎg����̂��킩��܂����B��ԑ厖�Ȃ��Ƃ͂ǂ��łł����Ԃ̒m�邱�Ƃ��ł��邩��ł��B�ڂ��͂��������Ƃ��낪�����Ǝv���܂��B
�u����������v�v�����@���炳��̃G�b�Z�C
���w�Z�̂���悭���Ă������v�͏����ς�����`�����Ă����B�K���X�̎M�ɐj������悤�Ȍ`�������B����������ׂ��Ƃ���ɂ͔����~������A���̎���͐^�����������B
���w�Z�̂���͗V�щ߂��ł������邭�炢�V��ł����B�Ăł��~�ł������܂��Ȃ��Œ��w�O�N���Ŏ������Ńq�[�q�[�������ł��錻�݂̖l�ɂ͐M�����Ȃ��قnj��C�������B���߂���ɒ��H���I����Ƃ��̂���̖���ł������ߌ�T���܂ŗV�B������V��ł��V�ё���Ȃ��Ă��܂ł��F�B�Ɖ߂������������B
������̂��ƁA�����̂悤�ɗF�B�ƗV�B�ߌ�Q���܂ł̓e���r�Q�[�������A���ꂩ��߂��ɂ���R���r�j�ɍs���āA�܂��P���ԃQ�[��������āA����̂T���܂ŊO�ŗV�B���̃X�^�C���ŗV�B�O���͂��Ȃ������B�S�������ȂǁA�y���߂Ă������낪�Ȃ������B�����X���Ǝ��v���C�ɂȂ�n�߂�B�V�тɖ����ɂȂ��Ă��Đe���Ăтɗ����A�Ƃ������Ƃ��悭�������B����Ƃ��܂��ē��������킯�����Ă����B
�u�����āA���������ĂȂ�����A���܂��������̂ɁB���Ԃ��Ƃ��Ȃ�ċC�Â������v
���̎��v�ɂ́A�����������ĂȂ������B�����킯����ɂ͑�ϓs���̂悢���v�������B
����Ȏ��v���A���͂����ǂ��ɂ��������킩��Ȃ��B���̎��v�͓����̂���߂Ă��܂����B�l���قƂ�ǗV�Ԃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ����B�ЂƂ̐ߖڂ��I������̂��Ǝv�����B�����̎��v�̑���ɂ��鎞�v�͂ǂ��ɂł�����悤�Ȏ��v���B���������Ƃ����Ԃ�����Ă��邱�Ƃ���������B���̂���́A�T�ɉ��x���V�ԂƂ��������������ȂǍl�������Ȃ������B�������A�l�͍��A���w�����獂�Z���ւƂ����l���̕���_�܂ł��Ă���B
�u���ꂩ��̎��ԁv�x�c�@�L������̃G�b�Z�C
���B�ڊo�܂����v�̉��B���������Q�Ă������B������A�C���t���Ȃ��ӂ�B���ɂ́A���������b�ɂȂ��Ă���ڊo�܂����v������܂��B���̎��v�ɂ́A�����Ԃ����b�ɂȂ��Ă��܂����B
����́A�O�N�O�B���̒a�����ɁA���̎��v�͂���Ă��܂����B�`�N�^�N�Ɖ��𗧂āA�傫�ȉ��Ŗ邻�̎��v�́A���̑厖�ȗF�B�����̂��߂ɁA�ƃv���[���g���Ă��ꂽ���̂ł����B�����A���w���ɂȂ����A�����炢�����Ǝ����ŋN���悤�B���͂���Ȃ��Ƃ��v���Ă��܂����B���̎�����A���͂��̖ڊo�܂����v�̂����b�ɂȂ��Ă���̂ł��B
������Ċ������������v���A���ƂȂ��Ă͂����̖ڊo�܂����v�B���������邿����Ƃ��邳�����v�ł��B�N����܂Ŗ葱���āA���Ə����ł��Q�悤���̂Ȃ狖���Ȃ��l�q�B�������A�N������Ă��܂��܂����B�ł��A���̖ڊo�܂����v�����邩��x�����Ȃ��Ă��ނ̂��ȁA�Ɗ��ӂ��Ă��܂��B
���́A���ꂩ������̖ڊo�܂����v�̂����b�ɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B���w�Z�O�N�Ԃ̎v���o���A���v�̒��ɍ��܂�Ă���̂ł��B���Ԃ͂��������Ɖ߂��Ă����Ă��܂�����ǁA���̈ꕪ��b���ɂ��Ă��������A�����v���Ă��܂��B���ꂩ��̖������A�������ĕς���Ă����̂ł��B������A���͎��v�Ƌ��ɐ����Ă���̂ł��B���ꂩ����A���̖ڊo�܂����v���ɂ��Ă��������ł��B
�u�p�b�|�p�b�|�A�n�g���v�v�����@���T������̃G�b�Z�C
���v�Ƃ����čŏ��Ɏv���o���ꂽ�̂��c���̉Ƃɂ������n�g���v�ł����B���̃n�g���v�͈ꎞ�Ԃ��ƂɁA�u�p�b�|�A�p�b�|�v�ƈ��炵�����Ŏ������Ɏ��Ԃ������Ă���܂��B
�̂͂��̃n�g�̐������܂�D���ł͂���܂���ł����B�Ȃ����Ƃ����ƁA���������e�ʂ݂�ȂŊy�����V�萢�Ԙb��������Ɛ���オ���Ă����̂ɂ��̃n�g�̐��̂����ŁA�u���A�����A��Ȃ��Ɓv�ƌ����Ă݂�ȋA��x�x���n�߂Ă��܂��̂ł��B�������ŋ߂ɂȂ��Ă̓n�g�̐��������Ă��N���A�肾���Ȃ��Ȃ�܂����B�����玄�̓n�g�ɏ������悤�ȋC�����Ă��ꂵ�������ł��B�����Ă����n�g������Ȃ��Ȃ�܂����B�ނ���A���Ă���p�����킢���Ǝv���悤�ɂȂ�܂����B
���N�̉āA�c���̉Ƃ����Ē������ƂɂȂ�܂����B�v���o�̂����ς��܂��������A���������ɂ������S���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B���͂��̏�ɔ����Ă܂�����ȉƂ��ł���Ƃ����Ă��܂��B�v���o�Ȃ�čŏ����疳���������̂悤�ɂ����Ă���̂ł��B�Ȃ����l���������̉Ƃɂ����肱��őԓx�ł��������Ă���悤�ł��B�������ɕ����������悤�Ȋ��������܂����B���������̒��ł��́u�p�b�|�A�p�b�|�v�Ƃ��̂܂ʂ��Ȑ����������Ă���̂ł��B���̏u�ԁA�u���A����ς肱���͑c���̉Ƃ��B�݂�Ȃ̏W�܂�Ƃ��낾�B�v�ƈ��S�ł����̂ł��B
���̎v���o�̕i�̓n�g���v�ł����B����͒N�ł���l��l�������Ƃ̂ł���f�G�Ȃ��̂��Ǝv���܂��B�v���o�̕i�͎������〈�邾���łق��Ƃł���s�v�c�ȗ͂������Ă��܂��B���͂���ȕi��������������Ă��������Ǝv���܂��B
�u�K�̖ڊo�܂����v�v��@�G���q����̃G�b�Z�C
�����g���Ă���ڊo�܂����v�́A�K�̌`�����Ă���B���w�Z�ɓ��w�������ɖ^�ʐM���炩����w�j�Ƃ��āA�����Ă����B�܂�A���̉Ƃ�9�N�キ�炢�������Ă��邱�ƂɂȂ�B�Ȃ��Ȃ����Ȃ��B�������A�u���͂�[�����A������[�N���ā[�A�N���ā[�B�v�ƌ����Ȃ���A�l���N�����B��͂Ȃ��Ȃ��ɂ��₩�ŁA�N�����ꂽ��g�N���Ȃ��ẮE�E�E�h�Ƃ����C�����ɂ�������B
����ȒK�̖ڊo�܂����v�́A�����Ƃ����ɒ��w�֓����������܂��A�����h�Z����w�����Ă���B�͂������Ǝv���͂������Ƃ͂ł���̂����A���͂����Ă͂����Ȃ��B�Ȃ����Ƃ����ƁA���̒K�ɂ͏��w�Z�̍�����̎v���o�����܂Ă���Ǝv�����炾�B�����h�Z�����͂������Ƃɂ���āA�v���o�������Ă��܂��悤�Ȃ�������B����Ȃ��Ƃ�����Ɏv���Ă���̂́A���������낤���B�Ƃɂ����A�K�̓����h�Z�����͂������Ƃ́A�ꐶ�Ȃ��̂ł���B
���āA���܂Ŏ����N�����Ă���A�����̊�������҂���Ă���K�����A�ŋ߂͂��܂�N�����Ă���Ȃ��Ȃ����B�Ȃ����낤�Ǝv���A�e�ɕ����Ă݂�ƁA�v��ʕԎ����B
�u���A�����łƂ߂Ă��B�v���E�E�E�B���܂ł���ق߂������Ă����K�ɂ��A��_��1�B����́A�������������Ƃ��B�ڊo�܂����v�Ƃ��āA�v���I�Ȍ��_���������K�ɂ́A�Ƃ肠�����A������Ď����N�����Ă��炨���Ǝv�����A�����A���͂ŋN�����悤�ɂ���낤�Ǝv���B
�u���o����̎��v�v����@��仂���̃G�b�Z�C
���̎v���o�̘r���v�́C�g���̂��o����ɂ�������r���v�ł��B���̏��߂Ă���������F���r���v�͂��o���������Ă����r���v�ł����B���F���ĉ��炵���f�U�C���̂��̘r���v�́C���o����̓��ʂȕ������̂ɂ�������炸�C������܂��m��Ȃ������������������́C���̎��v�����o����ɂ˂��葱���Ă��܂����B
���w�Z�l�N���̎����͘r���v�Ƃ������̂ɓ���Ă��āC���o���������Ă����r���v���ƂĂ������܂����v���Ă��܂����B�����������̎��v���˂���ƁC�����������悤�Ȋ�ŁC��������肩�킳��Ă��܂����B���͂悭���o����̉ƂɗV�тɍs���Ă��āC���̓x�r���v���˂����Ă��܂����B���ꂳ���̘r���v�Ƃ悭�����f�U�C���̘r���v�����ƌ����Ă��ꂽ�̂ł����C���̎��̎��́C���o����̉����r���v�������ɂȂ����̂ŁC���v���Α��Ȏ��������Ǝv���܂��B
���������Ęr���v������Ȃ��������o���C�������w�Z�Z�N���ɂȂ���������C�ˑR�u�������v�ƒZ���ꌾ�Ŏ��̎�ɉ��F���r���v��n�����̂ł��B����Ȃɖ����˂��葱���āC�����˂��鎖����߂����Ă�������ɂ�������Ƃ��̘r���v�����ꂽ�̂ł��B���ꂵ���Ɠ����ɁC�������G�ȋC���ł����B���̓��C���ꂳ��ɂ��o����Ƃ������Ă����l���ʂꂽ�Ƃ����b�����̂ł��B���͕��G�ȋC������C�ɐ�����C���ł����B���������ق������Ă������̘r���v�́C���l����̃v���[���g�������̂ł��ʂꂽ���l�̃v���[���g�Ȃ�Ă���Ȃ��ƁC���̏��ɉ���Ă����̂ł��B
�����Ƃق����������v��������čK���ȋC���͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
���ł����m�Ɏ��Ԃ������Ă���邻�̎��v�����͂����Ƃ��o����̑O�Ō������炵���������Ă�낤�Ǝv���܂��B
�u�`�����v�v�����@������̃G�b�Z�C
���v�͕s�v�c���B���ԂƂ���������Ԃ̒����������ɂ������Ĉ�������C���������ōs���̂��B���̒��ň�ԐS�Ɏc�鎞�v�͊w�Z�̎��v���B
�w�Z�̎��v�́C���܂łň�ԁC���ꂩ������[���ƈ�Ԏ����ł点�鎞�v���B�e�X�g���C�N���X�S�̂��Â܂肩����C�e�X�g�ɏW�����C���M�����钆�C������l�����ʂ�ɓ������v�B����ȂC�ɂ��Ȃ��Ƃ������傫�ȉ��𗧂Ď��Ԃ����̂����B�ɋ����Ă����B�ł��Ă���Ƃ����̉����ƂƂĂ��ł�B�ł��C���v���Ȃ���Ύ��Ԕz�����ł��Ȃ��̂Ōv��𗧂Ăčs�������邱�Ƃ��o���Ȃ��B
�����āC���C���B�ɂ͈ꕪ��b���ƂĂ���Ȏ����B����Ȏ��������炱�������ʂ�s�����鎞�v���K�v�ȏ�ɂ��������ɓ����Ă���悤�ȋC������B����ȂƂ����v���Ӓn���Ɍ����Ă���B
�ł��C���̗F�B�͎��v�����������Ƃ�������邮�����Ă��Ď₵�������Ƃ����B�悭�Ӗ��͕�����Ȃ������v�Ɋ����������₵�����Ă���Ƃ������Ƃ��낤�B
��̎��v�ł��݂�Ȃ̌����ɂ���Ď��v�ɑ��Ă��낢��ȍl�����o�Ă��郓���Ƃ͎v��������͂荡�̎������������Ɏv����Ƃ����݂̂͂�ȓ������Ǝv���B
�u�~�܂�ʂ��́v�K���@��h����̃G�b�Z�C
�����P�S�N�R���B���͍����s���~�����w�Z�𑲋Ƃ����B���̑��ƋL�O�Ƃ��āC���B�T�N���̓I���W�i���̊|�����v��������B�����Ō`�����߁C�f�U�C�����C�������Œ���C�F���ʂ��Ďd�グ�����v�B���̎��v�ɂ͎��̏��w�Z�U�N�Ԃ̊y���������v���o�C�ꂵ�������v���o�C��������̎v���o���܂��Ă���B
���̓f�U�C���ɂƂĂ��Y�B�ǂ������f�U�C���ɂ���C���v���o�[�����̂ɂȂ�̂��B�Ȃ�������C���̎q�Q�l���������Ƃɂ����B���ǂ��̏ے��B���͂��̎��P�Ԓ��̂悩�����q�ƁC�������������B���܂ł����ǂ��ł����܂��悤�ɁB�Ƃ����肢�����߂āB
���C���̎��v�͎��̕����ɂ������Ă���B���Ƃ������̓�����P�x���~�܂邱�Ƃ��Ȃ����������Ă���B���̓����Ă��鉹�́C�h�����Ƃ������Ē���ł��ē��ɂ͂܂��܂��傫�ȉ��ƂȂ��ĕ������Ă���B���̑����̃��Y�~�J���ȉ��́C���ɑO�i����Ƃł������Ă���̂��낤���B���������ɂ́C���̉����āC�Ȃ��ނȂ��������邱�Ƃ�����B���v�Ƃ͕s�v�c�Ȃ��̂��B
�����Ǝ������Ă��Ă��鎞�v�B���̑S����m���Ă��鎞�v�B���̎��v�͎����̂��̂��B���v�̂悤�ɁC�����ƕ��������Ă��������B�~�܂邱�ƂȂ��C�������ƂȂ��C�����̓������ł��������B�����āC���ꂩ��������Ǝ������Ă��Ă���邱�Ƃ�����āE�E�E�B
�u���v�Ƃ̎v���o�v���n�@���ۂ���̃G�b�Z�C
���v�͎��ɂƂ��āA��ɕK�v�ȂƂĂ�����ɂȂ镨�ł��B�ڊo�܂����v��|�����v�A�g�т̎��v�B���낢��Ȏ��v���g���Ă��܂��B�����A���̎��v�ɂ́A���낢��Ȏv���o������܂��B
�܂���ڂ́A�g�т̎��v�ł��B���܂蒷���Ԏg�������Ƃ͂Ȃ�����ǁA�m�ɍs���Ă���Ԃɂ��m�̎��v�����Ȃ��Ă��A�����ɂ��̏�Ō����邵�A�ߋ��������Ƃ��Ɏ��Ԃ��v�邱�Ƃ��ł���A�^�C�}�[�ɂ��Ȃ�B�m�ł������Ă���Ă��镨�ł��B
���́A�|�����v�ł��B���̕����ɂ���|�����v�ɂ́A���炳�ꂽ���Ƃ���������܂��B��́A�w�Z�ɍs���O�A���̊|�����v������ƁA�V���Q�T���������̂ɁA�e���r���݂�ƁA�V���S�O���ŁA�낤���x������Ƃ���ł����B�P�T�����x��Ă���Ȃ�ĐM�����܂���ł����B������́A�Ƃʼnߋ�������Ă��āA���Ԃ��v��Ȃ��炵�Ă��āA�ӂƎ��Ԃ����Ă݂�ƁA�v��n�߂��Ƃ��̎��Ԃƕς���Ă��܂���ł����B�b�j�����j�ƒZ�j�ɂ����������݂����Ɏ~�܂��Ă��܂����B�����������܂ܓ������Ƃ��Đk���Ă���̂ŏ����������납�����ł��B�����āA���Ԃ͌v�蒼�����ƂɂȂ�܂����B���̊|�����v�ɂ͍��炳��Ă���ł��B�����ǁA��������̎��v�Ƃ̈�̎v���o���Ǝv���܂��B
�Ō�ɖڊo�܂����v�ł��B�ڊo�܂����v�͎��Ԓʂ�ɋN�����Ă���邵�ƂĂ����ɗ����Ă���Ă��܂��B�����ǁA���̎��v���܂��A�������点����������܂��B�Q�Ă��鎞�ɓ��̏�ɗ����Ă�����A�x�������������ĉ�����Ȃ�������A���̑��F�X�Ȃ��Ƃ�����܂����B����ǂ���ł�����ς肢���v���o���Ǝv���܂��B���̂悤�Ȏv���o�����邩�炱�ꂩ������v��厖�ɂ��Ă��������ł��B
�u�����v�����@����q����̃G�b�Z�C
���v�̃R�`�R�`��������������ʂ�ʂ��Ď��̐S�ɐU�����Ă����B�V�[���ƂȂ������A���ړ`����Ă���B�R�`�R�`�Ƃ������ȊO�ɁA�Ɠ��ȉ��A�����ȉ��A�L�c�C���A�Ȃǂ����܂�Ă����B�ł��P�Ɏ��v�̓R�`�R�`�������������ɓ`���Ă���Ȃ��B
�߂����āA���݂������ŁE�E�E�B
���������A���͂ƂĂ����v����D���������B�f�W�^�����v�A�|�����v�A�r���v�A�j���v�A���낢��Ȏ�ނ̎��v���D���ŁA�ǂ����ɏo�����Ă����v������ɓ���A�e�����点�Ă����B�ǂ������̂悤�ɋP���Ă��āA�����Ƃ肱�ɂ����B�N�㕨�⌻�㕨�Ȃǂ̎��v�����ׂ��Ă��āA�ق����Ăق����Ă��܂�Ȃ������B��e�╃�e�Ƀ��K�}�}�������A�u�����Ĕ����āB�v�ƍ��点�Ă����B���v������̒��ł́A�P�O�O�ȏ�̎��v�̉������̎��ւƓ`����Ă����B
�����Ȏ��v�͂ǂ�������悳�����Ɍ����āA�y���܂��Ă��炦��B���������Ȏ�ނ������Ă��邪�A����ς莨�����܂��Ɖ����������Ă��鎞�v���D�����B�����Ȏ��v�̂��܂��܂ȉ����Ђт��A���������Ƃ��낪�D���ɂȂ�A�ǂ�ǂ�̂߂肱��ł����B���L�C�̖L�x�Ȏ��v�ɏo����Ă��Ȃ����v�B�ɏo����Ă��������Ȃ��Ǝv���B
�����Ă����Ȏ��v�̌��I�ȕ����ɖڂ������Ă����A��������葽�������čD���ɂȂ��Ă��������B
�u���ӂ���B�v�l�{�@��������̃G�b�Z�C
�s���N�̎��v�A���F�̎��v�A�̎��v�B�ŋ߂́A���X�ƐV�������v����������Ă���B���͏��������A�X�ɍs�����тɎ��v�����Ă����������B�������˂���A���˂���B�����炨�ꂳ�A�a�����ɗ~�����������v���Ă��ꂽ�B�Ƃ��Ă������������B������A�������̕����̎��v���B���́A���̎��v�����Ȃ��ƁA����̉^���������Ȃ�悤�ȋC�����Ă��܂��B�Ƃ������A���v�͕K������Ǝv�����E�E�E�B
���͂悭�x�������Ă��܂��B�����̎��ԂɉƂ��o�Ă��܂��B���������̂��B�ł�������A���͗F�B�̉Ƃɖ̎��Ԃɍs�����B����́A���ꂳ�S�Ă̎��Ԃ��ܕ����炵�Ă������炾�B���̂��߂ɂ��炵���̂ł͂Ȃ��Ǝv�������̂������Œx�����邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ����B�����A���̎��v�Ɋ���Ă��܂��A�ܕ��قǂ�����肵�Ă��܂��B����ȗ]�T�͂Ȃ��̂ɁE�E�E
�����ǁA�����ŋ߂͎��Ԃɗ]�T���ł����Ǝv���B�Ȃ��Ȃ�A�ŋ߂͌g�ѓd�b�̃A���[����ݒ肵�Ă��邩��B�����傫���̂ŐQ�Ă��Ă��A�������Ă��Ă��������Ă���B
������A���Ԃ������킩��B�g�ѓd�b�͕֗����ȁB�ł��������肪����B����͕z�c�̏�ɂ���Ɖ����S�R�������Ȃ��̂ł��B����ς莄�͒x���܂B
���v�͎������Ɏ��Ԃ������Ă����B���v���Ȃ��������l������������܂����B�����Ă͂Ȃ�Ȃ������Ǝv���B�̂̐l�͂ǂ�����Ď��Ԃ��������Ă����̂��낤�B���v�͖��������Ă����B���v�Ɋ��ӂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��ˁB
�u�����Ă���v�����@������̃G�b�Z�C
���̕����ɂ́A�ۂ����F�̊|�����v������܂��B�w�s�n�l���i�d�q�q�x�@�j�������x�̎��v�B���e�����̂͂��߂Ă̒a�����ɔ����Ă���܂����B�c���������̊�����傫�Ȋ|�����v�B�����Ȃ��炾�ł�������Ɗ|�����v������������Ă����悤�Ɏv���܂��B�����������|�����v�ɓd�r����ꂽ�S���P�O���A���̂Ƃ����玄�̎��Ԃ͓��������Ă��܂����B
�u�J�`�b�B�v�Ɠd�r����ꂽ�u�ԁA���v�̕b�j�͓��������܂��B�����Y�܂ꂽ��B���������Ă���B���v�̗��ɂ́A���̎Y�܂ꂽ���Ǝ��Ԃ��A�����}�W�b�N�ŏ�����Ă��܂��B���̎��v�͍��ł����̕����̓��̕ǂɂ������Ă��܂��B�����߂��������Ƃ��A�₵�������Ƃ��A���������Ȃ����Ƃ��������B�ǂ�ȂƂ��ł��A���̎��v�̗������邾���Ō��C�ɂȂ�܂����B�u�����Y�܂�Ă������Ƃ͊ԈႢ�ł͂Ȃ��B�����Əj�����Ă����l������B�v�����v���ƁA�Ȃ��C�������[���ƌy���Ȃ��āA�u�������Ί�ɂȂ��B�v�Ǝv���܂����B
�P�T�N�Ԃ����ƈꏏ�ɉ߂����Ă������̎��v����x�����A���v�̐j���~�܂��Ă��܂������Ƃ�����܂��B�Q�Ăĕ�ɑ��k����ƁA�u���\�g��������˂��B�����������ȁB�v�ƌ����܂����B���́A�u��ɂȂ������I�I�v�ƕ��ɖ����������ďC�����Ă�������L�������肽���B���̂���̎��͕K���ł����B�ǂ����Ă����v������������Ȃ���������ł��B�������e�ɁA�u�V�������v���Ă����邩��B�v�ƌ����Ă��A��Ɏ���c�ɂ͐U��Ȃ��������낤�Ǝv���܂��B���̎��v�́A���������Ă������Ƃ��A�F�߂Ă��ꂽ���̂�����B���̐S�̎x������������B
���݂����̕����̓��̕ǂɂ́A���F���ۂ����v������܂��B�F�����ă{���{���ɂȂ��Ă��A�j���~�܂��Ă��A�����Ǝg��������Ǝv���܂��B�����Ƃ��ꂩ��॥������l�ɂȂ��Ă॥�����B
�u�������Ǝ��v�̊W�v����@�S�G����̃G�b�Z�C
�����A���v����������ƌ��Ă݂��B���v�̓`�N�^�N�Ɠ����Ԋu�ŁA�������Ԃ����ށB���v�ɂƂ��ẮA�������Ԃ�������Ȃ����A���B�ɂƂ��ẮA���ꂼ��Ⴄ���Ԃ��B
�����u�����������ł܂�Ȃ��v�ƌ����l�����邾�낤�B�m���ɁA�w�Z�ɂ���Ǝ��B�͎��v�ɂ���Đ������d���Ă��܂��Ă���B�����A�������Ԃɓ����������Ă��邩�̂悤�Ɏv���Ă��܂��B�ł��A���̎��̈�u��u�̋C�����������Ȃ킯���Ȃ��B����́A��������Ɏv���Ă��邱�Ƃ�����ǁB����Ӗ��A���B�Ǝ��v�͑ΏƓI�ȑ��݂Ȃ̂�������Ȃ��Ǝv�����B���B�͎��v�Ɠ����l�ɍ��X�Ǝ�������ōs���B����ǁA���v�Ƃ͈Ⴂ�A���B�͎��Ɉ��v���o��������ł���̂��Ǝv���B
�ł��A���v�̒��ɂ��A�����v������̂��鎞�v�����邾�낤�B�Ⴆ�A�̂Ƃ��Ɏg�������v��A�v���[���g�ɂ���������v�E�E�E����Ȏ��v�B�ɂ́A�����Ɠ��ʂȎv�������邾�낤�B���w�ɂ��u�傫�ȌÎ��v�v�Ƃ����Ȃ�����B���̓ǂ{�ɂ́A�u�傫�ȌÎ��v�̉̎��͎��b�ł���v�Ə�����Ă����B�����A�M������Ƃ�����ǁA����ς肻�́A�Î��v�ɓ��ʂȎv�������������炱���A�N�������Ƃ��Ǝv���B
���B�Ǝ��v�̊W�́A�ƂĂ����G���Ǝv���B�����A�������ԊԊu�����ݑ����鎞�v������A�����Ǝ����̈ӎv�������Ă��邩�̂悤�Ȏ��Ԃ�����B�{���́A�S�Ă̎��v�Ɉӎv������̂�������Ȃ��B������m���߂邷�ׂ͂Ȃ�����ǁE�E�E�ǂ���ɂ��Ă��A���v�͎��B�̐����ɐF�X�ȉe����^���Ă�����ŏd�v�Ȃ��̂��Ǝv���B
�u���v�͐����Ă���v�V���@�ؓނ���̃G�b�Z�C
���̐��E�͋�ԓI���B���v�́A���̐��E�ɒP�ʂ������悤�Ȃ��̂��Ǝv���B
���v�́A���܂ł̗��j�̂��ׂĂ�����ł����B���E���̐l�X�̎v���o������ł����B
���v�́A���ׂĂ�m���Ă���B��Ԑg�߂ŁA�������B�Ɨׂ荇�킹�ł���B�����玄�́A���v���Ȃ��Ȃ�ƕs�����̂��Ă��܂��B
���́A�s�����x���������A�悭���v�����Ă��܂��B�R���r�j�Ȃǂ̏ꏊ�ŁA���v���Ȃ��Ƃ��낪����ƁA���͂������Ă��܂��B���������Ȃ̂����킩��Ȃ��ƁA���Ƃǂꂭ�炢�ŋA��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��ȂǁA����Ȃ��Ƃ����ׂĂ킩��Ȃ��Ȃ�B�����s���ƐS�z���������c��Ȃ��B���v�́A���Ɍv��𗧂Ă����Ă����B���ɂƂ��Ď��v�Ƃ́A�̂̈ꕔ�̂悤�Ȃ��̂�������Ȃ��B�Ȃ��Ȃ��ẮA�����Ȃ����́B���ɂȂ��ẮA�Ȃ�Ȃ����́B���v�͑傫�ȑ��݂��B
����ǁA�������ł͂Ȃ��B���E���̐l�X�����v��K�v�Ƃ��Ă���B�������v���Ȃ���A���̒n����̐l�X�͂ǂ��߂����Ă����̂��낤�B�v���o�̎��Ԃ����܂�Ă������Ԃ��A���ׂĎ����Ă��܂��B�����玞�v�͂Ƃ������ݑ����Ă���B
���B�͂܂��C�Â��Ă��Ȃ��B�ǂ�ȂɎ��v�����B�ɕK�v�Ȃ��̂��B����́A���v�����B�̋߂��ɂ��肷���邩�炩������Ȃ��B���B�́A���v�Ƌ��ɐ����Ă���B���A���B�́A���ڂŌ��Ȃ��瑫���Ɏ��v�̉���ʂ�߂��Ă���B����ǁA�����Ƃ����C�Â����낤�B���v�́A���̐������ݏo���Ă���B
�u���������鎞�v�v�T��@������̃G�b�Z�C
���͏�ɍ��ݑ����A����͏�ɐi��ōs���B�����̂��`�͕ς��ǁA�l�ƂƂ��ɐ����A���ݑ����Ă������v�B���v�͎��Ɍ������ƈ��炬��^����Ǝ��͎v���B�S�n�悢���̉��B���������ɐl��f�킷���B����Ȏ��v�͈�ŏ\�����Ǝv���B
���̕����ł́A�|�����v�A�f�W�^�����v�ȂǎO�̎��v���u���Ă���B����͎g���Â������́A�F�l�������������́A�V�������������́A�v���o���l�܂������̂���Ȃɂ��v��Ȃ����̂܂ł��܂��܂��B�̂Łw�傫�ȌÎ��v�x�Ƃ����薼�̂��̂�����B���̉̂ł́A�����������܂ꂽ�Ƃ��ɉƂɗ��āA����������Ɠ����Ƃ�������ł���B���͂܂����̐l���ƁA���ɐ����Ă��ꂽ�Ƃ��͖����B�ł�������ł��x���Ȃ����狤�ɗǂ��čs�����Ǝv���B
�����v���ɁA���v�͕K���i���Ǝv���B�o������Ƃ��͘r���v�������čs�����A�V�ԂƂ����A�ς���Ƃ������ׂĎ��v������B���̖���́A�����ƁA���߂��Ă���B�܂��A�V�тɍs���Ƃ��ɂ͕K���e���u�����ɋA���Ă���v�ƕ����̂Ŏ��v�����Ȃ��瓚����B�w�Z�ɍs���Ƃ������v�����邵�A���ƒ����A���v������B���Ԃ�m��ɂ͂ƂĂ���Ȗ��������Ă���̂Ŏ��͐����Ă��������łƂĂ����Ԃ͑���Ǝv�����B��ɂ��Ă��鎞�v�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����炷���Ɏ̂ĂĂ��܂��l�����邪�A���͎��v���~�܂��Ă���Ȏv���o�Ƃ��Ďc���Ă������Ǝv���B
�u��Ȏ��ԁv�����@�I��������̃G�b�Z�C
���̉Ƃɂ́A���v����������܂��B�������v���W�߂�̂��D��������ł��B��K�����łP�V������܂��B����ȂɕK�v�ł��Ȃ��Ǝv���܂��B�r���v�����ł������ς�����̂ɁA�Ȃ�ł���ȂɏW�߂�̂����s�v�c���Ǝv���܂��B����ǁA�����Ȃ������Ȃ���A�����ɂ͎��v���R����A�g�т����킹��ƂT�ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B�ł��g���Ă���̂͌g�тƊ|�����v�����ł��B���̎��v�͕K�v������܂���B
���͂�����ƂɎ��v�������Ă��c�O�Ȃ��Ƃɂ́A���Ԃ���邱�Ƃ��ł��܂���B�w�Z�����N����̂��炭�āA�V�����炢�ɋN���Ă���x�Q���Ă��܂��ĂW���O�܂ŐQ�Ă��܂��܂��B�����Ă�����Ɏ��v������ƌ����Ă��܂��B�e�X�g�̓��͂�����ƍs���Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂ŁA���傤���Ȃ��N���Ă��邯�ǎ��v�����܂Ɍ���ƃM���M���̎��ԂɂȂ��Ă��܂��čQ�ĂĊw�Z�ɍs���Ă��܂��B���Z���v���ȂƎv���܂��B�@
����ς莞�v�͕K�v�Ȃ̂��Ǝv���܂��B�����āA�����Ă������߂ɑ厖�Ȃ��̂̂P���Ǝv���܂��B��l�ɂȂ��Ă��A�����̎���ɂ��K�v�����A�}���ł��鎞�Ɏ��v���Ȃ��ƂƂĂ�����̂ł��ꂩ��́A���傭���傭���v�����悤�Ǝv���܂��B�����āA���Ԃ��Ɏ��邵�����肵���l�ɂȂ肽���Ǝv���܂��B
�ł��v���A�w�Z���炢�͂����ƍs���Ȃ��Ƒʖڂ��Ǝv���̂ŁA�܂��͂����Ɗw�Z�ɍs����悤�ɁA�ڊo�܂����g���ȂljƂ̎��v���\���Ɏg���Ă������Ǝv���܂��B
�������炻�̂������v�̗ǂ��������Ă��邾�낤�Ǝv���܂��B
�u�s�莞�@�Ŏ�������Łv����@��������̃G�b�Z�C
����A���F�B�Ə�쓮������K�ꂽ��A��������y���݂ɒJ���֑���L�������ł����B
�v���Ԃ�ɖK�ꂽ���߂��A�����Ȃǂ̓y���������A�܂�Ŗ��H�̂悤�ȏ����ȓ��ɖ�������ł��܂��܂������A���̎��A���R�A���铹����ׂ��������̂ł��B����͑喼���v�����ق֓����Ă������̂ł����B
�������́A�D��S����`���A���̔����قɍs�����ƂɂȂ����̂ł��B
���̔����ق́A���a��\�Z�N�ɓ��|�Ƃ̌́E�����N���A���W���Ă����喼���v��W�����邽�߂ɍ��ꂽ���I�Ȕ����قŁA���݂́A���ڂ̏�����������p���ł�������Ⴂ�܂��B
�������܂����A�ꌩ�����疯�Ƃ̂悤�ł��炠��܂����B
���ɓ���ƁA���̓W�����ɂ́A�g�̏�Ɠ������炢�̑傫���̑喼���v���A���\�ƕ���ł��܂����B
�t�����V�X�R�E�U�r�G���̗����ȗ��A���̋Z�p�́A�䎞�v�t�Ɛ��̐E�l�ɓ`�����A�]�ˎ���ɂ́A����Ƃ₻�̑��A�ˎ傽���ɂ���Ď��Ě�����Ă����̂ł��B
�喼���v�̎��ɍ��ݕ��́A�s�莞�@�ƌĂ�A�G�߂₻�̏ꏊ�̓��Ǝ��Ԃɍ��킹�āA���߂ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B
�d���ŖZ�������X���߂����������ɂƂ��ẮA�V���̏d��ł������Ǝ�������ł����喼���v�ɁA�C�����]�ˎ���փ^�C���g���b�v�����悤�ł����B
�l�Ԃ́A�̂��玞�ԂƂ������̂ɒǂ��Ă����̂�������܂��A�喼���v�̂悤�ȗD��Ȏ��̍��ݕ��ł�����A�����Ɩ������ɐ�������̂ł͂Ȃ����Ƃ��v���܂����B
�u�������v�v�V���[���@�c�W���g����̃G�b�Z�C
�Ȃ����q���̍�����������v���~���������B
��������߂Č������̂��Ƃ����ł��o���Ă���B
�l�̓j���[���[�N�̃P�l�f�C��`�œ��{�s���̏o����҂��Ă����B���̂����A������}���̂��A�����ɒʂ�߂����V�a�m�̍�����킸���ɋ�̂����肪�����Ă����B���̌��p���C�V�����[�b�N�z�[���Y�̂悤�ł������Ă��B
���N�������āA���������Ƒ��Ƌ��s�ʼn߂������B
�w�r���̒n���Łu���N�ʃZ�[���v�Ə����ꂽ���S���̏�ɁA�������v�������፬���̏��i�̒��Ŗ�����Ă����B�l�͂��ꂪ�A�ق�Ƃ��ɓ������̂��m���߂������l���݂Ɉ��|����Ȃ���A���U�̒��A�ꂩ���������B��̂��N�ʂł����~���͂����A���������Ă͂Ȃ���̂��Ɣ����}�����B
�u�i�j���@�J�b�^�m�H�v
�u�������v�v
�u�J�C�`���E�@�h�P�C�H�v
��ɂׂ͍������{�ꂪ�����ł��Ȃ������B����܂ʼn��̋^����Ȃ��b���A�S�ɉ����Ƃǂ߂��u�J�C�`���E�h�P�C�v�Ƃ������{����������ɂ́C�悤�₭�O�肩�Ȃ��ċ�������A���̎��̖l�ɂ͂܂ǂ��낱���������B
�u�|�P�b�g�E�I�b�`�I�v�Ƃ��₭�p��ł��Ԃ����B
�u�I�[�m�I�@�\���n�E�S�N�m�H�v�A�Ƃ����ꂽ�\��̕�B
��~�̎��v�ȂǓ����͂����Ȃ��Ƃ�������ł������B
���̂Ƃ���A�ڂ��͉�ɕԂ�A��܂ꂽ�����玞�v�����o���m���߂Ă݂��B
��������C��܂ł��C���̉������v���Î������B
�Ă̒�A�����Ă��Ȃ��B������肩�u�����͂�v�́A���̐j�̂悤�Ɏ��R���݂ɂ��邮��Ɖ���Ă����B
�������Ԃ��n���X�̂ǐ^�ŁA�l�����S�l�͏�����ȉ������v���߂���A������܂��̌��t�Ő^���ɋc�_�����Ă����B�l�X�̎��������b�����ɒ�����Ă����B
�u�J�G�V�e�L�i�T�C�v�ƕ�͂����B
�������������C�ƕ����܂ł����������B
�����C�l�͌��������D����Ɣ������������v���D�������Ȃ������Ă����B
�W�[���Y�ɂ����āC���̂Ƃ��̘V�l�̂悤�ɕ��������B�����S�̒��ŋ���ł����B
���{�ʂ����F����ꂪ�A���ߑ������Ă����B
����ł��C��ꂽ���v�̓����������������l���݂āC
�u�A�����J�ɋA������Ȃ����Ă������B�v�ƕ����p��ňԂ߂Ă��ꂽ�B
�u�E���v�A�����A���Ȃ������Ƃ���A�ӂ��ɗ܂����ӂ�Ă����B
�u�I�[�P�C�[�A�E�S�J�i�N�e���C�g�|�P�b�g�E�I�b�`�h���D�V���[���̑�Ȏv���o�́v�A�Ƃ����Ȃ��珟���C�ȕꂪ�߂��炵���������߂Ă��ꂽ�B
��ɗ܂�@���Ȃ���C�l�̓W�[���Y�̃x���g���ɉ������v�̃`�F�[����ʂ����B
����m�点�Ă���Ȃ������Ă����B�悤�₭�����������B
�ڂ��͓��ӂ��Ƀ`�F�[�������������o���A�݂�Ȃ��݂Ă����悤�ɂ��Ă݂��B�����Ȃ���C������Ƃ�����l�ɂȂ����悤�ȋC�������B
�l�́u�������v�v�͍Ō�܂Ŏ�������ł͂���Ȃ������B�����C�v�����������Ƒ��̑�ȋL���Ǝv���o�����ޖ������ʂ����Ă��ꂽ�B
���N�����Ɛ������B
�V�����N���}����ƁA�l�͂ǂ̍��ɂ��Ă����s�ʼn߂��������N������A�Ȃ������v���o���B�c�����̒�⍡�ł̓`���b�s���N�V�������e�́A�Ⴋ���̎p�����݂������Ă���B�����Ċ��̈����o���̒��ō������݂̉������v�ɂ����Ɣޓ��̖���������̂��C���̍����炩�K�킵�ƂȂ��Ă���B
�u�Ƃ�X�q�̎��v��v���c�@�r������̃G�b�Z�C (12���̃x�X�g�G�b�Z�C)
�̋u�̐Ԃ�����
�Ƃ�X�q�̎��v��
������܂��@�L���R���J��
���G���G�q�R�r���Ȃ��Ă܂�
���̃e�[�}���y���������Ă���ƁA���W�I�̑O�Ɏ����߂Â��ĕ����������̂́A������T�O���N�O�ł��傤���B�P�O���N�O�ɋΖ����Ă����w�Z�����đւ��邱�ƂɂȂ�A
�u�ǂ�ȍZ�ɂ��@�悢���낤���v�ƊF�Řb�������܂����B
�N�����u���́@�r㻂̂悤�Ȍ`�������@�����f���C���Ȃ��Z�ɂ͎~�߂Ăق����v�ƌ����̂���v�����ӌ��ł����B
�����ŁA�����V���{���ɂȂ���̂�\���A���̂��錚�����ق����ƁA�s���ǂɂ��肢�o�Ă��낢��Ȉӌ������킳��܂����B
���̌��ʁA�Z�ɂ̉����ɑ傫�ȂƂ�X�q�̎��v��̂��錚���ɘb���i�߂�ꂽ�̂ł��B����́A�����g�ɂƂ��Ă��q���̍�����̖������������ł��B
�n��̐l�́A��Ɍ������Ď��v�䂪���т���Ȃ�A�n��ɂ͎������̎�ő傫�ȓ����v������Ă����悤�Ƃ����b�ɔ��W���Ă������̂ł��B
���̂悤�ɑ����̐l�̒m�b�Ɗ��Ŏ��v��Ɠ����v��������Z�ɂ����������̂ł��B
�]����Ƃ��A�n��̊F����u���̂Ƃ�X�q�̍Z�ɂ��ꐶ�Y��Ȃ��ł��������v�ƁA�u�Ƃ�X�q�̌`���������v�v���L�O�i�Ƃ��Ă��������܂����̂�Y��邱�Ƃ��ł��܂���B
�������̕����ŁA���̋L�O�̎��v����������ł���̂�ڂɂ���x�ɂƂ�X�q�̎��v��Ɠ����v���v���o���̂ł��B
�u�ڊo�܂����v�̃P�[�X�v���c�@�c�삳��̃G�b�Z�C
�l�\�N�O�ɂȂ邪�A���w�Z�̈�N���̃N���X�}�X�v���[���g�ɁA���e���ڊo�܂����v���Ă��ꂽ�B�����l�C�����Ƃ낦�Ă͂��Ȃ��A�����Ƃ��Ă͂�������̂˂��݂̃L�����N�^�[�̉��F���[���}�C���̖ڊo�܂����v�������B���ꂵ���ĕb�j�̃R�`�R�`�Ɠ����̂��A���ꂱ�����Ԃ�Y��Č��߂Ă����B
�s�v�c�Ȃ��̂ŁA�ڊo�܂��������ċN���悤�Ƃ���̂ł��邪�A���̂悤�Ȏ��ɂ͖ڊo�܂�����O�ɋN���Ă��܂��B�܂��A�ڊo�܂����v����Ȃ������ƕ���������ꍇ������B���ۂɂ͖��Ă���̂ł��邪�A�n�����Ă��Ėڊo�܂����炢�̉��ł͋N���Ȃ��̂ł���B���̂悤�ɁA���w�Z�̒�w�N�ɂ͖ڊo�܂����v�ɗ��鐶���́A�K�v�̂Ȃ����̂ł������B�������A���v�Ƃ������̂��ӎ�������ɂ́A�d�v�ł������ƍl���Ă���B���v�̕����Ղ��v�������ׂ鎞�A�킽�������̔N��w�́A�A�i���O���v�̕����Ղ��v�������ׂ�B�P���Ȑ����̈����Z�⑫���Z�ł͂Ȃ��A���j�ƒZ�j�̊p�x�ł����Ԃ̌v�Z������B���̏ꍇ�͂��̎v�������ׂ镶���ՂɁA�ŏ��ɔ����Ă�������ڊo�܂����v�̃L�����N�^�[���t���ė���̂ł���B
���̎��v�́A���N�ʼn��Ă��܂������Ȃ��Ȃ����B���̍��ɂȂ�ƁA���v���ǂ����ē����̂����������N��ƂȂ��Ă���B���R�A�h���C�o�[�������ďC���ɂ����邪�A���G�ȃ[���}�C�d�|���̐������v���C���ł����ɁA�������̃l�W���c���ė��W�͕����邱�ƂɂȂ�B�������ĉ��x���C���̐^�������s���A�Ō�̍v�����������v�͎̂Ă��邱�ƂɂȂ�B
�������A�ڊo�܂����v�̓����Ă�����F�̉~���̋����̃P�[�X�́A�܂����̎茳�ɂ���A�a���F������Ă���B������̋����̃P�[�X���A�l�̎�ō��o���ꂽ���̂ł���B�킫���ł͂��邪�A���i�̓��ꕨ���厖�ȏ��i�ł��邱�Ƃ������ł���B�����̎��v�̐����̔��Ɋւ��l�����́A�����܂ōl���Ă����̂��ƁA���v�Ɋւ��l�X�̔\�͂̍����Ɋ��S���Ă���B
������T�O�N�O�̏��a�R�O�N�i�P�X�T�T�j�~�A���͍��Z�̉��Ɍ������Ď��]�Ԃ𑖂点�Ă��܂����A�����ƂƂ��ɑ傫�ȕs���������Ă��܂����B���Ԃ̔z���ɂ������Ȃ����v���Ȃ������̂ł��B
���Z���̌Z�ɗ��݂܂������A�����͐�ΕK�v������݂��Ȃ��Ƃ����A��ɉ]���Ɓu�������̂͌Â�����˂��v�Əo���Ă͂���܂������A��͂�~�܂��Ă��ē����܂���B
�d���Ȃ����̂܂o�����܂������A���]�Ԃ������Ȃ���s���͕�����ł����B
�������̑ҍ����Ő[�ċz���J��Ԃ��A�C�𗎂��������Ă���ƁA���̖��O���Ă�u���}��t�܂ŗ��ĉ������v�ƕ���������܂����B��o���ނ̊ԈႢ���ȂƋ��鋰��s���Ă݂�ƁA�����ɂ͖����z�ȕ��̊炪����܂����B�����āu������g���Ȃ����v�Ǝ����̘r���玞�v���O���A���ɓn���Ȃ���u�撣��Ȃ����v�ƌ����c���A�^�N�V�[�ōs���Ă��܂��܂����B
�����̐Ȃɒ����āA���̎��v�����̋��ɒu�����Ȑ��w�̎������܂������A���Ԃ����܂��g���ĂȂ�Ƃ������Ȃ�̌��ʂ��o�����Ƃ��o���܂����B���̉Ȗڂ����������Ă��Ȃ��A���̋x�e�ɓ������̂ŕ�ɓd�b�Ƃ���A���ɒm�点����u���������v�ƌ����Ă��������ł��B�ߐ�̖�������^�N�V�[�����Ă����̂ł��傤�B���i�j���Ɏ��͂��̘r���v���˂���܂����B����̓C�M���X�̌R�p���v�Łu�G�j�J�[�v�Ƃ������O�ł����B���߂̐j�ɂ͌u���h�����h���A�Â��Ƃ���ł��͂����茩���A�F�B�Ɏ����������̂ł��B
���͂P�T�N�O�ɖS���Ȃ�A�B��̌`���Ƃ����鎞�v�͖���h���������A�t���[�����K�тĂ��܂����B�j�͓������A�P�P���R�S���Ŏ~�܂����܂܂ł��B�Âтċ@�\���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����A�����o���Ď��ɓ��Ă�ƁA���̖����z�Ȋ�ƂƂ��Ƀ`�N�^�N�`�N�^�N��������ł���C�����ĂȂ�܂���B�{���Ɏ��v�͕s�v�c�Ȃ��̂ł��B
�u����������̂Ƃ����v����@�C�Ƃ���̃G�b�Z�C
�c�n�̉䂪�Ƃł͍��A���ɂȂ�ƃR�[�h���X�d�b�̂��ƌg�ѓd�b�A���ɏ������Ĉ����ۂ��ڊo�܂������X�Ɩ�A�Y�ꂽ����ɒނ���̂悤�Ȍ`�́A���Ńs���N�F�̖ڊo�����v����܂��B���̖ڊo�����v�́A���̖l���\�N���O�A�܂��Ƃ�ڂ������������ꂳ�g���Ă������̂ł��B
���v�̐j�̉��ɂ܂݂������āA�l��ނ̉��F������܂��B����͍��ł�����A�`���̏����V���K�[�\���O���C�^�[�̉̂Ȃ̂ł����A�l���c�t���̂��납�炾�q�������Ȃ��Ă����܂����B�܂������ˑR���A�K��Ƃ�ڂŎ~�܂�悤�ɂȂ�܂����B���̎��ɉ��������Ȃ�A�������Ȃ��Ă����܂����B�ł�����������Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ł��B
���̊ԁA���v�͋������z�������܂����B�l�����܂ꂽ�����A�Ƒ��������������A���v�͂Ȃڗ����Ȃ���������ւ�ɂ��܂����B
�����͂Ƃ��������Ȃ̂ŁA���͂ڂ��Ƃ������̂��Ă݂�ȖZ�����ł��B�ł��ڂ��͍Ō�̖ڊo�����v����X�����̂��n�߂�ƁA�̂��̂��ƋN���o���Ă����Ă��炭���ׂ����F�Ɏ����X���A���̂Ƃ�����ۂ�ۂ����Ď~�߂�̂ł��B�ڂ������́A�Ō�܂ł��̂�����Ǝ���x��̃��}���`�b�N�ڊo�܂��ƈꏏ�ɂ��Ă����悤�Ǝv���Ă��܂��B
�u�搶�̘r���v�v���Ƃ��@��������̃G�b�Z�C
���F�̕����Ղɍ����x���x�b�g���̃x���g�̎��v���搶�̘r�Ɍ����Ă����B���܂��͎v���o���Ȃ��̂ɁA���v�̈�ۂ͋����c���Ă���B�q�����������͗D�����s�A�m�̐搶����D���������B�u����������l�̏����ɂȂ肽���A��l�ɂȂ����炠���������v���������v�搶�̔����r�Ɍ��鎞�v�͎��̑�l�̏����ւ̓��ꂻ�̂��̂������B�₪�Đ搶�͌����̂��ߎd������߂邱�ƂɂȂ�A���ɂ͐V�����s�A�m�̐搶�������B���͐V�����搶�ɂǂ����Ă��Ȃ��ނ��Ƃ��ł����A���炭���ăs�A�m����߂Ă��܂����B
��l�ɂȂ������͓���Ă������v�Ƃ͈Ⴄ���̂���I��ł����悤�Ɏv���B�ǂ������^�Ȑ搶�Ǝ�������������Ă���悤�Ɏv���邩�炩������Ȃ��B
���݁A���͘V�l�ی��{�݂ʼn��E���Ƃ��ē����Ă���B���܂ւ������Ȃ���A�s�A�m�œ��w���������e�����肵�Ă���B���Ȃ��r�O�ł����ł��������҂̕�����������B����Ȏ��Ԃ������y����ł���B
�ӂƐ搶�̘r���v��������B���͎d�����q��Ă��Z�����āA���K�I�ɂ��]�T�͂Ȃ�����ǁA�����q�����������̎肩�痣��Ă�������A���Ԃ������āA���̐搶�̘r���v�Ɏ����f�U�C���̕���T�������E�E�E�A�ȂǂƎv�����肵�Ă���B
���ꂪ�����ւ̂��J���Ƃ������������Ȃ��B
�u�|�����v�ƉȊw�̐��E�v�����@�~�n������̃G�b�Z�C
���̊|�����v�́A�����Ȋw�̐��E�ɓ����Ă���܂����B
���w�����炢�܂ł́A���̉Ƃ́A�c�ɂɂ悭����^�C�v�̌Â����~�������̂ŁA�|�����v���`�N�^�N�{�[���{���Ƒ������������Ă��܂����B���̎��v�̎�܂��[���}�C�������͎̂��̎d���������̂ł����A2�̃l�W�͍d���ĉ�����Ȃ���Ȃ炸�A������������2��قǂ̎d���������Ƃ͂����A�C�X�ɂ������Ęr��L�����܂܂̎p���͌��\�炢���̂�����܂����B���X�r���~�낵�ċx�݂Ȃ���l�W�����������Ƃ��A����̂��Ƃ̂悤�Ɏv���o�����Ƃ��ł��܂��B
���āA����Ȋ|�����v�ł������A�q������Ă�悤�ɂȂ������A���́A���̎v���o���A���߂ɏ������悤�Ɏ��̉Ȋw�̐��E�ƌ��т��Ă��邱�Ƃ��킩���Ă����̂ł��B
���̊|�����v�́A�ӂ����J����ƓƓ��ȋ@�B�̖��̏L�����������A�[���}�C�̓�������C�ɓ`����Ă����悤�ȁA���������͋����U��������܂����B�����́A�r���v�݂����ȏ����ȋ@�B�ł͊����邱�Ƃ̂ł��Ȃ����̂ł��B���̋@�B�̑��݊��Ƃ������A�����Ƃ������A�������������̂��A�m�������łȂ��Č܊���ʂ��Ēm�邱�Ƃ��ł����̂ł��B
����ɁA�|�����v�́A�㕔���������ɌŒ肳��Ă����̂ŁA�l�W���������тɑS�̂����������X���Ă��܂��܂����B������A���̂��тɌX�����Ă����Ȃ��ƁA�U��q���r���Ŏ~�܂��Ă��܂��̂ł��B���������A���R�̌����݂����Ȃ��̂��A�q���Ȃ���ɑ̂Œm�邱�Ƃ��ł��܂����B
�Î��v�Ƃ����A�̐l�����̂ѐ̂��������ޕ��ł���Ƒ��ꂪ���܂��Ă��܂����A���ɂƂ��ẮA���ꂾ���ł͂Ȃ��āA�Ȋw�I�Ȑ��E�ւƎ����Ă��ꂽ���݂Ȃ̂ł��B���̂悤�Ȍo�����q�ǂ��ɂ������Ă�肽���Ǝv���̂͐e�o�J�̏؋���������܂��A���̎v����S�ɗ��߂Ȃ���q�ǂ��Ɍ��������Ă��������Ǝv���Ă��܂��B
���̈��p���Ă���r���v���ߍ����q�������B�d�r��ւ�������Ȃ̂ɂR���������Ȃ������Ɏ~�܂�B�u�����������ˁv�ƌ����K�b�N���B���̎��v�͑��q�̎v�������߂��Ă��镨���B�u���������ł͍ς܂���Ȃ��v
���q�̑�w�Ō�̓~�x�ݍ��N�͋A�Ȃ��Ȃ��ƌ����Ă����B�A�E�͓��肵�Ă��������Ƙ_�����������ƌ����Ă����̂ɉ��̋A���ė��Ȃ��B�҂��Ă�e�̋C�������l����Ȃ�Ďv���Ă�����w�Z���n�܂��ĊԂ��Ȃ����q���珬������B�y�A�̘r���v�������Ă����B�o�C�g�����Ă����̂ŋA�Ȃł��Ȃ������B�o�C�g�̂������������̂ł�������Ƃ��ꂳ��ɘr���v���܂����B�{���͎d���ɏA���ċ����������Ƃ��������ƍl�����̂����ǎ����ɂƂ��ăo�C�g�Ƃ͌������߂Ă̋����Ȃ̂ł�������Ƃ��ꂳ��ɉ������l���܂����B���Z�ɓ����ăo�X�ʊw���Ă���ǂ����Ă����v���~�����Ȃ�˂����Ď��v���Ė�����B���ꂪ�������Ċ������āA�A�A���߂Ă̋����Řr���v�点�Ă��炢�܂��B�g�ɕt���ė~�����v�|�̎莆�͓����Ă����B�e�̃X�l���Ă��Ȃ��牽���v���[���g���Ƃ͎v�������̂̋}�ɗ܂��o�Ă����B�d�x�̚b���Ő�������f�r���Ă����������A�z�[���X�e�C���ĉċx�݂̓A�����J�ŕ�炷�Ɣ�яo�������w���A�C�w���s�Ō������s�ő�w�������������ƌ����o�������Z���A���]�ԕ��ɓ���S���𑖂����ăn���n����������w�����A���������U���Ă������H�H�̑��q���o�C�g�Ƃ͌��������Ńv���[���g�Ƃ͋���������B���Z�̎������Ė�������v���������������玞�v�ɂ����ƌ������q�̐S�������������B
�����̎��v�͉��Ƃ����Օ���������Ǝ��ւ����̌��C�ȕɕ��A�B�厖�Ɏg���T�ƂȂ����������Z�ɓ������炱�̋L�O�̘r���v�������p�������B
�u���̊|���v�v���J��@���q����̃G�b�Z�C
�Â��Â��b�ł���B
�킽�����c�����̘b������A�������ꂱ�ꎵ�\�N�߂����O�̂��Ƃ��B
�킪�Ƃ̋��Ԃ̒��ɁA�����U�q���v���|�����Ă����B�����吳����̒����ɏ��т��������Ƃ��A�Ó�����甃���Ă������̂��Ƃ�������A����͑����A��������̂��̂ŁA������h�C�c���������悤���B�����Ղ̐����́A�T�E�U�E�V�Ƃ������[�}�������������A�O�ʂ̃K���X�ɂ͉������������Ă����B�Ƒ��̂����A����ЂƂ�Ƃ��Ă��̐}�ĉ����ꂽ��������ǂ߂�҂͂��Ȃ������B
����ď����Ă���̡�
�ƕ��ɐq�˂�ƁA���͑傢���
��h�C�c�łł������v������A���̎��̓h�C�c�ꂾ�B������ǂ߂�
�Ɠ��������̂��B
������̂��ƁA���Ԃő��o�����������ėV��ł����킽�����A�g�ݍ������܂ܐ����]���Ď��v�̊|�����Ă������Ɍ��˂����B���̂͂��݂Ŏ��v�̃K���X�����������B�K���ɂ��āA�킽���ɂ����͂Ȃ��������A�K���X������Ȃ������B
�������́A��j�J����ŃK���X��ڒ������B�Ƃ��낪�A���̏C�����݂̎��v�́A�K���X�̕\�Ɨ������ׂ��ׂɂȂ��Ă����B�������̓ǂ߂Ȃ����ɂ́A���ꂪ����Ȃ������̂��B
���Ԃ��������ߑ����ď\�N�߂��o�����Ƃ��A�O�͂̑�n�k���N�����B����E��풆�̂��Ƃ��B���̑�h��ŕǂɂ͑傫�ȋT����A���v�͗����ĐU��q�͔�сA��̃K���X�͔��o�ɍӂ����B
�������Ď��v�́A�킽�������̑O����p�������Ă��܂����B�������A���̉������������������̎��v�́A�킽���̐S�̒��ɁA�������ƂȂ��Đ��������Ă���B
�u��Ԃ��ꂵ�������o�[�X�f�C�v���[���g�v�������܂ꉫ��炿����̃G�b�Z�C
����{�����炳��ɓ쓌�ɂ���A�{�Ó��̊w�Z�ɓ]�Z���ĂQ�N�̊ԁA�l�t�������̋��Ȏ��́A�Ȃ��Ȃ����̗ǂ��F�l�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
�����ǁA���w�Q�N�̉Ă����肩��A���ł��ǂ��ł��ꏏ�̏��̎q�T�l�O���[�v���ł����B�y�������Ƃ��炢���Ƃ����L�ł��钇�Ԃ��ł������Ƃ��ƂĂ����ꂵ�������B
��������Ƃ��̊w�Z�ɂƂ����߂��C�������B
�������A���w�R�N�ɂȂ�O�Ɏ��͕��̎d���̓s���ŁA����{���̓ߔe�s�ɂ��钆�w�ɓ]�Z���邱�ƂɂȂ����B
�ߔe�̒��w�ɒʂ��悤�ɂȂ��Ă������͂�A���炭�͎��ɒ��̗ǂ��F�l�͂��Ȃ������B
�V���ɂȂ�A���̒a�����̂P�T�ԑO�ɁA�{�Ó��̒��Ԃ������珬��݂��͂����B�J���Ă݂�ƁA���ɂ̓o�[�X�f�[���b�Z�[�W�������ꂽ�J�[�h�Ƃ݂�Ȃ̎ʐ^�A�v���[���g�Ƃ��ĕNJ|�����v�͓����Ă����B
���������������ꂵ�������B�����Ď��̓��A���͓ߔe�̒��w�Œ��̗ǂ��F�l�����邱�Ƃ��ł����B
���ꂩ��P�O�N���o�B
���̕����̈�p�Ɋ|����ꂽ�A���g�Ŕ��n�ɊO�l�̒j�̎q�Ə��̎q���L�X���Ă鎞�v������ƁA�{�Ó��̗F�l�������v���o���B�����Ďv���B
�u�����݂�Ȃł܂�������ȁE�E�E�B�v
�u�Â������v�v�ᖽ�@�O��ꂳ��̃G�b�Z�C
���S���������牜�̔���Ԃ̐^���̒��ɁA�Â������v���|�����Ă��܂����B���̌��͉����ł��̂��Ƃ��ؒ�ł��B�����瑴���ɂ������̂��킩��܂����Ԃ�����Ǝ���ł��܂��B�{���{���{���ƒႢ�������ł��̎����̐��������Ă��܂����B
���������̎��v�͖��ł����B�j�Ɖ��Ƃ��ʁX�̃[���}�C�ɂȂ��Ă��Ă˂������������̂������Ƃ������Ȃ���Ȃ�܂���B��������\�l���Ԋ����Ȃ̂ł��B�����K�������Ȃ��Ǝ~�܂��Ă��܂��܂��B���̂˂������͎q�������̖�ڂł����B�o��l�Ǝ��Ƃŏ��Ԃ����߂Ă̎d���ł����B
���̎��v�����߂Ă��̉Ƃɂ������́A�ق�A�邼�B�邼�B�ƕ��������ߏ��̐l�������W�܂��Ă��ĕ����������ĂĂ����̂������ł����A�������w���̍��ɂ͒����v���������Ȃ��Ȃ�A�l�W�����������O�������A���������Ƃ������̂��������悤�ł��B
�Ƃ̂����߂ĎO�������������炢���̂ɁB�ȂǂƎv�������̂ł��B���オ�i�ނɂ�Ď��v�͏������Ȃ��Ă����܂����B�u���v�A�ڊo�܂����v�����Ęr���v�A��Ƃ̃{���{���H���v������A�������Ȃ��Ă����܂����B�����āA���܂��������܂Ȃ��Ȃ������������A�Î����v�͂����̒�����p�������܂����B�d�r�œ������v���ꏊ�ĒN���s�ւ������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�Ƃ������ƂɂȂ�c���Ă���̂̕�����ӏ��ɏW�߂ĕۑ����邱�Ƃɂ������A���̌Î��v���o�Ă��܂����B�ܘ_�����܂���B���v�̑O�̊W���J����ƐU��q�̌��ɉp���̎����\���Ă���܂��BANSONIA�@BRASS�@AND�@COPPER�@CO�D�Ƃ�����Ђ̕��炵���B�p�����č����͕s���ł��B�Ж��ǂ���^�J�Ɠ��������Ȃ̂����v�̒��͂܂��K�т����Ă͂��Ȃ��悤�ł��B
�u�L�~�̃R�R���E�E�v�v�������D�q����������̃G�b�Z�C
����͍�����P�O�N�O�̘b���E�E�B
��ȋ��R���d�Ȃ��āA���͂P�l�̒j���ƒm�荇�����B
�ł��A���̐l�Ǝ��͊C���z���Ȃ���Έ������͏o���Ȃ������B
���鎞�A���͈ӂ������āA���̐l�Ɉ����ׂ��A��s�Q��ɏ����
�ނɈ����ɍs�����B�K�^���E�E�E�S�g���E�E�P�W���Ԉȏ�̒����B
���͎��v�������Ė��������E�E�����瑋���猩����i�F��A�ԏ��̃A�i�E���X�œy�n�f���邵�����������B
�w�ɒ����E�E�}���ɗ��Ă��ꂽ�ނƏ��߂Ċ�����킹���B�D�����āA���₩�ŁA���߂Ĉ������C�����Ȃ������B
�F�X�ȏ��ɘA��čs���Ă���āA�O�����Â��Ȃ��ė������A���ƂȂ��ނ̘r�Ɍ��镨�������A���͖ڂ��������E�E
�ނ̂��Ă���r���v�̕����Ղ̌��肾�����E�E�B
�L���C�Ɍ��������Ă镶���ՂɎ��͓B�t���ɂȂ�A�W�b�ƌ��Ă����B
�u���̎��v�E�E���E�E�ǂ����E�E�����H�v�ނ͕s�v�c�����Ɏ��̊�����ĕ����ė����B
�u�����E�E���̎��v�E�E�L���C���Ȃ��E�E���Ďv���āE�E���A���v�����ĂȂ����A����Ȏ��v����Ȃ�Ēm��Ȃ���������E�E�v�v�킸������o�Ă��܂����u�{���v�������B
���̌�A�A��܂ł̂P�T�Ԃ͂����Ƃ����ԁE�E�E
�A��O���A�ނ͎��ɂP�̃v���[���g��n���Ă��ꂽ�B
����́A�ނƂ������̎��v�������B�u���̂��ł���ɂȂ��ĉ������A���A�K���}���ɍs������A�����Ȃ��Đh�����A�₵�����A�������ɋ���Ǝv���āA�����g�ɕt���Ă��ė~�����B�v���͋����Ȃ���A�ނ̘r�Ɏ����̘r���d�˂��E�E�E�������A�����������Ď��͔ނƗ��ꂽ�E�E�B
�A���Ă���A�h��������R���������ǁA���̘r�Ɍ��鎞�v������A���ꂻ���ȋC�����āA���ƂȂ��撣�ꂽ�B
�u�K���}���ɍs���v�ƒf�����Ă���R������A�ʂ�{���ɔނ͎��̏Z�ޒn�ɂ���ė����B�������v�Ɠ����ŁA�߂鎖�͖��������E�E
���̂܂܁u�v�w�̐l�����ԁv�Ƃ��č������ݑ����Ă���̂������E�E�B
�u�P�O���P���R�S�b�̔閧�v�Έ� �m����̃G�b�Z�C
���w���̎��̂��ƁB�l�ׂ̗̐Ȃɍ��邻�̏��q�́A�ƂĂ��s�v�c�Ȏq�������B�]�Z���Ă����q�ŁA���܂�F�B�����Ȃ��B�����l���Ă���̂��킩��Ȃ��Ƃ��낪���������炩������Ȃ��B���ƒ��͂������̊O���茩�Ă����B
�l�͂������ȏ���Y��āA�ޏ��Ɍ����Ă�����Ă����B������̎��ƒ��A��l�ŋ��ȏ����̂����Ă���ƁA�ޏ������ȏ��Ɂu�������Ƃ������Ă����悤���v�Ɨ����������B�������ƂȂ狳���Ăق����B�l���u�ȂɁH�v�Ə������B�ޏ��͐搶�ɕ������ʂ悤�A������
�u�������ቮ�̃J���o���A�P�O���P���R�S�b�ɉ�肾����v
�Ƃ����₢���B
�l��̐Ȃ͑��ۂŁA�����炨�����ቮ�̃J���o����������B���̃J���o���́A�c�Ǝ��Ԓ��A�����d�C�̗͂ŃN���N������Ă���̂��B�����A����ȉ�肾�����ԂȂ�āA�킩��킯���Ȃ��B
�u�ق�ƁH�v
�l�͋^�����B�����̑O���ɂ���A�傫�Ȋۂ����v�̕b�j���l�Ō��߂��B�P�O���P���R�O�b�A���ƂR�b�A�Q�C�P�E�E
�u���[�A�ق�Ƃ��I�v
�l�͋��B�N���X�̊F���������U��������B�搶�ɂ͖l����������ꂽ�B�ł��ޏ��̌����ʂ�ɃJ���o������]���n�߂��B�@�ޏ��͂����A���Ƃ������I���Ȃ����ȁA�Ǝ��v��̊O���Ȃ��߂Ă������߁A�J���o������肾�����m�Ȏ����ɋC�Â����̂��������B�l�́A���q�̂����ɂ��������z���A�Ǝv�����B
���̓�������ƒ��͂����A��l�Ŏ��v�����߂��B�`���C�����Ȃ�܂ł��Ɓ��b�Ɛ�������A�P�P���P�P���Ȃǂ̓��ɁA�P�P���P�P���P�P�b�ɂȂ�̂��l�ŃJ�E���g�_�E�������肵���B������Ȃ����Ƃ����A�ޏ��Ƙb���̂͂ƂĂ��y���������B����Ƃ��ޏ���
�u�Ȃ��b�j���đ����ˁv
�ƌ������B���������������ƒ��́A���v���i�ނ̂��x���Ǝv���Ă����̂ɁA�C�����ƕb�j�͂ƂĂ������āA���Ƃ͂����Ƃ����܂ɏI����Ă��܂����B
�u�e���̖ڊo�܂����v�v���q�@��l����̃G�b�Z�C
���@���̐e������������������̂́A�ߌ�R���������B
�������Ƒ��S���߂��݂ɕ�܂�͂������A�������ڂ��ɂ́A�����a�C�ŋꂵ�ސe���̎p�����Ȃ��Ă��ςނ̂��ƈ��g���镔�����������B
�i�[�X�X�e�[�V�����ŏ��葱�����ς܂��A�a���̌�Еt�������Ă���Ƃ��A���ۋ߂��ɒu���Ă������ڊo�܂����v���A�ӂƂ������q�ɂ��ӂ��낪�X�K�̑�����O�ɗ��Ƃ��Ă��܂����B�Q�Ăđ��������o���ĉ�������ƁA�������܂ŕa���ɂ������ڊo�܂����v���A�P�K�s���e�B�̉����̏�ɎU�����Ă����B
���̖ڊo�܂����v�́A���Đe�������S�E�������Ă������ɁA���̋��Ȃ��ӂ���̂��߂ɔ����Ă������̂������B�����A���Ȃ�̔N����̂ŁA���ɂQ�O���͒x���㕨�������B
����ł����ӂ���́A�����������Ă������v������ƁA�����Ƒ�Ɏg�������Ă����̂������B
���ꂾ���ɁA���̑厖�Ȗڊo�܂����v�𑋂��痎�Ƃ��Ă��܂����V���b�N�͑傫�������炵���A����܂Őe���̎���Y��悤�Ƃ��邩�̂悤�ɂƂ߂Ė��邭�U�����Ă������ӂ�����A�������Ɍ���������܂܁A�����ƃs���e�B�̉����̏�������낵�Ă����B
�ڂ��͂��ӂ���̌��Ɏ���悹�Ȃ���A�ꏏ�ɉ��������낵���B�������ɂ��ӂ���ɂƂ��āA����͑厖�Ȏ��v�������ɈႢ�Ȃ����ǁA�������A�u��������A�������N�����Ȃ��Ă��������v�Ɛe�����ǂ����Ō����Ă���悤�ɁA�ڂ��ɂ͎v�����B
����́@�m�����w�Z�R�N�����S�N���̒a�����������Ǝv���B�F�B�����킢���T�����I���A�f�C�Y�j�[�Ȃǂ̘r���v�������Ă��ā@���ɂق����ė~�����ă~�b�L�[�̎��v�����˂��肵���B���Ƃ��Ə��X�Ђ������m�̎��ɍ������������e�͘r���v���Ă����Ɩ��Ă��ꂽ�B
���悢��a�����̖邪����Ă����B���N���N����C������}����ꂸ�A�v���[���g���J����O����������ɂ�Ŏd���������B�u���v���ꂵ���Ȃ��v�����t���e�ށB�p���p���ƕ����������Ɠ����̔��̂Ȃ��ɘr���v���E�E�E�B����ȂƂ��̃Z���n���e�[�v�قǂ킸��킵����������͖̂��������B�����`�I�����J�������̂ɃJ�c�J�c�ƒ܂𗧂ĂȂ��ƂƂ�Ȃ��̂��B����ł��~�b�L�[�̎��v��r�ɂ��邽�߂ɂ͓w�͂�ɂ��܂Ȃ������B�����āA����ƊW���������B�ƁA�����ɂ́A���̗~���������~�b�L�[�̎��v�ł͂Ȃ��A�Ɏ��̂܂������̃~�b�L�[���������B�v�킸�u�~�b�L�[����Ȃ��I�v�Ɨ��e�ɂ����Ă��������B
���������A�e���育�킩�����B�u����A�~�b�L�[���Ǝv�������ǁv�u��������Ȃ����v����Ƃڂ��Ă���̂��A�{���ɂ킩���ĂȂ��̂��s�M�������͕���Ă������A�����Ƃ��Ď��̘r���v�͋Ɏ��~�b�L�[�������B���炭�͒�����C�ɂ��Ȃ�Ȃ��������A���ǕK�v�ɔ����Ē�����悤�ɂȂ�A���ꂪ�����̈ӎv�ɔ����ď�v�Œ����������B���ꂱ��o���h�����Ȃ肢����Ă��܂��قǐg�ɒ����Ă����B�Ɏ��~�b�L�[���Ȃ��Ȃ��̂Ă����̂���Ȃ��ƌォ��C�Â����̂ł������B
�u���������ގ��v�v�{�{�@����q����̃G�b�Z�C
�������߂Ęr���v������悤�ɂȂ����̂́A���N�̎l�����炾�B���܂Řr���v���������Ƃ̂Ȃ��������ɁA��w�i�w�����������ɁA�����ƕK�v�ɂȂ邩��Ƃ������R�ŕꂪ�v���[���g���Ă��ꂽ�̂��B���ʂȕ��ł��Ȃ��A�V���v���Ȓ��F�̘r���v�B���͐e�������߂ė��ꂽ�s����₵������A�������̘r���v�߂Ă͕���v���o���Ă����B���܂Řr���v���������Ƃ̂Ȃ������������A�������̎��v������ɂ͂߁A���ӎ��̂����ɁA���̎��v���̂�������ł����B����Ȏ����t�A�ĂƋG�߂��ς�邽�тɁA�����ɂ�����A�����̗F�l���o���A����Ɏ₵���������Ȃ��Ȃ����B�������A�ǂꂾ���F�l���o���Ă��A�������ƈꏏ�ɂ��āA�₵���Ƃ����y�����Ƃ����A���ɕ����������Ă����̂́A���̒��F�̘r���v�����B�܂��܂��ꏏ�ɐ������n�߂�悤�ɂȂ��Ĉ�N���o���Ă��Ȃ����A�v���o�����Ȃ�����ǁA���ꂩ�����낵���ˁB���ꂩ������Ƃ����ƈꏏ����B�����Ė����Ɍ������Ď�������ŁA��R�̎v���o������Ă������ˁB
�u����łv�ؑ��@�����q����̃G�b�Z�C (12���̃x�X�g�G�b�Z�C)
�����̎��Ɓi�V�����싛���s�j�́A�����v�Ƃ�����c�B������̓s���Ȃǂ����܂��Ȃ��ɁA��悤����Ȃ��A�����łB�e���r�����Ă��悤���A�������˂��Ă��悤���A��͂��߂���Ō�̈�ł��܂ŁA�������炵������B���Ă��˂��ɂ��u���v�܂ŕ�A�O�̓���悤�B�Ƃɂ����A�₩�܂����̂��B
�́A�������ɂ������Ă����[���}�C���ɔ�ׁA�w���܂̂�͉��ĕi���Ȃ��낤�x�ƁA��X���Ƃ܂����v���Ă����B���܂肩�˂āA���S�Ɏ~�߂Ă��܂������Ƃ�������B
�\���̂��̓��܂ŁA�����v���Ă����B���Ƃ̃R�^�c�ł���������ł������̗[�ׁA�u���\�L�v�̎��Ԃ��~���Ă킢���B�V�������z�n�k�[�[
�k�x�U�̏Ռ����˂��グ�ė����Ƃ���A�S�悪��d�B�ł�����������悤�ɂ��ĊO�֑ޔ����Ă݂͂����̂́A��k����x�A�O�x�Ƃ���Ă��āA�����܂�C�z�͂܂������Ȃ������B
���̌����Ⴆ���A������[�������B�邪�ӂ���ɂ�A���������݂āA���܂炸�����ɖ߂����B�Z���ł̒��A���܂���n�������邩�Ɛg���܂��A�s���ɓh�肱�߂�ꂽ�邾�����B
���ɂȂ����疾����̂��낤�H�@����قǁA�閾�����҂��ǂ������������Ƃ͂Ȃ������B���������A�����ɒ����ނ�������̂��낤���H�\�\�ۏ͂ǂ��ɂ��Ȃ��B
����Ȓ��ł��A�����v�́A�ς�炸�����ł����B��A��c�B�����ɐ����܂��Ă䂭���̊m�����ɁA�Ȃ��߂�ꂽ�B�w�������͖����A���Ȃ炸���͗���̂��x�ƁB
�₪�āA����݁A�������P���������B���̒��ɕ������u�����̎���v�́A����₩�ŁA�������j�����邩�̂悤�������B
�u�Z�C�R�[�O�j�v�i�@�N�ꂳ��̃G�b�Z�C
���a30�N��̏��߁A�r���v�Ȃǂ͍����ŁA�c�ɂ̒��w���̎������ł͂Ȃ������B���̑c���͏����Ȏ��v��������J���Ă����B���X�ɗV�тɍs���ƁA�c���͂����d����Ɍ������āA�����v��������A�r���v�̏C���Ȃǂ����Ă������̂��B�X�̃V���[�E�C���h�[�ɂ́A���܂��܂ȃf�U�C���̎��v�����ׂ��Ă���A�������������w���ɂƂ��Ă͘r���v���C�ɂȂ��Ďd�����Ȃ������B
���ł��A�Z�C�R�[�̎O�j�Ƃ����j���[�t�F�C�X�𒍖ڂ��Ă����B���̍��̎��v�́A�����Ղ̒��ɂ����ЂƂ����ȕ����Ղ������āA�����ŕb�j����������Ă���Ƃ������̂������B����͏������ēǂ݂Â炢�B�O�j�Ƃ����͍̂��ł���������O�̋@�\�����A����͘r���v�v���������ɈႢ�Ȃ��B
���v�ɂ�������Ă͂������A�����䂪�Ƃ͌o�ϓI�ɋꂵ���A�ȒP�ɔ����Ă��炦��悤�ȏł͂Ȃ��������A�c�����܂��A���w���ɋC�y�Ɏ���������̂ł͂Ȃ��Ǝv���Ă����悤���B
���w�𑲋Ƃ��āA�����m��������ɒ��t����ɍs�����Ƃ����܂����Ƃ��A�c������̃v���[���g���u�Z�C�R�[�̎O�j�v�������B�u�l�W�͂�������A�����������ԂɎ~�܂�܂Ŋ������ŁB�v�Ƌ����Ă��ꂽ�̂��A�����͂�����o���Ă���B��яオ��قǂ��ꂵ�������B���̈�ԍ����ȕɂȂ����B
�A�E���Ĕ��N���炢�o�������A�E��̒��Ԃƃn�C�L���O�ɍs�����ƂɂȂ�A���R�����̎��v�͍���ɋP���Ă���B��������Ƃ��������Ȃ��A�[���݂̒J��֗��Ƃ��Ă��܂����̂��B
���炭�̊ԁA�c���ɂ����ɂ��������A���N����ɓ����������ł悭�����f�U�C���̎��v�����B
�u�T�C���̂Ȃ����蕨�v�~�R�@�Ⴓ��̃G�b�Z�C
�ڊo�܂��������B
���[��A�N���邩���B
�z�c�̒��ŐL�т����āA���v�̐j���`�F�b�N�B��������A�V����������n�܂�B
�����Ղ��͂����肵�Ă��āA�������Ŗ����N�����Ă����ڊo�܂����v�B�T�����[�}���̍ȂɂȂ������ɁA���ٓ����̎��Ԃ������Ă���闊���������_���B
���̎��v���V���Ō��������̂́A�����p�[�e�B�̗����B
�u����̓��c����́v
�u���A����͎��̓�������v
�v�Ƃӂ���ŁA�p�[�e�B�ł�������v���[���g���J���Ă��������A�܂������o���̂Ȃ���݂��ЂƂ������B
�u�Ƃ肠�����A�J���Ă݂�����v
�����ɂ҂�����̒��悢�傫���A��F�̃V���v���ȃf�U�C���B�����̎��������@�\�������A���p�I�Ȗڊo�܂����v���o�Ă����B
���������N���H
�����玟�ւƏj���q������Ă��������B�Ȃ�ׂ���l���ꂸ�ɉ����Ă������肾���A���̃v���[���g�����́A���A�N���������̂��A�o���܂������o���Ă��Ȃ��B�����̓V���C�Ȑ��i�̐l�������̂��A�J�[�h���A���O����������Ȃ������B
�ӂ���Ŏ������ނ悤�ɁA�Ƒ����Ă��ꂽ�����҂́A�������Ĕ��N���o�������܂��킩��Ȃ��B�킩��Ȃ����Ƃłނ���A�����j���Ă��ꂽ�F�l�����S�����A�ӂ���̎���������Ă���Ă���悤�ȋC������B���S��Y�ꂸ�ɁA���̂����v�w�ł��悤�B���v�����邽�сA�����v���B���ꂪ�����ɂƂ��āA�ǂ�Ȃ���������������Ƃ��Ǝv������B
�u�r���v�����������v�q�}�}����̃G�b�Z�C
�u�����͒����������ł���H�ǂ��r���v������������Ȃ��v�ƕ�B�]�v�Ȃ����b���B
����̉āA���ɔ����Ă�������r���v�B�X�e�����X���A���p�`�̕����ՁB�u���w���̂ɂ��Ă͑�l���ۂ��v�ƁA�����A����ꂽ�B
�ȗ��A�����ł�����A�����̎��ȊO�A�Q�鎞���͂����Ȃ��B�K���X�͏����炯�B���ߋ������x���������B���w�A���Z�A��w�A�Љ�l�ƁA�����Ƃ����{�B�����̂̈ꕔ���B���Ă��Ȃ��ƁA���r���y���Ĉ�a��������B�ꐶ���̈�{�ł����Ǝv���Ă����̂ɁB
�u�Ⴄ��v
���̘b���ĔN��̗F�l�������Ȃ߂��B��������Ɍ�������B�D������ɂ������g���Ȃ��Ȃ邩������Ȃ��B���̑O�Ɏ����̂��߂Ɏg���Ȃ����B�����������������̂��A�ƁB
�u�m���ɂ���n���Ȏ��v����B�w���݂����v
���w�̎����炾�ƌ����ƁA�ޏ��͏������ꂽ������āA���Ⴀ�Ȃ������A�ƌ������B
�n���Ȃ̂��A����H���o�������A�킩��Ȃ��B�����A���ꂩ��f�p�[�g�Ȃǂ̘r���v����ɋ������킭�悤�ɂȂ����B
�O�\�̒a�����A�v�����Ęr���v�����B�S�[���h�ƃX�e�����X�̃R���r�B�����̓f�U�C������l���ۂ��B���߂ĕt���ւ��Ă݂����A����̔N�y�̒j�����ɂ����肵���B
�u���̕����A���̕��ɍ�����v
����ׂ��Ƃ��A���߂č��܂ł��Ă������v���Ђǂ��n���ŕ����Ղ��������Ȃ��v�����B���܂ł͂ǂ��炪���������Ƃ�����r�̑ΏۊO�������B�̂̈ꕔ�Ǝv���Ă�������B
���ꂩ�琔�N�B���Ȃ�A�Ⴆ�ΗF�l�̌������̐Ȃɒ��w����̘r���v���ǂ�ȂɃ~�X�}�b�`���������킩��B���������Ɏ����������Ă��炸�A��Ȃ����������B�����ėǂ����v���Ɗ��߂���̋C�������B
����ŌÂ����v�����邽�сA�����̎v�����ꂪ�C�p���������A�����Ɉ��������B�n���ŏ����炯�̂��̎��v�́A���w����O�\�܂ł́A�������ɖ��ڒ��Ŋ�ȂȎ����g������B
�u���v�͗F�B�v���Ł@��������̃G�b�Z�C
�ڊo�܂����v�͂킽���̕K���i���B�Ȃ���������ɍ���B�ጌ���̂킽���͖ڊo�܂����v���Ȃ���A�N���邱�Ƃ��s�\�Ȃ��炢�A������̋��Ȃ̂��B���R�ɖڂ��o�߂邱�ƂȂ�Ăł��₵�Ȃ��B���̂����܂������ɂ���āA����Ɩڂ��o�߂�̂��B����ł����܂ł̓{�[�b�Ƃ��Ă���B
�w������́A��́u�����悧�v�Ƃ������ŋN���Ă�������ǁA�Љ�l�ɂȂ��ăo�X�K�C�h�Ƃ����E�ƂɏA���Ă���́A�ڊo�܂����v�͗F�B�̂悤�Ɉꏏ�ɂ����B
�Ȃɂ���N�����Ԃ��O�����Ƃ����Ƃ����������B�ڊo�܂����p�ӂ��A���ԍ��ŃZ�b�g���A�Q�V���Ȃ��悤�ɍH�v�������̂��B��ڂ͉Е�m��ɋ߂����ŐS�����т����肷��悤�Ȗڊo�܂����v�ŁA��ڂ͔�r�I�Â��ȉ��B�킽���̗F�B�́A�킽���̂��߂Ɉꐶ���������Ă��ꂽ�B�ƂĂ����������B
���ɁA���ɐ\����Ȃ��̂����A���Z���Ƃ܂ł͂��Ă����r���v�́A�Љ�l�ɂȂ��Ă���A��������a���ɂȂ��Ă��܂����B
�Љ�l�ɂȂ肽�Ă̍��A�킽���ɂ͂��C�ɓ���̘r���v���������B�u���X�l�b�g�݂����Șr���v�ŁA���܂Ŕ��������v�̂Ȃ��ŁA��Ԓl�i�����������B�������A��T�Ԃ����Ȃ������ɁA�Ȃ����Ă��܂����̂ł���B����ŃV���b�N���痧�����ꂸ�ɁA���ꂩ��r���v�����Ƃ��Ȃ��Ȃ�A���������@��������A���݂Ɏ����Ă���̂��B
���ꂩ�璷�d�b�����Ă͂����Ȃ�����Ƃ����āA�d�b���ɍ����v�e����u���ꂽ���Ƃ��v���o�����B�����v���Ȃ��Ȃ�܂��Ɏ�b���u���Ƃ������Ƃ��B���͌g�ѓd�b�����y���Ă��邪�A�킽���̍��Z����ɂ́A�Ƒ����W�܂��Ă��镔���ɁA�d�b�������Ă������B����Œ��d�b��������̂�����A�����̂悤�ɕ��ɓ{���Ă��������B
���v�͎��Ԃ����ނ��ǁA�v���o���l�܂��Ă���̂��ȁB�Ȃ��߂Ď��v���Ă������ȂƊ��S���Ă��܂����B
�u�������v�̎v���o�v�ז�@�݂��q����̃G�b�Z�C
���Z��N�̎��A�u�ÓT�v�̎��Ƃ������Ă������������ѐ搶�́A���Ƃ��I���ɋߕt���ƁA�Y�{���̃x���g�Ɋ|���Ă���������v�����o���āA�����Ƃ����ɂȂ����B�����ŁA�ۊ�ŁA��������C���̐搶�̂����̂����肪�����Ă��܂����B�傫�ȕ����Ղ��A��ԑO�̐Ȃ̎��ɂ��������B���Ɖ��������m�F����ƁA�܂��u����L�v�̑������n�܂�̂ł���B���̗D��ɂ����v���铮�����A�����ɂ��u�ÓT�v�̐��E�ł������B���ɂƂ��ď��߂Č���������v�ł������B
���ѐ搶�̎��Ƃɂ́A��ꎟ���E���Œ����֓n�����b�A�u�ѐH�������v�̒����̒��̈��A�A���W��ԂŒ����嗤���ړ������b�Ȃǂ̎G�k�͍��ł��͂�����Ɗo���Ă���B�푈�̘b���w�Z�̎��ƂŘb�����搶�͑��������悤�Ɏv���B���e����������Ĉ��������ł��邪�A���ۂɊO�n�֍s���ꂽ�l�̘b�ɂ͂��͂�����̂ł���B
���|���ɏ������Ă������́A�ږ�ł�����搶�ɖ{���ɂ����b�ɂȂ�A�\��ɂȂ������ł��A���X�A�v���o���Ă͊��ӂ��Ă���B�搶�́A�o��̌��Ђ̎�Ɏ҂ł�����A���y�j�̌����҂ł��������B���Z�O�N���̎��ɂ́A�u���{�j�v�������Ă����������B
�e�����s�ɂ���u�F����Ձv�͐搶�ƈꏏ�ɁA���������k�����@�̂���`���������Ė�����B�u���{�j�v�Ƃ�������������E�̊y�����A�u�ÓT�v�Ƃ����D��Ȍ��t�̖ʔ����A���w�̎��y�����������Ă����������B
�搶����ʎ��̂ŖS���Ȃ��Ă����\�N�ȏ�o���Ă��܂������A���������Ă������A�搶�̎v���o�́A�������v�Ƌ��ɖY��Ȃ��ł��邾�낤�B���̒��̓f�W�^���h�̕����A�����Ȃ��ė��Ă��邪�A���̓A�i���O�h�̂܂ܐ����Ă䂭���낤�Ǝv���B
�u�����r���v�v�A��@���l����̃G�b�Z�C
��w��N�������N���ɂȂ�t�x�݂ɁA�]�c�����S���Ȃ�܂����B��\�Z�ł����B���C�ȂƂ��̑]�c���́A�Ԃ̉^�]����D���ŁA�悭������i�ɘA��čs���Ă���܂����B
���́A��w�ɓ�������A�����ɎԂ̖Ƌ�����낤�Ǝv���Ă��܂����B�������A�Z�����������āA���ǖƋ���������̂͑�w�l�N�̂Ƃ��ł����B
���ɂȂ��Ďv���܂��B
��w���w��A�����ɖƋ����Ƃ��āA�]�c�����h���C�u�ɘA��čs���Ă�����悩�����Ȃ����āB
�]�c���̌`���̂Ȃ�����A���́A�P�X�V�O�N���SEIKO�̎��v�����炢�܂����B
�����Ԃ��^�]����Ƃ��A���͕K���]�c���̌`���̎��v��g�ɒ����Ă��܂��B
����́A�]�c����������������Ă��Ă����悤�ȋC�����邩��ł��B���U�A�����́E���ᔽ�������]�c���ł��̂ŁA���̎��v�𒅂��Ă��邾���ŁA�ƂĂ��S�����v�����Ƃ�����܂��B
�܂��ɁA���S�^�]�̂����ł��B
���̎��v�͍������������Ă��܂��B�J�`�b�A�J�`�b�Ƃ����������މ����]�c���́u�����ȉ^�]������Ȃ�I�v�Ƃ������ɂ��������܂��B
�]�c���͖S���Ȃ�܂������A���v�̉��Ɍ`��ς��A�������������Ă���悤�ȋC�����܂��B
�Ђ������������A���ꂩ���������Ă��������B
�u�R�����̊|�����v�v���@���䂳��̃G�b�Z�C
��̉Ƃ̒��Ɋ���v�����邩�A�킩��܂���B�F�X�ȋ@�B�ɂ����f�W�^�����v�܂œ��ꂽ��A������Ȃ��ʂ�����̂ł��B
�����牽�\�N���O�̓��{�ł́A���v�͑�ϑ�Ȃ��̂ŁA�ꌬ�̉ƂɈ����A�r���v�Ȃ�Ă������厖�ɂЂƂ����Ă���ʂ̂��̂ł����B����ł��A�F���A���̎��v�ɍ��킹�āA����𑗂��Ă������̂ł����B
�����̍����炩�A���̊|�����v�̂˂����������Ƃ��A���̎d���ɂȂ��Ă��܂����B�˂��������ƌ�����Ƃ́A���ł͂Ȃ��Ȃ�܂����B�d�C��d�r��A���z�̌��Ŏ��v�������悤�ɂȂ�������ł��B
����Ɉ��́A���ݑ�ɏ���āA�w�L�т��Ȃ���˂������������̂ł��B���Ƃ��A���l�O�ł��d���������̂͊����������̂ł��B
���̌�ǂ�ǂ�ƐV�����@�B���o�����̂ɁA���̊|�����v�����́A�c���Ă��܂����B�ꂪ�S���Ȃ��������A�����ꏊ�ŁA�����l�ɁA��������A�{���{���Ɩ��Ă������̂ł��B
�Ƃ������Ƃ��ɁA�����ė��܂������A�|���鏊������܂���B�₪�āA�R�̉Ƃ����܂����B���{�̘̐b�ɏo�Ă���悤�ȉƂł��B���킸�Ɋ|�����v�͎R�Ɏ����Ă����܂����B���ɂ����Ă˂��������Ă��ƁA���������Ɏ������ݎn�߂��̂ł��B
�d�������Ċ������̂́A�l�Ԃ��@�B���ꏏ���Ǝv���܂����B���̌���A�R�֍s���x�ɂ˂��������Ă��܂��B
�������Ƃ��āA�Â��Ȏ����R�ʼn߂������Ƃ������Ȃ�܂����B����ȐÂ��Ȏ��ɁA���̌Â��|�����v���Ă���ƁA�̂����������v���o���܂��B�����̎��v�̒��ŁA���ɂ́A��Ԗڂɑ�Ȏ��v�ł��B��Ԗڂɂ́A�d���̎v���o������܂��B
����ȏ�ɉ��������A�q���̍��̎v���o�ƂȂ鎞�v�������Ă��āA�{���ɗǂ������Ƃ������Ă���̂ł��B
�u���j���̘r���v�v���싞�q����̃G�b�Z�C
���j���̒��r���v������B�X���T�T���B�w���p�[�Ƃ��Ă�1�T�Ԃ̎n�܂肾�B
�ق�������Ԃ����T���_�����ۂ�ƒu����Ă��錺�ցB����͂悤�������܁[���������x���ɐ���������ƁA�V�X�˂̃n�i���������������Ί�ŘL��������ė���B
�n�i����͑�D���Ȏ��㌀�����Ȃ��炨����H�ׂ�B��卪�̎ϕ����������ł����˂��v����X�`�͂�����ω߂�����v�Ƃ����̊��z�������Ă������Ǝv���ƁA��܂����������㊯���v�u���킢�����ɂ˂��v�ƓˑR���㌀�̘b�ɂȂ�B���㌀���I���ƁA�q���̍��̘b��^�]�Ƌ�����������̘b�������������ɍK�������Ɍւ炵�����ɘb���B
�����b�����x���J��Ԃ��n�i����Ɏ��͓c�ɂ̕�̎p���d�˂Ă��܂��B������r���v�������Ȃ��B�Ƃ����̂������r���v�ɖڂ�������ƂƂ���Ƀn�i����͔߂�����ɂȂ邩�炾�B�܂���l����̎��Ԃ�����Ǝv���̂��낤�B�Ƃ͂����P�P���S�T���ɂ͌�Еt�����n�߂Ȃ��Ǝ��̎d���ɒx��Ă��܂��B�n�i����̊|�����v�͉���������A���̓n�i��������ƌ��������������ɁA�f���������̘r���v�ɖڂ����B
�Ă̂��钩�A�����̂悤�Ƀn�i�����̌��֑O�Ŏ��Ԃ��m���߂悤�Ƃ����B����Ǝ��Ԃ����������B�r���v���~�܂��Ă����̂��B���̏�͌g�ѓd�b�ł��̂������A�g�ѓd�b�ł̓n�i�����߂��܂��Ȃ��ł����Ǝ��Ԃ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�s�ւȂ̂ł��̓��̂����ɐV�����r���v�����B���d���������Ȃ�Ƃ��X�̐l�Ɋ��߂��āA���S�h���ŕ����Ղ����₷�����v��I�B�Ƃ��낪���ꂩ��P�����������Ȃ������Ɏ��͉Ƒ��̉������邱�ƂɂȂ�A�w���p�[�̎d������߂��B
���j���̘r���v�́A�n�i����̏Ί�Ǝ����A�鎞�̂�����Ƃ��˂��悤�ȉ�����v���o������B�n�i����A���������C�Ŏ��㌀�����Ȃ���y����������H�ׂĂ���Ƃ����ȂƎv���B
����̈�ő���ꂽ���v�B
�����̓[���}�C�d�|�ŋ������ŏ��ŁA�h���t������������i�ł������B
�������������厖�Ɏg�����B���A���������B
�b�����āA�Ȃ��S�������v�������Ă��ꂽ�B
������̋ꂵ���ƌv����P�o����̂͑�ς������낤�B
������A���������������B
�u���������v�v���Y�@�R������̃G�b�Z�C
�P�Q�̒a�����������������̔ӁA���̋A���҂���тĂ����B
�u�R���A�a�����̃v���[���g�A���������H�v
���������q�˂����A������Ƃǂ��ǂ����Ȃ���A
�u�r���v�v�Ǝ��͓������B
���a�T�O�N�A���w�Z�ւ̓��w���T�����P�Q���A�F�B�̊Ԃł��A�e����̒a�����̃v���[���g�́A���v�����N�M�Ƒ��ꂪ���܂��Ă����B
���w�Z�Ƃ́A���B�ɂƂ��ẮA�܂������ʂ̐��E�A���������ɂ́A��l�̐��E���_�Ԍ������B
�r���v�Ɩ��N�M�͑�l�̂��邵�B�������x�����v���̍L�����J���ẮA�����̃x���g�������P���~���Q���~������Z�C�R�[�̘r���v�̎ʐ^���A�Ђ����ɐ蔲���Ă݂��肵���B
���̔ӁA���������Ă��Ă��ꂽ���v�́A��������Ă��������̃x���g�̂������ł͂Ȃ���������ǁA�ۂ����F�̕����ՂɁA�����x���g�̂����A�Ȃ��Ȃ��V�b�N�Ȃ��̂������B���F�͗��������Ă��āA��l�炵�������B
���́A�厖�Ɉ����o���̒��ɂ��܂��A���ɉ��x�����o���ẮA���v���͂߁A�l�W���������B
�s�A�m�̃��b�X���ɍs�����A�������ɍs�����A���悻�A�O�o���鎞�́A��������ɂ��̎��v���͂߂��B�r�������グ�āA���Ԃ�����d�����l�炵���ĂƂĂ��C�ɓ����Ă����B
�������Ă��܂ŁA���̎��v���͂߂Ă������낤�B
���Z�ɓ��w�������A�V�������v���Ă�������B
���̎��F�̎��v�A�Ȃ������ɂ͌���Ȃ������悤�ȋC�����邪�A���́A�P���ɂT���i�ނƂ������_���������B
�u���̎��v�v�ؑ��@�^������̃G�b�Z�C
�������w���̂Ƃ��A�����A�����J�ɗ��s���ăI���K�̎��v���Ă��Ă��ꂽ�B����͒��w��������ɂ͂��������Ȃ����̂������̂ŁA�厖�ɂ��܂��Ă������B
�ܔN��ɑ�w�ɓ������Ƃ��A��������o���Ă����B�o���h�̕��������^���ł���v�ł��Ȃ��A�����z���̕R�ɂȂ��Ă���A���܂茩�����Ȃ����̂Ȃ̂ŁA�����̎��v�������B
�������A���̎��v�Ƃ̕ʂ�͂�����ˑR����Ă����B���C�����z�e���̐��ʏ��ŁA���Ƃ��Ɏ��v���͂������̂������Ȃ������B�����ɋC�����Ď��ɍs���������v�͂Ȃ������B
�e�Ȑl���t�����g�ɓ͂��Ă��ꂽ�̂��Ǝv���A�t�����g�ɍs���Č������͂��Ă͂��Ȃ������B
������߂��ꂸ�ɁA��������������A�����Ăق����ƌ����ēd�b�ԍ���`���Ēu�������A�d�b�͂������Ă��Ȃ������B
�ܔN�Ԃ��厖�ɂ��܂��Ă����āA����Ǝ��o���Ă����̂ɂ���܂肾�Ǝv�����B
�������l�Ɍ��������B����͎����\�O�̂Ƃ����炻�������̂��y���݂Ɏ���Ă��������v�Ȃ�ł��B���傻����̎��v�Ƃ͈Ⴄ��ł��B�����ɐ���������Ȃ��悤�ɂƎv���Ă͂������̂��w�ɂȂ�Ȃ�ĐM�����܂���B
���������Ă��ꂽ���v�͌��̎��v�ƂȂ��Ă��܂����B���ɂ͉����Ȃ������̂��낤���B
�u���߂Ă̎��v�v�g���@���q����̃G�b�Z�C
�������߂Ď����ׂ̈ɍw�������E�H�b�`�͋M�Ђ�Presage�ł���B
���БO�̈ꌎ�Ɏ��v�X�ɍs���A���������鎞�v�̒��ŗB�ꎄ�̖ڂ��B�t���ɂȂ�
���̂�Presage�ł������B���̎��̈�ۂ͍��ł��N���Ɋo���Ă���B
Gold Chane��Pink Face�A�Z�j�ɃX�J�C�u���[�̐��ʂ�����A�˂����������ɂ�
�������ʂ����Ă���B
���L���鎞�v�͂��������邪�APresage�قLj�ڂŋC�ɓ��������̂͂Ȃ��B��
��قǂ܂łɑf�G�ʼn��炵�������̂ł���B
Presage���w�����đ������̂�15�N���߂����B���͎Љ�l���o�Č����A�o�Y���A
�̕�ƂȂ����B���̎��v�ƈقȂ�A���̎��v�͎��ɂƂ��ďd�v�ȈӖ������B
����x�ɍw�������Ƃ��̂킭�킭�����C������Љ�l�ƂȂ��]�A�ْ������v��
���������̂ł���B
Pink Face�����ޕb�j�͎��̗��j�����ނ悤�Ɋ����A�X�J�C�u���[�̐��ʂ͊�
����߂��݂̗܂ɂ��v����B
���͍�������̎��v�̕b�j�̂悤�Ɉ�����l�������ōs���̂ł��낤�B����
���߂Ȃ��珉�S�̐V���Ȃ�C�������ӂ�Ԃ�A����Presage���ɂ��Ă�
�������Ǝv���̂ł���B
�u���v�̎v���o�v�^��@�S�コ��̃G�b�Z�C
�|�����v�A�ڊo�܂����v�A�r���v�A�ۂ����v�A�l�p�����v�Ȃǎ��v�ɂ͂��������ނ�����܂��B
���̒��ł��ڊo�܂����v�́A�l�ɂƂ��Ĉ�ԐS�Ɏc���Ă��鎞�v�ł��B
�ڊo�܂����v�́A���������l�̖ڂ��o�܂����Ă���܂��B
���������A���������A���Ԃ�����Ή���炵�Ă���܂��B���܂ɂ͂��̉��������Ƃ������āA���������Q�����Ăق����Ǝv����������܂��B
�����ǁA���v���ƁA�ƂĂ��֗��Ȃ��̂��Ǝv���܂����B�ڊo�܂����v���g���A�Q�V���قƂ�ǖ����Ȃ邵�A���̉����č������n�܂�Ƃ����C�ɂ��Ȃ��̂ł��B
���܂܂ŁA���낢��Ȗڊo�܂����v�����Ă��܂����B�{�u��T�b�v��E���g���}���̐����o��ڊo�܂����v������܂����B�l�̖ڊo�܂����v�́A���ʂ̃x������^�C�v�ŁA���������邳���ł��B
�Ȃ̂ŁA������Ƃ����ڂ��o�߂܂��B
�����傫�����Ă��܂ɁA�т����肷�邱�Ƃ�����܂��B
���܂܂Œ��N����̂ɂ́A�ڊo�܂����v�̂������ŋN���Ă��܂����B���������A����̎n�܂�̍��}�������Ă��ꂽ�ڊo�܂����v�Ɋ��ӂ������ł��B
�����Ă��ꂩ�����낵�����肢���܂��B
�u�n�g���v�v�����@��������̃G�b�Z�C
�R�`�R�`�R�`�R�`�E�E�E�B���v�͒N�����Ă��Ȃ��Ă������Ɠ����Ă���B���v�̎d�����~�߂Ȃ��B���̉Ƃɂ͎��v���V����B�R�l��炵�ɂ��Ă͌��\������������Ȃ��B���̎��v�����̒��ň�ԑ��݊�������͕̂�̕����ɂ���n�g���v���B���͂����ȂƂ��낪���Ă��āA���v�����̖������ʂ����Ă���B�́A���������A���v�̏����������J���Ɛ��Ă��ꂢ�ȃn�g���������Ȃ�����Ă����B�����͏������邳���āA�������Ƒ��͏����C���C�����Ă����B
���v�ɂ́A�܂ڂ�����������悤�ȈӖ����悭������Ȃ����̂��Q�{�Ђ��������Ă����B�������m���獂���Ɉ����z���Ă����Ǝ��ɂ͂��̈Ӗ���������Ȃ����̂��������B�ł����A�����z�����Ƃɂ͂��ꂪ�Ȃ��B�ǂ����ɂȂ��Ȃ��Ă��܂����̂��B���̃n�g���v�́A���̈��z���̂��тɏ������������Ȃ��Ȃ����肵�ĉ��Ă������B�Ō�ɂ͓����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂��Ƃ��v����B
���̎��v���~�܂��Ďg��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����牽�������̑���Ȃ��悤�ȋC�ɂȂ�Ǝv���B�������܂������O���炠���āA���͂��̃n�g���v�Ƃ����ƈꏏ�ɕ�炵�Ă���B�Â�������Ă����̂������͂Ȃ��Ǝv�����ǁA�j�͓����Ă��Ăق����B�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����炳�т����B������A���̃n�g���v�ƁA�����ƈꏏ�ɉ߂����āA���Ԃ������Ă��炢�����Ǝv���B
�u���v�̖�ځv�R���@���I����̃G�b�Z�C
���v�͎������������Ă���Ԃ������Ǝ~�܂炸�ɁA�d�r�����܂ł����Ɠ����Ă���B�u���炢�ˁB�v�d���M�S�Ȏ��v�͂͂Ȃ������Ă��Ȃ��Ȃ��Ԃ��Ă���Ȃ��B����ɑ��Ď��͑ӂ��҂��B����������̂ɂ��N���������A���͕ꂳ��Ɩڊo�܂����v���K���ɋN�����Ă���āA����ł����͂Ȃ��Ȃ��N���Ȃ��Ė��f��������B�Ђ�͊w�Z�ł�������\���ԁA�G�A�����������I���ƌ����̂ɂ�����炸�ꕪ��b�����Ȃ����Ƃ̂͂��߂ƏI��������B��͂���Ƃ������d�����Ȃ��Ă��A�x�܂����Ԃ����ށB
�u������������B�v�Ɖ����������Ȃ�B
���͎��v�h���Ă���B����ǂ��܂莞�v���D���o�H�Ȃ��B���ꂵ���Ċy�����Ƃ��A�߂����ċꂵ���Ƃ��A�ǂ�Ȏ��ł����ɘa�����ɍ��܂�Ă����B�҂��ĂƂ����Ă������đ҂��Ă͂���Ȃ��A������Ȏ��v���������B�c���g�ŁA��������ŁA�c��������ŁA�ǂ�Ȃɔ߂����Ă����Ԃ͎~�܂��Ă���Ȃ������B
�����ǂ���͎��̎��Ȓ��S�I�Ȃ킪�܂܂Ő��E���ɂ͎��Ɠ������Ƃ��v���Ă���l�͂�������̂��Ƃ������B����ł����v�͎~�܂�Ȃ��A�肿���ɓ���������B���������̐��E�Ɏ��v���Ȃ�������A�����͉��������ʼn����Ȃ̂��A�����͍����Ȃ̂��S��������Ȃ��B������l����Ƃ�͂莞�v�͎Љ�̒��ł������Ȃ����̂̂��Ǝv���B
������������Ƃɂ����āA����Ӗ��e��肸���ƒ��������������Ă������ǂ��܂�e���݂��Ȃ��B���x������A�����������������Ԃ��A�������܂��O���炠��͈̂�����������B�\���N���̊ԓ����������厖�Ȏ��v�Ȃ̂ł��ꂩ��͑�ɂ��Ă��������B���ꂩ�璷���������ɂȂ�Ǝv���̂ŊȒP�ɉ��肷�邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ɂ������B
�u���܂ꂽ�N���v�n�� �I��q����̃G�b�Z�C
���̉Ƃɂ͑傫�Ȏ��v������B���A��������̉Ƃɂ���悤�ȃf�W�^�����v��A�i���O���v�Ȃ���Ȃ��B�R�`�R�`�Ɖ������ĂȂ���ꕪ�ꕪ���ݑ����āA���Ԃ̐���������炵�ċ����Ă���钌���v���B�f�W�^�����v��A�i���O���v�ɓd�r������悤�ɁA�����v�ɂ��l�W������B�l�W�������Ȃ��ƁA���̎��v�͎~�܂��Ă��܂��̂��B
���̎��v�ɂ́A�����������Ƃ��������̎v���o����������l�܂��Ă���̂��B������������������̉Ƃɂ��łɗ������ꏏ�ɔ������������B�������Ĉȗ������Ƃ��̉Ƃɂ���B���̎��v�͂����ȏ�i�����Ă������Ƃ��낤�B���������u�Ԃ��A���܂����đ������u�Ԃ��B
���͎v�������Ƃ�����B���͎����̐S�ɖ���������A�����~�܂��Ă��܂����Ƃ�����̂ɁA���v�͂Ȃ����m�ɂ�ǂ݂Ȃ��������ނ��Ƃ��o����̂��낤���B�S�̒��Ɏ��v������Ƃ���Α����A�\�ܔN�Ԑ����Ă������ŁA���̔N�����͐i��ł��Ȃ��Ǝv���B
���͗V�тɍs���Ƃ��A�O�Z�����炢�x�点�����Ƃ��������B����́A�����x�����Ԃ܂ŗV�ׂ�悤�ɂ��邽�߂������B����Ȏ����̐S�ɂ͈��S������A���̎��v��厖�ɂ��Ă������������ɐ\����Ȃ��v���Ă����B�V��ł��Ċy�����C�����ƈ������Ƃ����Ă��܂Ȃ��Ȃ��Ǝv���C�����������荇���āA�f���Ɂu�������܁v�ƌ��������ł��Ȃ������B
���v���~�܂肻���ɂȂ�x�Ƀl�W�������p������Ǝ����̂��Ă������Ƃ������炵���Ȃ�B�����m�邱�Ƃ̂ł��Ȃ��C���������̎��v�ɂ͂������Ă���̂������B���̎��v��厖�ɂ��悤�Ǝv�����B����́A����������厖�ɂ���̂Ɠ������Ǝv������B
�u���v�Ɛl�ԁv���c�@�m�炳��̃G�b�Z�C
�l�ԂƂ����̂́A���Ԃ̗���ƈꏏ�ɓ����Ă�B���v�́A���������j�ƒZ���j���ǂ��������������Ă���̂ł͖����l�Ԃ������̂��Ǝv���B
�l�̖��͎��ԂƂ������̂Ɍ��߂��Ă���Ǝv���B
1�b�o���Ƃɐl�̎������Z���Ȃ��Ă����ċ��āA�l�͐��܂�Ď��ʂ܂ł����Ǝ��ԂƋ��ɕ�炵�Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B
�����ɏW�����Ă���Ƃ��́A���Ԃ��o�̂́A�������W�����Ă��Ȃ��Ƃ܂�1����2���ƂȂ��Ă��܂��B
���v�́A���v�ł������Ă���̂������Ă��Ȃ��̂�������Ȃ��Ǝv���B
�����ł͂����Ă���Ǝv���Ă��Ă����̐l���猩��Ƃ����ĂȂ����낤�ƌ������ƂɂȂ�Ǝv������ł��B
�{���ɂ����č����Ă��鎞�v�́A�ق�̏������Ǝv���B�����A�F�B�̉ƂƂ��ɗV�тɍs���Ă��āA�����̉Ƃ̎��v��10���قǂ���Ă���5��10���O�ɏo���͂��Ȃ̂�5��10���ɂȂ��Ă���ƌ������Ƃ����邩��ł��B
���v�́A�����Ȃ��̂�����Ǝv���܂����B
�Ⴆ�A�r���v�A�ڊo�܂����v�A�����v�Ȃǂ��낢��Ȏ�ނ����邯��ǂ��̑S�Ă̎��v��1�b��60���1���A1����60���1���ԂƐi��ł����Đl�Ƌ��ɂǂ�ȂƂ��ł��ꏏ�ɐi��ł���Ǝv���B
�u�厖�Ȏ��ԁv�c���@�ʊC����̃G�b�Z�C
���̕����ɂ͂��̑O�܂Ŏ��v���Ȃ������B���v�͎��Ԃ�������v�����肷��̂ɕ֗��炵������ǁC���̂Ƃ��͂���Ȏ����l���Ă͂��Ȃ������B���̎���͌g�ѓd�b�Ƃ����ƂĂ��֗��Ȃ��̂�����̂ŁC���Ԃ�����Ƃ��͂�������𗘗p���Ă����B
������ꂪ����Ɏ��̕����Ɋ|�����v�������Ă����B���v�̓J�`�J�`�����̂ł����ɋC���t�����B���̓��̖�̓J�`�J�`�Ƃ����̂ň�a�������������ǐQ��ꂽ�B
���͒x�����肷��l�Ԃ�����C�ƂĂ����Ԃɂ̓��[�Y���B�ł��w�Z�ɍs���̂��x���ƁC�e�����邳�������悤�ɂȂ��Ă����B��������͖{�C�œ{��ꂽ�B���̓��͂����ƈȍ~�ƌ��S���ĐQ���B�����Ď��̓��̒��ɂȂ�ڂ��o�߂�Ɠ����ɔ��˓I�Ƀx�b�h�̉��ɂ����Ă��鎞�v�����̂����������Ō����B�����������������B���v�������u�ԃV���b�N�����ݏグ�Č��̋C���������B
���Ԃ������Ă����͂��܂�W�Ȃ��Ǝv���Ă������C�ŋߓ��Ɏ��v�ɂ����B
���̉Ƃɉƒ닳�t������B�����炻�̓��͒�����e���V�������Ⴍ�Ȃ��Ăǂ����悤���Ȃ��Ȃ�B�����甪���\�����炢�O�ɂȂ�Ɩ{���ɐS���a��ł��銴�����B�ƒ닳�t�����Ă����v����ɖڂ�����Ă��܂��B
����Ȃ���ȂŁC����ς蕔���Ɏ��v������̂ƁC�Ȃ��̂ł͌��\����Ă��邵�C�ނ��날���Ă������Ǝv���B�����āC�����͎��v�̗L���������āC���Ԃ���肭�g�����ƍ����̒��C�ڂ���Ɗ������B
�u��ɐ��������v�v�r�c�@�F�q����̃G�b�Z�C
�u���N�̉ԉ͋�P�̂悤�ɋ��ɋ����B�v�Ƒc�����A�r�̎�����������ƒ��������Ȃ���A�픚�������̎������n�߂��B
�u�������������ˁA�M���̐�ɔ�э��ނƂ��낾��������ǁA�w�����E��҂��Ă���B�x�ƌĂԐ������ĉ�ɕԂ�����A��ő��₦��l���ڂɔ�э���B�ł��A���̎v���o�̎��v�����́A�O���Ă�������s�v�c���ˁB���v���A���ɑ����Ė����~���Ă��ꂽ�ƁA�M���Ă����B�U��Ԃ������ɂ́A���̎p�͂��łɂȂ��A�w��������x�ƁA�������ꂵ�ސl�X���A�ڂ���Ă��A�܂Ԃ��̗��ɐ^���Ԃɉf���o����A�����Ă��A���߂�������������������B�v
���̎��c���́A�O�������v�������ɏE���グ�A��������Ƙr�ɂ����ӂ��A�F�����������B�������Ȃ���c���́A�ڂ̑O�̎��v�������ނ悤�ɁA��������̎�ŕ�ݍ��B
���̎��v���~���������̒��A�c��͎����Ă��������������āA�E���ɂ��{���ɏo�ł����B�畆�͏Ă�������A�E�W�����킢���c���������o�����̂͐����ゾ�����B���e�̈��̎��v�ƁA�Ȃ̈�����Ղ��N�������B
�u�c���������܂��̂��ꂳ�ˁA��̋�P�����āA�w���ꂢ�ȉԉ��ˁB�x�ƁA�������̂�����A���������Ə��Ȃ���܂𗬂������Ƃ��������Ȃ��B�Ȃ������̉ԉ̉��́A��P�̂悤����B�v
���v�̎v���o��������c���́A���̓��̖钆�A�c��̉��ŁA����悤�ɐÂ��ɑ����Ђ��Ƃ����B��㔪��N�A��������A���\��̎��̂��Ƃ������B
�c���̘r���v�͍����������ݑ����Ă���B���a�̉ԉ��A�݂�ȂŊy���߂鐢�̒����F���Ă��邩�̂悤�ɁB���A���̎��v�́A���̂����ł�����B���v�̉��ɂ́A��e�̑ٓ��ŁA�S�����悤�Ȉ��g��������B���v�́A�l�͂Ƌ��Ɏ������݁A���j���c���B
���N���A�ԉ͏オ�邾�낤�B�Ί�ʼnԉ������邱�Ƃ��A�S����肤�B
�u����A������������Ȃ��I���̎��v�I�v
�|���̓r���A��Ǝ��͈�̎��v���͂�ŋx�e�������B
�����������F���u�����v�B���v�̏�ɂ̓~�b�L�[�}�E�X���l�W�������ė����Ă���B�傫�ȕ����Ղɂ͐Ԃ��}�W�b�N��5�A10�A15�c�ƕ�̎��Ŏ��Ԃ̓ǂݕ��������Ă���B
���͏��w�Z�ɓ��w����܂ŕa��ŁA���x�����މ@���J��Ԃ��Ă����B�����̓_�H�Řr�ɂ͂����������������B
�������̗��e�͖Z�����ʉ�̎��ԂɂȂ��Ȃ������ɗ��邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
�����҂�����Ȃ��悤�ɔ����Ă��Ă��ꂽ�̂��A�u�����v�������B�u�����މ@�ł��܂��悤�ɁB�v���̎��v�̒Z���j�����Ɖ���12�ɗ���Αމ@�ł���̂��ȁB
�A���[�����̓~�b�L�[�}�E�X�}�[�`�B�P���̃I���S�[�����B���x���A���[����炵�ẮA���̓���҂������Ă������Ƃ����ł��o���Ă���B�����A�҂��������Ƃ����L���͂Ȃ��B���@���A��͎��v�̑��ɂ��ʂ�����݂�G�{��r�[�Y���Ă��Ă��ꂽ�B
���ꂩ��15�N�B�ʂ�����݂��G�{���r�[�Y�������Ȃ��B�����A���v�����͎̂Ă��Ȃ������B���N�̑�|���������蔲���č����ڂ̑O�ɂ���B�d�r�����Ă������A���[�������f�B�[�͖��Ă���Ȃ��B���܂Ƀ|���b�Ǝv���o�����悤�ɉ����邾�����B���������̓��ɂ͂��̃����f�B�[�����x�����x���J��Ԃ��t�ł���B�P���̃I���S�[���A�{���͏����҂����B�̂Ă��Ȃ������Ӗ������͍l����B
�Еt���������Ŗ�A��Ɂu���߂�ˁv�ƌ���ꂽ�B���͕�����߁u���C�Ɉ������v�ƌ����B�����Ȃ����̎��v�A���ꂩ������̂��ɂ��邾�낤�B���͕�̈���m���Ă���B
�u����������̂Ȃ��Łv�j����̃G�b�Z�C
�c�����A����҂��Ă����A�����B
�u��������܂��Ȃ́A����������v�u�Ⴂ�l�B�ɂ��y�����Ă�̂�v�u�����́H�v�u�d����v
�N����Ƃ��y�Y���������B�ʂ�����݂�ʕ��ɂ��َq�B�ÌI�́A���ƈꏏ�ɐH�ׂ����ɂނ��̂��ʓ|�������ăC�����ƌ����Ă���͈�x���Ȃ������B�����A���̍D��������Y��Ȃ��ł���Ă��邱�Ƃ������A�ł�������q�ł��悤�ƁA�₵�����䖝�������̂������B
����Ȃ�����A��̗��A��̂��߁A�v�������������x�݂��Ƃ����B�u�o�|���邩�H�v�ڂ��҂�Ε��Ǝ���q���A�炪�j��قǃj�b�R���Ɓu����I�s���I�v�ƌ��������w�P�N���̎��������ԁB
���͐E�l�Ȃ�����̂���ǂ��������Ă��āA���ł��i�����̂悳�ł悭���p����A�V�܂̕S�ݓX�ւƎ���A��čs���Ă��ꂽ�B
�ЂƂƂ���q���p�̃t���A�����Ă��A�����~������Ȃ������u�ꂳ��Ɏ��v�ł������ɍs�����v�ƁA���͎��v����ւƈ��������Ă������B�u����������ȁB����Ƃ����ꂩ�H�v�y�����Ɉ�l�����Ă��镃������̂͊y���������B���I�̂��A���Ⴊ�ݍ������A���̘r�ɉ��F���G�i�����̔�̉������v�������B�҂�����Ȃ��Ƃɋ����Ɓu��������������Ōv�������v�Ɠ��ӂ��ɕ@��Ԃ������B
�����������̂ɁA���͂��̎��v���悭�O���A���������o�����Ɏ������Ă��܂����B�u�ǂ����Ď��������H�v�u����Ă���肭�����Ȃ������B�₵���Ɂu�܂��������H�v�ƕ��͏��A���͖ق��Ę낢�Ă����B
�u���v�͂�������̂��Ȃ����Ԃ�����m�点��B���y�Y�������������͂��Ȃ��B�����炨�y�Y�����v������Ȃ��Ɍ����������B������B���߂�ˁv
�����������͎̂O�N���̏I���B�`������������邹�Ȃ��A�莆�ɏ������K���Ȏ����������B���ꂩ�玄�͖��肱�������̊�ɂ����Ǝ���������̖����悭�����B�����Ɖ��������ꂪ�������B���A���͓�������ŏ������҂��ݑ��������ƐS����肤�B
�u�m���ȃ��Y���v��{�@�^�߂���̃G�b�Z�C
���͏����Ȏ��v�̂悤�ɉ�����B����͐��ł������葫���ł������������B���������̎��v�͈��̃��Y���������ނ��ƂȂ�����������B�����Ɗ��Ɏw���������āA�\�������j�������Ƃ��A���̂܂Ԃ��͂��낳���B�[���Â��ł��L����A���v�̉��������̂��x�z���Ă����B
�������������A���̃��Y�����߂��Ă����B���Ɏ�āA�ۓ����m���߂�B���̃��Y�����R�R������������ł���B�����Ă������Ƃ̓��Y������邱�ƁB���v�����Y�������悤�Ɏ��̕s�m���ȁA�������������Ƃ̂Ȃ����̃��Y��������Ă����B
���̐��݂͂�Ȃɕ������Ă���̂��낤���B������������N�ɂ��͂��Ă��Ȃ��̂�������Ȃ��B���������Ă͂����Ȃ��B���������邱�Ƃ͎����̃��Y����������ƁB�����Ɖ�����B�N���ɓ͂��悤�ɁB
�N���̃��Y�������ɓ͂����B��̒N�H�Ȃ����ɕ������Ă����́H�s�v�c�ȋC���������Ă���B�������Ă��郊�Y���������ɈÈłɂ��鎄�̃��Y�����ĂыN�����B���̔g����m���Ă���̂́A�e�Ȃ̂��B����Ƃ��A�����̒m��Ȃ��l�Ȃ̂��B
�ˑR�������N���̃��Y���B���킽���Ζ��邢�������ɓ���B�J�`���Ɩ������v�̐j�B�ۓ�����������B�u���������͈��̃��Y����������ł���v���⑫���͒N���ɍ��킹�邱�Ƃ̂ł��郊�Y���B�ۓ��́c�c���܂ꎝ�������Y���Ŏ��������ށB�ז������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�߂������ɂ����������ɂ��A�N�ɂ��ז�����邱�ƂȂ������̃y�[�X�œ����Ă���B���̒N���̃��Y�����Ă݂��B���Ƃ͈Ⴄ�͂₳�B����ǂ��̃��Y���͒N�ł������Ă���B���S�ł��鉹�B���ɂ��������v���~�܂��������B���̎��܂ł͎����̃��Y�����Ɏ���Ă��������B��l��l�̒��̎��v�̉����B
�u�r���v�̂Ȃ������v�㓡�@������̃G�b�Z�C
�������̂́A�Љ�l�Ƃ��Ă̌����B�l�Ɖ�ꍇ�A���ԂƏꏊ�����߂�B���ɁA�x������悤�ȏꍇ�́A����ɂ��̎|�̘A��������B��������Ȃ���ΎЉ�l�Ƃ��Ă̐M���������B
������Ƃ������B���j���ɗF�l�Ɖ�������B���N���Ęr���v���Ȃ��̂��������B�O�ӂɓD�����ċA�����B�ǂ����ŗ��Ƃ����炵���B����̘r���v��T�������Ȃ��B�ǎ��v������ƁA�̎��Ԃ��߂Â��Ă����B����ĂĉƂ��o���B
�҂����킹�̏ꏊ�ɂ܂��ނ͌���Ȃ������B��u�A�r���v�Ŏ��Ԃ��m���߂悤�Ƃ����B�Ȃ������������B�r���v���Ȃ������ɕs�����悬�����B���͉������낤���B�܂��̎��Ԃ͉߂��Ă��̂��ȂǁA���܂łɂȂ��S�̂ǂ�߂����g�̂悤�ɂ����B
�߂��ɃX�[�p�[���������B���肱��Ŏ��v������T�����B���̑I�������Ȃ���~�̘r���v�����B�r�ɂ͂߂��Ƃ��A�C������������肵�Ă����B�҂����킹�̏\���O�������B�����Ŏ��Ԃ���������K���������߂Ēm�����B
�F�l�ɂ��̂��Ƃ�b���ƁA�����ȏ݂��ׂ��B�u���Ԓ��ł���B���ԂɎx�z����Ă��邩���ˁv�����A�����ɂƂ��Ď��v�͕K���i�ł͂Ȃ����B��N��ɂ́A�r���v�������Ȃ��������������Ɣނɘb�����B�ނ����ӂ����B��N�܂ł͒����B
�u������A�{���{�����v�A���C�H�v�����f�B����̃G�b�Z�C
������A�����V�Ɍ������āu�����`��v�ƌĂ�ł��鐺����������H�Z���Ƃ����đւ������A���Ȃ��̌��Ă��Ƃƈꏏ�ɉꂽ�{���{�����v���A���Ȃ��̖T�łɂ��Ə��Ă���Ȃ�A�u�{���{���v�ƕԎ������Ăق����ȁB
������A���Ȃ����O�O�Ɏ����������{���{�����v�́A���e�̂��Ȃ���莄�ɊS���Ă���Ă������Ƃ�m���Ă��H���Ȃ��͖����d���ŖZ�����������ǁA���Ԃ̃{���{�����v�͎��������Ȃ���A����������Ă�����B���]�ɜ���Ă��������A�Ӎ������������������ɕ����ꂽ�܂܂�������������������U���B�����I�����s�b�N�̑̑����e���r�Ō��Ȃ���A�^���Ď葫�������P�O���B��v����ƌ����O�͖����d�b���|�������Ă������ǁA�������Ȃ����Q�Ă��炾�����B�y������������A�{���{�����v�͍���ł����̂���Ȃ���B���Ȃ����������ŏ�����Ȃ��ƁA��v����Ƒ؍݂��Ă�����p�ɁA�ꂳ���ۓd�b�������Ă������A�{���{�����v�͂ǂ�Ȏv���ŕ����Ă������낤�ˁB���̖ڂɃ{���{�����v�̉��ŁA�����Ȃ��炠�Ȃ��̓��a�̗l�q��i���Ă���ꂳ��̎p�������B�u������A�����Ă��āv�Ɗ肤���ɁA�N���A������܂Ŗl��������̐S�����������邼�Ƃ���ɁA�{���{�����v���K���Ɏ���ł��Ă���l�q���B
������Ɨ���ĕ�炵�Ă������A���Ȃ��̂��Ƃ��v���o���@����Ȃ������̂ɁA����A�Ǒz���邱�Ƃ������Ȃ����B�V�̎����䏊�Ő�䥂łĂ���Ɓu�����ЂƂ܂ݓ����v�A�����C�Ŏ��̔w���𗬂��Ȃ���u���w���ɂȂ������玩���ő̂��v�ƌ������������B�S�̒��Ő����Ă�����āA�����������ƂȂˁB���Ȃ��̉��������{���{�����v�����̐S�̒��ɋ���B�����ĕs�v�c���ˁB���X�Ɖ߂��Ă����̂Ɏ育�������Ȃ��B����̖Z�����ɂ��܂��Ď��̗�����ӎ����Ȃ����ɁA�{���{�����v����肩����B�u���Ԃ͗L������A���ʂɂ���ȁv�ƁB
�u������Ȃ����w�j���̘r���v�v�e�@��������̃G�b�Z�C
���̂��q���̒��w�Z���w�L�O�ɂ͘r���v�ƌ��܂�������B����́A���̎��Ƌ��s�̕�̍l���B�u�����A�@���������w�Z�ɓ��w�������ȁv�ƁA�����݂���̔��ő����Ă�����ƁB��̉ו��̒��ɕ�̎ւ��͂������Ŏ��Г���̎��v���������Ă����B
����ŁA�R�l�̎��v�B���킢���A���̂��߂ɒ��w���w�����Y�ꂸ�ɁA��i�Șr���v��I�ё����Ă����B
�݂��̒��ɂ́A�Ă�p�����A���X�A�ݖ��A�p���A�����A�`���R���[�g�A�ʋl�߂ȂǁA�܂�ŎR���̈ꌬ�ƂɏZ��ł���Ƒ��ɑ���ו��̂悤�ł���B���̒��ɕK���A���R�l�̂��߂̕i�Ƃ������������������ɓ����Ă���B�����̔N�����g�킸�ɒ��߂āA�S�~�ʂƌܕS�~�ʂ��R�̕����ɕ����A�Z�핪���z���l���ē����Ă���B��������q���B�́A���̖�ɓd�b���āu���������A���肪�Ƃ��B�����ς��ו������Ă����B�v�ƁA���ǂ��Ȃ���A���������̓�������т�\�����Ă���B
�r���v�͊i�ʂ��B���܂�ɂ����������ȕi���݂āA�����Ǝg�����ɂ��܂�A�厖�Ɋ��̒��ɂ��܂�����ł���B
���͂ǂ�ǂ�i��ł����B���܂�ĂP�Q�N���߂��A���v��K�����q�������l�ɂȂ�A�p����Ă����̂��낤���B
���e�̎����A���Ƃ̖S��������r���v�����j���ɂ�������B
���̖S�����̌`���Ƃ��āA�厖�ɂ��Ă���B�܂��A��������������B���́A�ނ�R�l�ɖڊo�܂����v��n���Ă���B�厖�ɂ��Ȃ��Ă��悢�A���N������悤�Ɋ肢�g���ė~�����̂��B
������Ȃ��r���v�́A�傫�Ȏ��Ԃ����ށB�P�Q�N�Ƃ����P�ŁB
��撷�������Ă��������B�W�R�̎��͂܂���葱���ė~�����B
�u���̂Ђ݂v�X�R�@�ׂ���̃G�b�Z�C (12���̃x�X�g�G�b�Z�C)
�r���v!�N�̎�ɂ����鐶���K���i�ł���B
�R���A�����q���̂���i���a��\�N��j�́A�ƂĂ���̓͂��ʁA�����ʂ�w����̉ԁx�������B
���͑����m�푈�������Ȃ�́A���a18�N�ɍ����w�Z�ɓ��w�����B�����A�����̌��R�͐r�������A��H�ɂ��玖���������������B
�����w�Z�ɓ��w����ہA�N���������Ȃ��Ȃ���ɓ��炸�A�������z�����������ʁA����ƘZ�F�̃N��������T�����߂����ゾ�����B
����Ȏ���A���v�ƌ����ΉƂ̒��̊Ԃɂ���Â������v�A����Ɗw�Z�ōZ���搶������̍ہA�����ނ�ɉ������o������̉������v�ł���A���̂܂����������B
���a23�N�t�A���͐V�����w�Z�ɓ��w�����B�R���A���̂Ȃ��̂͑��ς炸�ŁA���ȏ��ł�������l��g�ŋ��L�����鎞�ゾ�����B
����Ȓ��A�������̃N���X�ɂx�N�ƌ����y�n�̑f���Ƃ̑��q�������B���g��᪁A���т��l�����ǂ��A�������̃N���X�ł͈�Ԃ̐l�C�҂������B
����Ȕނ�������A�����ɕ�т������ēo�Z�����ė����B���Ȃ������тł���B
�u�x�N�I���̎��ǂ������́H����ł��H�v
�x�N�͍m����ے�������A����ł����B
�ނ͕ʂɍ�����݂������Ȃ��A�̈�̎��ԂɂȂ�ΐl��{���C�ɓ�������Ă����B
�w�x�N�̎��̕�сA����͈�̂Ȃ낤�B�x
���̎������̊Ԃɂ��A�N���X���̘b�肾�����B
����y�j���̒��A���͔ނɂ����Ɛq�˂��B
�u�x�N�I�N�̎��̕�сA�C�ɂȂ��Ȃ��B�v
�u�N�A�����Ă����悤���I��Γ�������I�v
�x�N�͈ĊO�A�C�Ղ����Ȃ����ăX���X���Ǝ��̕�т��قǂ����B���͌ő���ۂ�Ō�������B�Ȃ�Ɓc������o�ė����̂͋�F�̃u���X���b�g�A���̘r�����v�������̂ł���B
�u�E���[�b�A��������B�v���͊��Q�̐����������B
�����A��50�N�B�����r���v������ƁA�t�b�g�v���o�������������N����̎v���o�ł���B
�u�r���v�͒j������炤!?�v�R�c�@�~�q����̃G�b�Z�C
���߂Ď����r���v������悤�ɂȂ����̂́A���Z�ɓ��w�����Ƃ��ł����B����܂ł͂��܂�K�v���������Ă��܂���ł������A���Z���w�C�R�[��������Ƒ�l�B�����Ęr���v���͂߂���Ă����C����������܂����B�X�Ƀo�X��d�Ԓʊw������Ƃ������Ƃ������āA���Ԃ��C�ɂ���K�v���������������炾�Ǝv���܂��B
���Z�ɓ��w����Ƃ����Ă��e��e�ʂ����w�j���ƌ����Ęr���v�̈�������ĖႦ��Ɗ��҂��Ă��܂����B�ł����ʈ���Ⴆ�������Ŕ��������Ȃ����Ǝv���Ă��܂����B���ꂪ�Ȃ������w���̒킩��Ⴂ�܂����B���w���̒�ɂȂ��r���v���Ă�������̂��Y��Ă��܂��܂������A���ł����̎��v�͑厖�ɂ��܂��Ă���܂��B�x���g���v�ŏo���Ă��鎞�v�������̂ŁA�����v�̕����̓��������ŁA���ւ��Ȃ��Ǝg���܂��A���ւ���Ɛ̂̎v���o�������Ă��܂������Ȃ̂ő厖�ɂ��܂��Ă���܂��B
���̒킩���������v�͍��Z���Ƃ��Ă����炭�g���Ă��܂������A���l���ɂ͕ʂ̒j������܂����v��Ⴂ�܂����B
����́A�X�C�X�̗L�����[�J�[�̎��v�ŏ����炵���������Ȏ��v�ł����B���̎��v�����ɂ��ꂽ�͕̂��ł����B���͎d���l�ԂŎq���̍��͂��܂�V��ł�������L��������܂���ł������A�v�t�����߂��������炠�܂�b���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B����Șb���낭�ɂ��Ȃ��Ȃ������ɐ��l�ɂȂ������j���ɕ��͘r���v������܂����B�ӊO�ȃv���[���g�Ɏ��͂��������ꂵ����������ǁA�f���ɂ��肪�Ƃ��������Ȃ������̂��o���Ă܂��B
���̕������v������Ă���O�N��ɂȂ��Ȃ��Ă��܂��܂����B���肪�Ƃ��͂����Ȃ��������ǁA���͖�������v���`�����Ƒz�����ł��厖�Ɏg���Ă��܂��B
���ɂƂ��Ęr���v�͑�ȉƑ��̈���܂����厖�ȕł��B
�u���v���Ă��̂͂�����������ł���v傖��@���V����̃G�b�Z�C
�����A�܂�܁A�u�[�u�[�c�c����Ƃ����錾�t�ł��B�����ɂ��ڂ��Ă��錾�t�Ȃ�ł��ˁB�c�����������₷���悤��l���b�������錾�t�������ł��ȁB���ꂪ���̊Ԃɂ���l�̌��t�ɕς���čs���킯�ł��B
�Ƃ��낪���̉Ƃł͗c����Řb���������܂���ł����B���͑��A��т͌�сA�����Ԃ͎����ԁA����ȕ��Ɋo���������܂����˂��A�ŏ�����B
�ŁA���v�������B���߂Ă̎��v�͓����o���n�߂��ቿ�i�q�������L�����N�^�[���̃f�W�^���t���E�H�b�`�ł͂Ȃ��A�����Ȃ��l�����̒��O�j�A�i���O�N�I�[�c���v�B�\��̒a�����̃v���[���g�ł����B�W���[�W�ɂ͍����܂���ł����˂��B�ł��A�T���߂ȃf�C�g�\�����͉t���f�W�^���ŁA�A���[�������Ƃ����q���S�����f���炵�����ł����B
�ȗ������𒅂�悤�ɂȂ��Ă��w���ɂȂ��Ă��A�w�L�𒅂�悤�ɂȂ��Ă������Ƃ����{�B�Ƃ������w�L�𒅂�悤�ɂȂ��āA����ƃs�b�^������悤�ɂȂ����A����Ȏ��v�ł����B
���v���Ă����̂͒��g�ƒZ�j�ƕb�j�����邮�����Ă�����A��Ԃ��ŏ�����ڎw���Ή�蓹�͂��Ȃ��Ă��ނ��B�c������g��Ȃ��������e�̎v�������߂��Ă�����ł��˂��A���l����ƁB
�܂����̂��A�ŁA���Ɋւ��Ă͉�蓹�����A��ԁE�����h�ɂ����ɂ��ǂ���Ă���悤�ł��B�ł��̐S�̐l���́c�Ȃ���蓹�����蓯�����J��Ԃ�����A�����������邮�������肵�Ă��܂��Ȃ��B��������O�j�A�i���O���v�̉e���ł��傤���˂��B
�O�\�Ή߂����̂����������ɐV�������v�ɕς��܂������A����ς蒆�O�j�A�i���O���v�ł��B���v���Ă��̂͂����������A�Ƃ����̂ɐ��ݍ���ł��܂��Ă����ł��ȁB������u�����v���́u�܂�܁v���́u�u�[�u�[�v���̂Ƃ��������v�ɂ́A���͈ꐶ����o���Ȃ��ł��傤�B
�u�����������{�����v�v������̃p�p����̃G�b�Z�C
�c�Ƃ̓r���łR�ɂȂ�q���ƍȂ��҂����킹�Ē��H�������B
�q�������̘r���v�������Ď��������Č������ƌ����o���Ȃ������Ă�����B
�u���O���傫���Ȃ����炻�̎��v������v���������ƊԔ����ꂸ�ɍȂ��u�����Ă悱��ȃ{�����v�v�Ƃ̂��܂����B
���͕��i���������Ă��̎��v�͒����Ă��Ȃ��A�厖�ȉc�Ƃ��ȃC�x���g�����鎞���������Ă��Ȃ��B
����20�N���O�Ɏ��̕������l�̏j���ɂƂ��ꂽ�����Ŕ������v���o�̐[�����v�ł���B
�����̓f�W�^���\�����l�C���������A�E�l�̕��̉e��������P�N�Ő��b�����덷�������Ƃ����L���O�̃c�C���N�H�[�c�ɂ����B�A�E�����̍ۂɍŏI�I�l�łT�l�c�������ʼn��̂������I�ꂽ�B
��ɏ햱����u�N������������Ƃ����r���v���Ă�������I�v�ƌ���ꂽ�B
�Ȍケ�̎��v�͑厖�ȏ�ʂɓo�ꂷ��悤�ɂȂ����B
�]�ݔ��̉c�Ƃł��܂��ܐ���Ɏ��v�D���̕������āA�u�������v�����Ă���˂����̓����̃f�U�C���͂�����˂��v
�Ƙb��������オ��A���̎��͌_��͓��������̂́A�Ȍ�͊���o����������̂����肻�̌�㓾�ӂɂȂ����B
�Ȃ͂�����V�[���ɓo�ꂵ���̃C���[�W�̈ꕔ�Ƃ��Ē蒅�������v���ȒP�Ƀ{���Ă�肵���̂ł���B
�����̎Љ��20�N�����ׂĂ�ے肳�ꂽ�悤�ȋC�ɂȂ�A��u�J�b!�ƂȂ�M�����̂����������A���̎��v�͉��̂��X�b�Ɨ��������s�v�c�Ȗ��͂��������B�ْ������ʂ�v�킸�{����o�����ʂŁA���̂P�b���ƂɊm���ɗ�Â̍��މ^�j������ƋC���������炮�̂ł���B
�u�{�����Ƃ��v�ƍȂɏ������������Ί�������Ȃ���A�m����20�N���o�Ə����ȏ�������P�����ȑO�̂��̂ł͖����A���܂ɂ͕���|���ł��o���Ă�邩�Ȃ��Ǝv���Ă���ƁA�q�����u�����������˂��v�ƌ����Ă��ꂽ�B���̎��v�������������̂��A���v�����Ă�����Ă��鎩���������������̂��͒肩�ł͂Ȃ��B
�u��̉������v�v���R�@�Njv����̃G�b�Z�C
���N�Q���A�F�l�ɉ���߂ɃI�[�X�g���A�ɍs�����B�ނƒm�荇�����̂́A�킽�����܂��Q�O��̂��됢�E�̂��������𗷂��A�ނ��܂����E���q�b�`�n�C�N���Ă������낾�B
�@�P�W�N�Ԃ�ɉ�����Ƃ���ŁA����܂łR�x�����Ă���̂ŁA�ʂɂǂ��֍s�������Ƃ����ꏊ���Ȃ��B��k����Ƀr�[��������ł��炰��������ł悩�����B
�u�悤�v
�u�����v
�}���ɗ��Ă���Ă�����`�ŋv���Ԃ�̈��A�́A���ꂾ���������B
�y�Y�ɂ́A�@�B�D���Ȕނɂr�n�m�x�̍ŐV�^�r�f�I�J�����A������ɂ̓J�V�~���̃Z�[�^�[�A���̃J�����ɂ̓��A���[�E�W�F�C�E�u���C�W��s�k�b�A�}���C���E�L�����[�A�X�W�f�B�O���[�Y�Ȃǂ̂b�c�����A�X�S�ɂȂ�ނ̕�ɂ͌��̃l�b�J�`�[�t��n�����B
�R����ނƃX�C�X�𗷂����Ƃ��A���Ԃ����Ƌ�̉������v���v���[���g���Ă��ꂽ�B���{�ɋA���Ă����A
�u�r�f�I�J��������ɂ���x�ɂ��܂����v���o�����B����������!�v
�Ƃ������[�����͂������B
�Ƃ��낪�������́A�������̍����{�^���ɕt���A�x�X�g�̃|�P�b�g����o���Ď��Ԃ��������ƁA�l�W�������̂͌Â��ǂ�����̓���ł��܂͂Ȃ��B�ŁA�Q�N���m�F�̂��ߖ����ɒu���Ă���B
�u���̂ق��͐Q��܂��Ɏ������m�F���Ă���l�W�������A���͉��������邽�߂Ɏ�ɂƂ�B���܂��̓r�f�I�J�������g�����т��낤���ǁA���v�͂P���Q�x�����܂����v���o������B�����ƍ����Ă�!�v
�ƁA�ł��Ԃ��Ă������B
��̉������v�́A���������Ɗm���ȍ��݉����������A��ɂ���x�ɔނ̊���яオ�点�Ă����B����������!
(���O�̂�����)
�u�v���o�̎��v�G�b�Z�C��W�v�ɑ����Ă����������G�b�Z�C�̒��쌠�́A�Z�C�R�[�C���X�c��������ЂɋA�����܂��B
�܂��A�݂Ȃ��܂̃G�b�Z�C�Ǝ����i�y���l�[�����L�ڂ����������ꍇ�̓y���l�[���j���A���z�[���y�[�W��Ɍf�ڂ����Ē����܂����Ƃ��A
�\�߂��������������B