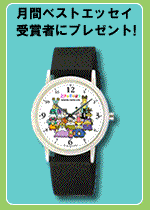2002年の作品
1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9-10月 11-12月
4月 (投稿順)
「腕時計に対する気持ちの変化」浜崎 誠さんのエッセイ
「黄色い時計」佐藤 克洋さんのエッセイ
「お守りの時計」池内 佐智さんのエッセイ
「ドラムと腕時計」川神 信弘さんのエッセイ
「恋は腕時計からはじまった」たから もかさんのエッセイ
「腕時計の思い出」渡辺 真一郎さんのエッセイ
「心も刻んでくれた時計」五十嵐 容子さんのエッセイ
「ペア・ウォッチ」栗原 小巻さんのエッセイ
「道しるべ」小山 信子さんのエッセイ
「私の腕時計」並木 秀雄さんのエッセイ
「息子のプレゼント」福田 雄三さんのエッセイ
「オヤジの時計」大森 和哉さんのエッセイ 4月のベストエッセイ
「腕時計の思い出」亀川 富雄さんのエッセイ
「高校三年生の腕時計」小原 淳子さんのエッセイ
「幼い私」清水 春菜さんのエッセイ
「青色のベルト」木岡 都姫さんのエッセイ
「お母ちゃんの宝物」北川 圭子さんのエッセイ
「あとからペアウォッチ」赤田 まりあさんのエッセイ
「不思議なAUTOMATIC」若杉 良子さんのエッセイ
「銀色の思い出」渡辺 麻子さんのエッセイ
「腕振り時計」石川 晃さんのエッセイ
「友達の月の腕時計」横山 尚美さんのエッセイ
「時計作りの元祖は誰?」木村 茲さんのエッセイ
「どこにいても。」三枝 由貴さんのエッセイ
「死を刻む時計」横田 友紀さんのエッセイ
「青い腕時計」木村 葉子さんのエッセイ 4月のベストエッセイ
「取り戻した時間」永山 裕幸さんのエッセイ
「お見舞い」絲山 秋子さんのエッセイ
「お姉ちゃんの時計」西沢 修一さんのエッセイ
「初恋の時」たけ坊さんのエッセイ
「銀色の腕時計のない1日」横山 和美さんのエッセイ
「ふたつの顔を持つ時計」前波 真一さんのエッセイ
「時代物」石原 敬三さんのエッセイ
「二年間の「いのち」」岩崎 麻衣子さんのエッセイ
「囲炉裏端の柱時計」かずえさんのエッセイ
「男は黙って・・・」 めぐさんのエッセイ
「パルテノン神殿と「クオーツ」男」小野 勝也さんのエッセイ
「濡れないダイバーズウォッチ」竹内 清訓さんのエッセイ
「腕時計外交」鈴木 捷立さんのエッセイ
「父からもらったはじめての腕時計」小形 幸子さんのエッセイ
「ジミーアンドパティ」鶴巻 琴江さんのエッセイ
「父の腕時計」松橋 昌道さんのエッセイ
「JIKANN」もうり テルユキさんのエッセイ
「初めての腕時計」佐藤 裕加子さんのエッセイ
「合格祝いの腕時計」山本 由美子さんのエッセイ
「絆のお守り」野元 みゆきさんのエッセイ
今から25年前、私が中学生だった頃、腕時計は高級品だった。
父は持っていたが、普段ははめていなかった。
腕時計を腕に付けるときは決まって旅行の時ぐらいで普段はタンスの奥深くとしまってあった。
腕時計という物はそれほど高級で憧れの品であった。
私が初めて腕時計を手にしたのは高校生になった時に父の知り合いからプレゼントされた。防水型の分厚いガッチリとした物だった。私はうれしくてうれしくて寝ても起きても四六時中付けていた。一日の中で何度か外す機会があった。それは、風呂にはいるときだ。その時はその大事な腕時計を机の引き出しの奥深くにしまい込み、誰にもさわられないように鍵を掛けていたことを思い出す。また、学校に行っても、外したくなかった。しかし、体育の時は、別で、そのときも、ハンカチで包み込み、鞄の奥深くに隠した。そんな私だったが、その大切な腕時計をなくしてしまった。二十歳を過ぎアルコールなる物を飲み始めた矢先、酔いつぶれ、気が付いたときは無くなっていた。悔やんでも悔やみきれない。そんな私だから、懇親会があるときは決まって、腕時計は外していくという習慣がついてしまった。こんな時こそ本当は必要なんだがあのときのことが今でも忘れられないのだ。現在腕時計は私の小遣いでも買える値段になった。そんな腕時計だが、長い間身につけているとどんなに安い腕時計でも愛着がわき他のどんな高級な物よりよく見えるのが不思議だ。
そんな私だけど、何時かは薄くて軽いほんのちょっとだけ高級な腕時計をはめてみたいと思うようになったのがこれまた可笑しい。
時間が正確なちょっとだけ高級な腕時計何時か私の腕に遊びにおいでと願う今日この頃である。
玄関の横にある棚に黄色い時計がぶらさがっている。僕が小五のとき買ってもっらたG-ショックもどき。バンドが壊れてしまい,もうしばらく使ってない。その時計は今も一時間ごとになる「ピッ」という音と共に時間を伝えてくれる。ふと夜に目が覚めたときに聞こえる時報の音が悲しく家の中に鳴り響く。新しいのを買おうと思っても,使えなくはない,すこし茶ばんだ黄色い時計を見て思いとどまる。
ある時,その時計の文字盤に文字がうつらなくなってしまった。とうとう変えどきだと思い休日を待った。どんな時計にしようかと思いめぐらした。しかし四日後,時計に文字が映っているのだ!しぶとい奴だ,と思いながらも,復活した黄色い時計を見てにんまりした。
いつの間にか中三,修学旅行が近づき新しい時計を買う決心をした。おなじみの電気店から,『くじが当たると全額払い戻し』という広告がきて今しかない!と思ったのだ。そして買ったのは,またもやG-ショックに似た時計・・・。残念ながらくじは外れたが,新しい時計はカッコ良かった。ヒマさえあれば時計をつけて散歩,と大変気に入った。机に入っている『おニュー』の時計を見てはニヤリ。しかし黄色い時計も忘れたわけでないはない。人生で最初に買ってもらった思い出の時計としていつまでも大切にしていきたい。
ある晴れた日の昼,黄色い時計の時報が「ピッ」と心地よくなった。
どうしても恋がしたくなる歌がある。
歌詞にのめり込んで、
「くーっ、わかるナー」
なんて、一杯飲んじゃって。
ありもしない過去や未来を作りたくなるときがある。
そして、少し悲しくなって、でも明日は何かが起こりそうな気がして夢路につくのだ。
いつからかこんなにも純粋に恋をしたいと思うようになって、そして、しなくなって4年が経つ。オリンピックも2回行なわれてしまった。前に活躍したいわゆる、「ベテラン勢」を今回も多く選んだ日本らしさが、もっとわたしを切なくさせるのだ。
西暦まで刻まれる私の腕には、きっとしょっぱいであろう革ベルト。自分の腕枕に頭をのせて、重いまぶたをひらくと、酔っ払ったわたしに語りかける冷静な時計がいつも居た。
ずっと一緒に居たい人には“永遠“を刻む時計をプレゼントするのだと、何かの本で読んだ。お互いにプレゼントしあったのだ。まだ上着が手放せない春だった。覗き込んだショーケースには私達の時間が一緒に詰まっていた。
おそろいのもう一つはきっと、大きくて優しい腕に今も行儀良くおさまっているだろう。そして、隣で笑っているであろう小柄な彼女にも温かい時を運んでいることだろう。
不思議だ。
別々のところでもこうして同じ時を刻んでいるというだけで、ちょっとキュンとして、ちょっとシアワセな気分。この時計が私とあの人のそばに〈在る〉だけで、この先ずっと何か大切なものと繋がっているような気がする。
同じ時計を持つあの人にも、どうか、新しい時がどんどん生まれていますように。
どんどん。どんどん。
ドンスカドンドン、ズカズカドンドン、仲間とグループを組んでロックドラムを叩いた。ドラムを叩くとき、いつも腕時計を外して叩くのが私の癖だった。
学園祭でのロック演奏の本番、ふとまわりを見回すと彼女の姿が目に入った。ここは男子校、女の子の観衆はどうしても目立つ。半年前まで付き合っていた子だったけれど、まさかこの学園祭に来てくれているとは思いもしなかった。ぎこちなく久しぶりの再会の驚きを伝えた後、演奏のために私の腕時計を恐る恐る彼女に預けた。
彼女の方をちらちら伺いながらの演奏はいつもよりオーバアクションになり、ハイハットを叩くテンポも少し速まったような気がした。彼女は爆音の中で静かにロックを聞いていた。あれから何も連絡をしなかった私を責めるかのように・・・。
演奏が終わって彼女から返してもらった腕時計を腕に戻したとき、異様な静寂の中で私の胸の鼓動だけが大きく聞こえた。その腕時計は彼女の体温で随分と生暖かくなっていた。爆音が消えた教室の中で、窓から吹き込んで来た柔らかい微風に彼女の長い髪が音をたてた。一瞬、お互いのわだかまりが解けたかに思えたけれど、腕時計の温もりはすぐに消えた。その微風には金木犀の香りが乗っていた。もう30年前のことになる。
人は、人生の所々を、たった今起きた出来事のように呼び返すことができる。金木犀の香りが漂うとき、彼女の手から腕時計を受け取ったあのときのことが今でもレモン色のストップモーションのまま、私の中によみがえる。
私は大学生になるまで腕時計とは無縁だった。
時間をそれほど細かに気にする必要もせまられなかったし、
いざというときは友達のものを見せてもらっていた。
そんな私が携帯電話よりも大事な存在に腕時計をおいている。それはある春先の出来事がきっかけだった。
高校を卒業して三年、周りも自分も就職活動のまっただなかの季節にいた。久々の男友達との再会に、リクルート用に購入せざるを得なかった腕時計をなにげなくつけていったのもそんな背景があったからだろう。
彼は気さくな性格で、男というよりもむしろ女友達と同じように自然に話せる「いいやつ」だ。喫茶店での珈琲をはさんでのおしゃべりも
いつもどうりにたあいないもので、数時間が流れた。
ところが帰りがけ、彼が私に時間を尋ねたとき「事件」はおこった。
ジャケットの袖の中の腕時計をのぞきこんだのは私ではなく、別の顔、そう彼だった。
突然の出来事は私を数秒かたまらせてそして、顔を紅潮させた、だけではなかった。
その日から彼は「いいやつ」から「気になる人」へとかわり、私は腕時計を大切におもうようになった。今度の待ち合わせはいつだろうか。また彼が時間をたずねる日まで
私のハートといっしょに、時は刻まれてゆくだろう。
親に買ってもらったものの中で、一番印象に残っているのは高校卒業の時の腕時計だ。
商店街老舗の時計屋・大正堂で、一時間以上迷ったあげく私が選んだのは、小遣いではちょっと手が出ないくらいのアナログ時計。金縁の丸顔、白い文字板にローマ数字が並ぶ。
「懐中時計みたいなの選ぶんだねえ」
大正堂の主人は、そう言いながら包んでくれた。
数日後、家の洗面台に似た時計が置いてあるのを発見した。よく見ると全く同じ種類だ。ただ、こちらは少し小型の女性物。なんでこんなものがうちにあるのだろう。顔を洗いながらしばし考える。
持ち主は姉だった。母親の話では、彼氏にもらったペアウォッチなのだという。よりにもよって、時計の趣味が弟と同じ男を彼氏にするとは…。おかしいような、情けないような、どこか複雑な気分。この一件、もちろん姉には内緒だ。
その後、大学での最初の三年間を私はこの時計と過ごした。なぜ三年かというと、四年生になる直前に不覚にも遺くしてしまったからだ。キャンパスからバイト先まであちこち捜して歩いたが、結局見つからずじまい。気に入ってただけにショックが大きかった。その反動か、以後、どうでもいいような安物のデジタルばかりはめている。
時計を買った大正堂も、就職で地元に戻る頃には既に店を畳んでいた。その跡地にはレンタルビデオ屋が建っている。
今では記憶の片隅にすっかり埋もれてしまった、一本の時計。それを思い出すのは、義兄の左腕の金時計を見る時だけである。
許していただきたいことがあります。
高校を出て社会人になったばかりの、三十四年前のことです。初夏の夜、近くの銭湯に行った帰り、車道と歩道の段差のところになにやら光るものが。拾ってみると,小ぶりの時計です。文字盤のガラスは割れて、泥で汚れていました。
家に帰って明かりの下で見ると,SEIKOの文字が目に入りました。言い訳になりますが,このアルファベットをみたとき,落し主に悪いと思う気持より自分のものにしたい気持が勝ってしまったように思います。
翌日、勤め先のデパートに入っていた時計店に持って行きました。拾ったことを悟られるのではないかと、どきどきしました。中を開けて調べていたお店の人から、五百円で修理出来ると言われホッとしたものです。
この五年前農家をやめた父には定収入がありません。父が出稼ぎに出ていた、高一のイブの明け方、母は脳溢血で倒れました。二年後母は,寝たきりになりました。
それでも父は働きに出て、私は高校生。母の面倒を見る人がいないので,札幌で家庭を持っていた姉夫婦が戻って、面倒を見てくれていました。
私の就職が決まっても、通勤に着る服すら用意してもらえません。東京の兄からお金を借りて,二、三枚の服を買いました。とても時計までは・・・つい・・・。
今はお洒落で安い時計が溢れ、私もブレスレット風の安いのを持っています。でも拾った時計はずっと手元にあります。ネジを巻くときのジージーという音が、アナログ人間の私には,職人さんの確かさや気難しさを想像させてくれます。
長い時間を経て、拾った時よりも落した人の胸中を思います。三十四年の間、心の機微も刻んでいてくれたらしい。ずっと大切にしますといって、許してもらうというのは,虫が良すぎるだろうな。
−恋人が出来たらペア・ウォッチをして街を歩いてみたいー
そんな願いが叶って、私はある日、彼とお揃いの腕時計をつけて街を歩いた。
私たちがペア・ウォッチとして選んだのは、その頃に流行っていたダイバーズ・ウォッチだった。彼が選んだのは派手なオレンジ、そして私はブルー。色は違うが、同じデザインの腕時計を左手にはめると、胸のときめきを覚えずにはいられなかった。
好きな人と同じものを身に付けるって、スゴく嬉しい。その腕時計からは、今、彼と同じ時間を過ごしているという一体感を感じることが出来た。そして、私たちはデートのとき、必ずその腕時計をつけていた。
しかし、腕時計の時は流れたまま、私と彼の心の時は止まってしまった。悲しい別れだった。
しかし、時は経ち、私にもようやく新しい恋が始まろうとしていた。
その日、私は新しい恋の予感がする彼と、彼の部屋でお酒を飲んでいた。
私には、酔うと腕時計をはずす癖がある。
私は、前の彼との思い出の腕時計をはずした。そして、すっかり腕時計のことを忘れたまま、その夜、自宅へと帰った。
翌朝、私は腕時計のないことに気付き、彼に電話をした。早速そのひの夕方に腕時計を取りに行った。既に別れた恋人とのペア・ウォッチとはいえ、思い出の腕時計である。心なし足どりが早い。
ところが、彼の家に着いた私に、青ざめた表情をした彼がこういった。
「ごめん。腕時計さ、どこにも見当たらないんだ。もしかしたらなんだけど、何かの拍子で棚から落ちて、このゴミ袋に入ってそのまま・・・。」
その日は、ゴミ収集の日だったという。
私はかなりショックだったが、新しい恋をするのに昔の思い出を引きずった自分に天罰が下ったと思って、静かに深呼吸をした。
「おめでとう。よく頑張ったね。」勤めから帰ってきた長男は手を差し出して握手求め、弟の肩をたたいた。「よくやった。よくやった。」と、感激してる。「うん。受かったよ。」本人以上に喜んでくれた兄に照れながら貰ってきたばかりの写真入の合格証書を見せた。
4つ違いの二男は、推薦入学で大学に入り自分の力を試したことがなかった。「マイペでースで気楽に生きるのが一番さ。」というのは口実で、落ちるのが怖い自信のなさに過ぎない。そんな兄が心配して、経済学部に入ったのなら簿記ぐらい分からないとね。と、一級簿記検定試験の受験を勧めたのだった。受かったら腕時計がご褒美だ。といわれてか、奮起して朝から晩まで電卓をたたいて、発表を待ち構えてた。
日曜日になると、長男は「約束だから奮発するよ。良いのを買いな。」と、二人でデパートへ連れだっていった。帰宅した二男はニコニコ顔して腕時計を私に見せた。幼いときに父親を無くしてた我が家で、長男は父親代わりになった積もりか自分の初任給を喜んで使った。
二男はその腕時計でタイムを計りながら次のステップの資格を目指して答案練習をしてる。長男からの贈り物の腕時計は、二男の人生の道しるべとなった。
赤や青のカクテル光線がくるくる回る光の中を、タキシード姿の新郎と、お色直しで一段とあでやかなドレスに着替えた新婦が入場して、参列者のテーブルのキャンドルに灯をともし始めた。フラッシュの放列がつづき、拍手が湧き、式は最高潮に達していた。やがて、司会者がマイクで言う。「恩師への記念品の贈呈です」。
それは思っても見なかった演出だった。新郎の高校卒業時の担任だった私に対して、感謝を込めて記念品を贈ってくれるのだという。それまで何度か教え子の結婚式に招かれた。そんなときはたいてい祝辞を頼まれたものだ。ところが彼の場合、その依頼の挨拶はなかった。かなり手広くやっている運送会社の息子だから、名士の招待客も多いのだろう。元担任が出る幕はないと思っていたのだが、こんな形で彼は私に彼の気持ちを贈ってくれたのだった。それが、現在も使っているセイコーの腕時計だ。
あれから、もう十年以上経つ。時計はベルトは変わっているが、正確に時を刻みながら、時々、彼のことを思い出させてくれる。学校の批判をしたり、授業をサボったり、そのたびに説教をして、尻をたたいたりしたものだった。でも彼は、それを彼に対する私の親愛の情と受け止めてくれたのだ。だからこそ、大学を終え、家業を継ぎ、結婚というとき
高校時代の担任であった私を思い出してくれたのだと思う。そう思うと
この時計は、単に贈り物というより、私の教師生活のなかで、よくがんばったでしょうという勲章のようなものだったと思う。「この時計、教え子のプレゼントなんだ」。時計が話題に上るとき、私はこの勲章を取りだして一人、悦にいる。定年を迎えた今年、彼のそうした表現がまたうれしく思い出される。
十年前の誕生日に息子がプレゼントしてくれた腕時計を、私はいまも大切にしている。
勤務先の外資企業が日本から撤退し、当時の彼は失業中だったから高価な時計ではない。
それだけに心のこもった贈り物とも言えるが、その腕時計の文字盤は、息子の手術の日に私が凝視した手術室の前の掛時計の記憶を呼び覚ます。息子には軽度の先天異常があり、2歳になるとすぐ全身麻酔の手術を受けねばならなかった。手術の2週間前から妻が付き添って入院させ、私も残業を免除してもらって病院に日参した。
それらの日々の多くの時間を、私は息子の手術が行われるはずの手術室の前で、廊下にいる他の家族に混じり、神仏を念じていた。
すると、手術時間の長短と手術の成功との間に、否定できない関係があることに気付いた。会社の業務と同じく、スムーズに運ぶ時の方が好結果を生む。
手術が予定より早く終り、執刀医が「どうだ、おれの腕は!」というように、肩をそびやかして出てくるときは大成功なのだ。午後2時ジャスト、全身麻酔の息子が手術室に運び込まれた。予定は1時間の手術だ。
私は、ひたすら時計を見つめ、早く終わりますようにと祈り続けた。
そして、思ったより早く手術室のドアが開き、小柄な執刀医が西部劇のガンマンのように颯爽と出て来るのを見たときは、安堵で全身の力が抜けた。
時計の針は2時47分を指していた。あの白い文字盤と長針の動きを、私は終生忘れないであろう。
「オヤジの時計」大森 和哉さんのエッセイ (4月のベストエッセイ)
オヤジの腕時計は傷だらけ。文字盤も陽に焼け茶色く変色していました。
友達のお父さんが革ベルトの薄い時計をしているのを見て、なんて格好いいんだろう、とぼくは自分のオヤジと比べていた。時計を比べ、恥ずかしく感じていたということは、オヤジをそんなふうに考えていたということだったんです。
オヤジは大工でした。毎日、朝早くから日暮れまで一生懸命働いていた人です。汗もかきます、皮のベルトではすぐにボロボロになるのでした。それは今だから分かることで、当時のぼくはそんなことは考えず、オヤジの傷だらけの時計を見ては自分の境遇を少しだけ悲観したものです。サラリーマンという響きに憧れ、そうじゃないオヤジを認めようとはしていなかったのです。
風呂に入るとオヤジの陽に焼けた身体に白い線がクッキリ浮かんでいます。時計をしていた跡です。そこだけ真っ白なんです。それが悲しくて、ぼくは目を背けたものでした。 背広を着てくれよ。皮ベルトの時計をしてくれよ。声には出せなかったけれど、ぼくはいつも心の中で呟いていました。今、ぼくは教師をしています。憧れていたスーツを着て仕事をしています。大学を出て採用が決まった時にオヤジがぼくにプレゼントを買ってやろうと言いいました。ぼくは時計をくれと言いました。その時計がぼくの腕に光っています。オヤジがしていた傷だらけの時計です。
時計をはめると暖かさに包まれます。感謝の気持ちなんて言うと大げさですが、頑張らなければ、という気持ちになります。
子どもを持ち、働くようになりぼくはオヤジの時計の意味を知るようになりました。月に五分は遅れる時計ですが、いつもぼくを奮起させてくれる時計です。
いつかは娘の彼氏に手渡そうと思います。
亡くなった明治生まれの父はとても物を大切にする人だった。とりわけ勤続30年の記念にもらった腕時計は宝物のように大切にしていた。その扱いようといえば毎朝きれいな布で腕時計をきれいに磨き、朝7時のラジオの時報で時間を合わせ、年に1度は近くの時計屋に分解掃除に出すという念の入れようだった。几帳面な父はまた腕時計の置き場所までキャビネットの上の中央と決め、はずした時は必ずその場所へ置いていた。私たち4人の子供は遠巻きに父の腕時計を見ることはあっても決して手にとって触るようなことはなかった。なぜならそれは父の一番大切にしている物であることを毎日の父の扱いで見ていたからである。その後、私たち子供もみんな成長して実家を離れ、父も定年退職して母と2人暮らしとなり、趣味の園芸三昧の生活を楽しみながらも肝硬変を患い67歳の生涯を閉じた。父の亡くなった病院から付き添って実家へ戻った時例のキャビネットのいつもの場所に父の腕時計が置かれてあった。子供の頃を思い出し懐かしい気持でそれを眺めていると生涯愛用した父の人柄が偲ばれ涙が出そうになった。
昭和30年、高校3年の私は、初めての腕時計をして、修学旅行で東京に出かけた。自由時間のために、母が駐在所の奥さんに頼んで、古い腕時計を貰ってきてくれたのである。
赤いビニールのバンドのついた腕時計を、私は何日も枕元に置いて寝た。夜のしじまの中で、時を刻む音が私をどんなに幸せにしたことだろう!時計を持てたということの他に、自由時間にボーイフレンドに会う約束が私を有頂天にしていたのだった。
中学校の頃、文芸部で一緒だった彼は、東京の高校に進学した。彼は向学心に燃える少年だったし、私はそういう彼に強い憧れを抱いていた。私たちはトルストイの人生やルソーの教育論について、文通で熱っぽく語ったものだった。
自由時間、私たちは丘の上(どこだったか思い出せないが)に座って、東京の街を眺めた。
「5時にはホテルに戻らなければ」
と言いながら、私は自分の時計をちらと見た。誇らしいような、恥ずかしいような気持ちだった。
古い時計はしばらくして動かなくなってしまった。私は大学を卒業し、中学校の教員になって、同僚と結婚した。
幼い頃はよくオモチャのデジタル時計を景品などでたくさんの『時計もどき』を私は持っていました。その『時計もどき』は時間合わせが大変で父でさえ取り扱えなかったものばかり。
小学6年生に私がなろうとしていた時、父母は離婚しました。私は元元、母方で暮らすことが決まっていたかのような以前と何ら変わらぬ暮らしを営んでいました。ある日、父は私を誘ってくれ、車で数十分のところまで遅くなってしまった誕生日祝いにと時計を買いに連れ出してくれました。
幼いながらも水泳、進学塾、ピアノ教室などと忙しい日々を過ごしていた最中のことでありました。
「デジタルの方がいいんじゃないか」という父の意見を気にせず私は秒針をチクタクと刻んでいく時計が新鮮に感じられ「こっちの方がいい。」と言って最新型の約2万円もするものを指差したのを今でも鮮明に覚えています。
その私が指差した時計が手元まで来た時、恥ずかしがり屋な私の言った言葉を聞いて父がさりげなく微笑んでいた思い出が印象的だった魔法のかかった数時間。
「お父さん・・・・ありがとう。大事にするからね。」何度人にほめられたか分からない時計。男女、年齢に関係なく使える私の自慢の時計。私の感情を読み取るかのように遅くなったり早くすすんだりする時計。今でも私の目の前でチクタクとまたとない時間を示してくれています。
初めて自分で腕時計を買ったのは、高校の入学祝をもらった時だ。私は一目でブレスレット型の腕時計を気に入り、高校3年間それで過ごした。それから、ポケベルがはやり、今はケータイ電話。腕時計の必要性が私の中でなくなりつつある。
そんな時、好きな人が出来た。毎晩電話で言葉を交わし、休みの日には遊びに行く間柄に進展していった。バレンタインの時に、手作りのチョコを渡した。彼はとても喜んでくれた。ホワイトディのその日、彼はグアムにいた。会社の旅行でい方ない。
私は、ふてくされながら我慢した。
声の聞けない三日間と半日。もちろん連絡もない。あれだけ、毎日の電話に『今日くらい』と思っていた気持ちが、薄れていく。時間が経つほどに気持ちが彼でいっぱいになる。……なんだかとても可笑しな気分。
「イマカエッタヨ」のメッセージに心が飛び出した。声が聞きたかった。会いたかった。飛行機が落ちた時は許してねと言われていた気持ちが穏やかになった瞬間、受話器から彼の声が聞こえた。
「空が真っ青でね。ドライブがとても気持ちよかったよ」と言う彼に私は会う約束を取り付けた。
天気の良い日に会った。車の中で私は彼に抱きついた。彼は私の頭をなでる。私はそれだけで嬉しいくて、触れられているだけで夢心地。そんな私に、彼から小さな箱が渡された。中には、鮮やかな青色のベルトの腕時計があった。
それは、それは鮮やかな青色。
彼は笑って私の腕にはめてくれた。そして「いつか一緒に行こうね。とても綺麗な空だったんだよ」と白い歯を見せた。
その約束は果たされることはなくなったけれど…… 鮮やかな青色のベルトはすっかりくすんでいまったけれど……
彼からの初めてのプレゼントは、いつまでもまっさらなまま、心の中に残っています。
私の父は昭和一桁生まれの頑固一徹。仕事一筋、家族で遊びに行った記憶どころか、買い物に行った記憶もない。亭主関白は極まりなく、子供の頃「父」というとただ、恐いだけの存在だった。今の私の主人のように、母の子育てに協力したことなんて一度もないだろう。そんな父に私はとっつきにくく話す事もあまりしなかった。
そんな父でも、私が小学6年生の頃冬のボ―ナスで母に腕時計を買ってきたことがある。母は、今もその腕時計のことを話すたびに「結婚して初めておとうちゃんが買ってきてくれやはった物」とその当時の苦労話を一緒に語ってくれる。7人兄弟の一番上のお父ちゃんの給料はまだ結婚していない兄弟のためにほとんど使っていたこと。たくさんの親戚づきあい。私たち子供に、満足なことがしてやれなかったと。そしてこの腕時計を買ってきてくれた頃、やっとちょっと家に余裕ができてきたこと・・・。
深い緑色をしたその腕時計は、幸せものだ。買ってはなくす私の腕時計と違って・・・。母と父の二人の歴史を背負いながら大切に大切に使われている。そして、母はきっとあの時計のおかげで今日の日を迎えられているのかもしれない。
そして、父はこの前10万円もする腕時計を自分のために買ったと嬉しそうに、私たちに見せてくれた。
遠距離恋愛の彼の腕時計は、あまり見かけないシルバーの凝ったデザインの物でした。私は「素敵ね」となんとなく言ったら彼は色んな所を探して私にプレゼントしてくれた。彼は私と出逢う数年前に購入したらしくなかなか売っていなかった。やっと見つけてくれたその腕時計はペアのセット売りだったのですが彼は こっそり買ってくれていた。ですから彼は今 同じ腕時計を2つ持っている。とても申し訳ない気持ちでいっぱいでした。
久しぶりに逢った日にプレゼント包装を開ける時の何とも言えない気持ちは今でも忘れられない。
毎日お互いの腕で同じ時を刻んでいるこのペアウォッチは時を追いかけることなく いつまでも同じ道を歩いて行こうという想いの“かたまり”のように感じています。
遠距離恋愛の私達にとっては、1000文字のメールよりも1秒の声が欲しい。そんな時を日々送りながら距離と時間が重なり合うことを夢見て秒針のようにカチカチと確実に音を刻んでゆく彼と私でありたいと思う。いつか同じ場所で同じ時を普通に過ごしたい。
腕時計を外しても2つ同じ場所に並べることができる日、そんな日のことを想いながら今は1つを机に置く。置けばその腕時計の裏に2人で撮ったプリクラが貼ってある。彼がプレゼントしてくれた日に2人で貼ったのです。彼も腕時計を外した時このプリクラを見ているに違いない。
その時だけは腕時計の裏がめいっぱい主役になるのです。
腕時計の裏のプリクラをじっと見つめて私はいつも気がつけば体育座りで膝をかかえている。
私には彼にこんな素敵なプレゼントは できないけれど今こうしてこの文章を書いていること、彼が見てくれたなら腕時計のお返しのプレゼントになるのではないだろうかとキーボードをいつになく熱い想いで打っています。
あれから何年経っただろう? いまも動いている不思議な時計。
オートマチックという時計を記憶している人は少なくなったでしょう。
いまから32年程前、当時三歳になった息子が、父から初めて買ってもらった腕時計。
当時は、画期的な時計と流行ったものです。息子が時間がわかるようになったと、喜んだ私の父がプレゼントした物です。
いま思うと、なんと大きく、さぞかし重かったでしょう。それでも、初めて腕にしたオートマチック時計を、毎日誇らしげに走り回っていました。
一度ゼンマイを巻くと、あとは腕を動かしているだけで、自動的にゼンマイが巻かれ、狂うことも止まることもありませんでした。
高校一年まで、スマートで細かった息子の腕で、時を刻んでいたものです。
私も、同時期にオートマチックの時計を購入し、重宝していました。
しかし新しい物が出回ると、なぜかそちらに目移りしてしまうもので、愛着していたオートマチック時計は、いま静かに時計入れの中で眠っています。
それでもこの時計が好きな私は、時々ネジを巻いて動かしてみます。
不思議なことに、いまも狂うことなく時を刻みます。
長年息子が愛用して傷だらけのガラス。いまは亡き父親。無数のガラス傷を眺めていると、息子の成長と、時の流れを感じさせられます。
この不思議な時計は、これからも大切にしていきたいと思います。私の年輪とともに……。
「あ・・・」ピンクのリボンを解き箱を開けた瞬間、思わず顔を硬くした。高校入学した年の誕生日。母が腕時計を買ってくれたのだった。高校には教室ごとに時計が置いているわけではないので、自分の時計が欲しいとは思っていた。スポーティーで可愛い、真っ白な時計が。だが、母の買ってくれた時計は銀色で事務的な、何の色気もない代物だったのだ。(私に選ばせてくれればよかったのに・・・)と内心腹が立ったが、贈り物にけちをつけるわけにもいかない。そして次の日から彼との学校生活が始まったのだ。友達が見つけて「可愛いね」と言う。だけど素直に喜べない。こんな時計をしていることが段々と恥ずかしくなってきて、隠して見るようになった。いっそ無くなってしまえば・・・。そうやって時計ショップを除く日々が続いた。
そして秋。待ちに待った体育会。半袖・ハーフパンツで気合を入れる。もちろん、邪魔な時計は外しておいた。その日は練習の成果が発揮され、絶好調だった。全体としても大いに盛り上がり、閉会式を迎えたのだった。お互いの健闘を称え合いながら帰ろうとした時、何か足りない存在に気付いた。・・・時計!!慌てて見回したが、無い。荷物を探っても、無い・・・。頭が真っ白になった。あちこちを引っくり返し、しまいには這いつくばって探した。可愛くない時計、銀色の時計・・・。汗と泥だらけになりながら、一緒にマラソン練習をしたかれとの思い出が胸をよぎった。何度も何度も2人でタイムに挑戦した。「いっそ無くなってしまえば」なんて・・・。ごめんねごめんね・・・。そうしているうちに溝にはまった彼を見つけた。もう二度と離さない。そう誓った。
それから3年。大学生になった私は母とも離れ、慌ただしい毎日を送っている。今日は1時限目から授業。時計をはめて気合を入れる。・・・銀色の朝。
腕時計をはめたのはいつの頃だろうか。多分高校に入学した時に父親に買ってもらった時だと思う。もう40年も前になる。
その時計というのは、町の時計屋の店先で、腕を振っている若者の立て看板があって、以前のねじ巻き式から自動巻きになったことが画期的というものだった。15歳の私でも斬新な時計に思え、高校の入学に父親にねだった。今にして思えば、貧乏人の子沢山の中でよくぞ長男の私に腕時計を買えたものと、目の前にいる老いた父親を見ると感慨無量になる。その腕時計をはめて看板の腕のように勢いよく腕を振っていたのを微かな記憶として蘇える。
その自動巻き腕時計をどのくらい使用していたか記憶がない。その後に買った記憶がないので長い間使っていたのだろう。
20歳の頃、初めてのデートを渋谷のはち公前で待ち合わせをした。
相手は高校の時の同級生。その場所で約束した時間の長針が12時を指しても彼女がこない。必ず来るものと信じて待てど、時間だけが確実に過ぎていく。自動巻き腕時計が止まってはならないと、腕を振り振り待ったに違いない。場所を離れれば、行き違いになるのを恐れて動けず、じっと待っていた。とうとう2時間を過ぎても彼女は現れなかった。
諦めのつく時間が2時間だった。その時間は過ぎて戻らず甘美さをまぶした、若き日の思い出である。
私の友達にはずっと腕時計を着けている子がいます。
その時計は紺色のベルトに、盤面には夜空のイラストが可愛くあしらってあります。
その時計を見れば、今の時間だけでなく、今日の月の満ち欠けの様子を知ることができました。
とってもお洒落な感じで、私はその時計をとても羨ましく思っています。私は、腕時計というものを今だ買い与えてもらったことがないのです。
今の時代、はっきり言って腕時計がなくても、携帯電話を見ればデジタルで時間がすぐ分かり便利なものです。
だけどあのレトロ感・古風なアクセサリーという私のイメージは、まだそれを持たない私にとても憧れを抱かせました。
それになんといっても、私は腕時計を身に付けたときのあの感覚が好きです。
時間を身に付けていて、触れている肌さえも時を感じ、同じ鼓動を刻む・・・そう考えるととても素敵なことじゃありませんか?友達の月の時計は、ベルトが剥げてきて少し衰えてきました。
それでも友達は時計を変えようとしません。その自分だけのアクセサリーを愛しているからでしょう。
ずっと着けていれば自然に愛着が湧くものだとも予想がつきます。今度、お小遣いが溜まったら是非、腕時計を購入したいと思います。
自分だけのアクセサリーを持って、刻まれる時間を常に身に付けたい願いを叶えたいのです・・・。
時計と言えば、昔からスイス。超高級腕時計や若者に人気のスウォッチなどが有名ですね。私の知識もこの程度だったのですが、最近次々と分かってきた事がありますので、お伝えしましょう。
フランス人なんですって、時計製造の元祖は。フランスのビューコートという村で一七四九年に生まれたフレデリック・ジャピーという人。彼は、一七七七年に時計製造機械によるはじめての時計製造工場を始めました。職人的な時計作りから、製造機械による時計作りに変革。そのために、次々と時計製造用機械を考案し、これら機械が隣国スイスでまず作られるようになったのが、スイスといえば時計となる原因だったという事です。
彼は一八一二年に亡くなりましたが、息子や孫たちは時計製造の知識を発展させ、ポンプ、農業機械、エンジン、カメラ、タイプライター等を製造する工場を次々と建設しました。そして二十世紀初頭には、六千人の従業員を擁する企業になったそうです。さて、これだけでは、ただの外国の成功物語で終わってしまうのですが、あるんです日本との関係が、次々と。
一九三六年(昭和十一年)パリ-東京間を百時間で飛行するという懸賞飛行の途中、今一歩のところで佐賀県の背振の山に墜落してしまったフランス人がいました。彼は、自動車会社プジョーの大株主にして技術者。墜落を知った村人は、濃霧の中から彼を助け、手厚く介護したそうです。そのおかげで彼は翌年には帰国することができました。もうお気づきと思いますが、彼の名前はアンドレ・****ジャピー。さてさて、これだけではただの飛行機事故で終わってしまいますが、まだまだお話は続きます。
日本人誰もが知っている飛行機「神風」との深い関係。そして、戻ってきたジャピーブランドの腕時計。私のプライバシーとの深い関係については、お尋ねがあればいずれまた・・・。 はい。
彼女は、二代目の時計だった。
高校入学祝いに貰った、少し大人びて小さい腕時計。
文字盤が1から12までを刻んでいるのではなく、金色の針が控えめに時を暗示してくれるのが15歳のプライドを充たしてくれた。いつもいつも。
その時計は私と一緒だった。
出かける時も、帰る時も、いつも一緒。それがいなくなったのは、5年後の夏。
15歳のプライドはすくすくと成長して、20歳のプライドに取って代わった頃。
彼女は電車の中で不意に姿を消して、私を戸惑わせた。金色だった枠は、もう傷だらけ。
ぴかぴかだった文字盤を覆うガラスには、小さく欠けていた。
新しい時計たちにその地位を追われかけていた彼女。遺失物届けを出してから数ヶ月、彼女が見つかったという報せが届いた。
彼女に会うために電車を乗り継いで行ってみると、彼女はもっと傷だらけになって、それでもやっぱり可憐な姿で、透明のビニール袋に入れられていた。それから数年。
彼女はまだ美しい姿で、私の腕にいる。
何度かパーツを替えたけれど、彼女は控えめに今も時を刻んでいる。
母が死ぬ日。
その日担当のM先生は,当番ではなかったけれど母の最期を看取るために病室に来て下さった。
「今日…だね」
神妙な面持ちで先生はつぶやいた。
先生の言葉どおり,母の呼吸はだんだんと弱くなっていき,やがて止まった。
病室に慌しく心電図が持ち込まれ,スイッチをつけるともう,母の最期の時は間近だった。
ロビーで待っていた親類たちを呼び,病室に戻るとすでに先生は右手で母の手首を握っていた。
先生は左腕の腕時計を見つめ,
「11時44分です。残念ですが…」
悲しみに襲われ,その後いつ先生が退室したかわからなかった。
落ち着いてから病室を片付け,荷物を持って廊下に出ると,スーツに着替えた先生が腕時計を見ながら小走りに病院を出て行く後姿を見付けてしまった。
あの時は気が付かなかったけれど。
先生の腕時計は,こうやって毎日のように様々な人間の人生の終わりの時を刻んでいるのだ。
もし腕時計に心があったなら,先生の時計は自分に定められた運命を恨んで,毎日泣いているだろうに。
時計は,持ち主の行動を刻んでいるのだ。
母を失った悲しみを乗り越え,私の腕時計は幸せな時をたくさん刻めるよう,楽しい毎日を過ごしていこうと,感じた。
「青い腕時計」木村 葉子さんのエッセイ (4月のベストエッセイ)
幼稚園の頃、父のあぐらの中が私の指定席だった。それほどふとった子供でもなかったけれど、父は私を「おりこうさんの子豚ちゃん」と呼び、時折左手首に万年筆で腕時計の絵を描いてくれた。時計の針を何時にするかがいつも問題だった。この前は夕ご飯の時間だったから、今日はおやつの時間ねと、少しずつ時計の読み方と時間の観念を覚えていったような気がする。おもちゃの腕時計もまだ見かけなかった時代だ。誰も持っていない腕時計がついた腕を友達に見せたくて、少しでも長持ちするようお風呂でなるべくこすらないようにしていた。
第一志望の高校に合格した時、制服やかばんは母と揃えたのに、なぜか腕時計は父と買いに行った。デパートをのぞいた後、商店街で2軒ほど時計店を回ってもなかなか決められなかった。せっかく喜ばせようとしてくれている父の勧める時計が今ひとつ違う気がして、私は焦った。白い文字盤にくっきりと浮き出たアラビア数字、茶色の革ベルトのものが父の好みだった。真面目で、几帳面な父そのままのような時計。「うーん。」と首をひねる私を見て、時計屋さんはもっと華奢なおしゃれな雰囲気のものを出してくれた。父は「少し大人っぽ過ぎやしないかね。」と言いながらも、「まあ、自分が毎日身につけるものだから好きなものを選びなさい。」と折れた。
結局、私が選んだ時計は、シルバーのつや消しのベルトに薄いブルーグレイの文字盤だった。帰り道、「文字盤に色がついていたら見にくいんじゃないかな。」と言っていた父は、きっと忘れていたのだろう。
あの文字盤の色はにじんだ青いインクの色、あれは、私の初めての腕時計、おとうさんの万年筆の時計だったんだよ。
人は各々ふとしたことから、封印された過去を振り返ることがある。私の場合は今、手元にある日焼けしたオメガの腕時計に、再会した時こそが少年時代の記憶を取り戻すきっかけとなった。
まだ日本が大掛かりな変貌を遂げる前の昭和40年代前半。その頃、中学生となった私は、何処にでもいる平凡な少年であった。が、一つだけ皆に誇れるもの、それがこのオメガの腕時計であった。とりたてて裕福な家ではなく、当時の平均的なサラリーマン家庭に育った自分が、身分不相応にもヨーロッパ出張に出かける父に「中学入学祝いに買ってよ。」と懇願してみた。駄目は承知で頼んだのだが、1ヶ月後に帰国した父が誇らしげな顔をして鞄から真っ先に出したのがキュービック型の頑強なケースに守られたこの時計であった。当時、特に小柄だった私にはバンドの駒詰めが足りず随分と長い間、腕からすり抜けてしまいそうな状態で使い続けた。自慢のこの時計は、それから数回の修理を経て私の時間を刻み続けてくれた。「買った時よりよっぽど金かかってるな。子供が喜ぶと店員に言われて買った安もんだったよ。」と打ち明けてくれた父であったが、クオーツ最盛期になっても私の私の道しるべとなっていた。しかし2回目のゼンマイが切れた後、当時の箱に詰めて保管した筈のそれの所在が、不明となってしまったのに気がついたのは、随分と年月を経てからのことであった。
それから20年。街の骨董市で無造作に並んでいたそれは、あの懐かしい昭和の時間を私に運んできてくれたのである。オレンジ針のストップウォッチのついたそれは、お世辞にも21世紀に求められる正確な時を刻んではくれない。しかし私にとってはせわしかい日常を忘れさせてくれる、そして少年期の風を届けてくれるかけがえのないた宝物なのである。
さりげなく、細心の注意をはらってさりげなく、孝司はポケットから黄色い盤面の時計を取り出した。
「これ、見舞い」その時計を私は知っている。背骨を折った孝司はずっと病院のベッドで寝たままだった。浴衣を着ていて髭も髪ものびていたけれど、彼の腕時計と枕元の私は、彼がお洒落だったことを知っていた。孝司は毎週私が行くたびにベッドに横たわったまま時計を見て、「とまってないよな、俺の時計」と言っていた。その腕がだんだん細くなるのを気に病んでいた。
お見舞いにそれを貰って腕につける時、震えるような気がした。辛い時間を思い出した。でも、ただ寄り添っていることしかできなかった気持ちは通じていて、時計はその証拠として存在していた。
私は心の病だったから、悩んで自殺を考えたこともあった。最後に時計をはずすイメージが浮かんだ。でもいつも、現実に自分の腕についている時計の重みが私を世の中に結びつけ、ひっぱり、つなぎ止めてくれた。
私は眠るときも時計を外さなかった。眠ったまま私がふらふらとどっかに行ってしまわないように、船の錨のように時計を意識して眠った。今も私の腕についている。煙草を吸うとき、時計は私の赤いシャツの袖からこれみよがしに黄色い顔をのぞかせる。もしも、何かで失うようなことがあったら私は手にけがをしたように痛みを感じるだろう。
4年前、大学を出て初めて社会人となる僕に、5つ年上の姉が就職祝いとして腕時計を買ってくれた。一緒にデパートへ出かけてなかなか気に入るものが見つからなくても根気よく付き合ってくれたお姉ちゃん。僕が実家を出て、一人暮らしを始めてから、お盆とお正月にしか顔を合わせることがなかったお姉ちゃん。
今でも大事に使ってるんだよ。去年、革のバンドが切れたとき、お店に行って修理を頼んだら、「もうパーツがない」って言われた瞬間、何かものすごく大事なものを失ったような気がしたんだ。でも別のお店の親切なおばちゃんが在庫を捜してくれて、もと通りの青いバンドが付いて戻ってきたとき、本当にうれしかった。腕にはめたら、何だか温かくて、そして身が引き締まる思いがしたのはなぜなのか。今なら分かるよ。
大学時代、自分一人で生活出来ているわけでもないのに実家のこと、家族のこと、殆ど気にもせず好き勝手やってきた僕。社会に出て、今身に染みるのは今まで支えてくれた暖かい家族の存在です。お姉ちゃんのくれた時計はちゃんとそれを教えてくれました。
今は結婚してアメリカに行ってしまったお姉ちゃん。もらった時計、毎日はめてるよ。日本に帰ってきたらまた会おうね。渡せなかった結婚祝い、渡すから。
僕が高校2年生の時、斜め前に座っていた髪の長い彼女に恋をした。とにかく彼女の事が気になって気になって仕方がなかった。
今思うとそれが初恋だったんだろう。まだ、恋に純情だったあの頃、彼女に告白する勇気がない自分がいた。
人づてに彼女の欲しい物が時計だと聞いた。僕はその日から、デパートに行けば時計屋さんに走っていき、彼女に似合いそうな腕時計を探した。目覚まし時計も可愛かったし掛け時計も素敵だった。
でも僕は腕時計をプレゼントしようと心に決めた。
気に入ってもらえるかどうかなんてお構いなしだった。若気の至りだったって事かな。今思うと笑い話になってしまうが、確かミッキーマウスとミニーちゃんの絵柄の腕時計だった。
彼女の誕生日に机の中に無造作に入れた腕時計。僕からのプレゼントだとわかった彼女は次の日、授業中に後を振り向いて笑ってくれたっけ。そして、左手にはプレゼントの腕時計をはめてくれてた。うれしかったなあ。
あれから10年、お互いに家庭を持ち、体格の良い父親としっかり者の母親になった2人だが、初恋の時を刻んだ思い出は今も心に残っている。
朝7時32分、家を飛び出す。一つ目の信号、ここで7時35分なら電車に間に合う。ちらっと銀色の腕時計に目をやる・・・ないっ忘れた!一体今何分?!一目散に走る。
駅に到着。改札口頭上の時計は7時39分。いつもより1分早い。
8時25分、職場の最寄り駅に到着。職場までの坂を登りきったところでいつもなら8時29分。鞄から携帯電話を取り出し時刻を確認。8時45分。えっっ。そこでいつも会うおばさんとすれ違う。あーびっくりした。この携帯、時刻が進んでいたんだ。
職場に到着。タイムカードの時計は8時34分。またいつもより1分早い。
本日のお仕事終了。いつもより少し遅れて職場を出る。坂を下りながら時刻を確認。19時33分。電車の発車時刻だがこの携帯電話、時刻が進んでいるから大丈夫。安心して歩く速度をゆるめる。駅に到着した瞬間カンカンカンカンと遮断機の音。いかん、のんびりし過ぎた。
19時50分、乗り換え駅に到着。次に乗る電車の入線まで約10分。停車中のこの電車内で目を閉じ音楽を聴く。この曲は何分間だっただろうか。そろそろ行こう。
乗り換えのホームに降り立つ。電車はまだ来ていない。しまった、早かった。
20時15分、自宅の最寄り駅に到着。時間を気にせずゆっくり歩く。
20時30分、帰宅。いつもと同じ。洗面所へ直行。あった、私の時計が・・・。銀色の腕時計よ、君は今日1日、ここで一体誰に時間を教えていたんだい?
翌朝7時32分、家を飛び出す。一つ目の信号、7時35分。ここから一目散に走れば7時39分に駅に着くはず。
駅に到着、7時40分。いつもと同じ。
銀色の腕時計よ、今日も1日、よろしく頼んだよ。
念願のメキシコ旅行を実現する際、文字盤が2つついている腕時計を購入した。上の大きい方の文字盤を日本時間に、下の小さな方をメキシコ時間にあわせて出発。両国の時差は15時間だ。
現地ではどこまでも続くジャングルをバスでひた走るとき、あるいは灼熱の太陽の下、遺跡を歩き回って木陰でひと休みするとき、ふとした合い間に時計に目をやり、両国の時間を見比べ遠い祖国に思いをはせた。国際電話をかけるときはとても重宝した。そして新しい時計が一層たよりになったのが9月11日、あの世界的大惨事が起きてからだ。
事件が起きたのが帰りの飛行機に出発する約1時間前、現地時間午前9時。搭乗口で出発を待つが、いつまで経ってもゲートが開かない。大勢の人波にもまれてテレビを見ると、ニューヨークのあの有名な高層ビルが倒壊し、煙をはいている姿が映し出されていた。
わたしはすぐさま公衆電話にかけつけ、自宅に帰国が延びることを知らせた。日本だとそろそろ日付が変わる時間。妻はすでに床に就いていてまだ事件の発生を知らず、驚愕した。勤め先には待機していたホテルの部屋から何度も電話をかけたが、外線が混んでいてなかなかつながらない。深夜3時にかけ直したらやっとつながった。日本はちょうどビジネスアワーの午前11時。両国の時間がひと目でわかる時計のおかげでこれら一連の行動は比較的スムーズにいった。
あとはなす術もなく、昼間はフライト再開の知らせを待ちながら気晴らしに散歩をするくらい。事件発生後はイライラしていたが、ときどき2国の時間を見比べ、今ごろみんな一杯やっている時間だななどとのん気に考えられるようになった。
現地待機の3日間、これが文字盤ひとつだけの時計だったら時間の経過だけを意識させられてイライラがもっとつのったことだろう。ふたつの顔を持つ時計は利便性だけでなく、気持ちにゆとりをあたえてくれる友人のような存在となってくれた。
「いや、時代物ですね。そろそろ新しいのと替えられたら如何ですか。お安くなっていますよ。」
電池を換えて半年、腕にはめようとして手元が狂って床に落とし、動かなくなって時計屋に出した時の店主の言葉である。
実はこの時計、妻が結婚前に贈ってくれた曰くづきの時計である。この十月で40年になる。確かに今では常識のパラショックとか、ウオーターレジスタントなどの機能も無い。当時は超薄型で流行の先端だったが、今はバンドの金メッキの金具も色あせ、見るからに時代を重ねてきた感は否めない。
しかし、時を刻ませたらぴか一だ。今までに調整してもらった記憶がない。電池交換時に時刻を合わせてもらうが、その電池がなくならない限り、的確に時を刻んでくれるのだ。
後で知ったことだが、この腕時計の購入に当たって、妻は三か月分の給料をはたいたようだ。誕生日に私が贈った指輪はその半額以下だった。
そんな引け目があるわけではないが、毎日、腕にはめていると、妙に落ち着いてくるのだ。この地方の方言で言うと、あずましい感じがしてくるのだ。
「そう言えば、前に電池交換したときも同じ事を言われな。」
「どうぞ。ただ、私はこの指輪をあの世まではめていくつもりよ。」
そう言って、妻は「どうするの?」と言わんばかりに茶目っ気な目で私を窺った。
「買い替えるわけないいだろう。本当に正確な機械だもの。国産品って、やっぱり安心できるよ。」
「でしょう?」
妻が満足気に言った。
私がはじめて腕時計というものを持ったのは、小4、10歳の十月だった。祖父が早すぎるお年玉としてくれたのだ。
あとから考えると「おじいちゃん早すぎ!」と思ったが、綺麗な細長の箱に魅了され、また普段は100円、200円にもうるさいドけちの祖父がこんな高いものを買ってくれるなんてと感激し、ありがとうとしか言いようがなかった。
黒い革ベルトで、秒針はミッキー・マウスが回転していた。どの服にも合わせやすいので、すぐにそれは私の生活必需品になった。小学校を卒業した、忘れもせぬ3月25日午前六時。祖父が病院で死の床についたとの知らせがあった。
祖父が亡くなった数日間は、忙しくて時計のことを忘れていた。
ようやく一段落ついて、さあ時計の活躍どきだと思ったら、ミッキーが逆さになっていた。時計は止まっていたのだ。私は一瞬「怖っ。じいちゃんの死と同時にとまったんやないか」とホラーマンガのようなことを考えた。
しかしさらに驚くのは、それをもって時計屋さんに行って電池交換した翌日である。電池交換から一日しかたっていないのに、ミッキーの腕時計は5時20分を指して止まっていた。
今まで幾度となく、水にぬらしたり落っことしたりしても止まったことなんかなかった時計が。ミッキーの腕時計。それは祖父の寿命を示していたのでは・・・。
その動かなくなった時計は、今でも綺麗な細長の箱と、未開封の説明書に保護され私の部屋で眠っている。私が、祖父からそれを手渡されたときの記憶を抱いて。
私の実家は雪深い新潟県にある。中でも豪雪地帯の方なので1月、2月になると、玄関はすっぽり雪で埋まり、二階の納屋からうちに入ることになる。
屋号「庄屋」の名にふさわしく古く大きな木造の家には、囲炉裏端に大きな柱時計が掛かっている。私が生まれ、物心ついたときにはこの鐘の音を聞いていた。一時間毎に、三時なら三回、十二時なら十二回、また、三十分毎に一回の鐘が鳴る。大きな家の古い柱に低く、低く響く音。
父が戦争に行く前、帰ってきた後にもこの時計は鐘と共に時を刻み続けたと言う。その父にしかられたとき、私はよく囲炉裏端の掘りごたつの中に隠れた。夏は練炭も消えているので中毒になる心配も無い。ただじっと父の怒りが治まるまで待ち続けた。三十分ごとに鐘が鳴る。鳴るたびにいつ出よう、もう少しだけ、と、また待ち続けた。
夕食時の時間になる。「もうそろそろ出なければ兄弟達がここに集まり、皆でここに足を突っ込んでくる。父の怒りは治まっただろうか?」そんなことを考えながら恐る恐る掘りごたつから出る。父も畑から戻ってきた。「ごめんなさい」頭をうなだれ謝ったのを覚えている。「手ぇ、洗ってこいや、真っ黒だぞ。」無表情で言う父。
私は囲炉裏端のあの場所で何時間、そして何回、拗ねていたのだろうか。父も柱時計もそんなことお見通しだったに違いない。柱時計の鐘は私に「もう出てきなさい」そういっていたような気がする。今なおその柱時計は健在である。
1994年8月の太陽が燦々と照りつける蒸し暑い日、海好きの彼と私は、この日も茨城の海へ海水浴に行き、その帰り道の出来事です。
火照っている身体に車の冷房を直に当て、日焼けの背中は痛くてシートにもたれることも出来ず、ただ「イタイ、イタイ・・・」と、独り言のように呟いていました。彼は「うるさいなー」と言いながら、私の背中を意地悪してポンポンと叩きます。私の言葉はいつものように左耳から右耳へと流されてしまいました。
この日は私の21歳の誕生日でした。「覚えているのかな?」と思いつつも、会ってくれていることだけで嬉しかったので、自分からそのことには一切触れませんでした。それにしても、いくら口数の少ない人でも「覚えていれば“おめでとう”の一言もくらいあってもいいのに。」そう思うと、だんだん腹が立ってきました。
私が急に黙り込んだのを知ってか、運転しながら助手席の前にあるボックスの中からなにやらごそごそと探しています。CD出して音楽聴こうとしてるんだ。もう、静かなのが嫌なら自分がしゃべればいいのに。勝手な想像はどんどん膨らんでゆき、私は窓の外を見て「ハァ〜」とため息をつきました。
ふと前を向くと、彼は黙って私に小さな箱を差し出しています。「エッ?」と思うと中には腕時計が。「覚えててくれたんだ!」と言う私に、彼は笑って「当ったり前じゃないか!」と、今度は私の頭をポンポンと叩きます。「ありがと」。私はその後、彼の腕時計をはずし、一秒の狂いも無く彼のものと合わせました。今なお、彼と同じ時間を刻み付けています。
パルテノン神殿。アクロポリスの丘を登って入り口を入ると、神殿までは蚊なりの傾斜だった。しかも真夏の地中海の太陽が白い大理石にはじけとんで、とにかく暑かった。神殿の裏にある美術館に寄って涼んでいると、守衛の男がしきりにわたしを見ていた。そのうちに「さくらさくら弥生の空にーー」と口笛を吹いた。それによってわたしが日本人かどうかを試そうとするようだった。わたしは親指を立てて守衛の男に合図したが、わたしはギリシャ語を知らなかった。知っているのはドラクマというお金の単位だけだった。仕方がないから「さくらさくら」を声を出して歌って見せた。すると守衛の男はわたしの近くに来て、太い毛むくじゃらの腕を出して、そこにはめられている金属バンドの時計を見せて、いかにも自慢げに「クオーツ、クオーツ」と言い、親指を立てた。わたしも同じようなクオーツ時計をしていたので、親指を立てて応じたのだった。するとなんとなく親しみが湧き、わたしがひとり旅だと言うことが分かったのか、近くに来て、写真を撮ってやろうという風にジェスチャした。ほとんど自分自身を撮ってないわたしはそれでも彼の善意に対して素直になってカメラを渡した。彼はしきりにわたしをあっちこっちに立たせ、日本のカメラを楽しむようにシャッターを押していた。しばらくしてまた時計の話になった。時刻を合わせてみた。勿論彼の時間にわたしが合わせたのだ。それにしても濃い体毛に覆われた腕で、バンドに毛が挟まって痛いのではないかと心配したほどだ。それに彼は眉毛が一本で、つながっていた。ギリシャ人にはこの手の眉をした男が多いと思う。一ヶ月ほどヨーロッパを巡り、フランクフルトから北回りで帰国し、写真を現像したら「クオーツ」男が撮ってくれた写真はみなぼけていた。クソ真面目にシャッターを押したから手ぶれだったろうと写真屋は云った。
もう何度目になるだろう?
浜辺に一人ポツンと座りぼんやりと海を眺めるのは。左手にはごつくてメカメカしいダイバーズウォッチが居座っている。そう言えばこの腕時計、水深何バーツまでOKと「いかにも濡らして下さいよ」といわんばかりの顔をしているが、まだ一度もコレを着けて海に入ったことがなかったことに気づいた。
いやたった一度だけ濡れたかもしれない。あの時。
あれは記録的な猛暑となった1990年の夏。
当時学生だった僕は夏休みのバイトにマリンスポーツのインストラクターを選んだ。アルバイト初日、その年はサザンの桑田佳祐が初監督した映画『稲村ジェーン』が話題となって、主題歌の『真夏の果実』が有線から流れていた。
「サザン好き?」先にバイトに来ていた学生が僕に聞いてきた。
「う、うん」質問よりもそいつのでかさに驚いた。
身長186cm体重120キロはあるサモア人体型。
「オレも。やっぱ夏はサザンだべ!」そういってニッコリ笑うと浅黒く焼けた顔がクシャクシャになった。
同い年ということもあってかこの夏初めて出会ったのに僕らはまるで昔からよく知っている友のように不思議と気が合った。
ある日、桟橋でヤツが徐に左手を突き出した。そこには買ったばかりのダイバーズウォッチが輝いていた。散々自慢した後、波の状態を見てくるとヤツがボートに乗り込んだ。
「その前に」そういうと腕時計をはずして僕に手渡した。
「コレ預かってて」
「なんで?」
「だって濡れると嫌だべ!買ったばっかだし!高かったし!」
「ハハハ」
でもそれきりこの腕時計が持ち主の元に帰ることはなかった。
事故だった。あいつは一人海に消えていった。
溢れだした涙が握りしめたダイバーズウォッチを濡らした・・・
あれからいくつも季節が通り過ぎ、また夏が訪れる。僕はちらりと腕時計に目をやる。レンズに反射した強い陽射しがまるで時を止めているかのように時計の針を見えなくしている。暑かったあの日のままに・・・
昨年妻の実家に行った折、義弟は腕時計の無い私にと愛用の一つを呉れました。今月の二日から一週間、米国のフロリダに嫁いだ娘が長女を出産し祝いに渡米しました。お雛様も飾りさて出発の日にどうしても時計が見つかりません(帰国後、「お父さん達の寝室のカーテンの裏にあった。」と娘からTEL)「見つかったらエリック(主人)に」と。フロリダ空港に着いたら妻も時計を日本に忘れ時刻が分かりません。見かねた娘は腕時計を妻に。そして無事帰国できました。米国の50州は四時間の時差があり、各空港ではその現地時間に合わせなければならずミスを犯す邦人が多くいるようです。なにしろ二日の午後五時に成田空港を発ち、十八時間飛行機に乗り続け到着が同じ日の二日、午後七時なのです。日本中がどこも同時刻の「日本人の感覚」では、理解するまで時間がかかります。義弟からもらった時計はフロリダで、フロリダで頂いた時計は祖母の腕で夫々正確な時を刻んでます。
3月29日
4歳のとき、初めて父に腕時計をプレゼントしててもらった。
手巻きの、文字板にプーさんの絵が書いてある、赤いベルトの腕時計だ。なぜかというと、3歳から通っていたエレクトーンに4歳からは近所のお姉ちゃんとバスで通うことになったからだ。
「自分で時間をちゃんと見るんだよ」って、笑顔で父がプレゼントしてくれたのです。うれしくって、暇さえあれば時計をしていたあのころ。
その時計は、ベルトは何度も交換したものの、手巻きで壊れることもなく、手には出来なくなる年になっても、机のすぐ取れる引出しの中に大切にもっていた。
就職して初めて海外旅行に行くときには、それをもっていって日本時間にしておいたし。
結婚した今でも、大切に宝石箱の中にしまってあります。
2歳の娘が4歳になったとき、娘にゆずるつもりです。
プーさんの大好きな娘もきっと喜んで使ってくれると思います。
小学生にあがった年の誕生日プレゼントは、腕時計だった。数日前父に何がほしいかと聞かれ、精一杯の背伸びをして「腕時計」と答えたのだ。
いとこはみんな年上だった。近所の子もみんな年上だったから、私以外はみな腕時計をもう持っていた。その頃流行ったデジタル時計を自慢げにする男の子もいたし、ミッキーマウスの腕が針になっているおしゃれな時計の子もいた。
父が選んだのは私が好きだったジミーアンドパティの腕時計だった。子供の腕にはちょっと大きかったけれど、嬉しかった私はそれをはめたまま朝ご飯を食べた。
私の誕生日はちょうど祝日なので、近所の子達と遊ぼうとそのまま外へ出た。高鬼やらかくれんぼやらして、走るために腕を振り上げると腕時計の重みを感じた。
昼になると母親達がご飯よ、と呼びに来る。でもその日は自分から家に帰った。腕時計に目をやり、「もうお昼だよ、帰らなきゃ」と言い置いて。そして「じゃ、また一時に集合ね」。シビレタ〜。
今思えばあの腕時計は楽しい時間を刻んでいたなと思う。何時から何時までだれちゃんと遊んで、何時には家でご飯が出来てて・・・。
それから塾に行くようになり、電車で高校に通うようになると、もう私はパティアンドジミーの腕時計はしなかった。色も柄ももっとシンプルな物に変えた。それと同時に腕時計の刻む時間も変わってしまった。この時間からこの時間まではこれをしなければならない、ということを教える道具になった。
昔々、楽しい時間だけを刻んでくれた腕時計、それを持てたことを今はすごく幸せだったと思う。
「父の腕時計」
私が「時」を意識しだしたのは、小学校3年の時だったと思う。父の赴任地の山間の村で私達家族は、暮らしていた。小学校6年生の兄の下に姉、私、弟、妹が居た。父は中学校の校長で、怖い、厳格な先生で、通っていた。私は5人きょうだいの中で一番わがままで小心者だった。そのころまで、時間といえば太陽さんの動きで十分足りていた。日暮れになれば家に帰ったし、朝日が射せば起きた。この頃、時計の読み方をならったのだろうか。「時」の感覚が敏感になった。朝食の準備が、少しでも遅れると「学校に遅れる遅れる」と泣き騒いで母を困らせた。兄や姉が、悠々としているのを見れば、十分に時間に余裕があるのが、判るのに、自分の思い通りにならぬことが気にいらなかったのだ。多分初夏の頃だった。ついに父親が、この女々しい、わがまま息子の性根を直しにかかった。泣き叫ぶ私の首根っこをしっかりつかんで、「ここに座れ」と茶の間に座らせた。父は腕時計をはずし、私の目の前の畳に置いて、「これを見ろ、針がここへ来るまで動くな」と命じた。黒っぽい皮のバンドのついた古びた丸い時計だった。秒針がないので長針がちくっちくっと僅かに時を刻んだ。弟は姉と出かけてしまうし、母は妹と畑へ出て行ってしまった。だれも助けてくれない。父は狭い庭先で草花に水をくれながらチラチラ私を監視している。絶対絶命だ。息はあらくなる。泣きべそで、ジット時計をにらんだ。時が過ぎるのを待てばいいのか、過ぎないのがいいのか、変な感覚だった。始業時間がどんどん近づく。時間が来ると父は言った「良し、走って行け」。自分は自転車で「急げ」の声を掛けて私の脇をさっと走り抜けて行ってしまった。私は夢中で高台の学校まで走りつづけた。結果は遅れはしなかった。父は時間を距離で体感させたのだと思う。それ以降、泣き騒ぎはやめた。時間と距離の関係がわかりだした、初めだった。
初めて自分の時計を持ったときから自分の人生は、時間との戦いであった。まず一番最初の戦いは、中学入試での問題と時間との戦い。辛くも逃げ切りその後も試験と時間との戦いがつずいていく。その後、少し色気ずいてきて彼女との戦いに時間との戦いの場が移っていくことになる。時間にルーズな私は、時計を10分進めることによって遅刻を防ごうとするが、時間は、まだ10分以上余裕があると私をそそのかす。また、その後も時間との戦いは繰り広げられている。私の中にいる時間との戦いは、自分がきずいていなくても私の存在が消滅するまで戦いつずけられていくのだろう。
小学校4年生になっとき、前から欲しい欲しいとねだっていた
念願の自分の腕時計を祖母からもらった。詳しいことは覚えてないけどセイコー社製で1万円もした素晴らしいもの。当時の私にはもったいないくらいの物。母からは「とてもいいものだよ。大きくなっても使えるようにあえてキャラクターがついてないシンプルなものをお婆ちゃんと選んだんだから大事にしなさい」と言われた。学校には腕時計をはめてきてはいけない規則だったので家に帰ると私は机の中にしまってある時計を出して眺めたりはめたりしてニヤニヤしていた。
その大事にしていた時計がある日なくなった。原因不明。多分私がどこかに落としたか・・・。目の前が真っ暗になった。あの日母に言われた言葉が頭の中で反復していて必死になって探した。
両親にはいえなかった。もちろん田舎のおばあちゃんにも。言われようのない不安感と自責の念という気持ちを始めて味わった。黙りとおすことは出来ないと思い母には言った。母は何もいわなかった。それ以来結婚するまで腕時計は買ってない。
腕時計は憧れだった。高校生になったら腕時計ができる。そのためにも絶対合格したいと思ったものだ。当時通っていた中学は腕時計は禁止だったから。合格発表で番号を見つけた後は両親とデパートに直行。その頃流行っていた日付表示のある丸形の時計に赤いバンドを付けてもらった。あの時の喜びは桜の季節になると毎年新鮮に思い出される。ゼンマイ式のその時計は36年経った今も時を刻み、五十路の私の腕に思い出と共に巻きつく。その間に何度パンドを変えたことだろう。腕時計の数は増えて多くはクォーツだが、このゼンマイ時計は一番のお気に入りである。一時故障して動かなくなった。時計屋さんに持参したら修繕費用が随分かかると聞かされた。でも貴重な時計ですよ、と言われて修理に出した。袖口からのぞく時計に目を止めて珍しがられることもしばしで、その後はひとしきりこの腕時計の思い出話に花が咲くのが常である。
先日老いた母がこの腕時計に気づいて「新しいのを買ったの」と言う。「お母さんが買ってくれたのよ」と答えると、遠い日を思い出したのだろう、しばし手にとって慈しむように眺めていた。母の胸にも去来したであろう懐かしい日々。この腕時計を買ってくれた母は今の私より15歳も若かった。お母さん、ありがとうね。お母さんもこの時計もずっとずっと大事にしたい。
「同じ時間を刻もうぜ!」
冗談まじりの言葉とはいえ、あまりに似合わないダンナのセリフにキャハハと笑ってしまった。二人の腕には買ったばかりの時計が光っている。十回目を迎えた結婚記念日のことである。
世間ではスウィートテンダイヤモンドのコマーシャルが流れる中、ペアの腕時計をお互いの記念品にしようと、デパートの売り場を子ども達を引き連れて下見を重ねた。ダンナも私も初めてペアのものを買うため、誰に見咎められるわけでもないのに、選ぶにもちょっと恥ずかしいような、でも嬉しいような…。
末永く使えるもので、体のごついダンナと小柄な私にしっくりくるデザイン。いくら十年に一度のことでも分相応の価格のもの。普段腕にするのに気を使うものであってはいけない。
どうにか意見がまとまった品は、アニエス・bのシンプルなデザイン。私の細い手首にはちょっと重い感じがしたが、ここはダンナの意見を取り入れて、めでたく二人のものになった。
それから二年ほどして、私は気分転換のつもりで以前使っていたエレガントな時計に変えた。それで半年ほど過ごした頃、ダンナにやっかいな災難が降りかかった。私は私だけの手で子ども達を守り、日々を送った。食事ものどを通らない、いつもお腹の底には鉛がゴロゴロしているような、でも生活は普段どおりこなさなければならない毎日だった。
どうにか元の生活に戻った頃、ハッと気がついた。ダンナと私の絆が緩んでいるのかもしれない。二人で同じ時間を刻むはずだったのに、私はあの時計をしていなかった。気にしすぎだとも、バカらしいとも思った。それでも私は、またペアの時計を使い始めた。ダンナと私を結びつけるお守りとして。
(注)この「思い出の腕時計エッセイ募集」に書いていただいたエッセイの著作権は、セイコーインスツルメンツ株式会社に帰属します。予めご了承下さい。