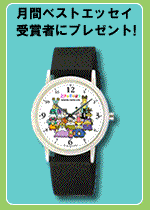2002年の作品
1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9-10月 11-12月
3月 (投稿順)
「思い出の腕時計」花野圭吾さんのエッセイ
「使わなかった腕時計」細江隆一さんのエッセイ
「高校生の腕時計」金本 優さんのエッセイ
「質屋に入った初めての腕時計」奈良克彦さんのエッセイ
もこもこさんのエッセイ
「初めて買った腕時計」山田章夫さんのエッセイ
「時をかける少年?」八田次郎さんのエッセイ
「父の笑顔」橋本奈緒美さんのエッセイ
「魔法のGショック」岩波里枝さんのエッセイ
「腕時計の思い出」なおさんのエッセイ
「流れゆく時間」中島 賢彦さんのエッセイ
「落としもの」kotsubuさんのエッセイ
「時計交換」倉木治子さんのエッセイ
「本当に安いのは・・・」せんむさんのエッセイ
原 奈保さんのエッセイ
「ささやかな名案」あおきまみこさんのエッセイ
「キャンバスの前でまっていた腕時計」福倉恵美さんのエッセイ 3月のベストエッセイ
「自動巻」幅 茂さんのエッセイ
「はじめての腕時計」木内彩乃さんのエッセイ
「母の腕時計」津田 展志さんのエッセイ
「勤続20年」川神信弘さんのエッセイ
「届けられた時計」長坂隆雄さんのエッセイ
「娘からもらった時計」召田 俊雄さんのエッセイ
「最後のプレゼント」加崎 菜実さんのエッセイ
「若いと言う事は」大脇明子さんのエッセイ
「重くて無骨な腕時計」三木将幸さんのエッセイ
「拾った腕時計」後藤 順さんのエッセイ
「父からのお願い」井田素さんのエッセイ 3月のベストエッセイ
「祖父がくれた時計」松井友希さんのエッセイ
「思い出の日の腕時計」伝田幸子さんのエッセイ
「時計はおこりんぼうさん?」米満 信代さんのエッセイ
「PRESAGEの思い出」makiさんのエッセイ
「父の腕時計」島田清純さんのエッセイ
「透き通った時間」もんたろうさんのエッセイ
「父のくれた腕時計」松下 弘美さんのエッセイ
「腕時計を初めてした時」あべ なつみさんのエッセイ
「はじめて&2つ目の時計」箕輪瑞穂さんのエッセイ
「腕時計達」米山 弥生さんのエッセイ
両親からの高校の入学祝いが、私の最初の腕時計である。うれしさで、腕時計が気になってしょうがなかった記憶がある。授業中などは、教室に時計があるのに、自分の腕時計を見てばかりだった。時間を知りたいというより、ただ腕時計を見ていたかった。
初めて自分で腕時計を買ったのは、社会人になってからで、入学祝いの腕時計をなくした後である。
それから今まで十数年、私が腕時計を買うのは決まって腕時計をなくした時である。このことは、国産の腕時計の品質の高さと、自分自身の注意力のなさを証明している。
いつも身に着けているものだけに、腕時計をなくすと、自分の分身をなくしたような、さびしい気分になってしまう。そんな時、私は急いで腕時計を買いに走る。時間が分からない不便さより、腕時計をなくしたさびしさを紛らわすために。
「きれいな時計ですね」
周りの誰かが、声をかけてくれる。何ともいえないうれしさが込み上げてくる。なくした腕時計のことなどすっかり忘れて、この腕時計を選んでよかったと、思う瞬間である。我ながら、おめでたい人間である。
そんな私でも、なくしていない腕時計がある。九年前に、大切な人から送られたブルーの文字盤の腕時計である。九年の間、私は何個(計算したくない)か時計をなくしたが、この時計だけは、なくしていないのである。
九年の間に、時計にはたくさんの傷がついてしまった。でも、文字盤のブルーは、もう二度と会えない贈り主の爽やかさと、やさしい心の深さを感じさせてくれる。秒針の動きは、その人と一緒に、今の時間を過ごしている気分にしてくれる。
思い出の腕時計は、思い出にしたくない、ブルーの文字盤の腕時計である。
数年前にフィジーへ研修に出かけた。時差があるときき、成田空港で時計を購入。日本時刻とフィジー時刻に合わせ、時差を時計で知り、二国で使う時計を分けておこうと思ったからだった。
ところが、フィジーに出かけてびっくりしたのは、時間に対する感覚の違いだった。俗に言う「フィジータイム」は、約束した時間にプラス一時間と教えられ、ええっとびっくり。レストランで食事を頼んでも、最初のビールは時を待たず登場するが、注文した食事はいっこうに出てこない。いらだってウェイトレスに聞けば「もうすぐ」としか答えない。イライラしながらも「フィジータイム」の話を思いだし、じっとがまん。そして待つこと一時間。ようやく料理は届き、空腹を満たすことができた。
考えてみればこの待ち時間。たいへん貴重だった。ビールを飲みながら会話が弾む。眼前には青い海が広がり、目の保養にはもってこい。涼しい風が吹き抜け、フィジーの夏を満喫。一時間待たされたと考えるとイライラするが、一時間ゆったりした時間を持つ機会を与えられたと思えば、なんだか得した気分になった。
結局フィジーにいる間、購入した腕時計は一回も使わなかった。郷に入っては郷に従えどおり、フィジーでは「フィジータイム」で通してからだ。時間に縛られてあくせく動くのは日本だけで十分。腕時計のいらないフィジーの生活はある意味快適そのものだった。
使わなかった時計はいま日本でフル活動している。フィジーで使われなかった分、腕時計が酷使されているような気がしてちょっと心が痛む。
30年以上昔のことです。県立高校に合格し入学式を数日後に控えたわたしに、横浜に住んでいるおばさんから入学プレゼントの「腕時計」が届きました。おばは、学歴がないのに苦学して英語を覚え、アメリカ人のお手伝いさんになっていました。茨城の田舎に住んでいるわたしには、おばさんの家での米国風の生活がうれしく、よく泊まりに行っていたのです。朝のトーストに英語で書かれたラベルのインスタントコーヒー、コーラ、雑誌。米国製の大きな冷蔵庫。アメリカ人の幼女との片言の英語を使っての会話。大好きなおばさんからの入学祝いに、わたしは大きな期待を抱いていました。
ところが、届けられた腕時計は、薄っぺらな金色の時計でした。今思えば、高級感のある本皮のベルトに腕にフィットする薄さの洒落た時計だったのですが、すべての友達が腕に嵌めていたのは銀色の厚ぼったい国産の腕時計で、日付と曜日が表示される時計でした。当時のわたしには、それが腕時計の標準であり、カッコよさの象徴に見えていたのです。入学式の晩、母親に「国産の腕時計」を買ってくれるようにねだりました。母は困惑したようでした。けっして裕福ではないわたしの家で、入学式までこぎつけて一安心したであろう母親でしたが、また難題が持ち上がったのですから。しつこくも言えないわたしは、入学式以来、腕時計を家の机の上に置いたまま学校へ行きました。
学校では友達の腕時計が気になって仕方ありません。「今、何時?」と言いながら時計を覗き込みます。時間を知りたいのではなく腕時計を見ることが目的で、わたしの腕にその時計が嵌められることを空想する日々が続きました。
4月が過ぎて、5月も半ばを過ぎた日。家に帰ると、机の上にSEIKOと書かれた腕時計の箱が置かれてありました。
腕時計を初めて持ったのは、大学二年生の春だった。中学に入ったとき、父が病気で働けなくなり、母がひとりで私たち子供三人を育てていた。とても腕時計を買ってくれとは言えない状況だった。姉だけは母の配慮だったのか小さな文字盤の腕時計を身に着けていた。私は当然だと思っていたから羨ましくはなかった。春のある日、私は母に言ってみた。「自分の腕時計を買ってもいいかな?」。母は微笑んで頷いた。私がアルバイトで貯めた金で腕時計を買いたいと思っていることは、うすうす感じていたのだろう。大学に入ってすぐの夏休み、そして休みごとにアルバイトをしてきた金は、腕時計を買えるぐらいは貯まっていた。いまの時代のように手軽に買える腕時計のない昭和三十八年のこと、腕時計は結構高級品だった。初めて腕に着けた時計は、セイコーの2針、シンプルなデザインだった。だが縁の金メッキは綺麗に輝いていた。なんど眺めても飽きなかった。当時の値段で八千円だったのを今も憶えている。母は、いい時計ねと喜んでくれた。数日後友人たち三人で飲みに行く話が出た。しかし、誰も金を持ってはいなかった。目ざとく私が腕時計をしているのを知った一人が質に入れろと言う。私は焦ったが必ず出してやるからと強引に質屋に連れて行かれた。腕時計で借りた二千円は、あっという間になくなった。質屋から受け出す数日の間、私は母の目が怖かった。同時に腕時計を持たなかった頃は、それほど気にならなかった「時」が頭から離れなかった。受け出したとき、まだ三日しか経っていなかったことに気付いた。私のなかでは優に一週間は過ぎている感覚があったからだ。初めて買った腕時計への愛着が、そう感じさせたのだろうか。京都の大学を卒業後、東京での社会人生活七年目まで私の初めての腕時計は正確に時を刻み続けた。
普段腕時計をしていなかった私も、海外出張となると話しは違う。
時間を気にしていないとトラブルのもとだ。日本のようにどこにでも時計があるという訳でなく、携帯電話も使えないからもっていくつもりもない。
急に決まったヨーロッパ出張。仕方なく近所のスーパーで安い腕時計を買い求めた。
日本時間に設定して8時間の時差を越えての旅。時差ぼけとハードワークでふらふらになりながら、日本の本社に電話をかける。
腕時計の時間は日本時間のままだ。ホテルの時計は夜中の一時になり、日本は朝の九時をようやく迎えた。やっと話ができる。日本と私をつなぐのは腕時計だけだ。
あわただしくて家族への電話は全くしていないが忘れている訳じゃない。まだ、一才の息子の世話と仕事で妻も一人さぞ大変だろう。話し始めたら気分が萎えてしまいそうで電話ができない。
現地での休暇もなく一週間がすぎ、予定通り帰国できる運びとなった。再び時差を越えての帰路。時間はどんどん腕時計の時間に追いついていく。不思議な感じだ。
日本につき電話するが妻は外出しているようだ。留守電に帰り着く時間を告げ新幹線に乗り換えて家路につく。駅に降り立つと妻と子供が迎えに来ていた。
意味もなく腕時計を見た。当たり前だが駅の時計と同じ時間。なぜかそれだけで出張中ずっと家族と気持ちがつながっていたような気がした。
初めて買った腕時計は、まだ、デジタルの腕時計がそれほど普及していなかった頃だった。テレビCMにつられて、デジタル腕時計に憧れて、初めてのバイトの給料で時計屋に行って買った腕時計。その時計をしたときは、CMの宣伝じゃないけどヒーローになった気分だった。今ではどこにでもある時計になってしまったけれど、一生忘れない思い出の時計です。
時をかける少年?
小学校六年の頃、ストップウオッチ付きの腕時計が流行していた。これさえあれば、弟と息を何秒止めていられるかを正確に競う事ができるし、百メートル走で十四秒の壁を破るにはこの機能がとてつもなく必要に思えて無理を言って母親に買ってもらった。
それは、セイコーの銀色に光ったクロノメータであった。大振りの銀色に光った時計は小学生には誇らしかった。アウトドアなんて言葉は無かったけれど、腕にはめているだけで、冒険家やヨットマンや飛行機のパイロットになったような気分を味わえた。
小学校には時計をして行ってはいけなかったから、専ら原っぱに遊びにいく時とボーイスカウトに行く時に腕にはめた。
嬉しさのあまり訳もなく時間を計測した。0時0分に秒針を合わせ、あそこまで何秒で走れるか、あの汽車は何秒でトンネルを抜けるかといったたわいのない時間遊びをしていた。
ある日、手持ち無沙汰にストップウオッチをもて遊んでいると、突然秒針が狂ったように回り出した。みるみる内に長針が一周していく。ひょっとして「時をかける少年?」(んなアホな)私はまわりを見回した。異次元空間に迷い込んでしまったのではないかと不安になったからだ。
夏の暑い午後の昼下がり、夏休みの物憂い日射しの中で突然タイムスリップしてしまう幻想が現実になった。息を飲みながらその時計の動きを追った。鏡に移る自らの顔にみるみる皺が増え人生が急速に短くなっていくような気配を感じた。
十分あまりで自動巻の腕時計のゼンマイは尽きてしまった。
その時遠くで母の間延びした声が聞こえた。
「敏郎、おやつ食べない?」
はっと我に返ると額に汗をびっしょりかいていた。
時計はその後何も無かったように動き出した。自動巻のゼンマイがいかれたんだろうと思っているが、何か腑に落ちない出来事であった。
初めて腕時計を買ってもらったのは高校に入学した時だった。母とではなく、当時あまり会話のなかった父につれられて、なぜか二人で街の小さな個人商店に買いにいった。私には全くなじみのない店だった。
ショーケースのなかにはなにやら高そうな腕時計が並んでいたが、どういったなりゆきだったか、初老の店主が三本の時計を私の目の前に並べそのなかから一本を決めることとなった。本当は他のものとももっとじっくりと見比べてみたかったのだが、生来の父の短気な性格と、あまり高いものはいけないなどと少々気がひけつつ一本を選んだように思う。四角い金色の文字盤でとてもシンプルな時計だった。
「お父さんのより高い時計を選んだなぁ。」
そう言ってお金を払いながら、普段は滅多に笑うことのない父がニコリ
と笑った。そんなはずはない、だって遠慮して一万円代のものを選んだのに…そう思い父の腕時計にこっそりと目をやると、シャツの袖口から色あせて傷んだ革のベルトがチラリとのぞいてみえた。
あれから二十年の歳月がたつ。もともと父は腕時計には興味があったようで、家計に余裕ができるにつれて高価なものも何種類か買い集めていたようだ。
この春、父がガンで死んだ。まだ五十代だった。弟たちは父の形見だといって自分たちの給料の何倍もする父の腕時計をあれこれと分け合っている。そんな彼らを横目でみていたら、今まで忘れていたあの日の父のやさしい笑顔がふと目に浮かんだ。
生まれて初めてバイトをした。自分で稼いだお金がまぶしく見えた。そのお金で買った腕時計、チャゲ&飛鳥のGショック。最新版で、ボタンを押すと光る、又ボタンを押すとメロディーをかなで、又押すとストップウォッチになり、又押すと作曲ができる魔法の時計。そんな時計があるときなくなった。旅行中にバスに乗っていたときはずしてそのままだった、一瞬にして血の気が引いた、ショックでそのまま立ち尽くしてしまった。もうあのバスは戻ってこないのか添乗員に聞いたが戻らないという、日本ならまだしもそこはアメリカ、誰かにとられたという不安がよぎる。皆はすでにホテルチェックインを済ませていた。私は、ホテル前で一人、同じバスが止まることを祈った。すると、バスが一台、ホテルに要があったらしく戻ってきた。私は何も考えずバスの運転手にドアを開けてと頼んだ。そして、客席へ行くと大事な時計がそこにはあった。どうやらまだ客は乗せていなかったようだ、旅に出ても戻ってくる、そしてものを大事にする大切さを教えてくれた魔法の時計と感じずにはいられない。
30年前の春。私は、父と二人で青函連絡船に乗っていた。大学生活を始めるための、短い旅だった。
兄が知的障害者で手のかかる子供だったため、私は幼い頃から、できるだけ親をわずらわせないように、良い子にしていた。何があっても両親には言わずに、一人で何とかした。
そんな他人のような父娘関係だったから、初めての二人旅は気詰まりなものだった。早く目的地に着かないかと時間ばかりを気にしていたが、津軽海峡の真ん中で、数年間使っていた腕時計が止まってしまった。
父に時計のことを言う気になれず、いつもどおりに黙っていた私を、船を降りてからの父の最初の言葉が驚かせた。
「新しい腕時計を買わなくちゃね」
何も言わず、態度に出した覚えもないのに、父は気づいていたのだ。
駅前の時計屋で新しい腕時計を選びながら、私は思っていた。きっと今までも、父は私のことを、きちんと見ていてくれたのだ。
私の方が他人のように感じていただけで、父は父なりに私を気にかけ、心配してくれていたに違いないと。
それ以来、たくさんの腕時計をしてきたが、そのとき買ってもらった腕時計はもちろん、ほかのも全部、こわれても捨てることができずに大切に保管してある。
腕時計は私にとって、親に愛されたことの証明書だから。
大学時代、新聞奨学生として学費を稼ぎながら、四年間学校に通った私は、卒業の記念品として新聞社から時計を贈られた。金縁、革バンドのその時計の裏蓋には私の名前が刻まれていて、両親に自慢げに見せたものだった。社会人一年生からの時を刻み続けたその時計が、十年の歳月の経過を告げた頃、私はその時計を父にプレゼントした。十年も使い込んだ中古品にも関らず、父はそれを大変喜び、出掛ける時には必ず付けていた。やがてその時計が更に三年の時を刻んだ頃、父はガンで亡くなった。私は時計をお棺に入れてあげようと思ったが、燃えないという理由で、葬儀屋さんに止められた。残った時計を今度は母が、父の形見として使うと言い出した。裏蓋に私の名前が刻まれ、持ち主を三人も代えることになったその時計は、今でも母のか細い腕で、時を刻み続けている。
「あら、なんか光ってる」。小学校5年生のとき、学校帰りの空き地で何か光るものを見つけた。砂を払って拾い上げてみると、それは紳士ものの銀の腕時計だった。私の両親はそれまで腕時計をしていなかったので、私にとって生まれて初めて手にする腕時計だった。キラキラと光り、ずっしりとした重みがある。あまりに高価そうで、その場から持ち去ることすらためらわれたが、家に持ち帰って母に見せ、そして交番へ向かった。
そんなことはすっかり忘れかけていた数年後のある日、突然警察の遺失物係から電話があった。腕時計の持ち主が現れなかったので、私たちのものになるという。いよいよ家に腕時計がやってくる。ウキウキしながら取りに行った。
それは自動巻きだったので、数回振ると再びちゃんと時を刻み始めた。そして、高価そうな重みをたたえたその時計は、当然のように父のものとなった。おしゃれにうるさい父なのに、その時計は妙に気に入ったようで喜んで会社へして行った。
数年後のある時、ふと母の腕を見ると妙な時計をしている。銀のずっしりした時計に、どうみても似つかわしくない黒の皮ベルトが無理やりつけてある。「なんか、それ、かっこ悪いよ〜」と、私はいった。「昔、あんたが拾ってきた時計だよ。お父さんが使い過ぎて鎖が切れたから、私が適当なベルトつけたの」と母。おしゃれに気を遣わない母のやりそうなことである。すっかり衣替えしてしまった時計に、おしゃれな父が喜ぶはずもなく、今ではすっかり母の愛用品となっている。
「いい時計してるね」
そう言ってヤツは私の手首に目を落とした。高校3年の期末テスト初日のことである。暑い暑い日だった。私は静かな部室で試験勉強をして、教室へ帰る所だった。お礼を言うため、ヤツの研究室に立ち寄っただけである。
「前から欲しかった時計なんだ」
「いくら?」
「一万四千円」
「ふぅん」
じっと文字盤を見ている。室内の空気はだんだんと熱気を帯びて来る。
「そっちは?」
「安物だよ、七千円」
「千円…」
「七千円」
四角いクリーム色をした文字盤を金色の秒針が闊歩している。バンドは茶色の皮。ありふれた時計だった。
「見せて」
私は黙って時計を外した。ヤツは手に取って時計を眺めている。銀色のベルトが変形しつつあるのを見て笑っていた。直さなくていいの?といった顔。
「そっちのも見せて」
ヤツは黙って時計を外した。私はそれを手に取って眺めてみた。秒針がヤツのように几帳面に動くのを見て、ちょっと笑った。
「付けてみていいよ」
ついさっきまでヤツの手首にくっ付いていた時計は、温かかった。安心出来る温かさ。私は時計を翳して見せた。
「これ付けて試験受けたらいい点取れるかな?」
「付けて行っていいよ」
「その間私の時計付けてていいよ」
「目立つだろうが」
とは言ったものの、何時の間にかヤツは私の時計を付けていた。
セーラー服に男物の時計。スーツに華奢な時計。
静寂を破り、廊下に友達の声が響いた。私を探しているようだ。
「目立つから、返す」
「そうだね。研究室じゃなくて、部室のドアから出なさい」
ヤツは風采の上がらない教師だった。ヤツはそれを知っていた。私はヤツがとても優しいことを知っていた。時計を返す時、ヤツは文字盤を見て呟いた。
「桜色だね、可愛いね」
室温上昇を察知して、エアコンが再び動き出した。涼しい風が頬を撫でて行く。時計は元の場所へ帰って行った。男のくせに細くて白い手。私は思った「生まれ変われるなら、あの時計になりたい」と。
高校時代、私は、とても安い時計でしたが、そこそこ気に入っている時計をしていました。ある日の事、同じクラスの友人が、自分の時計を見たいと言うので、貸したところ、「ものすごく軽いなあ。これ、安かっただろう。もう少し良いやつをしろよな。」などと、面白半分に言われてしまいました。自分でもその事は良く分かっていたので、その時は、笑って応えていましたが、いざ人に、その事を言われると、正直ショックでした。結局、急に、その時計をしているのが恥ずかしくなり、急いで新しい時計を買いに行ったのですが、今思えば、人に言われ、うろたえ、新しい時計を買いに走った、自分の姿そのものの方が、安い時計をしている自分より、ずっと恥ずかしかったなあと思います。本当に安いのは、時計ではなく、実は自分の方だったかもしれません。そう思います。
3年前の4月1日は、私にとって運命の日。暖めてきた夢がかなうかどうか。社会人になる誇りをもって、その発表を受けた。が、理事長からの言葉は「知的障害者入所更生施設の指導員職を命ずる」。そのたった5秒やそこらで私の10年間が崩れ落ちた。
知的障害者と聞いて、ほとんどの人が想像する程度の障害者ではなかった。重度といえば寝たきりの人を想像するのではないだろうか。しかし違う。体は元気そのもので、知的にだけ障害があるのだ。はじめは憂鬱でしかなかった。そんな人を見たことはないし、私よりも年上なのにむちゃくちゃなことばかりしている。カレーを無理やりつめこんでのどにつまらせて死にかけたり。服を破いてそれで便をなすっていたり。「なんなんだ?こいつらは!」って腹が立った。
けれども不思議なもので、一緒に生活をしているうちにそういった人たちに理解ができ、好きにもなる。障害なんて誰も好んで持っていない。そして町では見かけない程の障害者は施設にいる。まさに「臭いものには蓋をしろ」。どんな障害を持っている人も自分の親は分かる。面会の日にドアのところに群がる。言葉がなくても「あ、きたきた」とか「また来てないのか」なんて思ってるんだろう。彼らのそんな背中が切なかった。
そんな時、主任から腕時計をもらった。私の大好きなさだまさしさんの非売品時計。ゼンマイ式で一生使えるものだった。その人がなぜ私にそんな時計をくれようと思ったのか分からない。さださんが好きだといつも口にしていたけれど。私の事を認めてくれてるのかなって嬉しくなった。時計だけでも嬉しいけれど、その人にもらったことがそれに輪をかけた。その時計は挫けそうになった時、いつも励ましてくれた。
仕事を変わった今も、強く秒針をうち、私を励ましてくれている。
私が初めて腕時計を持つようになったのは・・・多分小学1年の時。
遊びに行った私の帰りが遅くならないように、母がいつも持たせていたのだと思う。
「6時までに帰っていらっしゃいよ〜!」
「わかった〜。」
そう言って毎日遊びに出かけていた私。
ところが、遊びに夢中になってしまうと時間になっても帰りたくない。もっと遊んでいたい。でも、約束は守らないといけないし・・・。そこで、名案!
時計の針を遅らせてしまえばいいんだ!時計のぜんまいを逆回転させ、私の時計はまだ「5時30分」。
よし、これであと30分遊べるぞ!・・・こんな事を毎日繰り返していたなぁ・・。
母はこんな子供の「仕掛け」にいつしか気づいたはず。
それも今となってはもう忘却のかなた。みなさんもこんな経験、きっとありますよね?
「キャンバスの前でまっていた腕時計」福倉恵美さんのエッセイ (3月のベストエッセイ)
高校生の時、同じ美術部の部長に恋してた。でも胸に秘めた思いで友達にも言えなかった。あの時の自分はなかなか話かける勇気もなかった。美術室で静かに油絵を描いて同じ時間を共有することが、ささやかな幸せだった。
あの日は、いつもより、美術室に行くのが補修授業のせいで遅くなってしまった。夕日の差し込む美術室はひとけがなかった。今日はもう皆帰っちゃったんだと、少し残念だった。ふとみると、イーゼルにキャンバスが出したままになっているのがあった。彼の絵だった。ふっと見ると、キャンバスの前に彼がいつも、腕にはめている時計がおいてあった。ばかみたいに、その時計にときめいた、いつも、いつも、彼と一緒にいる体の一部みたいに思えて、そっと手で触ってほお擦りした。
突然、美術室のドアがあいた。
「あれ、まだいたの?時計忘れちゃって。」
あの時私は、どんな顔をしていたんだろう。心臓が口から出ちゃうんじゃないかってほどどきどきした。握り締めてた時計を差し出して逃げて帰ってしまった。
結局、気持ちを伝えることもなく、過ぎてしまった高校生活。ちょっぴり甘くて切ない思い出だ。
そのころ、旅館(昔は、とまるところはいつもりょかんといっていました。どこでもホテルという今と大ちがいですね)へ行くと、必ず『腕時計、カメラ等の貴重品は帳場にお預けください』とありました。
30年以上も前、腕時計はすごい貴重品でした。ぼくは、高校の入学祝いに買ってもらいました。セイコーロードマチック、15000円。その値段がどんなにすごいかというと、高校の月謝が800円か1000円でしたからいまの授業料と比べると、10分の1。つまり、腕時計は10万円以上の価値だったのです。なんと、おまけに2000円のプラチナ万年筆が付いていました。
ぼくは自転車で10キロの道を通っていましたが、手の甲にリューズが当たってそこだけ硬くなってしまいました。やがて、時計を内巻きにして(女巻きといっていました)、学校に着くとすぐに外巻きにしたのを覚えています。
このロードマチックは宝物でした。大学時代も愛着して、傷だらけになってもとっておいたのに……。
「今日からデジタル」と歌った人も悪いのです。時代はデジタルと宣伝されて、ぼくも乗り換えてしまったのです。デジタル時計をしているも、少なくなりました。自動巻は、ちょっとしたブームです。
初めて自分だけの腕時計を持ったのは高校に入ってからだった。
「もう高校生になるんだもんね。時間の管理くらい出来るようにならないと」そういって、親戚のおじちゃんが専門の時計店に連れて行ってくれた。なんだか気乗りしなかった。今までだって時計なんかなくて何一つ不自由しない生活だったのに、無理やり腕時計をすることを強いられているような気がしたのだ。
古ぼったいけど、雰囲気がいい店だった。おじちゃんにうながされるままに、ガラス越しの腕時計たちを見つめた。どれも洒落ていて、きれい。けれど、どうもわたしの腕にはめるとしっくりこない気がした。
「これがいいんじゃないかな」今まで黙っていたその店のおじいちゃんが、小さな銀色の腕時計をべつの場所から取り出してくれた。ベルトは茶色。シンプルで細身の可愛い時計。私は二人の前でその時計をはめた。似合わないと思った。二人はいいじゃないかと笑っている。私はこれがいいと手早く言い、早く帰ろうと促した。決まってしまえばどうでも良かった。
後日届いた時計には、キレイな筆記体で私の名前が彫ってあった。そして、同封されていた手紙には、こう書いてあった。「あなたのじかんを貴重にしてくれる時計です。ただし、あなたにその気があれば。」
今では私の右腕に、あのときの腕時計が親友のようについていてくれる。つけ始めた頃の違和感もなくなり、私になじんでくれたようだ。それは、私が「その気」になったからに他ならない。
私達の小さい頃は学校が終わってから夕方まで遊びに夢中だ。カバンを玄関に掘り投げてそのまま遊びに行く。遊ぶ時間は大体5時頃までだ。近所の会社のサイレンが鳴ると一人抜け、二人抜けと自然に家に帰る。
大人もその頃になると知らない人でも「早よ帰り」と声をかける。だから時間を気にしながら遊んだ事はない。時間を気にしないで遊び呆けたあの頃がなつかしい。
時間を気にするようになったのはボーイスカウトに入ってからだ。集会や休みの日のハイキング、団体生活では時間を守らなくてはならない。腕時計は必需品だ。
私は小学校の六年の夏休みから入った。小学生で腕時計を持っている人は珍しい。それに高級品のイメージがあり、すぐに買って貰えない。父がいないので母の女性用の腕時計を借りた。
母の腕時計は小さな長四角で金色だ。バンドは金属でゴムのように伸びる。それでも私が腕にはめると大きすぎる。しっかり止まらないで腕のつけねまでいく。流石に落ちることはなかったが気持が悪い。それに女性用をつけるのに抵抗がある。腕時計でなく携帯用胸ポケット時計だ。
母の腕時計を借りていたのは半年だ。ボーイスカウトや模擬試験で借りる。ただ、余り使わなかった。母の時計は小さくて見にくい。駅や商店街に大きな時計がある。試験会場の教室にもある。なくても時間が余るのでポケットに入れたままだ。出来て余るのではなく出来なくて余る。ただ時計は持っているのと持っていないのでは心の持ちようが違う。持って入ればほとんど見ないのに、なければ時間が気になるから不思議だ。
自分の腕時計を持つと、母の腕時計を借りていた方が「カッコイイ」と思える。胸ポケットに仕舞われ、持っているだけの時計でも役に立つ。そんな思い出がある母の腕時計だ。
「お父さん、黒い皮ベルトでシックじゃない!」
「そうだな、昔はまだこれより高級な時計だったらしいが」
私は勤続20年表彰の副賞として贈られた黒い皮ベルトの腕時計を見ながら言った。
「これがぼくの20年分の仕事の証か」
普段しているチタン製の金属ベルト時計に比べると、軽くて小さくて心細いほどの感触だ。
「でも、頂けるだけいいじゃないの。20年目で首にならなくて」
「そうだな。貰えるだけありがたいよな」
「30周年になったら何をもらえるの?」
「昔は、海外旅行だったけど、このご時世だから、どうだろう?」
「それじゃ、この腕時計、大切にしないといけないね!」そんなある日、普段している腕時計が止まってしまった。代わりに引き出しにしまってある黒皮の腕時計をして会社に出てみた。いつもと違う腕時計のため、なんだか勝手が違う。日付も出ないし、腕に重量感がないのですかすかした感じがする。
「これ、20年勤続の時計なんだ」
「へえ、20年勤続でこの時計を貰えるんですか」
部下達が横目で私の腕をちらっと見た。なんだか左腕が少しだけ妙に重たくなった。「なぜか軽い感じがするんだよな、この時計」
「へえ、そうなの。でもりっぱな時計だと思うわ、この時計。ちゃんと刻んであるわよ。あなたの20年が」
妻に言われて黒皮の時計を裏返してみた。
時計の裏には、
“20年勤続記念 川神信弘 1999.5.5 ”
と書いてあった。また、急に左腕が重たくなった。
30数年以上も昔になるだろうか。昨日のように私の脳裏に浮かぶのは九州の武雄温泉での出来事である。全国代理店会議で私は武雄温泉を訪れた。その夜は芸達者な芸者衆に誘導され、50名を越す宴会は最高に盛り上がった。宴もお開きとなり町をさ迷う頃には,私の心は天下無敵の状態であった。翌朝,目が覚めた私は腕時計がないのに気づき青くなった。この時計は私が海外駐在員として初めて中南米に滞在した当時、免税港のパナマで清水の舞台から飛び降りる気持ちで購入した当時としては珍しい、自動巻きのオメがの時計であった。それ以来離したことのない、苦楽を共にした私の分身といってもよい思い出の時計である。併し、いつ、どこで、どうしてなくしたのか、全く記憶にない。諦めきれぬ傷心の心を抱いて東京の本社に帰り、1週間程過ぎた頃であろうか、九州のホテルから電話があり、時計を忘れていないかとの問い合わせがあった。跳びあがりたい程嬉しかった。併し、時計の紛失は誰にも口にしなかった私は合点がいかなかった。聞けば、宴会後の夜中、立ち寄ったラーメン屋台の主人が時計にきずき、着ていた浴衣からホテルの名前を思い出し、届けてくれたそうである。ホテルでは当日宿泊の客名簿から順次確認を取って、私に問い合わせるまでに1週間の時が経過していたのである。数日後、愛用の時計は無事に送られてきた。私の不注意から多くの人々の貴重な時間と労力を煩わせたことを思うと、恐縮で穴へでも入りたい気持ちがした。同時に武雄の人々の優しい善意が身にしみて嬉しく感じられた。後日ホテルを訪れ頭を下げる私に、逆にホテル側から恐縮され、思わず目頭が熱くなった。人々の善意に守られたこの時計は、今も私の手元で時をつげながら、武雄の人々への感謝の心を新たにさせてくれるのである。
「どうしてもドイツに留学したいの」
という娘を翻意させることに失敗し、穴のあいたようになった我が家では、夫婦の会話も途絶えがちになった。資金は働いて貯めたお金で十分だからとカバンひとつで飛び出して行ったが、つかの間はともかくそれ以上になると物入りもあるだろうし、いずれは送金のことも考えてやらねばなるまいと妻は盛んに気を揉んだ。
それくらいのことは止むを得ないとしても、早く切り上げ帰国させる方法はないものかと、私たち夫婦は靴の上から足を掻くような会話ばかりを続けた。
里心をつけさせるためにと思いついて、私はある日、娘の通った小学校に赴き、散り落ちる桜の花びらを集めて押し花にし、香りもいっしょに封じ込めて娘の住むブレーメンに送った。掌にのせてそれを開けばふるさとの数々が思い出され、はるかな日本のことに心を向かせるきっかけになるだろうと考えたからであった。
ほどなくドイツから包みが届き、なかに洒落た時計が入っていた。
「私は元気よ」
という簡単なメモには、このままドイツに滞在するという明白な意思表示がしたためられていて、以来、この時計は一日も休むことなく私の手元から離せられないでいる。
私の両親は、私が高校3年生の時に離婚した。
私は父と暮らす事となり、母とは離ればなれとなった。母は私が子供の頃から病弱で絶えず入退院を繰り返していた。
その為、私は母との良い想い出というものがあまりない。
離婚して離ればなれになって初めて母が私に贈ってくれた物は、腕時計だった。
安物だったが、母の精一杯の気持ちだったと思う。毎日肌身離さず身につけていた為、すぐに駄目になった。私は処分する気になれず、ずっと装飾品としてブレスレット変わりに腕にはめていた。
そして、私が30歳の時、3男を出産して1年後、母は50年の生涯を閉じた。
亡くなる2週間前、母は自分の命の期限を悟ったのか、私にブレスレットの腕時計をプレゼントしてくれた。
最後のプレゼントだった。
「菜実に最初にプレゼントした腕時計より、この腕時計は高かったのよ」と言った。
「ありがとう。大事にするね」
これが、最後の会話となった。
母が亡くなって4年の月日が経とうとしているが、ブレスレットの腕時計は一度も止まる事なく時を刻んでいる。
仕事中若い子に言いました。
「時計回りにお願いします。」
そこで言われたのは,びっくりする事でした。
「時計回りは 何の事ですか」
良く見ると 彼の腕時計は 針の無いタイプだったのです。良く考えてみると 携帯電話も デジタル表示 テレビもです。右回りと言えば良かったのですが 時計回りと言うのは 死語になろうとしているのでしょうか。
学校でも時計の見方は 習ったはずです。私達の年代になる人ばかりなのでしょうか 後30分頑張ろうとか言う時に アナログ式は見やすいのです。反対周りの時計があることも 知っています。ストップウォッチは どう出来ているかは 判りません。1/100秒まで 表示するのですから きっとデジタルだと 思います。
アナログ式の腕時計を 無くさないように頑張って下さい。
時計回りは 右回りだと言う事です。
中学受験の前日に祖父から腕時計をもらった。古びた、無骨なデザインのそれは、僕にとって初めての腕時計だった。
「これはワシが戦争時分からしとった時計や。試験でも生き残れるぞ」そう言って祖父は笑った。
子供の腕には大きすぎるその腕時計を握りしめ、僕は試験会場へと向かった。電車の中でその時計をよくみると、ツヤのとれた鈍い銀色をしたフレームの至る所に、細かな擦り傷が刻み込まれていた。そして、とても重たかったのを覚えている。
その腕時計を机の左上に置き、試験を受けた。異変は、午前中・二つ目の試験中で起こった。時計の針がビリビリと震えて、ちゃんと進まなくなったのだ。故障だった。(後で聞いてみると、二、三ヶ月に一度は修理に持っていっていた時計なのだという。)
「試験中に止まるなんて、縁起の悪い時計やなあ!」と僕は祖父に言った。祖父は「そうか。悪かったな」と済まなさそうにしていた。親父は怒り、僕を殴り飛ばした。間違ったことは言ってないのに、と当時の僕は思ったかも知れない。ただ、祖父のあの表情は今も心の奥に残っている。
中学受験には結局失敗してしまったが、僕はもう「腕時計のせいだ」と言ったりはしなかった。単純に、親父に殴られるのが嫌だったからだと思う。子供に、他人を思いやる心など滅多に起きないものだ。
その腕時計を机の引き出しにいれたまま、数年が過ぎた。
高校生の時、祖父は他界した。
大学生になり、一人暮らしをすることになった。引っ越し準備の時、机の引き出しの奥からその古びた腕時計を見つけて、ふと、祖父の事を思い出した。
そんな思い出の腕時計も、度重なる引っ越しのごたごたに紛れてしまったのか、今はもうない。
どろどろ疲れた体を終電車に乗せるにやっとだった。連日の営業会議でも新商品の開発がまとまらなかった。ぼんやりと車窓を眺めようとすると背中に硬いものが当った。それは、座席にひかかった腕時計であった。
それはガラス面や金属部品が磨り減り、持ち主が古老ではないかと想像した。使いふるした腕時計には、妙に人生の疲れのような色やにおいがした。私の心も疲れていたようで、感傷的になっている自分にその腕時計の持ち主に会いたいような衝動に駆られた。
翌日、交番に届けるつもりでそれを玄関先においた。ところが、私はすっかりそれを忘れた。それから三日がすんだ夕食時に妻が聞いた。「玄関にあった古い腕時計を子供が拾ってきたようで、捨てたわ」私はハッとした。妻に事情を説明しなかった。
ときおり、電車の座席に硬いものを感じたとき、あの腕時計を思い出す。その様子に隣に座った若い女性が苦笑いをした。赤面する私はすぐに下を向いた。
「父からのお願い」井田素さんのエッセイ (3月のベストエッセイ)
半年前、腕時計を購入した。自動巻きで重厚な時計。輝いている。メンテナンスをすれば一生使えると言われる時計だ。腕にはめているだけで、人格が上がったような錯覚さえする。
購入する時は緊張した。銀行からおこずかいを引き出す時は5分間迷ったのを覚えている。
自動巻ゆえ、しばらく動かさないと時を刻まなくなる。そこが、味があってとっても気に入っている。唯一、自慢のできる私物である。半年前、体調が悪かった。そんな時、今私が死んだら子供たちは私のことを、いったい、どの位覚えていてくれるのだろうか?と寂しさと不安を感じた。形見として残してあげられる物はある。釣り竿、カメラ、他にもある。
でも、私の正直な気持ちは違った。「ずっと子供たちと一緒に生きたい」「私のことを忘れないでほしい」と、父親としてのわがままを感じた。この私の、どうしても貫き通したいわがままをどうしたらいいのだろうか? と思ったとき腕時計しかないと思い購入した。
今は体調がいい。これからもいいだろう、きっと。でも、子供たちより先に死ぬのは私だ。5才の息子へ。
私が死んだらこの腕時計を使ってほしい。私の生きた時間を引きつづき生きてほしい。時計についたキズは直さないでおく。つらい時も、嬉しい時も、私の生きた証なのだから。
7才の娘へ。
あなたには、時計を買ってあげられなくてごめんね。でも、あなたはいずれ別の人と「時」を生きていくでしょう。
その日がくるまで、あなたの心の時計に一緒に思い出を刻ませてほしい。
どうか私のわがままを聞いてほしい。いいだろ。「一生」と言う時は長いけど、「一日」と言う時は短いと、最近よく感じている。
私が、大学に入学したときに、祖父が、時計を買ってやると、いった。
私は、うきうきしていた。祖父が、昔の、行きつけの、時計屋に、連れて行ってくれた。「ぼっちゃんには、どれをなさいますか?」店員の声が、した。見ると、年をとっている、老人であった。しかし、いつまでも、光り輝く、宝石の古い時計をしていたことは、今も、私の記憶に残る。その、店員は、ポケットから、懐中時計を取り出し、見せてくれた。祖父は、これにするか?と、いった。私は、首を横に振った。なぜなら、まだ、早いと思ったからだ。そこで、ガラスケースのなかで、少しさびかかったような感じのを、見つけた。祖父に、これがいい、というと、本当に、それでいいのかと、いった。私は、そのかわいい時計を今も大切に、している。
私が初めて腕時計を手にしたのは、高校入試に合格した時である。
名門と言われていた憧れの高校に入学出来たことで、父母は大喜びだった。そんなある日、父母は私と妹を連れて時計専門店に行った。片田舎に住んでいた当時の私は、様々な種類の時計を目の前にして、ただただ眩いばかりの思いであった。ウインドケースの中の腕時計の多さに戸惑っている私に、「これがいいなあ」と、父は丸形で黒い皮の腕時計を手にし私に示した。その時計はシルバーで文字盤は黒色のはっきりしたとても見やすいものであった。メーカーはセイコーだと店員は言っていたが、当時の私にはわからなかった。父は「セイコーの時計は狂わないからいい」、と自慢げに言っていた。私は父の示したその時計を腕にはめてしみじみ見つめていた。嬉しさがじんわりと湧いてきて思わず「これ欲しい」と小さな声で父に言った。
「これにしよう」と父は店員に手渡した。
こうして私は父の決断で買ってもらった腕時計をはめて、憧れの高校に通いはじめた。
事件は入学して二週間後の三時間目に起こった。体育の時間のため着替えをして体育館に向かった。クラスメートの皆が鞄や腕時計などは教室に置いて行った。体育の時間が終わって戻ると腕時計が無い。不思議に思って鞄を逆さまにしたり、机や洋服のポケットを捜したが無い。そのうちに他の人が「腕時計が無くなった!」と言いだした。「私も、私も」という声がした。結局、先生に届け出をしたのは四人であった。
父が選んで買ってくれた初めての腕時計。
家族四人で買いに行った思い出の日の腕時計。たった二週間であったが、私を輝かせてくれた大切な腕時計。
遙かなる過去の懐かしくも悲しい思い出である。あの腕時計は、いま何処で時を刻んでいるのであろうか?
私は1年生だと言うのに時計が読めませんでした。そんな私に母はダンボールで手作りの時計を作ってくれました。もちろん針も動くように作ってくれていました。その時計は怒っている顔をしていました。理由は時計と言うのは「ふん」「ぷん」の繰り返しでまるで怒っているみたいですよね。5ふん、10ぷん、15ふんと言った感じで。私はその時計を首から下げ、家族から「今何時?」としょっちゅう聞かれるようになりました。そんな家族のお陰で知らず知らずのうちに時計が読めるようになりました。今ではデジタル表示の時計が多くなってきていますが、私は結婚した今でも家中の時計全てがアナログの時計です。まだ子供はいませんが、もしコウノトリさんが運んできてくれて子供が出来たらきっと母のようなおこりんぼうさんの顔をしたダンボール製の時計をまず作ってあげたいと思います。時代はデジタル化しているけど中身はいつまでもアナログでいきたいものです。
10年前、彼に会うまで。
それまで時計にこだわりはなかった。
時間が分かれば良いものだし、動けば何でも良かった。
それなのに心を奪われたのが「SEIKO PRESAGE」。
彼の左腕にはめられた、シルバーと金のコンビの落ち着いた雰囲気。
留め金に「P」と刻印されているそのモデルは、
当時既に製造中止になっていたのか、お店で見かける事は無かった。
その時計の事が知りたくて何度も彼に話し掛けた。
彼はいとこのお姉さんからプレゼントされたものだと言った。
大切なものだと分かっても、男性用だと分かっていても、
その時計を譲ってほしくてたまらなかった。
もちろんそんな事は言い出せずに過ごしていたある日、
ふと自宅の姉の外した時計を見る…見つけた!
女性用のPRESAGE、こんな近くにあったなんて!!
早速別のSEIKOを購入。半ば奪うようにして姉と交換したPRESAGEは
あれから10年間流行に左右されることもなく、数度の電池交換を経て
私の左腕にはめられ続けている。
今では会う事も無い彼も、PRESAGEを大切にしていてくれるといいな…
時々電車の中でそう思ったりする。
私が小学校3年生の時だった。家族旅行の帰り道、父が車を路肩に寄せてパンク修理をしている最中、わき見運転の一台の車が突っ込んできた。ドーンという音と共に、父は六、七メートルもはね飛ばされて、土手の側溝に落ちて気を失った。
「パパ死んじゃうの?」
「わからない。頭を打ってるから心配よ」
「あっ、パパの腕時計が落ちてる」
父の腕時計は、バンドの部分が引きちぎれていた。それは金属製で、腕にはめるときは、金属の連結部分がジャバラのように伸びるような構造になっていた。母が言った。
「あなたこれを大切に持っててね。後で必要になるかもしれないから」
なぜか母はそれを私に託した。後で必要になるとはどういうことだろうか。もしかしたら父はこのまま死んでしまって、この時計は遺品になってしまうのだろうか。だとしたら何とか直さなくては。
私はプラモデル好きな、器用な少年だった。ちぎれたバンドの構造をすぐ理解して、ものの十分もかからずにその場で修理してしまった。これで母に喜んでもらえるだろうと思った。ところが、母が来て言った。「あの時計、警察の人がどれほどの衝撃だったか見たいんですって」
私は立ちつくした。必要とはこういう意味だったのだ。
「だって、パパの大切な時計、直したら喜んでくれると思って」
母も、息を吹き返した父も嘆息した。
奇跡的に父の怪我は軽く、その後三十年間歯科開業医として元気に働くことができた。小器用な少年は父の跡を継ぎ、歯科医師となった。身代わりとなったあのゼンマイ式の腕時計はもう現役を引退したが、父は今でもお守りとして大切にしている。
母の時計が好きだ。しっかりとしたにぶい銀色のベルト、透明度の高いガラスカバー、小さなギリシャ数字の文字盤、コチコチと正確に刻む針の音。地味なのに存在感のあるきれいな時計だ。
その時計は、母が社会人初給料で買ったらしい。はっきりとした値段は覚えていないそうだが、それなりに決意のいる値段だったとの事だ。
そんな母が私に、その時計を譲ると言ってきた。理由を聞くと、新しい時計を買ったからだそうだ。「華やかなデザインなのに安かったのよ」とご機嫌な母である。
かねてから母の古い時計を密かに狙っていた私は、新しい時計を褒めちぎり、古い時計をくれる事を母に承諾させた。
その時計を自分の腕にはめてみると、やっぱりすごくいい。シンプルで本当に良いものは、飽きが来ないと言うが、本当にそうだろうと思った。その時計は上品な光を放ち、私の背筋を伸ばしてしまうような、厳かな迫力さえもあった。
ご機嫌な私は、ルンルンとその時計を持ち去ろうとした。
ところが、である。母のストップがかかった。
「やっぱり古い時計の方がいいわねぇ。重みが違うわ。」
新しい時計を少し残念そうに横目で眺めながらも、母は誇らしげにそう言った。
かくして、古い時計は母の腕に再び返り咲いた。
悔しいけどどっちみち、母の古い時計が持つ迫力のある気品は、私にはまだ受け止められないだろうな。
これで良かったと思った。だってその時計は、シワの出てきた母の腕に納まってこそ、本当に輝いていたから。
それはきっと、母の青春時代・・・・・・透き通った時間が刻まれてきたからなんだろうね。
父は理容店を経営していた。昔風の所謂「散髪屋さん」だった。おしゃれな美容院や最新の設備を導入した理髪店に押され、その経営がうまく行っていないことは、子供にも分かった。
そんな父が中学の入学式の日に、ずっしり重い腕時計をくれた。当時のお金で3万円。決して安くはない。新中学生にとっては、寧ろ、高級過ぎた。どこからお金が出たのか、心配したが、聞けなかった。
「中学生は大人と同じや。ちゃんとしたものを身につけとかなあかん」
と、父は言った。
「これからは、時間も何もかも、自分で考えて決めるんやで」
と、付け加えた。
間もなく、その3万円の出所を知った。
父が子供の頃から収集してきた古銭だった。
毎週末、それらを取り出しては手入れしていたのに、時計を貰った日から、古銭を出すことがなかった。不思議に思って聞いてみた。
「どこにやったの」
「古銭は卒業や」
父はそう答えた。
しかし、どれだけ大切にしていたかは一緒に生活をしていれば分かった。
腕時計を買うために、古銭を売ってくれたのだと納得した。
それ以上、父に対して何も言えなかった。
それから、僕は自分の責任で、勉強に励んだ。そして、大学を卒業した年に、初任給から父に腕時計をプレゼントした。
「ありがとう」
父は言った。
「僕の方こそ、ありがとう」
僕のありがとうの意味を、父は分かってくれただろうか。
お友達のお家に遊びに出かけるとき、ママが腕時計をわたしの腕につけて「この長い針が3のところにきたら帰っておいでよ。」と言いました。わたしはお友達と遊んでいる時何度も何度も、時計を見ました。でも長い針も短い針もそんなに動きませんでした。だんだん時計を見るのを忘れて遊んでいて、あっと思って時計を見たら長い針は6を過ぎたところです。いっぱい遊んだけどなかなか3にはなりません。でも、ママが迎えにきて「3のところにならなかった?」と言うので、「6らへん」と答えたらママが笑いました。わたしは3になるのを待っていたのに???ママの言った3を過ぎて6になっていたんだって。時計の針は何回も何回も回っているんだね。わたしは腕時計をしてお姉さんみたいな気持ちになりました。
はじめて時計(腕時計)を持ったのは、小学4年生のクリスマスでした。サンタさんからのプレゼントでした。
ミッキーマウスの手が長針と短針の可愛い時計で、嬉しくて毎日していました。
それなのに・・・
お正月、羽根つきをする時に外して、そばにあった石の上に置いたんです。
そして、遊び終わって、そのまま家の中に入ってしまったのです。
20分ほどで気が付き、すぐに取りに行ったのですが、もうありませんでした。
ものすごくショックだったので、その時のことは、今でもハッキリ憶えています。
どうしても腕時計が欲しい私は両親に頼みました。
「そろばんの2級の検定が受かったら」という条件でした。
2級は難しく、受かったのは小学5年生の2月でした。
1年以上かかって、ようやく手に入れた2つ目の時計は、小学5年生には、贅沢なセイコーの2万円もする時計でした。
とても重く感じました。
その時計、仕事を止めるまで、15年間しつづけていました。
私の宝物でした。
私は就職をするまで腕時計とは無縁の生活を送っていました。正直、どこに行ってもたいてい時計はあるし腕時計がなくても不便と思うことはなかったのです。…ところが、就職先のスーパーで私が任されたのは、腕時計売場ではないですか!腕時計もしたことがない私が、いきなりお客様に腕時計を売る立場になるとは…本人もとってもビックリでした。そして、私は売るだけでなく時計の電池を交換したり、簡単な修理をするようになりました。そして、いろいろな時計と出会いました。お客様がとても大切にしている結婚記念日に買ったと言う時計、土にまみれて使っている時計、五十年ほど使い続けられている時計、など…。そして、時計が直って帰るとき、お客様からの「ありがとう」は、私の仕事の励みでした。そして、更に腕時計が時間を見るだけの道具ではなくなり、おしゃれの一つであったり、記念のものであったりする事を学びました。あの売場にあった時計達もいろいろな人に出会い、その人の人生を少しだけ飾っているのかな…などと考えています。今、仕事を離れ、また普段は時計のいらない生活を送っています。ただ、あの経験のおかげか(!?)私の所に腕時計が何本かあります。実は就職するまで本当に腕時計を一本も持っていなかったのに…。本当に不思議な縁でした。
(注)この「思い出の腕時計エッセイ募集」に書いていただいたエッセイの著作権は、セイコーインスツルメンツ株式会社に帰属します。予めご了承下さい。