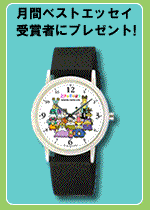2002年の作品
1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9-10月 11-12月
7月 (投稿順)
「二秒間の奇跡」南 佳風さんのエッセイ
「スワミの古時計」増山栄一エリックさんのエッセイ
「主人の腕時計。」小原 真己さんのエッセイ
「時と共に心に刻んだ事。」仲澤 恭美さんのエッセイ
「私の大切な腕時計」一井 愛子さんのエッセイ
「母の幸せ」田邊 広隆さんのエッセイ
「かなわなかった夢の行方」高根 広海さんのエッセイ 7月のベストエッセイ
「父娘の情愛」加藤 千織さんのエッセイ
「イモウトの秘密」伊藤 まきさんのエッセイ 7月のベストエッセイ
「傷だらけの証人」櫻子さんのエッセイ
「初めての時計」高木 せつ子さんのエッセイ
「初めて自分で買った時計の思い出」伴 靖雄さんのエッセイ
「束の間の休息」星逢児さんのエッセイ
「さあ、みんなでお別れを言いましょう」
母にそう言われ、私も一輪の花をそっと置いた。
しずかに目を閉じている祖父はまるで眠っているようだ。幼い私は、まだ人が死ぬことの意味がよく理解できていなかった。
「おじいちゃんが死んだのよ、明日はお葬式だから」
目を真っ赤にしてそう伝える母の言葉もうわのそら、
前の晩からお通夜で親戚の子供達が集まってきたのが
うれしくて家中をはしゃいで走り回っていたようだ。しかしさすがに次の日は違っていた。
朝から見知らぬおとなたちが入れ替わり弔問に訪れる。
そしてふすまをとったふた間の部屋が
黒い服でいっぱいに埋められた時に、
お坊さんのお経がはじまった。
お行儀よく座っていたので、
だんだんと足がしびれてきた。
足のしびれとともに、悲しみがこみあげてきた。
もう祖父は目をさまさないし、
いっしょに遊ぶこともできない、
やさしかった祖父とのことがいっぱい浮かんできた。焼香もひととおり終わり、
いよいよ永遠のお別れの時である。
一輪の花を置くときに、手が少しふるえた。
もう一度祖父の顔をのぞきみる。
しっかりあわせている両手の前に
愛用の腕時計が、そっと置かれてあった。1時32分、
ついこないだ習ったやり方で時間をよんでみる。
1時33分、あれ、針が動いた!
祖父はもう動かないのに、
この時計が生き物のように動いている事が
とてもに奇妙に感じた。
「お母さん、これ!」
私はそういって、さっとその時計をつかみとったのだった。あれからもう40年もたつのか。
ゆるくてぬけそうだった時計も、
今ではぎゅっと手首をしめつける。最近、この腕時計が私に語りかける。
「あの時はありがとう、もう駄目かとおもったよ。
君の勇敢な行為で助かったよ。
ご主人といっしょに黒こげも、まあ悪くはないが、
まだまだ動けるのだから、頑張らないと」私がつかみとってその時計をすくいだしたのはほんの二秒のできごと、
まさに二秒間の奇跡だったのである。カッチカッチカッチ、
「最後まで、あきらめるなよ」
時計が時々そう言って私を励ますのだ。
大学内の循環バスを待つ私の背中に何かがあたり、近くの芝生の上に落ちた。腕時計だった。それを拾い上げるや否や、私の前に立つ学生寮の2階の窓から顔を出し、「あのー、私の時計、大丈夫ですか?」と心配げに私が握る腕時計を見つめる日本人の女性がいた。それがスワミとスワミの古時計との出会いだった。それから私とスワミは次第に親しくなり、会うたびにスワミのジーンズのベルト通しの所にいつも下がっている、私とスワミを結び付けた赤い糸ならぬ赤い革バンドの女性用のエスプリの腕時計に感謝する私だった。
10歳の時に自分の小遣いで買ったこの腕時計をスワミは大変気に入っていて、折に触れて『おじいさんの古時計』のメロディで「小さな可愛い古時計、スワミちゃんの時計、10年いつも動いて来たご自慢の時計さ。スワミちゃんの病気の時に買ってきた時計さ。いつもいつも動いてるこの時計。」と替え歌を歌った。耳をあてると「スワミ、がんばれ!」と不思議にも聞こえるこの腕時計は10年間ずっと彼女を元気付けて来たのだった。
スワミとの3ヶ月はあっという間に過ぎ、夏期客員講師としてインディアナ大に来ていた私はオレゴンに戻る前、スワミにプロポーズした。彼女は、「私がオレゴンに行くまでの私の変わり!」と答えながら私に彼女の腕時計を渡した。しかし、スワミはオレゴンに来ることはなかった。彼女は交通事故に遭い、私が病院に着いた時にはスワミは危篤状態だった。真夜中、私の手にしっかり握られていた彼女の時計が突然止まった!やがてそこには「天国に昇る・・、時計ともお別れ・・」と口ずさみ、ぼう然と立ち尽くす私がいた。
私は辛い時、スワミの腕時計を耳にあて、今は「エッセ(エリック先生)、がんばれ!」と聞こえる秒音を聞きながら、「がんばらなきゃ!」と奮起する、私の愛したスワミの分までも
当時、彼氏だった現・旦那とのおつき合いが4年目を迎えた時に、
お互いに記念のプレゼントをしようということになり、いろいろ考えて、私は腕時計を贈る事にしました。
遠距離恋愛で、休みがなかなか合わなかった私達。
その日は、やっと予定が合って、2人で街へ買い物に行きました。
小さな時計屋さんのショーケースの中に、彼氏が欲しいと言った時計があったので、買ってあげました。
値札を見まちがえた私が、思っていた金額と違う値段を言われて焦っていると、お店の方が「いいよ、お姉ちゃんの思っていた値段でかまわないよ」と言って下さり、本当の値段よりも安く売って下さいました。
それからしばらくして、その時計屋さんはなくなってしまいましたが、あの時買った腕時計は、今も主人が毎日愛用しています。
買った当時、「いつまでも一緒に時を重ねていけたらいいな」と思っていた彼氏と結婚することができ、すぐに娘を授かり、家族になった今、
幸せを感じる毎日です。
いつまでも腕時計に、私達家族を見守っていってほしいので、大切に使うように主人によく言って聞かせます!!
昭和48年の3月。
私は、初めて腕時計を買ってもらった。小学4年生の時だ。父が、当時勤めていた会社の研修で、ハワイへ行った時のお土産だった。その頃、
小学生で腕時計を持っている子供などいなく、私は嬉しくて仕方なかった。その時計は、黄色のバンドのトムとジェリ−の時計だった。自慢の時計は、それ以来、何処へ行くにも私の左手首にはまっていた。
ネジ巻きだった時計は、いつも正確に時を刻んでいた。いや、むしろ私には、時よりも、手首にはまっている事の方が重要だったような気がする。時には、サウスポ−のふりをして右手首にはめたり、夏には日焼けのあとを自慢げにしるす、私自身のオシャレだった。
中学生になっても、相変わらず黄色の時計は、私の左手首にあった。
黄色のそれは、結構目立つし、ハワイ土産というのも、何やらブランドのように思っていたに違いない。いつも。時計は一緒だった。
高校に入学する頃、友人の誰もが腕時計を買ってもらっていた。私は迷った。16才の私に、トムとジェリ−は似つかわしくない気もした。
が、やはり、新品は欲しくなかった。黄色の時計が、自分に一番似合っていると思った。
父の土産の時計は、5年以上私の分身だった。ある日、バンドが切れ、時も正確に刻まなくなった。もう修理ができないとわかった日、私は泣いた。大事な大事な時計のかわりはみつからないと、私は泣いた。
そんな私に父が、自分の時計の中から1つ差し出した。男物の時計は大きく、私には少し重かった。セイコ−の文字が入った父の時計を、あの日以来、ずっと使っている。何故か自分で時計を買う気がせず、年を重ねてきた。
時計は、父からもらう物。そう心に刻まれているからかもしれない。
始めて腕時計を私が買ってもらったのは小学校の六年生の時でした。海軍の軍人だった父はスイス製の子供には勿体ないような立派な小さな時計でした。母に云われて毎日リューズを巻き大切に使っておりました。
その父も戦死して母も後を追うように原爆で亡くなりました。
やがて結婚して男の子が生れ、終戦後の厳しい生活の中で、私は子供がいても出来るような今では何処を探しても見当たらない筆耕の仕事を家で毎日ガリバンに向かってガリガリと書いておりました。その時計は机の上においていました。傍らで息子はつたい歩きをしながらおとなしく遊んでいたのですが、ふと気がつくと私の宝物がありません。子供が何処かにもっていったのではとおもちゃ箱や家中を探しましたが、何処にもありません。とうとう諦めて、二人目の子供が生れる前年に腕時計を主人とペアで買いました。その時の腕時計を未だ四十六年たった今でも腕につけております。
娘の年より一つ上の腕時計です。前のに懲りて買った時からお風呂に入る時以外は必ず腕につけております。時計が止まった時は修繕に出しますが、新しく買った方が安いのに私にとっては一生に二つ目の大切な大切な腕時計なのです。
一緒に買った主人の腕時計はとっくに毀れて後、何回買い換えたのかわからないくらいです。
主人ももう亡くなってから二十年近くなりますが、私の腕時計は私の腕で時を今も刻み続けています。きっとお墓の中まで一緒に持って入るのだと思っています。
母はいつも私にやさしかった。あれは、私が幼稚園の頃だったと思う。大人たちがしている「腕時計」が欲しかった。何気なく、腕に目をやり、時間を確認する仕草に憧れていたのだ。でも、当時はクオーツ時計が出始めた頃で、子供に買い与えるのに適切な安価な時計は少なかった。それでも、母は内職して手に入れたわずかばかりのお金の中から、買ってあげるよ、と言う。私は天にも昇るほど嬉しかった。
母に連れられて、早速、近所の時計店にいった。「これなんか、いいんじゃない?」母はミッキーマウスの時計を指差した。「いやだ、こっちがいい」と言って私が見ていたのは金属バンドのシンプルなSEIKOの時計だった。もちろん、ミッキーマウス時計よりも高価だった。でも私は袖をちらっとめくり、左腕を目の前に持っていき、「もう、三時か」なんて大人みたいに呟いてみたかったのだ。それには大人がしている様な時計じゃなくてはならなかった。店員さんも「こっちにしとけば、まあ、ものがしっかりしてるから、10年はもちますよ」と私の味方をしてくれた。しぶしぶ、母はその時計を買ってくれた。ぜんまいを巻いてもらい、時刻をあわせ、サイズ調整をしてもらって、腕に嵌めてもらうと、うれしくて仕方がなかった。母はそんな私を見てニコニコしながら、「いい時計が買えてよかったね、大切にしなきゃだめだよ」と言った。
腕時計は私の宝物となった。大切にしていたが、さすがに中学に入る頃にはバンドが壊れてしまった。そこで、バンドを外してしまって、キーホルダーを取り付ける事にした。その時計は中学を卒業するまで、使い続けた。時計店の定員さんが言った「10年以上使えます」は本当だった。
昨年、母が他界した。時計を買ってもらって有頂天の私を、嬉しそうに見つめていた母。それは、母の一生において最も幸せな時期だったのだと思う。あの時のやさしい笑顔を今でも忘れることはない。
「かなわなかった夢の行方」高根 広海さんのエッセイ (7月のベストエッセイ)
その時、僕は高校3年生だった。その頃の僕は自分の実力では到底合格しそうもない大学ばかりを志して、思わしくない模擬テストの結果を返されるたびにイライラを募らせていた。
その時のクラスの担任は、生物の授業中によく自分の若い頃の夢を面白おかしく語って聞かせてくる人だった。彼の夢は大学院に進んでイワナの研究をする事だったらしい。しかし、院に進む段階で小さなミスを犯し自分の大切な卒業研究を全てふいにしてしまったのだという。
そんな担任の授業を受けていた僕は、自分のかなわなかった夢を楽しそうに語る彼の神経が理解できなかった。それは、当時の僕が自分の夢をどうしても諦め切れない気分でいたし、諦めるものでもないと思っていたからだった。
そして担任との面談中、僕はふと彼のつけている時計に目が行った。それは黒い革のベルトにいぶし銀のイワナの装飾が施されている重い感じの時計だった。そして、その頃のひねくれた僕はそれを見て、諦めた夢をこういう形で引きずるのはごめんだと思った。
結局僕は、担任の止めるのも聞かずに自分の学力では手の届きそうにない大学ばかりを受験して全て不合格となった。浪人してもそれは変わず、翌年、仕方がなく自分の実力で合格する事ができた等身大の大学に入学した。
あれから僕は当時の夢とは全く違う道を歩いているが、今でも悶々とすると担任の着けていたイワナの装飾の時計を象徴のようにして思い出す。僕はずっと分からないでいる。彼の夢や想いは彼の心の中でどのような扱いとなって治まっているのだろうか。憧れてかなわなかった夢はどう自分の中で片付ければ良いのだろうか。そんな疑問は誰にも聞けないまま今も僕の心の中でくすぶっている。
「さぁ、ちぃ(私の愛称)、時計を買いに行こう」
唐突に、テレビの前の父がすっくと立ち上がった。
今から三十年前のことである。憧れだった航空会社に就職した私は、翌週の入社式、引き続いて一週間の合宿研修を目前にし、準備に余念がなかった。
私の時計はその八年前、中学入学時に父が、「中学生が時計なんか・・・・・・」という母の言葉を遮って入学祝にと買ってくれたものだ。金の縁取りに四角い白の文字盤のそれは、当初の赤のベルトから何度も着替え、その時は金色の鎖をつけ少々大人ぽくなっていた。
「いい、大丈夫、まだ使えるもの。勿体無いから要らない」
「いいから、早く用意しなさい」
と言いながら、もう玄関に向かっている。慌てて後を追う私の目に、母の不機嫌そうな表情が、一瞬、しかしはっきりと焼き付いた。
外は雨、傘をさしながら前後になって歩いた。駅前の時計店に着くと、
「娘がスチュワーデスに受かったものですからお祝いにと思って。お客さんの前で(腕を出しても)恥ずかしくない、ちょっといいのをください」
問わず語りの父に、愛想のいい店主の出してきてくれたものは、ぽっこり厚めの金の文字盤、クロコダイルの黒のベルト、当時流行りのオメガであった。
義理の仲の母には、幼い頃からいつも一歩引いていた私に対する、言葉に不器用な父の精一杯の意思表示、やさしさだったのだろう。嬉しいはずが何故か切なかった。
その父が逝って早や二十年、父娘の情愛の証ともなった二本の時計も、今は箪笥の中で静かに休眠中である。ふとした折りに目にするそれらは、あの帰り道、そぼ降る雨の中、父の胸中が痛い程に伝わってきて、後ろ姿が涙で滲んだことを思い起こさせてくれる。
「イモウトの秘密」伊藤 まきさんのエッセイ (7月のベストエッセイ)
幼い頃は、お兄ちゃんのお嫁さんになるのが夢だった。しだいに兄にまとわりつくことはしなくったが、無口だが優しい兄はずっと私の自慢だった。
同級生だったタカコが、その兄に恋をした。しかし、兄はタカコのことなど全く気がつかない様子で、彼女が家に来ても、無愛想に頭を下げるだけだった。
兄は東京の大学に進学し、二年後、私は地元の銀行に就職し、タカコは東京の専門学校へ進んだ。その年の夏、久しぶりにタカコが家に遊びに来て、たまたま帰省していた兄も珍しく私たちの会話に加わった。私は、急にタカコが憎らしくなった。私の知らない東京の話をしているからなのか、兄と親しげに話しているのがイヤだったのか、東京に戻る日の待ち合わせの約束までしているタカコに、驚くほど激しく嫉妬している自分がいた。
私は二人が同じ電車で東京へ帰るのを妨害しようと思った。
その日の早朝、私は兄の時計の針を一時間遅らせた。私の住む町では、一日に五、六本しか電車は通らず、一本乗り遅れたら次の電車まで何時間も待たなくてはならないのだ。
あれから十年が経ち、タカコは今、私の義姉である。あの日のことは、喉にささった魚の小骨のようにずっとひっかかっていたから、いつか謝ろうと思っていたが、先日タカコからこんな話を聞いた。
「あの日ね、家の用事で約束の電車に遅れちゃって、もうダメだと思って駅に行ったら、あの人、ホームで腕時計を見ながら待っててくれたのよ。『俺も遅れた。』なんて言っちゃって。」
心ならずも二人の恋の手助けをしたのは、私だったのである。義姉をがっかりさせないため、私はあの日のことは、自分だけの秘密にすることにした。
愛用している銀色の時計には無数の傷がついている。竜頭の上の金属も少しかけていて、それはそれは無惨な外見である。1995年1月17日に刻まれたものである。
この時計との出会いは10年前。生活費を捻出するために家庭教師のアルバイトをしていた大学時代、無事大学合格を果たした生徒のお母さんから頂いたものである。日々時間に追われ、身なりも構わない私にせめてとの思いが込められていた。
無地の文字盤からは正確な時間は分かりにくいようになっている。それが時間に少しルーズだった私には効果的であった。何しろ、正確な時間が分からないのだ。待ち合わせに遅れないよう、はやめに行動する習慣がついた。それだけでもありがたいのだが、学業にクラブ活動、アルバイトと分単位の時間に追われていた私に、自由な時間の概念をも与えてくれた。唯一にして大切な時計で、毎日私の手元で働いていた。
阪神大震災が発生した朝もこの時計を左手首につけていた。1995年1月17日、生涯忘れてはいけない衝撃の一日であった。下宿先は全壊だったが、私は生きていた。ガスの臭いが充満し、火と埃だらけの街を走り回った長い一日の終わりに体育館でふと時計をみると、傷が沢山ついていた。腕時計も私と一緒に、傷つきながらも、街をみていたのである。
大学卒業後関西を離れ、結婚して普通の主婦になった。世の中にはもっと贅沢できれいな時計は沢山ある。30近い女性に傷だらけの時計というのは似つかわしくないのかもしれない。しかし、私の歴史を見てきたこの時計を手放すことなどできないのである。
父が大学の入学祝いに時計を買ってくれた。掌に載せると、心地いい重みが身体の奥まで伝わってきた。思えば父が直接に何かを買ってくれたのは、それが初めてのことだったろう。照れくさかったのか、言葉もなしに時計ばかりが渡された。受け取る側もやはりなんだか照れくさく、うんでもすんでもなく受け取った。腕にはめて日にかざすと、文字盤の深い緑の色がちょうど萌え出した若葉のようで、時刻を確かめる度に顔がゆるんだ。うふふ。手首に感じる初めての重みが、大人の証そのものだった。必要もないのに時々目が文字盤の上に落ちている。うふっ。
その大好きだった時計を無くしてしまった。大学の芸術の授業の仕上げに実際に劇を上演する発表会の当日。小学校以来学芸会やら発表会に縁遠かった私が、公会堂の舞台に立つというので、父と母と二人が見に来た。来なくていいと言ったのに!。舞台の上から両親の顔を見つけた。途端ふっと頭の中が空白になった。せりふが消えた。はっと相手役の顔を見て、自分を取り戻すまでのほんのわずかな時間が、その時は何と長かったことか。幕間、高ぶった気持ちをなだめるために、飲み物を買いに自動販売機に行った。時計を外したことは意識にない。手首が何となく寂しいことに気付いたのは、劇が終わり、客席が空っぽになり、体の中の熱気がすっとどこかに抜け落ちてからだ。あわてて楽屋の中を探し回った。影も形も見あたらない。誰に聞いても知らないという。体中から力が抜けた。しかられるかと思った。が、手渡した時と同じように、父は時計については一言も言わなかった。ただ劇を「楽しんだ」と言っただけ。
就職後、今度は自分で時計を買おうと緑の文字盤を探したが、どこにも同じものは見つからなかった。娘の就職を見届けると間もなく逝った父の、唯一の私へのプレゼント。消えてしまって尚更に、今も鮮烈な深い森のような緑のきらめき。
いまから30年以上前になるだろうか、大学を出て3年ほど勤めた会社が倒産し、新しい会社を探して入ったのが外資系企業だった。当時は、外資系企業などというものは、日本の会社に入れなくて、しかも一寸横文字が読めるような連中が行く所と相場が決まっていた。
そこはドイツの会社で、ドイツ語か英語が出来ないと入れないというので、どうしようか迷ったのだが、当たって砕けろという気持ちで入社試験を受けてみた。
電話で日時を決め、出かけた所が丸の内のオフィス街のど真ん中。潰れた会社は、木造の今にも建物までもが潰れそうな酷い所だった。従って、丸の内はビルで囲まれた御殿のように感じられた。
その会社は、ドイツ本社の日本事務所みたいな小さな所で、株式会社ではなく、有限会社。丸の内のオフィス街のど真ん中に有限会社が有るということ自体不思議に思った。それに、有限会社という会社と関わったのも、その時が初めてだった。
応接室に通されたのだが、恐らくドイツ本国から取り寄せたのだろう分厚い皮が張り巡らされているソファーに腰掛けて待っていろということで、恐る恐るそこに腰を下ろした。皮の軟らかい匂いが、何か途方もなく贅沢に思えた。やがて、社長と担当者だという二人のドイツ人が入ってきた。しかし、先刻の日本人は来ない。ドイツ人から直接面接を受けるのかと思うともう観念した。
それでもまあ、なんとか意思が通じたようで入社することになった。そして、入社して4ヶ月目がボーナス支給日だった。どうせお印程度だと思っていた金額が、なんと給料の2.5ヶ月分出た。最初明細書を見た時、0が一つ多いが目のせいだと思ったのだが、良く見るとやはり間違いない2.5ヶ月だった。
その金で買ったのが「LORD MATIC 23JEWELS」だった。値段が、記憶がはっきりしないが、確か15,000円だったと思うが、これは確信が無い。給料が5万円そこそこの時代だ。
それから30数年、何度も分解掃除を繰り返しながら、現在でも使っている。ゼンマイの時計だというと、ほとんどの人が「おお、本当だ」と感嘆の声を挙げる。一生使える時計だと自負している。
大事にしていた腕時計が壊れた。台風の中歩いた翌日だった。今までこんなことはなかった。何より私の時計はウォーターレジスタントで、台風が来ようと雪が降ろうと一向にお構いなしだったのに。それとも単に電池と愛情が足りないのだろうか。
ただ呆けていても仕方がないので壊れた時計を持って街を彷徨っていると運良く時計屋を見つけた。店には若い店員の他にかなり年配のご老人がひとり。偏見かもしれないが私の中で「時計直し」はお爺さんと決まっている。
針の止まってしまった腕時計を差し出すと彼は見事な速さで時計を分解していった。アッと言う間に私の時計はバラバラになり、それを見ていた私は不思議な心地よさと軽い喪失感を覚えた。
どうやら直接の原因は電池切れらしいのだが部品の掃除もした方が良いとのことであった。お世話になった時計をたまには休ませてあげたい。定期的に掃除をすれば少しは寿命が延びるだろうか。「○万円程かかりますよ」とご老人の声。普通庶民の腕時計修理代は数千円がせいぜいである。しかし確か以前電池交換した時も「電池が特注だから」と言われてかなり代金をふんだくられた。そんなにコイツは特別なのか?…と疑問を抱きつつ口から流れ出た言葉は「構いません」。「大事な腕時計だから大切にしたい」と付け加えるとお爺さんは目を細めて一層嬉しそうに微笑した。訝しげに若い店員が見守る中、私はやはり「時計直しはお爺さん」であるという揺るぎない偏見を再構築した。
彼らは時計と共に生きているのである。時計と同じ時間を刻み、その瞬間を慈しむことを忘れない。彫りの深い皺と器用な手がその証であった。
私の腕時計が直るのは約四週間後。それまでにどれだけ世の中が変わっているだろう。私の心も時計とともに掃除せねばなるまい。秋の訪れを全身で受け止めつつ時計店を背にした。
(注)この「思い出の腕時計エッセイ募集」に書いていただいたエッセイの著作権は、セイコーインスツルメンツ株式会社に帰属します。予めご了承下さい。