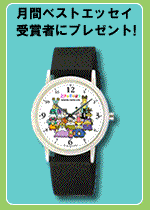�@
2002�N�̍�i
1-2���@3���@4���@5���@6���@7���@8���@9-10���@11-12��
�@11-12�� �i���e���j
11���x�̃x�X�g�G�b�Z�C�R���ɓ������āA�����i�������Ȃ��������߁A�����ǂŋ��c�̌��ʁA12���x�����i�ƍ��킹�ĐR�������Ă����������Ƃɂ������܂����B��낵�����肢�������܂��B
�u���̏��߂Ă̘r���v�v���X�@���b�q����̃G�b�Z�C
�u���Ƃ��ꂽ�H��ꂽ�r���v�v�����@�g������̃G�b�Z�C
�u��̖�̘r���v�v�]���@�݂ǂ肳��̃G�b�Z�C
�u�؋�����̎��v�vKentaro����̃G�b�Z�C
�u�킽���̎O��̐_��v����@���炳��̃G�b�Z�C
�u���l�ߑ����āv���@����q����̃G�b�Z�C
�u�ᒎ�v�q���@��������̃G�b�Z�C
�u�^�C���X���b�v�������v�v���{�@�E����̃G�b�Z�C
�u�������r���v�v�ē��@���q����̃G�b�Z�C
�u�V���v���v���c�@�҂���̃G�b�Z�C
�u�����ċ������v���c���@���ꂳ��̃G�b�Z�C
�u�q�[���[�v�p�J�@��������̃G�b�Z�C
�u�l�̃p�[�g�i�[�v����@�T�j����̃G�b�Z�C
�u��Ǝ��̎��v�v��A�@���b����̃G�b�Z�C
�u�l���̔��t�ҁv�����@���コ��̃G�b�Z�C
�u�Q�O�N�Ԃ�̘r���v�v�{���@�u�s����̃G�b�Z�C
�u���A�ڂ̑O�ɂ���A���Ӂv�{�R�@���q����̃G�b�Z�C
�u���F�̃y�A�E�H�b�`�v�����@���q����̃G�b�Z�C
�u���r�̘r���v�v�����@������̃G�b�Z�C
�u�r���v�̐S���e�X�g�v���c�@�M�q����̃G�b�Z�C
�u��������Ɂv�c���@�^�m�q����̃G�b�Z�C
�u��������₳��̘r���v�v�Γc�@���q����̃G�b�Z�C
�u�v���o�̘r���v�v�O�V�@�v���q����̃G�b�Z�C
�u���v��������q���̐���ցv����@�a�炳��̃G�b�Z�C
�u��ȑz���Łv�Ȃ����@����������̃G�b�Z�C
�u����������̊肢�A����������̋F��B�v�䂤����̃G�b�Z�C�@11-12���̃x�X�g�G�b�Z�C
�u�T���^�N���[�X����̑��蕨�v�É�@���~����̃G�b�Z�C
�u���߂Ă̘r���v�v���Y�@�G������̃G�b�Z�C
�u�ӂ��̎��ԁv�����@�������̃G�b�Z�C
�u���v�v�Ζ�@�A�q����̃G�b�Z�C
�u�r���v�̎v���o�v���c��������̃G�b�Z�C
�u�P�V�N�Ԃ��肪�Ƃ��v�R���@���q����̃G�b�Z�C
�u���߂Ă̘r���v�v�����@�p������̃G�b�Z�C
�u��l�̎��v�v���c�@���q����̃G�b�Z�C
�u�������ԁv��������̃G�b�Z�C
�u�l�̃A���F�j���[�v���c�@��������̃G�b�Z�C
�u�����r���v�������Ȃ��킯�v�{��@�בコ��̃G�b�Z�C
�u���܂���v�\���@��������̃G�b�Z�C�@11-12���̃x�X�g�G�b�Z�C
�u�r �� �E �J ���v���R�@�b������̃G�b�Z�C
�u�� ���v���R�@�b������̃G�b�Z�C
�u�r���v���Ăѓ����n�߂�v�{���@�u�s����̃G�b�Z�C
�u�r���v���ق����vatsuko����̃G�b�Z�C
�u���߂Ă̘r���v�v���c�@����������̃G�b�Z�C
�u�싞���v���c�@���q����̃G�b�Z�C
�u�w��ȁv���c�@����Y����̃G�b�Z�C
�u���E���̊���ɂāv�b��@�ɐD����̃G�b�Z�C
�u���̘r���v����v�㓡�@���v����̃G�b�Z�C
�u���̎���m�炳��āv�����@�q�O����̃G�b�Z�C
�u�⍥���Ƙr���v�v�{��@�j�N����̃G�b�Z�C
�u�����p���z���v�����@�a�q����̃G�b�Z�C
�u�����̎咣�B�v���肱��������̃G�b�Z�C
�u���a�{�P�H�v���� �z�q����̃G�b�Z�C
�u������̑厖�ȑ��蕨�v�n�Ӂ@����Ђ�����̃G�b�Z�C
�u���߂Ă̘r���v�v�R���@��q����̃G�b�Z�C
�u�r���v�̂��l�сv�㓡�@������̃G�b�Z�C
�u�q��đ��ƋL�O�܁v���c�@�[�q����̃G�b�Z�C
�u���F�����v�v���c�@��������̃G�b�Z�C
�u�A���N�����v�v�r��@�M��Y����̃G�b�Z�C
�u���v�ƈꏏ�ɉ߂��������ԁv���c�@�z�q����̃G�b�Z�C
�u�o����̎��v�v�����@��������̃G�b�Z�C
�u�����݂����̘r���v�v�����@��������̃G�b�Z�C
�u�M�d�i���������v�v�����҂���̃G�b�Z�C
�u���v�v���}���@��v����̃G�b�Z�C
�u�l�ԏL�����v�v�����@���H����̃G�b�Z�C
�u�v�[���v�N�q����̃G�b�Z�C�@11-12���̃x�X�g�G�b�Z�C
�u�������ЂƂ́A�����B�v�����@��������̃G�b�Z�C
�u�����������f�W�^���̘r���v�v��������̃G�b�Z�C
�u���̂Ƃ��v�ԍ�@��������̃G�b�Z�C
�u���̏��߂Ă̘r���v�v���X�@���b�q����̃G�b�Z�C
�������N�O�̎��ɂȂ�ł��傤�B
���̏��߂Ă̘r���v�́A���̘r�ɉ���������鎖�Ȃ��A�����痣��Ă����Ă��܂��܂����B
������\�ɂȂ鎞�A�c�ꂪ�����Ă��ꂽ���̂ł��B�Ȃ��A����Ă������̂��ƌ����܂��ƁA�́A�O�\�N�ȏ���O�̎��B�g�C���̓{�b�g���֏��ƌ����āA�����𗎂Ƃ��ƁA�X�g���[�g�ɁA�����ɗ����Ă��܂��̂ł��B�����E�����̏o���Ȃ��g�C���ł����B�c��́A�߂���������Ă��܂����B����Ⴛ���ł���B�����ė^���āA������̏o�����ł�����B�������A�r�b�N���ł��B�V���b�N�ł����B
���̏u�ԁA�����N�����̂��L���ɂȂ��̂ł��B�����ƂĂ��₹�Ă��āA�r�����R�ׂ��A���ʂ̘r���v�͂����ł����B�~�ߋ����Â������̂��A���ꂪ�͂��ꂽ�̂��́A�m���ł͂Ȃ��킯�ŁB
�����I�ƌ����Ԃ̏o�����ł����B
���̗L�����v�X�̕i���ŁA�l�i���ƂĂ������A�c��ɂ͐\����Ȃ��v���Ă���܂��B
����ȗ��r���v�́A���N�����̘r�ɂ��鎖�͂���܂���ł����B
�������A�d�������Ă����ŁA�ǂ����Ă��K�v�ɂȂ�A�܁A�Z�N��Ɏ����Ŕ������ƂɂȂ�܂����B
���̎����A���͖S���c��ɁA�������Ă��炢�܂����B���̎��͉̂i���t���������Ă܂����B������������̂ł����B
�������܂菈�ɗ��������̎��v���A�ǂ����ǂ�����āA���ǂ����Ă���Ȃ�āA���܂�l�������Ȃ��ł��ˁB�ł����̑厖�Ȏv���o�̂ЂƂȂ̂ł��B�c��́A���̐e����̐l�ł����B
�c��Ƙr���v�́A���������Ă��A�Y��Ă͂����Ȃ����݂ł��B
�u���Ƃ��ꂽ�H��ꂽ�r���v�v�����@�g������̃G�b�Z�C
���͑吳�Z�N�̐���ł��B�q�포�w�Z���o�ďA�E���A�������͂����Ĕ������ƌ��������̘r���v���ƂĂ���ɂ��Ă����B
�������w��N�̎��A�������̎��v�����ꂽ�B�����O�\�N���炢�o���r���v�ł����B
���R�͋��F�̈�l���w�Z�ɘr���v�����ė�������~�����Ȃ�A�����Ă����悤�ɂ�����������ł��B
���������C�Ɏ��v������d�������āA�אȂ̋��F���r���v�������Ă���ƌ����̂ŁA�r����O���ēn�����Ƃ����B
�̈ӂł͂Ȃ��Ǝv���������A�n�����Ǝv�����u�ԁA�r���v�����ɗ����Ă��܂����B
��u�A���F�����肽���Փ���}���ق��Ęr���v���E�����B���F�͒m���ӂł���̂��������A���肱�Ԃ����ł����Ă��̏�𗽂����B
���Ƃ��I���ƒ��ł����ꌬ�̎��v������Ɏ����čs�����B
���v������́u������������v�ƃA�b�T���������B�ǂ���畃���ĎO�C���⒲���Ɏ�������ł����㕨�ł������炵���B
���v������́u�ƂĂ��ǂ����v�������i��������������c�v�Ǝ����Ԃ߂�悤�ɂ��̘r���v��Ԃ��Ă��ꂽ�B
���ɂ͗��Ƃ��ĉ������C���Ɏ��������Ƃ������ɂ��āA�o�Z�̒��͉Ƃ��o��Ƃ��r�ɂ͂߂ďo�������B
�w�Z�ɒ����Ǝ��]�Ԃ̉ב䂩��J�o�������낷�Ƃ��A�r���v���J�o���̌��Ԃ������ĉ��H��ʊ�ŋ����ɓ������B
��P�����������낤���A������̗[�H���ɕ����ق��ď����ȕ�݂��o���Ď��ɂ��ꂽ�B�r���v�̐V�i�ł������B
���͉��̂��V�i�̘r���v�ɑf���Ɋ�ׂȂ������B���Ƃ��ĉ����̑�ɂ��Ă����r���v�����ɕ�������ł��B
���͗�������V�i�̘r���v���͂߂ēo�Z�����B���]�Ԓu����ŐV�i�̘r���v���O���J�o���ɔE���ċ����ɓ���悤�ɂ����B
���͎��v�����玄���������r���v�̘b���āA���̘r���v�����炵���B
�e���r�Ŏ��̎��r���v�Ɠ����̃R�}�[�V�����������ƐV�i�̘r���v�ɖڂ������S�傢�ɖ��������B
�O�N���̉ċx�݂��I��j�w���ɂȂ�Ƌ��F�̔����߂����r���v���͂߂ēo�Z���n�߂��B
���������������]�Ԓu����Řr���v���O�����͖����Ȃ�A�r���v���r�ɗL�邱�Ƃ��ӎ�����@����Ȃ��Ȃ����B���̌Â��r���v�������ɂ��@���f�����Ƃ������Ă��ꂽ�悤�Ɏv���B
�u��̖�̘r���v�v�]���@�݂ǂ肳��̃G�b�Z�C
�����20�N���O�A���������OL���������̘b���B�������P���Ȓ�����A����s���łȂ���OL�d���̖��C�Ȃ��Ɍ�����Ȃ��玄�͂����̃I�t�B�X���猩����a���̎��v����݂߂Ă����B���̎��v��12���ɂȂ����炱�̋C�̒���I�t�B�X���瓦�����B���̎��v��5���ɂȂ������̃l�I���̏u������ʂ����u�����Ȃ��������ƁB����ȕ�炵���x���Ă����̂���w���ォ��̗��l�ŋ���̈ꗬ��Ђɋ߂Ă���E�̑��݂������BE�͒��g�Œ��n���T���A�����ǂ��炩�Ƃ����Ύ��̕Ўv���ł�����������I�Ƀf�[�g��ݒ肵����I�ɒ��茞��I�n�����������E���ނ̍D�݂̏����������ʂꂽ��A�������ތǓƊ��𖡂키�A����ȓ��X�𑗂��Ă����B
���̓��������������B1�����̌����̖�A����ɂ͐Ⴊ�����Ă����B���̌Ăяo����E�͏o�Ă������̖̂��炩�ɕs�@���������B�r���v������X�����S�����ɂ��炸�������B���͈����݂�킷�ׁA�吺�ŏ��旯�߂̂Ȃ��b�������B�u�d�������邩��v�ނ͓r���ŐȂ��������B���͗܂�K���ɉ�����l��̒���f�r�����B�u���Ă��ꂽ��ł��ˁB�v���̎������o���̂��鐺������߂����B�U������Ɠ����̍]���N���B�u�������Ă���Ȃ����Ǝv�������ǂ���ς藈�Ă��ꂽ�B�v�ނ͍~���Ɏ���������܂��j���g���������������ɔ��B���̎����͐���ނƌ��킵�����͂��Ǝv���������B���������̏ꏊ�ŔނƂ���������Ă��B�m���ҍ�����6���H�Y��ʂĂĂ��ɓ��]���Ȃ���r���v������Ɖ���6���B�u�����ǂ������A���Ă���āv���������ď��Ȃ��甯�̐�����ނ̘r���v�ɐႪ�����A�ނ̂ʂ�����̂�������͂����ɏ����Ă������B���ɂƂ��ĒP�Ȃ�C�̍��������ɉ߂��Ȃ������ނ�3���Ԃ���̒��A�r���v�����߂Ȃ��玄��҂��Ă��Ă��ꂽ�BK�Ƃ̃f�[�g�ł͈�����������ƂȂ��Ă��܂����r���v������l�����ԉ������J�ƂȂ����B���̌��l�͌����A�Ⴊ�~�邽�сA���̖���v�������B�����ē�l�̈��̕���͍����Ɏ�������ł���B
�u�؋�����̎��v�vKentaro����̃G�b�Z�C
�T�����[�}�������ɔ��ĉ�Ђ���߁A��ė��s�ɏo���B�o���O�ɓK���Șr���v���Ȃ��̂ŁA���̈��o��������Ǝ��e�����̂��ꂽ�r���v���o�Ă����B���̕ϓN���Ȃ����v�����A�ЂƂڂ��䂢���͕̂����Ղ̕Ћ��ɕ����������Ă��邱�Ƃ������B���������A�e���u�Ⴂ���A�k���œ��{�c�f���s�������ɋ�y�����ɂ����؋�����̎��v���v�Ȃ�Ă����Ԃ��Ă��ȂƎv���o�����B����������͓�ė��s�ɂ͂����炦�������ƁA�x���g�Ɠd�r��ւ����猩���ɐ����Ԃ����B
�x�l�Y�G������`���܂Ńo�X�ňړ�����n�R��l���ɂ����āA�������͎v���̑����ɗ������B�m��Ȃ����Ńo�X�������o����ďh��T�����ȂǁA�n�}�Ƃ��̎����������肾�����B����ǂ��납�A�e���́g�؋�����h�Ƃ������t�������̒��Ŗ��Ƀf�t�H��������āA���������̎��v�͈�̂����̂悤�ȑ��݂ɂȂ��Ă��܂����B
�^�钆�Ƀo�X�ɗh���Ă��鎞�ȂǁA�Ȃ����悭���e���Ɏv�������点���B�e���̐l���͂͂����ď[�����Ă��̂��ƁB�L���J�[�v����D���ȌÖ{���̃I���W�Ƃ������}�Ȉꏎ���ŏI������e���͍K���������̂��ƁB�Ⴍ���Ċ��ł������Ȃ��������ɁA�悭����Ȃ��Ƃ��l���Ă��܂��B�������r���v�Ɏc���ꂽ�����̏����e���ɂ��P�����u�Ԃ����������Ƃ������������Ă���悤�ȋC�������B�Ⴉ�肵���̂ƃ`�������W���_�̂܂܂ɓ��{�k���c�f�ɔ�яo���A�^�Ă̓��{���S�O�L���A�Q�����������ĕ������Ƃ����B�����b�N�ɏ������u���{�c�f���v�̕����B�߂��s���h���C�o�[����u������[�v�̈ꌾ�������������Ƃ����B
��Ă���߂�ƋG�߂͓�߂��Ă���.�B��蓾���Ȃ��l�͂܂��T�����[�}�����n�߂��B���ɂ܂݂ꂽ�s�V���c�̑���ɂ܂��X�[�c�𒅂鐶���ɂȂ������A�����������̑��������v�͂܂��g�ɕt�����܂܂��B�l�ɕ������u���{�Ɠ�Ă̏c�f���s���o�������؋�����̎��v���v�Ɠ����邱�Ƃɂ��Ă���B
�u�킽���̎O��̐_��v����@���炳��̃G�b�Z�C
�r���v�Ɩ��N�M�ƃJ�����́A�j�̎O��̐_�킾�Ǝv���B���Ȃ��Ƃ��킽���ɂ͂����ł���B���r�Ɏ��v�����A�㒅�ɖ��N�M�������A���ɃJ�������킽���̊O�o�p���B���ꂼ��Ɏv�����ꂪ����B�킽���͍����Ȏ��v�͂ł��Ȃ��B���܂܂łɋL�������鎞�v�ł��ܖ��~�ȏ�̂��̂͂Ȃ��B�ł��킽���͎����őI��Ŕ��������v�͑�ɂ���B��������͖�������̂Ƃ��Ďg��������B������t�@�b�V�����Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�̂̈ꕔ���Ƃ��čl���Ă���B���⊴���Ă���̂�������Ȃ��B�Ƃɂ������C�ɂ͂���Ƃ��ȊO�͂����r�ɂ��Ă���B���Ă��Ȃ��Ɨ��������Ȃ��̂ł���B
�킽���͐M�B�ɓ߂̐��܂�ł���B�����֏o��Ƃ��A�����҂̌Z���킽���ɂ��ꂽ���v���A�킽���̐��U�ŏ��߂Ă̎��v�ł������B�I���K�̕��������̂������B�����ŗ\���Z�ʂ������Ă����Ƃ��A�����āA�����Ȃ��̂ŋ߂��̎����ɂ������ꂽ�B��ܕS�~�������B�ł����ǎ�����o�����ɗ����Ă��܂����B���܂���l����Ɛɂ������Ƃ������Ǝv���B�Z����킽����������������̂͂��̎��v�����߂Ă��������炾�B���炭���v�Ȃ��̎�����߂����A��w���ɂȂ����Ƃ������Z�C�R�[�̃N�E�H�[�c�������Ă��ꂽ�B���[���b�p���s�ɍs���ăM���V���̃p���e�m���_�a�̌��̔����ق֍s�����Ƃ��A��Ԃ̒j���A�킽���̎��v���݂āA�����̘r�������ē������v���Ǝ������Č������B�N�E�H�[�c���܂����������ゾ�����̂��B���܂킽���̘r�ɂ��Ă���̂́A���łɏ\�N�ɂ��Ȃ邪�A�Z�C�R�[�X�s���b�c�ł���B�킽���͖������Ă���
�u���l�ߑ����āv���@����q����̃G�b�Z�C
�X�k�[�s�[�A�L�e�B�����A�~�b�L�[�}�E�X�c�B�����~���������̂͂���Șr���v�������B���w�Z���w�N�ɂȂ������̗F�l�B�́A�[���ɂȂ�Ƃ��ꌩ�悪���ɂ���ȉ����r���v�������t���Ắu�����A��Ȃ���v�Ƌ����čs�������̂��B
���v���ĂƐe�ɂ˂����Ă��甼�N�قnjo�߂��A����Ǝ�ɓ��ꂽ����́A�Ƃ��낪�n�������Ɏ������ށA�����f���C���A�ܘ_�������Ȃ��A��l���g���̂Ɠ��l�́A���n�̂��̂������B�����Ղɏ����ꂽ���́u�r�d�h�j�n�v�A���ꂾ���B�����ăg�h���̕�̌��t�B�u���Z���ɂȂ��Ă��g���̂�v�B�����T�N�����������ɂ́A�h���Z���h�Ƃ������t���ʂĂ��Ȃ����������Ɋ������A���̂����^�ʖڂȂ����̎��v���T�N�Ԃ����l�ߑ�����̂��c�ƁA�r���ɕ�ꂽ�̂������B
�c�T�N�Ȃ�Ă��������͂����Ƃ����ԁB����Ȃ��Ƃ�m�����̂́A���̎��v�Əo�����10�N���o���Ă��炾�낤���B�C���t�����Z�������������A��w�������������A�Љ�l�ɂȂ��������A���̎��v�����l�ߑ����Ă����B�v�t���ɂ͑����̕��C�͂������A����������A���͌��l�ߑ������B�����̎��������̎����A���܂̎��������̎����A�������̘r�Ŏ������ݑ��������̎��v�B�����A���l�߂Ă����͎̂��ł͂Ȃ��A���͂��̎��v�̕��������̂ł͂Ȃ����B����ȋC�������Ă���B
�����܂ŕt���������̂�����A�җ�̎�������̎����Ď��̎����A���Ɍ}���悤�B�����Č}����Ŋ��̎��A�b�j�̉����Ȃ��炱��ȕ��Ɏv���̂�������Ȃ��B
�u�T�N�Ȃ�Ă����Ƃ����ԁB�ꐶ�����āA�����Ƃ����ԁc�v�B
�H�킸�H�킸�̏d�J���B�@���ɎႭ�Ƃ��o�C�J���ΔȂł̘ؗ������ɂ����E���������B
�܌��ɂȂ�ƃV�x���A�r���ɂ��t���K���]�痢�A������𐁂��B�������ɂȂ�A�e���l�ꑐ���c�����Ƙؗ�������������Â�H����A���ɗL��G�߂ł͂���B
���ɂ͒m�炸�ɓő��̌�Z������炢�A�C������A���E���J�����܂�܁A����̒��A��ЂƂŕ���s�i�����F�����̎p�����Ă��N�ЂƂ���҂ƂĂȂ������B
���k�_�Əo��N�͗��ΊĎ��ᔲ�Q�A���A�Ŗ������ЁB�������ۂ��̃N�Z�Ɂu���͕S���A�؋����肳�I�v�Ɗ����A�_��̘J���i���{�[�g�j������ƁA���Ă邾���̃W���K�C�����K���ė��邵�A�Ⓚ�����u���u���k���Ȃ���ł����������A���ɋ���ŗ��郏�Łu�I�C�A���ʂȁI�H���H���I�v�܃c�̕����O�c�͎��ɉ�������z�������B
���ߐ��Ă����A���i�_���C�j���O�N��ɂ���Ɗ������̃h�T�N�T������A�����̊Ԃɂ��݂��̑��݂���Y�����A�������B�V�x���A�ł̔ߊ肾������w�i��w�j�ɂ��ʂ���g�ɂ͂Ȃ��Ă������A���ԃg���b�R�����̐l�v�ł��A����ɂ͈�H�����Ă����v���K���i�������B�w��̎��l�����牂�����Ȃ��A�v�������˂����A���s�̌��邱�Ƃɂ��A����ڂ��͖Y�ꂽ���A����Ǝ�����̘r���v����ɓ���u����A�Z�C�R�[�����I�v�l�v���ԂɌ����т炩�������A���Ɂu������v�Ƃ͌����Ă��]��Ȃ������B
�����A��w����A��ƈ�ʂ̎莆�uN���S���Ȃ����v�|�̖��䂩��ł���B
N�ׁ̈A���ɗ������Ƃ͉]���A���������r���v�������ɗ��A�肳���A����ƋD�Ԓ����H�ʁB
�������u�Ɍ��^�V�������̕�W�ɐᒎ�������Ă����B��W���v��t���L�������L�����B
�A��Βn���A�R�������Z�b�Z�Ǝ����ɕ��������A��N��A�Ăщ䂪�r�Ƀo�`�b�I�ƃn�}�����A���̓����]���ʊ��G�A����Ȋ����͐��������A���Y�꓾�ʑz���o�ƂȂ낤�B
�u�^�C���X���b�v�������v�v���{�@�E����̃G�b�Z�C
�C�O���s�ɍs�����͖Y��Ă������Ă����邩��A�����g��Ȃ��Ȃ������̂�I��Ŏ����čs���B�����炻�̎��A���͏��w���̎��ɔ����Ă�������X�k�[�s�[�̘r���v�������čs�����B����ɂ͂�����Ƃ����Q�[�����t���Ă��āA�A���[���ɂ͖����ȋ@�B������B�͂����茾���āA��\��̏������ɂ͂�����ƕs�ލ����Œp���������㕨�ł��������B
��s�@���x�g�i���̋�`�ɒ����āA���͔������A�O�����ɃG�X�e��傢�Ɋy���B�������āA������Ɠc�ɂ̕��֍s���Č��悤�Ƃ������ƂɂȂ�A���R����N���[�Y�֍s�����B�N���[�Y�ƌ����Ă��|���|���D�̂悤�Ȃ��̂œD���̏���ړ����邾���ł���B���͂͂����茾���Ă��܂���C�ł͂Ȃ������B
�������A���n�̐l���g�p���鏬���Ȗ̑D�Ő�̏�ɂ���Ă݂�ƁA���̍l���͈�]�����B���z�̌���������ʂ͓݂������Ă���A���R����̗Y��ȗ���̒��Ɏ���n�����Ă������B�S�n�悢���������삯�����A���X�����C���ɂȂ����B
�ݕӂŒ��H�����A��@�̕��ɐ�����Ă���ƌ��n�̎q���������W�܂��Ă����B����╨���肪�قƂ�ǂ����A�����Ȃ����Ƃ͂��Ȃ��B�܂��O���l���߂��炵���ďW�܂��Ă���悤�Ȋ����ł���B
���͕s�ӂɎ����̂͂߂Ă��鎞�v�̂��Ƃ��v���o���A�h��ȃA���[������炵�Ă݂��B��Ăɂ��ǂ낢�ĕ�������q�������B�`�r��������Ƒ傫���q�����������ł���B
�v���A�������w���̎��A����ɖ����������B
�u�{���Ɏ��v���~������Ȃ��āA���̃Q�[�����~������ł���B�v
��̌������Ƃ͐}���������B�ł��A�O���₷�����ɂ��Ă͂߂��炵���A���Ȃ蒷���Ԃ�����˂����Ă悤�₭�����Ă�������B
���������`�Ƃ������ƂƂ��Ɏ��̐S�͏\�̂킪�܂ܖ��ɋA���Ă����B���̎��A���͑��̉���������Y��Ă����Ђ�����ɂ��̎��v���������ɒ��߂Ă����B
�u�������r���v�v�ē��@���q����̃G�b�Z�C
���o�Y���鎞�܍˂̒�����A��A���Ƃɓ��������b�ɂȂ����̂ŁA�C��������̂���̂���ŕ��ɂ͏����������ăZ�C�R�[�̘r���v���v���[���g�����B
���Ɠ������O�̎��v�͂��Ƃ̂ق��厖�ɂ��āA�̂悤�Ɉ����Ă���ƕꂪ�悭���Ȃ���b���Ă��ꂽ�B���̒��ɑ�ɂ��܂�ꂽ���v�́A�������܂ɊO�o���鎞�����r�ɂ͂߂��A�ƂɋA��Ƃ������ɓ�������o���̒��ɂƌ�����ɁA���܂���̖ڂ����邱�Ƃ͖��������悤���B
�_�Պ��ɂȂ�ƕ���͉��l�̉䂪�ƂɗV�тɗ���̂��y���݂ɂ��Ă����A�u��x�����������Ƃ�������v�Ɗ��������Ɍ����Ă��ꂽ���̘r�ɂ͌ւ炵���ɂ�������r���v�������Ă����B
����ȕ������������̒���������މ@���J��Ԃ��悤�ɂȂ��ē�N�]��A��Ȏ��v�́A���������̖T��ɂ������B
�܂�Ŏ��v����������Ă���邩�̂悤�ɕ�͎v���Ă����̂����m��Ȃ��B
�d���a�ɂ͏��Ă���N�l���������߉ޗl�̐��܂ꂽ���ɋ��˂ŕ��͐Â��ɗ������Đ������B
�ǖقŗD�����������A��J�ɋ�J���d�ˁA�����l�߂��������A�S���瑸�h�ł��闝�z�̕��������B
��������Ă��邹�����������͑�D���ȕ��̎���M�����Ȃ��v���ł���B
�O�\�N�Ԏ��������̑�Ȏ��v�́A�a�@�ŕ������Ă��܂����B
�a�@�̕��B���K���ɒT���Ă��ꂽ�������炸�A�܂�ŕ��̕��g�������Ă��܂������̂悤�ɁA��͂Ђǂ��������肵�Ă���B
�����c�O�Ŏd�����Ȃ����A�S�D�������́A�����Ɣ��݂Ȃ��猾�����낤�u�N������Ɏg���Ă����Ȃ�A����ŗǂ���v�E�E�E�ƁB
�u��������ˁA��������v
�u�V���v���v���c�@�҂���̃G�b�Z�C
�V���v���ł��肽���Ǝv���Ȃ��炭����Ȃ����ɂ��ӂꂽ�����ɏZ��ł���B����Ȓ��ŗB��V���v���ł���̂��r���v�ł��B���X�r���v�ɂ������͂Ȃ������B���ł��悩�����B�P�O�O�O�~���炢�Ŕ����Ă���f�W�^���r���v��A�Q�[���Z���^�[�̌i�i�Q�[���Ŏ�����r���v�ŏ\���������B
����Ȃ�����A�ӂƓ��������v�X�Ō������r���v�B�����������Ă��炸�A���n�ɍ��Ə����̐Ԃ����ō\�����ꂽ�f�U�C���B�ƂĂ��Ȃ��V���v���ł͂��邪�A�Â��ȑ��݊�������A�S�e�S�e�Ƃ������̃f�U�C���̂��̂��������̒��ł͖ڗ����Ă����B�u�~�����v�ƁA�v�����B�r���v�ɂ͉��̂��������Ȃ����������Ȃ̂ɁA���̘r���v�͂ƂĂ��Ȃ��u�~�����v�ƁA�v�����B�ڂ����l�i�͖Y�ꂽ���A�Q���~�ゾ�����Ǝv���B���P�O���A���P�O�O��������r���v�ɔ�ׂ�Έ�����������Ȃ����A�P�O�O�O�~�Ŕ�������A�P�O�O�~�Ŏ�����肵���r���v�ōς܂��Ă��������ɂƂ��Ă͌����Ĉ������z�ł͂Ȃ������B�u�Q���~����b�c�����������āA�{�����������āE�E�E�v�Ƃ����Z�R�C�v�Z�������悬�������A���ǁA�����~�����Ƃ����~���ɂ͏��ĂȂ������B
�ȗ��A�O���邱�ƂȂ����̘r���v�����Ă���B�d���ȊO�A�ǂ��֍s���ɂ����̘r���v�����Ă���B�������N�̎����̎������ň�ԍs�������ɂ��Ă���̂͂��̘r���v��������Ȃ��B�d�r�ƃo���h�����������ȊO�A������邱�ƂȂ������Ă���Ă���B�̏Ⴕ����������C���������ł���B�ł��A�u���͂�������v�ŁA�C�����o���Ȃ��قǂ̏�ԂɂȂ鎞�����邩������Ȃ��B�������玩���͔߂��ނ̂��낤�B��̑�l���A�r���v���ꂽ�����ŁA�ƂĂ��߂��ނ̂��낤�B
���������邾���̖��͂��A���̘r���v�ɂ͂���B
�u�����ċ������v���c���@���ꂳ��̃G�b�Z�C
���w��N�̒a�����B��͎��ɏ����Ȕ�����n�����B�u�a�����v���[���g����v�B�����J����ƒ��ɂ͋�F�̘r���v�������Ă����B���������͂߂Ă݂��B�r���グ�Ċ�̑O�ɕ����Ղ��߂Â��A�����ƌ���B�����āA�p�x��ς��āA�܂������ƌ���B���ł͂Ȃ��[���}�C�d�|���̘r���v�B���͂��ꂵ���āA�O�o�̓x�ɂ͂߂��B
�ӂ���w�Z�ւ͂��̘r���v���͂߂čs���Ȃ������B�������A�����̎��͕ʂ������B�����A�����̊|�����v�͑O�̍��̏�ɂł͂Ȃ��A���ʂɊ|�����Ă����B�������A�o�ߎ��Ԃ��C�ɂȂ�B���v������ɂ͊�����Ɍ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�J���j���O�����Ă���悤�Ɏv���Ă����₾���A�Ȃɂ��s���R���B�ꂩ���������r���v������ɒu���Ď��������B�r���v�����̏�ɂ���ƂȂ����������B�W�����Ď������Ɏ��g�߂�̂��B��̗�܂����r���v�ɏ��ڂ��Ă���悤�ȋC�������B
���̘r���v�͍��Z�ɓ����Ă�������̘r�ɂ�������Ƃ͂߂��Ă����B
�������߂Ď�ɂ����r���v�B���ꂩ��O�\���N�B���̘r���v�͉��ڂɂȂ�̂��낤���B����������x�ɏ��������ɂȂ�r���v�B�������A���߂Ă�������r���v�́A���ɂƂ��ĕ�̉�����ƂƂ��ɁA���U�Y����Ȃ��r���v�ł���B�����āA���̎������މ��́A�����č��ł����̐S�̒��ɋ����Ă���̂ł���B
�u�q�[���[�v�p�J�@��������̃G�b�Z�C
���w�Z�U�N���̂Ƃ��A�i�w�m�֒ʂ����ƂɂȂ����B�{�l�͎͍��Z���炠����̂ƐM���Ă������A���e���ʂɒ��w�����߂Ă����킯�ł��Ȃ������̂ŁA�����Ȃ��悭�킩��Ȃ��܂ܒʂ��Ă����B���R�A���т����������B
����������̐l�B�̓X�S�������B�w�Z�ł͌������ƂȂ����������W��������������A���̏m���I���ƕʂ̏m�֒ʂ��c�����m�����������B���������F�B�͊F�r���v�����Ă��āA���Ԃ����킹�ĕ��܂��͕�e�Ɖ�A�߂��̋i���X�ŗ[�т�H�ׂ�Ǝ��̏m�������̂������B�܂����w���Ȃ̂ɂ������薢�����l���Ă��ăG���C�ȁ[�A�Ǝv�������̂��B
�����Ŗl���C����V�A�����}�W���ɂȂ邱�Ƃɂ����B�l����l�݂����ɐ�̂��Ƃ��l���č����Ă݂��������B�����Řr���v�ł���B��������Ă�ƁA�u�l���v�������X����Ă܂��v�g�ɓ����̂��B�����ŕ��ɘr���v���˂������B�܂����w���Ȃ̂ɁH�ł��A�m�ł݂�Ȃ����Ă��A�Ƃ����ď������Ă�������B
�ŁA�~�����~�����ƌ����Ĕ����Ă�������̂��Z�C�R�[�́u�q�[���[�v�ł���B�����ȏ��i���͒m��Ȃ����A�����e���r�ŁA�u�q�[���[�A�q�[���H�ɂȂ�Ƃ��A�A�[�A�[�A����͂��܃@�[�v�Ƃ���CM���J�b�R�ǂ������̂��B�����Q���T��~���炢�������낤���B���w���������̂ł͂Ȃ����A�Ƃɂ���������Ă�������B
�b��o���h����u���[�N�ł�������CM�Řb��\���A�l�͏m�Ńq�[���[�ɂȂꂽ�B���m�ɂ͖l�̃G���[�g���v���q�[���[�ŁA�������ڂ�̖l�Ƃ̃~�X�}�b�`���b����Ă炵�����B�������A���������̃R���r�͍��Z�������蔲���A�^���L��������w�̎��ɂ�����A���̂P��������ɂ͈ꏏ�ɓ��w���ɎQ�Ă����B�l����Ȃ��Ȃ��A���̎��v���Ȃ��A�z���g�ɐl���v����Ă��ꂽ�̂́A�ƁA���R�����O�ɉt���Ɏ��������Ă��܂������́u�q�[���[�v���v��厖�ɂƂ��Ă���B
�u�l�̃p�[�g�i�[�v����@�T�j����̃G�b�Z�C
���̃A���[����������A�ޏ��ɃL�X������B
�Q�R���S�T���A�l�̎v�l��H�͂��̂P�̍s�����N�������߂����Ƀt����]���Ă����B�ǂ������������炪�������A�\��͂ǂ����ׂ����A�O�͊����Ă������������̂��������B
�S���͂����̂Q�{�قǑ����ۓ���ł��Ă����B�P�����P���Ԉȏ�Ɋ������B
�ޏ��̒a�����̑O���A�����ς�����Ɠ����ɏj�����ƁA�r���v�̃A���[�����Q�R���T�T���ɃZ�b�g�����B�ْ��������ĖY��Ă��A�T���O�ɋC�����悤�ɂƁB�������A���ۂ͖Y���ǂ���ł͂Ȃ������B�b�j���Î����A�����ς��u�Ԃ����������Ƒ҂��ł��ꂽ�B
�����āA�^���̎��ԂT���O�B�Â����������ɘr���v�̃A���[���������n��B
�����������B
���ꂩ��̂T���ԁA�ǂ����������͂��܂�o���Ă��Ȃ��B�����Ŗ��Ă��邩�̂悤�ȐS���̌ۓ������������ɋ����Ă����B
�u�n�b�s�[�o�[�X�f�B�v
�̊����ԂłT���A�l�͔ޏ��ɏ��߂ẴL�X���v���[���g�����B�����ς���Ă������ǂ����́A�����ǂ��ł��悩�����B���E�ň�ԑ����A�ޏ����j�����Ƃ��ł����Ƃ��������������ɂ���B���ꂾ���Ŗ����������B
��w�Q�N���̍��A�A���o�C�g���S�ē������Ď�ɓ��ꂽ���̘r���v�ɂ́A�Ƃ�킯�v�����ꂪ����B�w�����������Ɣޏ��Əo������������قڈ�v����̂ł���B�ޏ��Ɖ�Ƃ��͕K���A�����ɂ��̘r���v�����Ă����B�������̉��ł��i�{���͊O���悤�Ɍ����Ă����̂����j�W�R�ƋP�����̗E�p���ʐ^�Ɏc���Ă���B
���ł��A�P���̏I���̂T���O�ɂȂ�ƁA�r���v�̓A���[����t�ł�B���̃A���[�������сA���̓����v���o���B�����āA�V���ȂP���̎n�܂���v�킹��B�ޏ��Ƌ��ɕ��ށA���ꂩ��̎��Ԃ��B
�u��Ǝ��̎��v�v��A�@���b����̃G�b�Z�C
���Z�̓��w�����ԋ߂ɍT�����R���̂�����B��Ɠ�l�A�ߏ��̎��v������ɁA���̏��߂Ď��r���v��I�тɍs�����B��������l���I�̂́A�x���g���V���o�[�̋����łł����������ʂ̎��v�������B���A���̕����Ղ̃O���[���A�����ʂ����悤�ȃG�������h�O���[�������Ƃ������Ȃ������F�ŁA���������ڂŋC�ɓ����Ă��܂����B
���̌̋��ł͂S���͂܂��������̕��������B���w���̒��A���̎��v�����ɂ͂߂�ƃq���b�Ƃ����₽�����`����Ă����B���v�����������̘r�����x�����āA�����Ԃ�w���o����x�ɂȂ����C�����āA�Ȃ����S�n��������������ǁA��Ɖw�ɍs���Ă݂�ƁA������Ƌْ������悤�Ȋ�����������̗F�B�̎��ɂ��^�V�������v������̂������āA�Ȃ��ق��Ƃ����̂��o���Ă���B
���̃O���[���̎��v�Ƃ͍��Z�A��w����V�N�Ԃ��Ƃ��ɉ߂������B�Љ�l�ɂȂ��Ă�������炭�g���Ă�������ǁA���̍��ɂȂ�Ǝ���͊v�̃x���g�̐l�̕��������Ȃ�A�������F�̊v�x���g�̎��v���āA���܂ł͕̂�ɂ����Ă��܂����B
�x���g�̃T�C�Y����̎��ɂׂ͍������̂ŁA��̓S���̂悤�ɐL�яk�݂���x���g�ɑւ����B����ƍ��܂ł���ȂɃJ�b�R�悩�������v���}�Ɉ����ۂ����̂ɕς���Ă��܂����B����ł���́A�u���͂��̐F���D���Ȃ�B�����Ă������F����˂��B�v�Ȃ�Č����Ȃ���A���̌㉽�\�N���g���Ă����B�ꏏ�ɗ��s�ɍs�������ɂ����Ă���̂ŁA�����������킢�����ɂȂ�A�ʂ̋@��ɐV�������v���v���[���g�����B��́u����Ȃ̂��ق���������B�v�ƌ����ĂƂĂ����ł��ꂽ���A�o�����鎞�ȊO�͑��ς�炸���̎��v�����Ă����B
��͓��@���Ă�������v���͂����̂����₪�����B���ꂪ�B�ꕁ�ʂ̐����Ǝ����Ƃ����т�����̂��Ƃł��v���Ă��邩�̂悤�ɁB�����N���オ�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ������A�O���[���̎��v�͉��N���U��Ɏ��̘r�ɖ߂��Ă����B
���A���̎��v�͎��̃^���X�̏�ɒu���Ă���B�ׂɂ͂��ꂵ���Ă��܂�Ȃ��Ƃ�������ŏ��Ă����̎ʐ^������B�l���Ă݂�Ƃ��̎��v�͖{���̎�����ł��鎄��肸���ƒ������Ԃ��Ƌ��ɑ����Ă����B�������܂�ď��߂Ď��������v�́A��̍Ŋ��̎��v�ƂȂ�A�����Ď��̑�Ȃ����Ƃ��Ă��ꂩ����������ݑ�����B
�u�l���̔��t�ҁv�����@���コ��̃G�b�Z�C
�u���͋��Ȃ�v
���w���w�j���̘r���v�ɓY�����Ă����c��̒B�M�Ȏ��B�͂߂�ƃY�V�b�Ƃ����B�l�W���Ȃ��Ă��Â��ɓ����������v�B��l�ɂȂ����C�������āA�_���Ȗʎ����őc��̎������x���ǂݕԂ����̂��o���Ă���B�����āA�u�����������撣�邼�v�Ɛ������B
�������A���w���Ă���̎��͗V�ѕ������B������̂͒���e�X�g�̑O���炢�ŁA���������ڂ肬�݂������B
�����ƁA�o�`�����������̂��낤�B���͑c�ꂩ�����������v�����Ă��܂����B�{����Ǝv���ƒN�ɂ��������A�h�L�h�L���Ȃ��炱�������T��������B���������Ă��Ă��������Ȃ������B������j���A���������c�ꂪ�㋞����Ƃ������A���Ɍ��������B
�u�ŋ߁A���v�����Ă��Ȃ�����Ȃ����v
���͎d���Ȃ������B���͂��炭�ق��Ă������A�o�����邼�ƌ����A�����f�p�[�g�ɘA��čs�����B�����āA�������v��T���Ĕ����Ă��ꂽ�̂��B���z�������B�v���Ԃ�ɂ͂߂����v�͂Ђǂ��d�������B
�u���̐����A�y�������H�v
�A��r���A���ɕ����ꂽ�B���̂�������Ԃ�͕ꂩ�畷���Ă����ɈႢ�Ȃ��B�������Ȃ����������Őӂ߂Ȃ��̂��h�������B
�ȗ��A���v���͂߂邽�тɋC�������`�N�`�N�����B�K���X�ɉf���̏���b�j���u���̂܂܂ł����́H�v�ƕ����Ă���悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ������B
���̌�A���̐����͏��X�ɗ������Ă������B�^�K���͂��ꂩ�����Ă������𗧂Ē����A�����Ă��ꂽ�̂͂R�{�̐j�����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�l���̔��t�҂��B
���ꂩ��A�Q�Q�N�B�c����������E�����B�V�̏�ŁA���݂̎��͂ǂ̂悤�Ɏʂ��Ă���̂��낤���B
�������v�͐Â��Ɏ�������ł���B�����ł߂������ɂȂ�ƁA���͘r�Ɏ�����āA���C��������Ă���B
�u�Q�O�N�Ԃ�̘r���v�v�{���@�u�s����̃G�b�Z�C
�Q�O�N�Ԃ�Ɏ��̘r�Ɏ��v�������ꂽ�B
�ɂ߂̃o���h�����A����Ă��Ȃ����炩�A���������B
��͂荶�r��Ⴢ��悤�ȋC������B
�������߂̃N���X�}�X�v���[���g���B
���Ɣޏ��ɍS�����ꂽ�V���V��������Ȃ����A��������Əd���N���m�O���t�͊m���Ɏ��̘r�Ŏ�������ł���B
�����A���x���r���v�������B
�܂�ŏ��߂Ęr���v���Ă�������q�ǂ��̂悤���B
�C�����͓������낤���A�����̎��v�Ƃ͂��Ȃ�قȂ�B
�����̘r���v�̓t�B�b�g�����ǂ��Ȃ������B
����̎��v�́A�����łȂ�ׂ��������������Ǝv������̂�I�����Ă����B
�`�^�����̌y�����̂ɂ��邩�A�o���h�̗����ɃS�������Ă��Ď��ʼn�]���ɂ�������
�Ȃ��Ă�����̂ɂ��邩�A���v�Ղ̎��͂��ł��Œ肳��Ă�����̂ɂ��邩�E�E�E���낢���
��ނ������Ă��Ė��������E�E�E���̎�ނ̖L�x���͊�Ɠw�͂̐��ʂ��낤�B
�r���v�͐��n�Y�Ƃł��邪�A���̂悤�ȏł��ꐶ�����ɋZ�p�҂����́u���悢�v���̂���낤�Ƃ��Ă����̂��B
�܂��A��a���͂���B�ł��A�����Ɋ���邾�낤�B
���̍����Ɋ�����Ă���r���v�ɂ́A�ޏ��̎v�������łȂ��A���̂��낢��Ȏv���A�����Ă����������Z�p�҂����̎v�����l�܂��Ă���̂��B
��������̘r���v�E�E�E�ł��A�傫�Ȃ̂��ۂ̌Î��v������������̐l�̎v�����p���ł���B
���߂Ď�ɂ����r���v�Ɠ����悤�Ȏv�������������A����ȏ�̎v�����A�Q�O�N�Ԃ�̘r���v�͊��������Ă��ꂽ�B
�ł��A���̋C�����������Â��邱�Ƃ͓���B
����̎��ɂƂ��ďd�v�Ȏd���́A���̂��̎v���������Â��邱�ƂɂȂ邾�낤�B
�u���A�ڂ̑O�ɂ���A���Ӂv�{�R�@���q����̃G�b�Z�C
�������F�̑傫�Șr���v����D���������B
�����č��A���̘r���v���ڂ̑O�ɂ���B�����d�Ԃ̒��B�[���̃��b�V���ɏd�Ȃ��Ă��܂����s�^���A�K�^�������B���R�ɂ����̐l�ɏo�������B��N�Ԃ肩�ȁB
���̐l�͑�w�@�̔��m�ے��Ő����p�̌��������Ă���l���B�������͑�w�̔��p�قŎ����̃f�[�^���͂̃A���o�C�g�����Ă����B���̍��̈�N�ԁA�ٓ��ł��܂ɁA��T�ԂɈ�x���炢�̊���Ŋ����킹�Ă����B���̐l�͂����ɗ��鎞�͂����A�A���o�C�g�̎��ɂ����āu����ɂ��́v�Ɛ[�X�Ɠ��������Ă��ꂽ�B�����Ĉꌾ�A�u�����V�C�ł��ˁv�Ƃ��u�����͗₦�܂��ˁv�Ƃ��A���ɂ͂܂�ŊS���Ȃ����̂悤�ȑ䎌�������āA�h�A�t�߂̎g���Ă��Ȃ��֎q�̏�ɃJ�o����u���B�r���v���O���B�����āA�ׂ�̎����ɂ��Ă���A�ړ��Ă̊G�����Ă����̂��Ǝv���B�u�v���v�ƌ������̂́A���͂��̌����ڌ����������Ȃ�����B�����Ԍ�A�ނ͂܂������֗��āA���J�Ɂu���ז����܂����v�ƌ����A�r���v���͂߂āA�����Ă䂭�B
�r���v���O���͔̂��p�قœ����҂̓��R�̎d�����B�M�d�Ȕ��p�i�ɏ������Ȃ��悤�ɁB�����炱���ɂ���l�݂͂�Ȃ�������B�ł��A���̐l�̂��̎d����������Č������B�ɏ�̔��������������B�傰���łȂ��āB�̕���̏��`�̂��Ƃ��C�i������Ă����B
���̐l�������ɂɓ����Ă���A�����ƒu���ꂽ�r���v�߂�̂���D���������B�傫�Ȃ������̘r���v�͎��̓���ƂȂ��Ă����B�m���Ƌ��{�Ɛ������ƗD�����̏ے����B��������Șr���v���������l�ɂȂ肽���ȁB����A�Ȃ�˂B���ӂ����B
���ꂩ���N�B�c�O�Ȃ��痝�z�ɂ͒������B�ł��A���̌��ӂ͖Y��Ă��Ȃ��B�����č��A�ڂ̑O�ɂ��ꂪ����B�������悤���ȁH���̂��ƂȂ�Ċo���ĂȂ���ˁH�h���d�Ԃ̒��Ō��t�������E�E�E�B
�u���F�̃y�A�E�H�b�`�v�����@���q����̃G�b�Z�C
�����f�������́A��ƌ܍ΔN������Ă���B��ɂ͎O�l�킪���邪�����q�̏f����������ɉ��������炵���A�\�ɂȂ�Ƃ����̂ɍ��ł��f�������́u�˂������v�ƕ���Ă�ł͕���Ă���B
��l�͂悭���Ă���B�e�����ł��������ŁA�ʓ|�����ǂ��ď�ɂ��낢�B��l�����ԂƂ���͂����u��e���E���e���v�Ƃ���������ɂȂ�B
�f�������̗B��̎�͖��G�����A�܂��w�����������Ɂu�˂������ւ̌����j�v�Ƃ��ĕ`�����Õ���́A�f�������̌�����u�ь�v���Ɛu�������܂ŁA�����Ɓu���Ⴊ���v���Ǝv���Ă����B�{�l�͂��Ȃ莩�M������悤�Łu���q���łɍs�������`���Ă��ȁv�Ȃ�Č����B
�������f������f�ꂿ���ƘA�ꗧ���ėV�тɗ������̂��Ƃ��B�f�ꂿ���͓�l�̎q���̕�e�����ǁA�����݂����ȕ��͋C��Y�킹�Ă��鏗�����B����������Ēj�ɏ]���悤�ȃ^�C�v�B
�ӂƓ�l���������̋��̘r���v�����Ă��邱�ƂɋC�t�����B�����`�ŕ����Ղ̂Ƃ���ɏ����ȃ_�C�������ߍ��܂�Ă���B
�u���[�A�f�������B�y�A�E�H�b�`����v
�����͂₵���Ă��
�u�Α��\�ܔN�̂��J���ɉ�Ђ����ꂽ�v
���ɂ������͂ɂ���ł���B�ނ���f�ꂿ���̕������X�Ƃ��Ă��āA�ւ炵���Ɍ������B
���͏f��������̎��v����Ђ����������̂��ƁA������f�ꂿ���ɓn���ē�l�ł������̗l�q��z�������B
�N�ւ��d�˂��v�w���������̎��v���͂߂Ă���p�ɂ͖�������B�P�ɒ����ǂ��Ƃ��ł͂Ȃ��āA�R��z���āu�j�Ə��v�ł��葱���Ă���悤�Ȉ��S��������B�c��ȁu��炵�v�Ƃ����������ޒ��ł́A�v�w�̂�������A���F�̃y�A�E�H�b�`�͎��ɋ����Ă��ꂽ�B
�u���r�̘r���v�v�����@������̃G�b�Z�C
�u����A���̎��v�A��������̂���Ȃ��H�v
���C�Ȃ���̍��r���������͕�ɂ����˂��B
�u�����A����H�@��������̌`���̘r���v�B��������̂ɒN���g��Ȃ�������A�g�����Ǝv���ĂˁB���������Ɗ�Ԃ�v
������������̌����ɂ͏݂����ڂꂽ�B
���́A���H�S�Ђɓ������B�ˑR�̎��B�������������B���ԂɃ��[�Y�Ȃ��ƂɎ�X���𗧂Ă��B����ȕ����D�����������́B����͘r���v�������B���O�ɂ͔ނ����p���Ă����r���v���������ƕ���ł���B���Q������邽�тɎv���B�����傪���Ȃ��Ȃ����r���v�̎₵�����B
���������}�����B���̂���ɂȂ�ƁA�H���ׂ��Ȃ�A���Ȃ藎������ł���������������C�����߂����B�����ĕ�̘r�ɂ́A���`���̘r���v���͂߂��Ă���B
��̍טr�ɂ͎����킵���Ȃ��r���v�����𐁂��Ԃ����B�~�܂��Ă������̎��Ԃ����₩�Ȏ��Ԃ����݂͂��߂��B
���́A��e�̑O�ŕ��ɘb���������B
�u��������̘r���v�͂��ꂳ�g���Ă����B�悩�����ˁv
���������e���������悤�������B���̊�́A�݂����ڂꂽ��̊�Ɏ��Ă����B
�������̗����B��͒��f���Ă��������̌m�Â֏o�������B�~�܂��Ă�����̎��Ԃ������n�߂��B���̘r���v�ƂƂ��ɥ������B
�u�r���v�̐S���e�X�g�v���c�@�M�q����̃G�b�Z�C
�u�����ɂƂ��Ęr���v�Ƃ́H�v�Ƃ����S���e�X�g�������m���낤���B�܂�������\�̍��A�u���Ȃ��ŊO�o����ƈ�����C�ɂȂ邯��ǁA�ƂɋA�����炷���ɂ͂����B�����Ō��B�v�����������L��������B���̃e�X�g�́A�u���Ȃ��Ɨ��l�Ƃ̊W�v���Ӗ�����̂��������B�m���ɂ����ł������B���͂������l���ꏏ�ɂ��Ȃ��Ă͌��Ȃ����ɁA��������邱�Ƃ𖭂Ɍ������B�ꌩ�������Ă���悤�����A�ꏏ�ɂ��鎞�Ԉȏ�ɁA�����ЂƂ�̎��Ԃ���������B�܂�ŕ��D�̗l�ɁE�E�E������Ƃ��܂��Ă���Ȃ��Ă͔��ł�������ǁA���肢���ς��ł����݂���Ă͉��Ă��܂��l�ȁE�E�E�B
�Љ�ɏo�Ă��炭���āA�ނƏo������B���܂�Ɏ��R�ȏo��ɁA�g���ꂪ�^���I�h�Ƃ͋C�t���Ȃ��قǁB����Ȃ̂ɕs�v�c�Ȃ��ƂɁA���̘r���v�͕ς�����̂��B�ނ����߂ăv���[���g���Ă��ꂽ�̂́A�_�C�o�[�Y�E�H�b�`�������B����܂Ŏg���Ă������Ɖ����ς�����ƌ�����łȂ��̂ɁA���͂����C�̂Ƃ��ł��A�Q��Ƃ��ł��A���̘r���v�������Ȃ��Ȃ����B�Ў��������E�E�E�B���炭���āA���̔ނƌ��������B�����Ă��������\�N�ɂȂ�B���͂��̘r���v���A�����e�i���X�̎��ȊO�͂����Ȃ��B�ǂ�Ȏ��ł��A���̘r�ɂ��̘r���v���Ȃ��ق����A�s���R�Ȃ̂��B
���ɂȂ��Ă��̐S���e�X�g�́A�Ԉ���ĂȂ������̂��Ǝv����B���A�v���Q�S���ԑ��ɂ��Ă��A���͎��̂܂��R�ɂ�����B���͂��Ƃ����������悤�ƁA�ꐶ�A���̘r���v�����r�ɂ͂߂Ă��悤�Ǝv���Ă���B
�u��������Ɂv�c���@�^�m�q����̃G�b�Z�C
���Z���w�̎����炻�̎��v�͈ꏏ�Ɏ�������ł���Ă���B���w�̂��j���ɗ��e�ɔ����Ė����SEIKO�́uAvenue�v�Ƃ������v���B
���̓]�ŗ����x�R�͂ƂĂ��c�ɂ������B���m��ʌi�F�A���߂ĕ��������B�����A������2�����Ȃ������e���r�̃`�����l���B�������Ɨ���鎞�̒��ŁA���̍���ɂ������̎��v�͂������B�c�ɂ̍��Z�łP���ԂɈ�{�����Ȃ��d�Ԃɏ��x�ꂽ���́A���v�����Ȃ��炭�₵��B���̓d�Ԃ܂Ŗڂ̑O�̓��{�C�����Ȃ���҂����B�x�R�͍��ł����ɂƂ��đ��̌̋����B
��w�͑��i�w�����B�����͎��ԂƂ̓����B���v�Ƃɂ�߂��������Ė������i�B���܂��ܕ������֓]�ƂȂ�A�Ƃ���w�Z�܂łP���Ԕ��̒ʊw�ƂȂ����B�ꎞ���ڂ̎��ƂɊԂɍ����悤�ɁA����A����B�r�����ʼn��x�����v�������B��w��4�N�Ԃ͎��ɂƂ��Ă����ȈӖ��ł̗ǂ��o�����o�������������B
�����ďA�E�B�Ј���40�����̉�ЂŎc�Ƃ����������B�c�Ƃ������Ƃӂ�ӂ�Ɩ�����Ŏ��v�����āA�I�d�}�����B�I�d�������d�Ԃ��Ƃ������Ƃ����߂Ēm�����B�߂Ă��鎞�͕�����茾���Ă������A4�N���撣�ꂽ�̂́A��͂肠�̎d�����D���������̂��Ǝv���B
28�Ō����B�����ƐV�����s�̓n���C�ōs�����B�n���C�ɒ����āA���v���n���C���Ԃɍ��킵���B�y�������A�ꐶ�̎v���o�̎����ꏏ�ɍ���ł��ꂽ�B�ł��A�������ɋ������͊��̒��ł�����ԁB���ْ̋��̎����A�Â��ɏj���Ă���Ă����ɈႢ�Ȃ��B
�����悤�ŒZ�������A���͂قƂ�ǂ��̎��v��ʼn߂����Ă��܂����B���܂ɂ͈Ⴄ���v�����o�܂��������A������ԁA�Ƃ������͌��܂��Ă��̎��v���B
���������A�₳�����Â��ɁA���ɂ͌��������g�������̎�������ł���Ă���B�����āA���ꂩ��������Ȏv���o�̎�������ŗ~�����B
�u��������₳��̘r���v�v�Γc�@���q����̃G�b�Z�C
���́A�����A���w���̍��܂Řr���v�������Ă��Ȃ������Ǝv���B���Z�̓��w�j�ɏ��߂Ęr���v��c�ꂪ�����Ă��ꂽ�L�������邩�炾�B�������A6,000�~�̃Z�C�R�[�̘r���v�������B���a30�N�A�����A6,000�~�͍��������B���̗��Ƃ���ꂽ���w���̏��C����6,000�~�������B��̃o���h�͉����ւ������A���͂��̎��v���ɂ��Ă����B�������A��w����̉āA�R�o����������ɗ��Ƃ��Ă��܂����B�R�����ɒH�蒅�������ɋC�������̂��B�����̂����������ɂ����Ă��̖�͖���Ȃ������B�����A���R���鎞�A�o���ė����R����ڂ��M�ɂ��ĒT������������Ȃ������B���̎��A���s�����{�[�C�t�����h�Ƃ͊Ԃ��Ȃ��ʂꂽ�B���킭���̓o�R�������B���̌�����͐���A�r���v���Ȃ������B�����w�Z�ɋΖ����Ă��鎞�A���߂̃|�P�b�g�ɓ��ꂽ�܂ܐ���ɏo���Ė߂��Ă��Ȃ������B���̌�A�v����v���[���g���ꂽ���v���f�p�[�g�ŗ��Ƃ����B����͎茳�ɖ߂��ė����B���̎��͖{���Ɋ����������B
���A�茳�ɂ���Z�C�R�[�̘r���v�͉��ڂ��낤�B����͑厖�Ȏ������g�ɂ��邱�Ƃɂ��Ă���B���܂��ɂ������������̂�����Ȃ�����ł���B
�u�v���o�̘r���v�v�O�V�@�v���q����̃G�b�Z�C
�l�\�N�ȏ���O�̎��ł���B�������w�Z�Z�N�̎���͌������B
�u���w�ɍs������r���v�����Ă�����v
�u���A�{���B��H�v
���ɌZ�Ǝo���������A��l�͂��łɔ����Ă�����Ă����B�ł���ԉ��̎��ɂ͐G�点�Ă���Ȃ������B����قǑ�ȕ��������̂ł���B
���w�ɓ���܂ł��̘b�́A�Y��Ă����B���w�̓��w���̑O���A�r���v���Ă����Ƃ����b�͖{���ɂȂ����B
���̎��v�͍��ł��o���Ă���B���v�̕����������łȂ��A���r�A�����������̂ŁA���Ɠǂނ��A���߂͎��v�̓ǂݕ���m��Ȃ������B
�u�Y�͂U�A�\�͂X����v
�Ǝo�͋����Ă��ꂽ�B���w�Z�l�A�ܔN�܂ʼnƂɂ͎��v���Ȃ��A���̓ǂݕ�����N���ʂ܂Œm��Ȃ������B
���v�̃o���h�͐F�̔琻�B�Ђ��T�~���ʂ������B�G�i�����Ƃ��łȂ����ʂ̔琻�������B�������[���Ǝg���Ă����̂œ�A�O�N�Ńo���h���C���Ă����B�ł��e�͂Ȃ��Ȃ��V�����o���h�Ǝ��ւ��Ă���Ȃ������B�{���ɘr�ɂ͂߂��Ȃ��Ȃ�܂ʼn䖝�����B
���݂����Ƀ����[�Y�����������ł͂Ȃ��̂ŁA�����\�炢���������ꂪ�y���������B
�u�]�芪��������Ǝ��v����ꂿ�Ⴄ��v
�o�͎������v�������̂����Ă��Ď��X�������B
�Ă͊��������������A���v�̉��̎�����Ȃ�A���������v���͂߂��`�ɔ��������ꂽ�i�D�ɂȂ��Ă����B
�����A�E���Ă���A�o���h���`�F�[���̕ʂ̎��v�Ɏ����Ŕ���������
������A�Ȃ������琻�o���h�̎��v�����Ƃɂ������܂ܕЕt�����Ă��܂����B
�u���v��������q���̐���ցv����@�a�炳��̃G�b�Z�C
�������A�g�p���Ă��鎞�v�͓�ڂł���B��ڂ͍��Z���w���A���e���v���[���g���Ă��ꂽ�B�ΐF�̕����Ղ���ۓI�Ȏ��v�������B�������̎��v���͂߂Ă����ɁA�����ŊԔw���j�A�Ƃ������̕a�C�ɂ��������B���ꂩ�炵�炭���Ă��A���͓����̕a�C����������悤�ɂȂ����B���ꂩ��P�W�N�A���̎��v�͕��̕a�̐i�s�ƌĉ�����悤�Ɉ�b��b�A��������ł������B�����č�����T�N�O�A�����S���Ȃ������ɁA���̘r���v���̏Ⴕ�Ă��܂����B���v�̓y��Ƃ�������\���������Ă���Ă��܂��悤�ɂȂ����̂��B�܂�ŁA���ɔ����Ă���������v�����̎��Əd�Ȃ荇���悤�Ɍ̏Ⴕ�����ƂɎ��͉����̈������������B���͊����ďC�������Ȃ������B�����g�A���̎v���o�Ƌ��Ɏ��v���܂��A�S�̎v���o�̒I�ɂ��܂����ނ��Ƃɂ��āA�V�������v�ōďo�����邱�Ƃɂ����B�����āA���ɂƂ��ĂQ��ڂƂȂ鎞�v�́A�������̘r�̒��ŁA��b�A��b��������ł���B�܂�Řr���v�́A���̐l�������Ă��Ă���Ă���C������B�������v���O���͓̂������鎞�������B���̎��Ԃ͂������́A���̎��v�ƑΘb���J��Ԃ��Ă���B�U�������Ă��鎞�A���͎��v�ɖ₢������B�u�����A�R�O������������x�e���悤���ȁv�ƁB���v�͓�����B�u�܂��A�R�O������Ȃ����B�����A��P�T�������Ă݂���v�ƁB���͍Ăї͋��������o���B���͘r���v�Ƃ������Ĉ�����Θb���J��Ԃ��B���v�́A���ɂƂ��Ď��Ԃ������Ă���铹��Ƃ��������łȂ��A�l���̔��t�҂Ƃ����Ă��ǂ��Ǝv���B�������A���Ă��鎞�v�������č����Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�������A���͂��̎��v�Ɉ����������Ă���B�������̐l�����A���߂Ă��Ă���邩�炾�B�����Ď������B���サ�Ă����B���͍Ō�Ɏ��v�Ɋ��ӂ̌��t���q�ׂ����Ǝv���B�u�������Ԃ�m�点�Ă���Ă��肪�Ƃ��B���ꂩ������X�A��C�ɂȂ鎄�̂��Ƃ��܂��Ă��������B�����Ă��ꂩ������Ƌ��ɕ���ł����ĉ������B���̐l�������ߑ����Ă��������B���ꂩ�����낵�����肢���܂��v
�u��ȑz���Łv�Ȃ����@����������̃G�b�Z�C
�u�����ߌ�10���ɁA���̘r���v�ɘb�������悤�E�E�E�v
��w����ɒm�荇�����ނ��c�����ƂƓ����ɓc�ɂɋA��Ȃ���Ȃ�Ȃ����ɔނ͂��������Ǝ����̂��Ă����r���v�������Ǝ��Ɏ�n�����A���̘r���v�͒m�荇�����Ƃ����炸���Ɣނ����Ă������̂�����
�����Ď��������̘r���v��ނɓn���c�ɂɋA��A�E�����B
���݂��A�E�����ĂŖZ�����d�b�ő�����Ăяo�����Ƃ��܂܂Ȃ�Ȃ�����
���͔ނƂ̖ǂ���10�����傤�ǂɔނ̘r���v�ɘb��������
1�l�r���v�ɂނ����b��������͍̂ŏ��͋C�p���������C��������
�������ꂽ�y�n�Ŕނ������̘r���v�����Ȃ���b���Ă���̂��Ǝv���Ɠ��������߂����Ă���悤�Ŋ���������
�y�����������ƁA�炩�������ƁA���͖����ߌ�10���ɘr���v�ɂނ����b���Ă����E�E�E���̎��ނ̘r���v�͔ނ̑���Ɏ��̐S����������Ƃ߂Ă���Ă����B
���ꂩ��20�N�A���H��H�I���g�x�x���ƂƂ̂��o�̏���������v���r���v�����悤�Ƃ���E�E�E�v�͊o���Ă���̂��낤���A���̎��̂��Ƃ��E�E�E
���݂����炽�߂Ă��̎��̎���b�����Ƃ͂Ȃ�����ǂ����Ɗo���Ă���ɈႢ�Ȃ�
���̂悤�Ɍg�ѓd�b���Ȃ�����A�p�������Ȃ��A�ł����������Ɍ�荇�������̎��E�E�E�v�Ǝ��̑�ȑ�Ȏ������z���łł��B
�u����������̊肢�A����������̋F��B�v�䂤����̃G�b�Z�C�@�@�i11-12���̃x�X�g�G�b�Z�C�j
�u�l�A����������̂����̒��ŕ�炷���Ƃɂ����v
�N���ٓ��ɏh���Ă���
����������̘r���v�͉��₩�ŗD�����������݂͂��߂��u�����A�����A�����A�����v�B
���̍��́A����������̐S�����A�N�̎��v�������낤�ˁu�Ƃ���A�Ƃ���v�B�N�͂������A��������A�m���ɑ傫���Ȃ��Ă������B
���������A���X���ł�����������K�V�K�V�R�����ł��傤�B
����������́A���������A�Ƃ�����������Ȃ���A�Ȃ��ƂĂ������ȋC������������B
����Ȓ����Z���y�������X�́A�Ƃ����A�I�����}�����B����A�@���n�����ƌ����ς��悤�B�u�l�A�������O�ɏo�邱�Ƃɂ����v
����������̘r���v�Ƃ̐^���Ȃɂ�߂������n�܂����B
�Ȃɂ���A���v�j�̓��������ĂȂ��ʁA�x���̂��B
��������10�����A1���Ԃɂ�2���Ԃɂ���������u���[���A���[���v�B
�t�ɁA�N�̎��v�́A���ł��邳�������ɈႢ�Ȃ��u�ǂ����I�ǂ����I�v�B
�I���̌����Ȃ�������z���A�������߂����A�����ԋ߂ɌN���Y�܂ꂽ�B�Y�܂�Ă����̌N��r�̒��ɕ������A���̏u�Ԃ͍��ł��N�₩���S��B
�N�̎��v�͂����������Ȃ��Ȃ��ď����₵����������Ȃ�����ǁA
���������A���A���܌N���`�����ނ����
�N���Y�܂ꂽ���̓��A�������������Ƃɂ�߂������Ă����r���v�Ȃ�B
���ꂩ�����ł䂭�N�̎��Ԃ����ׂčK���Ȃ��̂ł����ė~�����B
���̘r���v�����邽�тɁA����������͊肢�A�����ċF���Ă���B
�u�T���^�N���[�X����̑��蕨�v�É�@���~����̃G�b�Z�C
�q���̍��A���̓T���^�N���[�X������ƐM���Ă��܂����B
5�̃C�u�̓��Ɏ���҂ɍs���āA���܂�̒ɂ��ɋ����Ă��܂�����A���̖鎄�̏��ɂ̓T���^�N���[�X�����܂���ł����B�ꏏ�Ɏ���҂ɍs�����F�B�͋����Ȃ������̂ŁA�T���^�N���[�X���v���[���g�������ė��Ă��ꂽ�炵���A���͎���҂ŋ����Ă��܂����������̂�����������A�����Ă͂����Ȃ��Ǝv���Ȃ���܂��|���|�����ڂ��Ă��܂����B
���̔N�̃C�u�̖�A���͕�Ɍ����܂����B�u�����͗ǂ��q�ɂ��Ă��ł��傤�H���N�݂����ɋ����Ȃ��������A�T���^���Ă���邩�Ȃ��H�v
��́A�u���������ǂ��q�ł��_���Ȃ�B�T���^����͖������Ă�����B�����A�����Q�Ȃ��ƃT���^����Ȃ���B�v�ƌ����܂����B
���N����ƁA�x�b�h�̖����Ƃɒ݂邵�Ă�������̃X�g�b�L���O�̒��ɁA���ꂢ�Ƀ��b�s���O���ꂽ�����Ȕ��������Ă��܂����B
���͂��ꂵ���ĉƒ��𑖂����āA�u�T���^��������[�B�v���[���g�����ė��Ă��ꂽ��[�B�v�Ƌ��тȂ�����т��܂����B
�J���Ă݂�ƁA�s���N�̃x���g�̃V���f�����̘r���v�B�Ƒ��S�������Ă���̂Ɏ������������Ă��Ȃ������r���v���T���^������āA�������A���̒N�̕���莄�̂���ԉ����̂ł��B
����Ƒc�����A�u����钆�h�A���K�^�K�^�����Ă��̂́A�T���^�����Ă��̂��Ȃ��H�v
�ƌ����A�����u������A�������g�C���ɂł��s���Ă�̂��Ǝv���Ă�����A�T���^�������B�v�Ƌ������悤�Ɍ����܂����B
���͗܂����ӂ�Ă��āA�u�Ȃ�ŁA�N���Ă���Ȃ������́H�T���^����ɉ���������̂ɁB�v�Ƌ����Ȃ���R�c���܂����B
���̓�����A�Ƒ��S���Ɂu�����ɋA���Ă���́H���т͉�������H�����ɐQ��́H�v�Ǝ��ԂɊւ��鎿�������悤�ɂȂ�܂����B
���̔N�A�T���^�N���[�X�͎��ɉ����r���v�Ƌ��ɁA���Ԃ̓ǂݕ��Ǝ��Ԃ����Ƃ������蕨�����ꂽ�̂�������܂���B
�u���߂Ă̘r���v�v���Y�@�G������̃G�b�Z�C
�������߂Ă��łɂ������v�̓f�W�^���\���̃~�b�L�[�}�E�X�̘r���v�ł��B���Z���w�̂��j���ɕ��������Ă��ꂽ���̂ł��B���Z�ւ́A�����x�ނ��Ƃ��Ȃ��ʊw���܂����B�������r���v���������čs���܂����B����͋L���ɂ̂������̕��̍ŏ��̃v���[���g�������Ǝv���܂��B���ꂩ��Q�O�N�������A����������̕������͒�N�ސE���āA�Ƃɂ���܂��B���̍����ނ����ɂ͂��炢�Ă������͔N���Ƃ�ɂ�āA�����������������Ȃ荡�͓��@���Ă��܂��B�����e�ƂȂ�A�e�̂��肪���݂ƈ���������Ă��܂��B�������̎��v���̂ɂ��A��J�����낤�������܂��B�����܂��c���q���B�̐ߖڂɂ́A���܂ł��S�Ɏc����̂��c���Ă�肽���Ǝv���܂��B�����ē��@���Ă��镃������ł������މ@���āA���C�ɕ�ƂƂ��ɁA���������Ăق������̂ł��B
�u�ӂ��̎��ԁv�����@�������̃G�b�Z�C
���N�̊ԁA�킽���ƔނƂ͗���ĕ�炳�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ����B
�킽���̓t�����X�B�ނ͓��{�B�����͔����ԁB
���l�̉Ƃɖ��ɂȂ�킽���ɁA�d�b���L�ł��鎩�R�͂Ȃ���������A�ނ��������Ԃ����߂āA�d�b�������Ă��Ă��ꂽ�B
���{����ŁA�t�����X���ߌ�B
���̎��Ԃ��߂Â��ƁA�킽�������͘r���v�Ƃɂ�߂��������B���̓��ǂ��ɂ��悤�Ɖ������낤�ƁA�w���ꃁ���X�x�̃����X�̂悤�ɁA���̎��Ԃ܂łɂ͑������点�ēd�b�@�̑O�ɒH�蒅�����B
�킽�������̘r���v�ɂ͕����Ղ��ӂ��������B�t�����X�̎��ԂƓ��{�̎��ԁB�ӂ��̎��Ԃ�����ׂȂ���A�킽�������͉����ɕ������邨�݂��̐��Ɏ����X���������B
�u�������������H�v�u�����̎O���B�������́H�v�u������̏\�ꎞ�v�B
�킽�������͘r���v���̂�������ŁA�������B
�u�����Ă�ˁv�u�����Ă�v�u����Ȃ���ˁv�u����Ȃ���v�B
�����̂Ȃ����t�����������āA�������悤�Ȏv���Ŏ�b���u���ƁA�Ղ�A�Ǝ��Ԃ̎�����āA�ʁX�̎��Ԃ�����n�߂�B
�r���v�̂ӂ��̕����Ղ̒Z�j���m�͔���]����Ă��āA���j���m�̊p�x�͂҂����荇���Ă���悤�ɁA�킽�������̎��Ԃ��A�ߌ�Ɩ�Ƃɔ���]���ꂽ�܂܁A�S�����҂�����Ɗ��Y���B
�ӂ��̒Z�j��]���点���܂܂ŁA�������̖�Ƃ������̒����A�ӂ��̘r���v�͒����ɍ��B
���N���߂����B�G�߂�����]�����B
�r���v�̕����Ղ́A�����A�ЂƂ����ł����B
�ӂ��̎��Ԃ͂���ƍ��ЂƂɂȂ��āA�킽�������̎��̏�ŁA������Ď������ݑ����Ă���B
����������p�̎��v���������̂́A���a�O�\��N�̂��Ƃł����B�������Z�̓��w�j���ɔ����Ă��ꂽ�̂ł��B�ی^�ŐԂ��v�o���h�̃[���}�C���̎��v�ŁA�����[�Y���������Ȃ�������܂���ł����B�����Ă���������̖�́A���ꂵ���ĕz�c�̒��܂Ŏ�������ŁA�����Ȏ��v���������މ������܂ł������Ă��܂����B
���̎��v�͒x�ꂪ���ŁA���v���Ɏ����čs���Ă͍��킹�Ă��炤�̂ł����A���m�ɂ͓����܂���ł����B�A�E���Ă�����A���x�����i�����ւ����肵�đ�Ɏg���܂����B
���Ɏ��������v�́A�A�E���Đ��N�o�������ɂ�͂蕃�����ꂽ���̂ł��B���̂Ȃ̂ł��傤�A�����́u�싞���v�ƌĂ�Ă������^�̎��v�ł����B�X�C�X���łP�S���̂������Ȏ��v�ł����B�E��ɂ��čs���ƁA�u�����I�������̂��Ă���ˁB�v�Ƃ��u�����āB�v�Ƃ������A�����̎��v�ł����B���v���ƁA�Ⴂ���ɂ͕s�������������̂����m��܂���B
�������g�Ŏ��v�����߂��̂́A�������Ă���ł��B���̍����s���Ă����u�h���X�E�H�b�`�v�Ƃ����͑��_�C���̕t�������^�̂��̂ł����B
�ŋ߂͈����Ȃ��̂ł����m�ŁA�̂̂悤�Ƀ����[�Y�������Y��Ď~�܂��Ă��܂����Ƃ��Ȃ��A�@�\������ɕ�����A�l���ꂼ��ɗp�r�ɍ��킹�Ďg�������邱�Ƃ��ł��܂��B
���͘V��ɂȂ�A�̈��p�������^���v�Ƃ̓T���i�����āA�����ς當���Ղ̑傫�����₷�����v��������p�h�ɂȂ�܂����B�ŋ߂͂ǂ��֍s���Ă����v�������āA���Ɏ����ďo��̂�Y��Ă��s�ւ͂���܂���B�ł��A�O�o����Ƃ��͂�͂�r�ɂ͎��v���Ȃ��ƁA�Ȃɂ��r�����т����C������̂ł��B
�u�r���v�̎v���o�v���c�@��������̃G�b�Z�C
�u������Ƌ�����u���Ȃ��H�v�Ȃ��Ȃ������Ȃ��ꌾ�ł���B���������������I�ƋC�������Ē��f�[�g�̓��B�ނ͎��̋C�����ɑS���C�t���Ă��Ȃ��l�q���B�ł̂Ȃ��Ί������ƁA���������������B���ꂱ��l���Ă�����A�����̃t���̂悤�ɕt���Ă����ނ����Ȃ��Ȃ��Ă����B
�܂��A���q�ɂȂ����̂�����c�ނ͐l���������Ԃ��Ă���悤�ȏꏊ�ł������q�ɂȂ��Ă��܂��B�����������g�ѓd�b�������Ă��Ȃ��ނ�T���̂́A���\���J���B������������X�����Ԃɖ߂��Ă����ƁA�t�@���V�[�V���b�v�̓�����t�߂Ŕނ������B�ނ͉�]�Y��ɂԂ牺�����Ă����~�ψ�̘r���v�߂Ă����B����������ƁA��e���������q���݂����Ƀj�b�R�����B
�u�u�������A���̘r���v�~�����v
�ނ͖��邢�ΐF�̃V���v���Șr���v���w�������B���͕Ԏ������Ȃ��ŁA�ނ̗~�������Ă���r���v����Ɏ��A���W�Ɍ��������B�������܂Ɂu���˂���v�����鎖������B���̕��͉��ł���ȕ����~�����́H�Ǝv���悤�Ȉ������肾�B
��v���ς܂��āA��]�Y������邭��Ă���ނɘr���v��n���ƁA���������ɂ����ɘr�ɕt�����B�ނ̘r���v�����Ă��������߂Č����B
�u�˂��A�������H�v�����Ŕ�������ł��Ȃ��̂ɁA���ӂ��Ɍ����т炩���B
�u������Ȃ��c�v���̌��������₽�������̂��A�ނ͖ق��Ă��܂����B�����̂܂܁A�w�Ɍ������B�ނ͘r���v�����x�����x�����Ă����B
�u�u�������A����悤���v
�u�����H�v�ނ̌��t���A���܂ŕ��������̂Ȃ��ނ̐��ɂт����肵���B���`�����ނƁA���Ɠ����l�Ɋ���������̂悤�Ȗ��C�����Ȃ������B
�u�u�������̎��D��������A�����Ղ肵�Ă����ǁv�ނ͑S�Ă킩���Ă����̂��B����Ȃɕʂꂽ���Ǝv�����̂ɁA�}�ɗ܂����Ă����B
�u�����̂���A�u�������̑���ɂ����v�ނ͒n���S�̊K�i�𑫑��ɍ~��čs�����B
���ꂩ��O�N�o����ǁA�ΐF�̘r���v�����Ă�����������ƃh�L�h�L���Ă��܂��B
�܂��A���̑���ɂ��Ă���ł��傤���H
�u�P�V�N�Ԃ��肪�Ƃ��v�R���@���q����̃G�b�Z�C
���߂Ă̓~�̃{�[�i�X�Ŏ��v�����B����͂V���~���炢�̂��̂ŁA�Q�O�N�O�̎��ɂƂ��Ă͎v�������������������B
���ꂩ��P�V�N�ԁA���͂��̎��v���ɑ�Ɉ����Ă����B���̎��v�͂��̂��납�炩�A���ɂƂ��Ă����̂悤�ɂȂ��Ă����B�d�r�͉��x�����������B�r���Ńx���g�̏C���������B�����Ȃ��Ȃ��ĕ����C���ɏo�������Ƃ�����B�@�������v���C�y�ɔ����鎞��ɂȂ��Ă������A���ɂƂ��ẮA���̎��v�͉����ɂ��ウ����݂ɂȂ��Ă����B
�Ƃ��낪�A���̎��v���Ȃ����Ă��܂����̂ł���B����͗��s���̂��Ƃ������B�͂��߂́u�����ɏo�Ă��邳�B�v�ƌy���l���Ă����B�����̒����A�ו��̒��ɂ���͂��Ȃ̂�����B
�Ƃ��낪������Ȃ��B����K���ɂȂ����B�v���q�ǂ����������̎��v���ɂ��Ă���̂�m���Ă���̂ŁA�ꏏ�ɒT���Ă��ꂽ�B���A���nj����炸�A�`�F�b�N�A�E�g����Ƃ������b���A��������������A�����ė~�����Ɠ`���A�z�e������ɂ����B�������A�z�e������A�������邱�Ƃ͂Ȃ������B
�P�V�N�Ԏg�����̂�����A�\���Ɍ��͎���Ă���B�ł������傫�ȖY�ꕨ�������悤�ŁA�Ȃ��Ȃ��v���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
���������Ă������ɂƂ��āA���v�͕K���i�ŁA���Ƃ̊J�n�A�I���A������Ƃ�����Ƃ̋��A�������̎��v�͎���������Ă���Ă����B�V�ċ��t�ʼn����ł������������ȂƂ�����A�P�V�N�Ԃ����ƁB
���炭���ĕv�Ǝ��v���ɍs�����B�����P�O���N�������̂ł�����L�O���āA�y�A�ł��낦���B
���R�ɂ����v���Ȃ������N�Ɏ��͂P�V�N�ԑ������d�������߂邱�ƂɂȂ����B�����ĐV�������v�ƂƂ��ɐV�����������n�߂��B
�u���߂Ă̘r���v�v�����@�p������̃G�b�Z�C
���ł����l�i�������A���w�����r���v�������Ă��Ă��������Ȃ�����ɂȂ�܂������A�̂͘r���v�Ƃ����A����͂���͑�l�̏ے��������̂ł��B30�N���O�A�܂��������w�����������A3�Ⴂ�̌Z�����w���ɂȂ�A���ɘr���v���Ă��炢�܂����B�䂪�Ƃ͂Ȃ������w���ɂȂ������j���͘r���v�ƌ��܂��Ă����悤�ł��B�����ɂ��ČZ�̐^�����肵�Ă������́A���̘r���v�������܂����Ă����܂����Ă��܂�܂���ł����B������Ƃł�������͂߂����ė~�����Ɖ��x�����݂܂������A�Z�������đ݂��Ă͂���܂���ł����B���������ĉĂɂȂ�Ƒ��ŊC�֍s���܂����B�Z�̘r�ɂ͘r���v�B�ւ炵���Ɍ����Č����܂����B�h�ɂ��Ă��炭���āA���̂��ƂĂ��@�����悩�����̂ł��傤���A�����đ݂��Ă���Ȃ������r���v���Z���݂��Ă���܂����B���ꂵ���Ă��ꂵ���đ����͂߂Ă݂Ȃ��ƁA���������r���d���Ȃ����悤�ł����B��������ɂ���X���r���ӎ����āA�}�ɑ�l�ɂȂ����C���B�p���Ȃ��̂ɕ������o�ĒN���ɋC�Â��ė~�����Ă��낤��B�傰���ɘr��U��グ���Ԃ�������B�S�������������̂��o���Ă��܂��B���ꂩ��3�N�B���悢�掄�����w���ɂȂ�A�r���v���Ă��炤��������Ă��܂����B���ɘA����s������́A��Œm����������̓X�B�����ƕ��V���[�P�[�X�̒��̘r���v�����B�ڂ�����ނ���ɋP���Ă��܂��B�ӂ�������������₾������A�����Ղ�������������������������A�K���X�����ʂ̂��̃_�C�������h�݂����ɃJ�b�g����Ă�����́A�x���g�����Ă��낢��B���N���N���ĂȂ��Ȃ����܂�܂���B���̂Ƃ��͖����ŕ�����܂���ł������A���ɑ�������ȂǂƂ͌����Ȃ������悤�ȋC�����܂��B�����Ƒ҂��Ă��Ă��ꂽ�悤�ȋC�����܂��B�U�X�����Ă���ƌ��߂��̂͋�̃t���[���ŋ����̃x���g�A�����Ղ͐ŕ��ʃK���X�B�����Ղ̂R�̂Ƃ���ɓ��t���ł��B���������ł����B���X�Ńx���g�̒����߂��Ă��炤���߂ɍ��r�������o�����Ƃ��́A�ƂĂ��h�L�h�L���܂����B���ꂵ�������ł��B���ۂɘr���v��K�v�Ƃ��鐶���́A���Z���ɂȂ��ēd�Ԓʊw������悤�ɂȂ�������̂��ƁB���w�����3�N�Ԃ͘r���v������@��ȂǂقƂ�ǂȂ������̂ł����A���w���ɂȂ蕃�ɘA����r���v���ɍs�����Ƃ́A��l�ɂȂ�V���̂悤�Ȃ��̂������̂ł��B�䂪�Ƃ̌������ĂƂ��ł��傤���B
�u��l�̎��v�v���c�@���q����̃G�b�Z�C
���w�Z2�N���B������ˑR�A�����r���v���Ă��Ă��ꂽ�B���܂��ܓ������X�ŁA�������̂�����������B�������č����o���ꂽ���B���i�ȕ��B���������́A�{���Ă��肾�����悤�ȋC������B�����炱���A���v�����A���̋@�����悩�������Ƃ̂ق��������������o��������B
�����̎�������ɂ͏�����l���ۂ����̂̂悤�Ɏv�����B�ނ��ނ��Ƃ����q���̘r�ɁA���̎��v�͏����s���������������A��������Ă��鎄������ƁA���͊��������ɏ��Ă����B
�u�ꐶ������悤�Ȃ��̂�I�v
�������A�d�r���ꂽ���Ƃ����������ɁA���̎��v�����Ȃ��Ȃ����B�����ɁA���s�̃V���o�[�̃u���X���b�g���̘r���v������悤�ɂȂ����B�����āA��w�ɓ����Ă���́A�r���v�������Ȃ��Ȃ����B�����N���Ƃ��������₵�����Ɍ����B
�u���̔����Ă�������v�A�{���͋C�ɓ���Ȃ�������Ȃ��̂��H�v
���̍��͎�����Ȃ������r���v�B20�ɂȂ��āA�悤�₭�������悤�ɂȂ�����A��������B
�u�Q�V���a�������߂łƂ��v
�n���ꂽ���̒��g�́A�r���v�������B�m�荇���ĂQ�N�B���߂ĉ����������A���łɒm���Ă������̂悤�ɋC���������B���X�A���������Ƃ�b�����сA���̐l�ɘb���ėǂ������Ǝv�����B�������ƂĂ����Ă����B
�ł��A�ނƂ͗��l�ɂȂ肻���ŁA�Ȃ�Ȃ������B���ɂƂ��Ĕނ́A�{���ɐM���o����Z�̂悤�ȑ��݂������B�u����ȍ����Ȃ��́A���Ȃ���v
�r���v��Ԃ����B
�o����ĊԂ��Ȃ��A�ނɍ������ꂽ���Ƃ�����B���̍����́A�ِ��Ƃ��Č�����A���̗ǂ�������ۂ��Ă����������B�F�B�Ƃ����W��I�����A�ނ��[�����Ă���Ă����B�Ԃ����r���v�����Ȃ���A�ނ͑������B
�u�������ɓ]���Ă��āA�P�N�ڂ͂������₵�������B�{���̌�����l���߂��ɂ��Ȃ��āA�ǓƂ������B�ł��A���݂ƒm�荇���Ă���̂Q�N�Ԃ͖{���Ɋy���������B�n���ɗ��ėǂ������A�Ǝv������B�ꏏ�ɂ������Ԃ�Y�ꂽ���Ȃ��B�Ō�ɁA��Ȑl�Ɋ撣���Ď��v�����Ƃ����v���o����肽���v�ނ͗����A�����ւ̓]�����܂��Ă����B
���̂܂ܗF�B�ł́A�����Ȃ��́H�ǂ����āA����Ȃ��ƌ����́H
���̎��v��u���āA�����狎���Ă��܂����肾�B�F�B���Ǝv���Ă����͎̂������������̂��낤���B
������������A�����Ɣނ������Ă����̂�������Ȃ��B
����͎��̎����ꂩ�A�A�A�B�킩��Ȃ��B���⎩���B
���������I�ɁA���́A�u���̂����痣��Ȃ��Łv�Ƃ͌����Ȃ������B�u�������ԁA��Ȍ��t�A�v���o�����肪�Ƃ��v
���͘r���v��������B���ꂩ��R�N�B
��Ȏv���o�����ɁA�V�����v���o�������݂Ȃ���A���̘r���v�͍������m�ɓ����Ă���B
�u�l�̃A���F�j���[�v���c�@��������̃G�b�Z�C
�l�����߂Ď��v���������̂́A���Z�ɓ��w�����Ƃ��������B
�Z�C�R�[�E�A���F�j���[�A���e�ɔ����Ă���������̂��B
�ȗ�12�N�ԁA�l�̐�����������Ă���Ă���B
�炢�Ƃ����A�y�����Ƃ����A�l��12�N�Ԃ����ׂĒm���Ă���B
�D���Ȏq�ɍ������Ăӂ�ꂽ�Ƃ��A��w�ɍ��i�����Ƃ��B�݂�Ȓm���Ă���B
������A�A���F�j���[�ɂ̓E�\�����Ȃ��B�S�������Ƃ����Ȃ̂��B�����⑼�l�ɃE�\�͂��Ă��A�Ȃ���������߂����B
�Ƃ��낪�ŋ߁A����ȃA���F�j���[�����q�����Ȃ��Ă����B�@�d�r�̐����Ԃ��Z���Ȃ��Ă����̂��B
�������Ƃ����Ƃ��ɐ�Ă��܂��A�͂�͂炷�邱�Ƃ��������B���т������ǁA�������낻������Ȃ̂��ȂƂ��v����B
�������Ŋ��̓��܂ŁA�A���F�j���[��r����͂������Ƃ͂Ȃ����낤�B
���łɂ��炾�̈ꕔ�̂悤�ȋC�����邵�A�����C�̂悤�ȑ��݂�������Ȃ��B
�l�ɂ͂Ƃ��ẮA�����b�N�X��I���K��艿�l���鎞�v���Ǝv�����̍��ł���B
�u�����r���v�������Ȃ��킯�v�{��@�בコ��̃G�b�Z�C
���͍��r���v�������Ă��Ȃ��B�Љ�l���i�ƌ����邩������Ȃ����A���Ԃ̃`�F�b�N�͌g�тł��܂��Ă���B�悭�A�r���v�Ƃ̊W�͂��̐l�̗��l�Ƃ̊W�Ǝ��Ă���ƌ����邪�A�{����������Ȃ��B����ۂNjC�ɓ��������̂��Ȃ���A�������Ă���̂͂���Ȃ̂��B�r���v�Ƃ����͉̂������ʂȊ���������B
�R�N�O��Ђ�ސE���A�F�B�ƃC���h�ɗ��s�����B�������r���v�������Ă������B����͕ꂪ�Ⴂ���g���Ă������v�ŁA���Ƃ��ƃA���e�B�[�N���D���Ȃ̂ŁA���̃N���V�J���ȕ����Ղ�seiko�̕\�L���ƂĂ��C�ɓ����Ă����B�܂��A�ꂩ���������̂Ƃ������Ƃ��Ȃ�ƂȂ��ւ炵���A�ڂ�ڂ�ɂȂ����x���g�������ō��̃��{���ɂ��ς����肵�đ�ɂ��Ă����B�����x���Ƃ���Ɉ�������������قǂŁA�����Ƃ��̎��v���g�����Ǝv���Ă����B
����Ǐ����Ăق�����ۂ��C���h�ł͘r�̃��{���͕s�����ŁA�܂����{�ɂ��鎞�ƈ���Ď��Ԃɒǂ�ꂸ�̂�т�߂����Ă����̂ŁA���s������Ǝ��v���͂����Ă��鎞�Ԃ������Ȃ��Ă������B�ړ����̓����b�N�̃|�P�b�g�ɓ���Ă����B�C���h�Ƃ������ƂŃ����b�N��o�b�O�ɂ��J�M�����ċC�����Ă����̂����A�|�P�b�g�܂ł͋C�����Ȃ������B�����Ă�����|�P�b�g�ɓ���Ă����͂��̎��v���Ȃ��Ȃ��Ă����̂��B���s�œ������̂��F�X���������A���̎��v�͂��܂�ɂ��傫�ȑ㏞�������B
�������ɘr���v������̂͂��ɂȂ邾�낤���H���l���ł���̂Ƃǂ��炪�悩�A�������g�C�ɂȂ�Ƃ���ł���B
�u���܂���v�\���@��������̃G�b�Z�C�@�@�i11-12���̃x�X�g�G�b�Z�C�j
�����ł����Ƃ́A�j�̌Z�����ŏ��̎q�̂��Ȃ��Ƃł����B�`��́A���̎q���~�����Ďd���Ȃ������̂ł����A�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��������̂ŁA�ł̎����g���̖��h�g���̕h�Ƒ�ɂ��Ă���܂����B�����A�ꔲ���ɖ��邭�ėD�����`�ꂪ�D���ł����B
����ȋ`��ɂ��A���������Ƃ��ЂƂ�������܂����B����́A�`�ꂪ�����Ă����l�X�ȕ������ł����B��ɂƂ��Ď��́A�g���킢�����h�Ȃ̂ŁA�����Ă���镨���ǂ�����킢�߂���̂ł��B���܂���`�̂����z�A�t���t���̃��{���A�������͗l�̃n���J�`�ȂǁA�ǂ�����w���̏��̎q�����ƌ������Ƃ���B�ł��A�`�ꂪ���܂肤�ꂵ�����ɔ����Ă��Ă����̂ŁA�u���ɂ͂�����ƁE�E�E�v�Ƃ͌������A���ƌ����Ď����ĕ������Ƃ��ł����A�{���ɍ���܂����B
��l�Ǝ�����������������A�`��͈ȑO�ƕς�炸�������킢�����Ă���܂����B���ɉ��x������ẮA�H����������A����������ł�����ׂ��������A�ʂꂽ��l�ɂ͓����ŁA��l�Ŋy�������Ԃ��߂����Ă��܂����B
�u���������Ă����Ȃ��͎��̖��I���������Ǝ���Ă����邩��ˁI�v
���ꂪ�`��̌��Ȃł����B
�������Č}��������29�̒a�����B�`��͘r���v���v���[���g���Ă���܂����B���ܕ��ł��Ȃ��A���Ԍ`�ł��Ȃ��A���̖��O�ƒa���̃I�p�[���������Ղɓ������������������͋C�̎��v�ł����B
�`��͌����܂����B
�u���̘r���v�͂ˁA����肾��B�ق�I���Ă����I�v
�`��ɑ�����A���͂��̘r���v�����Ă݂܂����B��������ċ`��́A
�u�ˁI�悭�������ł��傤�H���Ȃ���������l�����̂ˁB�v
�ƁA�܂�Ŏ��̋C������m���Ă������̗l�ɁA����������ۂ���ŏ��܂����B
���ꂩ��P�O�N�B�����A�`��̘r���v�́A���̘r�ɂ���܂��B�����ēV���֍s���Ă��܂����`��̑���ɁA��������Ă���Ă��܂��B
�u�r �� �E �J ���v���R�@�b������̃G�b�Z�C
���蕨����邱�Ƃ��A�ƂĂ���肾�B�܂��A��������͉̂��Ƃ��S�ɔ[�������邪�A�ِ�����́A�P�̂��\���ł��낤�Ƃ��f�肵�Ă���B���ꂪ�A���l�ł��낤�ƁA���������ς�ƁB�z�����A�`�ɂȂ���āA�C���ȂB
�ł���x�����A�r���v���w�����x�Ǝ�������Ƃ�����B����́A���̋L�O���ł��a�����ł��Ȃ����������B���̎d���p�̘r���v�̔�o���h�́A���Ȃ胈�^���^���Ă����B
���v�������Ȃ����ƌ����Ă��A�{���ɂ������肵�����v�́A����Ȃ�ɂ���B�Œ�ł����~�P�ʂɂȂ�B�ʏ�Ȃ�u�ԕi���Ă��ă`���[�_�C�b�I�v�Ɛ⋩���Ă����Ƃ��ł���B
�u���ׂ�����B�T�C�Y�͂���ρA��邢�Ȃ��B�ꏏ�ɒ����ɍs�����v�B�ނ́A�����B���������B���Ȃ���A���̍��r�ɁA����������܂��Ă����B�ւ炵���B
�O�Z���߂������������B��l�Ƃ����Z���̂悤�ɁA���݂����C�����Ă����B���v�̃T�C�Y���ɍs�����X�A���߂Ď���Ȃ��ŕ������B���ׂĂ��A�V�N�ȗ��������B
���v���X�̂����ɂ́A���E���̎��v���W�܂��Ă��邩�̂��炢�A�l�X�Ȏ��v���������B�u�{���́A���̃h���b�V�[�Ȃ̂ɂ��悤�Ǝv�������ǂ��v�B�����ƁA�R�O���~�ł͂Ȃ����B�����Ă���������v�̔����ւƓ����B���Ȃ��悤�ɂ��āA�ł��B�T���~�������E�E�E�R�O���~�̂��A�悩�����Ȃ��B�T���~�ł��A�[�������B�����ǁA�ǂ������S���̕ω����A���͕��ʂ̏��̎q���o�ɂȂ��Ă����B���ɂ��A�~�Ƃ����̂��������̂��ƁA�v�����B
�u���Ȃ��͋����A�����M�[�ł��傤�B������A�`�^���ɂ����v�B�t�������n�߂����ɁA�����Ȃ��������ꌾ���A�ނ��o���Ă��Ă��ꂽ���ƁB���ꂪ�A�����������B������B�������̎��́A����������̌������^�t�ɂȂ����B�������Ȃ��̂��낤�B����ǁA���̎��v�́A�ĂьĂэ�������҂��āA���葱���Ă���B�x���t�̏؋��A��B
�u�� ���v���R�@�b������̃G�b�Z�C
�����A���̐��ɖ{���ɂ��Ȃ��ƋC���t�����̂́A��������߂������낾�����B�ǂ����ĂP�N���A���̕s�݂������ł��Ȃ������̂��B�u��������A��������v�Ɖ�Ђɓd�b���������Ă����u�ԂɁA���̒��̉������܂��A�~�܂��Ă��܂����̂������B
�u��������ł��A���O�ɂ͉����c���Ȃ��v�����Ȃ��������́A���ɂ݂��ƂɁA�����c���Ȃ������B�ی����͐��O�����ɂȂ��Ă������A�o�c���Ă�����Ђ́A���z�̕��ɂē|�Y���Ă������B����ł���������I����āA���̎茳�ɂ́A�P���~�c�����B��������Y�̔��e�ɂ���̂́A�����肾���B
����Ȓ��A�Ђ������ƁA�B�ꕃ�ɔ����Ă�������r���v���o�Ă����B���Z�ɓ��w����ۂɁA��������ĂĔ����Ă����r���v�������B�@�ǂꂾ������ĂĂ������Ƃ����ƁA���͂n�ЁA�������ƕۏ؏����r�ЂŁA���v�͂b�ЁB�T�C�Y�����R�����ĂȂ��B�����ŃN���N�����B�u���\�Ȃ��O�ɂ́A��邢���炢�����傤�ǂ����B��v������A���v���v�B
���q������������A�݂�ȂƓ����悤�ȏ��̎q�炵���r���v�ɂ���������������B�ł��A���͂R�N�ԁA����������������̎��v�ƈꏏ�ɏ��q���ł̎��Ԃ��߂������B���ꂵ�������߂��������A�����ꏏ�������B
�u��������̐����Ă��鎞�Ԃ́A���������Ȃ��B�ł��A��������̎��v�́A�܂��܂�����������v�B�������Ǝg���ĂȂ������B���u���Ă����B�ł��A��v�Ŋ��Ȏ��v�B
�Ƃт���Â����v�X�ɂ����A���̎��v���Ăѓ������d�r�͂Ȃ��A�ʏ��荂�������B
���͂����ŁA�S�O�Ȃ��Ō�̂P���~���g�����B
�u�����c���Ȃ����Č��������ǁA�����Ǝc���Ă��炢�܂�������B��������A���ꂩ��������ƈꏏ�ł��A�����I�Ɂv�B���̎����A���̘r�̏�ŁA�܂������n�߂��B
�����N�A���́A������̕��ː����Â����B�ǓƂȕ��ː����̒��ŁA�����܂��������̂́A�܂�����Ȃ����̎��v���������B
�u�r���v���Ăѓ����n�߂�v�{���@�u�s����̃G�b�Z�C
���̎����Ă��鎞�v�͈�������B�������A��ꂽ�������v�B
���r��Ⴢꂪ����̂ŁA�r���v�͂��Ȃ���`���B
�E��ɂ͂߂�����̂��낤���ǁA�E�r�͗�����Ȃ̂�
�ז��ɂȂ�B
�Ȃ̂ŁA�������v�h���B
�������A�r���v�������Ƃ͂���B�ł��A�|�P�b�g��
���܂��A�r�Ɋ�����邱�Ƃ͂Ȃ������B
�͉̂������v�Ȃǔ����Ă��Ȃ��̂ŁA���邢�͔����Ă��Ă�
�{�i�I�ō����������̂Ŕ����Ȃ������B
���鎞������A���g���u�[���Ȃ̂��������v�̈������̂�
�o���悤�ɂȂ����B
��ꂽ�������v�͂��̎����ɔ��������̂��B
�������A�������v�͂�͂�s�ւŁA���x�����x�����Ƃ��Ă��܂�
���Ă��܂����B
���̎c�[�͍��ł���ɂ��܂��Ă���B
���������߂邽�߂ɁE�E�E
����ȗ��A���v�͔����Ă��Ȃ��B
�ł��A���̒��͕֗��Ȃ��̂��B
���v�@�\���������A�g�ѓd�b�Ƃ������̂����y���Ă��܂����B
�r���v�̑��݈Ӌ`�����ꂽ�B
����Ȑ܁A�����r���v����ɂ��镵�͋C�����܂��Ă����B
�u�N���X�}�X�v���[���g�͎��v�ɂ��悤�v
�ޏ������̂悤�Ȃ��Ƃ������Ă����̂��B
���������Ȕޏ��̊������ƁA�u�r���v�͂͂߂Ȃ���v�Ƃ�
�����ɂ����B
�������A������Ă��܂�����A�͂߂Ȃ��킯�ɂ������Ȃ��B
���v��������߂Ȃ��Ƃ�����B
���̒��ɂ͕t�����l�Ƃ������̂�����B
���v�́u�����v��v�Ƃ����@�\�����ł͂Ȃ��̂��B
�A�N�Z�T���A�v���[���g�A�X�e�[�^�X�E�E�E
���Ă��āA���̒��Ŏ~�܂��Ă����u�r���v�v�͍Ă�
�����o���̂ł��傤���E�E�E
�u�r���v���ق����vatsuko����̃G�b�Z�C
�q���̍��A�F�B�����X�ɘr���v���Ă�������������������B�������u�l�������Ă邩��ƌ����ĕK�v�Ȃ��v�ƁA�ǂ�ȂɎ����~�������Ă��A���e�͔����Ă͂���Ȃ������B
�Q�N���̃N���X�}�X�A�I�Ǝ��ł����������̓��A�w�Z�Łu�v���[���g�ɉ����������v�������������ƂɂȂ����B�����~�����������͓̂��R�A���Ȃ�ʘr���v�B���̃v���[���g�͂���ł͂Ȃ������B���A���Ԃ������ɉ���ė������A���͐����̂��Ȃ��ُ�S���ɂ����Č������B
�u���A�r���v�����v
�u�ւ��[�A�ǂ��������I�v�������玄���r���v��~�������Ă������Ƃ�m��F�B����A�������オ�����B
�u�ǂ�Ȏ��v�������!?�v
���͉ˋ�̘r���v�̓������ׂ������������B���F�ŁA���̃L�����N�^�[�ŁA�����Ղ̑傫���͂��̂��炢�ŁE�E�B��ʂ�b�����Ƃ���ŁA�Ƃ��ߏ��̈�l�̎q���������B
�u�����āv
�����A��ςȂ��ƂɂȂ����B����Șr���v�A�����ɂ͂Ȃ��̂��B�ǂ����悤�B
�A��āA���͋������B��Ɉ��������A�����ɋ������B�u�R����������A���āA�ӂ邵���Ȃ��ˁv�ƕ�͂₳�����������B
���ꂩ��S�N��A�U�N���̃N���X�}�X�B�d��X�Řr���v�������ƒ݂邳�ꂽ�A���邭��Ɖ��I�̑O�ɗ��������̋��̂Ƃ��߂��B�������̒�����A�D���Ȃ̂�I��ł����ƌ����Ă��ꂽ���̌��t�B�h�L�h�L���āi�ǂ�ɂ��悤�j�Ɩ��������̂Ƃ��̊������A�]�����S���Ă���B
�������Ď�ɂ����A�������L���b�g�̃s���N�F�̘r���v�B���N���v�������A����Ǝ�ɓ��ꂽ���̘r���v�B
���̘b������ƁA��́u����Ȃ��Ƃ����������H�v�ƌ����B���͂������Ȃ��B�ł���Ȃ��̎��v�́A�Ƃ��āA�v���o�ƂƂ��ɍ������݂������Ă���B
�u���߂Ă̘r���v�v���c�@����������̃G�b�Z�C
���Z�̓��w�j�ɁA�Q������̑c���������Ă��ꂽ�r���v�B���ꂪ���Ƙr���v�Ƃ̏��߂Ă̏o��ł����B���v�X�̃V���[�P�[�X�̒��ŐÂ��ɒN���Ƃ̏o���҂��Ă��������P�Z���`�߂�������A�i���O�̎芪���̘r���v�B�����Ղ������݂ǂ�F�Ŋp�̎�ꂽ�����`�̌`�����Ă��܂����B�����̌y�����v�ƈႢ�A�����ɂǂ�����Ƃ����d�݂�����܂����B��w�Ŏ��Ƃ𗣂�鎞���A�E�����܂��������X�Ɍ��������܂������������ƈꏏ�ł����B�y���Ĕ����r���v�����s���Ă��鎞���o���h���u���X���b�g���o�̂��̂ɑւ��������ŁA�����Ƒ�ȕł����B�Ȃ��Ȃ炻��͂����Ƃ����Ԃɑc���̌`���ɕς���Ă��܂�������Ȃ̂ł��B���v���Ă��������N��A�ň��̑c�������E���Ă��܂����̂ł��B����͂܂�Ŏ����̎������߂Â��Ă���Ɗ������c�����u�V���ł����Ǝ���������Ă��Ă���v�Ƃ������b�Z�[�W�ƈꏏ�ɔ����Ă��ꂽ�悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��̂ł��B
�������Ă���͎q��Ăɒǂ��A���̊Ԙr���v�͊O���Ă��܂����B�����āA���ł͔����Čy���r���v�ɑւ��Ă��܂��܂����B����ǁA��l�̔����Ă��ꂽ�ǂ�ȕ�����S�̂Ȃ��ł̈�Ԃ͂̕����������̘r���v�Ȃ̂ł��B�ł��A���̂��Ƃ͎�l�ɂ͓����ł��B
�u�싞���v���c�@���q����̃G�b�Z�C
�u����A�������k�����̌`���킯���~�����Ǝv���āB�v
�v���Ԃ�ɋA���������̕�Q��Ɍ����ԓ��ŏf�ꂩ��r���v����n���ꂽ�B
�́u���ł����v�̍ہA�����c��̘r�Ɍ����Ă����싞���ł���B�����A���p���ꂽ�w�l�p�r���v�ł���B
�c��ƕʂꂽ�̂͏\�̎��B�ڂ�Z��������A���܂�̋���B����������k�C���̑�w�ɐi�B�c�ꂩ�玄�̐g���Ă������Ŋw�����ɕւ肪�����Ă����̂����Â߂������A�����ɓǂ�łƌ����p�������������̂��v���o���B
�c��͒����ꂹ�ʂ���Ɛl�͎Ԃ����p�����B�����˂����ē��悵�A��l�̕G�ɂ�����ꂽ�P�b�g�̏�őc��̎�͗c�����̎�ɏd�˂��Ă����B
���̎��̘a���̑����ɗǂ��������������T���߂Șr���v���A�l�\�N�̎����o�Ď��̏��ɂ������B
��w���o�Ă��瓭���Â������ɂ͑傫���������͂����茩����b�j���̘r���v���K���i�������B�d���̍��Ԃ������Ă̂������ꔑ�̕�Q��ɂ���̍b�ɕ����Ղ������������m���߂Ȃ�����ł����B
�����̎��v���͂����A�c�ꂪ���Ă����悤�Ɏ��̓����ɕ����Ղ��������Ă݂��B���炵���߂Ă�����A�܂��j�������Ă���̂ɋC�������B�����A��`�ɂ��܂ł͂��̐j�̓����ƈꏏ�ɉ߂����Ă݂悤�B
�c����v���o���ƂƂ��Ɋ����̕ւ�ɂ��������t���v���o�����B
�E�E�E�����A��g����ɓ��X�����肭�����ꂽ����B�킪�g�ɑウ�Ă���肢�����ׂ��F�肨���B
�c��̕�O�Œ���l�߂Ă��������ꂽ�悤�Ɏ��͗܂��~�܂�Ȃ������B
�u�w��ȁv���c�@����Y����̃G�b�Z�C
��w�𑲋Ƃ��A�Љ�l�ɂȂ������ɔ������r���v�B���ʂǂ��Ƃ������ƂȂ��A�l�i���T��~���炢���������A���̌y���ƃt�B�b�g�����C�ɓ���A�ǂ��֍s���ɂ��g�ɕt���Ă����B
���N��A���싅�����Ă��Ďv��������o�b�g���X�C���O����ƁA�Ȃ����{�[���ƈꏏ�Ɏ��v�����ł������B�o���h���ꂽ�̂��B
�V�����o���h�ɕς��Ă��炭�t���Ă������A�Ȃ�ƂȂ��������肱�Ȃ��B�ȑO�̂悤�ȐS�n�����t�B�b�g�����Ȃ��̂��B���x���o���h�̎�ނ�ς��Ď������������������B�����Ŗl�͎v�����ăo���h���O���āA���v�̕����������Y�{���̃|�P�b�g�ɓ���Ď����^�Ԃ悤�ɂ����B
�ŏ��͂Ȃ��r�Ɏ��v���Ȃ��̂������������A�r�ɖڂ����u�����������v�Ƃ��炽�߂ă|�P�b�g���玞�v�����o�����Ƃ����x���������B����������Ă���ƁA�o���h���O���ꂽ�܂�ۂ̎��v�����ɂ��킢�炵���������A�|�P�b�g������o���Ƃ����s�ׂɂ��A�܂�Ńn���X�^�[��X�����|�P�b�g����o���悤�Ȋ��o���o����悤�ɂȂ����B�l����u���܉����H�v�ƕ�����A�|�P�b�g���玞�v���o���̂��ŏ��͏Ƃꂭ�����������A����ɂ��̃V�`���G�[�V�������y���߂�悤�ɂȂ��Ă����B
����ȊW�����������N��A���܂��ܗ�����������v�X�ŁA�l�͂���r���v�ɂЂƂߍ��ꂵ�A���̏�Ŕ������߂��B
���ꂩ�炵�炭���āA���̂܂�ۂ̎��v�͎p���������B�Ȃ������o���͂Ȃ��̂ɁA�ǂ���T���Ă����v�͏o�Ă��Ȃ������B
�ȗ��A�l�͊���̘r���v���A�r�ɂ͂߂Ă���B�����ʂ�r���v��r���v�Ƃ��Ďg���Ă���B���ł����X�A���Ԃ��m�F����̂ɖ��ӎ��ɃY�{���̃|�P�b�g��T���Ă��鎞������B�����āA�����ɂ��̊ۂ����G���Ȃ��̂ɋC�Â��A�₵����������B�l�͂����A�|�P�b�g�ɘr���v�����邱�Ƃ͓�x�ƂȂ����낤�B�����́g�����h�̎w��Ȃ�����B
�u���E���̊���ɂāv�b��@�ɐD����̃G�b�Z�C
�肩��̗�⊾���₽������G�炷�B�u�]�Z�̎��B�����Ĉ�ԋ��Ȑ��w�̎��ԁB��N���̎�����s��������������̍��Z���B��ɍ��i�����������B���̂��߂ɑ�R�������B���������������̓���҂��Ă����B���������w�A�킩��Ȃ���⑱�o�B�ł�͌����ɂłĂ���B�܂����܂����܂����B���̒��ōl���邱�Ƃ��ł邱�Ƃ���s���A��⊾�͎~�߂ǂȂ������B�s�ӂɏP���Ă����]���B���߂��E�E����f��̏u�Ԃł���B
�ӂƎ茳�ɒu���ꂽ�r���v�������B�{���ɖ��ӎ��̒��̍s���ł���B���������ɂ����r���v���B���ɂ͎������ɂ����搶���F�B���D���ȏ��̎q���A��Ă����Ȃ��B����������ɂ͂����Ă͂����Ȃ��B���X�ƁA����ɂ�����̂͂��̎��v�����ƂȂ�B������������������R�Ɛ��m�ɁB����ł��āu���߂�ȁv�ƋB�R�Ǝ����Ă���B�������Ă�z���B�����Ƒz�킹�Ă����āA�}�ɓ˂������B������悤�ȖڂŌ��Ă������Ď����~�߂Ă͂���Ȃ��B�����͊m�����͂��������Ă��܂����ޏ�����̒������������B�܂������A���̎��v�̐��i�͌��̔ޏ��ɂ�������ł���B�ǂ��ł������ꏏ�������B�������ꏏ�B�������A����ς���̏�ɏ��̎q�͒u���Ȃ��B����̗B��̖����A�r���v�B�����ɉ��x��܂��ꉽ�x�����̎������Ԃɖ|�M����Ă������E�E���������Ǝv���o�Ƃ�D������Ęr���v���u���߂Ă���v�Ƃ����̗l�X�Ȑ��i�����m�ɓ`����Ă���B�������Ď��v�͂��ɂȂ��������`����B�u�����������ĂȂ��ŁA�撣���Ă݂Ȃ�B���ɂ��Ă���Ă���B�c�莞�Ԃ́E�E�v�ƁB���̑z���͐S�̒��ɂ�������ƁB�����ꏏ�ɂ����F�B�ɗ�܂���Ă���̂ł���B��]���͉����֔�сA�����Ă܂����͈ӎ��̐��E�ւƖ߂�B���͈�l����Ȃ����I�����z���ƁA��]�Ȃ�Č�͑S�������Ȃ��B�����Ă܂���␔�w�ɗ����������Ă����̂ł���B���Ԃ͂��ƂQ�O���B��⊾�́A�����łȂ��B
�u���̘r���v����v�㓡�@���v����̃G�b�Z�C
���a�O�\�N��A���{���܂��n��������B�����a�C�ŐE�������A�䂪�Ƃ͌o�ϓI�ɐ��Ԃ̕��ς��܂������������Ă����B��̓��E�̂����ł���Ɠ��ꂽ���Z�ŗF�̑啔���́A�r���v�������Ă����B�ꂪ�A�u�r���v�����Ă��Ȃ��ăS�����ȁv�Ƃ����B�u���ɊW�Ȃ�����v��Ȃ��v�Ǝ��B����ǂƂ��Ă��~���������r���v�B���Z�O�N���ɂȂ��āA���߂Ď������r���v�́A�Z�����㌀�f��̑��y���̃G�L�X�g�������ăt�E�t�E�����Ĕ����Ă��ꂽ�B�F�ɒx��邱�Ɠ�N���������A�������Ċ������āB�o�X��d�Ԃ̒ʊw�Ō����č��炸�A��v�̍��r�����āA�r���v������������B�o������̂Ȃ�A�K��������̉p��ŁA�h�W�X�@�C�Y�@�}�C�@���X�g�E�I�b�`�h�Ƌ��т��������r���v�B�ꂪ�A�����Ă�肽���Ă������Ȃ��ŁA�����Ɨ܂��ʂ������r���v�B���Z����A���������ĂȂ������̂ɁA��ׂ̈ɏ��߂ẴA���o�C�g�ʼn҂��������Ŕ����Ă��ꂽ�r���v�B���A�l�R���V���N�V������O�̂悤�ɊF��Ȏ����Ă�r���v�Ȃ̂ɁA���̍��͂ƂĂ��������ґ�i�������B�ǂ̎��v�������悤�Ɏ�������ł���悤�Ɏv���邯��ǁA���܂�Ȃ�������������������������B���A�\��N�O�ɖS���Ȃ�������v�������ׂĂ���B
�u���̎���m�炳��āv�����@�q�O����̃G�b�Z�C
�͂��߂Ă�������ٗp�ی��Ŕ������̂́A���v�������B���̃_�C�o�[�E�I�b�`�́A�d�r������ē����Ȃ��܂܁A���o���ɂ��܂��Ă���B��x���g�ɋ߂������͎K�������o���A�Z���\�����������܂܂��B
���v�����Ǝv�����̂́A�ٗp�ی��̐�����ɍs�����Ƃ��������B�k��̃n���[���[�N�̃G���x�[�^�[�ŁA����I�[�o�[�̃u�U�[���Ȃ�܂ł����ς��ɏ�����l�����ƁA����ꏊ�͈ꏏ�B����͏c�ɒ��������ŁA�ǂ̓��Ԋu�ɒ����ʉ�������A�z�R���ɔ������ɐ��܂��Ă����B������̉�ꂾ�����B�����Ȃ́A�����Ă��Ȃ������B�������ߐs�����l�ɁA���܂�Ă����B�ǂ��Ȃ�낤�Ǝv�����B
������I����āA�����͂₭��������o���B�����o�������̂������B������U��悤�ɁA�A�E���T���˂A�Ǝv�����B���ɕ����̂́A�`�������B��w���w�̂Ƃ��ɒ�������̃X�[�c�͂������B���A���v�͂Ȃ������B�܂��͎��v���B
�������ē����o���ꏊ����̓I�ɂ��āA���邸��Ƌ��E�������͂��߂��̂������B
���̎��v��I�ԂƂ��A�ꎞ�Ԃ�����X�ɂ������낤���A�Ȃ��Ȃ����߂��Ȃ������B����ɂ��悤�B����܂āA�Ƃ�����l�̎����B���ɂ������́A�d�������́A�����ȗ��R�����āA�V���[�P�[�X�̑O�ŋ���ł͗��������B���E�������|�������̂��B���̎����v�́A���E�Ƌ��E�Ƃ�m�点�Ă����̂������B
���ꂩ�牽�x���A�E�̖ʐڂɍs�����B���̃_�C�o�[�E�H�b�`�����r�ɂ��Ȃ���B���ԂɊԂɍ������ǂ��������܂��肠���A�ʐڂ��I����ĈӖ��Ȃ����߁B���v�͂����Ȃɂ����킸�A�����Ԃ�����ڂ��Ɏ��Ԃ������邾���������B���T�������Ƃ��J��Ԃ��A�����悤�ɂ܂��ʐڂցB���܂ł��I���Ȃ��A�o���Ȃ��ꏊ�ɖ������悤�ȋC�����Ă����B
�A���o�C�g���������A�d�����͂��߂�悤�ɂȂ����B���R�̂悤�Ɏ��v�����Ȃ��Ȃ����B�g�ѓd�b�������͂��߂āA���ꂪ���v�����ɂȂ����̂������B�Ђ������ɂ��܂����܂܂̎��v�����܂Ɍ��߂�B�܂������Ă��B����͏I�����m�F���邽�߂��������B���x���]�E���邤���A���v�̂��Ƃ������Y��Ă����B
����Ƃ��A�ӂƂЂ������������āA���v���Ƃ܂��Ă��邱�ƂɋC�Â����B�Ȃ�̊�����������ł͂��Ȃ������B�K�v�̂Ȃ��Ȃ�������ɁA�C�����̂����悤���Ȃ������̂��B
����ɂƂ��Ē��߂Ă݂�B�����z�����x���g�͂���݂�������B���̂������K���X�ʂ͎w��ł������āB
���x�A�������Ă݂悤�B�������łȂ��������ނ��Ƃ��ł��邾�낤���B���̎��v�Ƒ��k���Ȃ���B
�u�⍥���Ƙr���v�v�{��@�j�N����̃G�b�Z�C
���ɂ͍��Z���ォ�炾����R�O�N���t�������Ă���F�l������B�Љ�l�ɂȂ��Ă܂��Ȃ����Ď��͔ނ̌�����I���̎i����Ƃ߂��B�ꏊ�͉��l�`�ɖʂ����R������z�e���B�����ł��܂�R���������Ƃ͂����Ȃ���l�̐���Ȕ�I���͎���s��ꂽ�̂ł���B������A���̂��Ƃɏ����ȑ��蕨���͂���ꂽ�B�i��̑�C���ʂ��������ւ̔ނ̗��e����̂���̕i�B�N�I�[�c�̘r���v�������B���͍��Z���w���ɗ��e�������������������̘r���v���g�������Ă������A���̓����玄�̍����ɂ͔琻�x���g�̃N�I�[�c�r���v��������悤�ɂȂ����̂ł���B���ꂩ���\���N�A���Օi�ł���d�r��o���h�����x�ƂȂ����������B���łɎ��v���̂��̂̉��i����z��d�r��o���h�ɓ��������ƂɂȂ낤�B�Q�A�R�N�O�A�ߐ�̋߂��ɂ����������Ȏ��v������œd�r���������Ă�������Ƃ��̂��Ƃ��B�����Ă��ꂽ�X��Ǝv����V�l�͂W�O���߂��Ă����ɈႢ�Ȃ��B������ƂɂƂ肩�������̂����A�Ȃ��Ȃ����u�^���J���Ȃ��B�̂��������͂̐��������邾�낤�B���������܂��傤���Ƃ��������قǍׂ�����Ƃ͂������ɂ݂����B�悤�₭���Ԃ����J�������ȓ������I�o�����Ɓu�������v�ł��˂��B���͂���Ȃ̍��Ȃ��ł���B�厖�ɂ��Ă��������ˁv�ڂ��ׂ߂Đ����ȓ�����`�����݂Ȃ���X��͂��ꂵ�����ɂ������B���ł����̎��v�͎��̍����ɂ܂���Ă���B�ނ̗��e�ɂ��������Ă��炷���ɁA��Ђ̃^�C�v���C�^�[�̊p�ɂԂ��Ă��Ă��܂��������\�ʂɂ�����̂́A���܂��ɐ��m�Ɏ������ݑ����Ă���B�r���v�͌��C�����A�Ƃ�g�ɂȂ��Ă��܂����ނɂ͍ŋߌ��C���Ȃ��B�Q�N�O�ˑR�����S���Ȃ����̂ł���B�������C�Ȃ�Η��N��l�͋⍥�����ނ�����͂��������̂ɁB
�u�����p���z���v�����@�a�q����̃G�b�Z�C
�O�\���N�O���l�̌�j�ɕ��ɔ����Ă�������A�[�����h�^�̂˂��������v�B
������͖��̘r�ɂ���B
���l���O����ȍs���̎��ɒ���哇�̒����ɒ��ւ����������܂�̕��͎��Ɂu���o�|���̕��𒅂Ă��Ȃ����I�v�Ɩ��߂����B�A��čs���ꂽ��͎��v������B�����ŕ��͕w�l�p�̎��v��В[���玄�̘r�ɒ����Ă������B
���ꎞ�Ԃ����������낤���A�u�悵���ꂾ�I�v�Ɩ������ɔ������߂����̂ł���B
�������Y�ꋎ��ꋾ��̈����o���ɓ����Ă����̂������Ă��Ă������B
�����6�����A�ꕪ�ł��߂���ƌ��ւɐm�������ɗ����Ă������B���x���v�����Ȃ��瑖�������Ƃ��B
�u�K���ɂȂ��v�ƖڂɈ�t�̗܂��ׂȂ��琸��t�̏Ί�ő���o���Ă��ꂽ���B
�����������ɂ��̐��ɗ����������̎v���������̘r�ɂ��鎞�v���݂đz���B
�������ƗD���������킹�����������̒j�B���x�ƂȂ�����o���ꂽ��n�B�I���͉Ƒ��ׂ̈ɓ��������ڂ��������B�����̖]�l�����͂����ĕ���ł����̂��낤���B
���o���Ă��Ă͂˂��������Ă��閺�̔w���ɐS�̒��Ő����������B
�M���͋M�����g���]�ޑf�G�Ȏ�������ŁA�ƁB
�u�����̎咣�B�v���肱��������̃G�b�Z�C
���w�Z�̂Ƃ����璇�̗ǂ��������Ƃ����B
�ʁX�̍��Z�ɐi��ł���͂Ȃ��Ȃ���@����Ȃ���������ǁA
�ޏ��̒a�����̏������ƁA�~�̂�����A���Z�r���ɋ��R�ꏏ�ɂȂ��āA
���]�Ԃ��߂Ē��X�Ƃ�����ׂ�������B�ӂƁA���Ƃ���ƂĂ��f�G�Șr���v�����Ă���̂ɋC�Â����B
�ׂ����F�̃x���g�A�ؖڒ��̕����ՁA���F�̐j�B
�[���̌i�F�̂Ȃ��ŁA����͖{���ɂ��ꂢ�Ɍ������B
�����`����ƁA���Ƃ����͊��������ɔނɂ�������̂��Ɠ������B
�ޏ��̗����A�����炢�n�܂肾�������Ƃ͕����Ă����B
���̎��������z���āA�ޏ��͈ӎv�̋�����Ŕ���ł���B
�킽���͏o���̌��������Ă��鎩���̕Бz�����v���A
�킽����������D���Ȑl����f�G�Șr���v�����炨���ƌ��߂��B
���ꂩ��Q�N�Ԃ̍��Z�����B
���Ƃ����̍����ł͑f�G�Ȏ��v�����Ԃ����݂Â�
(�킽���̒m��Ȃ��Ƃ���ŏC���ɏo������������Ȃ�)�A
�킽���̗��͍Ō�ɉ��邱�ƂɂȂ�B���Z�𑲋Ƃ��Ă��炭��������A�w�ł��Ƃ����ɉ�����B
�J�W���A���ȕ����ɕi��Y����悤�ȁA��F�̃u���X�E�H�b�`�B
�킽���̐S�z�͂������̂��ƞX�J�ŁA
�V�������v����������̂��Ɣޏ��͗]�T�̏Ί�Ō������B�ŏ��̘r���v�������Ă�����Ă�����������P�O�N�B
�킽���̍����ɂ͎����Ŕ������r���v������B
�����őI��Ŏ����Ŕ����B�P�O�N�Ԃł���Ȋ�т��m�����B
����ł��A�����N�����Z���X�̂����ؚ��Șr���v��
�����Ă���Ȃ����ƁA�~���߂Â��Ɩ����Ă��܂��̂��B�킽���͂P�N�x��đ�w�ɓ����Ēn���𗣂�A
����ȗ��ޏ��ɂ͉���Ă��Ȃ��B
���܂���ǂ����Ă��邾�낤�B
����ڂ��̎��v���ޏ��Ɏ��Ԃ������Ă��邾�낤���B
����Ƃ��ʂ̐l�ƕʂ̎��Ԃ�����Ă��邾�낤���B
�ǂ���Ȃ̂��͂킩��Ȃ�����ǁA
���̂Q�̎��v�������ޏ��̕ł���܂��悤�ɁB
�u���a�{�P�H�v���� �z�q����̃G�b�Z�C
���������e���̋��|�������Ȃ��܂܂̂Q�O�O�P�N�P�P���A�씼���ٍ̈��H�̓쓇�ŁA�v�̘r���v�������S���Ԃ̌��n���Ԃɍ��킹�A���̎��v�͓��{���Ԃ̂܂܂ŁA�t���[�X�^�C���c�A�[���X�^�[�g�������B
�p��b�\�͂Ȃ��̒��N�v�w�̓�l�O�r�́A���a�ȍ��Ńg���u���Ȃ��B�����͍������Ŗk���ւƌ����[���ɁA���n�œn���ꂽ�v�����g���`�F�b�N���ăM���b�I�z�e���ւ̌}�����A��`�o���T���O�ɂȂ��Ă���B��`�܂Ő����̋����A�����č������Ƃ͌����A���x��Ă��܂��͕̂K���B
�u���`��A����������˂��v
�Q�Ăēd�b������A�������蕽�a�{�P�����悤�ȓ����B�p�j�b�N�ɂȂ��������炪�o�J�݂����B
�P���ԑ����}���ɒ�������ꌏ�����ƂȂ������A�e���̂����������n����̍��Ƃ͎v���Ȃ����Ղ��B
���a�Ȃ��̍��ł́A���Ԃ̗��ꂪ�悻�Ə����Ⴄ�̂�����H
�y���̐₦�Ȃ��k�����A�炸�A���̂܂ܕ��a�̒��ɕ�炵�����B
���a�{�P�����������l�Ԃɂ��\���Ȃ��ɁA��̎��v�͂��ꂼ���
���Ԃ��x�݂Ȃ����ݑ������B
�P�O���Ԃɋy�ԋA���ւ̒��ŁA�v�̎��v�͓��{���Ԃɖ����߂��ꂽ�B
�u������̑厖�ȑ��蕨�v�n�Ӂ@����Ђ�����̃G�b�Z�C
��ԍŏ��ɘr���v���������̂́A���Z��N�̎��B�������x�@���Ƃ��ċΑ���\�N�ł�������r���v����w�j���Ɏ��ɂ��ꂽ�̂ł��B�n���������̋Α��L�O�Ȃǂ͂���������Ă��āA���Y�̂˂��������̘r���v�ł������A�ƂĂ������������L�����c���Ă��܂��B
�����g�͂���܂Ŏ��v�͎��ɂ͋S�傾�����̂ł��B���̂Ȃ�����{�ʂŁA��������̑厖�ȉ������v����̂����ɖ߂��Ȃ��������ŁA�ߋ�����ꂽ�����L��������ł��B
���̌�A���͌̋����痣��āA�Z�N�Ԃ̑�w�������o�ĎЉ�l�ƂȂ�܂����B�����ĉƑ������g�ɂȂ��āA�ӂƉ������n���ƁA����قǑ厖�Ȃȑ��蕨���������v���ǂ��Ȃ��������A�S������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�����A�̏Ⴗ��Ɠ����ɁA�����͂�肾�����f�W�^���^�̎��v��ւ��āA�ǂ����ɂ����Ă��܂����̂��Ǝv���܂��B
���������f�W�^�����v������ɗL������̏Ⴕ�Č���������ŁA���̏\�N�Ԃ��]��r���v�ɂ͉��̖��������𑗂��Ă��܂����B�����Ƃ�������̘r���v��厖�ɂ��Ȃ���������������܂���B
���A����g���Ă���̂́A�C�O�o���ŕK�v��������J���̕\�����o���鑽�@�\�^�̎��v�ł��B����͂����g���Ďl�N���o�ł��傤���B�J�����_�[�����Ă��Ċ��Ȃ̂ŁA���p���Ă��܂��B�����ЂƂ́A�`�������������A�����b�N�X�Ɏ������Y�r���v�ł��B����̓h���X�A�b�v�������Ɍ떂�����Ďg���Ă��܂��B
���̂悤�Ɏ��ɂƂ��āA���v�͖����Ă͂Ȃ�Ȃ����̂́A��ԑ厖�Ȃ��̂������Ĉȗ��A�����̂�����̂Ƃ��Ď�舵���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B������A�����b�N�X����W���Ȃǂ̍����i�͗v��Ȃ�����ǁA���̑厖�Ȏ��v��������x��ɂ���āA��������Ɋ��ӂ������Ǝv���܂��B
�u���߂Ă̘r���v�v�R���@��q����̃G�b�Z�C
���̍��A���Z�̓��w�j���Ƃ����Θr���v�ƌ��܂��Ă����B�Ƃ����̂͌���ꂽ�G���A�������ł̘b���낤���B���Ȃ��Ƃ��P�X�V�O�N�㏉�߂̎��̎��͂ł́A���̂悤�ȋ��ʗ������ł��Ă����͂��ł���B���̍��̎��ɂƂ��Ęr���v�Ƃ́A�P�Ɏ����������Ă���铹��ł͂Ȃ������B����͍��Z���̏A�Ђ��Ă͑�l�ւ̑����ݏo�����Ƃ����ؖ����̂悤�Ȃ��̂ł������B���w���ł͍Z���ᔽ�ƂȂ邽�߂ł��Ȃ������u�r���v�����ēo�Z����v����Ȃ��킢�Ȃ��s�ׂ��A���Z���ɂȂ������Ƃ����������������Ă��ꂽ�̂ł���B
���̏��߂Ă̘r���v�A����͎l�p���đ傫�ȁA�����Ղ̐F���Z���O���[�̒j���p�������B
�u�ǂ����Ēj���Ȃ́H�v�Ƃ��Ԃ����ɂ́A�u�������傫���Č��₷������v�Ɛ������Ă������A�ؚ��ȏ����p�����ɂ͂ǂ����Ă��������Ƃ͎v���Ȃ������̂��B
�]�ݒʂ�̎��v����w�j���ɂ���������́A���ꂩ��Ƃ������́A�C�ɂȂ��Ďd���Ȃ������B�K�v���Ȃ��̂ɍ�����グ�������ẮA���̓x�ɂR�`�S�Z���`�ړ���������̗₽�����G���A���������ъy���낤���B�����Ղ̈ʒu������ɂ�����A�O���ɂ��Ă݂���A�܂����ɒ��ڂ���̂ł͂Ȃ��A�����̑��̏ォ��͂߂Ă݂���ƁA�v�������Ȏ������Ă������̂��B�{��ǂނӂ�����āA�O�����ɂ����ƒ��߂Ă������Ƃ��������B
�����Ă��̓������̍��Z�ł́A�J�b�v�����m�͂��݂��̎��v�������������Ƃ������Ƃ����s���Ă����B�ނ̎��v�����肩��̂������Ă��鏗�̎q�́A�A�]�̓I�ł������B�ޏ��������g���A�Ȃ������������������������Ă���悤�ȁA�ւ炵���ȋ�C��Y�킹�Ă����B
����ȕ��͋C���x�z�I�ł��������A���ĂȂ�����ǁA�v���C�h�����͍����������́A������v���A�������Ȃ��̂Ɂu�ނ̘r���v�����Ă���v������Ă����ɈႢ�Ȃ��̂��B����Ȏ��Ȗ����̓��X�𑗂邱�Ƃ��ł����̂��A���̘r���v�̂������ł��邱�Ƃ����������悤�B
�u�r���v�̂��l�сv�㓡�@������̃G�b�Z�C
�ޏ����ł���܂ŁA�l�͘r���v���͂߂Ȃ������B�����ނ����䂢���G�������������B
���鎞�A�҂����킹�������B�X�̂ǂ����Ɏ��v�����邩��ƁA�y���C�����ł����B�҂����킹�̏ꏊ�ɁA�ޏ��̎p�͂Ȃ������B�l�����������������C�������������B�\�����߂���ƁA���Ԃ��C�ɂȂ�n�߂��B�X�p�ɂ��鎞�v��T�����B�����A�Ȃ��Ȃ�������Ȃ��B�l�͐S�̒��Ɂu�Ђ���Ƃ��āv�Ƃ̕s�����N���オ���Ă����B
�������������������Ă����B�O�\�����炢�Ƃ̐S�����ł��������A����͐l�Ԃ̐g����Ȏ��ԒP�ʂł������B�v�����Ēʍs�l�Ɏ��Ԃ����B�u�\���߂��ł���v���̌��t�Ɉ��R�Ƃ����B
�Z���̑҂����킹�B���ۂɖl�������̂́A����ł͔������߂��Ă����̂��B�Ƃ̎��v���Ԓx��ł��邱�Ƃ�m��Ȃ������B���̉����ł���҂����킹���Ԃ��A�Ԃ��x��Ă����B
�Ԃ��҂����炵���A�ޏ��̎p�͂Ȃ��Ɣ������B�����ڂ肵�Ȃ���ƂɋA�����B�ޏ��ɘl�т̓d�b����ꂽ�B�u�˂�����Ȃ��ŁA�r���v���͂߂Ȃ�����B�v�l�͂���ɏ]�����B
�u�q��đ��ƋL�O�܁v���c�@�[�q����̃G�b�Z�C
���́A���N������A�܂��ዾ�������āA�r���v������B��A�Q��O�ɁA�ዾ���O���āA�r���v���͂����B
���̈���ƍs�������ɂ��Ă���r���v�́A�V���o�[�̋����̃x���g�ɐ������Ղ̂�₲�����X�|�[�c�^�C�v�̂��́B�����ɂ��A��ҍD�݂Ƃ��������Ȃ̂́A�S�N�O�ɑ��q�����߂Ă̋�������A�����őI��ŁA�v�ƃy�A�łƔ����Ă��ꂽ���̂�����Ȃ̂��B������A���̎��v�́A���̎q��đ��ƋL�O�܂Ƃ�������B���́A���q�̋C�������ꂵ���A�ȗ��A�����r�ɂ͂߂ĉ߂����Ă����B�@
�����āA���̎��v������ł������Ԃ́A�v�Ɠ�l����ɂȂ������X�̎��ԁB
�v���A�o��œˑR�|�ꂽ�ƘA�����A�d�Ԃ̎��Ԃ����Ȃ���w�ɂ��������Ƃ����E�E
�a�@�։^�э��v�̌������̎��Ԃ��A�E�E
�����������v�̖ʉ�Ԃɍ��킹�ďo������Ƃ����E�E
�މ@�����v�ɕt���Y���āA�ʉ@����Ƃ��́A�L���ł̒��������҂����Ԃ��E�E
�����āA���E�����v���A���A���ӍQ�����w�ւƑ���}������Ƃ����E�E
�݂�ȍ���ł����E�E�E�B
����ɁA���ꂩ��́A��N���}�����v�Ƃ̈������̎��Ԃ�����ł����Ă����̂��낤���̎��v�E�E
�ł���A��l�̗����������A�Ί�������킹�鎞�Ԃ�����ł����Ă��炢�����E�E
���q�����ꂽ�r���v�E�E�E
�u���F�����v�v���c�@��������̃G�b�Z�C
����͒��w���ɂȂ�������̍��A�ꂪ�č����ĐV�������ƕ�炵�n�߂����A���͍č��ɔ����Ă����̂ō��܂łǂ���c�����ɏZ��ł����B
�������n�܂�A�����ׂ̈Ɉ�l�ŋN���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ莞�v���K�v�������B��Ќ�����̑c�����̎������̊��ɂ͉��F�����v���|�c���ƁA�u����Ă����B�Ȃ�������Ɏ����o���A�����̕��ɂ��Ă��܂����B�ォ��f���̕����ƒm�������A�����������Ă��邱�Ƃ̓i�C�V���ɂ��Ă����̂ł���B���ہA�����������͂Ȃ������Ŗڊo�܂�����Ɏg���݂̂��������ƂƁA�q���S�ɂ��܂荂���ł͂Ȃ����Ƃ�m���Ă������炾�Ǝv���B
���̎��v�͏f���̎茳�ɋA�鎖�����A���̌�����Z�E�Z��E�A�E�E�����ƍ��v�W��̈��z�������ɂ��Ă����̂����A�������ĂP�N���炢���������A���ɉ��Ă��܂����B�����Ƃ����Ɏ茳�ɂ͖�������ǁA���F�����v��������x�ɂ��̍��̎v���o�╡�G�ȐS���A�����Ė��f�Ŏ����̕��ɂ��Ă��܂����ꂢ�C��������݂�����̂ł��B
�u�A���N�����v�v�r��@�M��Y����̃G�b�Z�C
�����A�c�t���ɓ���O���炢�̎��A�e���r�ԑg�Łu�W���C�A���g���{�v�Ƃ����̂�����Ă��܂����B
����̏��N���A�g�����V�[�o�����˂��r���v���疽�߂��āA���b���������Ƃ����́E�E�E�B
�q���S�Ȃ���Ɂu�r���v���͂߂鎖���J�b�R�C�C�I�v�@�ƈ����ɍl���Ă������́A���̍�����r���v�ւ̎��������l�ɂȂ�܂����B
�ŏ��͘r�Ɏ��v�̊G��`���Ă��܂������A�}�W�b�N�ŕ`���̂ŁA�����C�Ő���Ă��Ȃ��Ȃ������Ȃ��A�������A�����A�`���̂ŏ��X�ɐՂ��c��l�ɂȂ��Ă��܂��A�e�������˂Ă�������̎��v���Ă��܂����B
�������A�{���̎��v�̏d�ʊ��ɖ��͂������Ă������́A��������̎��v�ł͖��������A�X�ɖ{���̎��v�ւ̎��������߂Ă����܂����B���w�Z�ɏオ�鍠�A�f�ꂪ�������A���̒U�߂���ł���f������ɂ́A�ƂĂ��������Ē����܂����B�f��v�Ȃ͒n���ɏZ��ł����ׁA���͔̂N�ɂP�C�Q����x�ł����̂ŁA���̎��Ƃ���Ɏv��������V��ł�����Ă��܂����B
���鎞�A�ڂɕt�����̂��f������̘r���v�B�����ɂ͒������A���@�\�̘r���v�ł����B���̍��́A��l���͂߂Ă��鎞�v�͕K���`�F�b�N���Ă����̂ł����A���̎��v�̎������͍��ł��n�b�L���o���Ă��܂��B
����ۂǃJ�b�R�ǂ��������̂��A�v�킸�A�u��������A���̎��v�A�J�b�R�C�C�ˁI�v�ƌ����Ă��܂��܂����B
�����āA�}�X�������u�v��Ȃ��Ȃ�����A���傤�����ˁH�v�ƌ��������̌��t�ɁA�u���������A����������Ƒ傫���Ȃ�����ȁB�v�Ɠ����Ă���܂����B
���ꂩ��Q�C�R�N�̊Ԃ́A�f������Ɖ�x�ɁA�u���ɂȂ����炭���낤�H�v�ƐS�̒��Ŏv�����A�����āA���v�̎��͌��ɂ͏o���܂���ł����B���X�A�u�Ⴆ�Ȃ�����ȁB�v�Ƃ��v���Ă��܂����B
����Ƃ����̂��A�u���傤�����ˁH�v�ƌ���������e�����Ă��āA��ŁA�����҂ǂ������Ă��܂����̂ł��B���w�Z�S�N�̎��̒a�������߂Â������A�����ɁA����͂��܂����B����l�͏f������ł��B�u���������āI�v�Ƃ����v���ɋ���Ȃ���A��݂��J������A������ƃP�[�X�Ɏ��܂����A�f������̎��v�������Ă��܂����A��ʂ̎莆�Ƌ��ɁE�E�E�B�@�莆�ɂ�
�@�u���h�Ȓj�ɂȂ������Ǝv���܂��B�ʂ�A���v�𑗂�܂��B���w���ɂȂ�����g���l�ɁI�v�Ə����Ă���܂����B���́A�u���w����߂܂��ė��h�Ȓj�͂Ȃ����낤�H�v�Ǝv���Ȃ�����A�������̂��܂�A�Ƃ̒���]���܂���Ċ�т܂����B�w�Z�̍앶�ɂ��A���̎��v�ɂ܂��b�����������L��������܂��B
�@���ꂩ��A���w�ɏオ��܂ł̂Q�N���̊ԁA���̈����o���ɂ��܂������v���̗l�ɒ��߂Ȃ���A���o���Ă����f���炵���f������Ɋ��ӂ��Ă��܂����B
�u���v�ƈꏏ�ɉ߂��������ԁv���c�@�z�q����̃G�b�Z�C
���̘r���v�͎����n�߂Ęr�ɂ������v�ŁA���Z�̂Ƃ��ɕ�ƈꏏ�ɓX�ɍs���đI�B���ꂩ�炸���ƈꏏ�ɓ������Ԃ��߂����Ă����B���ł͎��v�����Ă��Ȃ��ƁA���Ԃ�������Ȃ����č���悤�ɂȂ����B
����A�ǂꂾ���̎��Ԏ��v������̂��낤�H���ɉ�����������̂���Ȃ��Ă��A����Ȃ�̎��Ԍ��Ă���Ǝv���B
���̎��v�͋�����������A�̉������v�Ɏc��₷���B���̋G�߁A�����v������Ƃ��͗₽�����v�ɂ����ڂ��o�܂�������B���ꂩ��w�Z�ɍs�����߂́A�C���̈������߁B
����ł��A�g�ɕt���Ă��邤���ɁA�₪�Ď��̑̉��Ɠ����ɂȂ��Ă����B�����Ď��v���O�������A�u����������I������ȁv���ċC���ɂ�������B���v�̉������Ă����̉��ƈꏏ�Ɏ���������ɂ��B
���̎��v�ɏ����Ă���������Ƃ�����B���ʂ��Ă���w�Z�́A�������ē������w�Z���B�����肪�������A�����~�܂�c�Ȃ�Ďv�����B�����v���Ď��v�����Ă��A�����~�܂鎖�Ȃ�Ė����B�ł��A�ς��Ȃ������ō��܂�Ă����b�j�����Ă�����A�����������Ƃ��o�����B���v�́A���Ԃ������邾���łȂ���Â������ꂽ�̂������B
�u�o����̎��v�v�����@��������̃G�b�Z�C
�����A30�N�O�B5�Ώ�̎o�́A���w�Z�𑲋Ƃ���ƁA�莞�����Z�ɒʂ��A�a�щ�Ђɋ߂邱�ƂɂȂ����B���̗��Ƃ���ꂽ����B�~�̂�����A�j�̐l���A�e�Ƙb�����Ă����B���Ă��炦����ƁA�r���v��������ꂽ�e�B���v���A�A�E�j���B�h�A�z���ɁA�����ς܂��ĕ����Ă������́A10�˂���B�o����A���v�̑���ɁA�s���Ă��܂��Ɣ߂����Ȃ������B���ꂩ����X�͉߂��A�o��3�l�̎q�̐e�ɂȂ����B2�l�́A�������Z�ɓ���A���Ƃ����B3�j�V�́A�������܂����炵�����A�����Ȃ���A�莞���ɒʂ���J��m���Ă��邹�����낤�B���̎q�ŏI��肾����A�����ł��d���Ȃ��Ƃ����B���́A�������Z�ɒʂ킹�Ă�����������ɁA�������g�������B�u���v�ƈ��������ɁA�o�����Ȃ��Ȃ�Ƌ��������́A�����B�v
�u�����݂����̘r���v�v�����@��������̃G�b�Z�C
���͍��Z���ƌ�A���K�ŕa�@�ɋ߁A���ɓ������B���ł̊w�Z�ɔ������悢�A�����d��������B��y�ɏK���A���҂���Ɛڂ�����X�B�g�C���|���A���C�|���A�a���̑|�����B�Ȃ�Ȃ��A�c�ɖ��B���ɂ́A�����^�[�o���B���҂����A�t���Y���̉Ƒ��̕����A�₳�������������Ă����B�̏�ɂ��A3�N������A�撣��ƁB�e���𗣂�A���̒��ɂ��܂����X�B�S�ɁA�E�C�Ɗ�]�������B���ɂ́A�Y�݂��Ă�������A��܂��Ă����A�����̗F��A��y�A��i�B�����āA�r�ɂ́A�A�E�j���ɔ����Ă��ꂽ�ꂩ��r���v�B���Ԃ�����A�����͂���A�_�H�̓H�������킷�B�����āA�߂����Ƃ��A�炢�Ƃ��A���v������ƁA��������̊炪������ŁA�r���œ����o���Ȃ��Ȃ��Ďv���撣�ꂽ�B�d�r���ꂽ����ɂ́A�����Ȃ�A�S�ɗ]�T�����܂�Ă��B
�u�M�d�i���������v�v�����҂���̃G�b�Z�C
���v�������Ȃ��l�������Ă���炵���B�g�ѓd�b�̎����ł킩���Ă��܂����炾�������B
�����玞�v���Ăǂ��ł��������̂ɂȂ��Ă��܂����̂��낤�B
�����̓s�����q���ɒʂ��Ă������ɂ͍��ł��v���o�����Ƃ�����B���w�A��w������w�Z�ł܂��A�o�ϓI�ɂ͗]�T�̂���ƒ�̎q���肾�����B���ɂ͉ċx�݊ȒP�Ɂu�n���C�v���Ƒ����s�̎q�����Ăт����肵���L��������B������20�N�O�̂��Ƃ����炩�Ȃ蒿�������Ƃ������B�T�����[�}���̎q�ł��鎄�͏������Ȃ��Ă����B
�̈�̎��Ƃ̂Ƃ��A�M�d�i�܂�����A�F�����z�������ɓ���搶�ɗa�����Ă��炤���܂肪�������B����ȗT���Ȏq���������Z�Ȃ̂ɘr���v�������Ă���q�S�������̑܂ɓ��R�̂悤�Ɏ��v����ꂽ�B���v�͊ԈႢ�Ȃ��A�M�d�i�������B�����Ȃ�����A���Ƃ����肵����T���܂�茩����Ȃ��Ƃ������肷����̂������B���ɂƂ��Ă������������B�ł����͂ǂ����낤�H
100�~�V���b�v�Ŏ��͘r���v���q���ɔ����ė^���Ă���B�܂������̂������ኴ�o�ŁB
���z�ɂ͋C���������A�����ł��Ȃ��r���v�𓐂ސl�����Ȃ����낤�A�ƃX�[�p�[�K���Ŋ��Ƃ��̂�����ɂق��ق��u���Ă���B�����玞�v�͋M�d�i����Ȃ��Ȃ����̂��낤�H
��ɐ搶�������ĉ��Âڂ����M�d�i�܂ɘr���v�����Ă��������͂ǂ��ɂ������̂��낤�H
����������v�̋L���Ǝ��̉߂��Ă��܂����t�̓����������ɏd�Ȃ�B
�u���v�v���}���@��v����̃G�b�Z�C
�e��̌����̏�蕨�A�������͕��E�b�P�ʂœ����Ă���B�Q�P���I�̌���Љ�ɂ����āA�����������鎞�v�Ȃ����Ă͐����ł��Ȃ��ł��낤�B
���̎��v�́A���퐶�������Ă���Ύ��R�Ƀ[���}�C��������A���K�ɓ���������B���悭������Ă���N���[���G�l���M�[�Ȏ��v�ƌ����ׂ������m��Ȃ��B�������ꂱ��O�\�ܔN���ɂȂ�ł��낤���B�E�E�E����ł����m�ɍ��ꍏ�Ǝ������ݑ����Ă���B���̗��V���ɂ͎���������̂ł���B
�i���Ǘ����悭�Ȃ�������A��ƊԂ̕i���̍����Ȃ��Ȃ�A�܂���Ɠw�͂Œቿ�i�œ���ł���悤�ɂȂ����̂ɂ́A��X����҂ɂƂ��đ�ς��肪�������Ƃł���B�������ʁA��ƂɂƂ��Ă͍��܂ł̂悤�ɗ������Ȃ��Ȃ�A�꒷��Z�Ƃ����Ƃ��납������Ȃ��B
�����܂łɂ͂��낢��ȋ@�\���t�������v����������o���A���̎�ނ̑����ɂ͖ڂ���������̂�����B�I�����s�b�N���̐��E�I�ȃC�x���g�ɂ����Ă��A���{�̎��v���[�J�[�̖��O��ڂɂ���̂́A���{�̋Z�p����͂萢�E�ō������ł��邱�Ƃ̏؍��ł͂Ȃ����낤���B
�u�l�ԏL�����v�v�����@���H����̃G�b�Z�C
�s���N�S�[���h�̟������g���C�ɓ������B���������H���������Ȃ��B���w�̂���͂��ꂪ�ŐV�^�ŁA���e�ɂ͂��߂Ĕ����Ė�����̂������������B���m����ȃN�H�[�c���嗬�ɂȂ�A��������ĂȂ��Ǝv���Ă����B���̓X�P���g���B�@�B�̓����ƂƂ��ɐl�ԏL���������Č�����B�͂��߂Ď��v�ɍ��ꂽ�B�����ȕ������Əd���́c�c�y���Ĕ����̂������̏ƌ����v�����݂�ς�������B��ς��낤���A������o�債�ĕt�������Ă��������Ǝv�����B�����A���������Ƃɏ����p���Ȃ��B������\�N�̋L�O�ɂ������̎��v��T���Ă����B
�����O�̃f�[�g�̂Ƃ��A�ޏ��͂悭�x�������B���x�����̂��ƂŃP���J�����B��x�������̕����ꎞ�ԋ߂����x���������Ƃ��������B�ɂݕ����Ƃ������ƂɂȂ����̂��������H�����t�́A���̂܂܍��ɑ����Ă���B
�u���Ȃ����C�ɂ������̂Ȃ�A����������Ȃ��Ă������v�ƍȂ͗������Ă��ꂽ�B���݂��̎��v�ɋL�O�̕��������ނ��Ƃɂ����B�Ȃ́A�����s���Ƃɂ��܂����悤���B���́A�����r�ɂ͂߂Ă���B
���N�̉āA�Ȃ��ˑR�̕a�œ��@�����B��p�܂ł̕s���Ȏ��A�����҂����Ȃ��������̏\�Z���ԁA�R�C�c�͐Â��Ɏ������ݑ������B��p�͐������A�ǐ��ƕ�����މ@�ł����B�������N�ڂ��}���A���C�j�𑗂�I�����B
�Ȃ̑މ@�サ�炭�o��������A�����[�Y����ꂽ�B�l�ԏL���ƌ������Ƃ͉��₷���ƌ������Ƃł�����B�C���ɏo�����Ƃɂ����B���߂��A�Ȃ��C�ɂ��Ȃ��玞�v�̋A���҂����B
���C�ɂȂ����Ȃ�����B���ʂ�ɂȂ������v�������ɂ���B���́A�ߋ��������A�����Ė�����Â��ɍ��ݑ�����B���́A�ł��邾�������A�ȂƂ̎��Ԃ��Ƃ��ɉ߂������Ɗ肤�B�R�C�c�Ƃ܂��V�����v���o������ł��������B
�u�v�[���v�N�q����̃G�b�Z�C�@�@�i11-12���̃x�X�g�G�b�Z�C�j
�u���܂����B�v�Ǝv�������͂����x�������B��w���ɂȂ�������̖��q�o�����̐Ԃ��x���g�̎��v�̕����Ղɂ́A���łɐ��������Ă����B
����͎������w�Z�l�N���̂��Ƃ������B
�v�[���ɍs���Ĕ�э��r�[�A��ɘr���v���͂߂Ă������ƂɋC�Â����̂ł���B�������A���v�͉ƂɗV�тɗ��Ă����e�ʂ̖��q�o�����̎��v�Ȃ̂��B���͂ǂ����Ă����o�����̎��v�����Ă݂����āA�������莞�v�������̘r�ɂ͂߂��܂܁A�F�����ƃv�[���ɗ����̂ł���B
���i�͂₳�������q�o������A��Ȏ��v������Ɏ����o����āA���ɂ��Ă��܂����ƒm������A�ǂ�Ȃɓ{�邾�낤���B��╃�ɂ��ǂ�ȂɎ����邾�낤���B
���v���̂�������͓��������Đ��̓��������v�����Ă���A�������B
�u����Ȃɐ����������������A�V�����̂�������������B�v
�u���o�����̎��v�Ȃ́B�Ԉ���ăv�[���ɓ�����������́B�v
���������ɂȂ�Ȃ��猾�������悻�ɁA��������̓A�n�n�Ə��Ȃ���C�����n�߂��B
�u�ꉞ�A�����悤�ɂ�����B�{���͈�x�S���������Ȃ��ƁA�����~�܂����Ⴄ�����m��Ȃ����ǂȁB�v
��T�[�r�X���Ɨ��������Ȃ���������ɂ���������āA�����Ɏ��͉ƂɋA�����B�����āA�������莞�v�����o�����̃n���h�o�b�N�̉��ɒu�����B
���̌�A����тɎӂ�Ȃ���Ǝv���A���ǎ������킵�Ă��܂����B
�E�E�E���q�o�����͂������Ȃ��B
���ł��ĂɂȂ�A�v�[���̉��f�L�����̓�����k���ƁA�₳�����������q�o�����Ǝӂ葹�˂��Ԃ��x���g�̎��v�̂��Ƃ��ق�ꂭ�v���o���̂ł���B
�u�������ЂƂ́A�����B�v�����@��������̃G�b�Z�C
���͂قƂ�Ǖ��������Ȃ��B�Ƃ��������A�v����̂��������Ȃ��B����33�ɂ��Ęr���v�������Ă��Ȃ��B���s�Ȃǂɏo�|���鎞�͖��̐����鎞�v�̒�����ЂƂ��̂��B
���͂ǂ��ɂł����v�����邵�A�g�ѓd�b�ɂ����v���t���Ă���B�ЂƂ��炢���������̂͂킩���Ă��邯��ǁA���͂������������������̂ŁA�ЂƂ����ƁA�����Ɖ��\�N�����p���Ă��܂����낤�B������{���ɗ~�����r���v��������܂ł͔���Ȃ��B�{���͔��������̂��B�������̂��ЂƂB�Ƃ����Ă����̋����ł͉��\��������悤�Ȏ��v�͔����Ȃ�����ǁB�{���ɖ{���Ɉ��p����̂ɁA�܂��C���[�W�ʂ�̕��ɏ����Ȃ��B
���X�r���v������������z�����Ă݂�B�ǂ�ȕ��𒅂悤�B�J�W���A���Ȏ����ƃh���X�A�b�v���������B�ǂ��ǂ����Ă����B�����~�����Ǝv���B�ǂ��ɂł��A��čs�������B���E���̂��������Ŏ������ނ��Ƃ��ł�����A�ƂĂ��y�����ɂ������Ȃ��Ǝv������B�������V���v���ȋ�F�̎��v�������B
���鎞�͋��s�̗������ŐÂ��Ȏ������݁A���鎞�̓p���̃I�[�v���J�t�F�Ŏ��R�Ȏ������ށB�Ȃ��z�����邾���Ŋy�����Ȃ��Ă����B
���܂ő҂������ė����̂�����A�������z�́i���i���B�j�r���v�ɏ����܂ł��ꂩ����C���ɑ҂���ł���B �@
�u�����������f�W�^���̘r���v�v��������̃G�b�Z�C
�u�́[���@����͍������Ă��ꂽ���q���܂ւ̃v���[���g�ł��B�v�ƌ����ēX�����f�W�^���̘r���v���������܂����B�q�������͊��ł����������������킹�Ă��܂����B���͕S�~�ψ�ł������Ă��܂���ˁB
�����Q�T�N���O�̂��Ƃł����D�D�D�B
�o�͏A�E���Ă͂��߂Ẵ{�[�i�X���x������܂����B�����Ă��̂����ʼnƑ��݂�ȂɃv���[���g�����Ă���܂����B�o�͕��e�ɉ����ǂ����Ɗm�F���܂����B�u�f�W�^�����̘r���v�v�̃��N�G�X�g������A�����o�ƈꏏ�Ɏ��v������ɍs���܂����B
���̂���́A�f�W�^���Ńp�b�Ǝ������킩������́A�ŐV�Œ����������̂ł��B�ǂ�����Ă��D�D�D�D�����ł��B���������C�ɓ����đI�f�W�^���́A�R���~�ł����B�o�̃{�[�i�X�͔����̋��z�ɂȂ�܂����B
����ȋ��z�̂��Ƃ͒m��Ȃ����B�s�J�s�J�̘r���v���ƂĂ����₷���āA������������̊��ӂ̋C���������ς��̃v���[���g�Ȃ̂łƂĂ����ł��܂����B�r���v������p�͍ō��̏Ί�ł����B�����ĖS���Ȃ�܂ő�Ɏg���Ă��܂����B�f�W�^�����v�����邽�тɁA���̏Ί�Ǝo�̋C�O�̗ǂ��ƂR���~�̘r���v���v���o���̂ł����B
�u���̂Ƃ��v�ԍ�@��������̃G�b�Z�C
���͂S�N���O�ɂ͂��߂Ď����̘r���v����ɂ����B
���̘r���v�́��b�L�[���E�X�̎肪�����悤�ɂȂ��Ă��邢�����ăV���v���Ȃ��̂������B
���̓����̎��͂܂��A���w�Z2�N���B���̓�����������Ƃ킭�킭���Ă����B�܂����A�܂����A�����1�������炢�Ɋ������邭�炢�҂��ǂ����������B�����Ă��ɘr���v�����炦��u�ԁI
���́A����ۂB���̏u�Ԃ͂����Ƒ�l�ɂȂ��Ă��Y��邱�Ƃ͂Ȃ��ł��낤�B�u���ƂȂɂȂ����E�E�E�E�B�v
�Ǝv�����B���͂��܂����̂Ƃ��߂������ڂ��Ă���B
�Ȃs�v�c�ȃG�l���M�[���B�q���̂Ƃ��́A���ł͊������Ȃ����̃G�l���M�[�B
���ꂩ��4�N�̌��������ꂽ�B
�Ƃ���ŁA���̘r���v�͍����܂��g���Ă���B
�����A���̂Ƃ��̃G�l���M�[�͂��������Ȃ����ǁE�E�E�B
���ꂩ�����ɂ������Ǝv���B
�i���j���́u�v���o�̘r���v�G�b�Z�C��W�v�ɏ����Ă����������G�b�Z�C�̒��쌠�́A�Z�C�R�[�C���X�c�������c������ЂɋA�����܂��B�\�߂������������B