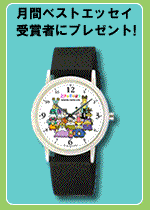2002年の作品
1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9-10月 11-12月
5月 (投稿順)
「銀色の腕時計」播磨 きみ子さんのエッセイ
「左腕に伝わるもの」DiGioさんのエッセイ
「先生に譲った腕時計」加藤 俊寿さんのエッセイ
「父が最後に選んだ時計」 遠田 秋子(とおた あきこ)
「お気に入りのカッコイイ時計を並べて」Mari Tozawaさんのエッセイ
「やさしい左うで。」樽見 祥子さんのエッセイ
「父の時計・祖父の時計」佐藤 希久子さんのエッセイ
「伯母さんの腕時計」原田 明実さんのエッセイ
「誕生日のビックリ箱」浅野 美幸さんのエッセイ
「母の時間」小林 倫博さんのエッセイ 5月のベストエッセイ
「再放送」Oguさんのエッセイ
「進んでる!」大脇 洋太郎さんのエッセイ
「止まらない時計」山崎 友美さんのエッセイ
「化粧箱の中身」福沢 ゆかりさんのエッセイ
「初めての腕時計」菅原 静枝さんのエッセイ
「おばあちゃんへ」永井 博子さんのエッセイ
「君の腕時計」山本 真理さんのエッセイ
「初めての腕時計」古口 美江子さんのエッセイ
「父がくれた時計」山田 史子さんのエッセイ
「腕時計に誓った夜」シンさんのエッセイ
「風水時計」二橋 莉枝さんのエッセイ
「ずっと嫌い」林 ちひろさんのエッセイ
「子どものにおい」しらい けいこさんのエッセイ
「腕時計」岩崎 恵さんのエッセイ
「私と家族を見ている時計」 鈴木 真紀子さんのエッセイ
「腕時計と息子の成長」小木曽 祐子さんのエッセイ 5月のベストエッセイ
「初めての腕時計」山本 裕子さんのエッセイ
「じいちゃん」清水 俊明さんのエッセイ
「過去と今を繋ぐ時間」SHALIMARさんのエッセイ
「片腕のおもいで」りゅうこ むつみさんのエッセイ
「オードリーと時間と私」太田 芝保さんのエッセイ
「もう捨ててしまえ」と夫は言う。
でも私にはどうしても捨てられない腕時計。
プラチナの銀色がタンスの奥深く鈍い光を放ちながら三十数年の時を刻むのも忘れ、じっと寝入っているのだ。
思えばその昔、春もまだ浅い日のこと、彼が大事そうにそっとシルバー色の時計のケースを私に渡して言った。
「指輪よりこっちの方が似合いそうだったから‥‥」
それが婚約指輪ならぬ婚約時計だつた。
きっと彼は指輪を買うのが照れくさかったのだろう。
「時計とは考えたものだ」と可笑しくも感心してしまった。
仲良く時を刻んでいくのには時計の方がいい、と私も思った。
その日から私はこの小さくて落ち着いた光を放つ時計が気に入って、どこへ行くときもお供の小物の筆頭にしていた。
それなのに、ある日時計は動かなくなった。
小さなネジが壊れてしまっているのだそうだ。
何回かの修理の後で完全に修理拒否を受けてしまった。
諦めきれずにいる私のために夫は街中の時計屋さんで修理をしてくれるところを訪ね歩いてくれた。
でも時計はなおらなかった。とうとうこの時計とお別れの日がやってきたのだ。
夫は「又新しいのを買えばいいじゃないか、これは捨てたら」と言った。
私は首を振った。そして時計は動かない銀色の身体をタンスの奥でじっと横たえていつか直る日を待っているのだ。
とある友人は、携帯電話を自分からはかけない。ではなぜ携帯電話を持っているのかというと、たまにかかってくる電話を受けるためと、腕時計の代わり、なのだそうだ。
確かに時間の確認をするだけなら、携帯に付いている時計機能で充分だ。というわけで、友人は腕時計を着けない。
でも、僕にとっての腕時計というのは、時間を確認するためのものというより、左腕のおしゃれなのだ。
僕の左腕を彩っているのは、オメガ・シーマスター。もう六年のつき合いだ。
デザイン、特に純正の金属ベルトのデザインに惚れ込んで購入したのが、使っているうちにもう一つの良さを知った。
着け心地だ。
時計から伝わる適度な重みには、どっしりした安定感がある。ベルトの腕に巻き付くようなかちっとした感触もいい。
以前、オールチタン製の「軽い」ことをウリにした時計を愛用していたことがある。実用には何の不満もない時計だったが、シーマスターの着け心地を知った後に着けたら、ウリであるはずの軽さに、なにか「味気なさ」を感じてしまったのだ。
言い換えれば、シーマスターの持つ重みが、一種の「高級感」を感じさせてくれたわけだ。
「高級感」とは、実用の範囲を超えた何かに感じるものだと思う。それは例えばデザインだったり、素材だったり、もしくはその物の持つ歴史や伝統といったブランドロイヤリティであったり。
僕は「オメガ」という、ブランドそのものにではなく、適度な重みがもたらす着け心地に「高級感」を感じたのだ。
軽量・スリムが流行の今、「重い」ことは欠点となりかねない。しかし、シーマスターはそれを「着け心地の良さ」という美点に変えた。いろいろ不具合も出てきているが、僕はまだまだシーマスターを手放す気はない。
私が高校生の頃、父は勤続20年のお祝いに会社からストップウォッチ機能のついた腕時計をもらってきた。周りにタキメーターの数字と30分の分針がついており、パイロットがはめるような時計であった。父とは以前から、もらったら私にくれる約束をしていたので、すこし大きめであったが私の腕にはまる事になった。
嬉しくて毎日、学校にはめて行っていたのだが、ある先生が私の時計に興味を持ち、テストで見回りに来た時に、机の上においてある腕時計を取り上げ、色々触っては「かっこいいなあ」を繰り返していた。
ある時、その先生から廊下に呼ばれて、「やっぱり、あのデザインの時計は探したんだが、ないんだよなあ。なんとか売ってくれないかな」と言われた。
先生と生徒の間で物の売買は何か不適切なものを感じ、空返事をしていたのだが、結局、何度も言われたこともあり、それ以上断りきれずに譲ることにした。
先生は教室へはその時計をしてこなかったが、休日のクラブ指導の時などは嬉しそうにはめている事を友人から伝え聞いた。
学年末の試験のとき、その先生の担当である数学はどう考えても追試になる点数を取ってしまったが、何故か追試対象者のリストに私の名前は無かった。自分の中ではすこし安心した気持ちと、そんなつもりで譲ったのではないのにといった感情が複雑に交錯していた。
あのときの先生はその後もきっと大事に腕にはめてくれていると思っているが、時々、雑誌などの記事でクロノメータータイプの腕時計を見ると、心の中に埋め忘れた穴のようなものを感じることがある。
私はお風呂に入る時以外は寝る時も時計を掛けている。極度に近眼の私は夜中に目を覚ますと必ず時計を見る。わざわざ目覚し時計を見るのがおっくうだからだ。夜中に時計を見るという点ではカシオのベビーGが最も私に適していた。小さなボタンを押すと明かりが付き暗闇の中でも確実に時間を教えてくれた。何年何月、秒まで的確に教えてくれた。ダイバーの私にとっては完全防水の役に立つ時計だった。しかしその時計は腕の留め金を固定する部位が取れてしまい、使うのを辞めた。初めて
時計を買って貰ったのは私が中学に入学する時だ。メガネと一緒にセイコーの時計を父に買って貰った。当時にしては約三万円と高いモノだと感じた事を覚えている。高校に入ると父の海外のお土産はいつも時計だった。ロンジン、オメガetc・・・私がそれらの時計をして行くと皆が羨望の眼差しで私の腕を見た。私が大人になり海外旅行をするようになった。あちこちの国でSEIKOの看板を目にした。ニューヨークでもタイムズスクェアーのど真ん中に大きなセイコーの看板を目にした時は驚いた。さすがに世界のセイコーだと実感した。アナタの時計はセイコーかと聞かれる事もしばしばあった。今、私がしている時計はブルガリだ。自分で買った時計の中では一番高いシロモノだ。この時計も日付が付いている。時として日にちを忘れる私にはファッションよりも機能性が重視される。そういう意味では両方を兼ね備えたブルガリを今は愛用している。時々アディダスのスポーツ時計もする。これは値段が安いわりには日付も付いて完全防水だ。時計の電池が切れたと言って時計屋さんで電池交換をしてもらうと千円する。千円出せば防水の新しい時計が買える時代になった。時計は私の体の一部だ。父が生前していたのは
セイコーのドルチェだった。そのドルチェは今でも刻々と時を刻んでいる。父が最後に選んだ時計はまさしくセイコーだった。
「お気に入りのカッコイイ時計を並べて」Mari Tozawaさんのエッセイ
結納返しは普段身に付けられるもの。やはり時計かな。彼と一緒に探しにいったのは“一生使えるくらいの良い時計”でした。毎週末に出かけてはいろいろかけて試しました。そこで、彼も私も気に入ってやはりどうしてもその前で立ち止まる時計がありました。今、しっかり彼の腕で輝く時計は、文字盤が黒・時計です。結婚を控えた私たちにはちょっと高価すぎる時計でしたが、これからの人生を一緒に歩んでいくには最高の時計でした。もっとおじさんになったら文字盤を白にすることも出来るらしく、彼もとても気に入っています。彼は私に指輪を、私は彼に時計を、それぞれ結納のために準備しました。指輪の内側と同様に時計の裏側にも文字を入れたい・・・。そんな私たちでしたが、入れたい文字が長すぎてお店ではちょっと・・・ということで、技術者さんに依頼してみると、しっかり文字が刻印できますというお返事で、早速送っていただきました。
返ってきた時計には、しっかりと文字が記され、結納のため水引までしっかりとついた頑丈な箱に入っていました。販売店の方も初めてご覧になったというほどのきっちりとした装いでした。裏に刻んだ出会った日の日付と彼と私の名前は、思い出とともに、今もきっちり時を刻んでいます。
私と彼の思い出と今を知る大切なアイテムです。一緒に止まることの無い、戻らない時を刻み続けます。今年の2月ホワイトデーに彼からもらった赤い文字盤の腕時計。彼が仕事から帰ってくると、隣に並べて微笑んでいます。
昔から父は、子供の事に無頓着で気が利かない。まるで戦時中からタイムスリップしてきたような頑固さで常に恐怖の対象だった。
そんな父が、珍しく私に時計を買ってくれた。だけれども、気の利かない父の事で、幼くて時計を自分で出来ない私が「ねぇ、時計をつけて」とねだると自分の子供が左利きなのにもかかわらず、ご丁寧に左手に巻いてくれるのだ。これが毎回の事で、私にとって時計は「左手につけるのものなのだ」という意識が固定され、習慣として残ってしまった。高校生になって、他人から指摘されて始めて気づいた私のくせ。だけれどもあえて直そうとは思わないで、左手に時計をつけている。
頑固で、気が利かないそんな父に時計をつけてもらった思い出は私の中で事のほか暖かく残り、この少し不便な左腕から優しく滲み出ていくようだ。
30年以上も前の、私の中学入学祝は万年筆、高校の入学祝は腕時計だった。それぞれ父から手渡されたときは、ちょっぴり大人になったような気がしたことを覚えている。
だから息子が高校に入学したときに、腕時計をプレゼントしたかったのだが、彼は要らないという。それは携帯電話で、すべてが用を足せるからだという。
そうか、時代が変わったのだな。手紙を万年筆で書くときのインクのにおいも、メールに代わり、竜頭を回して時間合わせをすることもなくなったのだな。
ところが、今年の大学受験のとき、携帯電話を試験場に持ちいれてはいけないと注意書きに書かれていた。
「時計ない?」
「私のでよかったら貸すよ」
そのとき、彼の父親が、
「これもっていけ」
と古い腕時計を差し出した。息子の祖父の時計だった。
祖父の形見の時計のおかげで、息子は無事志望の大学に合格できた。あの世から時計を通じて応援してくれていたに違いない。
時計ベルトの擦れた跡に合わせ、留め金具をベルト穴に通す。直径5・ほどの“マル”が出来た。その小さな輪が伯母の手首の太さだと知って、ことばを失った。
イエ伯母さんが八十一歳で亡くなり、愛用の腕時計を形見に頂いた。是非とも引き取りたかった。真新しい腕時計を初めてつけた伯母の姿を覚えている。私だけが。
三十数年前の春の一日、小学生だった私は伯母の買い物にお供をした。生涯独身だった伯母は、家庭を持った弟の末の子、私を可愛がってくれた。ちょっとしたお土産や小物を買ったり、時には外食。お供が楽しみだった。
その日、目指したのは、繁華街の片隅にある時計店。店のおじさんが、ショーケースから腕時計を出しては、柔らかい布で一拭きし、並べていく。伯母は一つ一つ値札を確かめる。
「いいなぁ。私も欲しいなぁ」
繊細なデザインの腕時計は、おとなの象徴のようで、どれも子どもの私にはまぶしかった。
やがて伯母が選んだ腕時計は、文字盤に数字のない、ごくシンプルな黒革ベルトのものだった。
伯母が丁寧にリュウズを巻き、私の耳に当てた。秒針が時を刻む音。速く、軽やかに…。
命あるものの息吹のような、その音。
「これはスイス製なの」。伯母は念願の買い物にとても満足したようだった。今思えば、都内に勤めを得た伯母の、決意の印しの買い物だったのだろう。
…その時の腕時計が、主を失い、私の手の中にある。革ベルトは今にも、ちぎれそうだが、当時のままだ。
晩年の張りがなく、皺だらけになった伯母の手を思い出す。命は果てる、という現実。
リュウズを巻く。伯母を真似て丁寧に。
時計が鼓動し始める。命あるもののように、静かに、確かに、時を刻む。刻んでいく。
その時計はデパートのショーウインドゥに飾られていました。一目で、そのやさしい形と美しさに魅了されてしまいました。それは、とても主婦の私が毎月のお金をどうにかして買える額ではありませんでした。でもあんな素適な時計で私の腕を飾ってみたいと、思いは増すばかりでした。
「私パートにでてもいい?」私をここまで動かしたものは、今まで何もありませんでした。少しぐらい嫌なことでも、あの時計のため、寒くても、暑くても、目標があるというのは、働くにも張り合いがありました。家事には一切迷惑はかけないという程のパートですから、目標の額には半年経ってもまだ手が届きませんでした。
そうこうしてる内に、私の誕生日がきました。主人はとてもうれしそうに、箱を一つ私の目の前に差し出しました。開けてみると、そこには欲しかったあの時計が光輝いていました。
「もしも、おまえが買ってなんて言ってたら、買わなかったけど、そうして頑張って働いているのを見ていたら、買ってあげたくなっちゃってね!」私はありがとうも言えずに、ただぼろぼろと涙をこぼすばかりでした。
「母の時間」小林 倫博さんのエッセイ (5月のベストエッセイ)
2年程前の事だったでしょうか。泣き出しそうな声で母から電話がありました。
「あんなあ、お父さんのなあ、時計が止まってしまったがよ。電池をな、換えに来てくれんな。」飛んで行きたい気持ちでしたが、僕はその頼みをうっちゃっておいたのです。
なぜならそれは、父の形見の腕時計だったからです。
父と母はずっと鹿児島で生きてきました。本当に仲のいい夫婦だったと思います。
息子が東京へ就職し、娘も千葉へ嫁いだ後は、さらに支えあって暮らしていました。
まだ若い60歳代の頃は強気なことを言っていましたが、歳を重ねる毎に先のことが不安になってきたのだと思います。
初めは絶対に嫌だと言っていましたが、娘夫婦が大きめの家を建てたのをきっかけに、住み慣れた田舎を捨てて関東に移り住む決心をしたのでした。
失うもの、得られるもの、みんなで話し合った上での「最良の結論」だったのです。
しかし、心身の労が祟ったのか、出発1週間前にして突然、父は他界しました。
母は放心し、全てを移住に積極的だった自分のせいにして閉じこもりました。
結局、母は遺骨を抱いてひとり千葉に来ましたが、外との交わりを絶ち、父が映っているビデオや写真を1日中眺めていました。
旅行に連れ出したり、新しい時計をあげたりもしましたが、変化はありませんでした。
母が変わり始めたのは、ここ数ヶ月のことなのです。彼女の中で何が変わったのかは知る由もありませんが、止まってしまった父の時計は、何故か仏壇から消えていました。
「鉄道員ちゅう映画を観たけどな、耳が遠くてな、筋がわからんじゃった。損した。」こんな元気な電話も来るようにまでなったのです。
もしも母が、残りの人生を自分の時間の中で生きようと考え始めたのだとしたら、、、。
涙が出るほど嬉しい、今日この頃です。
かつて私の好きだった人は、とても時計が好きな人でした。
その人が着替えるようにつける時計はどれもセンスが良く、高そうで、私はいつも新しい時計に気づくたびに見入っていました。
私の質問に嬉しそうに答えるあなたの顔を見たくて、いろいろ聞いたものです。その人の選ぶ時計はその人と同じくらい私も好きになりました。
今、その人とはもう会うこともないのですが、その人がつけていた時計を今でもいくつか覚えています。なので、電車に乗っていて、つり革を持つ手に同じような時計を見つけると、思わず顔を見てしまいます。そして全く見覚えの無い顔に少し安心し、苦笑い。きっと今頃は私の知らない時計をしているに違いないから。それでも流れる景色の向こうにあの頃の気持ちを思い出すことがあります。
時計は時を刻むもの、でもあなたがかつて持っていた同じような時計を見つけるたびに私の時間は巻き戻しされます。
目的地の近くでやる事は時計を少し送らせるのです.そのときの気分で秒単位であったり分単位であったりします.けして大きい数字ではないのです.
相手に会っているときに時報を確認するのです.もちろん時計を遅らせてありますから時報とは合いません。
そこで言う事は、
「進んでいるところは違いますね.時報まで進んでいる.」
日付変更線など日本には無いですから時報が合わないということはおかしいのです.でも言われた方は気分が良いと見えて少し勝ち誇ったようなふるまいをします.遅らせてあるとも知らずにです.
もちろん反対の時もあります.時計を進ませておくのです.
「遅れてる!」
反対の事を言うと笑われます.これは年下の人とか目下の人に言います.現代の時計は遅れたり進んだりが無いので全て自分でやら無ければなりません.正確に時を刻む今でこそ出来る事です.
8年前、祖父が亡くなった。それは不運としかいえない様な事故で、突然の訃報に私たちは皆号泣した。
納骨のとき、祖母からひとつの腕時計を渡された。
「骨壷と一緒に入れて欲しい」その願いに私は少し戸惑った。
祖父の愛用してたその時計は、持ち主を失ってもなお、確実な時を刻んでいたのだ。形見をそばに置きたいという気持ちと、祖父に返してあげなければという思い。そして命あるものを閉じ込めてしまうという後ろめたさ。結局私は、地面に膝まずくようにして、おそるおそる墓の中に手を入れた。
祖父を思い出すたび、墓に手を合わすたび、私の胸にはあの時の腕時計がよみがえる。そしてそれは確かに現在も、チクタクと時を刻んでいる…そんな気がするのだ。
中学の入学祝にと、祖母から腕時計を送られた。腕時計は、利き腕には着けない物らしいのだが、当時の流行歌の影響か、左利きに見られたくて、右腕に着けていた。ある日、うっかり時計をしたままソフトボールの練習にでてしまった。ピッチャー返しになった球を受けようとしたが、運悪く時計の金属バンドに当たり、手首に怪我をした。傷の手当てのために時計をはずしたところ、植え込みの近くに置いたまま帰宅してしまった。翌日探したが、見つからず、途方にくれた。その頃は、まだ時計が貴重品だったので、祖母にも、両親にも言えず、ず〜と秘密にしてきた。嫁ぐ時、整理をしていたら、その腕時計の化粧箱を見つけた。空箱だけど、あの頃の思い出、大人の証の時計をもらった誇らしさ、そして秘密、みんなこの中に詰まっていた。
私が腕時計と出会ったのは、6才の時。
大人たちが時々、ちらりと腕時計を覗くしぐさに目覚めてしまいました。そのしぐさが、大人だけが許される大人の証のように思えたのです。父の大きな腕時計を貸して貰っては、何度となく文字盤を覗くしぐさをしていました。
ある日、どうしても自分専用の腕時計が欲しくなり、ねだった私に、父は、どんな時計がいいかと尋ね、私の腕にボールペンで腕時計の絵を描いてくれました。お風呂に入れば消えてしまう儚い腕時計。わたしの初めての腕時計。嬉しくて嬉しくて消える度に書き直してもらったり、自分で書いては悦に入ってたり。それは世界にたった一つしかない私の腕時計。
今は幼稚園児の腕にもキャラクターのかわいい腕時計があります。豊かな時代になったものです。私も自分で好きな腕時計を買えるようになりました。
金色に輝く腕時計の黒い文字盤を覗く時、ふっと、あのボールペンで描いてもらった腕時計を思い出すことがあります。そして流れた時間の重さを感じます。あれからいくつもの腕時計が私と共に有りましたが、やはり、父が描いてくれた腕時計とあの喜びが、私の腕時計の原点です。
その年、高校の入学祝に贈ってもらったのは腕時計でしたね。「遠慮しないでいいからね。なんでも好きなものを買ってあげるよ。」と言ってくれたのを覚えています。私は幼い頃からねだるということが苦手でした。自分の気持ちをはっきり言うタイプのようで、自己主張ができずについつい我慢してしまうことが多かったように思います。おばあちゃん、あなたに対しても。たくさんいるいとこたちの中で「博子ちゃんはしっかりしているから」と子供のときから言われ続け、このレッテルをはがすのが怖かったんだと思います。いや、大人になった今もこの癖は直りません。
中学校を卒業したばかりの私には贅沢品だった腕時計。「おばあちゃん、私が欲しい時計はちょっと高いんだけど・・・」とバツのわるそうな顔して言うと「みんなには内緒だよ」と言って、押入れからお財布をだしてくれましたね。あれはへそくりだったのでしょうか。
今ではその腕時計もどこかにいってしまいました。でも、おばあちゃん、あのときの「みんなには内緒だよ」という一言は私の中にいつまでも残っています。
白内障の手術後、テレビがよく見えるといって喜んでいたと母から聞きました。若葉のまぶしい季節になりましたよ。こんどは、私が「みんなに内緒」の楽しいことを計画しましょう。
「おじいちゃんの形見」と言っていた腕時計は、金色で丸く。
見た感じだいぶくたびれた様子で。
見るといつも止まっていた。
なんでも、おじいちゃんが生前、片時も離さず愛用していたものらしい。
戦争も知ってる。
腕をゆさゆさと動かし、「巻いて」いる。それが、いつしか癖になっていた君。
腕時計を身に付けていない時でも、無意識に腕をゆさゆさ。
おかしくてふたりで笑った事もあった。
最後に会った時も、やっぱり時計は止まっていた。
−このまま、止まったままで
手を振らないでー
じっと君をみつめたら、やっぱり最後に手を振った。
止まった時間を「今」に合わせて、過去の時間に「さよなら」した。
あれ以来、君をーもちろんあの腕時計もー見ていないけれど。
きっと今ごろどこかで腕をゆさゆさしているだろう、君を
想ったら無性におかしくなって
ひとりで笑った。
高校に入学するとき、初めての腕時計をプレゼントしてもらった。
ガラスケースの中では輝くばかりのエレガントな腕時計が並んでいた。その中で最も気に入ったのは八角形の金色の時計だった。四角でもない円でもないというのが珍しくおもしろかった。普通の女性ものより大きくて、SEIKOの文字もことさら質の高さを感じさせた。紺色の皮バンドとよく映えて、とても素敵だった。左手をちょっと上げて新品の腕時計を見るとき、自分が少し大人の女性に変身したように思えた。
それから一年以上が過ぎ日、通学の途中でその大事な時計をなくしてしまった。すぐにあちこち捜したが見つかるはずはなかった。がっかりしたのは私ばかりではなく、親の方も同じだった。
しばらくして貴重品はもう戻ってくることはないと納得した頃、母は同じ時計を買ってくれた。「今度は気をつけてね。」との一言だけがかえって心にひびいた。この八角形の時計は他のものより値段が高かったから、同じのをまたもらえるとは思っていなかった。
60年代の終わり頃の出来事だったが、毎朝ネジを巻き、私はその腕時計を十数年以上も身につけた。ほとんど正確な時を刻み、今でもネジを巻けば動き出す。母は帰らぬ人となったが、この小さい時計は動き始め思い出を運んでくれる。
初めて時計を使ったのは、小学4年生だった。都内で中学受験の模擬試験を受けるために、父が買ってくれたのだ。日差しが柔らかい日曜日に、広い会場の端の目立たぬ席に座った。あたりを見まわすと、知っている友人は一人もいない。かなり心細い。ふと新品の腕時計を見ると、時計の真中に描かれた赤いスカートの女の子と目が合った。思わず微笑んでしまう。”かわいいね。これから、ずーと一緒だよ。うれしいな。そうだ、名前は何にしようかな”あれこれ名前を考えていると、テスト用紙が静かに配られた。いよいよテストが始まる。大きい針と、小さい針をまじまじ見つめ時刻を確認した。答えににつまるたびに、女の子と会話した。”ねえ、わからないよ。次を解いても良い?”すると、時計の女の子がやさしく微笑んでくれるのが見えて、安心した。気がつくと終了時刻だった。回答は、かなり空いていたが、あまり気にならなかった。なにより、10歳の少女には、テストの結果より、時刻を知ることより、腕時計の女の子と一緒に未知の時間に進んでいくのが愉快だった。その時計をつけていると、不思議にどこに行っても寂しく感じる事がなくなった。今思い出すと、一緒にいたのは、実は父の温かい思い、そう、愛情だったと思う。
久々に銭湯行ったら、脱衣所で、小さな子供がウルトラマンの柄のパジャマを着ているのを見て、少し懐かしい気持ちになった。なぜなら僕も小さな頃ウルトラマンの柄のパジャマを着ていたからだ。8歳の誕生日、母から腕時計を買ってもらい、正義の味方の一人二役を演じたりしていた。腕時計に「こちら地球防衛軍、応答せよ」とか言って、光線銃片手に現場に向かうのだが、あっけなくやられて、死にそうになったその時!用意していたパジャマに着替えてウルトラマンになるのである。
貰った時計はデジタル表示で、それが当時の僕にハイテクな気持ちを味あわせ、ますます地球防衛軍たる役を心酔させてくれたのである。
ウルトラマンの柄のパジャマの子供は僕の6歩程前、父と手をつないで、小さな足をちょこちょこ動かしながら、夜の銭湯の帰り道を歩いていた。
「僕はいつになったら、あの父子のように、自分の子供と銭湯に行けたりするのだろう?」ふとそんな気持ちが沸いてきた。
30歳を目の前に向かえ、未だ結婚もしておらず、来月で4年勤めた会社も辞める予定である。不安で寂しい気持ちになって、とぼとぼ歩いていたら目の前にさっきの父子が立ち止まって、空を見上げていた。つられて僕も空を見上げると、そこには赤い光を点滅させた飛行機が飛んでいた。僕はずっと夜空を見上げていた。飛行機はもう通り過ぎたけど、星がとてもきれいだったからである。ふと手を掲げてつぶやいた。「負けるもんか!」手首が少し光った気がした。街灯に腕時計のガラスが反射したのだろうか?僕は腕時計にこう言った。
「20年前の僕、応答せよ、僕は絶対負けないぞ!」
5年前、私は風水に夢中になった。ある日、金の丸版の腕時計が金運・人間関係の円滑を呼ぶことを知り、それから火がついたように時計店を巡り歩いた。金運を呼ぶには純金製が最も効果的だと風水の本には書かれていたが、それほど高価な時計を買える収入もなく、ましてそんな時計を置いてある時計店すら見つからなかった。結局、金メッキ張りのそれらしき代物を購入し落ち着いた。
純金以上に黄金の輝きを放ち、文字盤には天然ダイヤが散りばめられたロレックス調のこの時計は、通信販売で格安に紹介されていそうな物だった。しかも25歳の腕にはあまりに違和感があり、周りの人はなぜ数多く存在する時計の中でわざわざこの時計を選択したのか不思議がった。だが、2万円弱の時計で若くして富を築け、円満に世の中を渡っていくことが出来たら私の人生バラ色ではないか。そして、いつか来るべき風水効果を静かに待った。絵付けの趣味が実を結んでビジネスになるのだろうか?それとも、どこかの金持ちの男性と恋に落ちるのだろうか?夢は加速して広がって行くいっぽうだ。
だが、効果らしきものはなかなか訪れなかった。風水効果が最も現れると言われる2年目もあっさり過ぎ去り、いつの間にか5年が経っていた。その間、もしもの期待に掛けては多額を宝クジに投資し、パチンコに通い、ウン十万という無駄金を消費した。
結局この時計に教えられたのは、楽して富は築くことはできないことと、ギャンブルからの脱俗精神であった。
変な事ばかり覚えているなあ、とつくづく思う。”苦い”というほどではないけれど、25年経った今でも忘れていないという事は、こだわっているにちがいない。
今はほとんど出番はないが、大切にしている黒いリザード革のベルトのTISSOTがある。文字盤も黒でスクエア型。私が高3の時に、父親が旅行の土産に買ってきてくれたものだ。今見てもなかなかしゃれている。ベルトは2回ほど取り替えたと思う。
これにまつわる変な思い出は、高校の授業で”能”を観に行った時のことだ。校外授業でもあるし、少しおしゃれしようと私はそのTISSOT
をはめて行った。冬服の長袖の中に隠れていたが、担任の女性教師が気付いて「すてきな時計ね」と誉めた。父親の土産とか何とか話していると、クラスメートも数人集まって来て「見せて見せて」が始まった。しばらく言われるままに片腕を突き出していたが、だんだん気恥ずかしいのと、ウンザリして来たのとで、腕を引っ込めた。
その時、「何で見せてくれないの!」というきつい声と共に、私の腕はねじられる様に強く引っ張られた。女子バレー部のF子。日頃から私がうっすらと嫌っていたF子だった。おそらくF子も私を嫌いだったと思う。私はこういうF子の乱暴で無神経な所が。F子は「もう見せたくないから」などという私の素直じゃない所が。
たったこれだけの事。でもその一件以来、私ははっきりとF子が嫌いになった。今も、それがその年頃特有の幼い感情のぶつかり合いだったとは思わない。大人になっても、私はF子のようなタイプの人間が嫌いだからだ。
このTISSOTを見るたび、すぐさまF子を思い出すわけではない。随分長持ちしているなあと、懐かしい甘い気持ちになり、ぼんやりと学生時代を思い出し、次くらいにF子との一件に思い至る。そして、「あぁ、F子はがさつで本当に嫌いだったなぁ」と、今も変わらない”嫌い”の感情を確認し、また楽しむのである。
ちょうど10年前、10歳になった私は初めての腕時計を買ってもらった。その日は真夏の日差しが容赦なく照りつける蒸し暑い日だった。
「少し高いけど、大事にするんだよ。」
母はこう言って、私が長いこと使えるよう頑丈で、10歳の私には少し大人びた腕時計を買ってくれた。
翌日、私は初めての腕時計を持って、とにかく遊びに行きたかった。なにしろ小学5年生で腕時計を持っていなかったのは私だけだったので、友達にも自慢してやりたかったのだ。でも、友の顔を見ると、新しい時計のことなんかどうでもよくなって、すっかり遊びに夢中になった。当時、私たち2人は、大型スーパーマーケットから森にのびる長い坂道を自転車で2人乗りして走るのが大好きだった。一人が周囲に人がいないか確認すると、
「さぁ、レッツゴー!」
ブレーキもきかせないで、大脚ひろげて走るや走る、ビュンビュンビュンビュンキャー・・・・・その時の風を切って走ることの気持ちよさといったら、もう笑顔がこぼれ落ちんばかり。ところが、その日は運が悪かった。森にゴールイン!と思ったら、いきなり自転車がものすごい勢いで横転、2人ともひっくり返ってしまった。その拍子に、私の腕時計のベルトがすり切れてしまった。とっさに
「少し高いけど、大事にするんだよ。」
という母の言葉が、頭の中を過ぎった。友はしばらく黙っていたが、少したつとケラケラクスクス笑い出した。私も、なんだか急におかしくなって、腕時計のことなんかどうでもよくなって、やっぱり友と同じように笑い出した。そのうち2人でお腹をかかえるほど笑いこけた。
あれから10年。友は遠いところに引越し、2人があの森で会うことはもうないだろう。でも、変わっていないこと。それは、私が今もあの日と同じ腕時計をし、あの日と同じ時の刻む音を聞いていること。今でも私の無数の傷のついた腕時計を見ると、この出来事を思い出すのである。
高校時代,私はずいぶんな定期入れを使っていた。
プラスチック製の定期入れで、バリバリ割れていた。私はよく、その割れた部分に指をひっかけては痛がった。
付き合っていた彼は、定期入れにもそれを使っている私にも呆れていて、
「クリスマスには新しい定期入れを買ってあげるよ。」
と言ってくれた。でも私は、
「定期入れじゃなくて、ずっと身につけていられるものがいい。」
とねだった。結局、彼が私に贈ってくれたのは素敵な腕時計だった。腕に巻きつけるのももったいなくて、帰りの電車の中で何度も袋から出したりしまったりした。家に帰ってからも飽きもせずに、ずっと眺めた。授業中には時計ばかり見ているとおこられてしまうので、筆箱の中に入れて、筆箱を開けてみては彼のことを思い出した。
彼とは逢わなくなってからも、私はその腕時計と一緒にいた。前向きに生きようと思って、彼に関するものは処分しようとしたのだけれど、この腕時計だけは無理だった。一日中一緒にいた分、思い入れが強かったのだ。腕時計の針は動き続けるのに、私の気持ちは止まったままだった。
この腕時計と出逢ってから、もうすぐ2年と半年がたつ。時計の針はもう動いてはいない。残念なことに壊れてしまったのだ。それでも私はまだ持ち歩いている。
私の家にはもう三十年以上も時を刻み続けているボンボン時計があります。この時計は、三日に一度位ねじを巻いてあげないといけなくて、私か一つ下の弟がねじを巻いていました。いつも五分遅れていたり時には二十分位遅れていたり正確ではなかったけれど何故か買い換えもせず、いつもみんなの集まる所にあってゆっくりと時間を刻んでいてくれました。小学校・中学校・高校と成長していく私をそして家族をずっと見てきてくれたその時計は私がお嫁に行くときも動いていてくれました。でも、私がお嫁に行ってしまって、母も手の届かない時計になかなかねじが巻けず、「選手交代かな」と言って電磁式の時計を購入しました。新しい時計は間違いのない時間を知らせてくれるようですが、やはりボンボン時計がないと寂しいらしく電磁式時計の横に、ねじ式ボンボン時計を掛け「今日は十分遅れてるねー」などいつも会話のネタになっています。たまの里帰りは、両親の顔とボンボン時計を見て「ホッ」とします。きっとこれからもちょっと遅れた時間を刻みながらゆっくりと優しく見ていてくれる気がします。そんなボンボン時計は、私のそして家族の宝です。
「腕時計と息子の成長」小木曽 祐子さんのエッセイ (5月のベストエッセイ)
「お母さん、公園へ遊びに行ってくるね。五時には帰ってくるから。」
玄関で腕時計を見ながら、台所にいる私に叫ぶ息子は小学校六年生。
私が息子に初めて腕時計を買ってあげたのは、小学校三年生の時だった。遠足の班行動で時計係になったのがきっかけだったが、息子は初めて手にする腕時計を宝物のように大切にしていて、今も変わらず愛用している。
自分で取り外しが楽にできるようにとマジックテ−プで留めるタイプの腕時計だが、時が経つにつれて息子の手首が太くなり、留める位置が微妙にずれていく。それを見るたびに息子の成長を感じるのだった。
子供用の腕時計と言っても、いろいろな機能がついていて、私も時々貸してもらって、重宝している。
「お母さんは腕時計持ってないの?」
と聞かれて、電池交換が面倒で、すっかりしまい込んでいるとも言えず
「持ってないのよ。腕時計って高いからね。」
と答えてしまった私。それ以来、出かけるときには必ず、
「ぼくの腕時計、使っていいよ。」
と貸してくれる息子。
「ありがとう。借りて行くね。」
こうしたやりとりが心地よくて、当分息子の腕時計を貸してもらおうと思っているのだ。
最近は、息子も腕時計を目覚まし時計として使うようになり、生活に欠かせないものになりつつあるようだ。近い将来、朝から腕時計をして出かける日も来ることだろう。そして、その日が、息子にとって二つ目の腕時計デビュ−の日になるに違いない。
「お母さん、大きくなったら、ぼくがお母さんに腕時計を買ってあげるね。」
生意気そうな息子の顔。そんな息子の成長ぶりを私に知らせてくれる腕時計。これからも大切に見守っていきたい。
小学校1年生で時計の読み方を習うと、商店街の時計屋さんに行く度にショーケースに並ぶ腕時計が欲しくてたまらなかった。学校にしていくことはないけれど、放課後遊ぶ時に時計をしている友達が羨ましかった。それでも親に向かって簡単に「買って」なんて言える家の事情でないことは小さいながらに心得ていた。
それでもどうしてもあきらめきれないので、おこづかいをためて自分で買うことにした。可愛いデザインや色はお金を出せばいくらでもあるが、どうにか手が届きそうな子供用が当時の金額で2300円。白い文字版にオレンジの濃淡の四角が12コの数字を囲み、ベルトもオレンジ色というオーソドックスなものだった。今の浪費ぶりからでは誰も想像がつかないくらいにとても堅実な子供だった当時の私は、少ないお年玉を地道にためて1年がかりでその腕時計を買った。自分のおこづかいで買った物はその時計が生まれて初めてだったし、地味目なデザインもかえって大人っぽい感じがして子供心に満足だった。
放課後に外で友達と遊ぶ時、日が落ちて空が暗くなると腕時計に目をやり「もう帰らなくちゃ」というのはとても恰好がいいことだった。大事に使って小学校を卒業する頃までお出かけの時にも塾にいく時にもはめていた。
中学に進学する時に母がお祝いにシルバーメタルの大人らしい時計をプレゼントしてくれた。それでもオレンジの時計は大事にしまっておいた。
ところが従妹が遊びに来た時に、父が「時計はひとつあればいいからそれはあのコにやりなさい」と言った。私にとっては宝物の時計だったけど親に逆らえる性格でもなかったので黙ってあげてしまった。
今まで手許を通り過ぎていった物達は膨大な数で、忘れてしまったものがほとんどの中で、初めて買ったオレンジ色の腕時計は今でも鮮明に記憶に残っている。
「先生、見て見て!」
社会科見学などで時計が必要な時、子どもは決まって僕にこう言い、そして、得意気に周りの子に自分が嵌めてきた腕時計を見せびらかす。その姿を見ていると、自分が初めて腕時計を買ってもらった時のことを思い出す…もうこの世にはいない僕のじいちゃんは、不器用な人だった。
当時は、中学生になると腕時計を買ってもらえる習慣があった。小学校卒業を目前に控えたある日、僕はばあちゃんからこんな話を聞かされた。
「おじいさんが腕時計を買うてあげるって言ってはったよ」
いつもそうだった。無口で頑固なじいちゃんからの言伝は、いつもばあちゃんを通して聞かされていた。
そして、腕時計を買ってもらえる日がやってきた。僕は、じいちゃんと二人で、街で一番大きな百貨店へ行った。
「どれがええ?」
「これ」
僕は、所狭しと陳列されている腕時計の中から、デジタルとアナログの両方がくっついている二万円のものを選んだ。昔人間のじいちゃんとしては、アナログを選んでほしかったようだが、当時はデジタルが出始めた頃で、親戚の兄ちゃん達はみんなデジタル派だった。当然僕もそのブームに乗り遅れまいと買いに行く前からデジタルと決めていたのだが、そのデジタルとアナログが一つの盤面に共存している夢の腕時計を見て、即決してしまった。
しかし、当時の相場の倍の値段の高級な腕時計のため、「傷がついたら大変だ」と思い、それを嵌めてなかなか出かける気にはなれず、毎日家の中で眺めては一人喜んでいた。
結局僕にとっての初めての腕時計は、あまり日の目を見ることなく、その生涯を終え、今は実家の引き出しの奥深くに眠っている。実家へ帰った時、たまにその埃だらけの腕時計を見ることがある。今では恥ずかしくて誰もしそうにないそのデザインが、僕にとってはじいちゃんとの一番の思い出なんだ。
初めて手首に身に付けた物。大半は腕時計だと思います。ネックレスや香水という人もいると思いますが、私は腕時計でした。
改めて思い出すと、私が「自分の」腕時計を持ったのは高校生になったばかりの春。少し大人になった気がしたあの時は、持つ物全てが真新しく感じていました。私の場合はその時にしていた腕時計が、好きだった男の子から貰ったものでした。 中学3年生の時に引っ越してしまった私の大好きな人。その人から贈られた腕時計を身につけ、新しい学び舎に走っていった思い出。あの時の気持ちは鮮明に覚えています。
その時から現在にかけて、私は親友の贈り物には必ず腕時計にしていいます。 大切な仲間と共に、一緒に時間を過ごしたいという思いと共に。それが私の形にした友情の証なのです。
携帯電話を持つようになった昨今、時計をはめている人が少なくなったように思う。
私の友人もそういう人が多く、仕事以外で腕時計をはめる人はあまりいなくなってしまった。私もそうだった。
しかし、私はある日「好きだった人」に腕時計をもらった。彼は時計が好きで何個も持っており、私がそのコレクションを見たいといったのがきっかけだ。
私は時計に興味があったのではなく本当は彼と仲良くなりたかった。だからその話題のひとつにしようと思い、彼の家に行ったのだった。
彼は嬉しそうに時計の話をして、そしてその中のひとつを私にくれた。私の好きな色が青なので、新しいバンドもくれた。
その日から、私は時計をつけるようになった。
彼と会わなくなってからも、その時計は健在だ。服に合わなくとも、その男物の時計をつけている私ははたから見たら滑稽にすら見えるかもしれない。
しかし、時を刻むたび、私は彼のことを思いだし、そして、少しだけ切なくなるのだ。
初めて腕時計をはめたのは高校生の頃。はにかみ屋の少女が選んだのは、華奢だけど凛とした存在感のある時計。憧れていたオードリーヘップバーンのような時計。「オードリー」密かにそう名づけた時計。
大人の女性に近づきたかったあの頃。生まれて初めて働いて得たお金。何か記念になる物を買いたかった。自分だけの大切な宝物を。
どうすれば、もっと大人になれるのだろう?みんな、私のことを子供扱いして。そうだ!「自分だけの時を刻もう」
私はパートナーを探し歩いた。私の時を刻む使命を果たしてもらうのだから、責任感があって、誠実な人がいい。欲を言えば、はかなげな姿の中に凛とした美しさがある方がいいなぁ。そこで、出会ったのがオードリー。
インスピレーションで感じた。私と彼女の相性は100%!
どきどきしながら腕時計をはめた。するっと馴染んだ。まるで、初めから私の手首の一部だったかのように。
私と彼女はいつも一緒にいた。不思議と嫌な授業中も彼女を見るとやる気がでた。落ち込むたびに彼女を見ると自信が湧いた。辛い時は「私にだって、やればできるんだ!今もこうして、時を刻んでいるオードリーは私の一部なんだ。彼女も一生懸命働いている」そう思って、深呼吸する。文字盤にはめ込んであるガラスをそっとなでる。秒針がチッチッチッチ、と動いている。それに少し遅れて、トットットットッ、脈うつ鼓動。生きている自分、動いている時間、肌で感じることができた。私は彼女と共に成長した。
もう、彼女が時を刻むことはない。今は、宝箱の中で眠っている。役目を果たせてホッとしたような笑みを浮かべて。
自分だけの時を刻むことに成功した私は、希望の大学に合格し、趣味に勉強に充実した日々を送っている。今、私の手首の座は空いている。彼女ほどのいい女に出会えそうもないし、もう私は自分だけで時を刻むことができるのだから。
(注)この「思い出の腕時計エッセイ募集」に書いていただいたエッセイの著作権は、セイコーインスツルメンツ株式会社に帰属します。予めご了承下さい。