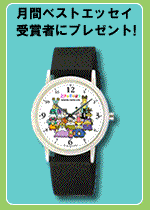2002年の作品
1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9-10月 11-12月
8月 (投稿順)
「蔵の中のつぶやき」はまだ たけしさんのエッセイ
「ずっといっしょ」田中 和枝さんのエッセイ
「分割払いのできる人生」城徳 ひろゆきさんのエッセイ
「ペアウォッチ」山口 いかほさんのエッセイ
「良い買物」山口 和美さんのエッセイ 8月のベストエッセイ
「デジタル嫌い」ジン子さんのエッセイ
「トクトクトク」古川 未沙さんのエッセイ
「アプリコットの花咲く里で」原口 昭一さんのエッセイ
「腕時計の思い出」松橋 昌道さんのエッセイ
「宝石箱の時計たち」村野 京子さんのエッセイ
「腕時計の思い出」高田 圭子さんのエッセイ
「日常の至福、こぼれ話」キャラメルまどんなさんのエッセイ
「僕の青い腕時計」ジャガーさんのエッセイ 8月のベストエッセイ
「日焼けの跡」こにし まおさんのエッセイ
来たよ、来やしたぜ!
カラリンコ、カララン コン、、、
ああいい音だね、長年いっしょの下駄の音、
相変わらず左足をひきずっていやがる、
決して聞き間違えやあしねえよ。
ガラガラ、ピシャ。
とうとう来たんだね。こりゃあたまんねえ、
シャラシャラ、、、
ほらほら、あれは札束をかぞえてる音じゃねえか。
やっとあっしを受けもどしにきてくれたんでやんすねえ。
ガラガラ、ピシャ、
カラリンコ、カララン コン、、、
あれ?引き戸をしめて、暖簾をくぐって、
ああ、とうとう行っちまいやがった。
なんでえ、利息の支払いだけかよ。
まあしようがねえやなあ、
旦那の都合もあることだし、
ちいとは気にかけてくれてるんだから、、、
ここは気長に待たせていただきまっせ。
それにしても、からだがうずうずしてたまんねえ。
あっしは、いつ何時でも休まずたゆまずコツコツやるのが務めだが、
こうも薄暗い部屋に閉じこもっていると、感覚も鈍るというもの、
同じコツコツでもやりがいもないねえ。
それにしてもこの頃始めて気づいたんだけど、
いつもあっしが同じ速さで動いていると
人様はちょっと勘違いなさってるみたいだね。
コッチンコッチンと規則正しく動いているようだが、
それは三次元の話であって、
時空世界では動く速さもちがうってわけで、
何となくご体験なさった方もいるでしょうね。
そうそう子供の時と大人になってからでは、
時間の速さがちがうと感じるあれだよ、
健康な時と病気で寝ているとき、退屈な時と楽しい時、
確かに同じ速さで時が流れているとは思えねえだろう。
そしてこれはあっしの哲学だがね、
人はお金持ちもそうでない方もいらっしゃるが、
この時間だけは、万人共通に与えられるわけで
不幸な境遇だからといってひるむこともあるめえ、
胸をはって生きればいいのさ。
そして充実した時間をどんどんためこんでいけば、
本当の幸せが来るってわけで、あっしを見ながら大あくびして
暮らしていかなくてもいいわけだよ。
あっしの事など、たまに気にかけてくれりゃあいいわけで、
たんと夢中な時を過ごしていただきたいもんだね。
まあうちの旦那も暮らしの為に
とうとうあっしをこんな質屋の蔵へいれちまいやがったが、
なんとか頑張ってほしいもんだね。
長年付き合った仲、いつか旦那の夢中な時間をそばで感じていたいものさ。それだけがあっしの望みでやんすよ。
なあ、旦那よ、あっしの事は、でえじょうぶだから思う存分頑張っておくんなせえ。
え?
おめえは誰かって?
名のるほどのものでもねえが、
横文字で言やあウオッチ、
ご覧って言う意味さ、
携帯用つまり持ち運び便利な腕時計さ。
私の宝物は、亡くなった主人が私の20歳の誕生日に買ってくれた腕時計です。その時計は、あれから30年近くたった今でも、正確な音を刻んでいます。2センチぐらいの四角い文字盤にセイコーと記されてあるだけの、極めてシンプルなものですけれど、休まず働きつづけています。主人が私の腕の中で生きているかのようです。
当時、私は時計を持っていませんでした。家が貧しかったせいでしょうか?昔は、値段の安いファツション時計なんてありませんでした。だから、時計は私には手の届かないものでした。別段、不自由は感じませんでしたので、私は時計をしない生活に慣れていました。
その日、彼は私に細長い小さな袋を差し出すのです。
『これからは、時間に遅れないようにしてください』と言って。
ピンクのリボンを解くと、銀色にキラキラ光る腕時計がでてきました。黒い皮のベルトだったと思います。私にとって生まれて始めての腕時計です。
『高かったでしょう?』
ありがとうの言葉を言うより先に、そう言ってしまいました。
主人は、嬉しそうな私を、ニコニコしながら見ていました。
その後、しばらくしてから私たちは婚約しました。もちろん私の腕には、あの時計が光っていました。それからは、いつもいっしょです。
友人たちは、外国のブランド時計やファツション時計を数多く持っています。しかし私は、思い出のこの時計だけで充分です。デザインはいささか古めかしくなってきましたが、『シンプル イズ ベスト』ですもの。
そして、それは今は亡き主人が私に残してくれた、青春と愛情の証でもあります。
ただ、この頃は、老眼が進んで、文字盤が見えにくくなってしまいましたが、、、、、、、
ドアのノブを開けるのにいつも、両手に持った買い物袋が邪魔をする。
鍵を開けるために買い物袋を土足の床に置くことに、なんだか抵抗がある。
昔は、薄暗い部屋に入ると点滅するする留守番電話が迎えてくれたものだったが、携帯電話のおかげでその活躍の場も消えてしまった。
本当に原色が少ない、空しく寂しい部屋だ、といつも思う。
電機メーカーの作ったン十万するロボットペットを買いたいとは思わないが、世話の要らない頭のいいペットがいればこの寂しさも少しは解消されるだろうにと考えたことがある。
「そんな事だから独身なんだよ。」と昨年、世話のかかる(?)女性を手に入れた友人から忠告された。
私は「芸術が進む道。」と決心して東京の美大に行った。
卒業して4年。
結局、手取り20万円の営業マン。
大学で「技術」は学んだが、自分の作品を見つけることができなかった。
芸術家、音楽家に多くいた不幸な奴の中の一人。
まあ、褒めてほしいのは、優秀な奴らが3年でやる事を、10年、20年かけて行うのもやり方だと自分に言い聞かせて、諦めていないこと。
ショーウインドウにディスプレイされている高級腕時計を一活払いで決済を済ます奴がいれば、一方で多少利子がついても、分割で手に入れる奴もいるという事だ。
いつか、そのときが来れば、高級腕時計も世話の要らないペットとして私の左手にいつまでもいてくれるだろう。
まだ、私にはあの時計は似合わないんだということにして。
両手に持った買物袋から、見きり品の野菜を冷蔵庫に詰め込みながら
私は分割払い人生を満喫している。
あれはまだ彼と付き合い始めの頃、初めてペアウォッチを貰った。値の張るブランド物ではなかったが、入社したての同じ会社に勤める同期の彼には、高い買物だったろう。社内恋愛はタブー、でもそんなリスクを侵してまで贈ってくれたことに、感動してしまった。
もちろん貰った翌日から私は会社に着けていった。彼も着けている。
「ばれないといいな・・・」「・・・ばれてもいいかな」
そんな複雑な気持ちが入り混じっていた。でもそんな大事な時計を私はなくしてしまった。その日は朝寝坊して、朝食もそぞろに支度をし、いつも着けてから出る腕時計を、「あとで」とポケットに入れて家を出たのだ。駅に着き、電車を待つ間、ポケットを探った。「ない、ない、うっそー!」バックにもない、駅構内もない。来た道にもない。しかたなく交番に行き、紛失届を提出した。
「そんなだらしのない女は嫌いだ。」「それじゃあ僕達のペアもおしまいだね。」小心者の私には最悪のリアクションしか想像できなかった。嫌われたくない一心で、こともあろうに同じ時計をデパートで買っていた。「ホンモノが出てくるまでの間だから。」そして毎日会社の行き帰りは下ばかり見て、家では警察からの電話を待った。
でも、やはりホンモノは出てこなかった。そしてニセモノもなぜか腕にしっくりしてきて、なくしたことさえ忘れかけてきた頃、彼と結婚することになった。
今では遠い昔の笑い話。「今でもその位、いやその10分の1でもいいから気を使ってよ。」という彼。「ねえ、あの時正直に言っていたら、何て言ってた?」と聞くと、「また同じの買えばいいじゃん、かな。」ということは、自分で買った分、損したってこと?なにはともあれ、優しい彼が、昔も今も大好きです。
「良い買物」山口 和美さんのエッセイ (8月のベストエッセイ)
夫はずーっとある腕時計が欲しかった。
でもそれは我が家の1ヶ月分のお給料に相当する額もするものだった。
「買っていい?」
「無理だよ。」
夫は毎日カタログを見てはため息をついていた。
私は毎日家計簿を見てはため息をついていた。
「買っていいでしょ?」
「絶対だーめ!0ひとつ取った値段だったらいいよ。」
毎日そんなやりとりのくり返しだった。そして1年が過ぎ、仕事に忙しい日が続いていたある日、
「今から腕時計買うぞ。今、銀座。」
突然の夫からの電話。
「えええー?・・・・・・いいよ。」
あれだけ反対していたのに、なぜだか私はオッケーしてしまった。「見てこれ、いいでしょ。きれいでしょ?」
嬉しくてしょうがないというその顔は、ここ最近の疲れていた表情とは全くかけ離れて輝いていた。
「これから仕事もっと頑張るね。」
子供のようにはしゃいでいる。
なんだかこっちまで嬉しくなった。それから何年か過ぎた今も、毎朝、腕にはめるたびに、
「うーん、いいなあ、引き締まるね。」
仕事から帰ると、
「ご苦労様。」
引き出しの中の専用ベットにそっと入れ、大切にしている。ホンモノを持った嬉しさ、
ずっと欲しかったものを持った嬉しさ、
他人にはわからない自分のアイデンティティー
私にはわかりあぐねていた、そんなものを夫から感じた。本当に良い買物をした。
時計は、昔ながらのアナログ表示が好きである。どこか暖かみがあって、遅刻してもやさしく許してくれそうな顔をしている。
デジタル嫌いなのは、私が学生時代ずっと水泳部だったことに理由の一つがあるかも知れない。岩崎恭子さんが「今まで生きてきたうちで一番うれしい。」と泣いた日も、私はプールで泳いでいた。もちろんオリンピックなどとは無縁の二流のスイマーだったが、0.1秒タイムを縮めるために練習する辛さは、おそらく彼女と大きな違いはなかった。泳いでいる時も、走っている時も、頭の中にはデジタル表示の文字盤があった。春夏秋はプールで、冬はグランドで、いつもタイムに追いかけられていた。あの無機質なデジタル表示の数字を見ると、今でも呼吸が苦しくなる気がする。
高校3年の夏、野球部の男の子とサッカー部の男の子に同時にデートを申し込まれたとき、迷った末、サッカー部の彼とつきあうことにしたのは、彼が時計に左右されるスポーツをしていたからだった。リードされたサッカーの試合で、刻々と時を刻む時計は過酷である。一方、野球は勝負がつくまで何時間でも続けることができる。きっとサッカー部の方が、話が合うのではないかと本気で考えた。そう言えば、野球場にあった時計はアナログ式の大時計で、サッカーグランドはデジタルの電光板だったっけ…。
あれから何年も経って、もう時計に追われるのはイヤだと思っていたのに、会社に遅れそうになりながら、毎朝駅までの道を全力で走っている私がいる。
電車に間に合うだろうかと見る腕時計は、もちろんアナログ式である。秒針が朝の光を反射してキラッと光るとき、私はいつも、あのプールの水面のきらめきを思い出している。
「心臓の音がする」
母が見せてくれた、栗色のベルトの、文字盤にミッキーマウスが描かれた腕時計を耳に当てながら私は小さな目を見開いた。華奢なその腕時計は、まだ小さい私の手の平にも頼りなくて、肌に馴染むベルトの皮の感触はどこか懐かしい空気を纏っていた。
「そうだよ、時計は心臓と同じ音がするんだよ」
まだ幼稚園にも行ってなかった私は、灰色の少しざらざらとしたソファーにうつ伏せになってよく昼寝をした。うつ伏せのまま傍にあるクッションに耳を当てると自分の心臓の音がする。私はそれが大嫌いで、明らかに耳にクッションを当てて横を向いた方が楽なのに、少し苦しいのを我慢してまでクッションを首に当てていた。どくっどくっどくっと、頭の中で響くような心臓の音を聞くたび、どうしてだか解らないけど恐くなる。それは未だに続いていて、中学三年生になった今でも、私は自分の心臓の音が恐くて聞けない。けれどあの時、百貨店のエスカレーターの傍にあった休憩用の椅子に座りながら聞いた、腕時計の心臓の音は、不思議と全然恐くなかった。
トクトクトク。
規則正しく一切乱れることの無いその音は、まるで水みたいな優しさを持っていた。こちらを拒むことなくただ存在するという無条件の包容。そして自分の心臓の音とは違う、生物の生々しさがないところも、私に安心感を与えた。
そういえばあの腕時計は何処へ行ったのだろう。小さい頃、お出かけの時だけ特別につけさせてもらえたあのミッキーマウスの腕時計。最近は携帯電話を持っているおかげで滅多に腕時計をつけない、つけたとしてもゴツゴツとした多機能の安いデジタル時計しか私は持っていない。だけど最近、あの優しい小さな心音を思い出す。少しお金が溜まったら、懐かしい音を聞くために新しい時計を買ってみようかと思う。思い出の欠片を眺めることが多くなった、少し成長した私のために。
たった1ヶ月の命でした。
その日はパキスタンの山奥で突然やってきたのです。朝まで元気に動いていたその時計は、お昼を食べていたほこりっぽい安食堂で静かに息を引き取ったのです。
無理もないことでした。長い旅に出る前日慌てて買った使い捨ての安物だったからです。日本の穏やかな気候の下で使われるべき時計を砂ぼこり舞うパキスタンに連れていった私が悪いのです。
山奥で新しい時計の調達もままならないまま、夕暮れ、浮かない顔して町外れにあるなじみになった食堂で豆料理をとっていました。
「どうした元気ないね」
店で手伝いをしている男の子がたぶんそんな意味合いの言葉をかけてくれました。私は壊れた時計をさして見せ、「ストップしたんだ」と時計の針が止まるジェスチャーをして見せました。その子はそれを見ると同情してくれたのか、揚げギョーザ風のパイを一個持ってきてこれを食べて元気を出せとジェスチャーしてくれます。時計を亡くしてすっかり意気消沈していた私はこの親切が心にしみました。
そこで私はふとした思いつきで、男の子の細い腕に時計をつけてあげたのです。動かないけどおもちゃにして遊んでくれるのならこの時計も浮かばれるだろうと思ったからです。私はその子に君にあげるんだ、プレゼントだよジェスチャーすると、最初きょとんとしていた男の子も事情が飲み込めたのか大喜びしてくれました。こんなに喜んでくれるのならあの時計も本望でしょう。
別れ際、男の子は腰に手を当てると民族衣装をしばっていたひもをほどいてこれを持っていけと言います。同じ「巻くもの」を私にプレゼントしたかったのでしょう。私は君が困るからいいよと言っても頑として受け取ってくれません。私はその使い込まれたひもをありがたく受け取りました。
夏デパートにアプリコットが出回る頃になると、あの男の子のことを思い出します。アプリコットの花咲く山里で出会ったあの少年のことを。
高校時代は郡部から市部の進学校へ汽車通学した。2時間に一本くらいしかない列車を逃すことはできなかった。時計が必要だった。兄姉が大学生だった我が家では、一番お金の要る時期だった。父は約束した。「目標を立てろ、そのハードルを越えたら腕時計を買ってやる」模擬試験、定期試験が頻繁に行われ成績が張り出された。何回もレベルに到達しない状態が続いた後、やっとこハードルを超えた。幸いに「持続する」という条件は無かった。ついに腕時計を手に入れた。図書室でも、教室でも時計を見た。プラチナ色が気持ちよかった。三針式だったがカレンダーもアラームもついていない、ごく普通のものだったが嬉しくてたまらなかった。自分の努力を誉めてくれているようでもあった。本当の大人になったような気がした。帰りの列車は、途中までは、通学生や通勤客でギューギュウ詰めだった。そんな中でも、受験雑誌や、教科書を読んだ。鼻持ちならないやつと、多分、回りの大人達は思ったかも知れない。しかし、母や父親に楽をさせるには、勉学しかない。と素直に思って頑張った。
父の、仕事に対する厳格さと、母親や子供に対するいいかげんさは、親から離れたい気持ちをつのらせた。田舎暮らしにもあきあきしていた。両親の苦労を知りながら、一人暮らしの大学生活を楽しんだ。腕時計も時が過ぎるにつれて数代目になった。私の腕で何時も「時」を刻んでいた。時計をとうして知った「時」は、人生そのものだと感じるようになった。物理的「時」と哲学的、宗教的、「時」が一致するように思えるようになったのも、いい年をしてからだ。私は今、「時を刻む」ことが、何を意味するのかますます考えてしまう。「時」がなかったら、自分は存在しないのかも知れぬと思ってしまう。今春私は母を無くした。頑固な父に仕え、個性ある5人の子供を育てた母と「時」を超えて話ができるようになったと思う。
私の宝石箱の中には、沢山の腕時計が入っている。真珠やダイヤより、数段きらめく中古の腕時計たちだ。
時計の好きな父がくれたものだ。母が急に逝き、肩を落とし小さくなった父。
それから父は、連絡もなしに突然我が家にやってくるようになった。手ぶらでかまわないのに、悪いと思うのだろうか、お金のない
父は、土産代わりに時計を持参する。
定年退職した後、アルバイトを始め、ホテルの温泉風呂の番台に座っている。一番多い忘れ物は時計だそうだ。ホテル側が、落とし
物としてしばらく預かった後、持ち主が現れないと処分する。機械いじりが好きで手先が器用な父は、それを譲り受け、磨き、修理出来るものは自分で直す。
「これはガラスに少し傷があるが、メーカー品だぞ。こっちはベルトさえ替えれば十分使えるから」
まるで我が子のように一個づつ取り上げ、いとおしげに説明する。
「質屋流れで中古だけど、お前にぴったりな時計見つけたぞ」嬉しい悲鳴である。
私は、とても大切な腕時計を二つ持っている。一つは中学入学の時、両親に買ってもらった初めての腕時計。もう一つは母の初七日の日、父がどうしてもと言って買ってくれた盤がベージュの薄くて上品なもの。もう何度もバンドをやり替えたが、今でもバリバリの現役である。
だからもう、これ以上腕時計はいらない。
けれど、父の、時計を見つめる輝くような瞳。子供のように無邪気に喜ぶ姿。そんな父を見たいがため、断れないでいる。
時間の流れと共に、ずいぶん年老いた父。
これから先、少しでも長く父と同じ時を過ごせたらと思っている。
私の宝石箱は、父から命を吹き込まれた腕時計たちで賑やかだ。父の笑顔が刻まれた、お金で買えない高価な時計ばかりである。
忘れもしない2001年7月6日。その日、彼に食事に行こうと誘われてちょっとおめかしして出かけた。レストランのテラスで会話もひとしきり弾みデザートまで堪能したあと、おもむろに彼が取り出したもの。それが腕時計だった。
「Will you marry me?」この言葉とともに彼からもらった腕時計はその時から毎日肌身離さず着けている一番大切なものとなった。
指輪でなく、腕時計。ダイヤモンドも真珠も輝いていないけれど、彼の愛情が一杯見えてちょっぴり涙が頬を伝った。もちろん彼はその後私の夫となり、私の隣で微笑んでいる。
いまは、なんじだろう?
時計を着ける習慣は無かった。
友達の女の子がもっていた色違いの時計を貰うまでは。
彼女が新調してきた時計は、
アンティーク調。アナログ。シンプルな文字盤にワイン・レッドカラー。
彼女の持つ柔らかな雰囲気が、味わいを増して感じられた。
すぐさま冗談でそれをねだった私に、
翌日いきなし、プレゼントがあるよ、と―。アンティーク調。アナログ。シンプルな文字盤に…琥珀色。
それなりに高価そうだったのだが、¥1000程度。
近所のデパートの“掘出し物”で拾ってきたらしい。
すっかりお気に召した私は毎日肌身離さず着け、腕を眺めた。おそろい、とは不思議だ。
彼女との仲も“お気に入り”どうし。キョリが面白い程減っていく。物への好意が人を結んだのだ。こんな至福、忘れたくない。
「僕の青い腕時計」ジャガーさんのエッセイ (8月のベストエッセイ)
僕の通った中学は私立だったから、制服を着て、腕時計をして電車で通学した。父がそのころ流行始めた文字盤が青い自動巻きを買ってくれた。通学の時、腕にはめた青い腕時計と、革のカバンに入った分厚い教科書の重さが誇らしかった。
しかし、僕とその青い時計は一ヶ月の付き合いで終わった。
学校帰りに地元の駅でいかにも不良っぽい少年に呼び止められ、あっという間に5、6人の少年たちに取り囲まれていた。
「ちょっと悪いけど、その時計貸してよ。」
言葉は丁寧だが、その方がよっぽど凄みが出る。
結局、ほとんど抵抗できないまま2,3発殴られて、青い自動巻きの腕時計と、制服の襟に付いている校章をとられて、恐怖と情けなさにとられた時計の文字盤のように青い顔をして帰った。
こんなときは兄に相談するしかない。
「よし、俺が取り返してやる。そいつらのいた場所に案内しろ。」
次の日の帰りに兄と待ち合わせて昨日の場所に行った。昨日の奴らが、駅の前の階段に座っていて、一番強そうな奴の腕に、僕の青い時計が光っていた。兄はつかつかと寄って行って、何事が話していたが、奴らの頭を一つずつ軽くゲンコツで叩くと手ぶらで帰ってきた。
「もうお前には手を出さないと約束させた。喧嘩で負けたんだから、時計はあいつらにやってしまえ。あいつらもきっと、制服着て時計して学校に行きたかったんだろう。明日からお前は俺の時計を使え。」
次の日から、僕は旧式の腕時計をはめて通学しなければならなくなった。
なんとも納得できない結末だったが、この年齢になってようやく兄の言った言葉の意味が分かるようになった気がする。
確か次の年も、水不足だった。
しかし私達はあの日と同じように、炎天下で練習を続けた。
直射日光を目一杯浴びた手首には、くっきりと肌白い腕時計の存在。
それが証明するように、あれから高校で腕時計をつけることはなかった。高校1年生の夏、私は演劇部に所属していた。
演劇部とは言っても、屋内で練習できるのは良くて本番前。
それまではずっと屋外駐車場でしか練習させてもらえない。
そして夏と言えば、どこの部活でも同じ様に「大会」という2文字が私達学生の前に立ちはだかった。演劇に時計は必須である。
大会には細かい時間設定が組み込まれていて、
道具搬入や芝居が1分でも過ぎようものなら即失格なのだ。
だから練習は本番さながらに厳しい条件を課される。練習をする度に疲労する身体と腕時計。
私のつけていた腕時計はダイバー仕様の安い腕時計だった。
故にバンドのゴム素材が、汗や日照りでボロボロになってくる。
毎日その繰り返しだった。ただでさえ「暑い」、そして「熱い」夏なのに…。
それは、時計の寿命すら縮めてしまう恐ろしい水不足だった。水がない。
水がない。
水がない。私の喉も、ダイバーウォッチも、水に焦がれた。
炎天下の中、私は早く練習が終わって欲しいと腕時計を見つめていた。
腕時計もまた、「早くダイバーになりたい」と願っていたに違い無い。夏が終わって、秋。
私は「大会」に負けた。
そしてダイバーになれなかった腕時計も酷使の末…負けた。
いとも簡単に、私の手首からスルリと去っていってしまった。…あれからいくつ時計の針が廻ったかは見当もつかないが、
歳を重ねるごとに腕時計をつけることも多くなった。しかし、あれから数年経った今でも腕時計が残した
「日焼けの跡」は、私達の想いと共に心に焼き付いたままだ。一生消えることのない、くっきりとした跡を残して…。
(注)この「思い出の腕時計エッセイ募集」に書いていただいたエッセイの著作権は、セイコーインスツルメンツ株式会社に帰属します。予めご了承下さい。