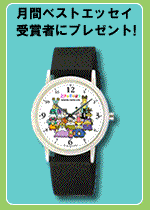2002年の作品
1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9-10月 11-12月
11-12月 (投稿順)
11月度のベストエッセイ審査に当たって、応募作品数が少なかったため、事務局で協議の結果、12月度応募作品と合わせて審査させていただくことにいたしました。よろしくお願いいたします。
「KING QUARTZ」岩崎 輝美さんのエッセイ
「二十歳のバースデープレゼント!」源 義弘さんのエッセイ
「ミッキーマーチ」浜崎 綾子さんのエッセイ
「祖父からの贈物」大内 康啓さんのエッセイ
「腕時計との出会い」岩本 幹治さんのエッセイ
「出逢いの一本」石川 真紀子さんのエッセイ
「はじめての時計は母の思いで」芦野 幸子さんのエッセイ
「四十年をこえて」佐藤 雅彦さんのエッセイ
「祖父の入学祝い」麻生 裕香さんのエッセイ
「Blue Watch」山下 順子さんのエッセイ
「時計」RIKKAさんのエッセイ
「天国の父ぽっぽやの命を刻む時計たち」長橋 富美惠さんのエッセイ
「戻ってきた腕時計」田亮太さんのエッセイ 11-12月のベストエッセイ
「曾おばあちゃんの時間」山田 布美子さんのエッセイ
「母の腕時計」細江 隆一さんのエッセイ
「父の時計」堀江 朋也さんのエッセイ
「思春期を刻んだ時計」中西 有美子さんのエッセイ
「ときの瞬間」内海 修さんのエッセイ
「父の残した腕時計」岡村 真理さんのエッセイ
「母からのプレゼント」橘 五月さんのエッセイ
「祖父の伝えたかったこと」中島 一浩さんのエッセイ
「スイスで買った30万円の時計」つゆ草さんのエッセイ
「白いクマと黄色い腕時計」佐藤 陽子さんのエッセイ
「時を再び・・・」三田村 晴美さんのエッセイ
「はじめての腕時計」臼井 千絵さんのエッセイ
「父から私へ 私から母へ」内山 弘紀さんのエッセイ
「おとな」小倉 かつみさんのエッセイ
「レアもの」安達 俊治さんのエッセイ
「はじめての贈り物」荻野 純子さんのエッセイ
「祝」みーはーママさんのエッセイ
「支度出来たか?早くしろよ、行くぞ!」父の声が飛んで来た。20歳になったばかりの私の誕生日。父がいきなり「お前もやっと大人になったんだから、これからはいいもんを身に付けろ」と言って私を買い物に誘って来た。「どこに行くの?」「いいんだよどこだって。黙って俺に付いて来い!」「・・・って言うかさ・・・どこ行くのよ?」なんてぶつくさ言ってる私を後ろに従え、さっさと表に出た父だった。父はあまり装飾品に拘る人ではなかったが、時計にだけは“拘り”を持っているらしい。取り留めのない話しをながら、父の行きつけの時計店に到着した。そして父が一言。「今日はお前の誕生日だからな。この店にある時計で一番気に入ったのを買ってやる」。「うっそぉ〜」思わず唸ってしまった。ぐるっと店内を一回り。しかし「気に入った物」なんてそう簡単に見つかるはずがない。それから一時間、店内の一箇所がキラキラと光っているのに気がついた。「ここよ!私はここよ!」まるで私を手招きするように、たった一個の時計が私を呼んでいる。ふらふらと呼ばれるままに歩いていくと、そこには見たこともないような美しい時計が私に向か
って笑いかけていた。“SEIKO KING QUARTZ” それも“男物” 金色のしなやかな体を、黒茶色のベルトで飾っている。「美しい・・・」私は一目でその時計と恋に落ちた。その時まるで私の心を盗み読みでもしたかのように、父が一言私に言った。「これでいいんだな!?」思わず父の顔を見つめてしまった。それから20年。未だにあの時の時計は現役で、元気に時を刻んでいる。何度電池を換えたことだろうか?あの時以来この時計を含め、いくつもの時計が私の手首を飾ったが、未だにこの“KING QUARTZ” を超える物に出会っていない。あの日以来私はこの時計に恋をしたまま、一緒に時を過ぎて来ているのだ。そしてこれからもずう〜っとずう〜っと一緒に私の人生を刻んでくれることだろう。
『DOLCE&EXCELINE』と聞いて、私は私の二十歳の誕生日のことを思い出しました・・・。
当時、大学2年生だった私は、勉学?とバイト!に明け暮れていました。そんな私に、いつも田舎の母は「きちんとご飯食べていますか?今しかできないことをしなさいねー」と田舎の野菜と便りを送って来てくれました。
そんな母と父に、ずっと心配や迷惑をかけてた私は、私の二十歳の誕生日に何かお礼をーと考えたのでした。二人ペアで何か記念になるものをと悩んで考えました。夫婦茶碗、お箸、座布団、布団、座椅子・・・いろいろ悩んで考えました。「私を20年育ててくれたお礼だよな・・・20年の歳月を〜時を〜」ということで、思いついたのがペアウオッチでした。
がんばって9月まで働いたバイト代を握りしめ、徳島内の時計専門店を訪ねた私でした。そこで薦められたのがSEIKOの『DOLCE&EXCELINE』でした。学生の私にはびっくりするような高価なものでしたが、私の成長の20年という時を考え、思い切って購入することにしました。私は二つの箱を握りしめ寮に帰って、徳島の名産「鳴門金時芋」と一緒に荷造りをして、私の誕生日の9月29日に届くように発送しました。
そして、運命の29日、母から喜びの電話がかかってきました。父はよそ行きの時だけ使うと言って、仏様に飾ってるとのことー。母も、化粧台の宝石入れに入れてあるとのことでしたー。
あれから、15年。あのペアウオッチはまだ時を刻んでいるのでしょうか?そろそろ、新しい時を刻む大きな柱時計でもプレゼントしようかな〜。大きな振り子で新しい未来の時を刻んでくれるように・・・。
小学生の頃、腕時計は大人がつけるものだと思っていた。でも思いがけなく買ってもらったのは、小学四年生の時だった。
「バスの時刻見るのに、ほしいな。」
普段は簡単にものを買わない母だった。でも私のつぶやきを聞いて買ってくれた。
私が目をとめたのはミッキーの赤い時計。デジタルの子供用のだった。それは、ボタンを押すとミッキーマーチが流れる。しかも三曲あって、ボタンを押す度に交互に鳴る。その頃は時計をする度に鳴らしていた。一人でバスに乗って習い事に行くとき、時計は活躍した。何でもないけど、ミッキーマーチを聞いた。
それから一年くらいたち、腕時計も、ミッキーマーチも珍しくなくなっていた。ただ時刻を知る道具になっていた。
その日はたまたま時計をしていた。友達親子に会い、母親同士が立話しをしていた。私は最近鳴らしていなかったミッキーマーチを鳴らしてみせた。
「音楽が鳴るんだよ。」
一曲目が終わるとまたボタンを押して、二曲目も三曲目も聞かせた。
「綾ちゃん、時計買ってもらって良かったわね。」
いつの間にか、おばさんが覗き込んでいた。
(買ってもらったのはずっと前だよ。最近、鳴らしてなかったし。)
時計をもらって私がはしゃいでいる、とおばさんに思われたのが恥ずかしかった。私は友達へのサービス精神としてやったのに。
でも、一年たっても自慢したかったんだろうな、と今は素直に思うのである。
私の祖父は、今では全く見られないタイプの鼻の下に立派な髭を貯え見るからに明治気質の残る頑固な人だった。
そんな祖父であったが私が初孫でもあり、両親が野良仕事で朝から晩まで働いていることも手伝って祖父には遊園地へ連れていってもらったり当時としては珍しく就学前に読み書きを教えてもらったりした。
そんな祖父が私立の中学へ入学することが決まったとき、バスでの通学は時刻がわからないといろいろ大変だろうといって時計を買ってくれた。時計を左手首に初めて着けた時、何だかちょっぴり大人の仲間入りができたような気がして嬉しい気がしたものだ。
その時計は当時売り言葉となっていた「自動巻」であり、文字盤は蛍光するグリーンであった。
その頃は蛍光する文字盤が嬉しくて手で光を遮って蛍光する具合をよく見たものだ。
クラブ活動で動き回るときも、数学が出来ずに先生にコンパスで頭をたたかれたときもいつも私の左手首には、鏡面だけは酷使された事実を主張するようにいろいろな傷が入り混じっている時計が私の中・高生生活を見続けていた。
そんな祖父はその後長生きして百歳の天寿を全うした。亡くなる頃の祖父は体も痩せ細り昔の威厳を垣間見ることはできなかった。
私も齢を重ねてくると否応なしに種の継続や祖父母、両親からの血のつながりを認識させられるなことがよくある。
そして私も頑固な人間なんだと感じるときは何故か祖父の白くて長い髭を思い出す。
そういう時、時計の一瞬一瞬の文字盤を刻んでいく針が悠久の時の鼓動であることを気付かせてくれる。
「腕時計との出会いの思い出」は人それぞれ違うであろうが、多くの人はいつ、どのようにして腕時計との出会いを果たしたのであろうか。誕生日やお祝い事・クリスマスのプレゼントとして?それとも時間に厳格な親から持たされたため?まだこの他にも様々な出会いがあるだろうが、僕の腕時計との出会いは少し変わっている。初めて腕時計が本当に欲しいと思ったのは小学校低学年の時であった。決して都会とは言えないところで小学校時代を過ごしていた僕は、塾や習い事など全くしていなかったため、普段の生活の中で特に時間など気にすることもなくのんびりと生活していた。当時は遊びに行っても暗くなるまで遊んでいたし、たまに帰るのが遅くなって親から叱られることはあっても、基本的には時間というものをあまり意識せずに過ごしていた。まさに空の顔色が時計そのものであった。ところがある日、いつものように仲の良い友達と遊んでいると、駄菓子屋の軒先にカプセルに入ったおもちゃ、いわゆる『ガチャガチャ』がありその中にガンダムの腕時計が当たりとして入っているのを知った。それが腕時計との初めての出会いであった。それからというものは、その腕時計を何とかして手に入れたいと思い、おこずかいをもらうとすぐにガチャガチャに走った。しかしガンダムの腕時計はなかなか出てはくれず、中にあるのは見えているのに自分の時には出てこないというもどかしい気持ちでいっぱいであった。そして何度目かの挑戦で、ついに念願の腕時計は自分のものになったのである。その日以来、学校とお風呂の時以外は常に腕時計を身につけ、スケジュール表まで作り大人のまねをしていた。事あるごとに訳もなく腕時計を見て「あっ、○時だからこれをしなくちゃ。」と真剣に遊んでいた。今思い返してみると懐かしくもあり、本当に珍しい出会いであった。今でもどこかに、その頃のように楽しい雰囲気になれる腕時計はあるのだろうか。
時計店に勤めていたことがある。
その店の中には、装飾用の輸入時計が壁にかかっており、いくつものガラスケースの中に、細工をこらした時計、遊び心を秘めた時計と腕時計がたくさん用意されていた。
この店に勤めるまでは、時計というのは、単純に、時計を知るためのモノであった。デザインや手につけた感じで、たくさんの中から、自分が選ぶものだと感じていた。
しかし、店員の立場で、一日にたくさん売れていく時計を見ていると、そうでもないことがわかってくる。もちろん、かぎられた時計と出逢う人は、同じ時計に何人もついてくるけれども、冷静にみていると、不思議な糸が時計と、それを買っていく者のなかには、ある気がする。
その店を訪れたお客様の中で、いまも印象に残るお客様がいる。
一人目は、年の頃が、高校生から大学生の少年。
まだ、青年ではない雰囲気をたたえていた彼は、時計をつけない主義といいつつ、時計には詳しい。時計についての説明に、じっと耳を傾けている。なぜか、売りつけるような真似はせず、話をしたくなるような気分になった。
二人目は、小学生の女の子。店に入って来た時から、気品が感じられた女の子。普段は、バレエを習っているのかと思わせるような、シャンとした感じがあった。その店には、どうしても売れないし、これからも売れないだろうという時計があったけれど、そのコを見たときに、どきりとした。時計の持ち主が現れたからだ。そして、そのコが私に言った。
「その赤い時計見せてください。」もちろん、時計との相性はバッチリ。こんな不思議な事がよくおこっていた。
この店に来て、人は一本の時計と出逢います。手の甲の厚さ、手首の太さによって選ばれ、さらに、実際に手に乗せた感じで絞り込まれていく。ひとめで、自分の時計とわかる人もいれば、間に人を介して、知る事もある。人との出逢いと、なんら違いがない。
私が子どもの頃はまだまだ時計はとても高価な物でした。
中学入学お祝いにというのが普通の時代・・あれは私が小学校5年のお誕生日母から手をされた小さな女物の腕時計。
周りはくすんだ金色でベルトだけが鮮やかな真っ赤。
「コレはねおかあさんがおばあちゃんからもらったたった一つの形見なのよ」といって私の誕生日にプレゼントとして形見のお裾分けとして私にくれたのです。
母の大切な物をくれた喜びとはじめての自分の腕時計・・本当にうれしかったしばらくは夜も枕元におき眺めながら眠った物でした。
そして私の中学受験、高校受験にもその時計で挑み合格。
母の思い出と祖母の願いが私を合格させてくれたようにおもい大切にしていました。それから20数年・何度も修理にだし「もう部品が有りません」と言われ動かなくなって仕舞った時計だけど思い出いっぱいそしてファースト腕時計ですもの大切に宝石箱にしまい鎮座しています。
だしては奈崖目様々な思い出をこの腕とけいとともに時に語っています。
四十年以上も前の話である。五年生のとき、初めて腕時計をもらった。といってもそれは、こわれた時計だった。
母方の叔父が交通事故であっけなくこの世を去った。二十台の前半だった。その四十九日の夜の形見分けの席で、叔父の時計が話題になった。事故の衝撃で正常に動かないうえ、血が付いている。誰も欲しがらないのを、叔父によくかわいがってもらっていた私が、訳も分からずもらったのである。血は、母がこっそりふき取ってくれていたらしい。父は苦い顔をしていた。
次の土曜日、私はさっそくその時計をして遊びに出た。一時間に二十分遅れる。四十分ごとに竜頭を巻いて針を進めなければならなかった。
しかし遊んでいるうちにそんなことは忘れてしまった。時計はまだ五時を指していると思った頃、六時を告げる役場のチャイムが鳴った。私はあわてて家に帰ったが、案の定父に叱られた。
「今何時だと思ってるんだ! そんな時計してるからだ。叔父さんに返してしまえ!」
母がとりなしてくれたが、父はがんとして聞かず、翌日、お墓へ返しに行くことになってしまった。
私は泣きながら墓前に腕時計を置いた。そして父に引きずられるようにして、墓地をあとにした。
それから四十年。その父も亡くなり、四十九日がすんだあとで、母は私を呼んで、これ、と言って腕時計を手渡してくれた。あの、叔父の腕時計だった。
母はあのあと、叔父の腕時計をこっそり持ち帰ってくれていたらしい。四十年ぶりに見る、叔父の腕時計。それには叔父と父と母と、幼かった私のいろんな思いが詰まっていた。そしてあいかわらず一時間に二十分、遅れるのである。
「四条のTで買うように」、「上等なものを選んでおやり」。それが祖父から、私の両親へあてたお達しだった。
中学生になる前の春休みのことだ。入学祝いに、祖父から腕時計を買ってもらうことになった。私はそのお達し通り、両親に連れられて、京都の四条通りにあるT時計店へでかけた。
両親が用向きを伝えると、私はお店の人に案内されて、ショーケースの前へ進んだ。遠慮など知らない私は、祖父の「好きなんを選んできたらよろし」との言葉通り、値段など見もせず、一目で気に入ったそれを選んだ。
祖父母の家に立ち寄ると、祖父は私の選んだ時計を見て、満足そうにうなづいていた。 それは当時、セイコーの最新モデルで、エメラルドグリーンの文字盤と、針はプラチナ色の凝った作りになっていた。本体も薄型で、周囲の友達からは、随分と羨ましがられた。
地元の公立中学に進学する私には、中学生になるからといって、特別な気構えはなかった。それでもさすがにその腕時計を手にしたときは、とにかく今までとは違うらしいという、不思議な自覚を感じたものだ。
食べるものも、身につけるものも、祖父は、さりげなく上質のものを選んでいた。好きなものを選べと言いつつ、祖父は時計を買う店とブランドだけは指定した。それはこんな祖父のこだわりだったのだろう。
私は学生時代はもちろん、大学を卒業し、就職してからもしばらくは、この腕時計を使っていた。そして祖父の言うとおり、確かな店で選んだ、確かな品物はこの間、傷むことも、あせることもなかった。
あれから三〇年近くも経とうとしている。今年、師走に入って間もなく、九十四歳の誕生日を一ヶ月後に控え、その祖父が他界した。
先日、弟が腕時計を買った。
セイコー製のクロノグラフ、シルバーバンド。濃いブルーのWatchだった。
重量感のある、ずっと見ていて飽きないほど、よくできたデザインのWatchだった。これ、もうちょっとさ、明るいブルーだったよかったのにねー。と私が言うと、
弟は、
ねーちゃんが買ったわけじゃないんだから、別にいいがね!僕は濃いブルーのこれが気に入ったんだから!文句いうな!!
・・・ん、まあねー、もう少し明るくてもよかったかも。と弟。どっちやねん!?
文字盤には、いろいろ数字が書かれてあって、時計の針とは別に、3つの小さな針がついていた。いろんな機能が入っているらしい。電池の要らない、永久的な品物である。
このタイプのWatchをみると、時々、飛行機のcockpitを思い出す。なぜだか私は、あの空間が好きである。昔、スチュワーデス物語がTVで放映されていたとき、cockpitと制服にあこがれて、パイロット目指そうかと、本気で思ったこともあった。
身に付けている時計のデザインで、その人のセンスや性格を、ちょっと覗い知ることもできる。
cockpitににた、クロノグラフのWatch。それをさりげなく身に付けている人に、
ドキッとしたことが何度かあった。なんでだろ?私も、今度Watchを買うときは、こんなタイプの、真夏の海のような、透き通ったスカイブルーのWatchだと、ずっと前から決めている。
弟に、この時計いくらしたの?と聞いてみた。4万ちょっとだった。
はあ〜?と、ため息が出た。
仕事をがんばった、自分へのご褒美として買ったのだろう。濃いブルーのWatchを、顔を近づけてしばらくじっと眺めていると、
横から、あんまり見るな〜!!とおこられた。とっさに私は、つばつけるぞ〜!食べるぞ〜!と反撃した。
こらー、やめろー!さわったら10万円だよっー!と脅迫してきたので、
私は、そのWatchを見てるだけにして、つばつけるのはやめといた。いま、たくさんの人が、携帯電話を使うようになった。
その中に、時計の機能も入っているから、携帯電話の時計を使う人が多くなり、腕時計人口が、減ってきたようだ。Watchもアクセサリーに近くなった。アクセサリーといえば、
指輪、ネックレス、ピアス、イヤリング、etc、いろいろある。
そのなかでも私は、ネックレスが好きだが、それよりも輪をかけて、Watchが好きである。あの、アナログWatchのカチカチといつまでも動く様子が、
まるで、息をしながら生きているような感じで、
なんだか、かわいいのである。
初めてペアで時計を買ったのは二三歳、十二月八日のこと。クリスマスのプレゼントにと、彼と一緒に買いに行きました。
クリスマス直前の店内にはプレゼントを求めるたくさんのお客がいました。ある人は友人へ、ある人は子供へ、ある人は恋人へ……
プレゼントを選ぶまなざしは、それぞれがみんな真剣でした。私達は三軒のデパートと一軒の時計屋を巡り、セイコー・LUKIAを購入することに決めました。文字盤のとても綺麗な青を見て「これしかない」と思ったのです。それは私達の条件を満たしたシンプルで機能的な時計でした。
お目当ての品を購入した時、混雑していた店内で私達はその場にいる誰よりも自分達が一番幸せだと感じていました。赤と緑でラッピングされた二つの時計を受け取ると、自然と笑顔になりました。
クリスマス当日は雪の降る白馬で過ごしました。スキーを楽しんだあとペンションでくつろぎながらワインで乾杯。外はもちろん銀世界……本物の雪に彩られた素敵なホワイトクリスマスでした。
私達は来年結婚します。
これからは喧嘩もすることになるでしょう。楽しいばかりの毎日ではないし、いつも笑顔でいられるわけではありません。でも一緒に歩いていこうと誓ったことを後悔しないよう、頑張ってみようと思います。
あの時二人で買った時計が今もこれからもずっと同じ時を刻んでいきますように。
「天国の父ぽっぽやの命を刻む時計たち」長橋 富美惠さんのエッセイ
平成11年12月13日諏訪の父が亡くなった。病院勤務の夜勤明けで一睡もしないまま沼津を出たときは未だ危篤状態だった。絶対に間に合うから、とるものもとりあえず車を走らせた。待っててよ待っててよ、今行くから、死んだら承知しないからね!声に出した思いっきり叫んだ。100キロの道が目の前で一本に流れた。脂汗が滲んでついにトイレタイムをとった。コンビニの公衆電話から病院へ電話した。「あ。今お亡くなりに....」山梨と長野の県境を号泣しながら運転をして病院についた。本人の希望で入った馴染みの病室に父はトレーナー姿でエンゼル処置を待っていた。姉が国鉄の制服を用意してくれた。エンゼルやらせて頂きますから、そういって父の着替えをした。長い爪も姉が整えてくれた。弟は淡々としていたが私は張り裂けそうだった。悔しかった。頑固で聴力障害のため無口な父だった。14、5から家を離れ国鉄を定年退職後もSLを愛し続け、アマ写真家になってしまった。孤独な一生だった。父の時計は暫くは諏訪大社の諏訪湖博物館に展示され、父の撮影したSL−D51最後の日の作品が、博物館の方々のホームページ「SLの煙/蘇える煙の里」に載っていた。東京の友人が探して電話をくれたのだ。ところが電話の向こうで大変なことが。偶然とはいえプリント中突然地震が発生、途端に(黒)の色に異変が生じ一転して煤(すす)色。指も染まらんばかりの真っ黒なD51が出てきてるんだよーーーと大騒ぎ。で、黒インクは空っぽになった。やっぱり...あのまま終わる訳ないって思ってたよ。よく似た性格の偏屈な友人を選んでその後も父は現れた。やっぱり、時計だ、そうこなくっちゃ。早速実家に帰り父の愛玩していた時計たちは蘇えった。40年前のセイコーもシチズンも。情けある、時計を心から愛する人たちの手によって。生きている。
「戻ってきた腕時計」田亮太さんのエッセイ (11-12月のベストエッセイ)
「亮太、珍しい人が来ているよ」
母の声に飛び起きた。居間では母が嬉しそうに茶を入れていた。焼香を終えて振り向いた男の顔を見た。
「時計屋の伸ちゃん?」
「懐かしいだろう。伸ちゃん、わざわざ来てくれたんだよ」
かつて、わが家の隣は時計店だった。そこの長男が伸ちゃんである。当時、お隣さんとは、家族ぐるみのおつき合いで、父は仕事が終わると、すぐに隣の庭先で「おい、早くせえや」と無頓着にも声をかける。すると「オーッ、今行くから」と時計屋のおじさんも来る。一杯やりながらの囲碁の勝負が毎日続いていた。
ひとしきり思い出話が終わった頃、柱時計が7時を打った。伸ちゃんは、思わず時計を見上げ、
「ああ、これも親父に買わされたんでしょう」と母に聞いた。
「買わされたなんて、ひょっとしたらこれもいただいてきたんじゃない」
「これもって」
私は、母をのぞき込んだ。すると母は
「お前がしている腕時計ね、きっと伸ちゃんのお父さんと勝負して、勝ったら50年間保障付きで使わせてもらうって約束したものよ」
父の形見だと思っていた。今年で40年にもなる品である。もしも父が拝借したものならば返さなくてはならない。私は丁寧に革のバンドをはずし、伸ちゃんに手渡した。伸ちゃんはしばらく弄くり回していたが
「きっとこれそうだよ」と返してよこした。
「おじさん喜ぶなら、これ持っていってくれよ」と私は彼にもう一度手渡した。
伸ちゃんはその腕時計を家に持ち帰って行った。
数週間後、腕時計が戻ってきた。手紙には、「保障期間が残り十年あります。可能な限り部品を新品にしました。もちろん無料です。私も田さんのところへもうすぐ行くことになります。そうなれば、返品不能ですから御処分ください」とあった。母さんは
「この時計、伸ちゃんとよく相談して使わないとね」
と言ったが、私は伸ちゃんの腕にこれと同じ時計がしっかりとはめてあったことを思い出していた。
曾おばあちゃんがいつのまにか老人ホームへ移っていた。もうあの田舎の家では、曾おばあちゃんに会うことはできないのだ。誰の所為でもなかった。この切なさを、何と言おう。
母と二人で老人ホームへ行くことになった。それとなく避けていたこの日がとうとう来てしまったのだ。会いたいという気持ちには、もはや素直にはなれなかった。ものではない曾おばあちゃんを「見に行く」ようでいい気分がせず、ずっと会いに行く勇気がなかったのだ。居た堪れない感情にもうすぐ自分が支配されることを、私は覚悟しなければならなかった。嬉しいだけにはならない自分が、申し訳なくて悲しい。
曾おばあちゃんは私の覚えていた通りの、ほとんどそのままでいてくれた。ただもうお手製のスカートではなく、緑のジャージに靴はマジックの名前入りだった。私は子供のような格好のおばあちゃんにほとんど何も言えず、ピンクの毛糸で編んできたくまのぬいぐるみを唐突に差し出した。受け取ったおばあちゃんの顔はいかにも女の子らしく綻び、私は内心ほっとした。私は丁寧にぬいぐるみを触るその細い腕に、また一際細い腕時計を発見した。「いいの、してるんでしょ」と大きな声で母が言うと、曾おばあちゃんはじわっと笑って「いっつも時計とにらめっこしてるの」と、金縁が剥げかかった安そうな腕時計を大切そうに眺めて呟いた。
周りにいた人たちなんて気にせず、私も大声で話し掛ければ良かったのだ。帰って来てからそう後悔した。でも時計とにらめっこする毎日ってどんな風だろうなんて考えていると、もう何も言えなかったのだ。ただ時間が過ぎるのを、あの腕時計で何度も確認している姿を思い浮かべるだけで、私は一杯になってしまった。
願わくばあの時計が、たんたんと時を刻みますように。早くもなく遅くもなく、おばあちゃんが思う時を、おばあちゃんに知らせますように。私は少しの魔法を、あの小さな時計に願った。
「腕時計プレゼントしようか」母に何回そう提案したことだろう。そのたびに母は首を横に振る。「まだ動くからいいよ」。母が就職祝いで母親からもらったものらしい。自動ねじ巻きの腕時計。全体が金色のちょっとおしゃれな時計は、子どものころの私のあこがれだった。
「いままでに壊れたことないの」と訊ねれば、「そりゃああるよ。何十年と使ってきた時計だもの」と答える母。
「でもそのたびに修理して修理して使ってきたの。一つのものをここまで大切にするのって、この腕時計だけかもね」
あとになって知ったが、その時計のメーカーはSEIKOだった。このメーカーが一番信頼できるから、と母は言う。
高校入学時に私も腕時計を購入した。母と同じく自動ねじ巻きとはいかなかったが、メーカーはもちろんSEIKO。以来何回か腕時計を買い換えたが、メーカーは変わっていない。
「私はこの腕時計だけでいいよ。正確な時間がわかればそれでいいんだから」
きっと母は死ぬまであの腕時計一つで済ませる気がする。そこまで大切にされた母の腕時計が、いまはなんだかうらやましい。
今は昔。北九州から東京へ大学受験に出発するプラットホームに父が見送りに来てくれた。出発間際、照れくさくて腕時計に目をやろうとしたが、そこには腕時計が無い。忘れてしまったのだ。
父は自分の時計を外して、窓越しにネジを巻きながら「お前にあげるよ」と、ぶっきらぼうに渡してくれた。
それから、受験、就職、結婚、と次々と変化していく生活は、この父の時計と共に、この時計の確実な秒針の刻みと共に生きてきた。この時計を失うあの日までは。
入社して3年後、会社の旅行先の温泉宿の脱衣場で盗難にあってしまったのである。悔しかった。父に申しわけなかった。自分のうっかりさに後悔をした。
その後は安物の時計をしていた。父がくれた時計と同じ物を買おうかとも思ったのだが、「グランドセイコー」という時計は私の給料では一寸高すぎた。
それから間もなく九州へ転勤。筆記具メーカーの営業として文具店さんを担当した。その中に時計店で万年筆も取り扱っているお店があった。そこの店主が「うちを担当した記念に・・」と上手に腕時計を奨められ、つい、月賦でグランドセイコーを買ってしまった。
それから何年も、その時計と仕事をし、生活をし、ネジを巻きながら父を身近に感じ、そしてこの時計で父の死亡時間も確認した。
何回か修理もして使っていたが、世の中はクオーツ、デジタルと変化をし、いつの間にか引き出しに壊れたまま眠ってしまっている。
そして定年を迎えるようになって、非常に懐かしくなり、今、眺めている。あの、北九州を出る時の父を思い出しながら。
そして、この時計の秒針に又、一働きしてもらって、これからの時を大事にしようと思っている。
私が初めて手にした腕時計は、25年前に、中学入学祝いに貰った手巻きの腕時計。銀色に輝くシンプルな腕時計は、ちょっと大人になった気分でした。毎朝、制服を着るのと一緒にねじを回し、時間を合わせて、登校しました。授業中、休み時間、試験の時、いつも時計はわたしに時間を教えてくれました。友達とけんかして、学校に行きたくなかった時もありました。でも、私の時計をはめると自然と学校に足がむきました。勇気を出して初告白。その時は、時計をしている手から、汗が吹き出てきました。合唱コンクールや文化祭、一所懸命な私を時計は見守ってくれました。悩んだり、笑ったり、怒ったり、泣いたり、感受性の高い中学生の私でした。その私の思春期を一緒に過ごした時計は、その当時の日記とともに、今でも思い出の宝石箱に入っています。
「自分の好きなもの選んでもいいの?」
腕時計を初めて持てるときって、ちょっぴり大人の仲間入りができる瞬間だ。37年前、中学校の入学式を十日後にひかえた3月のある日、デパートの時計売り場で、一緒にいた父に、私がそう言ったのだ。
前の日から嬉しくて、ほとんど眠られずに出かけた。それでも価格を見たら3万円くらいのものが並んでいた。その当時、腕時計のベルは、今では主流になっているクサリものが流行しはじめていたように記憶している。
選んだものはゼンマイが自動巻き。価格は2万5千円だった。親から買ってもらった腕時計を腕にはめ望んだ中学校入学式。周りの仲間が持っているものが気になる。クラス編成が決まって、教室の同級生と「腕時計」のデザインなんかで競い合ったことも楽しい記憶だ。
腕時計の本領が発揮できたのは、登校途中の始業時間までの確認や、中間試験と期末試験のときと思っている。起床の時間、始業時間、給食の時間、下校時間……。時間の割り振りを腕時計によって自然に学習し始めた瞬間だ。
巣立って社会にでるようになるころには、職場へ出社する時間も、当たり前だが遅れないように、余裕を持って出勤するようになる。学生のとき以上に腕時計に目をやる頻度が多くなる。腕時計を持っていることがカッコイイという認識か、時間を確認するための必需品へ変わった瞬間だ。
社会にでて、仕事以外に恋愛を体験し始める。好きな人と逢う時間が待ち遠しい。手帳やカレンダーの余白に、デートの待ち合わせ時間をカラーペンで走り書きする……。そんな時間を意識すると、社会的にもホンモノの大人になれた、と確認する瞬間だ。
わたしの腕時計の3時のところにあるカレンダーが刻む数字と時間。4度目のわくわくする瞬間が来る日が楽しみでならない。
父が亡くなって、14回目の冬がきた。この季節を迎えるたび、わたしは父の形見となったこの腕時計をそっと手にかざして見ている。
14年前、旅行先の事故で父は帰らぬ人となった。
緊急手術、しかし98%はダメであろう〜と医師の宣告を聞きながら
父の身に付けていたものを次々とバッグに納めながら、わたしはつぶやいていたことを思い出す。父はいつも腕時計をしない人だった。
「あ、お父さん、時計していたのね」
旅行という特別の行事には、いつもしないことを何故かする人だった。
例えば、時計。そして革靴。この革靴が命取りになったんだ!
いつものように運動靴を履いていけばよかったのに!
だから、階段から落ちたんだ!
わたしは混乱して訳のわからぬ言葉を投げつけ、パニックに陥った。
大好きな父だったから。父が死ぬという事実を受け入れたくなかったのかもしれない。泣き叫ぶわたしの横で静かに父の腕時計はコチコチ〜と
時を刻んでいた。まるでどんな時もこうしてあなたをみつめているよ〜というように。半年後父は静かに天国へ召されていった。
父のこの時計をわたしは今でも大切にもっている。
主をなくしたこの時計はあれからもずっと休むことなく、
コチコチカチカチ〜時を刻み続けているのだ。
不思議な時計。つらい時も悲しい時も、時は残酷。だけど楽しいことしあわせなことも生きているからこそ感じることなのだ。
生きていくこととは、時の流れを知ることだとわたしは思う。
父の残した腕時計はこれからもずっと、わたしの時を刻み続けていくだろう。コチコチカチカチ〜この音を聞きながらわたしは未来を生きてゆこう。
20年以上前母から金一色の時計を貰った。実は弟の初めてのヨーロッパ旅行のお土産だったのだが なにせバンドも文字盤も全て金メッキ。田舎の母では到底使えない派手な(しかしとてもよいセンスの)時計なので弟に内証で横流ししてくれたのだった。早速特別な日や、おしゃれをしたい日などに使うようにしていた。しかしとても使い心地がいいのと、皆から素敵ねと言われてスッカリ気に入りとうとう、ほとんど毎日してるようになった。そして今でも時々取り出しては大切に使っている。ずいぶん丈夫で長持ちしているように聞こえるが実はこれまで本当に何度ももうこれで諦めようかと思うことが何度もあった。その最初が、乗っていたボートが転覆して、時計も水浸しになってしまった時だった。それでも解体修理をしてもらいなんとか動くようになった。次は、ネジが中でどうかなったらしく一杯に巻いても動かなくなった。これも解体して直したのだが日本の部品じゃダメとかで高くついた。そして今度は固定されたバンドの留め金が壊れてしまいどうしようもなくなってしまった。しかしあきらめきれず、いつも親切にしてくれる時計屋さんに持っていくとジーっと見ていて「分かりました。やってみます。」と辛そうに返事をしてくれた。3時間ほどたって店に行くと「かなり難しいから明日になりそうだけど」という。あくる日出来上がった時計は昔のままに治っており留め金がパチンと小気味いい音で腕に収まった。恐る恐る料金を聞くと「これは僕の趣味の範囲で直したからお金要らないよ」と言うではないか。「それはダメです。あんなに時間取ったんですから」と言ったものの内心「幾らならはらえるかなぁ」とハラハラしていた。そんな私の心が見えてしまったのか「分かりました。千円ください。その代わり、この時計大事に使ってくださいよ」と言ってくれたのだ。それからはこの時計を今まで以上に好きになった。勿論、何時の間にか私の時計になってしまったことは弟にばれてしまったがもうそれは時効です。
祖父は特別な言葉も添えずややぶっきらぼうに、私が中学生徒になるといの一番にSEIKOの腕時計を買ってくれた。四十年程前のことである。「デフレ、デフレ」と騒がれている今だが、当時は中学生用でも正式な腕時計は一万円した。祖父は大阪の船場の繊維問屋を営んでいたが、新興諸国の勃興で自分の経営手法も思うようにならず、父に店を譲って引退していた。手元に潤沢な金があったのでは決してない。そういう祖父の事情を子供なりに知っていたから、思いがけなかった腕時計は嬉しかった。何しろ、私から見れば腕時計は高級品であった。父が大切に取り扱っていたのを見ればすぐに分かった。たった一つの腕時計で大人の仲間入りを果たしたような気分になった。
「文武両道」がどこからか吹き込まれた処世訓だったので、サッカー部のクラブ活動が終わると一目散に部室に飛んで帰り、すぐに着替えおじいさんが奮発して買ってくれた腕時計をして自転車に飛び乗り、自宅に帰った。何度も腕の時計を眺めながら・・・。
家に戻ってもお決まりの場所に早速、腕時計を「隠した」。二人の弟が物ほしそうに眺めていたからである。精密製品であるのを熟知していたから、妙に触られて壊したくなかった。そして、その弟達も中学生になった暁には私と同様に腕時計を祖父から貰った。祖父からの腕時計は中学生になった孫への大切なプレゼントだった。
祖父は岐阜の田舎の農家の次男坊。私が小学生の頃、私達兄弟三人を引き連れ生まれ故郷に凱旋したこともあった。小学校を出ただけで彼は大阪に出た。知り合いも全くいない都会。いかに心さびしい時間を過ごしたかは容易に想像出来る。繊維の問屋に丁稚奉公に来たのだ。祖父からの腕時計は、孫達にこれからの人生の荒波を乗り切る覚悟の重大さを伝える意味があったのではと今、思い起こす。当時は全く、思いもよらなかったのだが・・・。
小さな大学の小さな教室でのできごとでした。
大きな大学から偉い教授が講義にやってきました。
西洋政治思想史という選択の授業。
数人の生徒が、週に一度、その教授の講義を受けます。
教授は腕時計を教卓の端に置いて講義をします。
講義がはじまってまだ間もないころ、教授は教卓から時計を落としてしまいました。
教授は小さな教室の小さな教卓に、とても不慣れだったのです。
「この時計は、スイスで30万円で買った時計でね・・・」
多分、30万円だったと思います。
腕時計を落としてしまったこと、とてもショックだったようです。
教授の腕時計はその後も動き続けましたが、今まで遅れることの無かったのに、ほんの少しだけですが遅れるようになったのだそうです。
1年間の講義の中で
「スイスで買った30万円の時計が・・・」
という話を何度も聞いたので、教授はとても気にしていたのだと思います。
教卓が小さいからだと、ときどき愚痴を言いながら、いつも腕にはその時計が光っていました。
私が最初に持った腕時計は、忘れもしないナイロン製のベルトのキャラクターものだった。今考えてみるとなぜだか、その色はあまり自分の好きな色ではなかったのだが、多分キャラクターを優先させれば、色はそれくらいしかなかったのだろう。それでも私はそれが大変気に入っていた。買ってもらった時のことはよく覚えていないのだが、使っていた時期を考えると、多分小学校二年生の時くらいだったのだろうか。祖父が買ってくれた。
私はその頃、いくつかの習い事に、プールに、病院への通院に、と一人でバスに乗ってあちこちに行くことが多く、自分の腕時計を持ったことが誇らしくて嬉しいとか何とか言う以前に、おもちゃのような外見とは裏腹に、それはすでに自分にとってなくてはならない物であった。そしてまたそれは、外出先で出会った人々にとっては見知らぬ女の子との会話の糸口となっていた。一人で病院などに来ている子供の相手をしてやろうと思ったのか、それとも私がいつも後生大事に一緒に抱えてまわっていたぬいぐるみとのコントラストが興味深かったのか、いつも誰かが「かわいいワンちゃんだねぇ。」と言った後に、…いやそして私が「違うよ。クマちゃんなの。」と答えた後に、今度はその腕時計に目をやって「それは本物なの?」と聞いてきたものだった。「本物だよ。」と答えた私は、どちらも事実だから仕方ないのだけれど、我ながらなんとなく可愛くない答えばかりをしたものだと今では思う。
それにしてもいまだにそのやり取りのパターンを覚えているのだから、一度や二度ではなかったと思う。でも、同じことばかりを聞かれ、同じことを答えて、内心(やれやれ。)などと生意気なことを思いながらも、声をかけてくれる大人たちの優しさが私には伝わっていた。そんな思い出があるお陰で私は、しまいには薄黒く汚れてしまった、元は白かったクマと黄色かった腕時計をいまだに捨てることができないのである。
高校入学のお祝いから始まって、いくつか腕時計を持ったその中で、一番華奢でおしゃれで、そして高価だと思われるのが、交際開始間もないクリスマスに夫から贈られた腕時計です。
交際開始間もないのに、高価な時計を贈られたとき、正直言って躊躇しました。「君と二人の時を刻めたら・・・」という、今ではとても夫の言葉とは信じられないようなキザなメッセージと一緒に贈られた時計を手に、困惑の思いの方が強かったことを覚えています。お付き合いをやめましょう・・・ということになったら、この時計は返さなければならないだろうなあ・・・、だったら、今のうちに断っておこうか・・・etc。様々な思いが去来して浮かない顔の私でした。しかし、喜ぶはず・・・と思ったのに浮かない顔をしている私に、少々しょげている夫を前にすると、突き返すこともできず、結局その時計は私のものとなりました。
2年後に結婚し息子を出産、その後夫の仕事の都合で2年間の滞米生活を経験しました。ところが、その間フロリダのスプリングでその時計を水に浸してしまい、時計は止まってしまいました。直すこともできず、すっかり古ぼけてしまったその時計をそれでも大切にしまっておきました。
帰国して二番目の息子も生まれ、4年が経ったとき、私はガンを宣告されました。「時よ止まれ」「時を戻して」何度叫んだことでしょう・・・。辛い時間が過ぎました。
困難をくぐりぬけ、日常生活が戻ってきたとき、夫は「あの時計は?」と尋ねました。時計を手に夫は「直してみよう」といい、お店へ持っていきました。数週間後のクリスマス前、その時計は見事に復活して戻ってきました。今では、16年前と変わらず、華奢で繊細なその腕時計は時を刻み、私たちも幸せな時間を取り戻しています。やさしい針の進みを見ながら、共に刻んできた時の重みを夫の言葉と共に、改めて噛み締めています。
「あっ、重い。」はじめて腕時計をつけた印象を今も覚えている。私が10歳の時だ。その時計は兄のお下がりだった。兄はその当時はやりのデジタル時計を親にせがんで買ってもらい、大きくて、ぶ厚いガラスで覆われたその時計が私にまわってきたのだ。どう見ても女の子には不似合いな無骨な時計ではあったが文句はいえなかった。
それではあんまりだろう、というので母は私をつれて時計屋へ行き、ベルトだけ新品と取り替えることになった。あれこれ時計屋さんがみせてくれる中に、水色の地に赤い花が刺繍されたチロリアンテープのはりつけてあるベルトがあった。今思えば無骨な時計に全く不釣合いなとりあわせではあったが、私はそのベルトがとても気に入ってもうお下がりであることなど気にならなくなっていた。時計屋さんがベルトを取り替えてくれると、早速その場でつけてみた。・・・その時計は本当に重たかった。でもその重みがまたなんとも心地よかった。
その重たい時計をつけるのは、わたしにとっては特別のことだった。普段は大事に机の中にしまい、おでかけや旅行に行くときにだけつけるものだった。
あれから25年。いまや時計は小さく、軽くなり、100円ショップでも買える時代になった。10歳の娘もこの間くじ引きで時計を当ててきた。自分専用の時計がもらえて嬉しかったようだが、今は机に無造作におかれたままだ。ちょっと寂しい気がする。
そうだ、今度実家に帰ったら、あの時計を探してみよう。そして娘につけてやろう。「ね、腕時計って重たいでしょ。」
高校に進学したとき、それまでほとんど話しかける事がなかった無口な父が、「おめでとう」と声をかけた。手渡された小箱を開けてみると、腕時計が入っていた。丸型の国産品で、針だけが金色をしていた。本体はクロームメッキで、同色の、伸縮式のバンドがついていた。指先をバンドにくぐらせれば、瞬時に手首にはまり込むし、手を洗うときなどは反対の動作であっという間に取り外しが出来る。スタイルや正確さよりも、まずは滅法使いやすいところが気に入った。
この時計が、私が最初に手にいれた自分の腕時計だ。高校時代の3年間は、これを愛用し続けていた。その後は、ストップウオッチ付、ダイバー用などを皮切りに、国産、輸入品などを次々に買い替え、最初の時計は机の奥にしまいこまれたままとなった。
父は30年前に他界した。母はその後独りで生活していたが、90を過ぎるとさすがに足腰が弱くなり、介護施設に入所した。そしてある日私に不便を訴えた。施設に壁時計はあるのだが、やはり身につけている腕時計で、常に時間を確認したいと言う。腕時計はいくつも持っているが、ベルトやバックルが、不自由な片手では操作できないらしい。
「ゴムバンドみたいなものに付け替えてくれないかねえ」
私はすぐさま最初の腕時計を思い出した。探し出して母に提供すると
「これはいい。片手で扱えるし、文字盤も大きくてはっきり見える。これ高かったんだろうね」と大喜びだ。ネジが手巻きだが、指先は動くので問題ないという。
その半年後に母はなくなり、肌身離さなかった腕時計は棺の中にいれられた。父から私へ、私から母へと渡った腕時計。きっと今ごろは天国の父もこの腕時計との再会にびっくりしているだろう。
時刻を確かめたいから、時計を見る。バスはあと何分で来るのか。それに乗ったら何分ごろ駅に着くのか。急げば会社に間に合うのか。それとも遅刻してしまうのか。時計の針を頭の中でぐるぐると動かす。わずかなゆとりがあることを計算ではじき出し、ようやく落ち着くのである。
気がつくと、時計が必要になっていた。小学生の頃はどの電車に乗ろうと、目的地に着けさえすればよかった。学生の頃は次の電車に乗ることになっても、さほど苦にはならなかった。ところが、今となっては時計を忘れただけで一日が過ごしにくい。
まだ、小学校低学年だったと記憶している。時計がほしくなった。歳の離れた姉がいるせいか、大人の持ち物によく憧れた。同じものを持つことで、姉との距離を縮められるような気がしていたのだ。私は両親に時計をねだった。もちろん、必要ないと断られた。今思えば、それは当然である。歩いて五分の小学校へ行くのに、時刻表を見ることはない。歩きながら時計を気にし、「今日はいつもより三分早く着いてしまいそうだ。もうすこしゆっくり歩こう」などと、歩く速度の微調整をはかる小学生なんているわけがない。放課後、公園で遊ぶのに「三時十五分ブランコの前で」なんて約束をしたりしないし、向かう途中に時計に目をやり「時間があるからジュースでも飲んでいくか」なんてことをつぶやく児童はいない。時間に追われることのない一日なのである。それなのに、時計を買ってほしいとはなにごとか。両親はそう言ってあきれた。
それでも私は食い下がった。当時利用していた図書館は、バスで三十分ほどかかる駅前にあった。それを口実に、時計の必要性を訴えたのだ。両親は私のしつこさにいらだち、しまいには面倒くさくなったようで、とうとう時計屋へ私を連れて行った。
時計屋にはさまざまな形の時計があり、どれもが違う時を刻んでいた。目をまわしそうになりながら掛け時計の秒針を目で追っていると、店員が両親に声をかけてきた。両親は私に合う時計がないかと尋ねた。店員はにっこり笑って、時計をひとつ持ってきた。
それは白い時計だった。文字盤に数字はなく、かわりに編み下げの女の子のイラストが入っていた。とても軽い。「かわいいでしょう」と言いながら店員が私の腕をとり、その時計をつけてくれた。私はしばらく腕をながめ、頷いた。
両親が会計を済ませている。嬉しくてとびはねたいくらいだったけれども、じっとしていた。時計をつけるようになったら、もうそんなふうにはしゃいだりはしないのだ。なんて、変に大人ぶって。
時は過ぎ、高校を卒業した十八歳の春。私は映画館の階段の踊り場で立ち止まり、時計をつけてはしゃいでいた。大好きになった人から手渡され、舞い上がっていたのだ。
さらに十年が経った今。あのとき時計を贈ってくれた彼が、当時のペアウォッチをつけていたので驚いた。この十年、互いに違う時計をするようになっていたのに。
「うわぁ、なつかしいねぇ」
くたくたになった二代目のベルトをさすりながら、彼は照れくさそうに笑った。
「これがいちばん、つけていても邪魔にならないんだよね」
変わらない時計を見つめながら、私たちはしばらくのあいだ思い出話に熱中していた。
復員の時、時計を二つ持って帰った父。
時計はスイス製というだけで非常に高価な時代でした。
敗戦で頼るものが何もなかった当時、父はボルネオで終戦を迎えました。その時計は、いざという時に備えて生き抜くためのよりどころとして手に入れ、持って帰ったものでした。
その一つは、帰国後結婚してすぐに生まれた私の服に変わりました。小さな写真の中で、真っ白であることがモノクロでも良く分る、上下おそろいのベビー服。機嫌良さそうに顔をくしゃくしゃにして笑っている私。丸くて黒っぽい顔だけに、余計に服の白さが引き立っていました。私の、人生最初の写真です。
もう一つは、長い間父の腕に巻きついて本来の役割で使われました。巻かれる腕が私に代わったのは、それから十五年後、高校入学のことです。
「スイス製の時計だ。エニカという。」
「知らないな」
手巻きで、いつも時間を合わせていなければならない、日付の表示も防水もない、それでもスイス製というだけで価値がありました。結構喜んで友達に見せびらかしていたことを思い出します。
大事に使っていましたが、三十歳をすぎた頃、ついに役目を全うして、たんすの引き出しに入りっぱなしになりました。
引越しを繰り返しているうちになくしてしまった父の思い出。物心ついた頃から54歳の今まで、私と父以外に身につけているのを見たことがない「エニカ」。
年金をもらえる寸前、64歳11ヶ月で鬼籍に入った父をしのぶ。
今年十三回忌。
ミドルエイジになってから、私はボーイフレンドを得た。ふとした出会いだったけど、お互い、テレパシーを感じたのか、話があった。彼は無口で、私がおおかた喋っていたのだけれど、お酒を前に、アハハと笑いながら、他愛のない話なのに楽しかった。
私は北国、飯豊山麓の小玉川という風光明媚な過疎に住んでいた。彼はあたたかな千葉、館山で生活していた。ごくたまの電話と手紙の行き来で1年が過ぎた。
ふとした気まぐれで、館山を訪れることになった。海の幸、海辺の宿、そして、新幹線の切符までいただいてしまった私は途方に暮れてしまった。帰路立ち寄ったデパートの時計店。ふと目を引いたのが、黒い皮バンドのシルバーの腕時計。上品で品格があった。躊躇なく買い求め送り先の宛名を書いた。
びっくりするほど彼は喜んだ。机上に飾った時計の写真を送ってくれた。まもなくして、時計は毎日見るものだから、やたらな人に送ってはいけないという人がいた。ああ、そうなのか、、、気づかなかった私。彼は其のことを知っていたのかな?
死んだ祖父は、孫が高校入学のとき、お祝いとして腕時計をプレゼントするのを楽しみにしていた。孫は全部で10人。その中で二番目に時計をもらうことになった私は、合格発表の数日後、祖父のなじみの時計店へと連れて行かれた。あらかじめチラシでチェックしていたお気に入りの時計をショウウインドゥに見つけ、「これ。」と即決。貧しい年金暮らしであるはずの祖父は、金額に目をやることもなく、店主に頷いて見せた。「お名前、お入れしますよ。」大人になったような気がしたものだ。
高校入学後、はじめてできた彼氏との出会いと別れ、大学合格、今の主人との出会い、就職、結婚、そして二人の娘の誕生と、この時計の刻む時間とともに、いろんな時間を過ごしてきた。
思えば、祖父は時間に人一倍正確な人だった。「早く行って損することは絶対に無い。」と、母が子供の頃から運動会の場所取りも常に1番だったという。そんな祖父らしいプレゼント。残念ながら孫10人全員に時計がプレゼントされることはなく祖父は他界してしまったが、時計の裏の旧姓の刻印のまま、祖父の時計は今も私のもとで生きている。
(注)この「思い出の腕時計エッセイ募集」に書いていただいたエッセイの著作権は、セイコーインスツルメンツ株式会社に帰属します。予めご了承下さい。