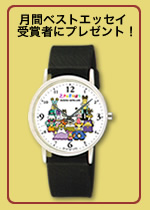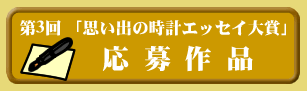 応募期間 2003年1月10日〜2003年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
2003年の作品
1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
![]() 1-2月の作品(8作品)
1-2月の作品(8作品)
1月度のベストエッセイ審査に当たって、応募作品数が少なかったため、事務局で協議の結果、2月度応募作品と合わせて審査させていただくことにいたしました。よろしくお願いいたします。
「壊れた目覚まし」赤目のうさぎさんのエッセイ
「法律」ごぼうさんのエッセイ
「斎藤材木店」畠山 恵美さんのエッセイ (1-2月のベストエッセイ)
「感動と自己嫌悪の時計」のちょさんのエッセイ
「6時にごはん」サンセット娘。さんのエッセイ
「懐中時計」YTマンさんのエッセイ
「決意の時計」馬上 千恵さんのエッセイ
「右腕の腕時計」ひろこさんのエッセイ
朝、目覚ましと共に起きる。それは、誰もが送る日常だ。
かく言う私も同じ。いや、むしろ3つもの目覚ましと共に毎日起きているという点では、誰よりもひどい日常なのかもしれない。
が、ある時、それは破られた。いや、自分自身で破ってしまった。
自分で、目覚まし時計を壊したのである。
まだ、10歳の時だった。
私にとってそれは、おそらく初めて自分専用に持った目覚まし時計だった。ミルクポットのような優しい曲線を描き、エメラルドグリーン(当時、それは流行りの色だった)の色を持ち、そして、セットした時間になると、『埴生の宿』を奏でる。子供心にシンプルで小洒落た様が「大人っぽく」、そんな目覚まし時計に大満足だった。
が、それを自分の手で壊してしまった。何が理由だったのだろう、つまらないであろう理由で、イライラしていた私は、その初めての、大人の一歩であるはずの目覚まし時計を壁に投げつけ、壊してしまったのだ。秒針がはずれ、エメラルドグリーンのそのなめらかな曲線は、鋭くえぐられてしまった。我に返って、それを見つめたのだが、もちろん、元には戻らない。「大人の一歩」を自分で壊してしまった。自慢の目覚ましが、自慢ではなくなった。
何故そのようになってしまったか、母は聞かない。私も言えないでいる。ただ、かろうじて動き続けるそれは、夜、寝る前に、セットしたくない代物へと、変化したのだ。できるなら、母に起こしてもらいたい。せっかくの大人への一歩を自分で手放してしまった。『自分一人で起きる』という大人の一歩まで・・・。
それから、いくつかの目覚まし時計にお世話になっている。
ただ、何を買ったらいいのか、いつも時計屋で音を鳴らしては止め、鳴らしては止め・・・。いつか、あの時計を見つけた時、私は迷わず購入するのかもしれない。一歩めを踏み直すために。
今から三十年前、私は全寮制の高校に入学した。今となってはすべてが懐かしいが、十五歳で初めて親元を離れた少年にとって、寮生活は辛かった。夕暮れになるとグランドのはずれの丘に登って、家のある方をながめて涙をこぼした。
舎監や先輩は一様に厳しくて恐かった。長く付き合うと人間味のある人もいたが、入学したての一年坊主にとっては、みんなが鬼に見えた。
その舎監たちがいる舎監室には、大きな時計が掛かっていて、寮生の生活はすべてがこの時計によって動かされていた。朝六時の起床から始まり、点呼、体操、朝食、授業・・・と私たちは常に駆け足で行動しなくてはならない。点呼や集合の時間に遅れると「外禁」(外出禁止・外泊禁止)というペナルティーが課せられ、月一回の自宅への外泊を楽しみに暮らしている私たちのような新入生にとっては何より辛いことになる。
新入生は要領が悪く、最初の一週間で軒並み「外禁者」として掲示板に名前が貼り出されていった。私は外禁にだけはなるまいと、小便も我慢して走りまわっていた。
ところが、ある日ついに夕食の集合に遅れてしまったのである。正確には遅れてはいなかった。私の買ってもらったばかりの腕時計では、まだ少し余裕があったのだ。新品の時計である。遅れたり進んだりするはずがない。私は必死の抗議に行った。舎監室の時計が間違っているのではないか。たった一分の遅刻で罰則にするのは非道ではないか・・・。
しかし、鬼の舎監は言った。
「ここでは舎監室の時計が法律だ。たとえ一分でも遅刻は遅刻だ。それが許されるなら、二分ならどうする。二十分ならどうするんだ。甘えるな!」
あれから三十年。あの日私は、社会で生きていくうえで大切なルールを一つ学ばせてもらったのである。
「斎藤材木店」畠山 恵美さんのエッセイ (1-2月のベストエッセイ)
通学路に、斎藤材木店があった。
朝、家を出るのが、七時四〇分ちょうど。斎藤材木店の前を通るのは、いつも『きっかり』七時四十三分だった。
曇りガラスだけど上部だけ少し透明の引き戸から見えるネジ巻きの時計。広く構えた事務所の真ん中の大きな柱にかけられた時計を見る。「今日も、ぴったりだ」と思って、私は、歩を進める。
帰りは、大抵三時五分を示していた。時計もわかりやすいが、私も授業が終わると真っすぐ帰ってくるわかりやすい子供だった。加算すると、家には三時八分に着くことになる。だが、家の時計は、どれもバラバラだった。当時はデジタル時計もないし、腕時計だって貴重品だったし・・・。私は、斎藤材木店の時間を信じることにしていた。
斎藤材木店の時計は、社長、私にとっては、近所の物静かなおじいさんが、ネジを巻いているとのことだった。毎朝八時に、どんなことがあっても毎朝八時に、ネジを巻くとのことだった。学校に着いている私には、絶対に見られない、すれ違いの習慣だった。
『斎藤材木店』が、つぶれた。理由は、小学生にはわからない。店も家も取り壊すのだよと、近所中が言っていた。それでも、しばらくは、時計は常に同じ時間を刻んでいたから、実感もなかった。
その朝も、やっぱり『七時四十三分』を見ながら、学校に行った。帰り。もう斎藤材木店は、こなごなになっていた。残骸の山の中、ちょうど柱があったところに、あのネジ巻き時計が置かれていた。時間は『七時五十九分』だった。おじいさんは、今日、ネジを巻かなかったのだと思った。そして、悲しくなって、その時計を持って帰ろうと思った。助けたいと思った。でも、工事の人に怒られた。
翌朝、もう、時計はなかった。もう私の『七時四十三分』もなかった。
倒産するとね、昔だから、夜逃げしたんだよ。でもね、おじいさんは、材木店が消えてしまうまで、そこに居たのだよ。朝八時ちょっきりに時計のネジを巻いていたのだよ。
壊されて「逝く」材木店を、おじいさんは、全部見ていたって、だいぶ後から聞いた。そして、おじいさんは、それからそんなにしないで、亡くなった、っても。
ーおじいさんのおもいが、痛い。
私の部屋のたんすの上にある自転車の形をした時計を見ると、感動と自己嫌悪とが同時にこみ上げてくる。
私は遅刻魔だ。だいたい約束の時間に五〜十分遅れてしまうことが多い。なぜだかよく分からないけれど。そんな私が大学二年生の時、サークルの新人研修指導員という大役を務めることになった。理由は簡単。
家が一番近かったからだ。私のいたサークルでは、一年生は最初の三ヶ月間、上級生とは別メニューの練習をすることになっていた。何人かの上級生がその指導にあたる。二年生の遅刻魔の私は、四年生の先輩方に混じって、指導員という大役を果たすことになった。
練習の最初のうちは、自分も「先輩として頑張らなくちゃ」という思いもあったのか、遅刻しないでいた。しかし慣れてくると、時間ぎりぎりにすべり込むようになって、そして遅刻するようになった。新人研修合宿の時のことだ。集合時間に遅れた私は、なんとか走ってバスに飛び乗るという、先輩としてはとても恥ずかしい失態を犯してしまった。こんな私だったが、一年生がサークルになじんでもらえるように、練習を工夫したり、相談に乗ったり、必死で頑張った。
研修期間が終わった時、研修生だった一年生が私に時計をプレゼントしてくれた。自転車の形をした目覚まし時計で、裏蓋には「研修生一同」という文字が入っていた。よく見るとその時計は時刻を十分進ませてあった。それに気がついた時、柄にもなく涙が止まらなかった。
普通は、こんな時計をもらったら、その後遅刻しなくなるのだろうけれど、私の遅刻癖は今だに直らない。「10分進めてあるから〜」と考えている自分がいる。
だから時計を見る時、私は感動と自己嫌悪とが同時にこみ上げてくるのだ。
「おじーちゃーん!!!」山道を30分ほど登り、一面の梅畑が見えたらもうすぐおじいちゃんの家、私は走りながら大きな声で祖父を呼ぶ。縁側で、私たちが来るのを待っていて、「おーい!!」と梅畑越しに返してくれるのが嬉しくて、私は息を切らしながら梅の香りいっぱいの道を駆け上るのだ。玄関が見える頃には、祖父も嬉しさを隠しつつ、庭いじりをしている姿がいつも見えた。
山深い徳島にあって、祖父母の家も山の中腹にあった。昭和をそのまま残したような家で、蒔でお風呂をたき、泉の水をくみ上げごはんを炊く。夕ごはんはいつも6時だ。「ボーンボーンボーン・・・」唯一居間にある掛け時計が6時を知らせると、それまでおもちゃで遊んでいた私も急いで食卓に滑り込んで正座する。時計が鳴り終わるまでに席につかないと「遅い!!」と祖父に叱られるので、この時ばかりはボンボン時計を頼りにしていた。
「あの時計が6つ鳴ったら、ごはんやで。おもちゃ、お片づけしてちゃんと来るんやで」まだ、時計を見て時間がわからない私に、祖父はそういって教えてくれた。多分保育園くらいの幼い頃なのに「6つ鳴ったら、ごはんのとこいかな」と思っていた自分を、今でも思い出す。「ボーンボーン」という音が、私にとって初めての時間の感覚だった。そして、家族みんなの楽しい夕ごはんのはじまりだった。
毎時毎時成り続ける時計も、私にとっては6つ鳴る時だけが大切なものだった。それから数十年経ち、ボンボン時計は私の父母の家に引越しをした。おじいちゃんとおばあちゃんの写真とボンボン時計、今でも6時になるとみんなで食卓を囲む我が家には、祖父母と囲んだ楽しい夕ごはんが今でも続いている。
父、いつの間にか70歳。見た目は50歳後半くらいに見えるのだが・・・やはり70歳。父はいつも懐中時計を持っている。外見は黒光りをしてシックであるが中のガラスはひびが入っており、よく時間が狂う。しかし、いつも持っている。
父の出身地?いや生まれた国は中米のメキシコである。祖父母はメキシコで果樹園を経営していたと聞く。太平洋戦争が激しくなり9歳のとき日本に引き上げてきた。父は日本人ながら日本語は片言だったらしい。9歳といえば3年生であるが2年生のクラスに入ったと聞く。あいさつやひらがなの読み書きは知っていたが日常生活に必要な会話や単語については、分からなかったそうだ。父がまず覚えなければならなかったことが時刻の尋ね方、答え方だそうだ。日本人というのは時間をとても重んじる国である。始業時間,集合時間,給食時間・・・。分刻み、いや秒刻みで動いている。そんなとき、父親が懐中時計を使って教えてくれたらしい。実は私もその懐中時計で時計の読み方を勉強した。もうすぐ100年たとうとしている父の懐中時計。おんぼろで、役に立たない時計であるが思い出のいっぱい詰まった時計。懐中時計、もうすぐ100歳。見た目は黒光りをしてなかなかかっこいい。もうすぐ私が持つことであろう。
ずっと辞めよう、辞めようと思っていた仕事を「続けよう」に変えてくれたのは、いつも愚痴を聞いてくれていた友人の言葉だった。
その日も、いかに自分の職場がやる気がないか、新しいことをはじめようとしても協力してくれないか、をその友人に訴えていた。じっと静かに聞いていた友人が口を開いた。
「いつも辞めたいといっている人の言葉なんて、誰も聞かないでしょ」。
そのとおりだ、と思った。ストン、と何かが落ちて、今までお腹の中にあった愚痴が消えていくのが分かった。
続けよう。とりあえず与えられた場所でベストを尽くそう。そう決心した直後、私が向かったのは、町の時計店だった。この気持ちを忘れないよう、物に残したかった。何の迷いもなく、いつも身に付けることができる腕時計にしようと思った。
じーっとショーケースの中を眺める。男性用で金属製、青い文字盤の時計が目についた。店員さんに出してもらい試しにはめると、心地いい重さが腕にかかる。これにしよう。しかし値札を見ると、なんと給料の3ヶ月分。ちょっと自分には不相応。でも欲しい・・。いろいろ考え迷ったが、買うことにした。なんといっても「決意の時計」なのだから、高くても気に入ったものにしたほうがいいと思ったのだ。
あれから4年。私は同じ仕事を続けている。やっぱりつらいことはあるし、違う環境に惹かれることもある。しかし、その度に腕にすっかり馴染んだはずの時計の重さを感じるのだ。できることをしっかりやろう。気持ちが少し引き締まって仕事に戻ることができる。
これからも決意の時計は私を励ましてくれるだろう。そして、いつか本当にこの時計にふさわしい人間になりたい。
私が最初に身につけた腕時計は、中学生になった春に両親から贈られたものだった。それは銀色のステンレス製のベルトにきれいなオレンジ色の分厚い文字盤をしたもので、その重量感が急に大人になったような気がしてうれしかった。両親が何も教えてくれなかったのか、右利きの私は腕時計は左にするものだということをまったく知らずに何の気はなしに右腕にしたのがきっかけで、今も時計は右腕である。何かを書いたり道具を使ったりする際に、右利きの腕にはめている時計はよくあちこちにぶつかって傷だらけになるのだが、腕時計は右にするものだと身体が思い込んでしまっているところがあり、不便を承知で続けている。
ところで、文字盤がオレンジ色の最初の腕時計はその後、学校で図工の時間に筆を洗っていてうっかり濡らしてしまい、あっけなく故障してしまった。左手にはめていれば濡れずにすんだかもしれなかった。当時防水機能のついた時計はほとんどなく、普段から水には気をつけていたのだが、うっかり濡らしてしまったのだった。それは、重量感のある腕時計をはめているのも忘れるほど、中学校生活にも腕時計にも慣れてきた証だったのかもしれない。
(注)「思い出の時計エッセイ募集」に送っていただいたエッセイの著作権は、セイコーインスツルメンツ株式会社に帰属します。
予めご了承下さい。