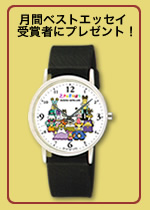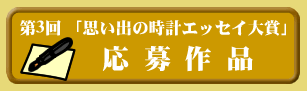 応募期間 2003年1月10日〜2003年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
2003年の作品
1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
![]() 10月の作品(28作品)
10月の作品(28作品)
「人を感じさせる時計」見上 万里子さんのエッセイ
「ゆめのきんどけい」岡崎 佑哉さんのエッセイ
「今、何時?」綾乃 なつみさんのエッセイ
「彼からもらった腕時計」なつさんのエッセイ
「ネジ巻き時計あれこれ」芝田 千鶴子さんのエッセイ
「似たもの同士だったのね」戸田 由美子さんのエッセイ
「シュール的に記憶された柱時計」青木 久美子さんのエッセイ
「私のワールドウオッチ」渡辺 均さんのエッセイ
「彼の時計 私の時間」かづよさんのエッセイ
「遅らせた時計」SUMIKOさんのエッセイ
「時計は万国共通語」白石 美津乃さんのエッセイ
「初めてのプレゼント」金子 雅人さんのエッセイ (10月のベストエッセイ)
「私の相棒。父が貸してくれた腕時計」境野 洋統さんのエッセイ
「実家の古時計」宮本 洋さんのエッセイ
「夢の時計」伊藤 都さんのエッセイ
「時計腕」野田 展子さんのエッセイ
「目覚まし時計」霜葉 紅さんのエッセイ
「頭が良い鳩さん」薮野 愛美さんのエッセイ
「丈夫な腕時計」木村 次男さんのエッセイ
「時間のない楽園」原田 由樹さんのエッセイ
「かあちゃんの時計」福山 裕教さんのエッセイ (10月のベストエッセイ)
「時計についてと称しまして」もちだ もちこさんのエッセイ
「リセット-生まれ変わる時-」すなぎさんのエッセイ
「父がくれた腕時計」北井 正毅さんのエッセイ
「少女時代」神野 絵理子さんのエッセイ
「私と時計、数々の想い出」阪谷 恭好さんのエッセイ
「紅く四角い目覚まし時計」小野 勝也さんのエッセイ
「猪の父と優美な時計」遠藤 聡子さんのエッセイ
男物の黒皮にシルバーの腕時計。セーターの上からリストバンドのように止めたスタイルがお気に入りだった。
男に負けないように、肩肘はってがんばって仕事をしていた頃。
会社の組合主催の飲み会で、いつにも増してビールを煽っていた。酔ってくると大きな腕時計が邪魔になってテーブルの上に置いた。
宴もタケナワになってくると、席の移動で座が乱れてきた。
お手洗いに行って帰ってくると、私が前に座っていたテーブルは別の課の男性陣に代わっていた。軽いノリの彼らを敬遠して別に移動しようと思ったが、時計を置いたままだ。
気が進まなかった席に着くと、隣の男性が声をかけてきた。私がスキューバダイビングを初めたばかりと噂を聞いたらしい。
「スキンダイビングを小さい時からやっている」と話かけてきた。スポーツが出来るようには見えなったので意外だった。魚の写真を撮っている話で盛り上がり「今度ぜひ一緒に」と誘われてその日は終わった。
次の日の朝、楽しかったけど、あれはナンパ?と考えながら腕時計をして驚いた。いつもの時計より重い。私の時計ではない。飲み会の席で間違えて持ってきたのだろう。返さなくてはと思い、時計の持ち主の手がかりを探そうとじっくりと見た。本当は私の時計とは色が同じだけで、クラシックで重厚な時計だった。酔っ払って見間違えたらしい。そして、隣の席に座った彼の物だと気がついた。彼も腕時計を外す癖があるらしい。彼の時計が彼はまじめでイイヤツだと語っているようだった。
「どうしたんだ」パパはゼミの仲間に会うたびごとにそう聞かれたそうです。今も会えば「あの頃、どうかしていたよな」と笑われるらしい。
パパは大学二年生だった当時、朝から晩まで銀座の画廊をぶらつき、それに飽きるとぷいと電車に乗ってあてどもない旅をして、平凡な田舎の風景に涙していた。――確かに今のパパを見ていると、これは笑ってしまいます。
左利きのパパの右腕には、見たこともないような古めかしい時計がはまっていました。螺鈿の文字盤を持った、いかにも貴族らしい金無垢の腕時計を、パパは銀座の薄暗い骨董屋で、免許を取って初めて買ったポルシェ911と引き換えに手にしたのです。
流行や女を追いかけることなど、些細なことに思えた。食べたいものを食べ、愛せる何かに出会うために生きる。出張も転勤もない学生なのに、パパはあの日々、一生の中で最も多くのものを見ていたのだそうです。
終わりは突然でした。眠りこけた大教室での授業、目覚めると時計は奇麗に消えていた。三日三晩、ほうぼうを探し、じっと目を閉じた。パパはその足で伸び放題の髪を切り、就職活動のためにスーツをクリーニング屋に出しました。
歯を食いしばり、こまねずみのように駆け回る平凡な東京の社会人として、パパはすみやかにバブル経済の激流に飛び込み、せわしくて下品で貧しい今の時代まで一時も休まなかったのです。だから結婚して、ママも僕もいるんです。
時計と共にいた日々、パパは殆ど人付き合いも絶っていたから、この時計を腕に付けて撮影した写真一枚ない。薄れゆく螺鈿の模様と古金の鈍い煌きの記憶の中で、パパは時々、早稲田の学舎に忍び込んだ泥棒氏もまた長きにわたり幽閉されたであろう、蟲惑の日々を思い出すのだそうです。
「二時半…えッ!?…あ〜ッ、止まってた〜」高校の部活帰り夕焼け空の下、海に近い江ノ電の駅。「今、何時?」と私に時間を尋ねた友は、「え〜ッ!?、ネジ式ィ〜!?」と叫んだ。腕時計のネジをせっせと巻く私。この代物は、十歳の誕生日に父が買ってくれた、私の最初の腕時計。我ながら物持ちが良い、と思いつつ毎日ネジを巻いていた。或る日、高校の廊下の壁に「初代」は誤って激突、ヒビ入りでちょっと見づらくなったが、使っていた。
次の誕生日、電池式の、アナログとデジタルが同時に見えるハイブリッド時計が、「二代目」としてやってきた。私はこの腕時計を愛用した。これが左手首にいないと落ち着かず、共に高校も大学も卒業して、就職しても使っていた。この頃になると、服装によってオシャレ時計をすることもあったが、それは借りてきた猫状態。本命は「二代目」だった。
しかし、「二代目」の寿命は思ったより短かった。電池を交換しようと時計屋さんに渡すと、「これは古いねぇ。電池もう無いかもねぇ。」……私は「三代目」を探した。まだ「二代目」の息のある内にと、探した。ハイブリッドのデザインが見つからなかった。アナログとデジタル、其々異なった時間も設定でき、海外に行けば、異国と祖国の時間を同時に確認することも出来た。何より、狂いが殆ど無かった「二代目」。私は探した。結局、代わりはいなかった。しばらくして、私は腕時計をしなくなった。
腕に時計がいなくなった。思った時に時間が判らず、時計を探す。時計の無い場所では、携帯電話を時計代わりにする。「今、何時?」人に聞くことが増えたかもしれない。
最近入院したが、手術で全身麻酔が効いている間、まるで時が飛んでしまった様だった。退院後に母曰く、「手術室から戻ってきて貴女、一番最初に“今、何時?”って言ったのよ。」……腕時計をしている母に、飛んでしまった時を確かめたかったのかもしれない。
このコンテストで「時計」とゆう文字を見た時、一番に思い出したのが、半年前まで付き合ってた彼氏のことだった。
時計屋の息子として生まれてきた彼は、時計が大好きで、デート中も時計の話しになると、夢中になって話してきた。
私もその影響で、もともと好きだった時計が、尚更好きになり、逢うたびにお互い、今日はどんな腕時計をしてるかとか見せ合うようになってた。
そんなある日、お店の調子が悪いとゆうことで、他のお店に働くようになった。
就職活動をしていても、受ける会社に、「自分のうちが時計屋なのに、他の店にくるなんて!」といくつも落ちていたけど、いつも前向きな考え方で、なんとか縁があった会社に就職するのが決まった。
しかし、喜んでいた反面、県外に出なければならないとゆうものだった。
遠くにいってしまう、出発のとき。
私にくれたものは、ずっと欲しがってた腕時計だった。
セイコーのちょっとレトロっぽいもの。
少し大きめだったけど、彼が使ってたものだと思うと気にならなかった。
その腕時計をしてたら、いっしょに時を刻んでるって感じがして、心が温まった。
半年に1度しか会えない生活。
ほんとに辛かった。
次第に、必要以上に束縛してる自分がいて、結果、振られるとゆう最悪なことになってしまった・・。
今でも、その時計を見ると彼の事を思い出す。
もう二度とすることのない時計だけど、彼のことは大好きだったから、すごく懐かしい気分になる。
すごく前向きな考え方をもってて、どんな人に対して優しい人だったから、彼に知り合えてよかった、って今でもすごく思う。
落ち込んでいるときでも、その時計を見ると、こんなとき、彼なら何て言うだろうって自分を励ましてる。
いつかもっといい人ができるまで見守っててね☆
今の若い人には、時計のネジを巻くということは想像しにくい行為に違いない。現在の時計はほとんどが電池で動いており、忘れた頃に電池を入れ替えればいいようになっている。しかし、私の子どもの頃は違っていた。腕時計にしろ、柱時計にしろ、ネジを巻き忘れると止まってしまうのだ。それは、時計が生きているような不思議な感覚でもあった。
昨日、小津安二郎の映画を見ていたら、「あんた、時計のネジを巻かないと、止まっちゃうわよ。」と言われた旦那が、踏み台を持ってきてそれに乗り、柱時計のネジを巻シーンがあった。ああ、そんなこともあったなあと、妙に懐かしくなった。
柱時計と同じように腕時計も、今は時刻あわせをするだけのポッチの部分を引き出してくるくるとネジを巻くのが普通だった。
手で回さなくても腕につけているだけで自動でネジが巻かれていくタイプの腕時計が発売されたのはいつの頃だったのか。 わりと新しい物好きの父親はさっそくその時計を購入していた。薄型のしかし文字盤は大きめのその時計は、振るといかにも中でゼンマイがぐるんと回るような音がした。私たち姉妹が争って時計を振りたがるのを、「振りすぎてもいけないかもしれない。」と取り上げて大事そうにしまっていた父親が思い出される。
その頃の我が家では、高校に合格したらお祝いに腕時計を買ってもらえることになっていた。私が高校受験の時、時計がなくては試験が受けられまいということになり、父親の時計を借りていく事になった。落としたりなくしたりしても悪いからと辞退したが、「いいから、気にしないで頑張って来い。」と言われ、時計を借りて受験に出発した。試験会場で自分には大きすぎる腕時計を机の上に置いて眺めていると、姉に比べてあまり出来のよくない私への父親なりのエールだったのだということに気づいた。
試験が始まるまでの間、そっと時計を振ってみるとぐるるんとゼンマイの音がした。父親が応援しているような、時計が励ましてくれているような余韻があった。
数年後、父は他界したが、今でも茶色い皮の時計は記憶に残っている。
もう十数年も前、私がまだ高校生だった頃。
その先生は、いつも自分の腕時計を外し教壇の机に置いて、それから授業を始めた。ある時、先生はそのどこにでもあるような、女子高生から見ると超おじさんっぽい、ちょっと疲れたような、そのアナログの腕時計を私達に見せながら「たくさんの機能が付いているデジタル時計を、なぜ僕は使わないか?」という質問をした。「アナログしか出来ないことが、ひとつだけある」と。結局、クラス全員わからなかった。答えは簡単だった。「一瞬見ただけで、あと何分か、残りの時間がわかる事」それがどうしたという感じだった。私達はもっとビッグな答えが返ってくるものだと思っていた。
あれから十数年。気が付くと私の愛用腕時計はアナログばかりになっていた。そして、ふとあの先生を思い出したのだった。今の私は仕事に家事に育児にと「あと何分」「あと何分」と常に確認し行動しなければならない。時間に大して追われる事のない高校生には、やはり理解できなかっただろうと、過去の自分にも納得した。まだあの頃の先生の年ではないけれど、私も先生と同じなんだと苦笑した。今でもあの先生の腕にはアナログ時計が着けられているだろうか。きっとそうに違いない。私がそうであるように、自分と時間で鬼ごっこを楽しんでいる様な先生だったから。さぁ、明日は週末だ、久しぶりにデジタルを着けてみようか。つかの間の小休止ということで。
1950年代から1960年代にかけて実家の時計は、階段横の柱に掛けられていた。雪が深々と降る冬の午後は、チクタク、チクタクと刻む振子の音が殊更耳に大きく響いた。子供の手の届かない所に掛けられているので、上を向かないと時は意識されない。それでも大して問題がなかった。時々発条が切れて振子が止まっていることがある。そうすると「今、何時なの。」と家中が大騒ぎである。影の薄い時計が大きな存在になる時である。時計は一家に一個。腕時計は、両親だけが持ち、外出時に時刻を合わせるので身近になかった。TVを付けても、一日中放送がある訳でないから時は分からない。ラジオをつける。それでも、正確な時刻が分からない時は、町内放送が知らせる時報を待って時を合わせた。それで用が足りる時代であった。
私が生まれた時からあったと思われる柱時計の振子の金色は、物心のついた頃にはうっすらと剥げ、鈍い銅色の地肌を表わしていた。振子の運動が気になって、両親の目を盗んで時計の下に踏み台を持ってきて上り、時計の蓋をあけて振子に触ってみたり、ねじを巻いたりしたこともある。手で左右に振子を動かしながら口でチクタクと言ったりした。なんとなく不思議な時の刻みを感じていた。
時の移ろいと共に時計も手動から電動へ、更にオルゴール付きの楽しい壁掛けへと交換されたが、一番印象に残っているのは最初に目にした時計である。上が八角形で下がネクタイのように下がった時計を思い出すと、その時計はいつも両親の家ではなく祖父母の家の前の庭にぶら下がった姿で瞼に浮かぶ。時には、裏の畑の真中に浮かんだ姿で思い出される。その理由は分からない。
ボーンボーンという北国の冬海の鈍色を思わせる、悲しく強い毎時音が今でも耳元にはっきりと響く。思い出とはこんなものなのか。脳裏にシュールリアリズムの絵のように刻まれた時計は今でも親の家の押入れ奥に眠っているはずである。
ワールドウオッチの指針が香港を指している。ここはロサンゼルス、東京の時間は何時かと指針を動かそうとしたが動かない。 秒針が2秒づつ進んでいる。ああ、電池がなくなりかけているのかと。 また今年も電池を交換する時期がきたかと感慨深げである。日本では会社帰りに時計屋さんに駆け込んで、親父さんと世間話をしながら電池交換をしてもらっていたが、ロサンゼルスではなかなか電池交換場所が見つからなかった。 時計を販売してくれるからといって電池交換は別である。昨年は悪戦苦闘の末、シアーズで電池を交換した。今年も日曜日にシアーズに行くことにしよう。
今から14年前に結婚と同時に購入した腕時計である。妻の贈り物ということになっている。竜頭とバンド部分の金メッキが薄くなった以外は、傷ひとつなく綺麗なものである。海外の出張や赴任に、いつも一緒についてきたのがこの時計である。時々、いい時計をもっていますねと日本人や外人に言われる。当時は、そこそこの金額であったが、実は値段の高い時計は、いくつも持っている。しかし、高い時計は、時としてパーティなどの場に似つかわしい時計で、決して仕事の雰囲気に似つかわしい時計では無い。 嫌味が無く、それでて格調高く、仕事に使えるという時計は、そうあるものでは無い。また、色々な機械を所持しているが、14年を超えて使い続けたものも無い。ここまで来ると愛着がわくもので、今後も私の人生と共に、ずっと歩み続けそうな予感がある。
時計を語ろうとすると、初めて買ったとき、父親の時計など、まだまだ語りつくせないほどの色々な項目が浮かんでくるものである。
毎朝、愛おしげに こりこりとネジを巻いていた。でも、時間が知りたいときはいつも私に聞いていた。
「今、何時? 」
あなたはあの時から、アタシが時間のある国に戻ると気づいていたのかもしれないね。
彼は、時間のない国の人だった。自分の才能ヒトツで食べてて、仕事が続けば徹夜をしたし、無ければ日がな一日寝て過ごしてた。
休みの日は同じ部屋で過ごしたね。たおやかで、穏やかで、暖かで親密な、同じ時間が流れてた。
「ねぇ、この部屋に時計がないってこと、気づいてた? 」
そう、その部屋には掛け時計はおろか、目覚まし時計の一つもなかった。……知ってたよ。うなづく私に意味深に笑ってる。そんないたずらっ子みたいなところも大好きだった。
不思議に伸び縮みしている時の流れに身を浸しながら、同じ早さで歩いていくことになるであろう幸せに酔っていた。
あなたが大好きだって言ってた、空の高い季節だったね。窓の外が白み始めたある日、心の底から「居なくなって欲しい」って言われてすごく傷ついた。
大切なものまで切り捨てて、ギリギリのところで潔い作品を作り続けているあなたが大好き。夢中な子どものままでいて欲しいから、アタシはそこから切り離されることを受け入れたよ。
時が質感を失っている国からの生還。今のアタシは時間単位に縛られる生活をしている。
彼が最後にくれたのは、いつも大事にはめていた腕時計。……皮肉だよね。あなたのいない時間と、時の持つ現実感を実感させられているよ。
でも、捨てられない。アタシは今日もネジを巻き続けてる。こりこり…こりこり……。
7年前、私の傍には2時間遅らせた時計があった。それは、夫が仕事で駐在しているインドネシアのジャカルタの時刻に合わせてあった。
結婚して6年目の6月、私は初めて妊娠した。夫と二人、待って待って待ち焦がれた子供だった。初めて聞く赤ちゃんの心音に二人で感動し、初めて感じた胎動に二人で喜んだ。生まれたら一番最初に夫に抱っこしてもらおうと思っていたのに、おなかの赤ちゃんが7ヶ月になった11月、夫は突然の辞令でジャカルタに赴任していった。そして、私は時計をひとつ、2時間遅らせた。
朝11時、ジャカルタは9時だ。今日も元気に仕事を始めたかしら、と思う。お昼の2時、ジャカルタは正午だ。ちゃんとご飯を食べているかしらと心配になる。
秋が過ぎ、冬が来て、クリスマスもお正月も実家で母と静かに過ごした。
「パパ、今いないんだから、上手に元気に出てきて、ママを助けてよ」とわたしは赤ちゃんに語りかけていた。その声が聞こえたのか、2月の晴れた朝、元気に産声を上げてくれた。
そして、私もその子を抱いてジャカルタに旅立った。一緒に暮らすために。もう、2時間遅らせた時計はいらない。同じ時を過ごせるんだもの。今度は3人で。
私の初めての海外旅行は1979年、はるか昔である。当時は1ドルが300円を超していたと思う。
わが家の家訓は“高校を卒業したら自立”である。だから自分から大学へ行きたいと言った手前、学校にかかる費用をアルバイトで稼がなければならない。疲れを取るために授業では居眠りをした。それでも卒業証書は手に入れた。
社会人になったらお金を貯め、海外旅行をしようと決めていた。ところが人生は思うようにいかない。働き出したら、何故か勉強する楽しさに目覚めてしまい、数年働いたお金で保育の専門学校へ編入し、再び学生に戻った。外国は遠のいた。
そんな訳で海外へ出かけたのは20代の終わり、約20日間のフランスとベルギー一人旅である。
ベルギーのブリュッセルから列車でパリへ帰るホームでのこと。
あいにくその日は国鉄のストライキで列車の時間が乱れていた。ホームで待っているとアナウンスは聞こえるが、何を言っているのか聞き取れない。一体、何時にパリ行きの列車が来るのだろう。ホームの人に私の英語とフランス語のごちゃ混ぜ語で聞いてみるのだが、答えが返ってこない。
そこに通りかかった年配の恰幅のいい紳士が私に話しかけてくれた。私が列車のことを知りたいと思っているのはわかったらしく、何か言ってくれたが私には通じない。私がわかったという表情になかなかならないので、彼は困って少し考えた。
やおら彼は毛深い手首を私の目の前に出し、何をするのかと思ったら、腕時計のネジを回して針を動かし、ある時間で止めた。そして指差す。やっとわかった。彼が動かしてくれた腕時計の針の時刻にパリ行きの列車が来るのだ。
私はうれしくて「わかった、わかった」と首を何度も振って見せた。「メルシーボークー(どうもありがとう)」と覚えたフランス語でお礼を言った。
あれから海外へは何度も出かけている。いろいろな国で大勢の親切な人に出会ったが、あの日の紳士は彼らの先頭に立っている。
「初めてのプレゼント」金子 雅人さんのエッセイ (10月のベストエッセイ)
ある日、ディスカウントショップで買い物をしていた時、時計コーナーで千円の腕時計を見つけた。それは、見ようによってはとても千円とは思えないほど、精巧に作られたものだった。
ぼくは、実家の親父の誕生日が近いことを思い出し、半分冗談のつもりでプレゼントしてみようかと考え、その千円の腕時計を買った。
親父の誕生日、ぼくはその腕時計を手渡しながら尋ねた。
「これ、いくらくらいに見える?」
「うーん、一万円くらいかな」
ぼくは、自分の思惑どおりに親父が答えたことに満足していた。一万円の腕時計といえば、戦前生まれで、これといった贅沢をしたことのない親父にとっては、それなりに高価なものに違いなかった。
しかし、実家に行くたびに、その千円の腕時計を大事そうに使っている親父の姿を見ているうちに、さすがのぼくも、いつかは本当の値段を打ち明けよう、そしていつかもっと高価な腕時計をプレゼントしようと思い始めていた。
しかし、いつかは言おうと思いつつ、なかなか言い出せずにいるうちに数ヶ月がたち、そのうち親父は癌で亡くなった。ぼくは、その腕時計の本当の値段を打ち明ける機会を、永遠に失ってしまった。そのことは、後々までぼくの心の中に引っかかっていた。
数ヵ月後、実家に行った際に、一人暮らしをしている母とそのことが話題になった。その時、母は意外なことを言った。
「あの腕時計をもらってすぐ動かなくなったんで、電池交換をしてもらいに行ったんだけど、その時、時計屋から、あの腕時計が電池交換と同じ位の値段だって聞かされて、お父さん知ってたみたいよ。でも、お前が初めて買ってくれた誕生日プレゼントだからって、ちゃんと電池交換して大事に使ってたのよ」
ぼくは小さい頃に、親父から毎年誕生日プレゼントをもらっていたことを思い出していた。そして、高価な腕時計を買ってあげることはできなかったけど、たとえ千円の腕時計でも、ぼくは最後に、親父に誕生日プレゼントをあげることができてよかったなと、その時思った。
ぼくは心の中のつかえが、少しだけ下りたような気がした。
「私の相棒。父が貸してくれた腕時計」境野 洋統さんのエッセイ
高校に入ると腕時計をするものだと、当時の私は知らなかった。だから、入学式前のある日、「高校に入るとこれが必要だから、しばらくの間貸してあげるよ」と父から渡された箱が何であるのか、開けるまでピンとこなかった。
開けると、それは白い文字盤が上品な、ステンレスの輝く腕時計だった。裏を返すとそこには『勤続三十年記念・XX株式会社・昭和五十一年』と刻まれていた。一年ほど前に勤め先から贈られたものだった。「俺の腕時計はまだ元気に働いているし、お前の新しい門出には新しい時計が似合うよ」と言ってくれた。「でも、勤続三十年記念の刻印付きでしょ。腕にはめるとやけに重いなあ」と言いながらも、私はうれしかった。こっそり時計屋で調べると、同じものが七万五千円と表示してあった。
高校生活が始まり同級生たちのと見比べると、誰より私の腕時計が輝いて見えた。私はわざと右手首に巻いて、いつも視界の隅で眺めては誇らしく思った。
それから二十六年。今でも借りたままになっているその腕時計を、私は相変わらず右手に巻いている。ガラスの端のキズは高校時代のものだ。大学時代を過ぎ、吊り革をつかんで通勤する時も、飲み屋でビールを飲む時も、バイクに乗っている時も、いつもこの腕時計は右手にあった。時々、汗の匂いと垢で汚れたステンレスのベルトを歯ブラシと石鹸でゴシゴシ磨く。二年に一回くらい電池交換のために時計屋に持っていくと、「こりゃ、いい時計だね」と言われて得意になった。新しい腕時計を買おうとは思わなかった。
ある時、父が言った。「まだその時計していたのか」。「勤続三十年記念を背負ってるからね。そう簡単に捨てられないでしょ。」と私。その父に最近、新しいドレスウォッチをプレゼントした。五万三千円だった。「もらったものより安いけど、まあ、これが今の俺の精一杯の実力」と言って渡した。「もらったことになっちゃったの?!」と父は笑った。
実家には大きな黒塗りの振り子時計がある。昔、父が買ったものだ。横幅が40センチで縦が1メートル以上はある。玄関に入ると、だれの目にも飛び込んでくる。
なんでこんな大きな時計を買ったのだろう、この家のサイズに合ったものが他にもあったはずだ、と幼な心にも、私は不思議だった。
ボーン、ボーンと家中に響くのんびりした音。刻の数だけ鳴り渡る。夜が更けると、さらにゆっくりしたペースに感じた。打ち終えたときには、ホッとしたものだ。
時刻が多少遅れ始めても、両親はあまり気にしなかった。だから気になる者が時間を合わせる。結局それは、高校生になって電車通学をはじめた私の仕事になった。
時計のガラス扉を開けると、ネジ穴が二つある。カチッ、カチッと目一杯両方のネジを巻く。指先に力が必要で、これが大変だった。
大学に入って私が上京してからは、大時計の時刻を気にする人はいなくなった。たまに帰省すると気になって、さっそく足台を用意しネジ巻きをしたものだった。
時刻に針を合わせて、重い振り子を適度に左右に振らせる。振りが適当でないと時間に狂いが出る。その調整にひどく苦労したものである。
結婚して、嫁ぎ先の茨城から三人の子供を連れて夏休みには新潟の実家に帰った。やんちゃな子供から目をひとときも離せない私は、時計の遅れを気にかける余裕をなくしていた。
その子供たちも巣立っていった。ここ数年、何かと用があって、ひとりで実家に出かけることが多くなった。大時計はいまでも同じ位置にある。のんびりと見上げるが、もうすでに動かなくなってしまっている。両親とともに逝ったような時計、もう一度、ボーン、ボーンというあの音が聞きたい。
20年前母との別れは呆気ないものでした。
母危篤の連絡の後を追うように母死すの知らせが来た。姉と手をとって泣いて泣いて、一周忌が過ぎた時思い切って生前母が好きだったハワイへ姉と傷心旅行に行きました。日付変更線で腕時計の針を戻しながら私が「日付変更線上で時計の針を逆にグルグル回したら一日だけ希望の年に時が戻るといいね、そしたらお母さんに逢えるのに」と言って2人で時計の針を何度も回した。
そして二十一世紀の今私は近い将来大きな掛け時計の針を祈りを込めて思いっきり逆回りをしたら行きたい過去に一日だけタイムスリップ出来る時計をきっと誰かが作ってくれることを祈る思い待ってます。
「どうして右腕に時計をしているんですか?」
私がよくされている質問だ。
私のように右が利き腕の人は、普通腕時計は左に付けるもの。右にすると、字を書くときに、時計が机に当たってたしかに書きにくいし、どう考えても邪魔でしかない。それなのになぜ?
実は、元々は私の腕時計は“左腕組”だった。
みんなは、私が何かロマンチックな理由で右腕にはめているのだと思ってくれる。例えば、昔好きだった人が右腕にはめていた云々…。しかし、残念ながらそんなロマンスめいた事がきっかけではない。
それは、高校時代のある放課後のこと。私は何を急いでいたのか、校舎の階段を必死に駆け上がっていた。と、その時、片足を踏み外し、前のめりになったところを、左手一本で全身を支える格好で転倒し、その瞬間左手のぐきっと言う音を聞いた。
結果として、左手首の筋を痛め、数週間使い物にならなかった。それゆえ必然的に腕時計は右手にせざるをえなくなったのだ。
しかし、怪我が治ってからも、腕時計は私の右腕に居座った。慣れとは不思議なもので、いつの間にかそれが自然になり、それに…ちょっと人と違うことをしてみたいというささやかな抵抗心も芽生えてきたのかもしれない。
いつかまた左腕に時計をする日が来るのだろうか?その時はせめて怪我がきっかけでないことを祈るのみ―。
結婚して20年、家具類は別として、当時のTV、冷蔵庫、などほとんどの生活必需品は買い換えてしまっている中で、私の持っていた小さな目覚まし時計が今も使われている。もう朝のアラームは必要なく起きられる様になってしまったが、休みの前日など習慣で、ついスイッチをいれてしまう。すると、水を得た魚のごとくアラームを鳴らし、健在振りをアピールしている。当時はモダンなデザインの目覚まし時計だと思っていたが、今では、懐かしき昭和の時代、と言った風情の持ち主である。今までに何度か、新しいものに入れ替えようとしてみたが、なぜか元の場所に居座っているおかしな時計。落としても壊れるわけでもなく、電池を換えてやるだけで、正確に時を刻んでいる。毎晩何の気なしに時間を確かめる為に、枕元に引き寄せるだけの小さなデジタル目覚まし時計。「相性ってあるのかな」と思う。大切にしてやろう。
私の祖父の家には、昔からはと時計があります。毎時間、「ポッポ」と時刻の分だけ、鳩が鳴きます。私は、小さい頃から、(なぜ、 鳩が時刻の分だけ鳴くのかな)と疑問に思っていました。考えた末、年中の時、≪本物の小さい鳩が中に入っいる≫と自分なりの結論を出しました。そして、次の日から、幼稚園に行くと、私は、毎日のように、友達や先生に自慢しました・・・。「うちのおじいちゃんちに、はと時計ってやつがあるの。その時計は、他のと違って、時計の中に本物の生きている鳩さんが入っててね、5時になると「ポッポ」って5回という感じで、毎時、鳴くんだ!その鳩さん頭良いと思わない?だって、時間を知ってるんだもん。すごいよねぇ。」という感じに・・・。今、考えてみると、(そんな馬鹿な事があるものか!!)と言いたくなりますが、ある意味、小さい頃の私は、''天才的な?発想の持ち主''だなぁと感心してしまいます・・・。
今、私が愛用している腕時計は息子が20年前に初給料で買ってくれたものである。先日、電池を交換したとき時計店の老主人は「まだまだ使えますよ」と言って、電池の新しくなった腕時計を渡してくれた。
愛用の腕時計は、いまだ無傷と言いたいとろだが残念ながら、裏蓋の表面に針で引っかいたような傷がある。15年前、韓国で働いていたときに電池が切れ、交換したときに付けてしまった傷である。当時、韓国ではセイコーの腕時計を持つということは憧れの的のようであった。さぞかし店員も丁寧に取り扱ってくれると期待したが、見ている前で、荒々しく裏蓋を開けて電池の交換をした、そのときに付けてしまった傷である。
お陰で裏蓋の傷を見るたびに異国の地で頑張ったことが、懐かしく思い出される。韓国の2月は寒い、流れている川の水が全面氷るほど寒い。そんな中、立ち上げた工場の生産品が作るところから不良になり、朝早くから夜遅くまで時を忘れ、幾日も過ごした。こんな時も腕にした時計だけは時を正確に刻んでいた。
私も今では定年退職した。愛用の腕時計のように丈夫で長持ちと、健康管理に気を使う昨今である。
そろそろウォーキングに出かける時間がきた、真っ赤な夕焼けが美しい、20年来の友を腕にして出発する。
「たいへん!寝坊した!」
夫を起こすのはもちろん、私の重要な仕事のひとつだった。目覚めが良い私は、いつも目覚まし時計が知らせる前に目を覚ます。そのことには自信があると自負していた。なのに。よりによって大切な会議がある、という日に。
急いで夫を起こした。寝坊した、といってもまだ7時である。会社は9時から始まり、自宅から電車で約1時間。8時に出ても十分間に合うのだけれど、夫はそれを良しとせず、7時には家を出る人だった。その日夫は朝ごはんも食べず、身支度をして話しもそこそこに慌てて出て行った。
ふと気がついて、テレビをつけてみた。画面に表示されている時間は、6時30分。なんと。目覚まし時計が狂っていたのだった。おっちょこちょいな私は他の掛け時計などには目もくれず、ただその目覚ましの時刻だけを信じて行動していた。今頃夫は、いつもより空いている電車に疑問をもちながら、腕時計を見てびっくり(もしくは安心)していることだろう。
ふと、時間の概念がない世界を思った。個人の体内時計にまかせて世界が回れば、どんな風に変わるだろう。それでも、満員電車はいつも満員で、3度の時間にはいつもお腹がすくのだろうか。私たちはしかし、時間に管理されている。そして常にそれに翻弄しながら暮らしている。たかが、文字盤に刻まれただけの数字に。こうやって時間を読み違えば、全てが違って見えてくるというのに。
時計を気にしなくてもいい世界がこの地球上にはないのだろうか。いや、そんなばかげたものに支配されずに生きていくことの素晴らしさを知っている人々だけが住む楽園が、きっとあるはずだ。夫と2人でいつかそんな楽園の住人になれたらいいのにな、と思う。心から。
「かあちゃんの時計」福山 裕教さんのエッセイ (10月のベストエッセイ)
就職試験の日の事だ。飛び起きた私は枕元に置いてある時計を見、顔面蒼白となった。
(寝過ごした!)
そう思うやリュックサックにスーツを押し込み、動き易いジャージに着替えた。バスで行くつもりであったが、そんな余裕はどこにもない。
(道は混んでる、自転車しかない!)
冷や汗に包まれた体を忙しく動かしながら私はそう思った。横では両親が、
「あら、今日が試験の日?」
そんな事を言いながら、のんびり朝食を食べている。
「間に合わん、時計貸して!」
私は机の上にあった母ちゃんの時計を腕に巻き、キョトンとしている両親を尻目に全速力で家を出た。そのまま自転車に乗った。
それから国道を二十キロばかり全力で走った。こんなにも急いだのは人生初の事であろう。母ちゃんから借りてきた赤いバンドの時計をチラチラ見ながら、
「間に合わん、まじで間に合わん…」
悶えながらペダルを踏みまくった。無我夢中という言葉があるが、まさにこの事をいうのだろうと私は思った。
会社に着いたのは母ちゃんの時計によると定刻の一分後、つまり遅刻であった。
(駄目だった…)
私は肩を落とし、人の少ないところでスーツに着替え、指定の場所に重たい足取りで向かった。受付に着き、名前を言い、ゆっくりと顔を上げた。
(まず、時間に遅れた事を謝らねばならないだろう)
そう思い、口を開きかけた。
が!
私の死んだ魚のような目に飛び込んできたのは信じられない希望であった。
受付の上に掲げられた時計が五分前を指していたのである。
(あ!)
その事で私は母ちゃんがいつも言う言葉を思い出した。
「10分前行動よ、何事も10分前行動」
そう、母ちゃんの時計は10分進んでいたのである。
(助かったぁ…)
私はその場に崩れ落ちると、
「どうしました?」
問う受付嬢に、
「いや、何でもありません」
そう返し、ひたすら母ちゃんの時計を撫でてあげたのである。
常に何かを探してる私。
カフェでのおしゃべり、お店に入った瞬間でも、捜してる。
妙にせかせかと斜め45度を見上げたら・・・あった!!
時間は午後3時10分ナリ
「あと、7分余裕あるナ。」
そのへんに腰かけて読みかけの、いま一番ハマってる小説を読む。
うちの父は几帳面に拍車をかけて大変な人であった。あのゴツゴツとして父の油がこびりついて少しベトつくあの腕時計だけを見てきた。
あれしか見たことがない。幼心に時計というものはそう再三と変えるものではないんだと思った。父は会社から戻るといつも決まった場所にそれを置く。朝は朝で決まった時間きっちりに起き、儀式としてそれを身に付けるようで、「いざ、出陣!!」という気合いもそれに感じた。
サラリーマン社会の厳しさもなんとなしにその時計から伝わった。
それにしても頑丈な時計でした。父のように休むことなくへこたれる
ことなく働き続けました。来年私は成人を迎えます。父はいったい
どのくらい今まで働いてきたのでしょうか・・・?確か、18の頃から
と言っていたから、もうかれこれ30年以上かぁ、と思って気付く。
私がまだチャラチャラと遊んでいた時からもう父は・・・と。
壊れないあの腕時計はありきたりの言葉だけど父そのものだ。
いつか言いたい、「お父さん、お疲れ様と。」
まだ少し照れくさいから言えない!!ごめんなさい、こんな娘だけど
お父さんのこと少しは尊敬してるんだよ。あの時計を見てこっそり背中
をのぞいてた私。口で言えないから、この場所をお借りさせていただき
ました。
気がついた時に、なぜか時計は17時24分を指したたままでした。私は今までそれとなく忘れたフリをしていたようでした。
ささいな事で口論をして家を飛び出す・・・とはよくある話ですが、今考えてみてもかなり激しいやりとりでした。(ここでは省略します)
翌朝、リビングで待ち構えていた母親はおもむろにこう言いました。
一つため息のあと、「もう、限界です・・・。」
私は冷静さを保ちつつ心の中でうなずくことしかできませんでした。
そしてもう一つ、 「一緒に暮らさない方がいいと思うよ。」
その顔があんまりにも悲痛を極め、はかなげだったので私はいよいよかとここらで腹をくくり荷作りも早々慌しく支度に取りかかりました。
後ろ髪を引かれる思いとは全く正反対の清々しい面持ちで、げんきんな私はこの新しい門出をひそかに待望していたようでした。
1DKのそこは小さなお城、愛読書やお気に入りのガラクタたち、いっぱい
いっぱいの宝の山の中でしばし至福の時を満喫していました。
ある日、時計がない事に気付きました。「とりあえず」まあ時計くらいは持っていった方がいいだろうとあの日慌ててカバンに詰め込んだアレは壁から取り外した際に止まったままの状態のアレは17時24分を指したままでした。それを見たとき、少し自分の中で静寂な空気が広がりました。あの日、あの時の時間は止まったままで、それは私自身のような気がしたからです。私には時間がなく、それはどんどんと知らない内に落ちていく虚栄の中で今を発見した時でもありました。規則正しく響くあの耳障りのカチカチ、せかすようでうんざりでした。人は時計によって動かされ、支配されながらも純粋に今を充実させようと必死です。落胆したり驚喜したりと忙しくもある毎日の中でも結局は枠の中でしか生きて行けない動物だとばかり思っていました。
腕時計が欲しいと初めて言い出したのは小学5年の冬の頃でした。塾に行くからと理由をつけてねだりました。それは子供向けの丸いふちどったミッキーマウスの時計でした。親としては非常に時間にルーズでいい加減で甘ったれの私もこれなら少しはマシになるだろうという意図だったようです。買ってもらった当初は嬉しさの余りいつも肌身放さずの生活でした。腕を振り上げて時計を見上げるしぐさまでもなんだか大人の仲間入りを果した気がして晴れがましい気持ちでいっぱいだったように思います。
そのうち、だんだん時計をしなくなり、最初はそれに気付いた親も、
「買ってあげた時計はどうしたの?」
「あー、今日はしない。」
それから、ポツポツとしたりしなかったりを繰り返してとうとう無くしてしまいました。我ながらダメな子だと思います。
今、部屋の時計はなくもっぱら携帯で時を感じる生活です。かみしめる緊張感に無縁でいて、時を刻むリズム、何かに向かって進んでいないという現実。どれもこれもです。
時計の針が止まると電池を入れたりネジを回し、電話で時報を聞き、今の「今現在の本当の正確な時間」に合わせる。そうして整えてまた新しく動き出す時計、またリセットできたという妙に得した気分が好きで私は時計が止まる瞬間を心待ちしていたみたいです。人生はそう簡単にリセットは出来ない事実の上で架空の世界を味わえるものでした。
近頃そう言えば聞いてなかったナと思い出すうちはまだもう一度やり直せるんじゃないかと思い始めました。あの音はまた私をせかし始めるでしょう。けれどもそれは私自身のなにものでもない尊いものとなるでしょう。今、「何時」でも構わないと思える勇気はまだありません。ただ、また始めてみたいと思いました。私はダイヤルを回しました。ちょうど4コールきっかり鳴ったあと、あのカチカチに似たなつかしい柔らかさが受話器いっぱいにじんわりを響きました。
「あ、もしもし?私だけどさ・・・元気?」
今日もそれぞれの時間は無限に広がり終わる、確かに可能性だけを信じたいけれどとてつもない大きなものへの挑戦のような気もしてドキドキしています。
中学に入ったら時計を買ってくれるように父に頼んでいた。普段の細々したものは母に頼めば何とかなるが、時計だけは父に頼んでおかねばと前から念を押していた。父は元来ああだこうだと教訓を押し付ける方でなく、例え子供でも真剣に主張した事には寛大だった。世間にあるうるさいだけの父親ではなく、全面的に信頼できた。普通は成績が上ったらとか、何かが出来る様になったからという見返りの条件があるものだが、私にはそれはなかった。その時は無性に腕時計が欲しかったのである。中学生になって希望に溢れていた私は、腕時計の感触で心がきりっとしている充実感を思い浮かべていた。他人がうらやましがるのも少しは頭の隅にあった。純粋には、いよいよ気も引き締まり、しっかり勉強に励もうという気持ちに燃えていたと思う。
入学式も近くなった時、父は自分の腕時計をきれいに磨いて渡してくれた。
「これを持っていなさい」
「えっ、これ?お父さんはどうするの?」
「父さんは別にいいんだ。使わないから」
その夜はフトンの中で腕にはめた時計を摩りながら喜びをかみしめた。もう五十年程前のことで、その頃、腕時計は大変高価で、今のように簡単に買えるような物ではなかった。
「約束だったからな」
謹厳実直そのものの父は約束を守る事をとても大事にしていた。腕時計は中学生にとって必要不可欠なものではなかったが、気まぐれに父が約束したものではない。私の時計に対して憧れる気持ちを大切にしてくれたのだ。時を大切にすることと約束を守る事は同じと教えてくれたと振り返る。自分の必需品を手放してまで約束を果たしてくれた父の意思には切ないほどの感慨が蘇える。
今となっては、携帯電話に付いている時計で、事をすましてしまうことが多く、味気ない時計生活を送っている私であるけれども、記憶に強く残っている腕時計がある。
青春まっさかりであった中学二年生の夏、学校行事でアメリカに短期留学をしたのだが、飛行機に乗ることも、ましてや外国に行くことも初めての経験で、私はかなり浮かれた毎日を過ごしていた。あちらで見たもの、手にしたものはすべて新鮮でかっこよかったのだ。
ピンクやら紫やらやたら派手な色を使っている(スウオッチ)で、日本では(ソニープラザ)に沢山の種類が置いてあり、飽きずに何時間もながめていたものだ。父親はいつも仕事で不在、母も常に不機嫌な我が家では、買い物をしにでかけることもなく、私も弟も、欲しいものはひそかに眺めて満足するのが普通だった。
学校行事ということで、娘にみじめな思いをさせたくない親心だったのだろう、私は生まれてはじめての大金をその留学期間のおこずかいとして持たされていた。
とても奇抜なデザインで、母からは大不評だったけれども、真っ黒にやけた腕にその時計はやたら似合い、腕時計焼けができるほどいつも身につけていた。
昔、就職先の先輩社員からポケットから小さな時計を取り出して、君この時計を買わないかと言われ買ったところ、直ぐ故障したので修理に出したところ、紛失したと云う理由で他の安っぽい時計を返却され、その時計が高価だったのではと思った。
三十才代の時、高価な防水時計を購入し、浴場などで皆さんから羨ましい目で見られていました。これもいつの間にやら消滅しました。倫理研究所の会員となり、早朝起床しなければいけないので、目覚し時計を二千円で求めました。これは妻に随分強く叱られましたが五百円で古物店に売却しました。
妻はやはり、高価なクラシック調の柱時計を購入し、今も隣の部屋から振子の音が聞こえてきます。
長男が結婚して、嫁さんから十万円の腕時計を贈られましたが、もっと安価な物だったのでしょう。現在の腕時計は安価でしたが、大切に使用します。
妻が入院してすぐに病院の近くの時計屋で買った。あまり高価でもなく、使い方も簡単だった。やがて妻は白血病との壮絶な戦いの末、他界した。その時計が妻の最後の命を刻んだようなものだった。わたしは気力を失った。なんとか回復しようと中国の蘇州大学へ講師として一年間の留守をした。トランクのなかにその目覚まし時計をいれた。蘇州大学の専家楼の自室の机の上に時計をおいた。電池のある限り時計は動き続けた。想像してみてもそれは驚くほどの持続力なのだ。時間が流れる。それを人間の意識の内側へ引き込むために秒・分・時間のメカニズムが連動しながら決して休まない。それは感じやすくなっていたわたしには、とてつもない存在の悠久性に思われたのだった。その輪廻のなかに妻の命の時が刻み込まれている。毎朝、わたしは目覚ましがなる前に起きだし、昧爽のキャンパスを歩き回ったのだ。やがて帰国の時がきた。荷造りしていると助手の朱健明くんがきた。
「先生、この時計ぼくに下さい」
あまりものを欲しがらない朱くんがはっきり言ったので、わたしは好感を抱き、同時に思いのこもった時計を中国へおいてゆくのもいいだろうと思った。
「とまったら電池を入れ替えるんだよ」
わたしはそういって渡した。
その後、五年ほどして蘇州大学をふたたび訪れた。朱くんがわたしを家に招いてくれた。そのときわたしは紅くて四角い目覚まし時計を棚の上に見つけた。わたしはなにもいわなかったが、この質素な若い学者の部屋で時をきちんと刻んでいたのだな、と思った。それはなにかとても大切なものとの再会であった。
亥年の私の父は、仕事一筋人間だ。仕事が好きかは知らないが、目標に向かってまるで猪みたいに突進するのが大好きなのだ。彼の口癖は「遮二無二」である。
高卒の父は、当時波に乗っていた製鉄会社に勤めだして「遮二無二」働いていたものの、学歴というどうしても越えられない壁にぶち当たり、どんなにがんばっても、自分が大卒の人より出世することはないのだと、転職を決意したらしい。私がまだ2、3歳の頃の話だ。
しばらく無職の状態が続き、その間自分で商売を起こそうと考えたこともあったようだが、結局彼はまた会社勤めをすることにした。当時の写真を見ると、私を抱く母は長い黒髪で…というのはおしゃれではなく、パーマなんて贅沢ができなくて伸ばしっぱなしだったのだと最近聞いた。我が家は4人も娘がいる。今さらながら、仕事が見つかってよかった。
商売する野望は果たせなかったが、会社で働いていても自分の給料は自分の稼ぎからとるのだと、彼はやはり遮二無二働いた。
勤続5年目に、彼は皆勤賞をもらった。そのときの副賞が、20年経った今も居間で主役の座を守っている、木目調の置時計だ。
普通、転勤は命ぜられるものらしいが、遮二無二働く父は自ら志願し、おかげで我が家は毎年のように住所が変わった。志願しているから引越費用は自己負担で、母は、「うちは引越貧乏よ」と言っていた。
毎年変わる仮の住まいはいつも冴えない借り家だったが、代々の居間で主役を務めるその時計は、文字盤に白く優美な装飾がほどこされ、なんとも上品な雰囲気だ。雑然とした我が家の居間には不釣合いながら、家族皆に気に入られ、今も変わらず時を知らせてくれている。
そろそろ定年を迎える父は、以前より仕事が忙しくないらしい。無趣味だから定年後が心配、という周囲の見解は杞憂で、今度はゴルフの打ちっぱなしで300ヤード飛ばすのだと、新たな目標めがけて猪突猛進中だ。こちらも相変わらずである。
(注)「思い出の時計エッセイ募集」に送っていただいたエッセイの著作権は、セイコーインスツルメンツ株式会社に帰属します。
予めご了承下さい。