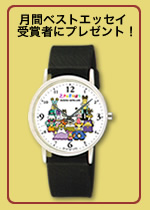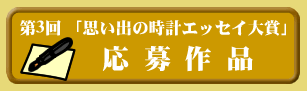 応募期間 2003年1月10日〜2003年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
2003年の作品
1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
![]() 3月の作品(21作品)
3月の作品(21作品)
「タイとビールと腕時計」田中 建治さんのエッセイ
「じじの古(振る)時計」庄司 光郎さんのエッセイ
「ばあちゃんとボンボン時計」和田 敏明さんのエッセイ
「とまりかけた時計」及川 なみきさんのエッセイ
「私の婚約時計」久留 陽子さんのエッセイ
「今度は私がねじを」神田 としさんのエッセイ
「祖父の柱時計」藤原 貞枝さんのエッセイ
「父のため息、二つ分」keiさんのエッセイ
「父と母とガラクタ時計」桐木 完さんのエッセイ
「時計が彼女になる」倉崎 直哉さんのエッセイ
「セイコー5」いぬこさんのエッセイ
「二つの時計」藤井 正男さんのエッセイ
「母のねじ巻き柱時計」 関戸 清さんのエッセイ
「ふりこ時計」石黒 ひろみさんのエッセイ
「おじいちゃんの拘り」梅田 忠彦さんのエッセイ
「流れる時間」土佐 ゆうこさんのエッセイ
「3時」奥田 輝子さんのエッセイ (3月のベストエッセイ) 特別賞
「ご長寿の秘訣」しろぞうさんのエッセイ
「父からの腕時計」藤井浩之さんのエッセイ
「山の神様の時計」まんまさんのエッセイ
「長火鉢」八木 嘉さんのエッセイ (3月のベストエッセイ)
その会食の目的はクレーム処理だった。
当時タイ駐在中の僕は主に日本向け冷凍水産物の輸出に当たっていた。タイに来る前はジョギングを好みハーフマラソンに出る程だったが、ここは熱帯である。油っこい料理を毎日食べ、運転手付きの社有車で通勤の日々は確実に贅肉を付ける。暑い国はビールも美味い。
冷凍物運搬には冷凍コンテナーを使うが熱帯である。問題も頻発し、コンテナー会社とのクレーム処理も重要業務である。その日もコンテナー会社の大村さんという駐在員とのクレーム処理で夕食となった。
クレーム処理であるから楽しい会食には中々ならない。クレーム金額の査定と交渉である。目の前のビールが減らぬままお互いの主張が続く。案の定、話は進まず、後はもう日本の本社間で話して貰うかと諦め始めていた。
その時ふと大村さんの腕時計に目が行った。セイコーのスーパーランナーである。マラソン専用の時計だ。
大村さんに問い合わせた。やはりランナーである。それもタイで走遊会という組織を立上げ、現在会員30名余とのことである。この暑いタイでと呆れる僕に、大村さんはタイがいかに走る環境にあるかを説明してくれた。目から鱗がおちた。
こうなると話は早い。クレームは瞬時に示談、僕は走遊会に入会、暑いタイでレースに参加、ビールで乾杯、だ。
それから4年間。暑いタイでフルマラソンを5回走破し、その間レース後のビールで贅肉も維持し、そして帰国した。
僕より一足早く帰った大村さんとは、今でも時折京浜東北線のとある駅前の居酒屋で一杯やる。ビールを飲んで混んだ通勤列車で帰る。
大村さんの腕には、やはりあの時計が光っている。
今から40年近く前になろうか。父からのお下がりの時計が動かなくなったので、初めて自分で時計を買った。当時、はやりの自動巻きだった。就職して間もない頃なので月賦だった。
私は、時計は時を正確に刻んでくれればいいという考えだったから、2年前になくしてしまうまでは、その時計一つしか買っていない。35年以上、一度も壊れず分解掃除もなしで、私のために働いてくれた。
孫の沙織が物心ついた頃のことだった。私が、その時計を持って振っているのを見て「じじ、何をしているの」と不思議そうな顔をして尋ねた。その頃には、もう自動巻きの時計をしている者などほとんどみられなかった。休みの日には時計をしない私は、時計をする時は、その時計を手に持ってしばらく振り、秒針が動いているのを確認して時刻を合わせていた。沙織にはそれが不思議だったのだろう。
私は、「この時計は古い時計でね。振ることで中のゼンマイというもの巻いて、巻いたゼンマイがゆるむ力で動くんだよ」と説明した。機械のことに疎い私は、その説明が正しかったのかどうかわからないが、沙織はなんとなく納得したようだった。
沙織は、「ようするに、じじのふる時計ね。ふるは古と振るの意味よ」と言う。まだ、小学校にも入っていない時だったので、私は感心してしまった。私は思わず「そう。じじのふる時計だよ。さおちゃんは、うまいこと言うね」と頭をなでた。少し重く感じられたので買い換えようと思っていたが、それを聞いて、まだまだ使うことにした。
ところが、机の上に置いたその大事な時計を、猫がいたずらしてごみ箱に落としたらしく、なくなってしまった。家族全員が机の上にあるのを見たといい、それ以外に考えられないということになったのだ。
それから2年ほど経つが、まだ諦めきれないでいる。
ばあちゃんは今年で91歳になる。ばあちゃんの生まれたところは、茨城県の酒丸というところで、まるで「おしん」の家みたいだったそうだ。
さすがに、奉公には行かなかったみたいだけれど、学校には、下の乳飲み子のきょうだいを背負って行っていた。昔はそういう風景も変ではなかったようだ。
そんなばあちゃんは、東京で空襲に遭ったり、夫に早く先立たれたたり、苦労をしてほっと息をついてみたら91歳だ。それでも、「ふぉっ、ふぉっ、ふぉっ」と笑いながら、今を楽しく生きている。まったく、たまげたもんだ。
ぼくは、たぶん、寺山修司の映画に影響されたせいだと思うのだけれど、古いふるい、ボンボン時計を買ってきた。始めは動かなかったのだが、適当にいじくっているうちに動くようになった。いったん動き出すと、ぜんまいさえちゃんと巻いてやれば、ちゃんと、動く。
ばあちゃんは、そのボンボン時計の音を聞くと「まるで、昔に返ったみたいだよ」と懐かしげに笑う。
ばあちゃんの瞳も、ボンボン時計も、さまざまな時代を、長い時間をかけてみてきたのだろう。だから、大事にせねばならないと思う。
まだまだ、いいことあるよ!ばあちゃん。
長生きしてな。
そう、思いながら、今日も、ゆっくりと、ボンボン時計のねじを、巻く。
ばあちゃんが吐血を繰り返すようになった数日前、主治医は「これが峠となるだろう」と言いました。入院、延命を断った私達は、ばあちゃんが天に昇る瞬間を、この自宅で看取ろうと改めて覚悟した所です。
ばあちゃんが痴呆になってからの二年間、私は勤めていた仕事を辞め、ばあちゃんといつも一緒、同じ空気を吸ってきました。でも、今思えば私の介護は失敗続き。「私だけご飯が貰えない」と、食事の後にも泣いていたばあちゃんを無視したこと。粗相をしたことを隠していたばあちゃんに思わずカッとなり「ばあちゃん!これ!」と声を荒げた時の、ばあちゃんの怯えた目つき。そんな私をばあちゃんは、いつでも慕ってくれていました。私の姿が見えなくなれば、「なみちゃんがおらんようになった!」と、涙声で私を探していましたよね。そんなに束縛しないでと、介護にほとほと疲れていた一頃の私は、ばあちゃんと二人きりの時間が長くなればなるほどに、その涙声が耐えられず、ただばあちゃんの声を聞きながら部屋の片隅で泣いていたものでした。
こんあに全てが後悔だらけ。だから、ばあちゃん。今になって「ごめんな、ごめんな」なんて、哀しい言葉を口にしないでください。粗相をしてしまったことを、そんなに後ろめたそうに私に告白しないでください。ばあちゃんの嘔吐は何度でもとります。だから、そんなことに感謝しないでください。
ばあちゃんのこと大好きです。延命を断ったのも無理な苦痛を与えたくないと、これも一つの家族なりの愛情の印。わかってください。私の夢は「世界で一番幸せな介護をされた」ばあちゃんになって貰うことでした。私にはまだ多くの悔いが残っています。それでも、残された時間の中で、出来るだけ後悔を少なくする為に、私は愛情を注ぎ続けます。だから神様、もう少しだけ彼女の古い時計の針を、止めてしまうのを考え直して貰えませんか。
「誠実に愛せるひとが現われたら、指輪代わりにアンティークの時計をプレゼントしようと心に誓っていました」
前から考えていたことです、といつになく重々しい口調で、彼はいった。
付き合い始めて2年、私達のことは両親や友人に知れ渡っており、結婚は時間の問題といったところだった。
私はといえば、ダイアモンドがはまった指輪には、あまり興味がなかったので、この奇妙な申し出を喜んで受けた。
週末、かねてからの打ち合わせ通り、彼が信頼を置いている店に時計を探しに行ったが、なかなかこれはというものが見つからない。20世紀半ばにアメリカで作られたという時計は、シックな色調の割に、どことなくはではでしいデザインだったし、懐中時計を改造した、ふた付きの時計は、センスはいいのだがあまりに大き過ぎて、私の手首には不釣り合いな印象を与えた。
店内を眺めていてふと目にとまったのは、黒い文字盤が月の満ち欠けのような記号で囲まれている時計だった。それは天体に詳しい彼と、占星術が大好きな私には、何よりふさわしいものに思われた。
「それ、見せていただけますか」
思わず、私は店員さんに声をかけた。近くで見ると、月の満ち欠けと見えたのは、白い丸マークで構成されている、時刻をあらわす目盛りが、長い年月のうちに欠けたり、薄く黒ずみ始めているからだった。サイズは女性用のものより、ひとまわり大きいボーイズサイズ。
「戦前の日本で作られた時計です」
店員さんはそういった。
その時計は今、私の手首で時を刻み続けている。婚約時計、そして彼にまつわる思い出は、数えきれない。時計をなくしたと大騒ぎして、あちこち捜しまわった結果、枕の下に転がっていたこと、二人で温泉旅行をした際に、時計をつけたままでうっかり湯舟に浸かってしまい、青くなったこと…。思い出は私達が年を重ねるのとともに、これからもさらに増え続けることだろう。
夜七時の電話。
受話器を取ると「もしもし」という母の声の向こうから、父の咳払い、そして、ぼぉん、ぼぉん、ぼぉん、と耳慣れた柱時計の音が聞こえてきます。するとたちまち、父母のくつろぐ居間の光景が目に浮かび、そこに引き込まれていくような気がしたものです。
三十年近く十日に一度の決まり事だった実家からの電話は、いつもこんな始まりでした。この決まりが崩れて二カ月後の昨年三月、父が亡くなりました。葬儀を終えた夜、母とふたりきりになって初めて、柱時計の針がとんでもない時刻を指しているのに気づきました。
母がポツンと言いました。「ねじを巻いていたのは、おとうさんだったからね」と。迂闊でした。いつも途切れることなく聞こえていたため、てっきり自動で動いているものと思っていたのです。
大きなため息とともに、また母が呟きました。「お父さんがいないんじゃ、もう駄目だね。この時計も、私も……」
「そんなことないわよ。今度は私がねじを巻くから。大丈夫、ちゃんと動くようになるわよ」
居間の南側、鴨居よりも高く掛けられた柱時計に、父が使っていた踏み台では手が届きません。そうだ、脚立にあがればいい。左右ふたつあってコツが要るっていうねじだって、ゆっくり慎重に巻いていけば、きっと大丈夫。
ぼぉん、ぼぉん、ぼぉん、と時を告げる音が、また家中に響くようになれば、父のいない寂しさが薄れる。七十五歳でひとり暮らしを始める母も、必ず元気を取り戻せる。そんな気がしてならなかったのです。
あれから一年。光沢のある焦げ茶色をした柱時計は、ねじを巻く手のおぼつかなさにもかかわらず、少しの狂いもなく動いてくれています。
茶の間に掛けられていたのは祖父の柱時計であった。祖父自らが購入したという意味ではないと思う。祖父が他界したのち後に、それは「祖父の柱時計」という一つの存在になったのである。暗褐色でつやがあり、その重さは見ただけで計れる気がして子どもの目から見ても重みのある時計であった。二段の踏み台を時計の下に据える。大人は下の段、子どもは上の段にのり、蝶の羽根のような金具でゼンマイを巻く。「ギギーッ」と巻くと、「ギュルン」と戻る。「ギギーッ、ギュルン。ギギーッ、ギュルン。」と繰り返すうちに「ギュルン」の戻りが小さくなって「ギュッ」となり、ゼンマイがしっかり巻けていくさま様が手に伝わる。金具を収め、扉を閉じる。丸いガラスの向こうにはローマ数字で書かれた文字盤があり、四角いガラスの向こうには真鍮の振り子が見えた。そうして時計が斜めになっていないか目を凝らす。「コチコチ」とも「チッチッ」ともつかないその音は振り子の動きに微妙に遅れて聞こえていた気がする。
明治生まれの祖父であった。まだ時代がおおらかに呼吸していた頃で、羽振りのいい生活の御多分に洩れず、舟遊びに芸者遊び、ツツジの宴に菊の宴、書画骨董三昧の祖父であったと聞く。しかしそう言うつれあいに対し、いかなる時も、たとえば祖父が芸者衆を引き連れて戻った時にも歓待し、祖母は妻として賢婦人を通したと母から聞いた憶えがある。祖母はいつも着物の人であった。夫が他界したのち後も、白い足袋をはき割烹着をつけた祖母が、踏み台の下の段にのり、手を伸ばし、祖父の柱時計のネジを律儀に巻いていた姿が浮かぶ。後ろ姿しか見るすべのなかった子供時代のあの頃であるが、どんな表情で巻いていたのだろう、覗いてみたかったもんだと思ったのは、私が当時の母の年に追いついてからである。
私は二度、腕時計をダメにした。
洗濯機の底から母が発見し、父に、「買ってやったのに意味のない奴だ。ものを大事にする癖をつけろ」と怒鳴りつけられた。
高校に通うのに必要だろうと買ってくれたのだが、腕時計をつけるのが嫌な私は、いつも制服のシャツに入れっぱなしにしてしまう。そしてそのまま一緒に洗濯。
数ヵ月後に釘を刺されながら買った時計も、結局は母に発見された。その時から、父は時計のことを何も言わなくなった。
高校卒業と同時に、新幹線で半日もかかるような遠い県に就職が決定した。
そこでの仕事も、生活も慣れ始めた冬の頃だった。
十気圧防水という頑丈な、シルバーの腕時計を見かけた。パープルの文字盤がひどくキレイで、私は子供のようにショーケースに張り付き、動けずにいた。それを見ていた彼氏が、買ってやろう、と言い出した。
ベルト調整で待っている時、彼氏はもっと華奢なやつでも……と別のものに目移りしたようだった。だが、性能が私に合っている、と昔のことを話すと、彼は笑って頷いた。
その時の『保険』は未だ活躍せず、時計は今も、パープルの文字盤の上で時を刻んでいる。
時計をつけて、初めて帰った夏。新幹線の中で私は、時計のことを聞かれたらどうしようと、どきどきしていた。……聞かれたいような、隠したいような。
だが、父は何も聞かなかった。
街に出た時、時計をつけていないと「買ってやっただろうが」と毎度呟いていた。母と一緒に、後ろで笑ったっけ。
もう、父は私を怒らない。ふてくされた文句も言わない。
あの壊した時計は、今も捨てずに持っている。時は刻めずとも、私に、父の少し寂しげなため息を聞かせるから。
我が家には、奇妙な装飾をほどこした時計が山のようにある。腕時計、掛け時計、置時計その他なんでも。母が、父と母とそれらの時計のことを話してくれたのは、妹がはじめて彼氏を家につれてきた日の晩のことだった。
「母さんとお父さんは同じ美大にいたんだけど、つきあいはじめて驚いたのはね、とにかく絵を描きだすと、ほかのことは目に入らなくなること。声をかけても聞こえてない。返事をしないんじゃないの。ほんとうに聞こえてないの」
最初はそのアーティストぶりを誇らしく思っていた母なのだが、あまりにもデートの時間をすっぽかされるのに閉口し、なんとかならないかと父に苦情を言ったらしい。
「そしたらなんていい返したと思う? “集中しているときは、ずっと自分の絵がつくりあげられていくのを見ていたいんだ。もちろん時間は守りたい。だけど、それには時計を見なくちゃいけない。けれど、目の前の絵より魅力的な時計がないんだ。だから時間がわからない。仕方ないじゃないか”」
そんなことを恋人に言う父も父だが、しかし母も母なのである。ならばと安物の時計を大量に買ってきて、自らそれらを装飾し、その「作品」群を次々と父の自宅のアトリエに送り込んだのだ。そしてアトリエが奇妙だが個性的な時計であふれかえったころ、ようやく父が苦情を言った。
「時計は見るようになった。すばらしい作品たちだ。だけど頼むから、どの時計の時間が正しいのかだけはわかるようにしてくれ」
母は妹に言った。
「あんた私に似たところがあるから、あのコにプレゼントするときには誰かに相談してからにしなさい。私以外の誰かに」
時計付きの、ジッポ・ライター。
二十歳の誕生日に恋人がプレゼントしてくれた。コロリと寝かせると親亀、小亀のあんばいだ。子供なら戦車!と表現するかもしれない。タバコを吸わないぼくにとってはライター付きの時計といったほうがしっくりくる。外出のときはいつもこいつをジーンズの尻ポケットに入れておく。今では違和感もない。ふとしたときにひょいとこの時計を取り出すと、周囲の人がみな注目するので気分がよい。「今何時?」と聞かれた時など最高だ。ガンマンのように右手をひらりと後方へまわし、ライターの付いた時計を見せつける。「彼女からのプレゼント?」必ず聞かれる。そうなんですよ。と答える。お気に入りの一品だ。
ところがこいつはすぐに逃げる。イスに座ったときなど特にだ。自動車教習所の車の中で逃げたときはコトだった。背もたれとシートの間に入りこんでいて、なかなか見つからなかったのだ。一時間のうち五十分は教習で使われる。捜索時間は十分しかない。結局三時間無為に待ちぼうけをしてしまった。近頃はイスから立つたびに尻をなでて所在を確認している。無くさないよう気をつける。
ある日、いつものように尻をなでていて思い知った。これはこいつをプレゼントしてくれた恋人の策略なのだ、と。いつも一緒ですよ。しかしいつ逃げるかわからないから大事にしなさいね。いつも気にかけておきなさい。私を忘れてはいけませんよ…。こんな想いを、『無くしやすいが携帯する』小さい時計にたくしたのであろう。
もらってから四年たつが、ぼくはすっかり彼女の策にのせられていたのだ。少々くやしい気もするが、たった一個の時計のおかげで二人の関係は良好だ。これからも続くに違いない。なにしろイスから立ち上がるたびに、尻をなでながら、いつも一緒だよ、と思うのだから。
30年以上前の話なのですが・・高校時代。
当時、女の子が男物の時計をするのが流行っていました。それも、彼氏の物なら、自慢もできますよね。
私はつきあいはじめた大学生としばらくの間「腕時計」の交換をしました。もちろん私の希望です。
その時計が自動巻きの「セイコー5」です。
女子高生の細い腕にでっかい時計は「かっこいい」。文字盤の中に5という字が入っていましたね。コチコチという音が彼の心臓の音のような気がしてそれもドキドキするものでした。
その大学生は今では夫です。先日、雑誌をみていたら、復刻版「セイコー5」を見つけました。懐かしく、又優れたデザインだと改めて感じました。あの自動巻きセイコー5・・・夫が中学合格で両親から贈られた「初めての腕時計」ということでした。今は夫の実家のどこかで眠っている時計です。探して腕に巻いて、起こしましょうか・・あのころの「ときめき」が蘇るでしょうか。
自分の書斎には二つの時計がある。一つは30cmほどの八角形をしたクオーツの掛時計である。80歳で彼岸に渡った母の形見である。63歳のときバスから降りる際に転落した母は,腰を骨折して寝たきりになり、長兄の元で療養生活をしていた。顔を出した折に、枕元の目覚し時計が小さくて見えーへんで,文字盤の大きい時計が欲しいわ」とねだられ,自分がプレゼントした。「これなら、ヨウ見えるわ」と嬉しそうに枕元に立てかけたの覚えている。以来17年母の元で過ごしてきたが,今は自分の書斎でとぃを刻んでいる。
もう一つは昨年の2月だったか,長男が,「お父,景品にもらった目覚まし,あげるわ」と,置いていったプラスチックのおむすび形の本体に,飾りのベルが二つついた高さ10cmほどの時計である。使いさしの単三の乾電池を入れると、コチコチと動き始めた。そして,3月1日,38年勤めた高校の教員を退職するまで残り1ヵ月となった卒業式の日の朝のことである。出勤時にコートを羽織った手がその時計にあたり,棚から落ちて蓋が開き,乾電池が床に転げ出た。その場は急ぎ拾い,元の戻して出かけた。自分が送る最後の卒業生達に証書を授与し、式辞を述べ,滞りなく式を終えた。夕方帰宅して着替えをしていた折に,何気なく目覚まし時計を見た。秒針が逆に回って入るではないか。一瞬、「ええー」と目を疑ったが,確かに逆回りに時を刻んでいる,何とも言えないミステリアスで,ロマンチック,またセンチメンタルを感じ,興味半分でそのまま放置した。が,一ヵ月後電池切れで止った。代りの新しい電池を入れると,今度は正確に時計回りで秒針が動き,今日まで逆に回ることはない。やはり,行ってしまった「時」は元に戻ることはない。
今,自分の書斎で,二つの時計がコチコチと音を合わせて時を刻んでいる。
一人住まいの母の家に、大きなねじ巻き時計が柱にかかっています。私が少年時代一緒に住んでいた頃は、その時計のねじを巻くのは私の役割でした。力いっぱい巻いた感覚が、今も指に残っています。時を刻む音、時報を打つ鐘の音は家中に響くような大きなものでした。それでも住んでいるものには、家が呼吸をしているようであり、まさにはつらつと生きているように思え、けっして苦にはなりませんでした。
母が一人住まいになってからも、その柱時計は振り子を元気よく、右左に振って時を刻んでいます。ねじは母が踏み台に乗ってまいているのです。
時たま家に帰ると、母と一緒に時計も「お帰り」と迎えてくれるようです。床に就くと、時計の音は母の子守唄のよううにも思え、本当に安らかに眠れるのです。
その母が急病で倒れ、あっけなく亡くなってしまいました。
跡かたずけがすんで、ふと気がつくと、柱時計が止まっています。私は昔を思い出しながらねじを巻いてみました。
力を入れたとたん、小さな金属音がして、ねじが軽くなりました。ねじが切れたのです。時計も母と一緒に死んだのでしょうか。その晩の静けさは、今までに味わったことのない深く寂しいものです。聞きなれた時計の音がしない家はとても生きているようには感じられません。
母を失ったことをしみじみとその静けさのなかで実感し、なかなか眠りにつけませんでした。
『おおきな古時計』の歌が、はやっているけど、私のうちにも、ちいさなふりこ時計がありました。ふりこ時計が、30分になると、ボーン、例えば、12時になると、12回ボーンという音やチクタクチクタクと、聞こえる音がすごく癒されました。
そんな私でしたが、小学生の頃、時計が止まると、父に「ネジまわして」と言われると、イヤな気持ちになりました。それは、めんどうだったからです。嫌々ながら、ガチャガチャガチャと止まってしまった時計のネジを回し、ふりこをゆすり、動くと、なんか安心しました。
ずっと安心させてくれた時計だけど、時の流れにはかてず、歌のように動かなくなってしまいました。
今私は、仕事場でチクタクチクタクと、動くふりこ時計を聞いています。
おじいちゃんは、若い頃から時計は外国製が好きで、海外にでると良く買った。ローレックス、オメガ、ウオルサム、ダンヒルなど。だがみな壊れて、「愚のコッチョウ袋」に入れてある。これは、おじいちゃんが「金の無駄使い」の反省を込めて作った袋だ。全部で七つ入っている。おじいちゃんはよほど阿呆なのか、イカサマばかりを掴まされた。
最後にこの袋に入れたのは、アメリカで買ったウオルサムだ。帰国の前日、メイシーズと言うデパートで時計を買う心算で街に出たら、老紳士風の日本人に「私、あのビルで土産店をしています。お寄りください」と言われ、日本語を使う愉しみで、付いて行った。「先ずビールを」と注がれ、一気に飲み干し、ウイスキーの水割りも飲み、すっかり酔ったところで宝石、時計を並べ始めた。彼は「市価の半値」と言って迫ってきた。遂におじいちゃんの手がウオルサムに伸びてしまった。
帰国して、これを取り出したが動かない。直ぐ時計店に走った。「お客さん、これ錆付いていて、修理はできません。」と言われ、おじいちゃんは驚き、体から血が引く思いをした。今の時計も直ぐに寿命が来る。困った。
そんな時ふと思い出したように、机の中を掻き回していた。「バーちゃん、あったぞ、セイコー社の時計がでてきた」「あら本当に? え、時間も日時も正確だわ」。出て来たのはキング・クオーツだ。机の奥底で二年間、正確に鼓動し続けていたこの時計に深い敬意の念にかられた。「時計はセイコーに限る。メカが良い。正確で、デザインが優れている。」と確信した。おじいちゃんの古稀を祝って、子供たちはセイコー・ドルチェを贈ってくれた。今其れが、おじいちゃんの腕で微笑んでいる。
しかし古稀に成っても、なぜ時計に拘りを持つのか不思議でならない。
もお辛い時間が随分長く続いている。
いつかは忘れ行く事だとしても、あまりに耐え難い時間ではないか。
私は失恋をしたのだ。
そう、たいした事ではない。
皆が体験することで、いつかは時間がどうにかしてくれるものだ。
でもよく考えてごらん。
あんなに愛せた人が他にいるかどうか。
たった一人の大切な人と、自分の人生の中で巡り会えたのに
なぜその人を失ってしまったのだろう。
「時間がたてば忘れられるよ」
「他にもいい人なんて沢山いる」
何て言葉、そんな言葉にいったいどんな意味があるんだい?
何十人何百人と言う人と出会ったとして
その中で心に残る人が一体何人いるって言うんだ。
自分の中で自分を支えてくれた、その人が今はもおいない。
これが、この事は時間の問題ではないと思うんだ。
さあ、もお辞めてくれないか。
時を刻むのを辞めておくれ。
私は年をとりたくないんだよ。
あの人となら、ああ、何も怖くはないのに。
時を刻む事が君の仕事ならしかたがない。
時間を進める事が、君は楽しくて仕方がないようだ。
私には止められない。
私は日に日に年をとり、あの人を忘れる事だろう。
それでも忘れないで覚えていておくれ。
私が私の全てで愛した人がいた事を。
いつか今を忘れる日が来たとしても
なにもなかったみたいに、君はカチカチと
音を立てて進んで行くんだね。
それがとても悲しいよ。
僕の腕がとても暖かい。
あの子といた時間を君が思い出させてくれているのかい?
もお一度あの子に会えるのなら
愛していると伝えよう。
今いる時間、あった一秒でも、この時間を
自分の大切な人と過ごしたいではないか。
この瞬間でさえ、一人で過ごすのはもったいないと
君が教えてくれているのだから。
「3時」奥田 輝子さんのエッセイ (3月のベストエッセイ) 特別賞
小さい頃、一度だけ午後3時が2回きたことがある。
その頃親は共稼ぎで、家にはおばあちゃんしかいなかった。いつもお昼を食べてから、近くの小さなお菓子やさんにつれて行ってくれて、いくつかのお菓子を選ばせてくれる。なぜ、私をわざわざつれて行って選ばせるかというと、おばあちゃんが選ぶと、かりんとうだったり、おせんべいだったりするからだ。私はクッキーやチョコなどがすきだけど、そういうお菓子はおばあちゃんには分らない。
その日も私は、おばあちゃんといつもの様にお昼を食べてから、お菓子やさんに行って、自分の好きなお菓子を選んだ。絵本を見たり、玩具で遊んだりしながら、おやつが出てくる3時をワクワクしながらまっていた。そして、テレビの上に乗っている時計の針がやっと3の所に来ると、おばあちゃんが台所から、お皿にお菓子をのせて持ってきた。それはいつもより美味しく、あっという間になくなってしまった。何もなくなったお皿を見て、私は悲しくなった。それは、いつもよりとっても美味しかったからだ。それを伝えると、おばあちゃんはテレビの上に乗っている時計をとって、後ろのねじを回し始めた。すると、その時計は何事もなかったかのように、3時10分前にもどった。そして10分後、魔法のように時計はまた3時になって、おばあちゃんが、お皿にお菓子をのせて持ってきた。
これが一生で、多分一度きりの3時が2度来た日。遠い記憶の幸せな時間。
今、おばあちゃんは寝たきりになってしまった。もう歩く事もできない。今でも、おばあちゃんの寝ているベットの横に座って、時計を見ると思い出す古い記憶。しかし、私は今でも待っている、おばあちゃんがベットから、起き上がってテレビの上の時計をまわす事を。
最近色々な人のおうちにお呼ばれすることが多いのですが、人により置いている時計の数がずいぶん違うことを認識しました。
総じて時間厳守の人は時計の数が多く、遅刻常習犯は少ないようです。
多い人では一部屋に平均3−5個はあり、どの角度からも見えるようにしているので、時計の少ない部屋にいるとどうも落着かないそうです。
時間を気にすること=時計を気にすることになるのですね。
ということは時間を大切にする人は時計も大切にするのでしょうか。
なんと素敵な。
昨年、某男性シンガーがカバーしてヒットした童謡の名曲「大きなのっぽの古時計」。この曲の主人公も自分の一生をそいとげるくらい時計を大切にしてたとしたら、さぞかし時間を大切にしていたのでしょうね。
しかもご長寿だし。100歳没ですもの。む?ということは時計を大切=時間を大切=寿命も大切?ということでしょうか。ご長寿の秘訣ここにあり、ですね。
小さいときから、父が出勤前に腕時計の竜頭を巻くのを見て育った。チラリとTVの画面を見て時間を合わせていたように思う。大人の男が、「これから仕事に向かう前」の儀式にも思われた。1974年、小学校4年生の時に初めて両親が私に買ってくれた腕時計も手巻きだった。小学校には着けていけなかったのだが、朝食後父と一緒に自分の腕時計の竜頭を巻いた。
1992年父親が亡くなった。遺品として、父がずっと愛用していた1954年製の手巻きのロンジンと、私が勧めたブライトリングの2本を引き継いだ。28歳になっていた私はその形見の腕時計の由来を、妻と一人娘に話した。幼い一人娘も黙って聞いてくれた。
2003年。私の手元には、自分で買ったスイス製腕時計6本と、1974年製の初めての手巻き腕時計、、、、そして父の遺品2本がある。
ロンジンとブライトリングも使ってはいないが、他の腕時計同様4、5年に1回のオーバーホールだけは欠かさないでいる。
一人娘の「将来の旦那さん」に”生きたまま”譲りたいと考えているからだ。
私の父は「山仕事」をしていた。草刈機やチェンソー、なた、のこぎりを使って山の手入れをする仕事。時には、滑って怪我をしたり、夏場は熱中症にかかったこともあった。雨の日は仕事に出られず、晴れの日だって、苦労の割にはお金にならない。母と二人で働いてようやく生活できるほどだった。
いったん山に入ると、一緒に働く人の声だって聞こえないくらい離れた場所でそれぞれ草を刈ったり、苗を植えたりする。昼食時と仕事の上がりは時計が頼り。12時にご飯、夕方4時に上がる。きつい仕事から開放される時間。だからだろうか、時計が好きだった。「1週間に2秒遅れる」だの、「これは電池の持ちがいい」だの時計には厳しく、大事にもしていた。
そんな彼が、思い思って買った高価な時計を、仕事中、山に落としてしまったことがあった。大切なものだからこそ腕にはめず、ナップサックのポケットに入れていて、気づいたら失っていたそうだ。広い山の中でどこで落としたのか見当もつかない。来た道をたどって探したが、結局、時計は見つからなかった。
1ヶ月ほど経って別の山を手入れしていた時、父は金色に光る何かを見つけた。嘘みたいだが、偶然にも、それは某有名ブランドの金の時計だったそうだ。人も入らないような山の中で、どのくらい置き去りにされたままだったのだろう、あまり傷は無かった。ひいきにしている時計屋さんに持っていき、どうしたらいいか尋ねた父。安価で掃除と修理を引き受けてくれ、父に使ってやったがいいよ、と言ったそうだ。
ありえないような偶然の話に、父は、山の神様が落ち込んでいる自分に贈ってくれたプレゼントだと言っている。
この時計の一件で、父は、この厳しい仕事が見かけより、嫌いではないんだろうと私は思えてしまうのだ。それは神様がいつも見守ってくれている仕事だから?
社会人になって二月めに腕時計を買った。もう三十年も前のことで、五ヶ月月賦だった。ガラスは厚くてクリスタルのようなカットになっていた。ベルトは金属製だったこともありそれまでの時計と比べて重さがあり、腕にはめると存在感があった。半そでになる夏場には特に映えた。そして、いかにも新人サラリーマンという感覚で颯爽と通勤したものである。ただ、五年ほどたった頃には一日に二分ほど遅れるようになったのと、うっかり落としてガラスが少し欠けてみっともなくなったので、新しいのを買った。それで、その時計を田舎の父に渡した。明治生まれの父の感覚からすれば腕時計は高価なもので、いわゆる一生ものであった。単純に父は喜んだ。そして、時代劇に出てくるような長火鉢の引き出しにしまった。そこは父にとっての宝物を入れる場所で印鑑や貯金通帳、宝くじ、保険証書など大切なものが入れてあった。私が捨てようと思った腕時計がそんな貴重な品物の仲間入りをしたのである。私は驚くと同時にどっか恥ずかしかった。そして、その頃からボーナスが出たときや帰省したときに品物を買って父に贈るようになった。銀製と刻印されたキセルや父の散髪用の電気バリカン、あるいは低周波按摩器だったり、ロッキングチェアになったりした。故郷を離れて暮らす私にとっての親孝行は物を贈るかお金だったのである。これといって持病があるわけでもなかったのに、その後六年ほどであっけなく父は死んだ。母によれば、テレビの十二時のニュースが始まるとあの腕時計を取り出し、時間を合わせ、しばらくは腕にはめてみていたという。ベルトは小さくできる限界まで調整してあったのに、細くなった父の腕にはあわずだらりとぶら下がっていたという。お坊さんが「何か思い出の品物はありませんか」と言ったとき、私はためらわずにあの時計を棺の中に入れたのであった。
(注)「思い出の時計エッセイ募集」に送っていただいたエッセイの著作権は、セイコーインスツルメンツ株式会社に帰属します。
予めご了承下さい。