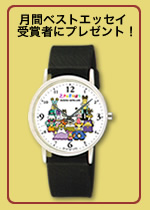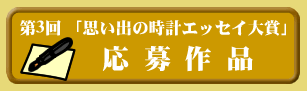 応募期間 2003年1月10日〜2003年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
2003年の作品
1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
![]() 7月の作品(11作品)
7月の作品(11作品)
「仕事場」池田 久美子さんのエッセイ
「大切な40年前の腕時計」栗谷川 福子さんのエッセイ
「左手の安心感」佐久間 純子さんのエッセイ
「青の時代」夏野 陽さんのエッセイ
「おやつの時間」金子 雅人さんのエッセイ
「待つ母」伊藤 都さんのエッセイ
「家の中を活気付けた柱時計」吉田 淳子さんのエッセイ
「娘がくれた思い出の時計」稲木 英生さんのエッセイ
「優しい音」ふじい さとえさんのエッセイ (7月のベストエッセイ)
「いじめられっこの事」ポン太さんのエッセイ
「長いつきあい」白石 敏男さんのエッセイ (7月のベストエッセイ)
「ボーン、ボーン、ボーン」
夜中に目が覚め、ひとりでトイレに起きることが怖かったあの頃。やっとの思いで、意を決して起き上がると必ず聞こえてくる、異様なあの音。背後を何度も振り返りながら、ぐっすりと寝ている家族を起こさないように、そっと起きる。するとなぜかいつも同じ回数だけ音を奏でていた。誰かの仕業なんじゃないかと思ったこともあった。その音に、子供ながら恐怖心すら感じていた。
たった8畳の部屋で仕事をしていた大きな父を見下ろすかのようにかかっていた時計。戻しても戻してもその針は進んでいく。正確な時間を刻めないなら、時計の意味がないじゃない、なんて思っていたけど、なんだか、今では、懐かしさすら感じる。随分と高いところにかかっていたようにも思えるが、手を伸ばしてみると、意外にも届きそうだ。あの頃との時の流れを感じる。
そんな振り時計も、主を失ってからか、静かに時を刻むのを辞めた。いつ見ても一定の時をさしたままの状態だが、誰もその時計を処分しようとはしない。時計って、時間を教えてくれる事だけが、その使命かと思っていたが、少なくとも我が家ではそうでもないらしい。
あの不気味な調べは、もう聞こえてこないが、それを見るたびにあの頃の想いや父の面影がそっと浮かんでくる。
「今も使っている40年前の腕時計」栗谷川 福子さんのエッセイ
今も使っている40年前の腕時計
数日の旅行に行くとき、必ず取り出してネジを巻く腕時計。今どきはもう見かけないセイコーの腕時計。40年以上も前、高校と大学時代に使っていた。母が私と一緒に新宿三越に行き、セイコーの腕時計を買ってくれた。自分で買わなかったのだから、父が働いて得た給料を使ったに決まっている。父は厳しかった。
中学時代のことだ。いずこの子供も同様であったが、私も、「クラスでみんな持っているから腕時計を買ってほしい」と父に言った。父はそれを聞いて私に言った、「『みんな』というが、ホントにみんなか?クラスで何人、腕時計を持っているか、あした学校で調べてこい!」
結果を報告しなければ、父は次の段階に進まない人。終戦後、昭和20年代から30年代にかけて、子供はおおむね小遣い銭など貰わなかった。必要なものをその都度、親に頼んで買ってもらった。お金を渡されたときには必ず領収書とお釣を親に手渡すのが我が家の慣わしだった。つまり、父からの命令であった。たとえ、1円であっても。
だから、翌日、クラスの生徒全員が腕時計を持っていたわけではない、という事実が判明したので、私は腕時計を買ってもらえなかった。
しかし、父が希望していた都立高校に私が入学したとき、父はセイコーの腕時計を買ってくれた。今なお、正確に時を刻んでくれているその古い腕時計。現在は、世界中のどこでも、安いクォーツの腕時計が出回っている。が、突然、どこかで電池が切れたらアウト。電池を入れるまで使えない。だから、私は旅行にその学生用腕時計を持っていく。なぜ、いまだに使えるのかわからない。修理にも分解掃除にも出していない。どんなに高価な高級腕時計にも負けない最高級の一品。古くて最も新しいセイコーの学生用腕時計。終戦後、さまざまの苦労をした両親からのプレゼント。だが、今も生きている。
近頃あまり腕時計をしている人を見掛けない。友人達も皆携帯電話の時計機能を利用している。そういう私もここ数年ファッション以外で腕時計をしたことがないことに気がついた。昔は何かの記念日(例えば誕生日や入学祝)にいろいろな時計を貰った覚えがある。久しぶりに子供の頃からの宝物入れを覗いてみた。そこには皮のバントが擦り切れ、電池切れでもう動いていない時計たちがねむっていた。両親に初めて貰った時計、彼とペアで買った時計、自分でお金を貯めて買った時計。その一つ一つを手にとって眺めていると思い出が甦ってきた。
今でも忘れられない彼がいる。でもだいぶん昔のことなので雰囲気しか思い出せないけれど。その彼の仕草で一番思い出深いものが腕時計を見る仕草だ。背の高い彼が不意にうつむきかげんで時計をみる。私は彼のその仕草が何よりも好きだった。
私は思い出の時計を一つ自分の左手首につけてみた。昔ながらの感覚。「あーこの装着感、安心感だ。」忘れていた感じ。きっと私の忘れられないあの人も今もどこかで相変わらず腕時計をみながら幸せに暮らしているだろう。そう願っている。
大学時代の友人に出会った。口では「変わらない」と言っていても、「お互い年を取ったね」と感じていた。ただただ懐かしかった。大学を出ると直ぐに国へ帰ってしまった彼女。今何をしているのか聞かなくても、お互いに解りあえている。言葉を選びながらの会話は長くは続かなかった。時間を確かめるようにふと見た腕時計にすべての想いが凝縮されていた。そして、「まだ大事にされているのかい?」と私の腕時計をたたいた。その彼女の手にも同じ腕時計があった。一緒に旅行した時、ホノルルの免税品店で買ったペアウオッチだった。学生時代最後の思い出に二人でプレゼントし合った時計だった。さよなら相棒、そして学生時代。
小さい頃、ぼくは大人がしている腕時計にあこがれて、左手首のあたりに、よく腕時計の絵を描いて遊んだ。広告などで見かける時計は、決まって10時8分あたりを指しているものだが、ぼくの絵の中の時計は、いつも3時を指していた。もちろん、3時=おやつの時間という刷り込みが、ぼくの中にできていたからに違いない。
小学校に入学してからは、リューズで針をクルクルと動かすだけの、オモチャの腕時計を買ってもらい、得意気に腕にはめた。その時も、時間は決まって3時を指していた。
小学校高学年になって、ようやく手巻き式の腕時計を買ってもらった。今度は「いつも3時」というわけにはいかなかったけど、自分の腕時計が3時を指していると、授業時間中でも、なんとなくワクワクしたものだ。
それから30年の時が過ぎた。
世の中不況だというのに、仕事中は息つく暇もないほどに忙しい毎日が続いている。だから午後、部下にお茶を入れてもらう時になって初めて、もうそんな時間かと、ふと我に返ることがたびたびある。そんな時、何気なく左腕に目をやり、自分の腕時計の針が3時を指しているとなんとなく安らいだ気分になるのは、きっと子供の頃のその記憶のせいなのかも知れない。
九代続いた夫の生家を今たった一人で守っているのは九十二歳の義母です。長男の夫が何度か同居をもうしでましたが「私はここで死ぬ」と首を縦にふりませんでした。夫は定年後月の半分は生家で植木の手入れなどして母と過ごしておりましたが、都会づれした息子に義母の風当たりは強くやることなす事不満を言いました。
それでもたった一つ義母が夫を当てにしていることは各部屋に掛けた柱時計の電池交換でした。ところが一年半前夫が倒れてリハビリの生活に入るとあれだけ気丈だった義母が電話口で只息子を「頼む頼む」と言うばかりでした。先日夫をショートステーに預けて義母を見に行くと各部屋の柱時計は全て止まっており「電池交換をしましょうか?」と言うと「あの子が達者になった来る迄待つ」と言いました。この義母が生きているうちに家中の柱時計が叉活発に時を刻むように夫を達者にして帰って来るからと小さくなった義母の背中にそっと誓いました。
今は亡き母から聞いた話である。
その当時日本はまだ貧しかった。
戦後間もなく結婚した二人は、間借りした六畳二間に新所帯をもった。
わずかな家財道具でのスタートだった。
しばらくして父が柱時計を買ってきた。
柱時計一つ加わったことで生活自体が活気付いた。
そんな中、私が生まれた。
あまり音のない生活の中で柱時計がボンボンと時報を告げると、両手両足をバタバタして「キャッキャッ」と声をあげて喜んだそうだ。
時報が五時、六時を知らせると一緒になってその同じ回数の足や手を寝たまんま動かすそのしぐさが、かわいらしく母も我子の成長を喜び、次の時報を待ったものだと、ゼンマイ掛けを忘れない様に、そして又その時報の音で目を覚ましたりはしないかと、気を使った事もあったと記憶をたどりながら話してくれた。
その時計は、私が大きくなるまで働いてくれていた。
娘がカナダへ語学留学で出かけました。帰国するときに、国際電話で「お父さんのお土産は何がいい」と聞かれました。今の腕時計が古くなったので、実用的な時計を買ってきてもらうことにしました。その時計はあまり聞いたことのない名前でした。スイス製のものと思いますが、日本のメーカーのものと外見は差がありませんでした。
お土産でもらったので、早速、使いました。しかし、クウォーツ時計にしては1ヶ月も経たないうちに、少しずつ遅れるようになりました。リュウズを引っ張り出して、時刻を修正するのに爪が痛くなるほどでした。1年も経たないうちに動かなくなり、自分で電池を交換しました。時計の心臓部のムーブメントはスイス製で、電池はアメリカ製のものでした。
思い出の時計を面倒見ながら使っていると、なんとなく愛着が湧いてきました。私が若いころに使っていたゼンマイ式の時計を思い出しました。毎日のゼンマイ巻、数日に1回はラジオの時報を頼りに、正しい時刻を合わせることで、時計を使いこんできました。自分が面倒をみないと、いうことを聞いてくれない機械はまるで友達のようでした。
終戦直後の日本製品は安物の代名詞で、安いだけで品質があまり良くなかったのです。その後、工場の品質管理の技術が向上し技術開発が進み、安くて良いものが日本製品の特徴になりました。今の時計は一度購入して時間を合わせれば、永いこと何もしなくても正確な時刻を教えてくれます。電池や時刻合わせもいらない時計もあります。正確な時刻を教えてくれる精密機械です。そのため時計に求めるものは、ブランドとデザインだけになったような気がします。
娘にもらった時計には愛着があり、2年ばかり使い続けました。電池の消耗が早く、時刻合わせをするわずらわしさで、娘が嫁に行った後は机の引き出しで眠っています。絶えず面倒をみないと動いてくれない時計は、人間味があるのかも知れません。
「優しい音」ふじい さとえさんのエッセイ (7月のベストエッセイ)
昔、祖父の家の居間には古い振り子時計があった。振り子の音は止むことなく時を刻み、一時間ごと、ボーンボーンとずしりと響く音で時を知らせた。
幼かった私と妹は、時計の音を怖がり、時計が鳴り出すとビクリとして耳をふさいだ。そんな私たちを祖父はおかしそうに眺めながら、「ほら、今3回なっただろ。今は3時ってことだよ。」と教えてくれた。まだ時計の見方を知らなかった私たちは、それ以来、時計の音を数えて、時間を知るという事に夢中になった。「あっ、5回なった!5時??」と言うと、「そうだよ。当りだ!」と祖父が笑った。いつの間にか時計の音が怖くなくなり、カチカチいう音も、体に響くボーンボーンという音も、心地よいものになっていた。
それから時が経ち、私も大きく頃、その振り子時計は動かなくなり、新しい時計がやってくることになった。次の時計は、振り子時計ではなく、静かな音の鳴らないタイプの壁時計だった。その時、なぜかとても悲しくて寂しかった。そこにあった振り子時計は、あまりに当たり前にあったけれど、だからこそ大切だったんだとその時初めて思った。「寂しいね。」というと、少し笑って祖父が頷いた。
いつか、あの音に似た振り子時計を、祖父にプレゼントしたいと思っている。
いじめられっこだった私は、小学校も中学校もさほどいい思い出なんか無い・・・・・
いじめられると言っても、今のようにクラス全員が加わると言う物ではなく、一部の男子からのからかいのような感じで、それでも学校なんか行きたくもなかった。
毎日「ブス」などといわれると誰だって傷つく物である。
やはり先生は何もしてくれなかった、こういうときは、大概家族だけではどうしようもない。
まあそれでも女子に友人が少しいたのがせめてもの救いだった。
何とか中学を卒業して、高校へと進学した、その時買ってもらったのが、ミッキーマウスのついた、アルバの時計だった、林檎を落とすゲームのついた時計のベルトはクロで、当時どうしてもその色に妥協できず、お店でわざわざこげ茶色に変えててもらった。初めてクラスに入ってびっくりしたことに同じ中学から来た人が少なくほとんど知らない人たちばかりだった、人見知りと心にひずみを持った私の心は「不安色一色」だった。
やがてそれが幸いすることも知らずに・・・
初めて隣になった女の子が話しかけてきた「何処の中学?私は隣の市なの。」私はびくびくしながら、答えると「何故そんなに恥ずかしそうなの?これから一緒なクラスなのよ、かわいい時計ね、見せて」それからだった、生まれて初めて学校が楽しいと思える生活がやってきた、私の時計はクラスで評判になった、「見せて、ゲームさせて」と色んな人が話しかけてきた、初めはオドオドしていた私も時計を通じてクラス全員と話もできるようになった、なにより、相手の顔を見て話が出来るようになった。
時計の話だけでなく、たわいも無い雑談や、ジョークなど、当たり前の事だが、それまでの自分の生活が一変した。
相変わらず同じ中学出身の子達からは、「最近生意気だ」などといわれていたが、そんなこともいつしか気にならなくなった。
時計一つでこんなに毎日が変わるものかと自分でも驚いた。
高校三年間使ったその時計は今でも机の中にあり、時を刻んでいる。
「長いつきあい」白石 敏男さんのエッセイ (7月のベストエッセイ)
三十五年前のある日曜日の朝、家の裏で紙くずを燃やしていた妻が「お父さんたいへん」と、あわてたようすでとんできた。
前の日探していた腕時計が、火バサミにはさまれて、まっ黒に焼け焦げ哀れな格好でだらりとぶら下がっている。
一歳になったばかりの娘の仕業だった。目に付くものを手当たりしだいにちり紙に包んでは捨てていたのだ。やむを得ず高かったが新しい時計を買った。
ちょうど三十年経った五年まえガラスの内側に水滴がついていたので分解掃除をしようと時計店に持って行った。
店の片隅で、腕ぬきをして片目にレンズをはめたいかにも職人さんといった感じの、オヤジさんが座っていた。修理代は二万円だという。買ったときの値段と同じであった。
「お客さん、この時計まだまだ使えますよ」
ちかごろは古いと見たら、そろそろ買い換える時期ですねぇ。というのが普通なのに、この職人さんは腕に覚えありとみた。愛着もあるので直してもらった。
先日の朝、ネジを巻くと手ごたえがない。
そんなおり、まるで見計らったかのように『職人のプライド』という、新聞のシリーズものにあのオヤジさんが載っていた。「古い時計でも、メンテナンスするのが時計職人のプライドです」と、いっている。あの職人さんは使用人ではなく、そこの社長さんだった。
持って行くと「ゼンマイが切れましたね。在庫がないので探して直しましょう」と、当然直すものと決めている口ぶりである。
「いい時計ですよ。三十五年間使っても、うら蓋の金メッキが、しっかりしています」
「それじゃあ、おねがいします」
「はい、お預かりします。お代は一万円になりますが、先にいただいてよろしいですか」
娘のおかげで手に入れたこの時計。もう少しつき合ってもらうことにしよう。
(注)「思い出の時計エッセイ募集」に送っていただいたエッセイの著作権は、セイコーインスツルメンツ株式会社に帰属します。
予めご了承下さい。