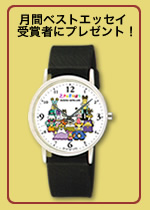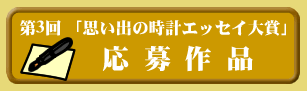 応募期間 2003年1月10日~2003年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
2003年の作品
1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
![]() 11月の作品(26作品)
11月の作品(26作品)
「ペアウオッチ」冨樫 緑さんのエッセイ
「地球防衛軍」佐々木 裕一さんのエッセイ (11月のベストエッセイ)
「掛時計-文字盤の数字」田口 厚さんのエッセイ
「私の初めての腕時計」東江 真貴子さんのエッセイ
「熟年なりし親恋し」柏本 貴子さんのエッセイ
「狂った家族」高橋 幸男さんのエッセイ
「父の証」山田 東加さんのエッセイ (11月のベストエッセイ)
「彼からもらった腕時計」堀江 美由紀さんのエッセイ
「ショーケースの中の腕時計」西都 新吉さんのエッセイ
「「すぎおと」さんとチャイムの時計」東元 正臣さんのエッセイ
「ゲン爺」トムちゃんさんのエッセイ
「両親の愛の証拠(あかし)の腕時計、再び・・・」内田 純近さんのエッセイ
「腕時計でオトコゴコロを操る方法」村井 葉子さんのエッセイ
「ミッキーの耳のような…」柳原 光代さんのエッセイ
「一コマあたりの時計の話」伊藤 朋子さんのエッセイ
「ディズニーウオッチ」金子 雅人さんのエッセイ
「娘と父の時計」あおぞらさんのエッセイ
「お似合い。」ぶいさんのエッセイ
「まだ動いてるよ」唯東 花音さんのエッセイ
「魂の証明」達口 さくらさんのエッセイ
「もう動かないその時計」中井 ちぐささんのエッセイ
「ペア時計の秘密」あやさんのエッセイ
「小人さんの観覧車」橋本 康子さんのエッセイ
「初めての腕時計」星川 千里さんのエッセイ
「一分一秒の戦」横山 蘭さんのエッセイ
「ドルチェはわたしの恋人」北條 五十彦さんのエッセイ
18年間、時を刻みつづけている左手の腕時計は、彼とお揃いのペアウオッチ。当時恋愛中であった私たちの付き合いに、終止符を打とうと決めたその日、彼が銀座のあるデパートで買ってくれたものである。
明日から別々の人生を歩もうと決めた筈なのになぜなの。いまさらペアだなんて何よという気持ちもあったのだけれど、お互い嫌いになって別れを選んだ訳ではなかった。
彼は埼玉県、私は九州の福岡県に住んでいた。遠距離恋愛の上に、私が四つ年上である。当時はまだまだ年上女房は珍しく、周囲を説得するだけならいざ知らず、当人同士にも世間体や、常識にとらわれているところがあった。彼は社会人になって2年目。ようやく仕事が面白くなってきたところだから、「結婚」は遠い先のことだったのだ。
今思えば、なぜ私はこの時、結婚の二文字にこだわったのか不思議な気もするが、29歳になろうとしていた私に、「まだ行かないのか」と言う周囲の目が突き刺さっていたのだと思う。
彼の選んでくれた時計は、金に燻しをかけたアンティークなデザイン。文字盤は白く、ベルトは蛇腹になっていて留め金を止める必要もなく取り外しがとても便利な物だった。
私は腕にした瞬間から、傷つけないように、傷つかないようにと注意を払い、来る日も来る日も表面のガラスを磨いた。寂しければ文字盤を見つめて語りかけては愚痴を聞いてもらい、楽しいことがあれば左腕に向かって報告したりもした。
5年間、それぞれの場所で時を刻んでいた腕時計は、今、同じ家の中にある。そう、彼と結婚したのである。そして13年の時が重ねられている。
二人のことならすべてお見通しのペアウオッチ。思わず襟を正す。あの日以来時を刻みつづけてくれた腕時計に感謝をしつつ、久しぶりに二人分のガラスを磨いてみた。
「地球防衛軍」佐々木 裕一さんのエッセイ (11月のベストエッセイ)
幼い頃の私は学力という意味で少し他の幼児より遅れてたかもしれない。小学校1年生の頃、同級生の”今何時?”、” 何時だよ” という会話が理解できなかった。時計の読み方がわからなかったのだ。
2年生になった時、そんな私をやや心配したのか、祖母がおもちゃに近い腕時計を買ってくれた。プラスティック製ながら、蓋付きタイプで、開けると文字盤が現れる。このスタイルがひどく私の気を引いた。が、私はそれを時計とは認識しなかった。なぜかそれを地球防衛軍の無線機に見立ててしまった。当時のテレビ番組の影響だったのだろう。黒光りしたふたをパカっと開けては青い文字盤に向かってしゃべり、他の隊員との通信を図るという寸法だ。かちかちと動く針は、私にはひたすら防衛軍ならではのハイテク装備の象徴としてのみあり続け、それゆえにいやがおうにも正義の戦士としての気分は高揚してしまうのであった。
空地には仲間と見つけた我々の秘密基地があって、連日そこで防衛軍ごっこだった。基地といっても古い材木で囲んだ2m四方の場所があるに過ぎない。そこに3人程の仲間と入り込んで、戦闘開始だ。目の前に相手がいるにも係わらず、我々の会話はすべて腕時計の無線機を通じて行われた。持ってない隊員はマジックで腕に描いたりした。”異常あるか?”、”異常ありません”、”あ、隊長、バルタン星人が現れました!”、”よし、全員出動!”といった具合だ。
そんな使われ方だったので、時計はすぐ埃だらけになり、時計として使われる前に壊れてしまった。私はとてもショックで、動かない針をじっと見つめ念力で動かそうとまでした。
初めての時計というのは忘れないものだ。が、あの時計には、とうとう本来の時間を示す仕事もろくにさせてあげられずじまいで大変申し訳なかったと思う。でも一方では、一途な子供地球防衛軍の任務にちょっとはいっしょに心躍らせてくれたかな、ともちょっぴり期待している。
転勤を終え古巣のわが家に戻った時、中学一年の三女が懐かしそうに居間の掛時計を見上げ呟いた。
「あっ、あの文字盤の数字、時計を読めない私のためにパパがマジックで書いたのよね」
そう、あれは六年前の事になる。小学校へ入学して間もない三女は算数が大の苦手で、時計を見て「何時何分」と読むのにとても苦労していた。教育に熱心でない私など、そのうち九九を習い5の段を覚えると、自然に身に付くだろうと余り気にしていなかった。ところが、一流大学を目指す高校三年の長女が家庭教師ではそうはいかない。スパルタ教育は毎夜続き、彼女はヒステリックに叫ぶ。
「何で分からないの! 長い針が1の時は5分なの。だからぁ、これは8時5分!!」
三女はノイローゼ気味に泣き叫ぶ。
「だってぇ、レナちゃん分からないもん!」
見かねた私はある日、珍しく父親の指揮権を発動した。
「今すぐ、家にある時計を全部持って来なさい! 全部だよ!」
「???・・・」
いぶかる長女を尻目に、私は掛時計の文字盤に次々と黒いマジックインキで数字を書き込んだ。1の脇には5を、2の脇には10、3の脇には15と・・・。
「レナちゃん、これならわかるでしょう?」
「うん、分かるよ。9の時は45分でしょ!」
絶句する長女。
「そんな・・・。こんな親、初めて見たわ」
しかし私は、自分をこの上無い合理主義者だと自負している。そんな訳で、わが家の家中の掛時計の文字盤にはすべて黒い数字が書き込まれている。たった一つ、私の目の隙を盗んで妻がこっそり隠した、お気に入りのミッキーマウスのからくり時計を除いては・・・。
しかし、時を超えまたもや問題は発生するのである。英語が大の苦手な三女は時計を見上げ、ヒステリックに叫ぶ。
「8時5分は英語で何て言うの? ああもう、分かんないよ!」
両親からの高校入学のお祝いが「私の初めての腕時計」だった。母親と近所の時計店へ行き、特に目に付いたわけでもない単純な形のその腕時計を選んだ記憶がある。高校卒業も近い頃、アルバイトを終えて帰る途中、腕時計が無いことに気がついた。一緒にいた友達も探してくれたが、見つからず諦めかけた。その時、何気にジーンズのポケットに手を伸ばすと「あった!」友達は呆れたが、私はホッとした事を覚えている。その時に『ずっ~と、持ってみようかな!』という気持ちになっていた。それから高校を卒業し、専門学校、就職と私の腕には、意識することなくその腕時計があったように思う。24歳の頃、単身でカナダに向かう機内でも私の腕にはその時計があった。普段よりも特に必要とする日だった。しかし、なんと、途中で電池が切れて針が止まっていたのである。「まったく~こんなときに、使えないなぁ~!」と嫌気がさしていた。乗り継ぎのため降りた空港で、通じるかな?とドキドキしながら「What
time is it now ?」と聞いたりもした。それでも不安で時計を探した思い出もある。
カナダで、仕事をしていたある日、腕を見ると時計がない!床を見渡しても無い。歩行経路を辿っても見つからない。ベルトがゆるみ落ちたのか?何時から無いのかも全く検討がつかない。とうとう無くしてしまった。高級でもなく、デザインもありふれている、でもとても愛着があった。結局、高校の頃の様にポケットから見つかることもなかった。
あれから十数年が過ぎ、今では数種類の腕時計を持っている。高級ではないが気に入ったデザインもある。しかしあの時計ほど愛着は無い。腕時計の数だけ、気持ちも分散されているのかもしれない。でも大切に使っていれば、いつか愛着をおぼえるのだろう。
毎日、当然のように身につけていた腕時計。あの時、無くしてしまったが、いまでも心に残る『私の初めての腕時計』である。
「しっかり持っとけよ」「うん、わかった」、柱時計にネジを巻く父と兄の会話だ。三年生の兄は腰をかがめ父が落ちないようにと、必死でイスにしがみついていた。ネジを巻く音が『ギリギリ、ギリギリ』と、泣き出し父の手が針を持った瞬間『ボォンー、ボォンー』と,お礼を言うかのように部屋中に響き、兄と私は「にこ」と顔を見合わせた。明治生まれの父は、とても器用な人で「味噌、塩辛、酒」と、魔法のように作り納豆は畳を上げてわらに包んで床の下に入れ、不思議そうに覗く私に美味しい納豆が出来るぞ~、と頭をなでて抱き上げたのだ。また庭でニワトリを飼い母にその世話を任せ、貝殻をカナズチで粉々にたたき草とヌカを混ぜ合わせて餌を作る母も、楽しげである。毎日コケコッコーの声で起こされ,生みたての玉子を取りに行きこつかれて泣いていた私に、「父ちゃん仕事に行くよ」と、『、ボォンー、ボォンー』の音で教えてくれた柱時計。あれから50年余り父の宝物『終戦後闇市でなけなしの金』で買った柱時計は、主を無くしいつの間にか影を潜め、バブル期に粗大ゴミに捨ててしまった。今、平成の不況にぶつかり父の生き方に重ね合わせ、後悔の念にかられている。二人の息子に恵まれたが私の生き様で、何を思い出として語ってくれるか?ささやかな期待で老後の青春をおおかしたいと思う。
天井と壁の際が、欄間のように激しく縦揺れした。これが母がよく言う大震災かとも思った。これで最期かとも思った。激震は、「ドスーン」という衝撃と音を残し終わった。
茶の間、家族は一つの炬燵の中だった。誰彼となく、何が起きたのかと板の間に出た。もう、足元の床板は落ち、縁側の雨戸は吹っ飛び、雨降る道路に晒されていた。黒い影の大型トラックが道路を塞いでいた。
「逃がすな!」
「警察に電話だ!」
咄嗟に兄弟が口々に、トラックを逃がすまいとして、闇の道路に向かって叫んだ。私も怒鳴った。
「バカヤロウ!」
居眠り運転だった。センターラインを越え、雨の路面をスリップするように反対車線を突っ切り、道路に面する我が家の廊下に突入。、運転手の咄嗟のハンドルの切り返しで、また道路に戻り、後部を縁側の角にぶっつけ、やっと止まった。
運良く家族はトラックの下に巻き込まれずにすんだ。そのまま直進したら、恐らく家族全員死んだだろう。本当に奇跡的な思いがした。あと数メートルのことだった。
台所の柱時計は、七時三十五分を指して止まっていた。その頃からゼンマイを巻いても、思うように時を刻むことがなかったが、いつしか暗い納戸に追いやられた。たまに「ボーン」と思い出したように鳴ってみせた。
やがて、この事故以来、我が家に立て続けにトラブルが起こり始める。その変調は事故が起こる前、柱時計が狂い始めた数年前、姉の早逝に始まったような気もする。
今はないあの柱時計の狂いは、今もって直せていない。九十歳になった母ひとり、あの事故のあった家でずっと背負い続けている。
母が言う、
「長生きすれば一杯悪いこともある」
ずっと家族を見守り続ける柱時計のようだ。
「父の証」山田 東加さんのエッセイ (11月のベストエッセイ)
「それじゃあな。」
そう言って父は家を出ました。
母と折り合いが悪く、離婚することになったのです。
「お父さんどこに行くの?」
弟が聞いても答える人は誰もいません。
私は父のうしろ姿を見つめながらポケットに入っている腕時計を握り締めました。
「いいか、よく聞け。お父さんはお母さんと別れることになった。どちらが悪いっていうんじゃない。たまたまそうなってしまったというだけだ。でも、間違えるんじゃないぞ。お父さんはお前も弟も、もちろんお母さんだって今でも大好きだよ。ただ今度からは少し遠くから見守るようになったんだ。」
いきなり私だけを呼んで、父は語りました。
「お前は長女だ。だからお父さんの代わりにお母さんと弟を支えてやってくれ。ほら、これがお父さんの代わりになる証だ。」
そして父はいつも身に着けていた、銀の文字盤に茶色の革ベルトが付いた腕時計を私に差し出しました。
幼かった私は父と母が別れるということがよくわかりませんでした。ただ「じゃあ誰がお父さんを支えるの?」と本当の意味がわかっているのかという感じに聞いてみると、父は苦笑いをし「お父さんは強いからいらないんだ。」と答えました。
あの後、こっそり見た父の頬を伝ったのは何だったのでしょうか。
あれから6年経ち、小学3年生だった私はもう高校1年生になりました。
父とは年に一度の年賀状でしか会えません。住所の書いていない年賀状は父の居場所すら教えてくれません。
ただ、あの日の時計が私の腕の中で一刻一刻と時を刻むごとに、私は貴方との繋がりを感じています。
その腕時計は今年で7年目になる。耳にあてると「チクチクチク」と、今でも何ら変わりない安らかな音を奏でている。その音と共に、温かな思いが私を包む。
「あっ時計がない」と気がついたのはその時だった。
7年前、私はとても大好きだった人から告白をうけた。新宿ではめずらしく人通りの少ない路地裏だった。私たちは何度も何度もこれ以上ないというくらいの愛の言葉を交わしていた。その時、ふと目にした私の腕には愛用していた時計がなかった。
「あっ時計が・・・」
華奢なデザインをしたその腕時計は、それまでにも何度か落としそうにはなっていたが実際に無くすことはなかった。気に入っていたのと、どこかで置き去りにされている腕時計の寂しい姿を想像すると、とても悲しかった。そんな私に気づいてか、彼は自分の腕から時計を外し、私の腕にそっとはめた。
「これからはこの時計が二人の時間を刻んでくれるね」
なんともキザな台詞だが、その時は彼の優しさに涙があふれんばかりだった。
その彼とは、今年で7年目の交際になる。
彼から貰った大きい腕時計も、順調に時を刻んでいる。
そしてこの先も、私たち二人の時を優しく見守ってくれることだろう。
腕時計が並ぶコーナーで彼女の視線が止まった。
表参道の洒落た店でのウィンドー・ショッピングは僕には退屈な時間だったが、彼女は何かに魅入られているようにショーケースの中を覗き込んでいる。
「何か気に入った?」
と尋ねると、視線を動かさずに彼女は「うん」と言った。
「この時計ね、友達なの。失恋して落込んでた時にね、自分で自分にプレゼントしたの。それから悲しい時もつらい時もずっと一緒だったの。だから、わたしにとってはこの時計は友達なの。」
と指差す右腕にはショーケースと同じ腕時計があった。
「あ、おんなじだ。」と僕が驚くと、彼女は振り返って微笑んだ。
知り合ったばかりの彼女と僕の距離は、この腕時計よりも近くなるのだろうか。再び、ショーケースに目を奪われている彼女の横顔を観ながら、彼女にちょっとだけ近くなった自分を僕は感じていた。
「「すぎおと」さんとチャイムの時計」東元 正臣さんのエッセイ
母が死んで、わたしは和歌山の実家を相続することになった。もとは魚問屋をしていた大きな家である。母は小さい頃この家に移ってきて以来、死ぬまでをこの家を出たことがなかった。姉が先にいい人を見つけて嫁いだために、跡取として婿養子を迎えたからである。わたしは18歳で大学に進学するためにこの家を出てすでに45年になっている。主の居なくなった家を整理していると、かつて父母が寝室としていた2階の床の間にあるもの入れから1台の古い時計が出てきた。それは丸みを帯びた凸型で木目の美しい時計である。この時計の文字盤には3個のネジまき穴があった。それぞれ時計動力用、時報用、チャイム用である。このチャイムは木製の箱によく共鳴して素晴らしいウエストミンスターメロディーを奏でたのを覚えている。
子どものころ、母はこの時計を「すぎおとのおじやん(おじいさん)の嫌った時計」と言ってよく話題にし、笑ったものである。すぎおとのおじやんとは落語家と言うよりトーク番組の名司会者、人気タレントの明石家さんまさんのおじいさんである。南紀で魚の干物を商い、後に奈良県に移ったというが、どういうわけか私の祖父と懇意であったのか、よく泊まっていたそうである。すぎおとさんもさんまさんに劣らぬ頭の回転のよさ、ユーモアのセンス、饒舌でみんなを楽しませてくれたようである。そのすぎおとさんを悩ませたのがウエストミンスターのチャイムが鳴る時計だった。15分ごとに1節、2節、3節とチャイムのメロディーが長くなり、1時間目にフルメロディーに時報が続くので、煩くて眠れないというわけである。客間の床の間に置かれたこの煩い時計の音を止めることが出来ず、さまざまな椿事があったことを聞かされた。私は家を出て以来、規制したときにすぎおとさんがさんまさんのおじいさんとのことを聞いたが、この時計にまつわる面白話のことは忘れていた。母が死んでそれらのエピソードを聞く機会を失ったいま、発見したその時計に記憶というものがあれば「明石家さんまさんのようだった」というすぎおとさんの思い出話を聞いてみたいものである。
学生時代アメリカへ旅行した時、ロスの空港でバッグを紛失してしまい、帰りのチケットまで売らなければならなくなってしまった。仕方なく日本人街のレストランで給仕をして生活していた時、ゲン爺に出会ったのである。彼の家にスクールボーイとして住まわせてもらった。その10ヶ月の間に多少の旅費も出来、旅行の準備も整った5月の末、ゲン爺がテラスで昔話をしてくれた。サンフランシスコに着いた時の話、米屋のバイトをして密輸米を隠した話やバークレーの大学での話などである。なにかその話をしているときのゲン爺の目には若い頃の輝きが残っていた。その時いつも手にはめていた腕時計をはずし、米屋の主人から貰って大切にしていたものだと言い、「使ってくれ」とプレセントされた。それはブローバーの手巻きの、ごついと言う感じのする腕時計だった。時計を持っていなかった私には貴重なプレセントだった。それから2週間後ヨーロッパへ渡り、予定より2年遅れて日本に帰る途中、ロスに立ち寄り、ゲン爺に再会した。ゲン爺は涙ぐみながら、「良く無事で帰ってきたな」と言い、日本に帰って、また出て来い。と言って別れた。その時、時計のお礼を言うと、戦争中リザベイションの中でその時計を盗られ取り戻した話などしてくれた。ゲン爺にとって大切な人生の時計だったのを知り、胸に熱いものを感じた。大切にしなければならないと思っている。今でも腕にはめていると、傍にゲン爺がいるようで、テラスで昔話をしてくれた時の輝いた目で語りかけてくるようで、ゲン爺のことが懐かしく思い出される。
「両親の愛の証拠(あかし)の腕時計、再び・・・」内田 純近さんのエッセイ
私の左腕で、グランド・セイコーが小さく囁き続けている。亡き父自慢の逸品である。夫をこよなく愛した母が、肌身放さず身につけていた時計でもある。几帳面な父は、毎日定刻、決まった回数、リューズを巻くのを日課にしていた。入院中も服薬の時間を見るために、片時も腕から外したことがなかった。臨終を覚悟した日、「有難う。腕時計を外してくれ、ユックリ眠るよ」、その夜に他界した明治生まれの父。夫の死を理解出来なかった母は、止まったままの腕時計を、自慢気に腕にしていたものだ。止まった時計のリューズを巻くために、手首から放そうとしたら、凄い形相で睨まれたものである。この時計から愛する人の愛撫を受けていたのだろう。夫を追うように静かに他界した母の腕から、時計を外すときに、悲しみが突然溢れてきて、涙がとまらなかったものだ。「お母さん、時のない天国で、愛する人と暮らすのだから、腕時計は外します。二人が生きた証拠(あかし)として」
子供を育てるための貧しい生活の中の、唯一つの贅沢品、グランドセイコー・・父自慢の腕時計。夫婦愛を貫いた大和撫子に、愛する人の愛撫を伝えたグランド・セイコー・・母自慢の腕時計。
私の左腕で囁き続けてくれ・・グランド・セイコーよ。
・・命の大切さを。夫婦愛の大切さを。親孝行の大切さを。・・
両親の愛情を伝える形見の腕時計に、再び命を吹き込むために、セイコー福岡支店に修理を頼んだら、見事に息を吹き返しました。これからは不肖の息子が大切にします。懺悔の意をこめて。
現在、アプローチしたい男性がいる女性へ。
初めてのデートのでは、腕時計をしないで出かけましょう。
効果1:時間を気にせずにデートを思い切り楽しめる。また、女性が時間を気にしている様子がないということは、男性に安心感を与えられるものです。
効果2:彼に「いま何時?」と聞くきっかけができる。腕時計を見せてもらうために手首に触れれば、スキンシップにもなります。
効果3:「時計持っていないの?」と、腕時計をプレゼントしてもらえるかもしれない。
時間が知りたくなったらケータイでチェックすれば済むことです。
彼と仲良くなれますよ。ぜひ、お試しあれ。
銀色のミッキーマウスの耳の部分のような形をしたネジを今でも覚えています。
小さい頃、柱にかけてあった振り子時計。古いアパートだったので少し傾いていたのかもしれません。たまに止まっていました。それに気付くたびに、父に支えられながらネジを回すのが好きでした。
良くは覚えていないのですが、アパート取り壊される事になり、立ち退きをした際にそのまま残してきたようです。
ボーン・ボーン・・・と時を告げる音も懐かしい。遊び疲れて眠る私と違い、夜中の音は親達にはうるさかった事でしょうが…。
何かの拍子に思い出すたびに、今でも懐かしさと切なさと感動が入り混じったような気分になります。
ずっとなくしたくない小さな宝物のような思い出です。
一番古い思い出の中の小さな私は、夕日が差し込む部屋で一人で食事をしている。両親は共働きだったので祖母がそばにいるはずだが記憶にない。
6時を指す針、掛け時計が低く響き6回鳴る・・・。夕日が傾くまでが私の小さな一日だった。それからいつも電車で行くデパートがすぐ窓の外に見えるマンションに引っ越した。相変らず私は一人で遊んでいた。日曜日の昼過ぎ、テレビはいつもゴルフを映していた。父親が吸うタバコの煙の充満した臭いが嫌で私はマンションのエントランスで遊んだ。私の部屋から聞こえる3時を指す鳩時計の音が母親の帰り時刻を教えてくれた。綺麗にブロウされた髪型をして帰ってくる母親はいつも一瞬、違う人に思えた。朝起きて皺くちゃの襟が黒ずんでいるワイシャツ姿の父親がソファーで寝ている姿をたまに見かけるようになったのもその頃だった。放課後、住宅街の中の暗い公園で門限までの時間まで二人して肩を寄せ合いベンチに座っていた冬、あんなに寒い夜だったのに話す言葉を必死で捜していた。公園の表情のない丸い時計は9時4
5分だった。あの日ほど1分が打つ打刻が30分に加算されることを祈った事はない。再婚した父親と久しぶりに喫茶店で会うことがあった。深いシワが目元に入ったくしゃくしゃの父親の顔と向かいあって座った。どこにも見当たらない気がするその腕にはめていた時計は手の油にまみれて変色したあの日の腕時計だった。遠いあの日、ゴツゴツした時計の金具が抱き上げられる時にあたって痛かった。公園での軽いひとときがやんわりと思い出された。胸が締め付けられる気持ちになる思い出の中には必ず時間と時計が交差している。悲しくて泣く時も死にたいと思った時もお腹は空き、時計も気にする。そんな自分がとても可笑しい。でも、なんでか私はどうしても、大切な人がいて何か贈り物をしたいと思う時はのぞいてしまうのだ。ついつい、時計が沢山並んでいるお店に足が勝手に動いてしまうのだ。
ある日、実家の押入れを整理していると、子供の頃に遊んでいたオモチャが、ぎっしりと詰まった段ボール箱の中に、傷だらけのディズニーウオッチが転がっているのを発見した。文字盤にドナルドダックが描かれているそれは、ぼくが小学5年生くらいの時に、両親から初めて買ってもらった腕時計に違いなかった。
いったい、どういういきさつで買ってもらったのか、はたまた、買ってもらってからどれくらいの期間使用していたのか、今となってはまったく思い出せなかったが、5歳になる娘に時計の読み方を教える教材代わりにでも使えるかなとふと思い、自宅に持ち帰った。
夜、家族が寝静まってから、ぼくはその腕時計のことを思い出し、上着のポケットから取り出した。そういえば手巻きだったかも知れないとふと気付き、ネジを巻いてみた。こんな安物の時計ではあったけど、耳に押し当てると、それはクオーツ時計とは違う、チッチッチッチッ……という小気味よい連続音を発しながら動いた。そういえば、昔の腕時計ってこういう音だったよなと、なんだか無性に懐かしさが込み上げてきた。
ぼくは何十年ぶりかでその腕時計を腕に巻いてみた。その途端、この腕時計をはめながら、同級生とよく野球や自転車遊びをしていた少年時代のことがにわかに思い出されてきた。そうか、あの頃にこの腕時計を使っていたんだった……と、忘れかけていた子供の頃の記憶が、次第に蘇ってくるのを意識した。それと共に、日頃の仕事の疲れやストレスが、なんだか少しだけ癒されていくような気がした。
ネジを巻き忘れるとすぐに止まってしまうし、文字盤の図柄が図柄だけにちょっと気恥ずかしくもあるけれど、平凡な毎日にあって、もう一度この腕時計を使って非日常的な気分に浸ってみるのも悪くないかなと、ぼくは思った。そうして、
「いつか腕時計を使う時が来るまで、ちょっとだけ借りるね」
と、娘の寝顔に向かってささやいてから、眠りについた。
「ゴウ、ヨン、サン、ニイ、イチ。ほーら、ピッタリだ」
とお父さんは自分の腕時計が一秒もちがわないことを毎日私たち子供にじまんしました。朝ご飯をたべるときNHKの6時50分の天気予報のあとテレビの時計と自分の時計があっていることを確認することがお父さんの儀式でした。
私と妹が高校生になって「またやってるよ」とバカにされても、私が結婚することになって家での最後の朝食の日も欠かしませんでした。
そんなお父さんの時計がついに壊れて動かなくなってしまいました。お父さん以上に私と妹はショックをうけました。
時計屋さんに持っていっても古くて部品がないとのこと。そこで私と妹でプレゼントすることにしました。
お父さんの希望は前の時計となるべく同じように。セイコー社のもの。シルバーのベルト、シルバーの文字盤。日づけがわかること。さすがに30年前と同じデザインのものはありませんでしたが素敵な時計がみつかりました。
お父さんは早速新しい時計をつけて
「ゴウ、ヨン、サン、ニイ、イチ。ほーらぴったりだ」
と確認しています。孫に「もういいよ~、わかったよ」と言われながら。
彼女に貰った腕時計は渋い銀色のベゼルにグレーの文字盤。すごく薄くてスマートで、今までごくごく普通の腕時計しかしていなかった僕は最高に嬉しかった。
初めて着けた日。会社のみんなにさりげなく披露した。
「お前の顔には合わんぞ。」
「ホストが着けるみたい。」
「それは俺にこそふさわしい。」
とにかく僕には似合わないという評価だ。悔しいのもあったが、そんな評価を彼女に言えるものではない。どう?みんなの反応は?って聞かれても、
「いい時計って言われたよ。」
そう言って苦笑いしていた。
それでもお気に入りはお気に入り。ずーっと左手首にはその時計。いつのまにか「彼女」は「妻」に変わり、今では既に「お母さん」だ。
ある日職場で後輩が、
「いい時計ですね。よく似合ってるし。高いんですか。」
そう僕に言いやがった。思わず僕は彼に手を差し伸べた。がっちり握手を交わしたが、彼は「何故に握手を?」と戸惑い気味。
最早左腕の一部と化した我が腕時計を眺めながら、僕は久しぶりに妻と時計の話題。後輩のコメントを話しながら、
「俺も30半ばにしてちょっと垢抜けたかな?」
調子にのってそう言うと、
「年とっただけよ。全然顔に似合ってないし。」
何てこった!プレゼントしてくれた張本人がそう思っていたなんて・・・!意気消沈。
でもボソッと一言。
「時計の方がお父さんに馴染んだんじゃない?」
その一言がせめてもの救い。少し気を取り戻して、複雑な気分ではあるが、左手首の友人と握手した。
ひんやりとした手触りと、未だに傷の無いガラス面。
『まあお前に合わせてやってるのさ。』
そう彼に言われた気がして僕はまたしても苦笑いなのだった。
腕時計を持っていなかった私に、主人が初めて腕時計を買ってくれた。『学校に行くのに時間が分からないと不便だろ?』と。結婚した頃私はまだ学生で、いつも時間を携帯とかで確認していたけれど、授業中には見る事できないからその言葉にひどく感激したのを覚えている。丁度読んでいたファッション雑誌に載っていたブランド物の腕時計。アナログで数字とか一切入ってなかったけれど、そのシンプルさが主人の性格を現しているようで、だから余計に主人が身近に感じた。左腕にいつもつけて、電車の中で、授業中に、お昼休みに、そして家で主人の帰りを待つ時にその時計は私と共にある。ある日突然主人が亡くなった夜も、身につけていた。主人の時間は30年を迎える前に止まってしまったけれど、私の時計は今もまだ動き続けている。私の命と一緒に、主人がくれた時計が一緒に時を刻み続けている。時間を確認する度に、一緒に歩いてきた時を思い出し、これから歩いていく一人だけの道に主人の面影を見る。ずっといつまでも、私はこの時計だけをつけているだろう。
「僕は、時計は円、文字は1,2,3のアラビア数字、そして秒針があるものと決めているんだ」二人でその通りの時計を買いました。居間の壁でカチカチカチと秒針が時を刻み始めました。
夫は科学を愛する人でした。「少し」「かなり」より「あと1日」「まる3年」という表現を好みました。
「もうすぐよ」と夕食の支度をする私に「すぐって何分?」と聞き返します。「そうねぇ、あと15分」と答えると「アンタの15分は20分」と笑います。「今何時?」と聞くと「今ヒマンジ」と返します。具体的なイメージを共有することが大事なのだそうです。確かに私は主婦太り。
「時間を秒で考えたことある?」と聞いてきます。「1分は60秒だから1時間は3600秒、1,2,3と8万数えたら1日が終わって、人生80年寝ずに数えて25億・・」電卓をたたきながら私は「人生って長いの?短いの?」と迷います。
「私には見えて、あなたには見えない霊の世界はナンセンス。科学はすばらしい。誰にも平等。証明できなければ無と同じ」と言う夫が死後の魂だけは信じているのです。「魂は肉体が生み出すもの。だから人間はすばらしい。死んだら無」と考える私に「アンタは僕よりずっとサイエンティストだ」と寂しげでした。
半分まで数えて、夫はこの世を去りました。翌日も、次の日も、時計の針はその時刻を指したままでした。
「ほら、僕の魂、見えるでしょ」
『ゴォーン ゴォーン。」夜になるとやけに大きく聞こえるその音が嫌いでした。一つの音符では表せないような音。重く歴史的な渋さを感じさせるそれが、幼い頃の私には恐怖だったのです。
その時計は、柱時計で父が毎朝決まった時間に双葉のような形の鍵でねじを回していました。一日忘れてしまうと止ってしまうのです。けれど、忘れなくても決まって翌日には数分遅れていました。そんな柱時計。私は、役に立たないし、音への恐怖もあったので早く捨ててしまえばいいと思っていました。そんな私の気持ちなど全く知らずに、父は毎朝の仕事を続け、時には埃を乾いたタオルで拭いてあげました。とてもいとおしそうに ・・・。
ある年の瀬。大掃除中、父がいつもより丁寧にあの柱時計の掃除をしていました。下にぶら下がっていて、いつも揺れている振り子。金色に光るそれは、少し錆が入ってきていました。
「もう古いから捨てちゃえば?」そう言った私に、父が静かに話し始めました。手を休めることなく。「これはね、結婚する時に遠くへ嫁に来るお母さんにおじいちゃんが託した柱時計なんだよ。おじいちゃんは、天国へ行ってしまったけど、この時計は、おじいちゃんそのものなんだ。」
あれから三十数年。もう動かなくなったその時計は今でも父の家のあの場所に掛けてあります。おじいちゃん時計です。
大学時代、とても好きだった先輩がいました。彼女がいるのを承知で卒業の時に告白しましたが、あえなく敗退。それでも、家が近くて駅で時々見かけることがあり、なんとなく彼のことをふっきれませんでした。ある朝駅で声をかけられ、お茶に誘われました。驚きながらも期待していましたが、話は、海外に勤務することになった、ということでした。私はただ泣かないようにうつむいていました。
その時視界に入ってきた彼のブランド物のおしゃれな時計が印象に残って、アルバイトをしまくってペアの女性ものを買いました。私の服装には似つかわしくない華奢な時計でしたが、買ったという達成感に満足しました。
さらに数ヵ月後、バイト先の喫茶店に彼がたまたま来ました。一時帰国しているんだ、と説明してくれる彼に水を出すと、ちらっと時計を見られた気がして、恥ずかしさに火を吹きそうになりました。彼は、悟ったのか、「ごめんね、婚約するんだ」と一言。
以来すっかり落ち込んでいた私でしたが、あるときバイト仲間の一人が「自分にプレゼント買ったんだ」と腕時計を見せびらかしてきました。私のものとペアの時計でした。決して安くはない時計なのに「一緒に時間を刻めるようにさ」という彼に吹き出してしまい、「ばかみたい」と言いながら、自分もばかなことをしていたな、と実感。すべて吹っきれた瞬間でした。
彼とは改めてカジュアルな時計を送り合い、ときにカジュアルに、ときにオシャレに、「一緒の時間」を刻んでいます。
その夜、家族が眠ったのを確かめると私はそっと起きました。もう一度、見たいという気持ちを抑えきれなかったのです。それは、祖母から母、そして私の中学進級祝いに譲られた小さな腕時計でした。僅かに遅れるのが、機関士であった父にはがまんできないらしく、ラジオの時報に合わせてよく調節をしてくれました ですからその日もなにげなくのぞいた父の手元に、私は吸い寄せられてしまったのです。
やがて、顔を上げた私を見て父がゆっくりと言いました。
「これは生きものだから、もう見てはだめだよ」と。
それからというもの、私の鼓動と同じように小さな音を立てているその時計の裏側が気になってしようがなかったのです。でもふたはピッタリと合わさっています。あれこれさわっているうちにかすかな窪みを見つけて、そこに父の細いナイフをあてるとじわりと動きました。
見ると、外国映画にあるような遊園地の観覧車が小気味よく回っていて、そばには赤い帽子の小人達が順番を待っているようでした。隣では、シーソーにのって歌をうたっている子どもがいるではありませんか。私の腕時計には生きた小人達がいたのです。
その日からいく度、裏側をのぞいたことでしょう。その度に、自分のしていることが、いつか彼らを傷つけるだろうと怖かっただから、もう決して開けないでおこうと何度も誓ったのですが、蓋を開ける瞬間の心のときめきにはどうしても勝てなかった。
ある日のこと、小人達の歌声が急に聞こえなくなり針も止ってしまったのです。思い切って開けてみると、あたりはシーンと静まりどこにも元気に飛び跳ねる小人達の姿はありませんでした
そして、50年の時間が過ぎてしまいました。
私の忘れない腕時計は、43年前中学の入学祝いに、初めて買ってもらったものだ。
当時、腕時計をしている中学生は数えるほどだったが、祖父が、溺愛している孫のたっての希望で、散財してくれたのだ。
丸い文字盤に付いている、真っ赤なベルトの色が晴れがましかった。
自分の時間をいつでも確かめられることは、大人に大きく近づいたようで誇らしい思いがした。
あれは、入学して半年が経った頃の、体育の授業の時だったと思う。
財布や腕時計のような貴重品は、必ずその時見学することになっていた生徒に預けることになっていた。私もそれに従ったのだが、授業が終わってみると、私の時計だけが見あたらない。
クラス中が、大騒ぎになった。
次の授業を知らせるチャイムがなっても、先生が深刻な顔で時計を預けていたクラスメイトと、話していたことを覚えている。
「確かにここに、置いておいたのです。」泣きそうな顔で、答えていた彼女の顔も忘れられない。
どう考えても、意図的に誰かが持っていったとしか考えられないような状況だった。
預けなければよかった。歯ぎしりしたいような後悔と腹立たしさを、でもそのクラスメイトにぶつけるわけにはいかなかった。
彼女も、在る意味被害者なのだ。
結局、腕時計は見つからずじまいだった。
大切なものを失った悲しみは、なかなか消えなかったけれど、諦めが付いたのは、しばらくしてそのことを知った祖父の一言を聞いてからだ。
「それ程までして欲しかった子がいたのだ。あげたと思えばいいじゃないか。」思いがけない言葉が、私のもやもやを払拭した。
私にとって初めての、とても短いえにしの腕時計は、祖父の心の広さを改めて確認できた、忘れられないものとなった。
学生時代は、よく腕時計をなくした。なくしてしまうのは、決まって部活中だった。例えば、腕時計をしたまま走って、バンドの内側に汗をかき、気持ち悪くなってはずし、そのままなくしたり、腹筋中に腕時計が地面に当たって文字盤が傷つくのではずし、そのままなくしたり。こんなふうに腕時計をなくしてしまうことが多かったので、そのうちに腕時計をしない習慣がついてしまった。
しかし、就職してから、腕時計は必需品になった。というのも、大手外食チェーン店に就職たことで、一分、一秒でも早く、お客様に商品を提供することが仕事になったからである。
お客様が並ばれてから、注文を伺い、注文を取り揃え、商品を提供するまでの時間が、全て秒単位で決まっていた。そこで、上司に腕時計を買うように言われた。店内に掛け時計はあるが、顔を少し上げないと見えず、その顔を上げるという動作がロスタイムになっているからと。
その為、久し振りに腕時計を購入した。デジタル表示で、ストップウォッチ機能がついた腕時計である。おかげで顔を上げることなく時間がすぐ分かり、お客様の注文を伺ってから何秒経ったか等を計測することにも大変役立った。
一分一秒の時間と戦った4年間。腕時計は私の良き相棒であり、なくてはならない存在になった。
現在は転職してしまったのだが、腕時計で時間を常に確認してしまう癖はまだ残っている。それ以上に、腕時計をつけていなかったら、左手が軽く感じられてしまい、落ち着かないのである。
20年前に銀座で買った腕時計を今でも愛用している。セイコードルチェ角型金色メッキの1980年モノである。故障もなく、唯、もくもくと正確な時を刻みつづける。
10角にカットされたデザインが妙に気に入った。“DOLCE〝はイタリア語で、日本語に訳すと「優美」、名前も実にお洒落である。恋人と呼ぶには少々てれるが、もっと内容が知りたいので、東向島にあるセイコー時計資料館を訪ねた。週末の土曜日午後3時から4時までの1時間、駆け足の観覧だった。入場は無料で、予約制とのことだった。先客のカップル1組が案内人の説明に耳をかたむけていた。予め私は、DOLCEの研究目的で電話を入れておいたので、すぐ2階の展示室へ案内された。そこには創業から現代にまでの歴史が一目で分かるように工夫されており、特筆すべきことは、あの日本中が感動した東京オリンピック成功の陰に、超高水準技術のすべてを全世界にアピールできた功績は、社史の輝かしい一頁に刻印されていた。一瞬当時の興奮が甦る。お目当てのものが陳列してある硝子ケースを覗き込むと「お客様、もうお気付きですか、一般のものはただ並べてあるだけ、この品に関しては、ほら、台を一段高くしてあります・・・。」特別扱いの高級品であることが、あん黙の内に理解できた。なんだか自分までが、昔のお殿様待遇になったような気持ちにさせられ、いいものを持つと心が豊かになり、人生が明るく楽しくなる。時計に教えられた人生哲学だった。
セイコーでいちばん人気のあるものは、何と言っても“グランド、セイコー〝だろう。世界の一流品と折り紙をつけられても不思議ではない。精度の高さにおいて、スイスの高級品を抜いて世界の頂点に立った。実力のある男好みのする”メカ〝と評判である。隠れたファンも多いのではないでしょうか。ある雑誌に映画監督S氏の写真が載った。腕に巻かれているものは“G、S〝男の渋さが滲みでていた。
(注)「思い出の時計エッセイ募集」に送っていただいたエッセイの著作権は、セイコーインスツルメンツ株式会社に帰属します。
予めご了承下さい。