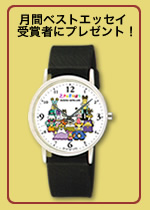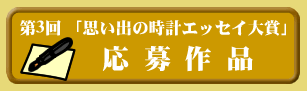 ������� 2003�N1��10���`2003�N12��31�� |
|
|
|
|
�@ |
|
2003�N�̍�i
1-2���@3���@4���@5���@6���@7���@8���@9���@10���@11���@12��
![]() 6���̍�i(19��i)
6���̍�i(19��i)
�u���v���R�@�b������̃G�b�Z�C
�u���Ԃ̌��v�ێR�@�Ђ�q����̃G�b�Z�C
�u���v�̎~�܂���v��@�\�q����̃G�b�Z�C
�u���Ƃ��Ȃ��̓����b�v�x�c�@�m������̃G�b�Z�C
�u����҂���̔����v�v���c�@���q����̃G�b�Z�C
�u�����v�A�\�N��̐^���v�c���@������̃G�b�Z�C
�u�d���f���v����@�^�m�q����̃G�b�Z�C
�u�ڊo���v�ƈꏏ�Ɋ撣�����Ό��v�g�c�@�~�q����̃G�b�Z�C
�u�����v�͉ƍ�����H�v�z�܁@�x�q����̃G�b�Z�C (6���̃x�X�g�G�b�Z�C)
�u���߂Ď��v���K�������v�O�J�@��q����̃G�b�Z�C
�u���������̐Ԃ��r���v�v��@�^�R������̃G�b�Z�C
�u�c���̘r���v�v�㓡����̃G�b�Z�C
�u�W���N�X�̘r���v�v�{��@�a�b����̃G�b�Z�C
�u�������Ԃ�@�߂��āv�с@�����炳��̃G�b�Z�C (6���̃x�X�g�G�b�Z�C)
�u�C���������v�vnocho7����̃G�b�Z�C
�u�����������v�v�������@�悤�����낤����̃G�b�Z�C
�u�x���v���@�h�_����̃G�b�Z�C
�b�j�̉��ŁA�C�������B���ڂŌ��ƁA��p�O�Ɍ����Ă��������ł͂Ȃ��炵���B�u�����Ă�v���āA�ڂ���m�F�ł����u�ԁA�܂��b�j�̉������������B�w���̉��̓C�����x�B
��������̎�p�������B�����A�����ς��͎c�����B�ł��A�����Ɛ����Ƃ���ɂ͒����ǁi�h���[���F�̉t�r�o�ǁj�������āA�E��͓_�H�ŌŒ肳��Ă���B�������܂��܂������Ă���炵���A�����������Ȃ��B
�U�O�b�ɂP��A�b�j�͎��v�̕\�ʂ̂ǂ����ɁA�K�V�b�Ƃ������B���ƁA�P�Q�b�ɂP��A���Ԃ�ׂ̕����̐l�H�ċz��̖c��݂��ڂމ�������B�ǂ������A�J���ɐG��B�ł��A�g�̂������Ȃ��̂�����A�䖝���邵���Ȃ��B�ł��A�䖝�ł��Ȃ��B���������Ȃ�����A�N�ɂ��`���炦�Ȃ��B���̕����ɂ́A�����Ȃ��B���̑̏L���A��L���̏L�ɂȂ��āA�����ށB�K�V�b�A�v�[�E�v�V���E�B�u���[�A�������������Ȃ��Ă����́B������悤�ɂȂ�����A��ɂ��̎��v�A�Ԃ��Ă��B�l�H�ċz������v�B
���ꂩ��A�Q����ɁA���͌��X�̕a���ɖ߂����B���ēf�������ŁA�C���C�������B���̕����ɂ������A�䕗���s�����炵���B
���ꂩ��A�S�N��A���x�͉E������̑S�E��p�̂��߂ɁA�����a���ɂ����B�u��p�̌�A���̕��������̓C���ł��B���̎��v���C���ł��v���Č������B�ł��A�������̑��̂Ȃ������́A�@�ގ��ɂȂ��Ă����B�����āA���̎��v�����łɁA�Ȃ������B
���x�́A���̂�����������B�o�����ʂōĎ�p���āA�厡�オ�h�^�o�^���Ă�̂𑼐l���̂悤�Ɏv���Ȃ���A���̂��Ȃ����v�����Ă����B���t���ς�낤�Ƃ��Ă����B�ł��A�������������B���̂�����ɂ́A���v���Ȃ�������������Ȃ��B
���ꂩ��A�܂��Q�N�o���āA�����[�͊ۂV�N�A�E���͊ۂR�N�ڂɓ������B���̎��Ԃ́A�����Ǝ�������ł���B
�K�V�b�A�v�[�E�v�V���[�B���́A���̖����A��ԍŏ��ɕ��������A�b�j�̉��B
�u���Ԃ̌��v�ێR�@�Ђ�q����̃G�b�Z�C
���̂̂���Ȃ��u���v�ɁA��������Ă��閲�������B
�ڊo�߂āu�����A���ꂾ�v�ƁA�C�Â����̂́A�킪�Ƃ̒����v�ł���B���炭�A���̎��v�̕b�j�����Ȃ��特���Ă���ƁA1�b�Ԃ�2�x�u�J�`�J�`�v�ƖZ�������ɓ����Ă���B�v���Ζ��������A���̎��ɍ��킹�āA���������Ɛl���𑗂��Ă����̂ł���B
�Ƃɂ����A���v��ւ������Ǝv���A�X�ɏo�������B���܂��܂Ȏ��v���Ă���B���͑������Ƃ��āA�b�j��1�b���Ƃ�1�x�����������ƁA�������L����āA���₷�����ƁA�Ȃǂ���ɑI�ʂ��Ă���ƁA�ڂɂƂ܂����̂��u�U��q���v�v�ł���B
�����q���̂���A���R���P�ʼnƂ��Ă��ꂽ�B�_�Ƃ��c��ł����c��̉Ƃ�2�N���A��炵�Ă����Ƃ��̂��ƁB�Â��Ȗ�ɁA�U��q�̉����u�R�`�R�`�v�Ǝ��ɐS�n�悭�������A���������L������݂��������B
���̒��A������A�X�s�[�h����ɂȂ����A�Ƃ͂����A�������ނ̂܂ŁA�C���C���Ɛi�ޕK�v�͂Ȃ��Ǝv���B1����60�b�A1���́A24���Ԃɕς��͂Ȃ��̂ł���B
���������A���̎��v�����߁A���܂Ő��b�ɂȂ��������v�ƌ�サ�Ă�������B���E�ɂ�ꓮ���U��q���A���ɂ����������Ȃ��ŁA������肵���C���ŁA�߂��Ȃ����ƁA�����Ă���悤�Ɋ������B
�u���v�̎~�܂���v��@�\�q����̃G�b�Z�C
�ڂ��̉Ƃł͋��Ԃ����v�̕����ƌĂ�ł���B�����̎�͑傫�Ȑ����̍��Ԃ��̊ێ��v�Ƃ���������B���N�����\�N���݂�Ȃ����������ė͋���������Ă��ꂽ�ڂ��̉Ƃ̑�ȑ�ȕB
�u�n�b�n�b�n�b�n�b�v���A�����������͂ڂ��̖ڂ̑O�Ől�̉��{���ċz�����āA����ł�����f���o���Ȃ��ŁA��C�l�`�̂悤�ɖc��オ���ĉ�������Ă���B�J���҂̊X�E���B���\�N���O�ɂ��������Ɠ�l�ł��̊X�ɂ���Ă��������������͎��ɕ������œ������B�����h�u�l�Y�~�F�̍�ƕ��ƍ�ƖX�łɂ��ɂ����Ȃ�����̍H��X���������ЂƂ�ŕ�������Ďd��������Ă����B���m��ʓy�n�Ŏ����̋��ꏊ�������邽�߂ɉ����l�����A�����^�킸�ɐ����Ă����B�����o������Ƃ��Ɋێ��v�Ɏ�����킹�Ă����̂͑O�ɐi�ޗE�C�����肢���Ă����ˁB����Ȃ�����������傫�ȉ�Ђ̐l�����́u�I���W�v�ƌĂB�i�C���ǂ��Ȃ��Ă����������͑傫�ȉƂ����Ă��B�������͂�ɂ͕K���ƂɋA���Ă��āA�䏊����͂����������̑�D���ȃl�M����̗��Ă��̓����Ƃ��������̖��邢�����������B�ˑR�����������ł����������͂ЂƂ�ڂ����ɂȂ����B�ڂ��͕��d�̑O�ɍ����Ăۂ�ۂ�傫�ȗ܂𗬂��Ă�������������������������B���ꂩ�炨���������͂悭���s�ɏo������悤�ɂȂ����B���j�̗[���ɏo�ē��j�ɋA���Ă��邨�����������ڂ��͉w�܂Ō}���ɍs�����B�傫�ȃ����b�N��w�����ďΊ�ʼn��D������o�Ă��邨���������Ƃڂ��͎���Ȃ��ʼnƂɋA�����B���̍K���Ȏ��Ԃ��ڂ��͖Y��Ȃ��B
�ڂ��͂����������̎���������B����������������Ԃ��Ă��ꂽ�B���̂Ƃ��Ɠ����傫�Ȏ�B�u����������B�����s���ȁB�����������v�����������̎��v�͂��������~�܂�B
�u���Ƃ��Ȃ��̓����b�v�x�c�@�m������̃G�b�Z�C
�˂��A���ڂ��Ă�H���Ƃ��Ȃ������߂ďo��������̂��ƁB
���̒a�����̓���������ˁH
���Ȃ��͗��s��G-shock����Ȃ���C-shock��������ǁc
�{����߂��݂����Ȃ����������̊���̑S�Ă�m���Ă���B
���Ȃ��̂������Ŏ��͐F��Ȑl�ƒ��ǂ��Ȃꂽ��I
���Ȃ����g���炩���Ă�����ŕs����������������Ȃ����ǁA���͂��Ȃ��Ƃ���Ċy���������B
���Ȃ��͂������ˁI���݂����ŊF�̏Ί�������o���Ă�B
�������Ȃ��̂悤�ɂȂ肽���Ȃ��B
�˂��A�v�X�ɎU�����悤���B
��̉��̂�т�Ɓc
���̎��ɂ͎��ɂ�������ЂƂ�����Ƃ����Ȃ��B
����I��Ɏ~�܂�����C������I
���`���Ƒ҂��Ă邩��ˁB
��l�Ŏ���������ł������B���ꂩ��������Ɓc
�u����҂���̔����v�v���c�@���q����̃G�b�Z�C
���Ƃ̋߂��ɗc�����ʂ��Ă����f�Ï����������B�D�������Ȃ���������ƍ��̋Ȃ�����������̘V�v�w����l�ł���Ă��������Ȑf�Ï��������B���ƌZ�͕��ׂ��Ђ��ƕ�ɘA����Ă悭�s�������̂��B����҂���ɍs���̂͂ƂĂ�����������������y���݂ɂ��Ă��������������B�f�@���Ɋ|���Ă��锵���v�ɉ�鎖���B�f�@���ɓ����Ĉ֎q�ɍ���Ɛ搶�̓��z���ɔ����v��������B�^���ǂ���Δ�������������|�b�|�[�Ɩ��Ȃ��炻�̂��킢���p�������Ă����B���̈�u���c�����ɂƂ��Ă͂��܂�Ȃ������u�Ԃ������B�������Ȃ����̂ق����������ꂽ���́u��������I�����͔����o�Ă��Ă��ꂽ�I�v�ƐS�̒��ŋ��B���˂̎��͂����Ƃ��̔����v�����߂āu�������͉����Ă�낤�E�E�v�ƍl���Ȃ��玩���Ȃ�ɋC�����炵�Ă����B
�V�[���Ƃ����ْ�����f�@���̒��ł��̔����v���������̐S��a�܂��Ă��ꂽ�B���ɂƂ��Ă��̔����v�͓��ꂾ�����B���v�������Ƌ߂��Ō��Ă݂����A���̑��̒���`���Ă݂����A��������Ȃ��Ƃ��v���Ȃ��猩�߂Ă����B���v���Ƃ��̔����v���f�@���ɂ������͎̂q���B��a�܂��悤�Ƃ����搶�̗D�����������̂����m��Ȃ��B���ꂩ��R�O�N�߂��o�����͂��v�w���S���Ȃ�ꑧ�q���ʂ̏ꏊ�ł���җl�����Ă���Ƃ��B�������̐f�Ï��͍��������̂܂܂炵���B���͔N�ɐ������Ƃɖ߂�Ȃ������̋߂���ʂ�x�ɐf�Ï��ł̂����Ƃ��v���o���B�搶�̗D������A���̋Ȃ�����������̒��˂��������p�����������������ƁA�傫�Ȓ��˂ɋ����̂��܂苃�������ƁA�����Ď��̑�D�����������̔����v�̂��ƁB�����������獡�ł��f�@���Ɋ|�������܂܂Ȃ̂��낤���ƂӂƎv�����B
�u�����v�A�\�N��̐^���v�c���@������̃G�b�Z�C
�킪�Ƃ̒��j�~�Y�L�N�́A��˂̍����炵����Ɂu�W���A���E�}���}�E�{�[���{�[���v�Ɠ�̌��t����悤�ɂȂ����B�Ȃ̂��Ƃ��u�}���}�v�Ƃ��A�����u���������v�ƌ������x�̍��ł���B���R�{�l�Ɂu�~�[�����A�Ȃ��ɁH�v�ƕ����Ă��A�������Ԃ��Ă���͂����Ȃ��B�Ƃ��ɍȂ́u�}���}�v�Ƃ������t�������Ă��邩��A�����ɉ�����i���悤�Ƃ��Ă���̂��낤�ƋC�ɂ��Ă����B
�䂪���������̂́A���ꂩ��Ȃ�Ə\�N���o���Ă���ł���B�[�H��̒c���ŁA�u���₢�⎞�̌o�̂͑������̂��ˁB���̃~�Y�L�N���A�����������w�����v�ȂǂƁA�̂��v���o���Ă����B
�u�Ƃ���ŁA���̃W���A���E�}���}�E�{�[���{�[�����ĉ��������낤�ˁH�v�ƓƂ茾�̂悤�ɂԂ₭�ƁA�u�����A����A���v����B�����������̉Ƃɂ��邶��Ȃ��B�\�Ƃ��Ƀ{�[���{�[�����Ė��v�ƁA�ނ͂��肰�Ȃ��������̂ł���B
�u���`�A�~�[�����A�o���Ă���́I�v
�Ȃ������đ吺���グ���B
���ɂ��Ďv���A�u�{�[���{�[���v�ƌ�������^����Ɏv�����͎̂��v�ł���B�킪�Ƃ����ׂĂ̕����Ɋ|���v�͂��邪�A�݂�ȓd�r���̊ی^���B��ˎ��̃~�Y�L�N�ɂ́A���Ƃɂ������l�W�����ŐU��q���̒����v�ƁA���̎���قLj�ې[�������̂��낤�B�����Ȃ�Ɏv���������t���u�W���A���E�}���}�E�{�[���{�[���v��������ł���B
����͎������w���̍�����g���Ă����B�����������ݑ�ɏオ��A��̌��Ƀl�W���������݊��������̂����A�����ɘr�����邭�Ȃ��Ă��܂������Ƃ��v���o�[���B
�������ɎO�\�N���o�Ǝ��������āA��N���Ƃ̒����v�͐V�������ɑ������B
�����Ă��̓����Ȃ��Ȃ��������v�ͥ�� ���A���w��N�̃~�Y�L�N�̕����ŁA�C���e���A�Ƃ��đ��̐l���𑗂��Ă���B
�u�d���f���v����@�^�m�q����̃G�b�Z�C
�X�^�[�g�̑傫�ȗ��ǂ̉��Ɠ����ɁA�S�[���̉��ɂ���^�C���̓d���f�����A�J�^�J�^�Ɖ��𗧂Ăē����o�����B�X�^�[�g�͂܂��܂��������B�������������A�X�s�[�h�ɏ���Ă����B�������܂������A�C�t������S�[���O�ŁA�����̂悤�ɓd���f�����m�F�����B
���w�ɓ����Ė{�i�I�Ɏn�߂����㋣�Z�́A���̂��Z�����̏ꍇ�A��Ƀ^�C�����C�ɂ���B�݂�Ȃň�Ăɑ���̂ł���L�^�Ȃ�ĊW�Ȃ����ǁA�g���b�N�ɂ͂W���[�������Ȃ�����A�W�l�����g���ɕ�����đ���B������A�Ō�͋L�^�ŏ��ʂ����߂�B���������̎��Ԃ̒P�ʂ�0.01�b�ɂȂ��Ă����B
�Z���o�����������Ă���B�����Z����������Ă���o�ɁA���̃x�X�g�L�^��b���ƁA�K���A�܂��܂����ƌ�����B�o�͌����̏������܂Ői���炢���������B�x�X�g�L�^�������C�ɘb���B���̋L�^�͍��̎��ɂ́A�ǂ�Ȃɒǂ����������Ă������ȋL�^���B�ږ�̐搶�͎o�̎��Ɠ����搶�ŁA�o���悭�m���Ă���B�������̂ŁA�ǂ������瑬���Ȃ�̂��ƕ����ƁA�ő����Ă��܂����o�́A���̎��A���̎����₹�Ă����Ƃ����B������Ă��玄�́A�H���Ȃǂ��l���邱�Ƃɂ����B���������Ȃ�̂�����Ă����B�X�N���b�g�������Ƃ��悤�ɂ����B���ی�̗��K���A���܂ł͓��Ă��~�߂�h���Ă��čŌ�܂ŃO���E���h�ɏo�Ȃ��������ǁA�ŋ߂͂ł������}���ōς܂���悤�ɂ����B
�������ĂQ�N���̃V�[�Y���ɓ������B�܂��o�̋L�^�ɂ͓͂��Ȃ����ǁA���N�̏H�Ƃ͑S�R�Ⴄ�B����ς�o�ɂ̓o�J�ɂ���邯�ǁA�����ɒǂ����ƌ����Ă�����B�����o�̋L�^�����́u�v���o�̋L�^�v�ɂ��Ă݂��悤�B���̃`�����X�́A���߂ďo�ꂷ��S�̉�B
�u�ڊo���v�ƈꏏ�Ɋ撣�����Ό��v�g�c�@�~�q����̃G�b�Z�C
���N���͎O���̓��Ƃ����������邪���̑��N������̋��Ƃ��Ă���B
���̎��ɉł��������܂����B
��Ƃ̎�w�Ƃ��Ȃ�Α��N���͕K�{�����A�܂����n�A�ƂƂ̓��������B
������͐e�ɋN�����Ă��炢��������Ƃ̏o�A�E��Ō����j���ɉ����~��������!���A�ڊo�����v�ƕԎ��������A���A���̑傫���������������Ē������ڊo�����v�́A�G���[�[�̂��߂̃I���S�[���t���A�p�A�`�͗��h���������₳�������ɂ͎q��S�ɕ������Ă��܂��B�u�����v����Ȃ�Ŗڂ��o�߂�̂�����ƈ�w�S�z��������A�������F�́u���v�A���v�v�ƌ����ė�܂��̌��t�������B
�œ��蓹��ƈꏏ�ɉł���ɗ����B�V�����s����A���Ă��Ă����o�ԁA�Q��O����N�����邩�Ƃ��̂��Ƃ���A���ɐj�����킹��肭�I���S�[�����Ȃ��Ă���邩�ƌJ�Ԃ��m�F���ڊo�����v�ɔq��œ��̂������ɂ����ĉ��ɂȂ邪���x���ڂ��o�ߏn���o���Ȃ��B
���ǖ������x�݂��I����Ďd�����n�߂�Ɛ������P���Ă���B�y���̎����~�~�Y��ԁA�Ƃł́A�ǂ��łƌ����悤�Ɗ撣���Ă������A�E��ł͊F��Ȃ̍D�ӂɊÂ��Ă��������̎��������B�~�̌��N���͐h�������B�����܂ٓ̕����A�v�̂����������A���ɋN���Ȃ��ƊԂɍ���Ȃ����l����Ηǂ��撣�������̂ł���B���ł͒N�̋C���˂��������̓��ɂ���Ď��R���݂ɑ��N���A����Q�����Ă���B�����ƒ����Ԃ����b�ɂȂ������̎��v�́A���ł͉����o���j���������A�ǂ�����ƍ\���Ď�����̕����璭�߂Ă���B�v���N�����u�����v�Q�V���Ă��܂����A�ł��܂��Z���Ȃ�Ƃ��Ȃ�Ƃ���������悭�悭�݂�Ύ������̎��͊̂�ׂ��Ă��܂����B�{���ɂ����b�ɂȂ���߂ă^���X�̏�ɏ���ꂽ���v�ɓ���������B���������������B���ł�����ς葁�N���͋��A���Ԃʂɂ��������������ɑO�ɐi��ł������Ǝv���B
�u�����v�͉ƍ�����H�v�z�܁@�x�q����̃G�b�Z�C (6���̃x�X�g�G�b�Z�C)
���a�R�W�N�A���{���܂��n�����A�����炩���������̂��b�B
���w�Z�̓��w�����琔�����o���A�w�Z�ɂ��Ȃ��ݎn�߂�������A�S�C�̐搶���ˑR�A�u�����Ƀe���r������l�A����グ�āv�ƕ������B
�u�n�C�b�I�v�A�u�n�C�b�I�v�ƁA������������ւ炵�����Ȏ肪�オ��A�������C�ɂ���ɂȂ�����B
�u�~�V��������l�v�@�u�d�C��������l�v�E�E�E�E�E
�搶�̎���͑����A����ɉ����ċ��肷�鎄�́A�������ɗD�z���ɐZ��͂��߂��B
�����A�ǂ̎���ɂ��N���X�S��������グ�邱�Ƃ͂Ȃ��A�����Ă��Q�^�R���x�̋��肾�����Ǝv���B
�u�킽���̂����́A�Ȃ�ł������v�Ƃ������o�Ɋׂ�͂��߂����A
�u���v������l�v�E�E�E�E�E
�����A�����Ɏ��v�����������ȁH
�`�N�^�N�ƐU��q�����钌���v�A�{�[���A�{�[���Ǝ���m�点�邠�̎��v�A�������v������Ō����A�ǂ�����Ƃ������̎p���ڂɕ����B
�݂�Ȃ�菭���x��Ď���グ�����́A���܂ł̐����͂ǂ��ւ��A�搶�̊���܂��������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
�u�����āA��������̘r���v�����邶��Ȃ��v�S�̒��ł������������̂́A�������Ƃ�ł��Ȃ��������ɂȂ����悤�ŁA���̓��͈���S������Ȃ������B
�����ċA�蓹�A��ςȂ��ƂɋC�������B
���������ƒ�K��I
�u�����Ɏ��v���Ȃ����Ƃ��킩���Ă��܂��I�v
���ł����Ƃ̕��u�ɂ́A���̎����e������ĂĔ����������v���A�ق�������Ԃ��Ė����Ă���B
���݂̊��o�ł͑���ɂȂ肻���ȁu�ƒ뒲���v�����A���v�������ƍ��̂ЂƂƂ��ꂽ����́A�����ď������h�����肾�������̗c�����̎v���o�ł���B
�u���߂Ď��v���K�������v�O�J�@��q����̃G�b�Z�C
�A���͉��N���̎����낤�������v�̓ǂݕ����K�����̂́A�p�������������͑��̐l��肨�悻��N�߂��Ă悤�₭���R���݂Ɏ��v��ǂނ��ƂɂȂ����E�E�E
�����Ɍ��������͂ǂ�Ȋ|���Z���A����Z���A��Z���A���v����肾�����A��Ȃ̂Ɍܕ��A��Ȃ̂ɏ\���A�\��Ȃ̂ɘZ�\������ȁA�Ƃ�ł��Ȃ��s�v�c�ȋ@�B�ł���B
�䂪�Ƃ͓����Ƒ��S���d���������Ă����A���̎��v�w�K�̒x��ȂNjC�ɂ��Ă���҂͂��Ȃ������A����Ƃ���A�F�B�ʂ��낤�A�V�Ԗɂ����Ԃ͕K�v�ł���B
������S�z�����S�C�̐搶���Ƃɓd�b���|���Ă����B
�u���v���ɑ����x�ꂪ����̂ʼnƂł��w�����Ă������������E�E�v�т����肵���Ƒ��́A�ߏ��̏m�̐搶�ɋ삯���A�m�Ƃ����Ă��A�����o���̂����w���A����ŋߏ��̂������q�B�̏h����w�����Ă����A����͂���́A�C�̒���������ŁA���ł��o���Ă��邪�A����Ȑ搶���w�����ł������A�ꃖ���������Ȃ������Ɏ��v���}�X�^�[���A���̏ꏊ���C�ɓ��������͂��ꂩ��A�h��������Ă͖K�˂鎖�Ȃ�B
���w�Z���Ƃ܂Ő��N�ʂ����B���ӂ͏��a�T�O�N�O��Q�O�O�O�~�������A���Ȃ�q�����E������ɈႢ�Ȃ��A�����̉�����Ȃ̂ɃN���X�}�X��܂ŊJ���Ă���āA�������q�B�̑��̂��ꂳ��I���݂������B����ȕꂿ���搶�ɍĊJ�����A���R���Ƃ̋߂��̃X�[�p�[�ŁA�u����I�}�[�����Ȃ��H�v��납��}�ɗ����������т����肵�ĐU��Ԃ�ƁA�����w���������搶����͂肠�̂Ƃ��̏Ί�ŗ����Ă����A�m���A�m�����́u�������v�ƌĂ�ł������A�ǂ������킯�����̌�����́u�搶�I�v�Ɛ��ɏo���B�u�����C�H���������́H�v���肫����ȉ�b�ł��邪�A�����ɂ����̂͂R�V�̎��ł͂Ȃ��m���ɂP�O�̎��������B
�u���������̐Ԃ��r���v�v��@�^�R������̃G�b�Z�C
���ł����邭�n�R�ȗ�؉Ƃł��邪�A�����͂����ƕn���������B
���͂R�˂��炢���������낤���B�Q�l�ڂ̒킪���܂�邽�߁A�c�ꂪ��̏o�Y�����̂��߂ɉ䂪�Ƃ�K��Ă����B
�ǂ����Ă��r���v���~�����Ă˂������L���������ɂ���B�~�������̂ł������Ă��炦�Ȃ��̂�������O�������̂ŁA�����ő��ɕ����˂��������Ƃ͂Ȃ������̂����B���R�͖Y�ꂽ���A�~���������B
��p�ȑc��́A���̂��߂ɖю��Řr���v��҂�ł��ꂽ�̂������B
���ł��N���Ɋo���Ă���B�V�b�N�ȐԂ��F���������̎��v�̊ۂ������Ղ͔�������肳��Ă��āA�����͏�ɁA��D���Ȃ���̎��ԁA�R���������Ă���B
����A�c�ꂩ�炨�����͂����B��w�𑲋Ƃ����̂ɖ����A�E�����܂�Ȃ����̂��߂ɁB�ł�����͑f���Ɋ�ׂȂ��B�������āA�����Ȃ���ꐶ�����w�͂����̂ɂ��̗L��l�B��������B��Ȃ���B���肳��������B�N����炵�̑c��ɐS�z��������Ȃ�āB
���̘r���v�͍��ǂ��ɂ���̂��낤���B
���N�O�A��\�܍ŖS���Ȃ����c���̈�i�̒��ɁA�č����̘r���v���������B�㐶�厖�Ƀn�[�h�P�[�X�ɂ��܂��Ęr���v���A�c������x���͂߂����Ƃ��Ȃ��B���̘b���炷��ƁA�I���A�����ČR�̏��Z�ƁA�c��̌��g�ł��������s�F�T�̒����ƕ��X�����������̂������B�H�ו��ɍ����Ă���Ƒ������̋C�����������c���̍s�ׂɁA�c��������{�����B���Ԃł́A�쎀�҂��o���قǂ̎���ɁA�c���́A�e�ʂ���������y���ƂȂ���ꂽ�B
�c���̑��V�̂Ƃ��A�ނ̗F�l���u�������ɂ́A���h�Ȏ��v�����邻���ł��ˁB�ƕ�`���̘r���v�炵���ƌ̐l�͎������Ă����ȁv�Ƃ̕����������B�푈�ʼnƂ��ƍ������ׂĔR���Ă��܂������ŁA�c���͂��̘r���v���ƕ�Ƃ��āA�Ƒ������̏ے��ɂ����������̂��낤���B���̘b�̂��ƁA���͕��d�̉��ɂ��������Ŗ������āA��O�s�o�ɂ����B
���x�A���̘r���v��������̂́A���̑��V�̓����Ƃ����B�c���͉��̈⌾���c�����A���̐�����������B�����A���ق̂܂܂ɘr���v�����͎c�����B���ꂪ���ł������̂��ǂ��ł������B�����A���ꂪ�킪�Ƃ̉ƕ�Ƃ��Ă̒n�ʂ���������������B���������ƁA���ɓ����ɘr���v���c�����낤�B�c�����҂������A���̉ƕ���ƕ�Ƃ��ĐV�����������낤���B
�u�W���N�X�̘r���v�v�{��@�a�b����̃G�b�Z�C
���������Ƃ����Ə������������̘b�B���v�ƌ����A�ǂɊ|�����Ă�����̂ŁA�e�������Ă����r���v���A�܂����v���Ă������̂ł��B����Ȏ��A������ɂ������v�Ƃ����̂͂Ƃ����ƁA��ΉE�r�ɂ͂��邱�Ƃ̂ł��Ȃ����v�������A�E�����Ȃ̂ŁA���r�ɒ��ڏ������r���v�������̂ł��B���Ԃ͂����Ă��R���B����̎��Ԃł��B�����͂������A�x���g�̌��܂ł����Ă����悤�ȋC�����܂��B
���̍��̂��Ƃ������Ă��܂��A�����炭�A���w���̍��A���̋L���̒��̂P�ԍŏ��̘r���v�Ƃ����̂́A�X�k�[�s�[�̊G���`���Ă���A�x���g�͒��F���ۂ��F�������悤�ɉ����Ă��܂��B
�ǂ����āA���̎��v�������̒��ɂ���̂��Ƃ����ƁA�N���ɔ����Ă�������Ƃ����̂ł͂Ȃ��A���̂����̎��v���͂߂ĐQ��Ǝ������N���������ԂɋN���邱�Ƃ��ł����̂ł��B�T���ɋN���悤�Ǝv���ƂT���ɁA�U���ɋN���悤�Ǝv���Ƃ��̎��ԂɂƂ����悤�ɁB�ʂɑ����N���ĉ���������킯�ł͂Ȃ������̂ŁA�܂��A�Q�Ă��܂��̂ł����A�����̌��߂����Ԃɖڂ��o�߂�Ƃ����̂������������̂ł��B���̂���̎��́A�����W���N�X�̂悤�Ȃ��̂������Ă����̂ł��傤���H
�v���o�Ɏc���Ă��鎞�v�������P�BOL�����Ă������B�ʔ̂Ŕ������r���v�ŁA�����Ղ��P�E�Q�ł��A�T�E�U�ł��Ȃ��A��E��Ə�����Ă��������v�B���͂��������Ȃ��Ȃ�A�x���g����i���ꂾ�������߁A�x���g�������ł��܂���ł����B�j�Ă��܂��܂������A�������C�ɓ����Ă������߁A���A�̂Ă�ꂸ�ɁA���̒̕��ŁA�����Ă��܂��������炭�B
�����g�A�g�ѓd�b�����悤�ɂȂ��Ă���A�r���v�����Ȃ��Ȃ�A���܂ɂ��Ă��A�u�������ȁH�v�Ǝv���ƁA�����g�ѓd�b�����Ă��܂��܂��B�̂ɔ�ׂ�ƁA���낢��ȃf�U�C���̎��v�����̒��ɏo����Ă���̂ɁA������Ƒ������Ă���C���ł��B
�u�������Ԃ�@�߂��āv�с@�����炳��̃G�b�Z�C (6���̃x�X�g�G�b�Z�C)
�������Q�̎��A�����̒j�q���Z��A�N�ƕ��ʂ��n�߂܂����B�܂�����m��Ȃ��̂ő����z�����Ȃ���y�����莆�̂��������Ă��܂����B������ނ��炱��Ȏ莆���͂��܂����B-�l�́A���������Ђ�݂ƊԈႦ���Ă��܂����B�悭�Ԉ����̂ō���܂��B�����A�Ђ�݂̃t�@�����������͂�������ނւ̃C���[�W���Ђ�݂ɂȂ��Ă��܂��A�����莆�ɂP�x�������Ă���ƌ���ꂽ���Ƃ̂��鏬���q���Ə����ďo���܂����B�܂��Ȃ��d�b�ԍ������������A�d�b�ł��b���悤�ɂȂ�܂����B�ނ͎��̐����Ă܂��܂�����Ă݂����Ȃ����炵���A�킴�킴���̍Ŋ�w�܂ŗ��Ă���邱�ƂɂȂ�܂����B�ߑO�P�P���ɉw�̉��D���ő҂����킹�A���͑��߂ɒ����ĉw�Ɋ|�����Ă��鎞�v�����Ȃ���ނ�҂��܂����B��11���ɂ͉��D���ӂ�͑҂����킹�̐l�����l���܂������A���̒��ɍ��Z���炵���l�͂�������l�A���͎v�킸���������݂܂����B���Ђ�݂ɂ͎��Ă������ʃw���Ȋ炪�����Ă����̂ł��B�Ƃɂ������̋��ȃt�F�C�X�������̂ł��B���̐l�������������Ă��܂��B����Ɏ��v�����Ȃ��玞�Ԃ̌o�̂�҂��܂����B�u���Ԃ�@�����߂��āv�ƋF��܂����B�Ƃ��Ƃ��A��l���������ɂ��Ȃ��ɂȂ����Ƃ��A�ނ͂͂�����ƌ�����炵���A���̂܂܃z�[���ɓ����Ă����܂����B����ŕ��ʂ͏I���܂����B�ނ��܂��������Ɠ����C�����������̂ł��傤�B��u�ɂ��ēV������n���ɗ��������̋C�����͍����w�̎��v������Ǝv���o���܂��B
�u�C���������v�vnocho7����̃G�b�Z�C
�F�B���厖�ɂ��Ă��鎞�v������B�~�b�L�[�}�E�X�̃f�W�^�����r���v���B���Z���w�̎��ɕ�ɔ����Ă�������̂��ƌ����Ă����B
���Z�̍��͂悭�V���̂��B���̎��v�ɂ̓~�b�L�[�̃e�j�X�Q�[�����ł���悤�ɂȂ��Ă��āA�x�ݎ��ԂɂȂ�ƁA�V���Ă�����Ă����B���鎞�A��������S����ޏ��̌��Ă��Ȃ����ɃA���[����ݒ肵�A���ƒ��ɖ�o���悤�ɂ����B����Ăӂ��߂��Ă����ޏ��̎p�͍��v���o���Ă�����B�������d�Ԃ������ꂽ�B����Ȃ��킢���Ȃ��V�т��J��Ԃ��Ă����B
��w���o�ďA�E�������A�v���U��ɔޏ��̉ƂɗV�тɍs�����B���̏�ɂ͉��������Âڂ����~�b�L�[�̎��v�������Ă������B�u�˂��A���낻��V�������v�����Ȃ�[�v�ƌ������ɔޏ��́A�u���͂��A�������̎����Ă鎞�v�A�݂�ȉ�ꂿ����āA�����̃~�b�L�[�̎��v���������Ɠ����̂Ȃ���ˁv�Ƃ����āA�����o�����������B�����ɂ͂Ȃ�Ə\�{�߂��̓����Ȃ����v�������Ă����B�u�����A���̎��v���ĂȂ���ˁ`�B�܂��A�~�b�L�[�������Ă������ł������ǁv�B
�Ȃ�ƂȂ��C�܂�����C�����ꂽ��A�u�ȂC�������ˁ[�v�Ɗ�������킹�Ă��̘b�͏I������B
����A���Z�̓������̌������ʼn��N���U��ɔޏ��Ɖ�����B�u�˂��A�~�b�L�[�̎��v�͂܂������H�v�Ǝ��͏�k�����ɕ����Ă݂��B����ƁA
�u���̂��[�A���ʘr���v�̓d�r�̎������Ăǂ̂��炢�H�v�u��������10�N���炢����Ȃ��H�v�u���̎��v�A�����Ă���18�N�o�̂ɁA�܂������Ă���ǥ���H�v�u�����H�I�d�r���ւ������ƂȂ��́H�v
�u����v�u���́A�A�A�܁A�����Ă邩�炢����Ȃ��H�v�u���A���[����ˁH�v�u�ȂC�������ˁ[�v���������Ă��݂������ɘb���ς����B
���Ԃ�A���ꂩ����ޏ��Ɖ���тɃ~�b�L�[�̎��v�͘b��ɂȂ�A�����Ă��݂��̂̂��Ƃ��v���o���Ȃ���A�Ō�ɂ́u�ȂC�������ˁ[�v�Ƃ����ĕʂ�Ă����A�����Ɣޏ��ƃ~�b�L�[�̎��v�̎O�p�W�̖�����z�����āA�������������Ȃ����B
�u�����������v�v�������@�悤�����낤����̃G�b�Z�C
�������10�N�ʑO�̘b�ł���B
���e���؍��̏o������A���Ă����B���݂₰�́A�T���X�����̘r���v�ł������B���́A���̎��v���C�ɓ���A�����g�ɂ��Ă����B
��w����A�̋��ɖ߂�A�n���̗F�l�����ƗV�B
�����āA�F�l�̉ƂɁA���̎��v��Y��Ă��܂����B
���̒��A�F�l�̏��̎q����d�b������A�u��������A���Ȃ����Y�ꂽ���v���A�a�����Ă������ǂƂ�ɂ�����H�v
�u����A������v�ƁA�w�肳�ꂽ�ꏊ�ɍs���ƁA�ޏ�����ɑ҂��Ă����B
�u���̎��v�����Ȃ��v���́A�ޏ������ɍD�ӂ�����Ă�������m���Ă����B
�u���̎��v���ɒ��ՁI�v�u��Ɏg������v�Ƃɂ�������Ĕޏ��͌������B
�u�S�����A���̎��v�͕��e����̃v���[���g������E�E�E�v
�ޏ��́u�킩�����v�ƌ����A���Ɏ��v��Ԃ��A���̏���������B
���̌�A��w�̂����ʂɖ߂�A���́A��w�̗F�l�Ǝ������݁A�����������ŁA�͌��ŗF�B�Ƒ��o������Ă����B���̎��A���̎��v���O��āA��ɗ�����Ă��܂����B���ǁA���v�͌�����Ȃ������B
���̎��A�ޏ��Ɏ��v��n���Ă�����Ǝv���ƁA���ł��S�ꂵ���v���B
�t�̋ꂢ�v���o�ł���B
����ȗ��A���́A�r���v�����������Ȃ��B
�u�����T�O����A���������ɂ��Ȃ����B�v��̂��̌��t�͎��ɂƂ��Đl�Ԃ̌��E��������ɏ[���Ȍ��t�������B��ыN���A�H�����ۂ炸�A�J�o���������đ���o���B�w�܂łU���B���s���đ�����H�̑������w�ւ̈�{���ł���B�����̓��ݐ�̌x��@�����n�߂�B�ǂ�ǂ�߂��̓��ݐ�Ɉڂ��Ă���悤�ɁA�x�������Ă���B�d�Ԃ̉����傫�������Ă���B�C���ł�B�����ʼnw�O�̊K�i�ł���B�K�i�ɒ����̂��d�Ԃ�葁����Δ�я��邪�A�x��������撣���Ă݂Ă�����ȃh�A�͖ڂ̑O�ŕ܂��Ă��܂��B����ȑ厖�Ȏ���������傫�Ȓ����v���Ƃɂ������B���̃[���}�C����T�ԂɈ�x�����̂����̖�ڂ������B���鎞�A���v���Ƒ��ɖق��ĂP�O�����i�߂����Ƃ��������B�����A��ɋN������Ă������̂悤�ɍQ�Ă��A�P�O���̂�Ƃ��搉̂��Ă������A�w�ɂ��Ĝ��R�Ƃ����B�ꂪ���v�����ɖ߂��Ă������̂��B�u�o�V�b�B�v�w���Œ|���̉��������B�x���҂ɑ��鍂�Z�̔����ł���B�ɂ������A���̎��قǎ��Ԃ̐��m���K�v���ƒɊ��������Ƃ͂Ȃ������B�����䂪�ƂŎ�������ł��钌���v�B�[���}�C�������Ȃ���̘b���ł��鎞�v�ւƐ������Ă���B
(��)�u�v���o�̎��v�G�b�Z�C��W�v�ɑ����Ă����������G�b�Z�C�̒��쌠�́A�Z�C�R�[�C���X�c�������c������ЂɋA�����܂��B
�@�@�@�\�߂������������B