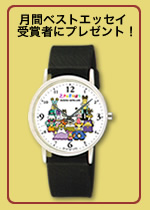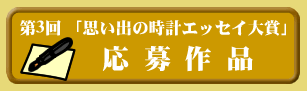 応募期間 2003年1月10日〜2003年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
2003年の作品
1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
![]() 5月の作品(19作品)
5月の作品(19作品)
「初恋」伊藤 夢津美さんのエッセイ
「銀色の腕時計」山田 理恵さんのエッセイ
「父の腕時計」山本 かおるさんのエッセイ
「書斎の懐中時計」菅沼 博さんのエッセイ
「初めての懐中時計」天ちゃんさんのエッセイ
「待合室の時計」秋山 朱実さんのエッセイ
「祖母の時計」澤 佳子さんのエッセイ
「初恋と腕時計」mayuさんのエッセイ
「道具屋さんの時計」富山 薫さんのエッセイ
「せんたく」たれこあらさんのエッセイ
「母のミタラマキ時計」杉原 真由美さんのエッセイ (5月のベストエッセイ) 特別賞
「お先真っ暗でも・・・!」宮内 はと子さんのエッセイ
「生まれるまで、生まれてから」坂本 祐子さんのエッセイ
「竹中大工さん」畠山 恵美さんのエッセイ
「時計はひとつがいい」関戸 清さんのエッセイ
「思春期の神器」日野 竜也さんのエッセイ
「2階から腕時計」小沢 みえさんのエッセイ
「見えない壁」小林 絵美子さんのエッセイ
「掛け時計に託した夢」吉田 伊知郎さんのエッセイ (5月のベストエッセイ)
私が高校生の時、東京に住む姉が「安物だからいつ迄動くか解らないよ」と言ってまるでおもちゃの様に軽くてかわいい女物の腕時計をくれました。
まだまだ腕時計は高価な時代でしたので私のとって夢のようなプレゼントでした。
当時私にはバスケット部にあこがれの先輩がいて友達と体育館に行ってバスケ部の練習を見るのが日課でした。その日は友達が風邪で休みだったので私は一人で体育館に行きました。しかしもらったばかりの腕時計が気になって腕をまくっては時計ばかり見ていました。その時、「今何時?」と言って目の前に憧れの先輩が立っていました。先輩は私の腕時計をのぞき込んで、「腹減ったなーラーメン食べに行く?」と思いがけない誘いをしてくれました。
約束通り校門で待っていると「お待たせー」と言って出てきた先輩は三人連れでした。期待はずれにちょっとがっかりしながらもバスケ部の大きな先輩三人に囲まれた気分はお姫様みたいでした。
その後私がバスケ部のアイドルらしいという噂がたっていると友達に聞きました。
1年後東京の大学に合格した先輩が十時の列車で上京すると知人を通して連絡がはいりました。
駅に行くと友達に囲まれた先輩が私を見て大きく手を振ってくれました。
ちょっと腕まくりをしたその手には大人の象徴のように立派な腕時計が輝いていました。
ただ憧れだけで終わった私の初恋でしたが社会人になって初めて買った私の腕時計は憧れの先輩の腕に輝いていた時計とそっくりの男物でした。
十五歳。私がオシャレに一番興味があった時期。そして、ロック音楽に興味を持ち始めた時期である。八十年代半ばのこと。
当時、私は大きな腕時計をするのが、最高にカッコイイことと思い込んでいた。
どうしてだろう? いまとなっては理由が思い出せない。雑誌かテレビで、憧れのミュージシャンが、大きな腕時計をしているのを見たのかもしれない。
ある日、応接間のサイドボードの引き出しに手をつっこみ、探し物をしていると、父親の腕時計が出てきた。
重たくて大きな銀色の腕時計。止まっている。でも、壊れているわけではないようだ。ネジ式らしい。
私は腕にはめてみた。かなり大きい。留め金をはずさなくても、手をキュッとすぼめるだけで、腕時計をはめたりはずしたりできた。
腕時計をはめた腕を眺めてみる。私の手首からはみ出しそうなくらい大きい。
「カッコイイ〜!」
私はこの腕時計が欲しくなった。
それで、父親に腕時計を見せ「いらないのだったら、私にちょうだい」と言ってみた。
父親は「なんでサイズの合わない腕時計を欲しがるのかわけがわからない」と不思議がりながらも、あっさりくれた。
それからは、セッセとお小遣いを貯め、チケットを手に入れてライブに行くとき、目一杯のオシャレをした私の腕には、大きな腕時計がはめられるようになった。
ライブ中、振り上げる私の腕を、重くて大きな腕時計は行ったり来たりした。そして、激しく手の甲を打ち付けるのだった。そのためライブが終わると、私の手の甲にはいつも青タンができていた。
でも、そんなこと、私は全然気にならなった。オシャレは体をはってするものだし、ライブは体をはって楽しむものと思い込んでいたのだ。十五歳の私は。
「時計」といって私が思い出すのは父の腕時計である。銀色で20年前の当時は目新しかったデジタル表示の大きな腕時計。父は「これは見やすうて、ええなぁ。」と喜んでいた。しかし、その時計はたった8ヶ月の間しか父に使われる事はなかった。父はバイクに乗っていて起こした自損事故で下半身が麻痺し、入院していた。その時「時間が分からん。不便や。」と言う父の為に母が、その時計を買ってきたのだった。父は「これは便利や。お前にも今度買ってやるからな。」と私に言ってくれた。その言葉が嬉しかった。しかし事故から8ヵ月後、父は持病の悪化もあり、嘔吐した者を気管に詰まらせて、突然に亡くなってしまった。私が小学校6年生の冬であった。危篤の知らせを受け、病室の父の元へ行くと、すっかり痩せて、まるで枯れ枝のようになってしまった腕で時計だけが光っていた。買った時に手首に合わせた腕時計が肘の関節でようやく留まっていた。その腕時計を父と共に棺の中に収めようかという話もあったのだが「私がもらいたい。」と頼み、たった一つの形見として私が譲り受けた。父の葬儀の終わった晩、私は一人でその時計を自分の腕にはめてみた。ずっしりと重く、ひんやりとしていた。この時計が肘にくる程父は小さくなっていたのかと改めて涙があふれた。その後時計は私のお守りとなり、学生時代の試験の時には必ず机の上に置いていた。大人になり常に身に着ける事はなくなつたが、時々デジタル時計を見ると優しかった父を思い出して少し切なく、懐かしくなる。
明治生まれの父は、大正時代から昭和の太平洋戦争敗戦まで電気機関車の機関士だった。
隔日の二十四時間勤務で出勤する早朝六時国鉄の制帽・制服姿が凛々しく思い出される。
出勤の時、ズボン右前ポケットから長い鎖のついた懐中時計を取出し、時刻確認の仕草はいつも同じで格好よかった。
「行ってきます」静かな声と煙草の紫煙を玄関内に残し、必ず母に見送られていた。
父が時計を手放しているのは、寝床と入浴のときくらいで、いつも腰に鎖で下げられ、機関士の命のように大切に扱っていた。
勤務明けで帰宅し父が仮眠中、枕元に置かれた時計を眺めたことがある。裏蓋に国有鉄道の文字が刻まれ貸与された時計だった。
兼業農家の我が家の春、田植え作業に大わらわの午後だった。作業中に父が泥田へ両手を突っ込み、形相鋭くまさぐり始めた。
「ひろし! 時計を落とした探せ!」
制服のズボンと農作業のズボンでは、時計の取り付け要領に不具合があったのだろう。
太い長い頑丈な鎖が幸いした。まさぐる私の指先に鎖が絡まり、拾い上げられた。
「針は動いているよ」
「動いていても泥水が入っている。分解掃除に出さなきゃあいかん」
謹厳な父の綻んだ笑顔が忘れられない。
父の定年と共に、その懐中時計は国へ返還された。しかし、その後も外見は全く同じ懐中時計を購入し、愛用していた。
父が亡くなり形見となった懐中時計は、文字盤の明瞭さが好まれ、引き続き母が愛用していた。その母も、今は逝ってしまった。
残された懐中時計は、書斎の壁に昔の鎖と共に釣り下げられ、私を見守っている。
書斎に座るたび、父母愛用の時計の文字盤に注視され、竜頭を巻くと、刻む音に父母の面影を思い出し懐旧の念が生ずるのである。
初めて時計をはめたのは小学校のころで、電池で動く腕時計でした。そんな私に母が中学にあがったころに手動の腕時計を買ってくれました。つまみを下にくるくる回すとカチコチと秒針が動きだすのがのが面白くてわざと巻かずにほっといては巻きなおしたりしていました。家にははめているだけで、自動的に巻いていく腕時計もありブンブンうでを振り回したこともありました。
そんなある日、時計屋さんの閉店セールでふたがついている懐中時計を見つけ前々から「かっこいいなぁ」とあこがれていたこともありすぐに買って帰りました。ところが右のほうにくるくるまわしてもも振り回してもいっこうに動かずとうとうふたがパカンと取れてしまいました。
「この時計壊れてる。まいても動かん」と母にもっていくと、「ちゃんと動くし、壊れてるのはふただけよ」といわれました。
あんなにまいたのに動かなかった時計がコチコチと動いていました。
「まいてなかったんでしょう」といった母の手元を見ると、右左と左右につまみをひねっていました
巻き方を知らなかった私の思い出と一緒にその懐中時計のふたは壊れたままとっておいてあります。
次女が鼻にビーズを入れてしまい。総合病院の耳鼻科に行った。
そのついでに、子宮癌の検診をした。
結果は初期の上皮内癌だった。
31歳、子宮を摘出した。
その後、定期検診の為に病院へ通った。
予約制なのだが、短くても10分は待たされる。
定期検診は細胞を取るためと前回に受けた検査結果を聞くためだ。
2つの娘の機嫌をとりながら待つ。
待合室の時計の動きをもどかしく感じていた。何度となく見る。
まだ、1分しかたってない。ふ〜。
娘に絵本を読みながら、チラチラと時計を見る。
不安そうな私に、主治医は毎回こう言った。
「貴方は完治したのです」その言葉はなにより嬉しかった。
18年たった今でも、あの待合室の時計を見ながら待った時間を思い出すことがある。私の一番長い時間だった。
毎年夏休みになると両親の実家に帰省していた。遠くはなれて暮らす祖父母だったが、私はおばあちゃん子でその三週間はいつも祖母の側にくっつき、歩いていた。気位の高かった祖母は外出する時は必ず抜かりないおしゃれに気を配っていた。指輪、ネックレス、時計・・・。祖母がいつも見につけていた高価な腕時計は自分で巻かなくては針が動かない時計だった。細いアームは銀色のブレスレットのようで、私は祖母のその柔らかくふっくらした腕に付けられた時計が大好きだった。祖母が付けているのを見てはその腕時計に触るものだから、祖母は良く「おばあちゃんが死んだらこれはあげるからね。」と言っていた。
時が経ち、3年の闘病生活でふっくらしていた腕もやせ細り、時計のアームを十分に広げずともスルスルと通ってしまうくらい細くなっていた。そして、祖母は亡くなった。
形見分けで、その時計が私のところに来た時、時はすでに止まっていて、アームには緑青(さびのような物)がでていた。持ち主が長い間付けていなかったから。
今は私が新しく時計の持ち主となり、ねじを回して時を刻む。この時計と一緒にいるだけで、祖母がいつも傍らで手をつないでいてくれたような昔の気持ちになるのは時が送ってくれた大切な「思い出」というプレゼントなのでしょう。
小学3年生のとき、私はクラスの人気者のN君に初恋をした。席替えで隣同士になったとき、N君は気軽に私に話しかけてきた。いつも面白い話をしてくるN君と話す時間は、私にとって特別なものだった。ある日、N君の机の周りに男子が群がっていた。中心にいたN君は、腕時計を持ってきていた。確か、学年誌でやっていた応募者全員サービスの、コンパスやら温度計やらがついた多機能ウォッチだったと思う。それを細い左腕につけてN君は自慢げに見せびらかしていた。授業が始まるチャイムが鳴ると、彼は慌てて腕時計を外して机の中に潜ませた。放課後、ランドセルを背負ってふとN君の机を見ると、例の多機能ウォッチのベルトが見える。当のN君はもう帰ったらしい。私は何を思ったか、その腕時計を取ってスカートのポケットに入れた。そして走って家に帰り、自分の部屋の机の引き出しの奥にしまいこんだ。深い意味はなかった。ただ単に、N君のお気に入りの物を自分が持っていることで、N君の特別な存在になれると思ったのだ。もちろんそんなわけがない。次の日の朝教室に入ると、N君は泣いていた。クラスメートの数人が集まって、N君をなぐさめている。理由は言うまでもない。友だちの一人に、N君の腕時計を知らないかと聞かれた。私はとっさに「知らない」と答えた。その後はどきどきしっぱなしだった。日が経つにつれて返しにくくなった。取った所を誰かが見ていたんじゃないかとか、お母さんが掃除中に見つけるんじゃないかとか、何よりも、大好きなN君に嫌われたくなかった。数年過ぎ、中学3年になって、N君とまた同じクラスになった。何気なく腕時計のことを話すと、彼は苦笑いして、「そんなものあったね。もう使わないし、あげるよ」と言った。そんなわけで、今も多機能ウォッチは家にある。初恋の、淡い思い出といっしょに。
今日は、仕事も上手くいかず寂しい気持ちになっていたので、ちょっと遠回りをして頭でも冷やして帰ろうかと思い、仕事の帰り道に見つけた大きな時計のお話です。雨がジャンジャン降ってきて「あーあー、今日は、涙雨だなぁ」と思いながら車を走らせていると小さな骨董屋さんを見つけました。私は元来骨董好きで「あれ?こんな所に骨董屋さんがあるぞ」と思いながら近くに車を止めて骨董屋さんの入り口のドアを開けてみました。顔だけだしてキョロキョロ当たりを見るのですが真っ暗でよく見えません。私は「今日は」と言いながら中に入って行くと中は意外と広く奥の方から声が聞こえてきました。「今日はもう終わりだよ」と言う声と同時に明かりがパッと付きました。その時私の目に止まったのが丸くて飴色に光っていた精工舎と書いてある大きな時計でした。とてつもなくでかく、しかも動いていました。こんな大きな丸い時計を見たのは初めてです。どの位眺めていただろうか。自然と声をかけていました。「おじさん、この時計が私の家に一緒に連れて行ってくれと言うとるけどいくらかな?」と尋ねて見ました。おじさんは、少し赤ら顔でお酒を飲んでいたようです。にやにやしながら「いいだろう!この時計。なんつーたって100年は、経っている時計だからなぁーちゃんと動いているだろう」と言いながら「は、は、はー」と高笑いをしていました。ちなみにこの大きな時計、私の元に来たのが、それから2年後?何度となく通いました。今では、私の部屋の壁にでんと構えて人の出入りを見つめています。
洗濯したてのズボンからポロ。腕時計が出てきた。23年愛用した時計だ。悲しかった。水を被ったのにまだけなげにも動いてる、さすがメイドインジャパンの精密さ。
年の為、点検にだしたら、分解修理で6000円かかるとの事、・・・物入りの今月の家計と照らし合わせて考えあぐねている、
それなりに大事にしたつもりだが、多感な頃の思い出の詰まった時計としてはあまりにあっけない末路であった、
洗濯した時計、6000円だして現役復帰するか、もう思い出の品として箱に入れて保管しておくか只今選択を迫られている。
「母のミタラマキ時計」杉原 真由美さんのエッセイ (5月のベストエッセイ) 特別賞
幼い頃、母がしていた青いブレスレット型の腕時計。出かける前、母はバスの時間を気にしながら掛け時計と腕時計の時間を合わせ「クルクルしといて、お母さん準備するわ。」と言ってあの時計のネジを巻くよういつも私に手渡した。銀で縁取られた青い小判型の宝石が連なったような造りのその時計は、母の頼み事をも忘れさせ、小さな娘の心をうっとりさせた。密かに腕にはめて目より上に掲げてみると肘までずりおちる。この青い輝きは、父に読んでもらったしりとりの絵本で覚えた、青い宝石=サファイヤだと私は勝手に思いこんだりもしていた。ふと我に返り、背筋を伸ばしてネジを巻く事が出かける前の私の仕事だった。けれど、どうしてこの時計だけは使う前にネジを巻くのか、私は幾度か母に尋ねたことがある。母は笑って「この時計は初めてのお給料で買った、ミタラマキ時計やから。」と答えた。この返事に私は、異国の時計の種類か何かなのかと長い間思っていた。時間を見たら巻かなければならないレトロなゼンマイ仕掛けの時計だという、その言葉の意味にやっと気づいた時、私がセーラー服を着ていたように思う。外に出ると母がスッと降ろしてつないでくれる手の高さが、ちょうど私の目線にあたる。青いサファイヤの時計に薬指には紅色の小さな珊瑚の指輪。私は嬉しそうに両手で母の手を握ったりマジマジと眺めたりした。人ごみにはぐれそうになっても青と赤の宝石のついたあのお母さんの手を探すのだ。あれから私も母となり、里帰りした実家の引き出しで思いがけずその時計に再会した。その瞬間、どこへ行くのも母のおしりにくっついていた、幼いあの頃の思い出がまるで風でめくれるアルバムを見るようによみがえったのだ。私は、小さく見える「見たら巻き時計」少しだけ触れてみて、そっと思い出と共に引き出しを閉じた。
私は大学の時、1度留年した。田舎から上京し、のんきな1人暮らしを満喫してたら授業の出席日数が足りなくなったのだ。留年する前はやばい、と思い朝寝坊をやめ、とにかく授業に出ることにした。そんな私に父は高い腕時計を贈ってくれた。父が初めて、海外に行ったときに大枚はたいて免税店で買ってきたものだった。『ブランド物で高いんだから大事にしろ。』と言われ、当時安物しか持ったことのない私はその価値もわからず腕に巻いた。そして、この授業を逃したら絶対単位を落とすという日、案の定私は寝坊し慌ててアパートをでた。ところが駅に着いてから時間を確かめようとして、腕時計がなくなっていることに気付いた。部屋を飛び出て時間がないので走りながら時計をしたのがいけなかった。落としたのだ。『…こんな日に限って。』思い切って電車に乗ろうとしたが、あきらめきれず、アパートまでの道を戻った。なにせ、10万円以上もするのだ。それを振り切って授業に出る勇気はない。今思えば馬鹿なことをしたと思う。道を這うようにして探し回った。見つからない。『きっとあんな高価なもの誰かが拾って持っていってしまった。』―その授業をすっぽかし私は結局、留年した。父に時計をなくしたことを言うと、ひどく残念がっていたが怒りはしなかった。さすがに時計を探していて留年したとは言えなかった。―あれから数年経ち、私は就職し、また転職もした。モットーは『人生は肝心なところで判断を間違えるが、それでも図太く生きていける。』―あれ以来、自分のために高い時計はどうしても買う気にならない。だが最近、父には一生物の時計を贈った。たとえ失くしても怒らないという覚悟を持って…。
昨年8月に生まれた次女の出産時の思い出、それはひとつの置時計です。突然の破水であわただしく入院した病室。
急なことで、主人は駆けつけられず、上の子供たちを両親に預けての一人きり。
3人目で出産には慣れているとはいえ、心細さはあります・・。強くなる陣痛に耐えようと、ベットサイドの小さなテーブルに手を突いたとき、目の前にその時計がありました。
三角形のどこにでもある時計。中では秒針に合わせて天使がくるくると踊っていました。それからの時間は時計に両手をかけ、ずっと時計とにらめっこ。陣痛は痛みの感覚が段階ごとに一定で、どのくらい痛みが続くか、どのくらい痛みが治まっているかだいたい測ることができるので、時計の秒針と天使をにらみつけるように見つめながら、陣痛と戦いました。
その状態で数時間。いよいよ分娩室に移る時になって、時計から手を離そうとしたのですが、うまく離せません。
どうやら何時間も体重をかけるように時計につかまっていたのですっかり手がしびれていたよう。汗で、私の手も時計もびっしょりでした。無事娘を出産し、病室に戻った私の目の前には時計。
気を紛らせてくれて有難う、と心の中で感謝して眠りました。
翌日からは娘と同室。娘はひたすら眠る赤ちゃんで、3時間おきに授乳が必要なのに6時間以上眠ってしまうこともしばしば。
結局、娘におっぱいをあげる時間を確かめるため、また時計とにらめっこ。時計を見つめ続けた一週間でした。
正確に時を刻む秒針の音に、とても救われ、落ち着かせてもらいました。いい出産ができたのはひとつの時計のおかげです。
先日、アルバムを整理していると、病室で娘をだいて笑っている私の後ろにはあの時計。
懐かしさでいっぱいになりました。
うちの壁時計は、2週間に10分遅れる。2週間を基準に10分進めておくから、2週間に一度しか正しい時間を表示する日はないと言ってもいい。トホホ。
電池の残量がないわけではない。むしろ、残量がないときは、火事場のなんとかじゃないけれど、これがもうおもしろいようにトットコトットコ進むので、わかりやすい。
別に、朝はテレビが時を表示してくれているし、ビデオのデジタルは常時時間を教えてくれているし、置き時計も各部屋にあるから、「時間がわからなくて、非常に困る」ということにはならない。されど、この壁時計だ。
木枠の正方形・トランジスター。時計の右脇に『新築記念 昭和51年1月 竹中』と消えそうな白い文字で書かれてある。昔って祝う気持ちを時計にしたんだったよな。
私が中一の時、裏座敷3部屋を新築した時に、竹中大工さんからいただいたものだ。
あの家は、とにかく広かった。竹中さんの時計は、その中央で誇らしそうにしていた。
けれど。12年前、わが家は競売にあった。そして今この家が、わが家になった。いろんなものを捨ててこなければならなかったけど、竹中さんの時計は捨てられなかった。『新しい生活も、大丈夫だ守ってやる』と、時計は語っていた。やっぱり、家の中央にかけた。
たった26年の間に、竹中さんは亡くなってしまった、とても若かった。父も8年前に亡くなった。新築した座敷、うれしそうにお酒を飲んでいた二人はいない。
母が「この時計、終わりにしてやろうか」とポツリと言った。「2週に一度進めればいいんだから、まだ終われないさ」。
竹中さんの時計の刻(とき)の中に、わが家の思いがあるのだよ。お父さんも竹中さんも生きている。あの日の私たちも、居る。
あっ、今日の時刻はちょうど。明日、10分進めなきゃ。
<電池は単2で、二年おき交換です>
昔は時刻がゆったりと流れていたように思う。我が家の柱時計もゆっくりゆっくり振り子を振って時を刻んでいた。その時計が我が家では唯一の時計であったので、誰もがその針の指す時刻を正しいと認めていた。ずい分と古びて、結構遅れていたらしいが、それでも比較するものがなかったので、遅れていると指摘するものは誰一人いない。。そしてたとえ遅れていたとしても誰一人それに困ることはなかった。みんながひとつの時計を中心に生活しているからだ。
昔は人もゆっくりと暮らしていたのだ。
近頃は、時間も人もあわただしいようだ。周りには一杯時計があって、競るように時刻を刻んでいる。人はそれに合わせるように立ち働く。悪いことに、そのたくさんある時計が、どれも少しずつ違う時刻をさしているので、本当に正しいのがどれだか分からないことだ。人は遅れてはいけないと思い、どうしても一番進んでいるのを頼りにしてしまう。そして人も競るようにはしりだす。時計に急かされ生きているのだろうか。
時計がひとつだけなら、その時計を信じたらいい。しかしふたつになると、正確のはずがいつかおのおの違う時刻を刻むことになる。正しいのはどれか分からなくなるわけだ。
時計はひとつでいい。それを信じたらゆっくりと生きられる。
思春期の象徴といえるものは、きっと誰にだってあるだろう。僕にとっては、それが時計だった。中学生になる時、僕はどうしても時計が欲しかった。「中学には腕時計をして行ける」と知ったからだ。僕は決意をもって、父に言った。「腕時計欲しい」「ええよ」あっさり。父は戸棚から、黒いデジタル時計を取り出して「これやるわ」と言った。ついに、僕は腕時計の所有者になったのだ。いとも簡単に。
そうして手に入れた腕時計を僕は、中学の三年間、ほとんど外さなかった。時には寝る時さえも。おかげで左手首だけやたらと細くなり、おまけに実に臭い。度を過ぎた愛着ぶりだった。きっと、僕が腕時計にこだわったのは、単純にそれを身に着けていることが、「大人っぽく」思えたからだ。でも、そう思うこと自体、「大人」でない証拠であり、実際僕は、「少年」にもなりきれない「子供」だったのだろう。
しかし、時計と僕の日々は、ある日あっさりと終わる。中学卒業間際、ささいなことで父と口論した僕は、自分の部屋に戻って、時計を壁に叩きつけたのだ。時計のことなど、父はなにも言わなかったのに。なぜだろう。もしかすると、僕はそれを壊すことで、「子供」から「少年」になろうとしたのかもしれない。
翌日、父は僕に言った。「今日は時計してへんのか?」バツが悪かった。「落っことして・・・液晶が壊れて・・・」僕は嘘を吐いた。「そうか」と言って父は自分の腕時計を外し、「これ使っとけ」と僕に渡した。僕は罪の意識を感じながら受け取った。だからだろう。壊れた時計を、僕は自分の部屋の机に丁寧にしまいこんだ。大切なものを、自らの手で失ってしまった後悔を、胸に秘めて。その時、僕は確かに「少年」になっていたのだと思う。
その時計は、今も机の中にある。僕の、「思春期」という名の祭事の、神器として。そして、「少年」から「大人」になった今の僕の腕には、自分で買った時計が、時を刻んでいる。
「いってきまーす。」今朝は、左腕に時計をはめていませんでした。昨夜から、部屋中を探しても、見つからなかったからです。
電車通学だったので、時計がなくても、定刻に電車がきます。いつも左腕にしているという感覚があるためなのか、“今日は、(時計を)していなかったんだ。”と一日中落ち着かず、そして少し寂しい日でした。
その腕時計が見つかったのは、意外な場所でした。
その頃、私はマンションの2階に住んでいました。隣の家は、そのマンションの大家さんが住んでいました。腕時計は、2階の窓から落ちたらしく、大家さんが持ってきてくれました。
「2階から落としてしまったみたいね。でも、無キズですよ。」
と言ってくれた時、ガラスの部分が割れなくて良かったと思いました。その時計は、どこにでもあるようなもので、高価なものではないのですが、文字盤が見やすくて、とても気に入っていました。
左腕にしていなかった一日を過ごしたことで、腕時計の存在の大きさを実感したのです。
そして、2階から落としてしまっても、細い秒針が動く強さに、感動しました。細くても、強い意志を持っているような秒針は、今でも、一秒一秒の時を刻んでいます。
我家の子供達は、レーシングカートをやっている。遊園地のゴーカートのエンジン付きのものでレースをするのだ。
普段は何気なく通り過ぎてしまう、1分にも満たない時間。しかし、それがカート場ではとてつもなく長い時間感じる。コースによって多少の違いはあるものの、大体のコースが40秒前後で1周することができる。レースになると、その1周のタイムによって予選を走る順位が決まる。そしてとらえどころの無い1秒の何百分の1という時間を、ライバル達と競いあうことになるからだ。
一瞬たりとも気の抜けない時間を、何度も何度も過ごしながら、子供達のトライは続いていく。その様子を、私はコース脇のPITから息を呑んで見守っているのだ。子供達のトライの結果を知っているのは、私の手に握られた、ストップウォッチだけである。なかなか破ることが出来なかった見えない時間の壁を、見事に乗り越えてくれた瞬間を、私に教えてくれたのも、このストップウォッチだった。どんなに暑い灼熱の夏も、手が切れそうに寒い木枯らしが吹く冬の日も、ストップウォッチは私と一緒に子供達の走りを見守ってくれて、子供達の成長を私に教えてくれたのもこのストップウォッチだった。
きっとこれからも、ずっとずっと、見えない壁へのトライは続いて行くことだろう。そして私は、このストップウォッチと共に、それを見守りつづけて行きたいと思う。
「掛け時計に託した夢」吉田 伊知郎さんのエッセイ (5月のベストエッセイ)
私が物心ついた時から、我が家には一台の古い掛け時計があった。既に時を刻むことをやめ、アンティークとして余生を過ごしていた。私も気にかけたことなど一度もなかったし、家族にしても同様だった。ただ、いつの頃からかそこにあったのだ。私の幼少時の写真や8mmには、決まってその時計も写っていた。単に我が家では写真を撮るというと、決まってポーズを取る場所があり、そこに時計が置いてあっただけのことだ。しかし、フィルムが余った時など、父も母も私も何故かその時計を撮ったりするものだから、我が家のアルバムにはその時計が多く写っている。
理由あって、私は家族と7年ほど会っていなかった。先日、実に7年振りに家族と再会した。そして7年振りに実家に帰った。家の佇まいに表向き変化はなく、父母の極端な老け込み様に、いささか私が感傷的な気分になりつつ家に入ると私は驚嘆した。時計、時計!時計!!部屋中に古びた掛け時計が掛かっているではないか!それも十や二十ではない。何百という数だ。聞くとこれだけではないという。物置は当然、居間も寝室も私の部屋だった場所まで古時計に占領されている。壁という壁には隙間なく時計が掛けられ、残りは堆く積まれている。一体何故こんな事態になってしまったのか?母によると、私が家を離れて間もなく、父は突如として骨董に目覚め、殊に古時計に並々ならぬ執着を見せ、あっという間にこんなことになってしまったのだという。父は古時計を集めることで、何かを埋めようとしていたのだろうか。私は決して泣くまいと思っていたが、この古時計の山と、その前で幸せそうに微笑む父を見ていると、無性に涙が出てきてどうしょうもなくなってしまった。
(注)「思い出の時計エッセイ募集」に送っていただいたエッセイの著作権は、セイコーインスツルメンツ株式会社に帰属します。
予めご了承下さい。